茨城県つくば市の中でも筑波山の北部に位置する株式会社 筑波山江戸屋様は、筑波山が織りなす壮大な自然に抱かれ、その絶景を望む温泉と、地元食材を活かした創作和食で知られています。長年の歴史と伝統を受け継ぎながらも、常に新しい時代のお客様のニーズに応えようとする姿勢が随所にうかがえます。本記事は、この魅力的な旅館の女将様である吉岡様の言葉で、旅館の魅力、宿泊業界が直面する課題、そして未来を担う若者への思いをお伝えします。今回は、歴史ある旅館の魅力や業界が直面する課題、そして若者への温かいエールについて、代表取締役社長 吉岡様にじっくりとお話を伺いました。
<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>
【旅館の魅力と若者への期待】
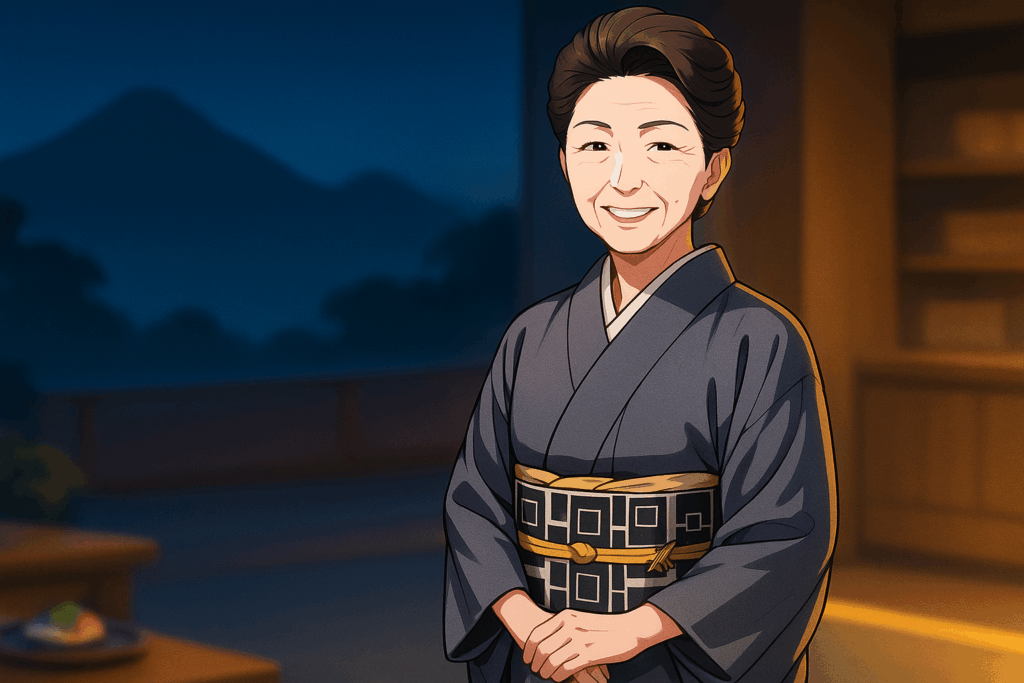
私どもが運営するこの旅館は、茨城県つくば市の中でも筑波山の北部に位置し、筑波山の豊かな自然と一体となれる絶景の温泉、そして地元食材をふんだんに使った創作和食が自慢です。長年培ってきた歴史と伝統を受け継ぎながらも、常に新しい時代のお客様に満足いただけるよう、日々努力を重ねています。
特に強く感じているのは、これから社会に出る若い方々、いわゆるZ世代の皆さんが「好きなことで生きていきたい」という思いや、「共感できる職場を選びたい」という強い気持ちを抱いていることです。私どもは、若い皆さんが持つ「やる気」やSNSでの情報発信力といった強みを認識しています。その一方で、社会経験の不足という課題にも目を向けています。学生の皆さんが、早期離職といった若者と企業双方にとっての不利益を避けるために、魅力的な経営者のリアルなストーリーや企業の魅力を伝える活動をしていることには、私も共感しています。これは、皆さんが夢を見つけ、社会貢献できる場を見つけるための大切なヒントになると感じています。
旅館の運営においても、私の姿勢は明確です。歴史や伝統を重んじつつも、若い世代が運営の中核を担い、彼らの感性を取り入れた「若い人が来て満足できる」宿づくりを進めています。例えば、地域への貢献として、筑波山のロゴが入ったTシャツをスタッフが着用し、その一部が自然保護に寄付される仕組みを取り入れています。また、従業員が主体となって夏祭りや子供向けの遊びを企画するなど、働く私たちが楽しみながらお客様を迎え入れる環境が整っています。このような取り組みは、従業員にとってもやりがいとなり、お客様にとっても忘れられない体験になっていると感じています。
取材担当者(高橋)の感想
この旅館様は、日本の豊かな歴史と伝統を大切にしながらも、若い世代の価値観や働き方を深く理解し、それを取り入れようとされている点に大変感銘を受けました。特に、従業員が主体となってお客様に楽しんでもらう企画を考えるという文化は、私たちZ世代が求める「やりがい」や「共感」をまさに体現していると感じました。歴史と新しさが融合した、まさに理想的な職場環境ではないでしょうか。

【宿泊業界が直面する現代の課題】
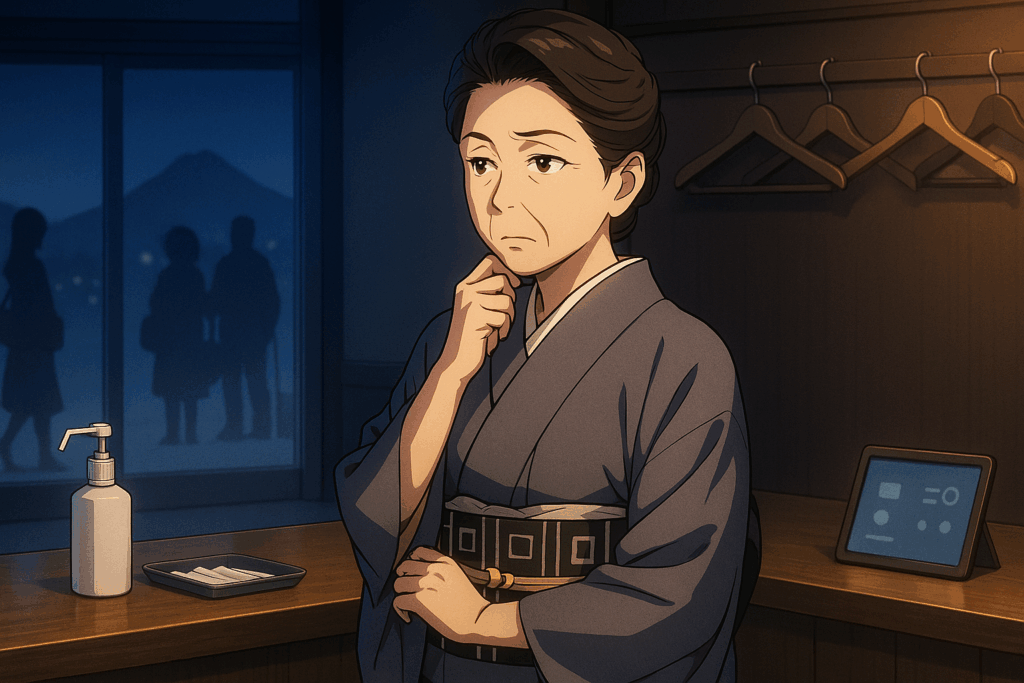
コロナ禍を経て、宿泊業界全体が新たな局面を迎えています。お客様の行動様式や求めるサービスが変化し、正直なところ、私どもも「どのように変化に対応していけば良いのか」という戸惑いを日々感じています。以前はマスク着用や消毒液の設置、お客様との接触を避ける対応が求められましたが、現在はどこまでお客様に寄り添うべきか、その距離感が非常に微妙になっています。お客様によって対応を変える必要があるほど、多様なニーズが存在していると実感しています。
また、全国的な課題である人手不足は、宿泊業界にとっても大きな問題です。コロナ禍で多くを制限せざるを得なかった状況から、人材確保は喫緊の課題となっています。当旅館では、2年前から新卒の大卒採用に力を入れています。さらに、コロナ禍以前の約10年ほど前から積極的に留学生を受け入れています。彼らは語学力を活かして海外からのお客様を迎え入れたり、日本文化である生け花を習得したりと、多様な形で活躍してくれています。彼らが日本の文化を好きで、この仕事を選んでくれていることが私にとって喜びです。
ホームページに関しては、正直なところ、今の流行りやトレンドを取り入れ、視覚的に訴えかける情報発信が不足していると感じています。ホームページは比較的早くに制作し、何度かリニューアルもしていますが、歴史的な部分を伝えることに重きを置いてきたため、「今来てどうなのか」という部分が十分に表現できていないのではないかと考えています。お客様に当旅館の魅力をすぐに感じてもらい、足を運んでいただくための工夫が、まだ足りないと感じています。
取材担当者(高橋)の感想
コロナ禍がもたらした変化と人手不足は、宿泊業界全体にとって深刻な課題であると改めて認識しました。しかし、この旅館はそうした困難に対し、新卒採用や留学生の積極的な受け入れ、さらにはお客様との関係性構築まで、多角的な視点から解決策を模索されている姿勢に感銘を受けました。特に、外国人材の活用は、単なる労働力としてではなく、彼らが日本の文化を愛し、理解しようとする姿勢を尊重されている点が感銘を受けました。

【変化への対応と外国人材の活用】
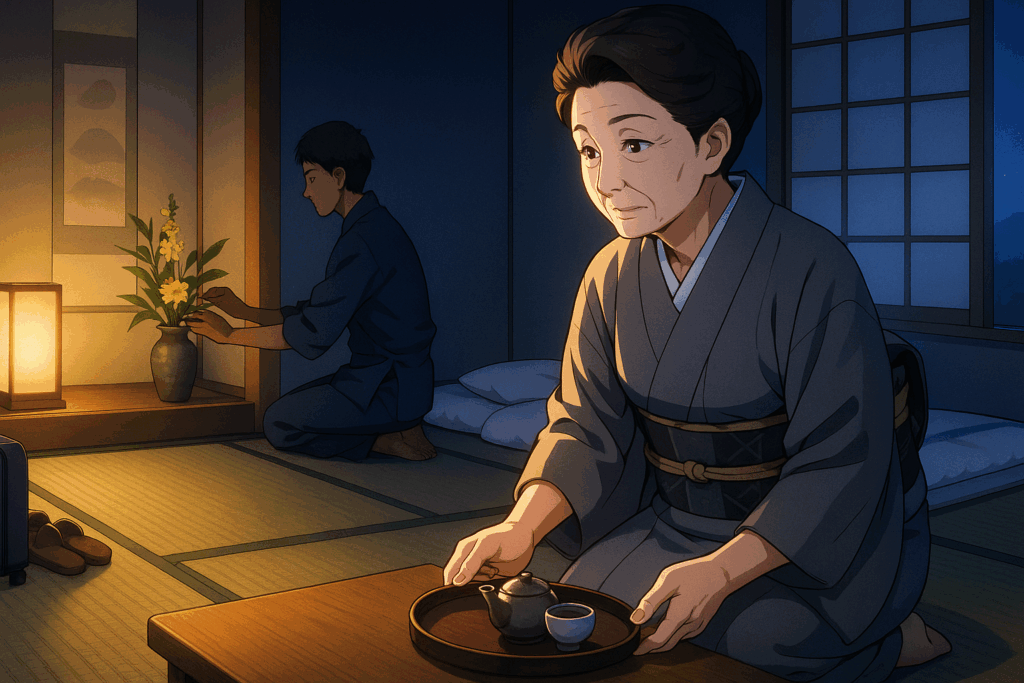
お客様がより満足できる滞在を提供するため、私どもは様々な工夫を凝らしています。例えば、コロナ禍を経てお客様との接触を減らす必要性が生じた経験から、お客様がご自身のペースで過ごせるような客室のあり方を模索しています。布団をあらかじめ敷いておくことや、お茶や茶菓子を部屋に用意しておくことなども検討しています。これは人手不足への対応だけでなく、現代のお客様のニーズに合わせたサービス提供のために必要だと実感しています。
また、お客様のニーズの多様化に対応するため、一人旅のお客様への対応も強化しています。以前は一人のお客様をお断りすることもありましたが、今は男性だけでなく女性の一人旅も一般的になりました。このようなお客様にも快適に過ごしていただけるよう、平日の一人宿泊プランなど、よりきめ細やかなサービス提供を考えています。動画による情報発信も重要だと感じていますが、現在はまだアカウントがあるだけで、十分に活用できていないのが現状です。若い世代の感性を活かし、当旅館の魅力を視覚的に訴えかける工夫がこれからの課題だと捉えています。
外国人材の積極的な受け入れは、グローバル化が進む現代において不可欠だと考えています。中国、スリランカ、ネパールといった国々から来た留学生たちが、当旅館で活躍しています。例えば、ネパール出身のスタッフは、日本人でもなかなか習得が難しい生け花を学び、館内に花を生けています。彼らが日本文化を深く理解し、愛しているからこそ、この仕事に取り組んでくれていることが嬉しいです。日本は少子化が進み、日本人だけでは労働力を賄うことが難しいと感じており、外国人材は言葉の面でも大いに助けになっています。
取材担当者(高橋)の感想
宿泊業界が直面する課題に対し、女将様が具体的な解決策を模索されている姿勢が印象的でした。特に、お客様との新たな距離感を模索し、一人旅への対応を強化されている点、そして外国人材を単なる労働力としてではなく、文化的な貢献者として受け入れている点は、今後の旅館業のモデルケースになると感じました。デジタル化への課題認識も持たれており、進化し続ける老舗旅館の姿に感動しました。

【旅館業の未来と若者へのメッセージ】
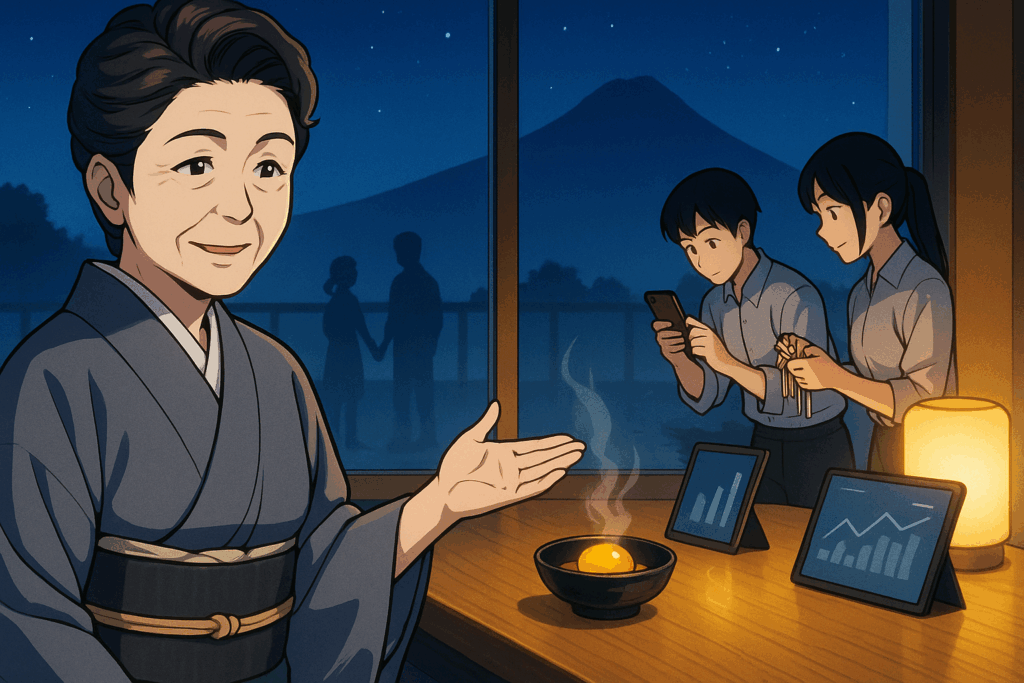
コロナ禍は私どもにとって大きな転換点となりました。この4年間で、業界全体が大きく変化し、多くの旅館が混乱している状況を目の当たりにしてきました。特に、補助金などの情報収集や申請もインターネットを通じて行われるようになり、私たちだけでは対応しきれない部分もありました。しかし、こうした経験は、デジタル化への対応の重要性を改めて教えてくれました。当旅館の現場の平均年齢は比較的若く、20代のフロントスタッフや40代の調理人など、多様な世代が活躍しています。SNSを通じた情報発信は若い世代の得意分野であり、積極的に取り組むべきだと考えています。
私どもは、働く若い世代に「人と関わること」の重要性を伝えたいと考えています。現代の若者はSNSの発信力など素晴らしい強みを持っていますが、対面でのコミュニケーションに苦手意識を持つ人もいるかもしれません。しかし、旅館という仕事は、多様な背景を持つお客様と出会い、様々な人生経験に触れることができる貴重な場です。例えば、国体などで皇室の方がお泊まりになった際の厳格な対応や、三世代家族の温かい交流など、普通では経験できない多くの学びがあります。
こうした経験は、若いうちにこそ積極的に身につけてほしいと願っています。人と深く関わることで、新たな世界が広がり、自身の将来の目標を見つけるヒントにもなるでしょう。困難を恐れず、一歩踏み出してほしいと思っています。当旅館は、筑波山の豊かな自然、絶景の温泉、地元の新鮮な食材を活かした創作和食など、多くの魅力を兼ね備えています。例えば、茨城県産の新鮮な野菜や奥久慈卵(おくくじたまご)といった地元の名産品を積極的に料理に取り入れ、お客様に特別な食体験を提供しています。私たちの旅館が持つ歴史と伝統を守りながら、若い世代の感性を取り入れ、常に新しい価値を創造していくことが、これからの旅館業の未来を築く上で最も重要だと考えています。
取材担当者(高橋)の感想
コロナ禍を乗り越える中で、デジタル化の重要性を再認識されたこと、そして若者のコミュニケーション能力向上に期待を寄せられている点が印象的でした。旅館という場で、お客様との多様な出会いを通じて人生経験を豊かにしていくというメッセージは、まさに「人との繋がり」を重視する私たちZ世代にとって、深い学びとなりました。この旅館が持つ歴史と革新が融合した魅力は、今後も多くの人々を惹きつけ続けることでしょう。










