株式会社わだまんサイエンス様は、「ごまで世界平和」を理念に掲げ、香りと機能性、個性豊かなごま製品の企画・開発・販売を手がけています。ごまリグナンやごま若葉といった機能性素材の展開、OEM製品受託、植物酵素や化粧品開発まで幅広く事業を展開しています。京都に「ごまの専門店ふかほり」や「胡麻屋くれぇぷ堂」といった店舗を構えるほか、全国の百貨店での催事販売、オンライン通販も行い、ごまの魅力を国内外に発信しています。特に、「セサミグリーン運動」を通じてごまを通じた平和活動とビジネスの融合を目指す社会貢献活動にも力を入れています。今回は、「ごまで世界平和」という理念の原点と多角的な事業展開、そしてセサミグリーン運動が描く未来まで、代表取締役社長・深堀勝謙様にじっくりとうかがいました。
<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>
【創業の原点:お金と権力に縛られない生き方への問い】
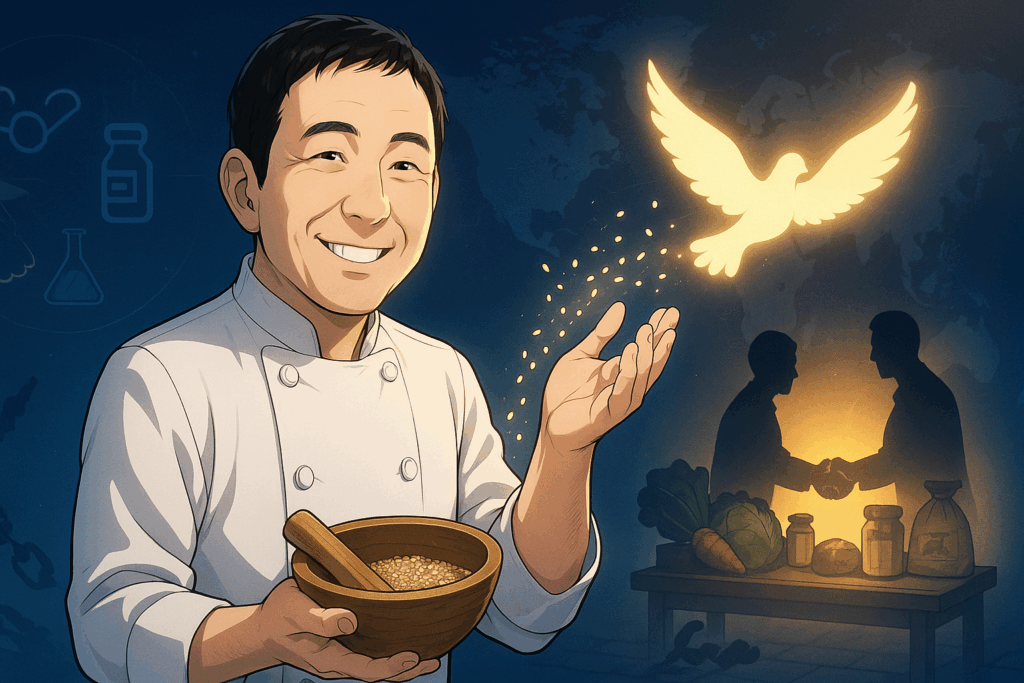
私は若い頃から「本当にこのままでいいのか」という心の声をずっと抱いていました。社会に出ても経験も知識もない中で、ただ何かに貢献したい、社会で存在意義を感じたいという思いが強かったのです。しかし、魅力的な会社や経営者の考え方を知る機会も少なく、結局ミスマッチを起こして挑戦をやめてしまう20代が多いと感じていました。私自身もまた、お金や権力に縛られていると感じる経験をしてきました。
私のキャリアは宝石屋さんから始まり、営業を学ぶために製薬会社に8年間勤務し、その後、酵素を作る会社に2年間、ごまの卸店に2年間勤めました。多くの転職を経験する中で、「自分の能力に対して、この給料では足りないのではないか」「企業側はもっと安く評価しているのではないか」という、お金が自分の価値になってしまう問題に直面しました。会社を辞める理由の多くは、お金と権力に縛られていることにあると捉えていました。
このような経験から、私は「お金とは平和の道具でなければならない」と考えるようになりました。そして、コロナ以降は「お金の存在しない国を作るぞ」という思いで、ボランティアとして物々交換の場を設け、そこから多くのファンが生まれています。私にとって、ただ利益を追求するだけの経営ではなく、「どうしたら人が喜ぶか」という計算に長けていることの方が、はるかに重要だと感じています。
取材担当者(高橋)の感想
深堀社長の創業の経緯には、多くの若者が抱える「このままでいいのか」という問いかけや、経験不足から来るミスマッチへの問題意識が強く表れていると感じました。お金や権力に縛られるのではなく、自らの心の声に従い、愛を基盤とした経営哲学を確立された背景には、社長自身の葛藤と挑戦があったからこそだと深く共感しました。

【「愛」を基盤とした経営哲学:人々の喜びを追求する事業活動】
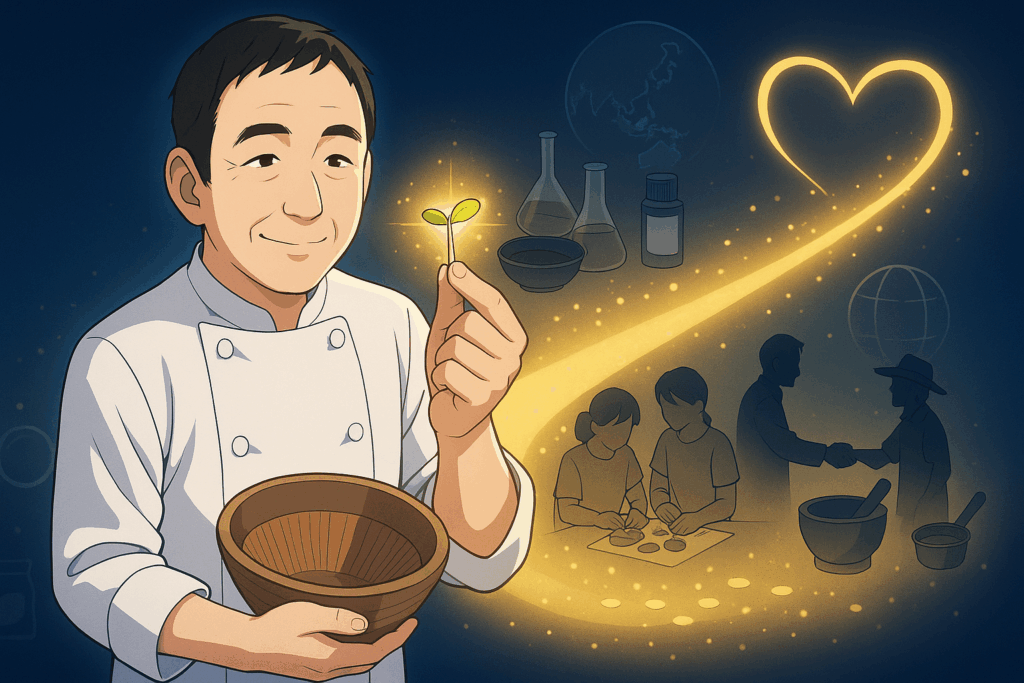
私は会社を立ち上げる際、とにかく「愛だけでチャレンジしよう」と決めました。自分の利益を追求するのではなく、人々の困り事を解決することがビジネスであるべきだと考えています。例えば、ごまに至るまでの経緯として、宝石屋時代に喘息で倒れて入院した際、「これからは付加価値よりも必要価値のあるものだ」と感じました。その後、ごまを食すことで喘息が治った経験から、ごまの可能性を強く感じたのです。
製薬会社時代には、自分で生薬を口にして味を調べ、成分と味の関係を理解する中で商品開発の面白さを知りました。この経験から、ごま業界に入ってからも発芽ごまやごま化粧品、世界初のごま若葉の青汁など、様々な製品を生み出してきました。当時、発展途上国の人々が手作業で作るごまの業界は利益が少ないと思われがちでしたが、そこで働く人々が生き生きとしている姿を見て、お金だけではない価値があると気づきました。
東日本大震災の際には、会社が赤字で倒産の危機に瀕していたにもかかわらず、いても立ってもいられず現地へ飛び込みボランティア活動をしました。その中で出会ったボリビアの方を通じてJICAの民間連携調査団に参加し、パラグアイの貧しいごま農家が品質基準の厳しさから作物が返送される「シップバック」問題に直面していることを知りました。私はお金がない中でも、杵と臼でごまを挽く方法やフライパンで美味しくごまを煎る方法など、現地でできる商品作りを教えました。
これが国立アスンシオン大学の課外事業となり、最終的には外務省のホームページで紹介されるまでになりました。また、私はB型就労支援施設の方々と一緒に商品開発をしています。彼らが作った商品を「ゴマソムリエ」ブランドとして最高に美味しいものとして販売し、彼らが社会で活躍できる力を与えることを目指しています。私にとって、利益は「後からついてくるもの」であり、まずは社会的に弱い人々の力になる製品作りや、人々の困り事を解決することに焦点を当てています。
取材担当者(高橋)の感想
深堀社長の「愛」を基盤とした経営哲学は、単なる美談ではなく、具体的な行動と成果に結びついていることに驚きました。自身の経験や社会の課題に真摯に向き合い、お金ではなく人の喜びを追求する姿勢は、ビジネスの本来あるべき姿を教えてくれるようでした。特に、パラグアイでの支援活動や就労支援施設との連携は、弱き人々に寄り添う社長の深い人間性が表れており、感銘を受けました。

【お客様との深い繋がり:「誰から買うか」の価値を創造する】
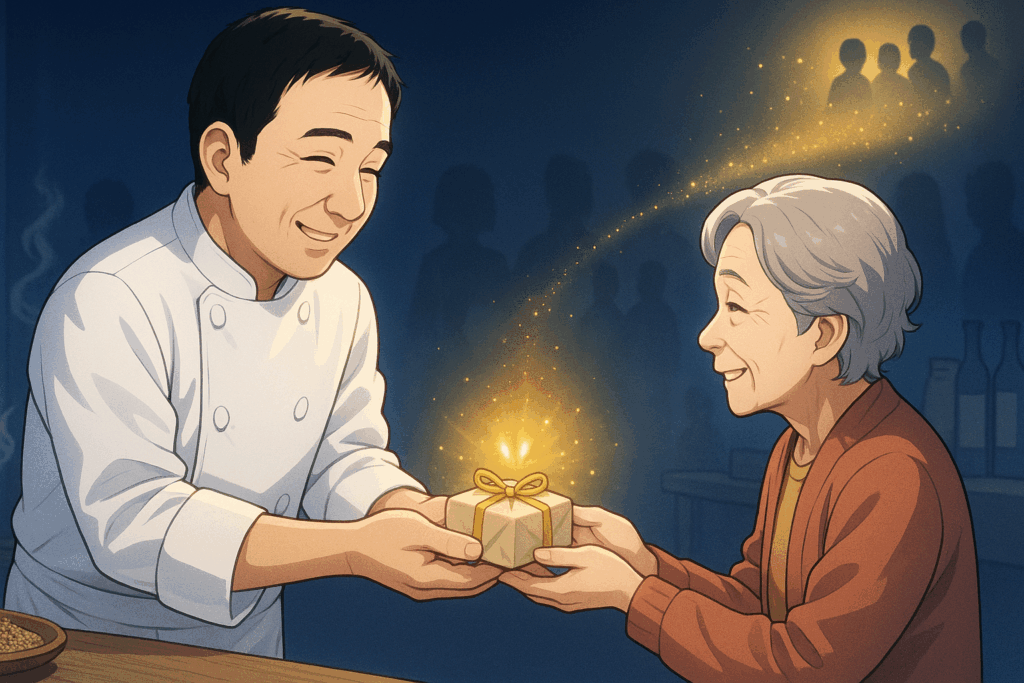
これからの時代は、どれだけ商品が良くてもダメで、「誰から買うか」が重要になります。私は、お客様との深い心の繋がりを築くことを大切にしています。例えば、百貨店での催事販売では、ごまが好きな高齢のお客様が多く、「私一人だから一個でいいの」という言葉をよく耳にしました。最初は「なぜ一人だとわざわざ言うのだろう」と思っていましたが、多くの方が寂しさを伝えているのだと気づいたのです。
それからは、「またお待ちしていますね」「2ヶ月後、また来てくださいね」と声をかけ、時には小さなプレゼントも添えてお渡しするようにしました。すると、そうしたちょっとした心遣いから、お客様が私のファンになってくださいました。インターネットでいくら安く買えても、最終的には「寂しさ」には限界があると考えています。信頼できる人から買いたい、自分のことを理解してくれる人から買いたい、という気持ちは、美容院選びにも通じるものがあると思います。
私は、あらゆる発信において、自分を見せようとするのではなく、「愛のある一言」や「感謝を伝えること」を心がけています。ごまの美味しい食べ方や時短レシピを紹介するのも、お客様の「どうやって食べたらいいか分からない」という困り事を解決するためです。そうした発信が結果的に人々の喜びにつながり、それがビジネスの成功にも繋がると信じています。
取材担当者(高橋)の感想
「誰から買うか」という価値観は、現代の消費行動において非常に重要な視点だと改めて感じました。お客様の表面的な言葉の裏にある「心の声」を深く汲み取り、それに応える社長の姿勢は、真の顧客志向だと思います。SNSを単なる自己アピールの場ではなく、「感謝を伝えるツール」として活用されている点も、社長の人間性が滲み出ており、多くの学びがありました。

【未来へのビジョン:ごまが繋ぐ平和と助け合いのコミュニティ】
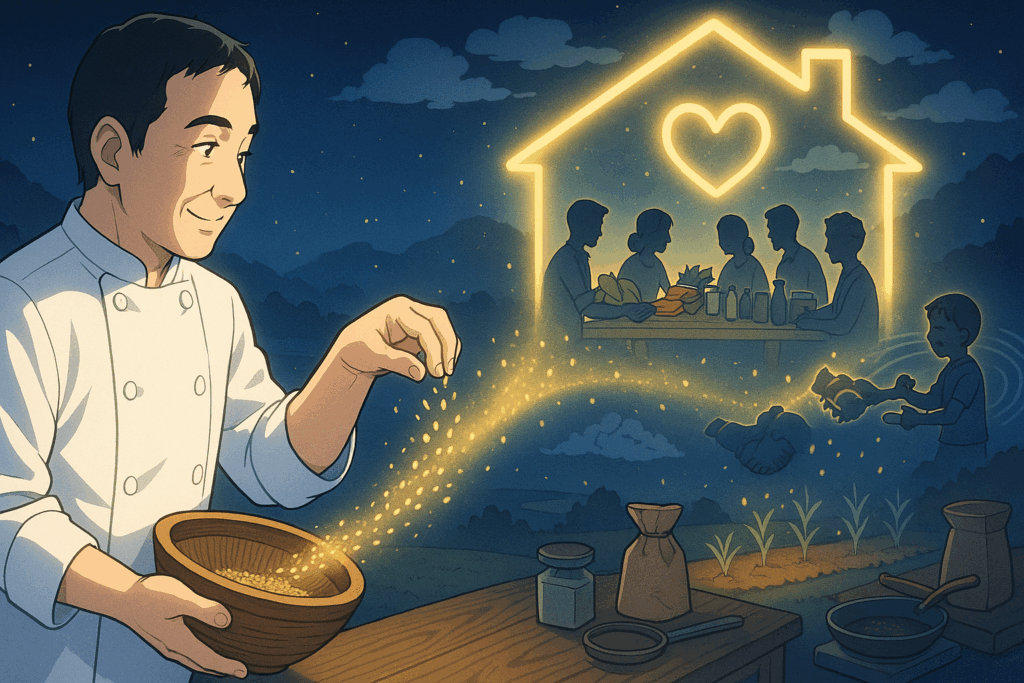
私は、会社を大きくしたいとは全く思っていません。しかし、応援団や仲間は非常に多いのです。なぜなら、私は自分の見つけたノウハウや知識を惜しみなく共有し、愛をもって人々に接しているからです。例えば、ごまは混ぜ方一つで香りや味が変わり、それは心の持ちようによっても変わると考えています。私は「どういう心持ちが一番美味しくなるか」を追求し、そのやり方を今、伝え続けています。
直近では、物価高騰の影響で2年間値上げを我慢し、前期は赤字を出してしまいましたが、お客様には「応援したい」という気持ちで支えられ、過去最高の売上を達成できました。この経験から、私は「ごまインシェルター」という構想を抱いています。これは、愛のある人々だけが集まり、一人暮らしの方々が寂しさを感じずに、野菜などを持ち寄って物々交換ができる、憩いの場所です。
私の人生は「愛を蒔けば、必ず収穫期が来る」という考えに基づいています。かつて、マツコさんの番組でごまを杵でつきながら「ありがとう」と言っていた私の姿を見た小学生の男の子が、いじめを克服し、自らも「ありがとうのごま」を作るようになりました。彼はその後、私を訪ねてきて弟子になり、今では太鼓の音を鳴らしながらごま製品作りに携わっています。
愛を伝える行動が、巡り巡って人々の心を動かし、ビジネスの成功にも繋がっていくのです。人生はあっという間です。目の前の損得に振り回されるのではなく、自分の命を人々のために燃やし尽くすことが大切だと信じています。もし今、若い方々が何か得意なことや学んだことがあるなら、お金をもらわず無料で他の人に教えてあげることを勧めています。一見、損に見えるかもしれませんが、それは琵琶湖の水が水蒸気になり、雲となって雨が降るように、必要な時に財が与えられる「愛の循環」だと私は思っています。
取材担当者(高橋)の感想
「お金の計算に長けるよりも、どうしたら人が喜ぶかの計算に長ける方がいい」という深堀社長の言葉は、私の心に強く響きました。ごまインシェルターの構想や、「ありがとうのごま」の物語は、深堀社長の「愛」が単なる理念ではなく、具体的な行動を通じて社会に影響を与えていることを示しています。このギブの精神こそが、これからの時代を生き抜く上で最も強力な武器となると確信しました。










