富山県氷見市に拠点を置く有限会社中村海産様は、大正10年(1921年)創業の老舗みりん干しメーカーです。創業以来、「おいしくて、体にやさしいみりん干し」を追求し、化学調味料や保存料を一切使用しない製品づくりを続けてきました。定置網発祥の地である氷見市で、「世界中の魚ぎらいな子どもをゼロにする」という壮大な目標を掲げ、伝統的な製法を守りながらも、現代のニーズに合わせた先進的な設備で安心・安全な食品を提供しています。みりん干しだけでなく、スイーツなどの新しい商品開発にも挑戦し、常に進化を続けている企業です。
<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>
【長男として家業を継ぐことになった経緯】
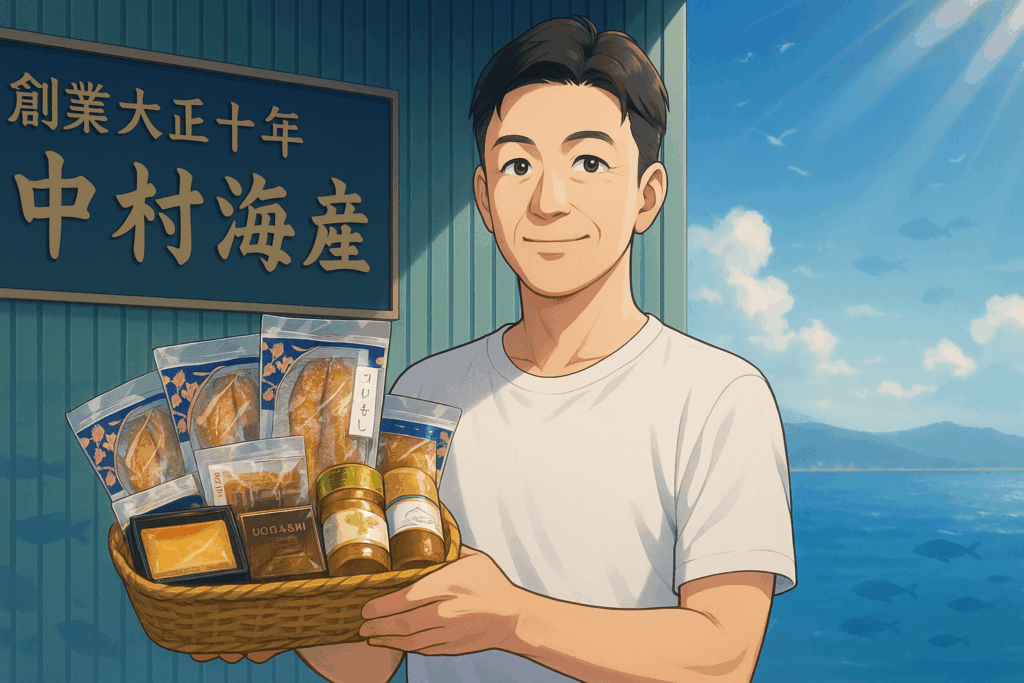
私は元々、会社を継ぐ予定ではありませんでした。三兄弟の長男であるため、弟が継いでくれれば自分は自由に生きていけると考えていました。高校卒業後は県外に出て、大学や専門学校に通い、関東で就職も経験しました。
しかし、26歳の時に過労により体に腫瘍ができ、肺と肺の間に腫瘍が形成されました。手術を受けましたが、転移の可能性がゼロではなかったため、26歳から27歳頃まで抗がん剤治療を受けました。その影響でうつ病を患い、会社を辞め、約2年間は引きこもりのような生活を送っていた時期があります。
そのような中、2011年の東日本大震災の頃、父から富山に戻らないかと声がかかりました。当初は療養目的でしたが、地元に戻ったことが会社と関わるきっかけとなりました。少しずつ体調が回復する中で、父や母、家族に迷惑をかけながらも、療養を兼ねて仕事を手伝い始めました。そして、父が60歳になった2016年に、「65歳になったら引退するから、あと5年の間に準備しておけ」と告げられ、そこから家業に専念することを決意しました。
この5年間は、営業活動や展示会出展など、仕事だけに集中しました。そして、父の言葉通り、2021年7月に正式に世代交代を果たし、社長に就任しました。元々は継ぐ予定がなかった私が、病気を乗り越え、多くの人々に支えられながら、今に至ります。
取材担当(高橋)の感想
中村社長の半生は「波乱万丈」そのものだと感じました。20代という若さで大病を患い、さらにうつ病を経験され、2年間も引きこもられたというのは、計り知れない困難だったことでしょう。そこから立ち上がり、家業の社長としてご活躍されているお姿は、私たちZ世代が直面する様々な課題を乗り越える上で、大きな学びとなります。

【逆境を乗り越える哲学:自己との向き合い方】
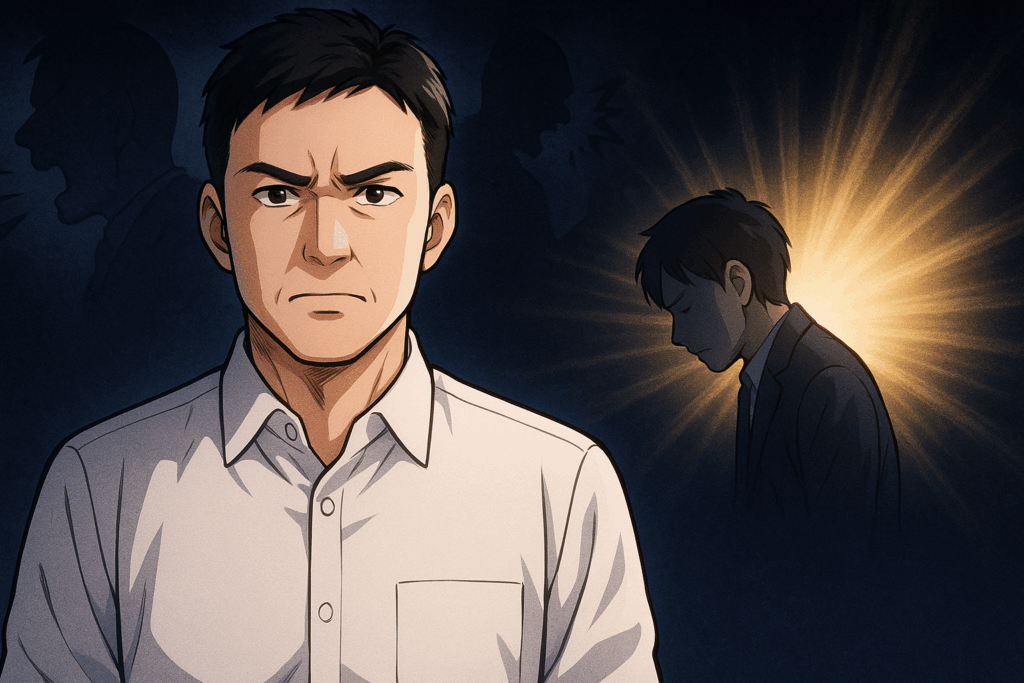
うつ病から立ち直ることができたのは、本当に多くの人々の支えがあったおかげだと認識しています。当時お世話になった人々、そして迷惑をかけた人々、様々な人々に支えられて今の自分があります。これは幸運だったと言えるでしょう。一方で、うつ病の原因となった当時の上司に対しては、今なお強い怒りの感情を抱いているのも事実です。このような感情も、私を突き動かす大きなエネルギーの一つになっています。
私自身は、自分に対してあまり期待しない人間です。自分を「未熟だ」「至らない」と評価することもあります。しかし、自分に対するそうした怒りのエネルギーも持ち合わせています。苦しい経験があったからこそ、立ち直れた部分もあるのだと感じています。自己肯定感はそれほど高くありませんが、良いものは良い、悪いものは悪いと、人にも自分にもはっきりと伝えられるようになりました。
以前の私は、言いたいことを言えなかったり、分かっていないのに「分かりました」と答えてしまう人間でした。しかし、様々な経験を経て、今は恥ずかしげもなく本音で話せるようになりました。これは、言いたくても言えない人が世の中に多く存在することに気づき、私自身が変われたからこそ理解できたことです。どん底まで経験したからこそ、今の「やるしかない」という強い覚悟が生まれたのだと感じています。
取材担当(高橋)の感想
中村社長は、過去の苦い経験やネガティブな感情までも、今の行動のエネルギーに変えられていることに驚きました。多くの人が挫折や失敗で立ち止まってしまう中で、自身の「弱み」や「不完全さ」を隠さず語り、それを強みに変えていく姿勢は、私たち若者にとって非常に学ぶべき点だと感じました。この「反骨心」こそが、社長の原動力なのだと思いました。

【日々直面する経営課題と未来への挑戦】
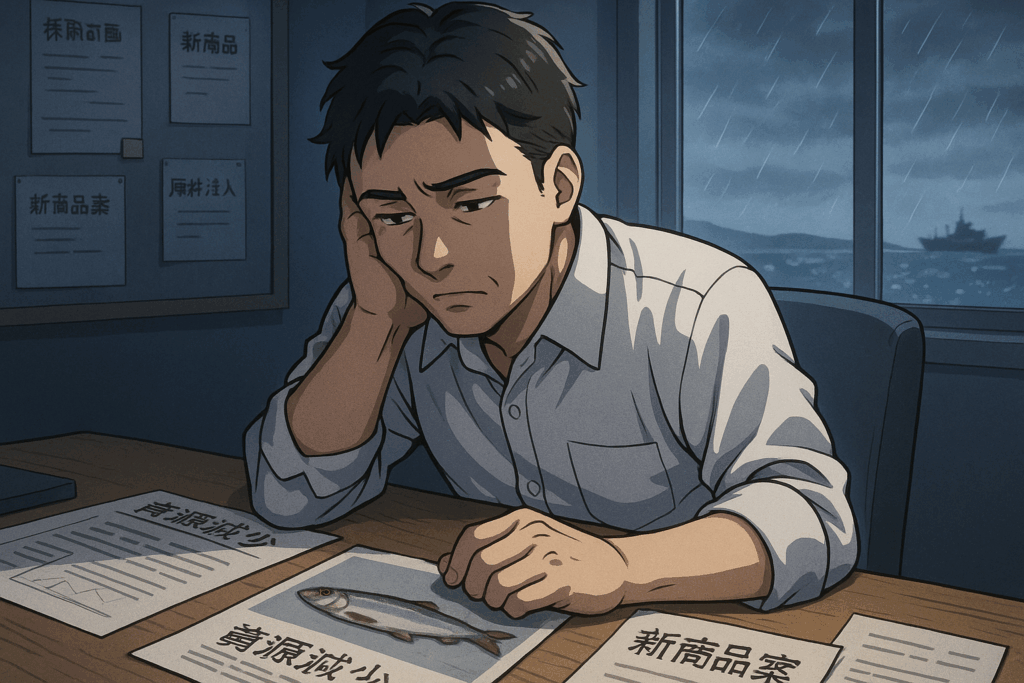
経営者の仕事は「華やかである」と思われがちですが、実際には困難に直面することも多く、日々試行錯誤の連続です。社員の仕事の割り振りや、目標と実際の結果のズレをどう埋めるかなど、細かいことも含めれば課題は山積しています。
現在、私たちが直面している大きな課題は、社員の採用です。少しずつ人は増えていますが、まだ十分ではありません。また、事業面では、みりん干しの主力商品である「カラフトししゃも」の確保が年々困難になっていることです。これはアイスランドやノルウェーなど海外からの輸入に頼っている魚ですが、過剰な漁獲や海水温の上昇、クジラやマグロといった大型魚による捕食の影響で、資源が枯渇しつつあります。
当社売上の7割から8割をカラフトししゃもみりん干しが占めているため、これは会社存続に関わる「死活問題」です。このリスクを限りなくゼロにするためには、他の魚でカラフトししゃもに代わるみりん干しを開発するか、あるいはみりんに頼らない、全く新しい事業を立ち上げていく必要があります。課題は多岐にわたりますが、一つ一つ着実に対処していく所存です。
取材担当(高橋)の感想
創業100年を超える老舗企業である中村海産様が、これほど具体的で深刻な課題に直面していることに驚きを隠せませんでした。特に主力商品の資源枯渇という外的要因は、一企業ではどうにもならない大きな壁であり、その中で新たな事業戦略を模索されている姿に、経営の厳しさと、それでも前向きに進もうとする社長の強い意志を感じました。

【自律を促す人材育成:考える組織を目指して】
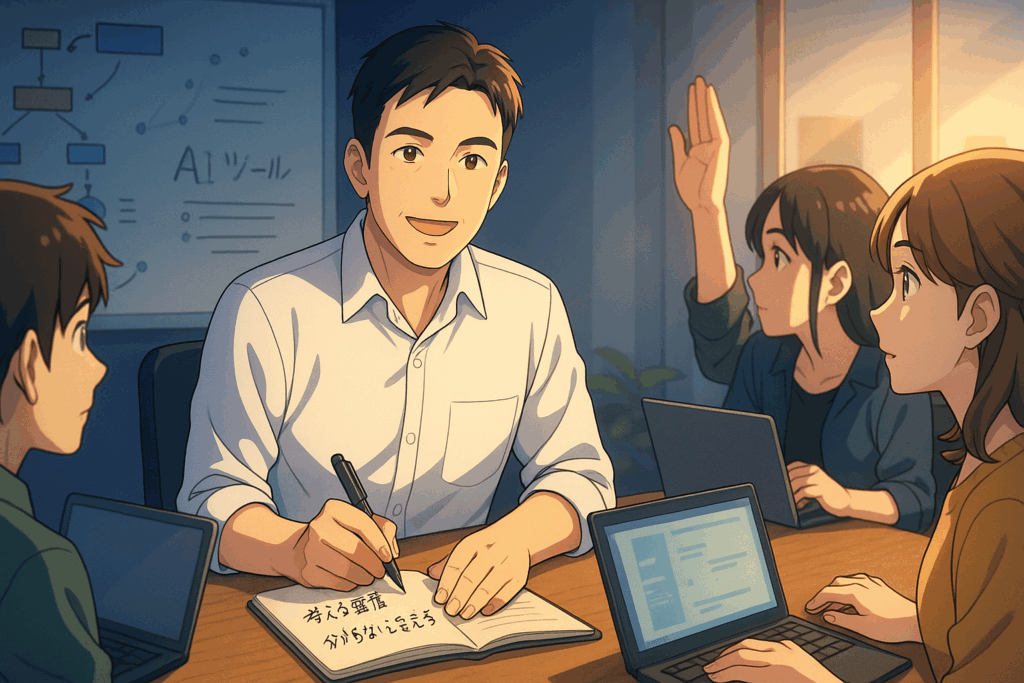
社会人になる皆さんには、ただ指示された通りのことをこなすだけでなく、常に「何か自分にできることはないか」と、プラスアルファを考える姿勢を持ってほしいと考えています。そして、「分からないこと」を「分からない」と、臆することなく言えるようになることが非常に重要です。何が、どこが分からないのかを具体的に言葉にすることで、理解が深まり、自身の成長にもつながります。
当社では、社員には常に自ら考え、行動する習慣を身につけてほしいと願っています。例えば、新しいデジタルコンテンツの制作や情報発信の取り組みにおいても、外部の専門家に全てを任せるのではなく、社員自身が主体となって試行錯誤を重ねることを重視しています。AIツールなどを活用して、動画の再生回数を増やす方法や、コンテンツのフックとなる要素を分析し、社員同士で議論しながら進めています。
楽をしようと思えば外部に頼ることも可能ですが、それでは社員の考える力や、自分で解決策を見つける力が育ちません。時間をかけ、自ら試行錯誤を重ねることで、ある一定のレベルまで到達すれば、あとは自動的にできるようになるものだと信じています。社員一人ひとりが自律的に学び、成長することで、会社全体としての持続的な強さが生まれると考えています。
取材担当者(高橋)の感想
中村社長は、社員の方々に「考える力」と「行動力」を身につけてもらうことを何よりも大切にされていると感じました。分からないことを恐れず、自ら課題を見つけ、AIのような新しいツールも活用しながら解決策を探求する姿勢は、まさに現代の企業に求められる人材育成のあり方だと思います。短期的な成果だけでなく、中長期的な視点で社員の成長を促す中村社長の哲学は、私たちZ世代が社会で活躍するための重要なヒントとなるでしょう。










