株式会社ニコン日総プライムは、「すべての人が活躍できる社会を創造する」をミッションとする人材サービス企業です。私たちは、「働き続けられる社会を創造し、日本の豊かさを取り戻す」ことをパーパス(存在意義)として掲げています。働く意欲のある方々の新たな挑戦と活躍を支援し、世代と時代を超えて、働く人たちが共鳴し合える社会の創造を目指しています。
弊社の事業領域は「人材サービス事業」と「キャリア開発事業」の2つに分かれています。キャリア開発事業においては、外的・内的な要因が複雑に絡み合う移行期のミドルシニア・シニア人材に特化した支援を行い、主体的なキャリア形成を促進できる機会を提供しています。私たちは、すべての働く人が活躍を続け、お客さまの事業成長を促進させる社会の創造を目指しています。
<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>
【シニア活用を最大化するための「二刀流」ビジネスモデル】
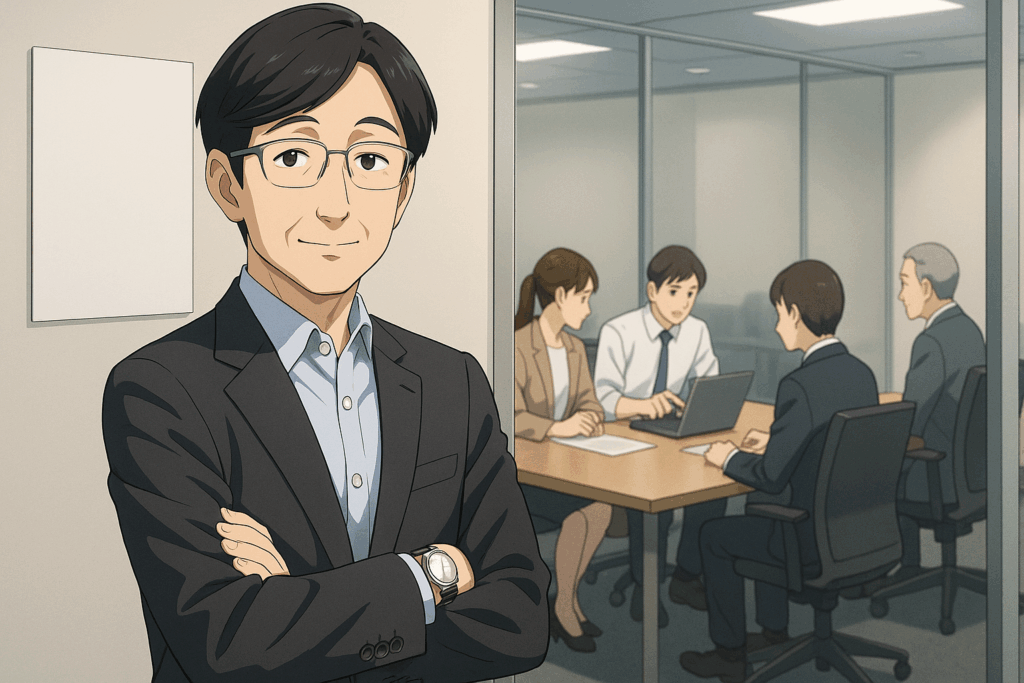
弊社の最も大きな目的は、シニア人材をしっかり活用することにあります。具体的には、シニアの方々の仕事を開拓し、適切な職場にご紹介していくことが最大の目的です。ただ、シニア人材の活用だけでなく、一般の若年層を対象とした人材派遣も並行して行っています。現在、シニア層向けと若年層向けの事業の割合は、おおむね半々です。
弊社のシニア人材は、親会社であるニコンで定年(60歳)を迎えた後、再雇用の形で弊社へ移籍してきます。現在、約700名のシニア人材が活躍しており、その多くは、これまで培った知識や経験を生かしてニコンの業務に従事しています。一方で「新たなフィールドで挑戦したい」という方には、ニコングループ以外の企業や自治体など、活躍の場を広げる支援も行っています。
このシニア層と若手層の両方を扱う「二刀流」のビジネスモデルは、人材派遣業界においてほとんど見られない新しいスキームです。弊社がこのスキームを立ち上げてから約5年が経過しました。このモデルは、日本の少子高齢化や人手不足という社会課題に対応し、シニアの雇用を創出するとともに、数の少ない若年層の雇用も並行して支える重要な役割を担っていると考えています。
取材担当者(高橋)の感想
シニア人材の活用を目的としつつ、事業として成立させるために若手派遣も行う「二刀流」モデルは、まさに現代日本の人口構造の課題に正面から取り組むものだと感じました。特に、ニコンの定年後の再雇用の受け皿となりながら、「ニコンの外」での活躍まで支援している点に、社会的貢献の高さを見ました。立ち上げから約5年という新しさにも驚かされました。

【シニア人材の活躍の場と意識改革の必要性】
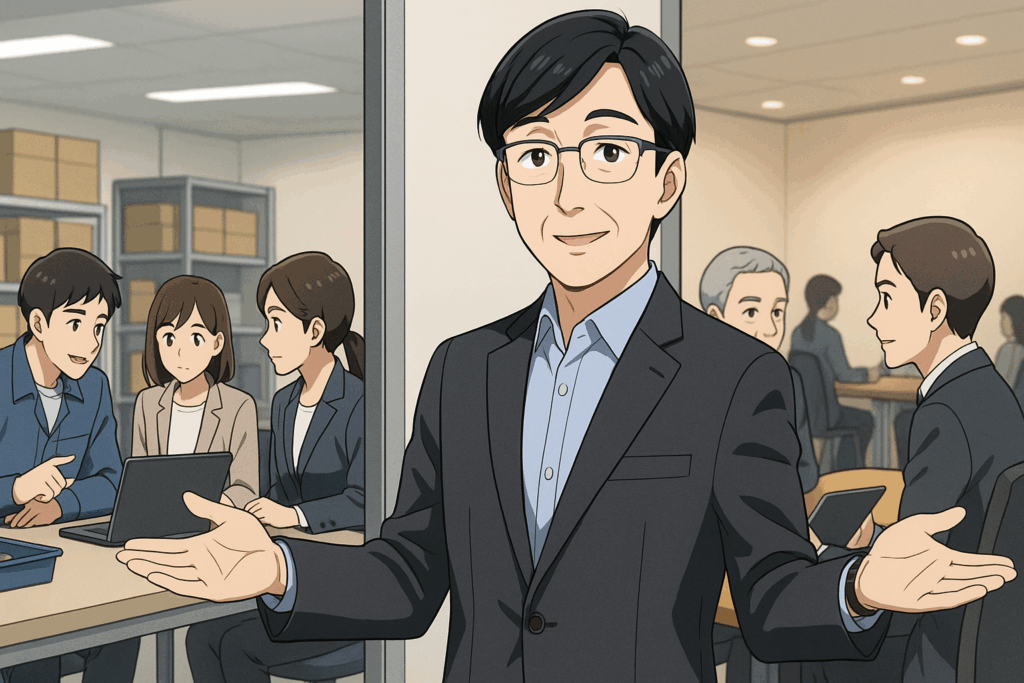
現在、ニコングループ外で働いているシニア人材は、約100名弱というイメージです。大企業で働いてきた方が、再び大企業で働くというルートはほぼないのが現実です。そのため、弊社がシニア人材を派遣しているのは、中小企業やベンチャー企業、そして地方自治体など、社会で人材が不足していて**「シニア人材でも歓迎したい」と言ってくださるところが多いです。特に地方、すなわち大阪のような大都市ではない小規模自治体では、圧倒的に人手が不足しています。弊社も地方創生の流れに合わせて連携を進め、実際に10名弱の人材を地方に送り込み、地域活性化に貢献しようとしています。
しかし、シニア人材の活用には難しい課題もあります。実際に就労しようとしても、受け入れ体制が整っていない、あるいは現地で想定していた職務が用意されていないといった事態に直面することもあります。
最も越えていかなければならない課題の一つは、やはり働き手であるシニアの意識を変えることです。大企業で長く働いてきたシニアは自社以外の環境を知らず視野が狭くなりがちで、過去の成功体験や自信が新しい環境への適応を難しくすることがあります。そうなると、小さな会社では周囲から敬遠されてしまいます。そこで弊社では、シニアの方々に対し、謙虚に**「みんなから可愛がられるシニアになってください」**というテーマで、マインドセットに関する研修を行っています。
さらに、受け入れ先の経営者側にも意識改革が必要だと感じています。経営者の中には、シニアに対して「頑固で融通が利かない」と敬遠する方もいます。しかし、受け入れ側も意識を変え、経験を持つ人材を活用する門戸を広げていただかないと、社会全体でのシニア活用は難しくなると考えています。
取材担当者(高橋)の感想
シニアの活躍の場が中小企業や地方に集中している現状は、日本の構造的課題を浮き彫りにしています。人材を送り込むだけでなく、働く側の意識と受け入れる側の意識の双方を変えていく取り組みが印象的でした。長年のキャリアで培ったプライドを、新しい環境に合わせて「可愛がられるシニア」へと転化していく姿勢は、年齢を問わず求められる柔軟性だと感じます。

【若手採用戦略と環境の変化】
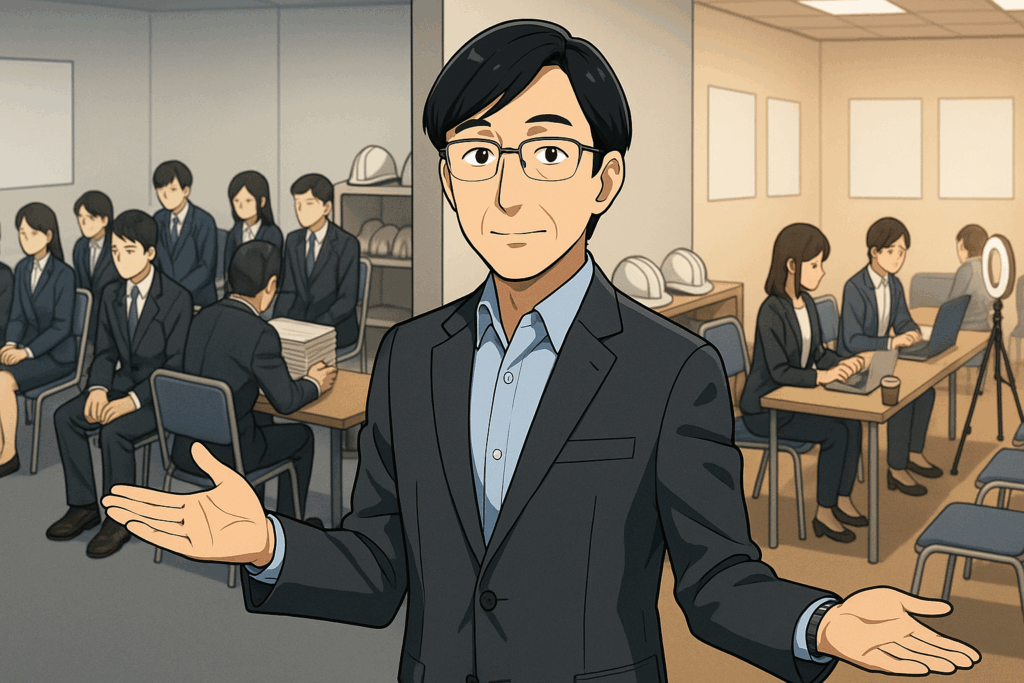
若手の人材は、基本的に中途採用を中心に行っており、新卒採用は現在実施していません。募集方法としては、求人広告や採用サイトなど、一般的な派遣会社と同様に多様な媒体を使っています。若手社員の主な就業先は、親会社の日総工産(製造業に強みを持つ会社)のネットワークを通じた製造系への派遣や、ニコンへの派遣です。
採用を取り巻く環境は大きく変わりました。かつては「就職氷河期」と呼ばれる時期があり、当時は各社が採用を絞っていたため、行き場のない方々が相当数いました。昔は採用広告費を多くかけなくても人が集まりましたが、現在は若年人口の減少により、完全に売り手市場へと転じています。その結果、弊社はあらゆる採用手法を用い、募集費用を積極的に投下しなければ対応できない状況です。経営者が若手を好む傾向があるのも事実です。若手は伸びしろが期待でき、活力があるため歓迎されやすい一方で、経験豊富なシニアよりも“白地に色をのせやすい”という見方が働く側面もあります。
取材担当者(高橋)の感想
若手の採用手法は一般的な派遣会社と同様である一方、シニアはニコンからの再雇用が中心という異なる二つの採用導線を運用している点に、この「二刀流」ビジネスのマネジメントの難しさと妙味を感じました。氷河期から現在の売り手市場への完全な転換という実感値も、就活生として強い示唆になりました。

【人生100年時代のキャリア形成と「変身資産」の重要性】
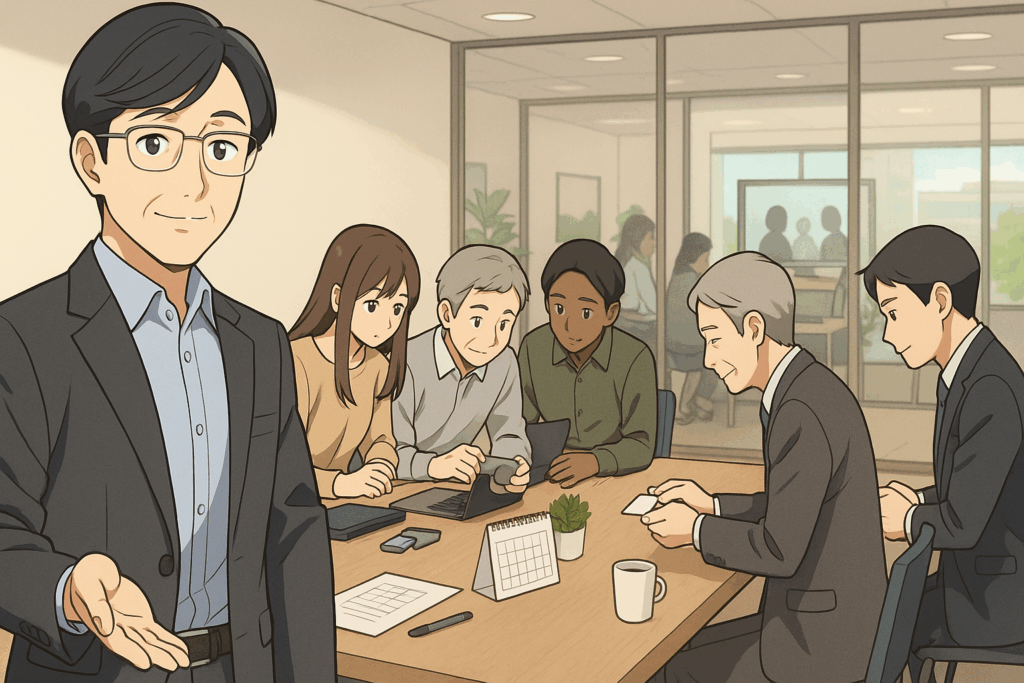
弊社の目的はシニアの活躍最大化であり、その実現のために多様な働き方を模索しています。例えば、従来の「人材派遣」という枠組みにとどまらず、特定スキルを持つシニア人材を、そのスキルを必要としている複数の会社に紹介する「人材シェアリング」のような働き方です。A社は月曜日、B社は火曜日といった形で働くイメージになります。あるいは、若手のチームにシニアがいることでまとまりが出る、若手×シニア、さらには外国籍人材との多様な組み合わせ(ダイバーシティ)を通じて、日本社会が元気になっていくようなビジネスの広がりを強く望んでいます。
人生100年時代、これからの若い人たちは、一つの会社にとどまらず、働き方を変えたり学び直しをしたりするキャリア形成が求められます。リンダ・グラットン氏の著書『LIFE SHIFT(ライフシフト)』でも述べられているように、自分を変化させ新しい環境に適応する力を「変身資産」と呼びます。
この変身資産の中で最も重要になるのが、人脈やネットワークです。これは、キャリアの転機や新しい挑戦に直面した際に大きな支えとなる資産です。一社で長年働いてきたシニアは、社内ネットワークに偏り、外に出たときに人脈が乏しく立ちすくんでしまうケースがあります。だからこそ、若い人たちは、学業だけでなく学生のうちから社会との関わりを広げることが非常に重要です。アルバイトやボランティアなどで積極的に人と関わることを意識し、人脈形成に努めることが、今後の長いキャリアを築くうえで必要不可欠だと考えます。単に働くだけでなく、その場で出会う人たちと信頼関係を築く(友人になる/意見交換を重ねる)といった積極的な関わり方が大切です。
取材担当者(高橋)の感想
シニアの知恵と若手のエネルギーを組み合わせてチームで成果を出すという未来像は非常に魅力的でした。私たち学生に向けた提言として、キャリアの最重要資産が「人脈・ネットワーク」であるという点は大きな学びです。アルバイトやボランティアを社会との接点づくりと捉え、出会いを関係性へと育てていく姿勢を実践していきたいと感じました。










