松田食品工業株式会社は、業務用味付油揚げ、大豆製品、寿司・おでん具材、冷凍惣菜の製造を手掛ける食品メーカーです。来年は創業80周年を迎えます。特に、いなり寿司の味付け油揚げでは全国各地の食文化に合わせた約300種類もの製品を開発しており、地域ごとの味覚に対応するきめ細やかさが特徴です。コンビニ、回転寿司チェーンやスーパーマーケットで目にするいなり寿司の皮は、当社及びグループ製品であることが多く、日本の食卓に深く根差しています。
国内に3社、海外には中国大連に1社のグループ会社を展開しています。海外工場はアジアやヨーロッパにも製品を輸出しており、味付け油揚げメーカーとしては珍しいグローバルな事業展開をしています。現在、グループ全体で約1000人の従業員が活躍しており、人々の食を支えるだけでなく、その豊かな食文化を未来へと繋ぐ役割を担っています。今回は、300種のいなり用味付け油揚げに象徴される多品種開発の舞台裏と、中国・欧州へ広がるグローバル展開の狙い、そして創業80周年を見据えた“日本の食文化を未来へつなぐ”次の一手について、代表取締役社長・松田様にじっくりとお話をお伺いしました。
<聞き手=高橋宏甫(学生団体GOAT編集部)>
【社長が歩んだ独自の道:家業を継ぐまでの道のり】
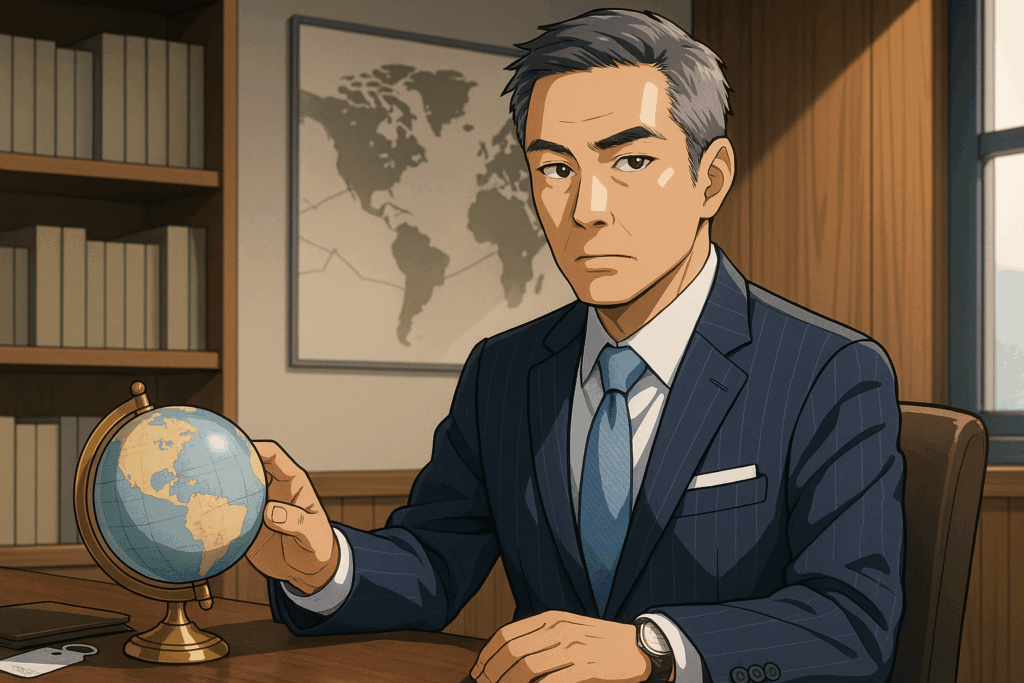
松田食品工業の3代目社長である私は、2024年に社長に就任しました。私の道のりは決して一直線ではありませんでした。幼い頃から家業を手伝うことに反発を覚えた私は、自由を求めアメリカへ留学しました。運良くカリフォルニアの大学で学び、その地で「インディペンデント(独立)の精神」を深く考えるようになりました。それは、優れた他者を目指すのではなく、自分自身は何者であるか、どのような点で人と異なる価値を発揮できるのか、海外生活はその点を深く探求することの重要性を教えられた経験でした。
帰国後もすぐに家業を継ぐことはせず、大学院へ進学しました。その後は金融業界、特に外資系の投資会社でファンドマネージャーを目指し、数十億、数百億という資金を動かすダイナミックな仕事に憧れていました。当時は日本に「M&A」という言葉が浸透し始めた時代であり、自身の夢を追い求める日々を過ごしていました。
しかし、様々な巡り合わせを経て、最終的に家業である松田食品工業に入社しました。以来20年間以上、グループ会社のあらゆる現場を経験し、汗を流してきました。私が2年前に社長に選ばれたのは、この全現場での経験が評価されたからではないかと考えています。現在、グループ全社の社長を務めており、日本の食文化を世界に発信し続けています。
取材担当者(遠藤)の感想
社長ご自身の言葉から、幼少期の家業への反発、アメリカでの「独立」の精神の確立、そして金融業界での夢と、非常に多様な経験を積んでこられたことが伝わってきました。一見すると家業とは全く異なる道を目指されていた方が、最終的に家業の現場で20年以上を過ごし、その経験が3代目社長としての信頼を勝ち得たというお話は、私たち学生にとっても「自分の人生をどう生きるのか」という問いに対する一つの示唆を与えてくれるように感じました。

【企業成長の原動力:「人材」を「財産」と捉える哲学】
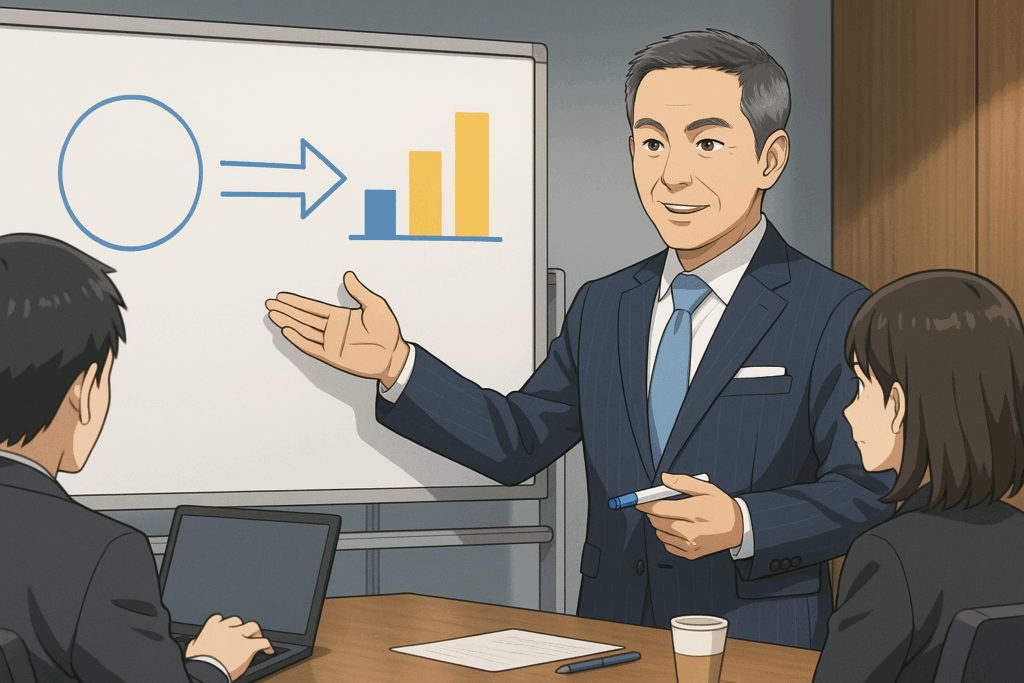
松田食品工業が大切にする価値観の一つに、「人の成長なきところに企業の成長はない」という強い信念があります。これは、社員一人ひとりの成長こそが会社の成長に繋がるという考え方であり、そのためには「学びを止めないこと」が不可欠だと私は強調します。学生だから勉強するのではなく、いくつになっても学びを止めない限り、人の成長は止まらないと私は考えます。会社に勤める人材の成長なくして、この会社、企業の成長、そして未来はありません。
また、私は世間一般で使われる「人材(材料の「材」)」という言葉に対し、「人財(財産の「財」)」であるべきだと語ります。会社にとって社員は、利益を生み出すための「材料」ではなく、かけがえのない「財産」であるという哲学です。だからこそ、会社は社員が学び、成長できる環境を提供し、その成長が会社の発展を後押しするという、共存共栄の関係を目指しています。
この理念は、国内各地、さらには中国大連に広がる多様なグループ会社、文化や言葉の異なる従業員にも共通認識として浸透させるよう、私は自らアピールしています。働き方改革が進む現代において、単に休日を増やすだけでなく、その時間を自己成長のための学びに充てることの重要性も促しており、社員の人間的成長を深く願っております。
取材担当者(遠藤)の感想
人事担当者の方から以前「人材は材料ではなく財産である」というお話を伺い、深く共感した覚えがありましたが、社長ご自身からも改めてその真意を直接お聞きし、その価値観が会社全体に深く浸透していることに感動しました。個人の成長が会社の成長に繋がるという考え方、そして学び続けることの重要性は、就職活動を控える私たち学生にとっても、会社選びの重要な指標になると感じました。

【「段取り八割」と「苦労はありがたい」の精神】
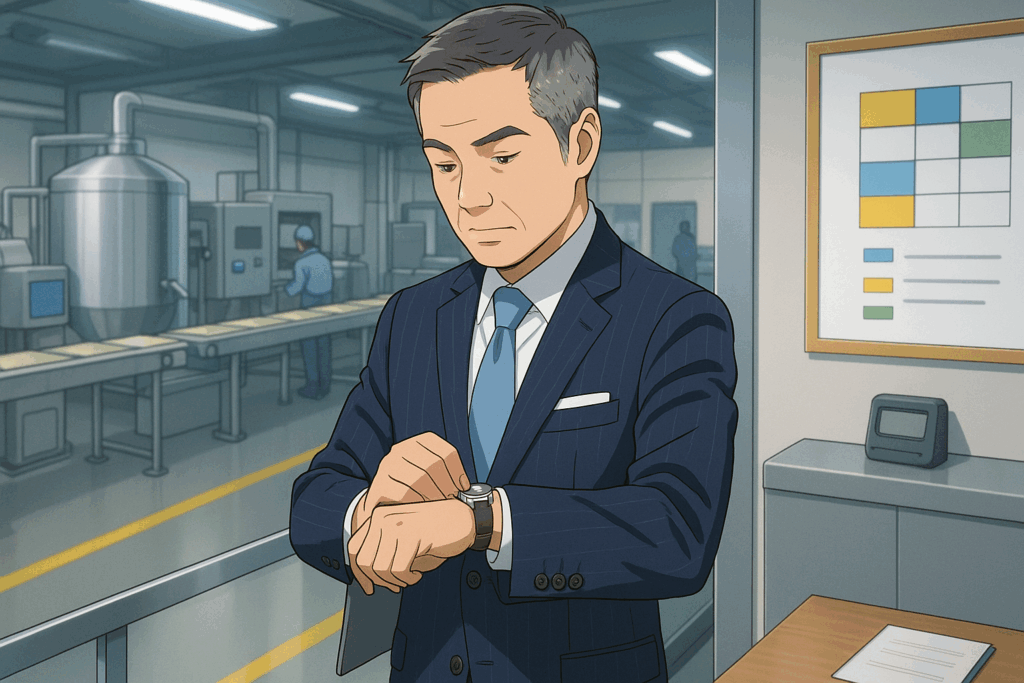
私が会社経営、そして人生において非常に重視しているのが「良い結果は、良い準備と段取りで決まる」という教えです。特に製造業の現場においては「段取り八割」という言葉を教えられてきました。良い結果の8割は事前の準備によって決まり、残りの1割は努力と実行力、そして予期せぬ出来事に対応するための最後の1割の余裕が必要だと私は説きます。これは、日々の業務計画から人生の目標設定まで、あらゆることにおいて良い準備を怠らないことの重要性を示しています。
さらに、私は「苦労」に対する独自の解釈を持っています。一般的にネガティブに捉えられがちな「苦労」を、「ありがたいもの」として受け止めるべきだと私は語ります。困難や試練に直面した時、「しんどい」「辛い」と捉えるのではなく、「これは自分を成長させるための機会だ」と感謝の気持ちを持って向き合うことが、乗り越える原動力となると私は考えます。
「登れない山はない」という言葉に象徴されるように、人間には登れない山はありません。エベレストでさえ、多くの人が登頂を目指し、成功しています。困難を「しんどい、辛い」と捉えるか、あるいは「乗り越えよう」と前向きに取り組むか。その捉え方一つで結果は変わります。現在の辛さや困難は、与えられた試練であると捉えるべきです。これを乗り越えた先にこそ成長があると考えれば、前向きに取り組む意欲が湧いてくるでしょう。苦労を苦労とは捉えていません。もちろん、現実として辛いと感じる瞬間もありますが、私に立ちはだかる困難は全て、ありがたいものとして受け止めようと努めています。
取材担当者(遠藤)の感想
社長の「段取り八割」という言葉には圧倒されました。取材前、私自身も準備をしてきたつもりでしたが、社長の徹底した準備の姿勢には学ぶことばかりで、良い結果を生み出すには準備が不可欠であることを改めて痛感しました。また、「苦労はありがたい」というお話は、とにかくネガティブに捉えがちな困難に対する見方を大きく変えるきっかけとなりました。このポジティブな思考は、今後の私の人生においても大きな指針となることでしょう。

【若者へのメッセージ:夢を持ち、強みを伸ばせ】
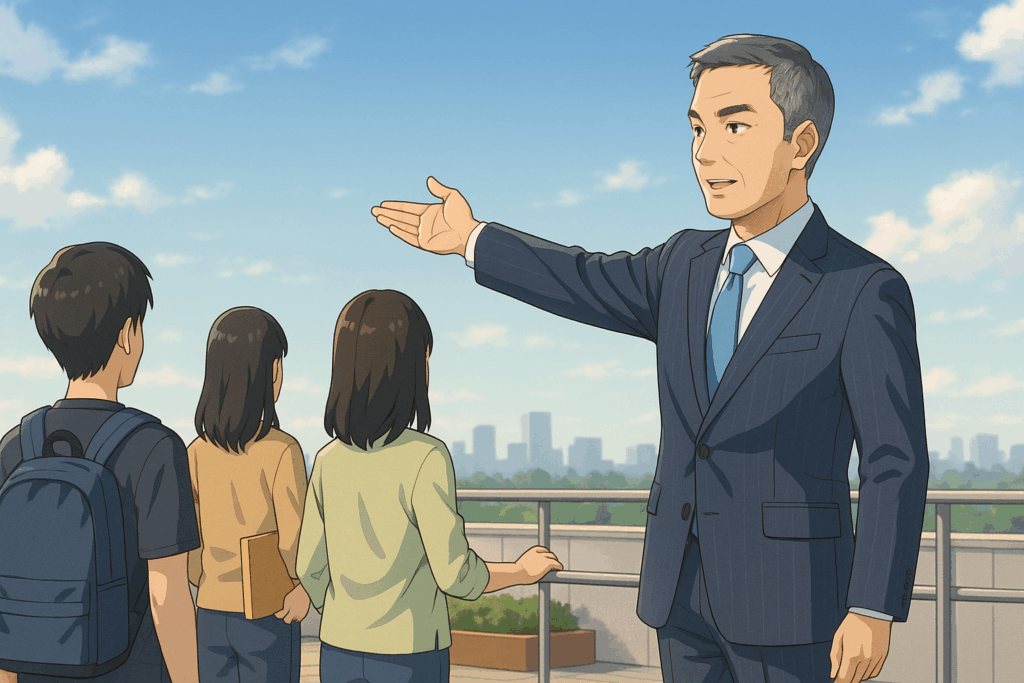
就職活動に臨む学生たちに対し、私はまず「自分の持った夢に人生は概ね比例する」というソフトバンクの孫正義氏の言葉を引用し、夢や目標を持つことの重要性を説きます。現代の若者には夢を持てない、どうせ頑張っても無駄だと考える傾向が見られますが、たとえ小さなことでも、自分の人生をどのように歩みたいかという明確な目的を持つことが大切だと伝えています。夢を持つ瞬間から、その実現に向けた行動や思考が始まるのです。
次に、自身の「強み」を徹底的に伸ばすことの価値を語ります。学生時代はオールマイティに優秀(例えば「5教科オール5」なんて言葉)であることが求められがちですが、社会に出ればそうではないと私は指摘します。コーンフレークのパッケージ裏にある栄養素の五角形のグラフのように、すべての分野でバランスを取る必要はなく、自分が得意とする分野をどこまでも突き詰めるべきだと私は思う。弱みを克服しようとするよりも、強みを伸ばすことに時間を費やす方が、人生を豊かにし、成功へと導く鍵となります。
人生はあっという間に過ぎ去るものであり、特に大学時代は有限で貴重な時間です。この時期にこそ、自分の強みや可能性を深く見つめ直し、将来に対する確固たる「志」を持つことが、後悔のない人生を送る上で不可欠だと思います。
取材担当者(遠藤)の感想
現代の若者、特に私たち学生は、将来への不安や福利厚生ばかりに目を奪われ、夢を持つことや会社の理念に目を向ける機会が少ないという課題を私自身も感じていました。社長の「夢を持て」「強みを伸ばせ」というメッセージは、まさに今、私たちが聞くべき言葉であり、就職活動におけるミスマッチを防ぐ上で、社長の思いを聞くことの重要性を改めて認識させられました。この言葉を胸に、私たちも自身の強みを伸ばし、社会に貢献できる「人財」を目指していきたいと強く思いました。










