大江ノ郷自然牧場は、鳥取の素晴らしい自然を背景に、見て、食べて、体験する、「農」と「食」のナチュラルリゾートを提供する。私たちが大切にする食づくりは、鶏たちが教えてくれた。自然飼育で健やかに駆け回る鶏は、空気、水、環境、そして愛情を持って育てることで、健康的な卵を産んでくれる。食品づくりや料理においても卵づくりを手本とし、自然に寄り添い、地域の方々のご協力のもとで行っている。パンケーキを提供するカフェ(ココガーデン)やレストラン(大江ノ郷テラス)、体験教室など、いくつもの食が楽しめるリゾート空間を提供し、地域と共に日本の農業を未来へ繋ぐことを目指している。今回は、「農と食のナチュラルリゾート」が生まれた背景と、地域とともに紡ぐこれからの挑戦について、代表取締役社長・小原様にじっくりとお話を伺いました。
<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>
【創業の原点と、業界の「当たり前」への挑戦】
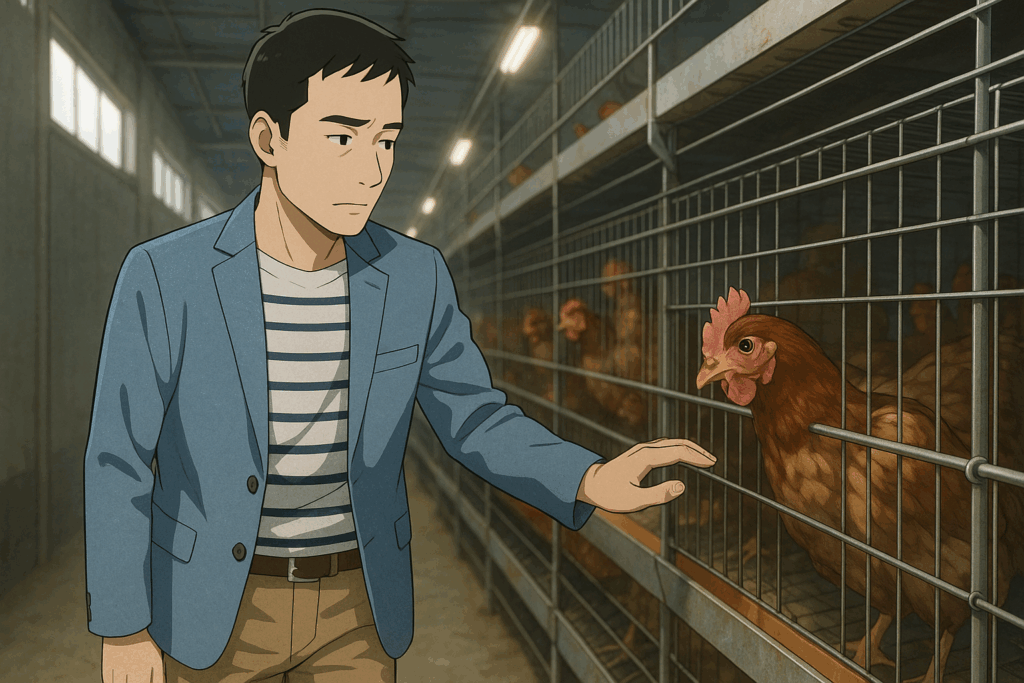
創業は平成6年です。私自身が創業者で、もともと父が養鶏をしていたことが、この養鶏の世界に入る一番のきっかけでした。20代前半に業界に入った頃、世の中の養鶏の99%がケージ飼いでした。ケージ飼いとは、鶏をケージに入れて人が管理するシステムのことです。管理が容易で生産性も高いため、日本では主流の方法でしたが、私も当初は当たり前のようにこのやり方で進めようと考えていました。
しかし、20代の中盤頃から、このケージ飼いというシステム自体に疑問を感じ始めました。工場のような場所で鶏を飼っていたため、「鶏を飼っている」という感覚が薄れ、鶏たちが道具のように感じられました。さらに、鶏たちがストレスから殺し合い、死んでいく様子を見るうちに、「これをずっと続けていくのはどうなのだろう」と、漠然とした違和感が芽生え始めました。
ただ、その状況を打開する力は当時の私にはありませんでした。その頃に知った平飼い(鶏が自由に動き回れる広い場所で飼う方法)をやりたいと父に話しましたが、「現実的ではない」「売り先がない」と反対されました。若造の夢物語だと見なされ、売れないものを作るのは会社として難しいという現実を思い知らされました。そこで私は一度、父の会社を辞めてサラリーマンになり、もう一度自分自身で考え直そうと転職しました。
取材担当者(高橋)の感想
業界の99%が採用する常識(ゲージ飼い)に対し、「鶏が道具のようだ」と感じた小原社長の感性は非常に鋭い。理想と現実のギャップに直面したとき、夢を捨てるのではなく、一度会社を辞めサラリーマンになるという「戦略的な撤退」を選んだことは、現状を変える力をつけるための学びの期間だったと理解できる。自分の信念を諦めず、その実現のために、別の視点から学ぶ行動力やチャレンジ精神は、特に就活生がキャリアを築く上で大きな学びになるだろう。

【地方を「商機」に変えた再挑戦と起業】
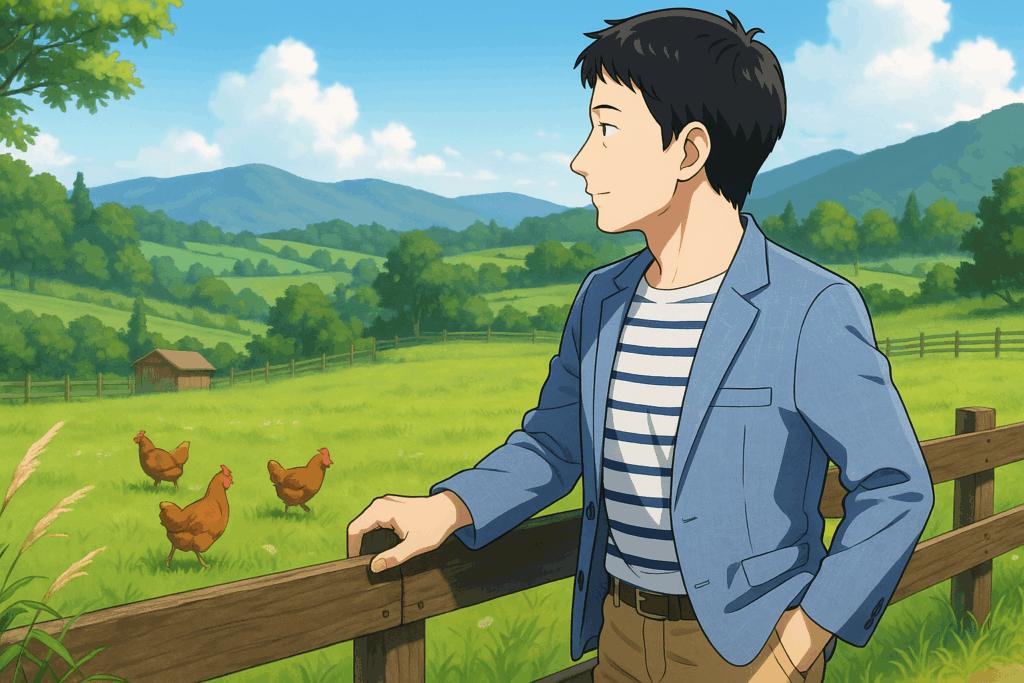
サラリーマン時代は、養鶏農家さんにひよこを届ける同業の仕事に携わりました。この仕事を通じて、養鶏経営を販売側という異なる視点から見る機会を得ました。さまざまな経営者のやり方を見ていく中で、「やり方次第で自分でもできる」というヒントと気づきがありました。20代後半でこの気づきを得て、父のもとでは諦めた平飼い養鶏でも、規模を小さくして自分一人で食べていくだけならやれるのではないかと考え始めたことが、再挑戦のきっかけでした。
特に、平飼い養鶏の価値について深く考えるようになりました。例えば、大阪のど真ん中で鶏を飼うのと、自然豊かな鳥取で飼うのとでは、どちらの卵に価値があるかといえば、おそらく鳥取の卵でしょう。一般的な土地の価値でいえば都会の方が高いですが、養鶏に関しては田舎の方が優位性があります。
私は鳥取が好きで、この生まれ育った場所こそが商機があり、プラスになる商売だと考えました。この「田舎」という要素こそが、自分の武器であり、一番の売りになると確信しました。県外に出ていたときは都会への憧れもありましたが、食べ物、空気、水、自然など、そばにあったものが本当に良かったのだと気づかされる機会が多くありました。鳥取から全国に向けて、この自然の中で育った卵を販売しようという思いが、最後の背中を押してくれました。そうして、本当に、たった一人で平飼いを始めたのが事業のスタートになりました。
創業当初は一人で始め、鶏が大きくなって親鳥も飼うようになると、やるべきことが増え、販売もしなければならず、かなりのフル稼働になりました。創業から4〜5年ほどは、近所の方や母に手伝ってもらいながら進めていました。社員という形ではありませんでしたが、2000年頃から社員を雇い始め、少しずつ社員が増えていきました。
取材担当者(高橋)の感想
一度は現実の壁に阻まれた平飼いの夢を、サラリーマンとしての販売側の視点を持つことで再構築したストーリーは、就活生がキャリアを考える上で示唆に富んでいる。都会の価値観が絶対ではないこと、そして**自分の生まれ育った地方の魅力を、市場における「武器」として捉え直す視点の重要性を強く感じた。固定観念にとらわれず、異なる角度から物事を見て新たな活路を見出す姿勢は、社会で生き抜くために非常に重要だ。

【辺鄙な地で夢を公言し実現した「卵のテーマパーク」構想】
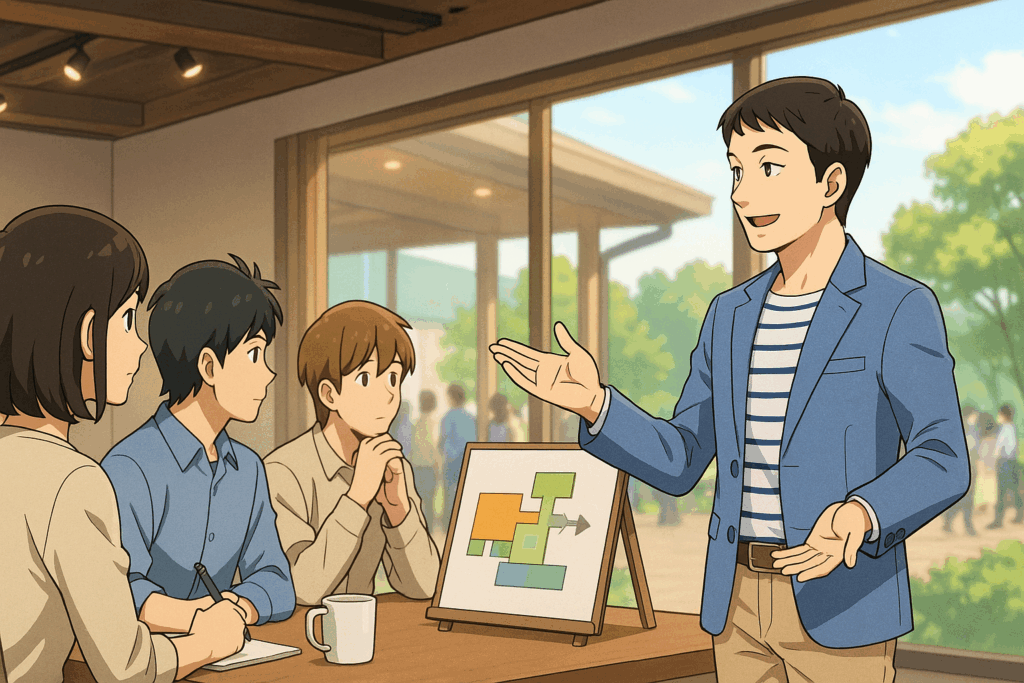
創業当初は、今のような施設を建てようとは一切思っていませんでした。最初は、人が来て卵を食べるといった体験ができる「観光牧場」を作りたいという小さな願いがありました。しかし、日本に鳥インフルエンザがやってきたことで、野鳥との接触リスクが高い観光牧場は実現が難しいと判断し、この道は断念せざるを得ませんでした。
ただ、自然豊かなこの場所にぜひ来てほしいという気持ちは変わりませんでした。そこで、観光牧場に代わるものを考え、2008年に小さな施設をスタートしました。16席のカフェと、牧場の卵を使ったスイーツや卵かけご飯を出すお店です。この時、心の中では「ここを卵のテーマパークのような場所にしたい」と漠然と思っていました。
当時、私たちが事業をしていた場所は、鳥取市からも離れ、道が行き止まりのようなところで、国道にも面しておらず、相当探さないと来られないような場所でした。そのため、「こんなところで何を寝ぼけたことを言っているのだろう」と思われるのが嫌で、その夢を口にすることはできず、心に秘めていました。
ただ、オープンしてみると、誰もが予想しないほど多くのお客様が来てくださいました。そこで、自分の夢が現実になるかもしれないと思い、夢は自分で思っているだけでは現実にならないと考え、社内の仲間にちゃんと話そうと決めました。私は、2020年に向けてここを観光地にし、当時の年間3万人から10倍の年間30万人に来ていただける場所にすると断言しました。これは鳥取の人口の半分に相当する方々に来ていただかなければならない規模でした。ありがたいことに、施設を増やし、この目標に共感してくれる若い社員がたくさん入社してくれた結果、2020年を待たずして、2018年には年間30万人の目標をクリアできました。コロナ禍前には年間35万人から36万人ほどのお客様に訪れていただくまでになりました。
取材担当者(高橋)の感想
「卵のテーマパーク」という夢を公言し、当時の来場者数の10倍という壮大な目標を掲げたことに、強いリーダーシップを感じた。その夢を社員と共有し、共に目標達成に向けて邁進した結果、それが予定よりも早く現実に変わったという話は、**ビジョン共有と目標設定の力の大きさ**を物語っている。現在の目標が鳥取県の人口を超える55万人であることから、常に挑戦し続ける原社長の姿勢に刺激を受ける。

【100年企業を目指すビジョンと、次世代への期待】
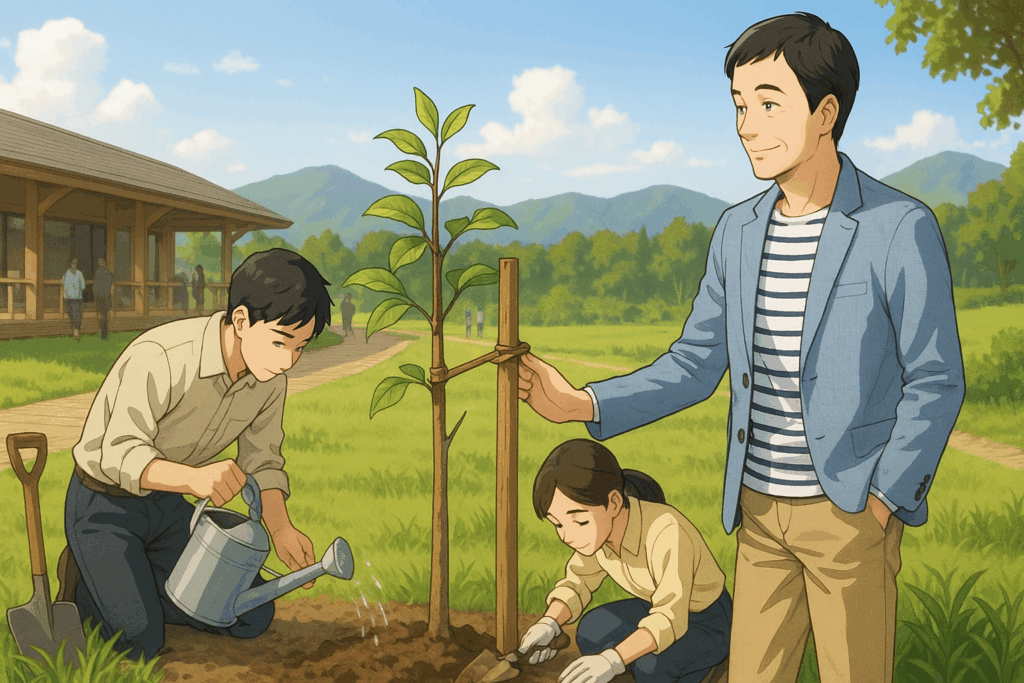
私たちが目指しているのは、「地域に愛されて100年続く会社」です。これは一貫して掲げている目標です。自分たちだけが良いのではなく、地域と共に持続可能な街を創りたいと考えています。私たちが100年続けば、その可能性が現実味を帯びてくるはずだと考えています。それが私たちの方向性です。
100年先は私が生きていないため、次世代に託すことになります。そのために何をするかという長期的な視点と同時に、短期的な目標も持ちながら、これから一つずつ実行していきたいと考えています。物事を見る際には、常に長期的な視点を持つようにしています。
私たちは、基本的に「鳥取から出ない」という方針を決めています。大江ノ郷自然牧場というブランドは、鳥取の自然の素晴らしさを伝えるというミッションを達成するために、鳥取にいることが最も良いと考えています。その地域を代表する会社になることが、私たちの理想です。鳥取の自然や美味しいものを付加価値としてお客様に届けたい。通販も行っていますが、来ていただくか、商品をお届けするかという形で、価値を高めていきたいと考えています。
若い社員の採用においても、地元でしかできない仕事であることに魅力を感じてくれる学生が多いようです。当社は養鶏だけでなく、お菓子、食品、今ではチョコレートまで製造しており、作っていないものがないくらい、さまざまなことをやっています。やることが多様化していますので、やりたいことが見つけやすい環境です。
また、ここは「これしかできない」という職場ではないため、社内で職種をいくらでも変えることができます。もし入社した職種が合わなくても、会社の風土が好きであれば、職種を変えて頑張ることができます。会社が変わっても、相手は人であり、上司も人であり、やる仕事が変わるだけで、本質的にはどの会社でもやっていることは同じはずです。そこが他社とは違う魅力かもしれません。
学生の皆さんには、「何でもいいので、何か一つをきちんと続けること」を大事にしてほしいと思っています。それはアルバイトでも、研究でも、遊びでも構いません。夢中になって打ち込めることをしっかり持ち、それをやり抜く経験を若い時に持つことが、社会に出てから大きな違いを生むと思います。
物事をすぐに切り替えてしまう癖があると、会社も切り替えてしまうことになりかねません。しかし、何か一つのことをずっとやり抜いた経験があれば、それが自信になり、どんな職種や会社で働く上でも必ず必要になる「やり抜く力」につながると信じています。
取材担当者(高橋)の感想
「鳥取から出ない」という決断と、地域に根差し、愛される100年企業を目指すビジョンに、地方創生に対する強い決意を感じた。また、学生へのアドバイスとしていただいた「やり抜く力」の話は、私自身の学生団体運営経験にも通じるものであり、非常に心に響いた。目標に向かって継続し、やり抜くことの重要性を、未来の社会人として行動する上で心に留めておきたい。










