株式会社サンテックは、オフィス家具、什器、機器の製造販売を行うメーカーです。親会社である内田洋行様のグループ企業であり、親会社のブランドであるオフィス家具のOEM/ODM生産を主に行っています。長年培ってきたスチール家具の開発・設計ノウハウに加え、薄板精密板金加工やパイプ加工といった独自の製造技術を保有しています。製品の企画開発から設計、製造、塗装、組立、梱包まで、お客様の多様なニーズにワンストップで対応できる一貫生産体制が最大の強みです。また、社員の誇りとなる会社を目指し、自社ブランド「&FREL」を立ち上げ、ホーム用家具のBtoC市場にも挑戦しています。
<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>
【社長就任までの経緯と当時の状況】

私が株式会社サンテックに赴任したのは、2013年7月です。当時私は46歳で、親会社の内田洋行から来ました。私がサンテックに来たきっかけは、2008年のリーマンショック以降、会社の業績が非常に厳しく、赤字決算が続いていたからです。親会社の方では経営計画部に在籍していたのですが、会社からサンテックの業績を見極める、つまりこのまま事業を継続していいのか判断するという重いミッションを負って、子会社の社長として赴任しました。
見極めというのは、このまま会社を続けて良いのか悪いのかを判断する役割でした。しかし、私は単に現状を持って「良いか悪いか」を判断するのではなく、会社の再建、もう一度浮上していくことを前提に、やれることは全てやろうと決意しました。やり尽くして浮上しなかったら、その時初めて「良いか悪いか」という決断を出すという覚悟で取り組みました。
私は親会社から来た人間であったため、プロパー(生え抜き)ではないことに対する社員の不安や距離感は多少なりともありました。そのため、社員の士気を下げないように、まずは親会社の「兜を脱ぎ」、サンテックで起きている全てのことを理解し、できるだけ同化しながら経営を進めるよう心掛けました。この経験が、その後の困難な挑戦の基盤になったと思っています。
取材担当者(高橋)の感想
赤字が続く会社の存続を左右する「見極め」の責任を負っての社長就任は、凄まじいプレッシャーだったと感じます。社員の方々の不安や距離感がある中で、組織の力を結集するために「親会社の立場を脱ぐ」という姿勢を示されたのは、困難な状況を打開するための強い意志の表れだと感じました。

【 V字回復の道のり:最も苦労した経験】
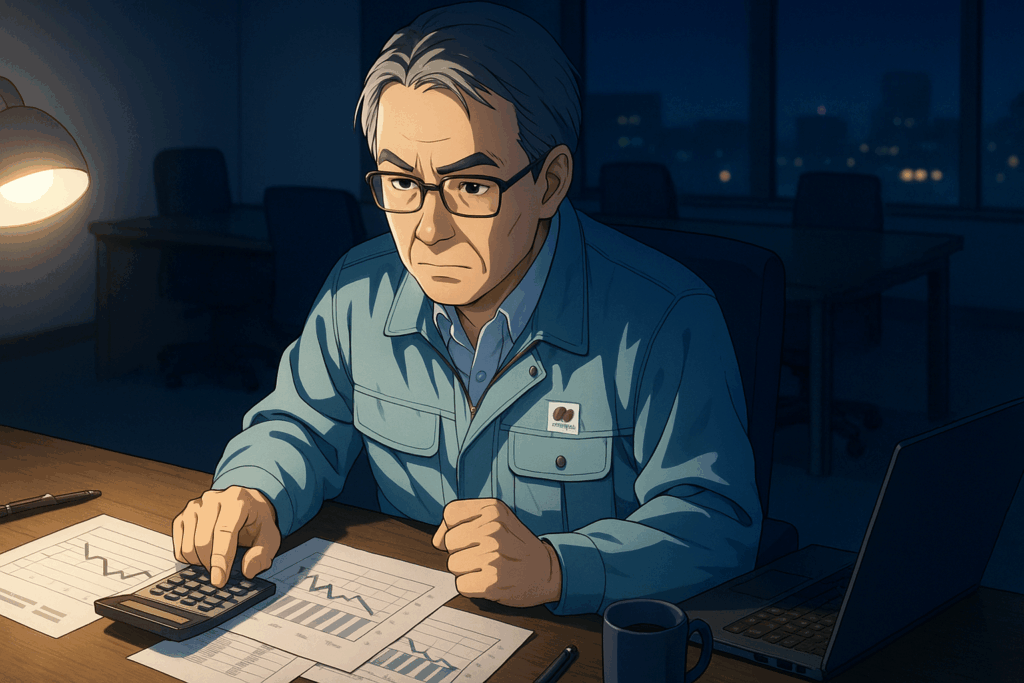
私が就任してから最も厳しかったのは、V字回復を実現するためのプロセスでした。V字回復をやるためには、一度全部、悪いものを出し切るということが必要です。私が赴任した1年目は、赤字が続いていたにも関わらず、さらに大きな赤字決算を計上しました。続く2年目、私は社内そして親会社に向けて「絶対黒字にすること」と宣言し、実行に移しました。この2年目が、背負うものが大きかったこともあり、最も厳しかったですね。
当時のサンテックは赤字が続き、社内の雰囲気は暗く、社員にも不安が少なからずありました。加えて、本社から来た、面識のない人間に対する距離感もありました。私は「孤独と緊張感の中で持てる力を最大限使って」経営に当たりました。経営者というのは孤独だとよく言われますが、社員の信頼を得て、黒字化を果たさなければならないという重責を背負っている感覚は非常に強かったです。
厳しい状況を乗り越えるためには、まず社員に「この人について行こう」と信頼してもらうことが重要でした。小さな成功や結果が出始めると、それが増幅するように信頼度が高まっていき、社員の活力ややる気も高まっていきました。そして2年目に黒字を達成した際、私が感じたのは達成感というよりは、「良かった」という安堵感の方が強かったです。同時に、「二度と赤字にはしないぞ」という強い決意を新たにしました。
取材担当者(高橋)の感想
孤独と緊張感の中で、V字回復という極めて困難なミッションを遂行されたというお話は、鳥肌が立つほどにすごいと感じました。そのような状況下で、社員に「この人について行こう」と思わせるための粘り強い根性や、信頼獲得への努力こそが、会社の再生を可能にした最大の力だったのだと理解しました。

【変化する事業環境への貢献と自社ブランドへの挑戦】
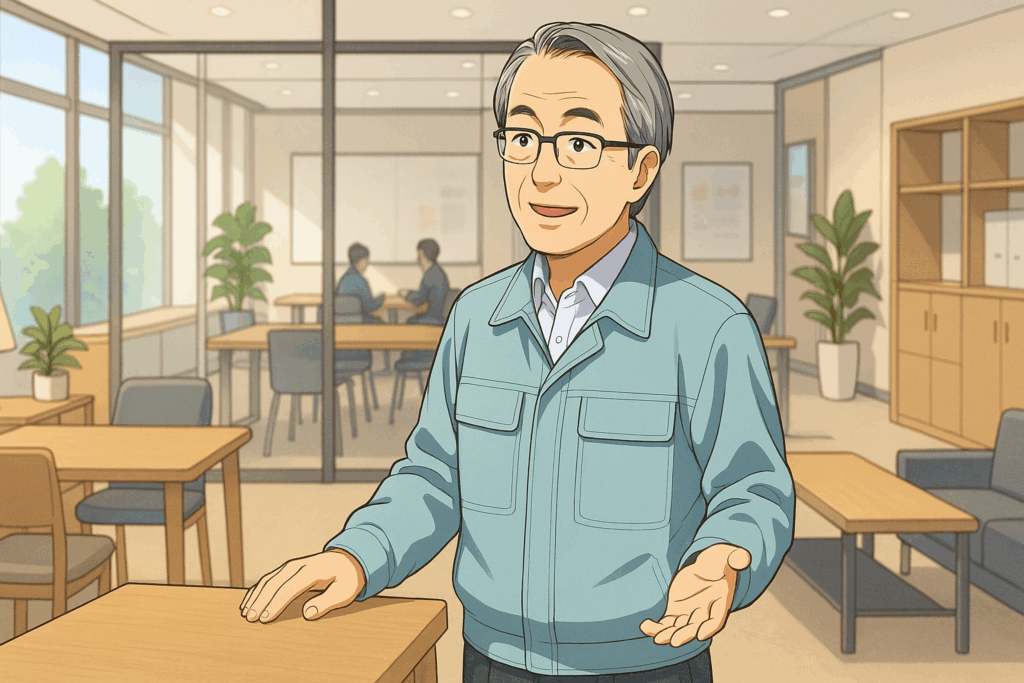
サンテックの主要事業はオフィス家具の生産であり、親会社の内田洋行のブランド製品を開発・製造しています。今、働く場や学ぶ場は大きく変わってきています。特にコロナ禍を経て、在宅勤務やハイブリッドワークが普及し、「せっかく出社してもらうのであれば、生産性の高いオフィスにしなければならない」という考えが強まっています。
オフィス環境への投資は、単に仕事の生産性や創造性を上げるというだけでなく、若手の採用や定着という面においても非常に重要視されています。オフィスの改築や新規投資は、今や経営者の重要事項の一つになっています。我々はオフィス家具の生産を通じて、お客様の価値向上を実現するお手伝いをしているとも言えます。
言い換えれば、この事業活動を通じて、お客様に貢献し、社会貢献や会社の存在意義を実感できています。また、我々は親会社のブランド製品をOEMで作る「黒子」的な側面がありますが、社員がより誇りを持てる会社にするため、独自のチャレンジとして約4年前から自社ブランド「&FREL」を立ち上げ、新規事業を展開しています。これはB2C(ホーム用家具)の市場ですが、立ち上げの苦労は尽きません。しかし、この挑戦は、新しい人材、特に若手メンバーの入社にも繋がり、精神的な高揚感を生み出していると感じています。親会社と同じB2Bの世界で戦うのではなく、家具を作るノウハウを活かし、現在の親会社と競合しないB2C市場を定めています。
取材担当者(高橋)の感想
サンテック様は、親会社様との安定的な関係性の中で、あえてB2Cブランドを立ち上げ、変化を恐れずに挑戦し続けている姿勢は、経営ビジョンである「成長し続ける会社でありたい」という強い思いがあるからだと感じました。

【経営者として大切にする「継続性」と「従業員ファースト」】
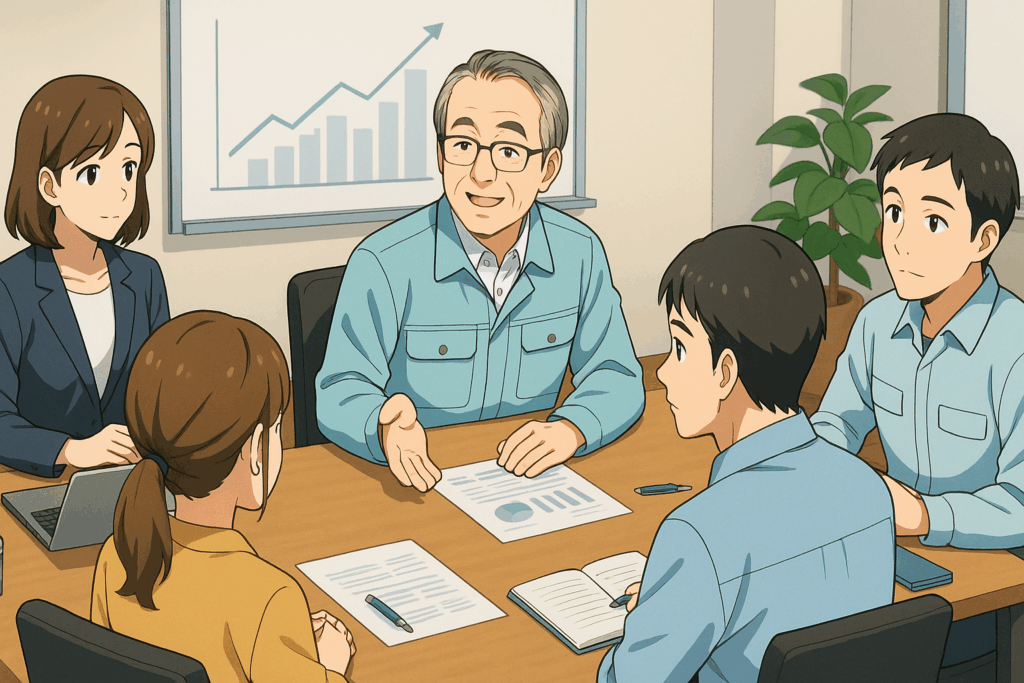
経営者として最も大切にしていることの一つは、「ゴーイングコンサーン」、すなわち企業の継続性です。設立から55年になるサンテックが事業を継続していくことは、そこで働く社員の生活を守るという意味でも非常に重要だと考えています。過去に赤字からの再建を経験したため、「二度と赤字にはしたくない」という思いが非常に強くあります。大きな不況が来ても、赤字に陥らないような、強固な事業構造や収益構造を作っていきたいと思っています。
事業を継続し、収益構造を維持・強化していくためには、短期的な視点ではなく、中長期的な視点での方針が不可欠です。私は、現況に満足して現状を維持してしまうと、その瞬間、成長が止まると思っています。世の中は常に進んでいるため、自分が立ち止まっているということは、相対的に見れば後退しているのと同じだと捉えるべきです。常に中長期の視点を持つことを重要視しています。
そして、もう一つ強く打ち出しているのが「従業員ファースト」です。会社は結局のところ、従業員の力の総和によって成り立っています。意欲のある社員に長く働いてもらうことで、会社の中の人的リソースや組織力は必然的に上がります。若手の早期離職が問題となる現代において、会社として社員の期待にきちっと応えていく姿勢が、社員の定着率向上にも繋がっていると感じています。この「従業員ファースト」は、この2~3年特に強く意識している部分ではあります。
取材担当者(高橋)の感想
「現状維持では相対的に交代している」という考えは、私たちが目指す方向性とも通じるところがあり、深く頷きました。また、会社の継続性を守るために従業員ファーストを打ち出し、若手の定着率向上に繋がっているという点は、私たちZ世代が求める「安心」と「成長」に応える素晴らしい経営方針だと感じました。

【学生時代に「やり切る」ことの重要性】
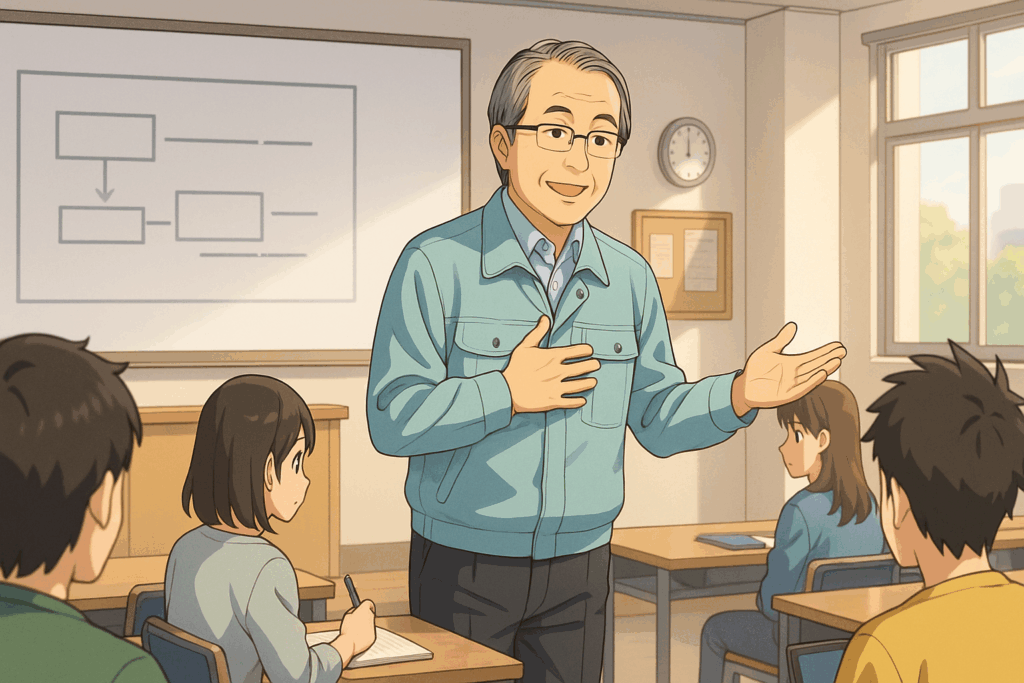
学生時代にやっておくべきこととして、まず、今皆さんが行っているような「同じ意思を持った仲間との活動やコミュニケーション」は非常に大切です。もちろん勉強は必要ですが、それ以上に仲間作りやコミュニケーションの経験は社会に出てからも必要となります。社会人になると、長い夏休みのような自由な時間はなくなります。大学生は圧倒的に自由な時間が多いので、その若い時にこそ、存分に色々な経験やチャレンジをしてもらいたいと思っています。
経験の中でも、日本国内だけでなく「海外を見てほしい」という思いから、留学や旅行などで外の世界に触れることを推奨しています。また、実用的な経験として、社会人になってから取得が難しくなるため、学生のうちに運転免許を取得しておくことも、一つの経験として良い機会だと思います。
そして最も重要なのは、学生時代を通じて何かを「極める」こと、つまり「これ以上できないと思えるぐらい没入し、努力し、やり切る」ことを見つけて欲しいという点です。何か一つのことに集中力を持って「やり切った」という事実は、後の人生で大きな自信となります。
この経験こそが、将来困難にぶち当たった時に、自分が強く踏ん張れるための「後ろ盾」となるのです。例えば、大学の部活やスポーツで成果を出している人が大手企業などにオファーされるのは、その経験を通じて培われた強さや人格形成が評価されているからです。このような経験は、会社に入るためだけでなく、その後の人生においてもすごくプラスになるのだろうなと思います。
取材担当者(高橋)の感想
「学生時代に失敗しても大したことはない」からこそ、興味を持ったことに没入し、徹底的にチャレンジすることが大切だというメッセージは、就職活動を控える学生にとって非常に響くものでした。このやり切った経験が、社会に出てからの活躍や、自分に自信を持って人生をブレずに過ごしていくための礎となるというお話は、私たちZ世代が今すぐ行動すべき指針だと感じました。










