キャリアフィットグループ株式会社(CFG)は、1985年(昭和60年)にビルメンテナンス・ビルサービス業を目的として、クリンネスジャパン株式会社として設立されました。その後、2005年(平成17年)にキャリアフィット株式会社に社名変更し、2023年(令和5年)に現在のキャリアフィットグループ株式会社となりました。代表者は代表取締役社長の村上様です。
本社を札幌市に置き、北海道本部、道南、道北、東北本部(青森・弘前・八戸)、東京、九州本部(大分・福岡)など、広範な事業拠点を展開しています。CFGグループは、人材サービス(REC)、施設保安・清掃(マネジメント)、介護・施設給食(ケアシステム)、交通誘導・雑踏警備(トラスト)に加え、学校・研修(アカデミー)、外国人就労(インターナショナル)、IT事業(クリエイト)、障がい者協働事業(LSO)など、多岐にわたる事業を展開する実業集団です。
<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>
【バイトから始まった異色のキャリアパス】
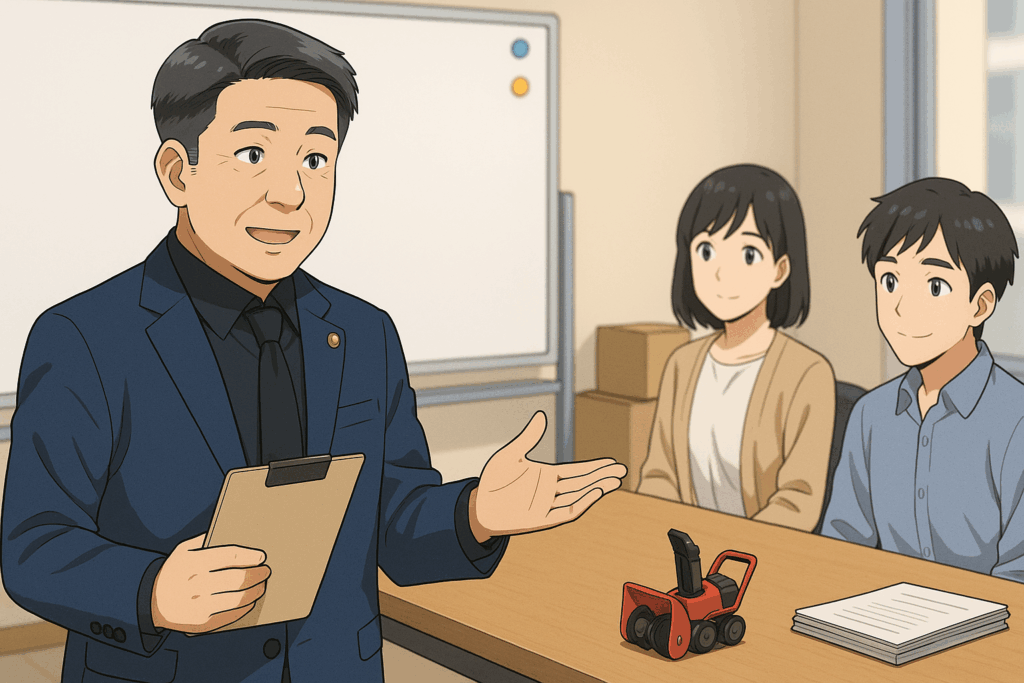
私のキャリアは、一般的な新卒入社とは大きく異なる道のりから始まりました。高校時代、先生の勧めもあり、志望していなかった私立高校(ミッションスクール)を受験しました。政治部の新聞記者になることを志しており、国語を得意としていたこともあり、最終的には日本の大学ではなくアメリカのカリフォルニア州の大学に進学しました。
卒業時にアメリカでの就職を決めていましたが、親から「お前をアメリカ人にする覚えはない。いいから帰ってこい!」と大反対され、やむなく帰国。帰国は秋ということもあり、就職活動に最も不向きな時期でした。就職活動を邪魔しないよう、週末限定でバイトを探しました。そこで見つけたのが、週末の除雪機販売のアルバイトです。短期間で販売実績を挙げ、社員登用の話が来たのが今の会社です。私はバイトから社長になりました。
配属先は人材派遣事業部。メンバー全員が転職し、空っぽの部署でした。同じく新人の上司と二人で部門の立て直しを任されキャリアがスタート。しかし入社当初の2年間は上司との意見の不一致で、毎日辞めることばかり考えていました。それでも「辞めても人脈は残る」と考え、「次の仕事に移るための人脈作り」という前提で一生懸命働いた結果、非常に高い成績を上げました。最終的に辞表を出した私に、会社は上司ではなく私を残す決断をしてくれました。
取材担当者(高橋)の感想
社長ご自身も海外での挑戦をされていたことに感銘を受けました [前回の感想]。就職困難な時期にバイトとして入社し、その短い期間で除雪機をポンポン売ってしまう行動力や実績は、会社にとって「欲しい人材」として認められる説得力があります。また、最初の困難な環境で「辞めるための人脈作り」と割り切って努力し、結果的に成績を上げたというエピソードは、どんな環境でも目標を持って行動することの重要性を教えてくれます。ネガティブな経験を「反面教師」としてポジティブに転換する姿勢は、就活生にとっても大きな学びになるはずだと感じました。

【経営者としての役割意識と「通訳」の責務】
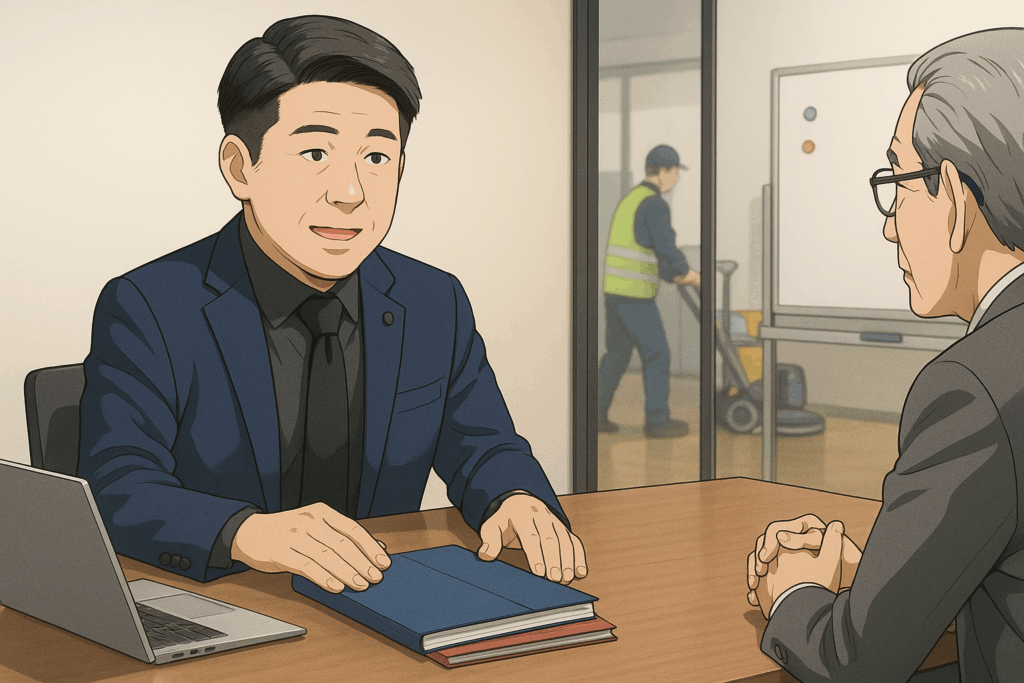
私は創業者とは血縁関係がなく、「赤の他人」として入社しました。当時の役員の中では私が圧倒的に若く、社長になることは想定していませんでした。しかし、社長に就任する頃には、当時4つあった事業部のうち一番小さかった部門を最も大きく成長させ、会社の売上を5〜6億円から17億円超へと拡大させるなど、確かな実績を上げていました。そのうち半分近くは私の部門が占めていました。
数字的な実績だけでなく、私が経営幹部として求められた要因は、創業者に対し「意見を言っていた」点にあります。週に1回は必ず大喧嘩。個人の感情ではなく、役職者としての責務として議論を重ねることで、他の誰よりも社長と強い信頼関係が育まれました。決定前に異議がある場合は意見を言うことが重要だと考えていましたが、決まったことは必ず守る。この両立を大切にしていました。
また、指示を受けていないにもかかわらず、20代の頃から毎年必ず、会社の「長期ビジョン」のレポートを自主的に作成し、提出していました。私は自身の役割を、現場と経営者の間に立つ「通訳」であると認識しています。例えば、創業会長は清掃業のプロですが、人材業については詳しくありません。私は人材業の責任者として、業界のトレンドや課題を踏まえ、「人材業は今こういう状況で、こういうことに注力すべきではないか」と解説する役割を担ってきました。経営者に対して常に意見を述べ、業界の解説者として振る舞ってきたことが、社長としての資質を磨く上で重要な経験だったと感じています。
取材担当者(高橋)の感想
若くして役員となり、創業者と週に一度大喧嘩をするというエピソードは、その熱量と覚悟に驚かされます。しかし、それは個人の感情ではなく、役職として会社の成長のために意見を戦わせるという信頼に基づいた関係性だという点が重要だと感じました。また、自らの領域を「通訳」として定義し、現場と経営層を繋ぐという役割意識は、専門分野を持つ人材が経営に参画する際の理想的なスタンスではないかと思います。自主的に長期ビジョンを提出されていたという行動力も、指示待ちではなく会社を牽引する気概を感じます。

【社長に求められた真の資質:「場を明るくする力」】
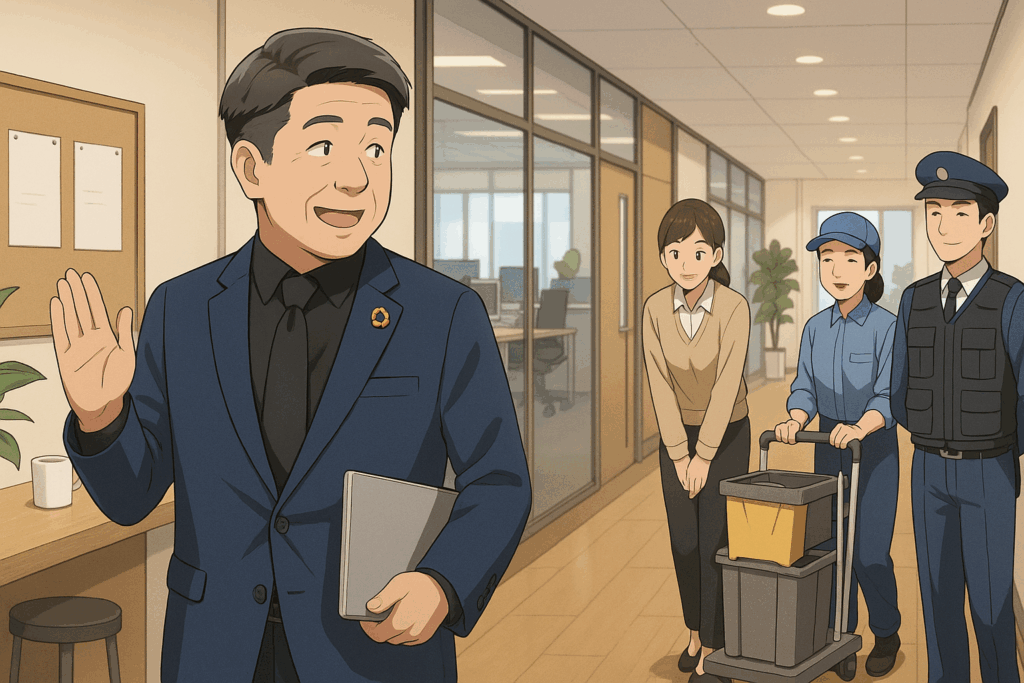
社長に就任した理由について、私は当初、優秀な成績や部門の拡大といった実績が評価されたものだと思っていました。しかし、就任からしばらく経ったある日、M&Aで買収した会社の関係者が会長に「なぜ村上さんが社長なんですか?」と尋ねた際、初めて会長から聞かされた真の理由に驚きました。
会長が語ったのは、数字や実績とは異なる、私の根本的な資質でした。「村上君があっちこち歩くとね、そこが明るくなるんだよね」。会社の中で様々な部署を歩き回る際、社員たちが笑顔になり、場が明るくなる。その存在感こそが、社長に選ばれた理由の一つだったのです。私はその時初めて「あ、そういうことだったんですか」と気づき、非常に嬉しかったです。
私は自身を「社長係の係員」だと考えています。これは権威を振るうという意味ではなく、会社全体を円滑にするチームの一員という考えの表れです。経営者として結果を出すことは大前提ですが、それ以上に、組織全体の空気や士気を高め、社員が自発的に動ける環境を整えることの重要性を、会長の言葉から学びました。社員の士気を高め、組織を明るくすることが、結果的に会社への最大の貢献につながると信じています。
取材担当者(高橋)の感想
社長になる理由は「成績」や「数字」だと思っていましたが、最終的に会長が語ったのが「場を明るくする力」だったという事実に非常に感動しました 社長の明るさが組織を動かす原動力となっているのだと感じました。仕事で結果を出すことはもちろん重要ですが、それに加えて、その人が持つ人間的な魅力や周囲に与える影響力が、経営者としての根源的な資質になるという点は、就活生にとっても新鮮な発見ではないでしょうか。

【地域社会に必要とされる「100億円企業」への道】
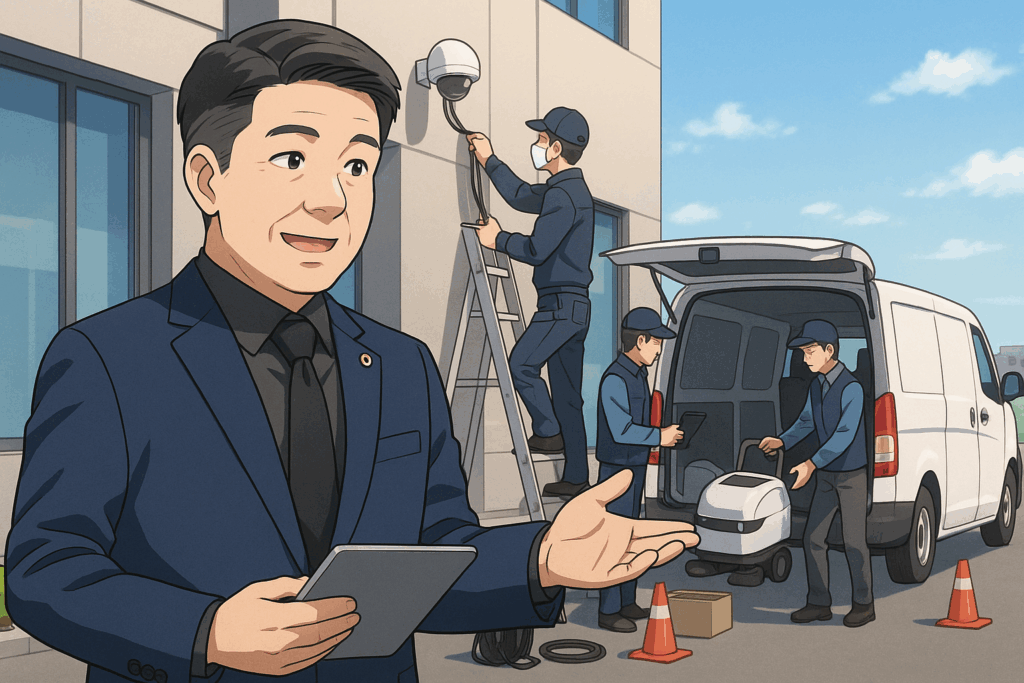
キャリアフィットグループの長期ビジョンとして、私は「最低100億円の年商を持つ会社になりたい」という目標を掲げています。これは単なる規模拡大を目的とした数字ではありません。企業が社会から求められる水準があり、都道府県レベルで支援される企業規模はおおよそ年商100億円だと聞いています。
地域社会の中で生きる企業だからこそ、「地域社会に必要とされる規模」になる必要があると考えています。ただし、この数字はあくまで「手段」であり、「目的」ではありません。この目標を達成することで、働く一人ひとりの自己実現や「働きがい」、そして従業員の「幸せづくり」を実現するための基盤が整うのです。
会社が創業30年を超えられたのは、ダーウィンの進化論のように「変化できるから生き残れた」からだと考えています。企業が創業から30年存続する確率はわずか0.2%。現状に満足せず、次の30年に向けて変化し続ける必要があります。今後は、既存の「人による売上」(人材派遣・清掃など)に加え、「人によらない売上」を追求しています。清掃ではロボット化、警備ではカメラによるシステム導入など、効率化を進めています。
さらに、オフィスを構えていない地域でも、警備と清掃など複数事業を掛け合わせた「コンサルティング事業」を通じて地域企業の成長を支援する構想もあります。人口減少という社会要因を背景に、既存市場に固執せず、転職市場の拡大や事業の多角化・高品質化を進めることで、持続的成長のメソッドを確立していきます。
取材担当者(高橋)の感想
100億円という目標が、「国や地域が守るべき社会インフラ」としての存在意義から逆算された「手段」であるという考え方は、非常に論理的で分かりやすいと感じました 。また、企業が30年存続できる確率が0.2%という話から、絶えず変化し、社員の幸せを追求していく姿勢は、経営理念が形骸化していない証拠だと思います 。特に、今後のコンサルティング業への注力や、「人によらない売上」へのシフトは、人口減少社会における成長戦略として非常に実践的であり、企業規模の大小に関わらず適用できる学びだと思いました 。

【学生へのメッセージ:運を良くするための「挑戦」と「出会い」】
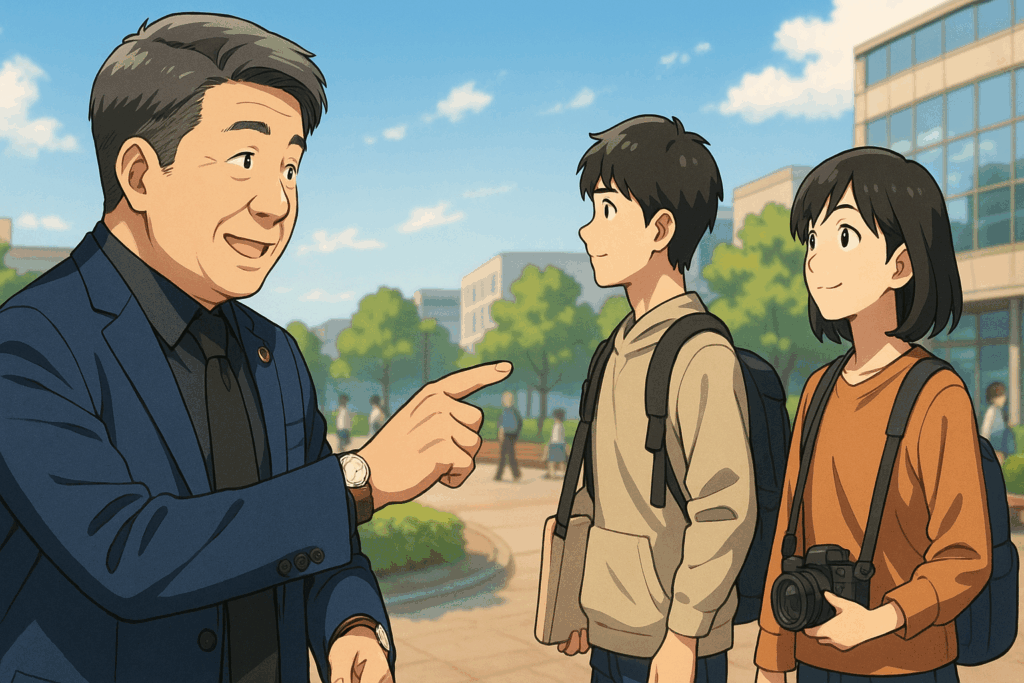
学生の皆さんに最も伝えたいのは、「挑戦」することの重要性です。私はアメリカへの挑戦を通じて、運の良さとは「多くの出会いをしていること」だと学びました。運が悪い人は、単に出会いの数が少ないだけ。だからこそ学生時代こそ、さまざまな人や物事に触れ、見聞を広げることが大切です。
私は裕福な家庭に生まれたわけではありませんが、留学費用を親に負担してもらった恩義から「無駄な1日は絶対に作らない」と決めて生活していました。毎日必ず何か新しいことを学ぼうとする習慣が身につきました。時間の大切さと、チャンスをつくる基盤を忘れないことが重要だと思います。
高校時代には時間を浪費していた時期もありました。だからこそ後になって「もったいなかった」と気づけたのです。すべての経験には意味があり、そこから何を学ぶかが大切。挑戦し、時間を大切にしながら多くの出会いを重ねることこそ、未来を切り開く鍵になると考えています。
取材担当者(高橋)の感想
「運がいい人は、いろんな出会いをしている」という法則は、運は偶然ではなく、自ら作り出すものだと教えてくれます 。学生時代は有限であり、時間を大切にし、積極的に多様な経験を通じて視野を広げることの重要性を改めて認識しました 。










