株式会社アスター美容は、昭和48年(1973年)に設立された、50年を超える歴史を持つ企業です。化粧品・医薬部外品の研究開発および製造販売を行っており、特にヘアサロンなどで使用される業務用のシャンプーやトリートメントのOEM(受託製造)を長年にわたって手掛けています。当社の製品はほとんど自社ブランドでは販売していないため、一般の消費者にはあまり知られていませんが、国内外のブランドメーカーに製品を提供しています。社員規模は約100名(2025年現在)、年間売上高は約25億円です。私は2年前に外部から代表取締役社長に就任しました。会社の将来を見据え、継続的な成長を実現するための組織改革を、社員と共に推進しています。
<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>
【異業種への転身と経験を活かす論理的なアプローチ】
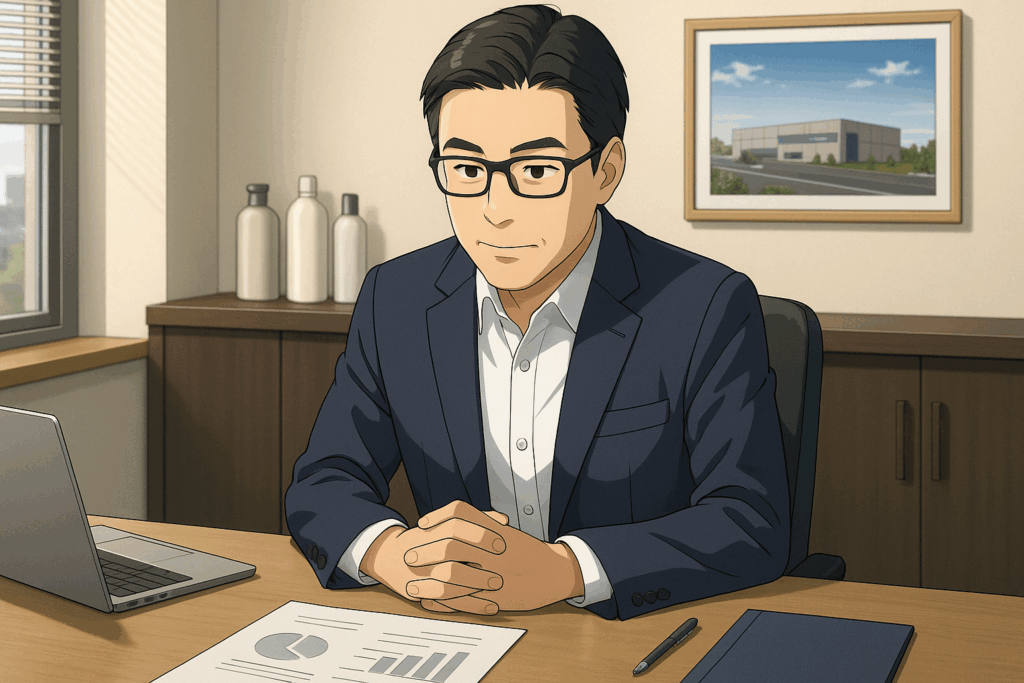
私はアスター美容の社長に就任しましたが、それ以前は化粧品業界には全く関わっていませんでした。前職はプリンターやスマートフォンなどの情報通信・IT系メーカーで、事業責任者を務めていました。定年の時期を迎えて前職を退職し、ほぼ引退するつもりでいたのですが、知人からの要請を受け、経営を引き受けることになりました。
異業種への挑戦は、これが初めてではありません。以前、コピー機などのドキュメント事業を30年以上担当した後、同じグループ会社内で携帯電話やスマートフォン事業の責任者に異動しました。この異動は、技術・競合環境・顧客層・ノウハウのすべてが異なる環境での挑戦でした。この経験から、自分の専門とは全く異なる分野であっても、努力と論理的な考え方次第で成果を上げられるという自信を持つようになりました。
化粧品業界は、前職のコア技術とはかけ離れた分野です。私は、このまったく経験のない業界で成果を出すために、まずは客観的な視点で会社を理解し直すプロセスを踏みました。具体的には、商品の技術的競争力はどこにあるのか、サプライチェーンの構造はどうなっているのか、どのような技術者を育成すれば成功につながるのか、といった点を一つずつ整理し、理解を深めました。業界が違っても、論理的に物事をとらえ、現状の課題とあるべき将来像を描き、社員と共に取り組んでいけば、道は必ず開けると確信しています。私は今、この新しい挑戦の真っ只中にいます。
取材担当者(高橋)の感想
IT業界の事業責任者から、全く異なる製造業である美容OEM企業の社長に就任するというキャリアパスは、極めて大きなチャレンジ精神と行動力を示していると感じました。しかし、社長が過去の経験を活かし、新しい業界でも「客観的な目線で現状を理解し、論理的に課題を捉え直す」というアプローチを徹底されている点は、私たち就活生にとっても、環境が変わっても通用する普遍的な仕事の仕方を学ぶ上で非常に重要だと思います。

【「目に見えない経営危機」からの組織文化の変革】
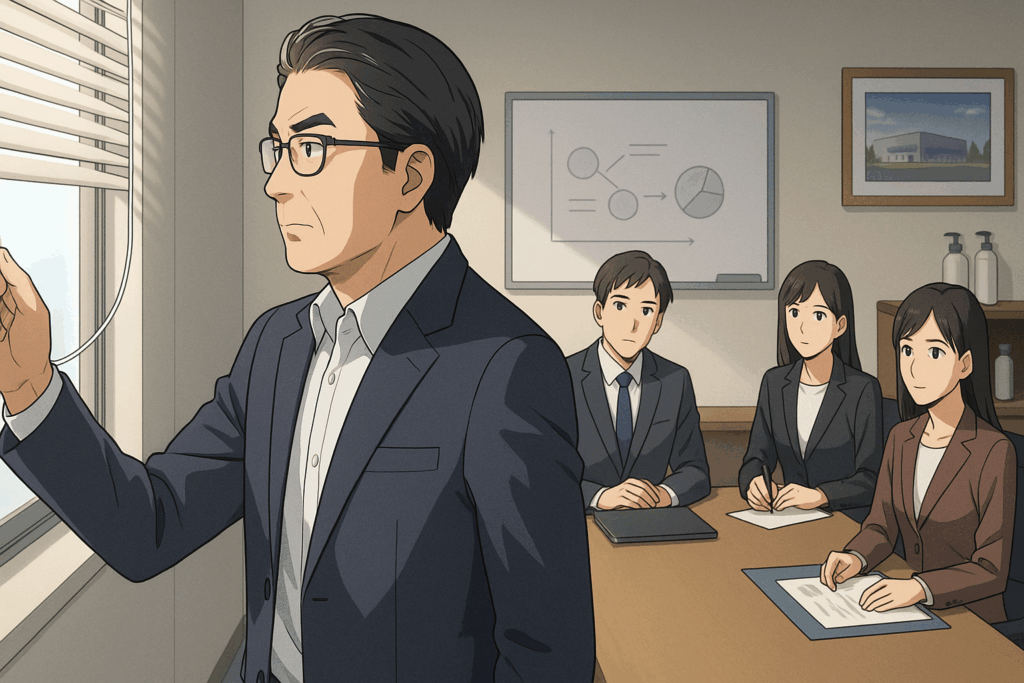
創業から50年を超えるアスター美容は、お客様からのご注文が途絶えなかったため、表面上の数字だけを見れば経営的な危機には直面していませんでした。しかし、会社の将来を考えると、社内的には「目に見えない経営危機」に直面しているという課題認識を持っていました。
この「目に見えない経営危機」は、主に企業文化や仕事の進め方、そして人の課題に起因していると考えています。組織は、長期間同じメンバーで仕事をしていると、どうしても同じ価値観の中に閉じこもり、内向きになりがちです。世の中が常に変化しているにもかかわらず、組織内部で過去の価値観が重視され続けると、その傾向はさらに強まります。これは、ゴルフで正しくないスイングを身に付けてしまうと、続けるほどに矯正が難しくなる状況に似ていると思います。
私が目指しているのは、単なる現状維持ではなく、継続的な成長を実現できる組織の基盤をつくることです。同じことを同じように続けているだけでは、物価やエネルギーコストの上昇などの外部環境の変化を背景に、利益は徐々に目減りしてしまいます。結果として、現状維持すら難しくなります。そこで、社員が将来に向かって「この会社で頑張っていこう」と思える環境を整えるとともに、社員の生活がこの会社の上に乗っているという責任を明確にし、成長と利益の両立を追求しています。
継続的に競争力を高められる会社となるために、この2年間は、意識や考え方の「窓やドア」を常に開けておけるよう、社内改革に取り組んでいます。具体的には、部門や階層を越えた対話の場づくり、外部知見の取り込み、業務プロセスの見直しなどを進め、固定化した前提や慣習を意図的に揺さぶることで、組織が自律的に学習し続ける状態を目指しています。
取材担当者(高橋)の感想
創業50年以上の安定企業であっても、「目に見えない経営危機」に直面し、それを変革しようと試みている事実に驚きました。社長は、社員がこの会社で働くことに誇りを持ち、成長を実感できる環境を作ることが目的だと明確にされています。特に、トップダウンやワンマン経営になりがちな組織を避け、社員一人ひとりが継続的に競争力を改善し続けられる組織の基礎を作るという取り組みは、持続的な企業成長への強い覚悟を感じました。

【成長の鍵となる人材戦略と個の経営者意識】
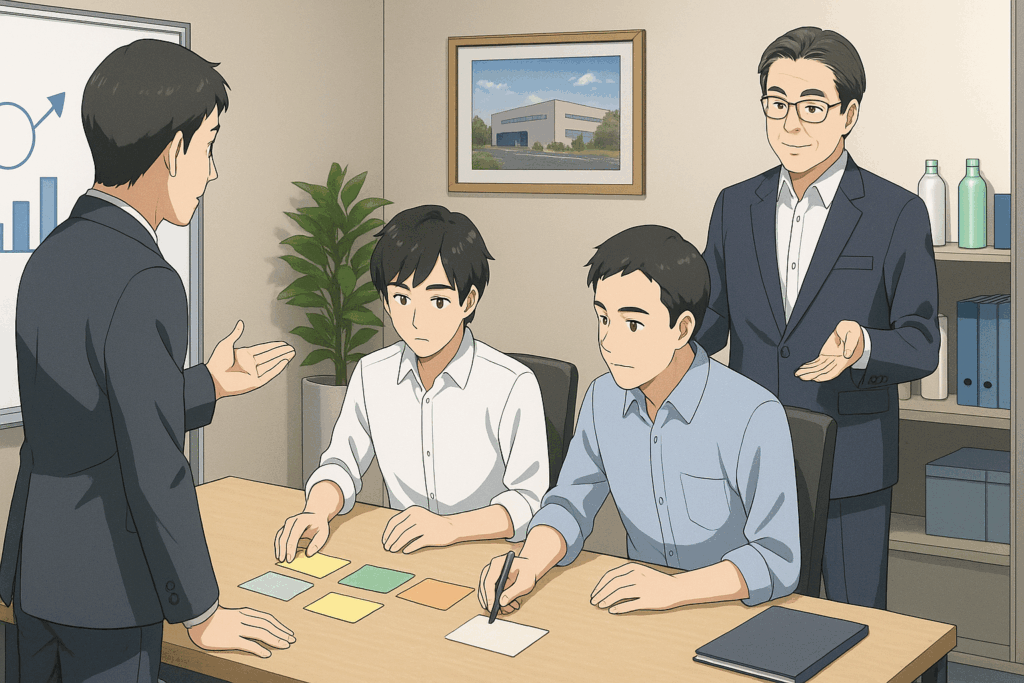
組織文化の硬直化を防ぎ、意識のドアを開けるために不可欠な要素が「新しい風」です。この新しい風を吹き込む役割は、主に中途入社の社員が担ってくれると考えています。中途採用者は、多様な価値観と外部の経験を持っているため、「世間ではこうしているが、なぜうちはこうなのか」といった意見を発信できます。そうした視点が社内の議論を活性化させることにつながります。多様な意見が語られることで、議論を通じて最も良い選択を導き出せる会社になると期待しています。
一方で、新卒採用も会社の長期的な成長には欠かせません。新卒社員が入社すると、中堅社員が育ちます。社員を育てる最も早い方法は、部下を持つことです。新卒社員を指導する立場になることで、中堅社員は自身の考え方や行動を再認識し、若い世代の感覚にも触れることができます。Z世代が持つ柔軟な発想やデジタル感覚を取り入れることで、会社全体が新しい価値観に対応できる組織へと成長していきます。
私は社員に対して、「一人ひとりが経営者」という意識を持つことを求めています。「経営者がいて、その下で働いている」という受け身の意識ではなく、自分自身が経営者という立場に立ち、自ら意見を持ち、目標を設定し、努力する姿勢を大切にしてほしいと考えています。その結果が会社の成長につながり、同時に自分自身の喜びにもなります。会社の成長軸と自分の人生の成長軸が重なり、互いに上昇していくことが理想です。1日の半分以上を会社で過ごすからこそ、会社の成果が輝けば、自分の人生も物質的な豊かさだけでなく、自己成長を通して輝くと信じています。社員を採用するということは、単に給料を支払うだけでなく、その人の将来や成長に責任を持つことでもあると強く感じています。
取材担当者(高橋)の感想
社長が「社員の生活が会社の上に乗っかっている」という責任感を持ち、社員の成長を会社の成長と同軸で考えているという話は、私たち就活生にとって非常に心強いメッセージでした。特に、新卒採用が中堅社員を育てる仕組みになっているという視点は、入社後のキャリアアップを具体的にイメージする上で学びとなりました。面接時には、会社見学や現場社員との意見交換を推奨し、ミスマッチを防ぐという取り組みも、社員を大切にする会社の姿勢を示していると感じます。

【業界の展望と継続的成長への具体的な挑戦】
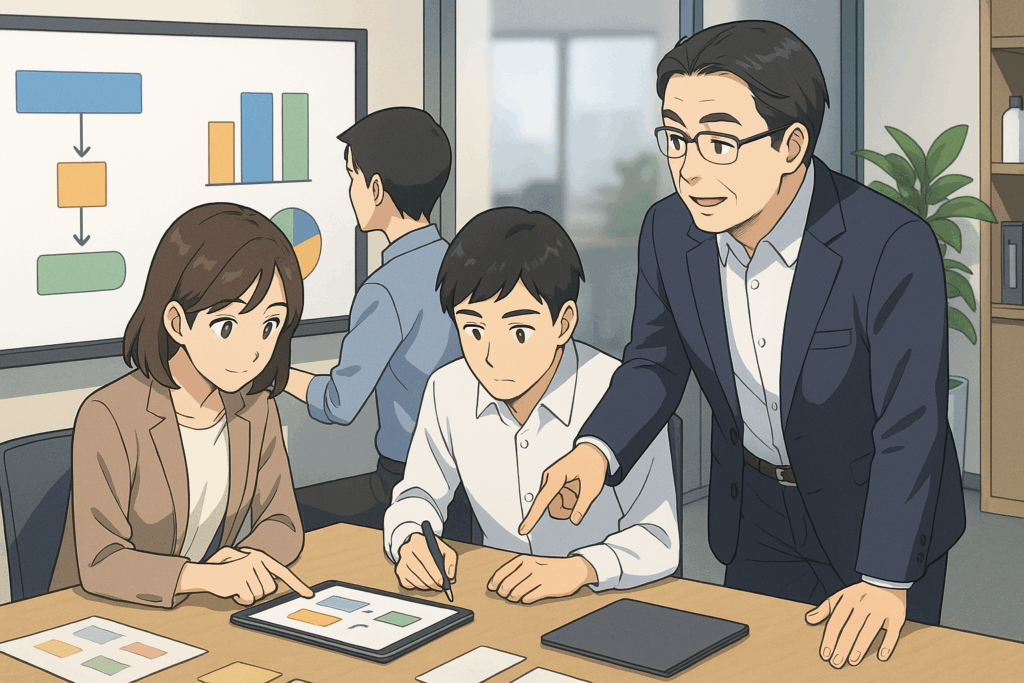
化粧品・美容業界のマクロな展望について、日本の人口は減少しているため、サロンルートの商品市場が今後大きく右肩上がりで成長するとは見ていません。しかし、市場全体が縮小傾向にある中でも、競争に勝って成長する企業は必ず存在します。
成長の鍵は、主に40代・50代の女性層の需要増加に対応することにあると考えています。この年代は髪のエイジングや悩みが顕在化しやすいため、サロンでのプロフェッショナルな施術や、機能性の高い薬剤に対するニーズが大きいからです。そこで、私たちは新しい原料や天然由来成分などを積極的に活用し、お客様に喜んでいただける付加価値の高い製品を継続的に開発していきます。
会社を成長させるための取り組みは、精神論にとどまりません。社員一人ひとりが「今日の仕事」だけではなく「明日の将来」を見据えて働けるよう、仕事の仕組みそのものを改善しています。具体的には、会計の理解を深める研修、開発アプローチの見直し、品質工学への理解促進、さらにDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進など、多岐にわたる分野で学びと仕組み化を進めています。目指すのは、社員が親戚や同級生に対して自分の会社を「自慢できる」と胸を張って言える状態です。
私は、永続的に社長を務め続けるという考えではありません。会社を変革することが私の役目だと考えています。変革が進めば、次の世代にバトンを渡すべきだと思います。創業から50年を超えてきた会社ですが、私は社員に対して「過去の50年を見て今日の仕事をするのではなく、これからの5年を見据えて仕事をしよう」と伝えています。社員と共に、より良い会社をつくり、さらに良い未来を引き寄せるべく、日々取り組んでいます。
取材担当者(高橋)の感想
人口減少というマクロな課題を認識しつつも、特定の年代層の需要を見据え、高機能な製品開発を通じて成長を目指すという戦略は非常に明確だと感じました。また、社長がDX推進など具体的な改革を、社員に主体的に取り組ませる形で進めている点に、真の組織変革への強い決意を感じました。社員が「自分の会社」として誇りを持てる環境を作るという目標は、私たち若者が企業選びをする上で最も重要視する点の一つだと改めて認識しました。










