【異色のキャリアと理想追求のための創業】
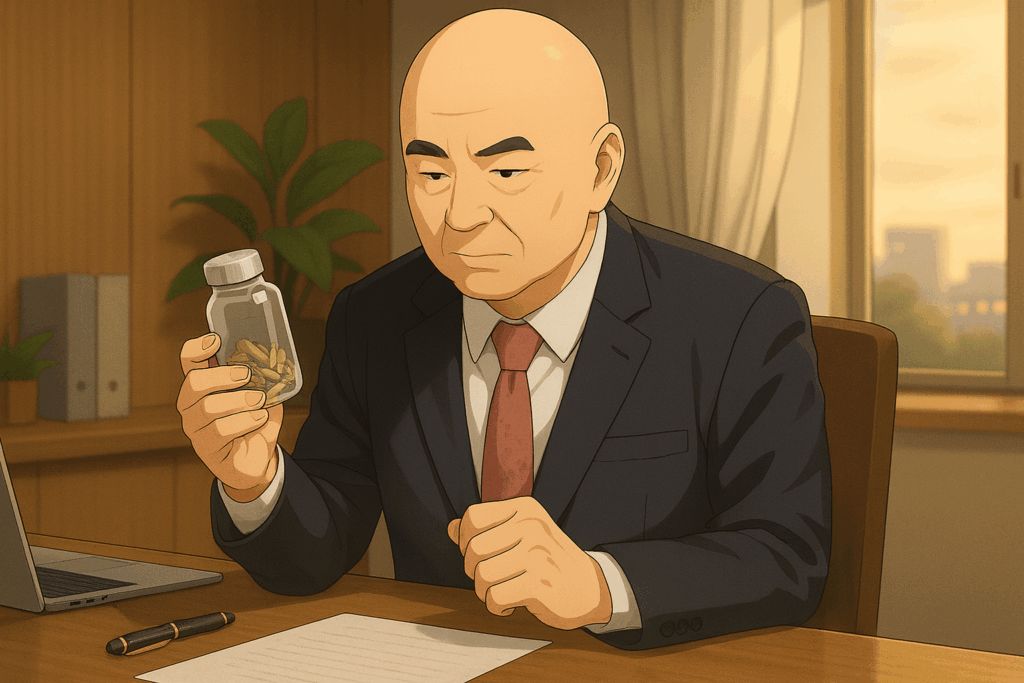
私は1998年に、45歳でサラリーマンを辞め、現在に至るまで26年間、起業して社長を務めています。大学を卒業した当時はオイルショック(1973年)の真っただ中で就職難の時代でした。最初に勤めた大阪の帽子・婦人服店では海外勤務を希望して入社しましたが、その年にフランス支店が閉店となり、挫折を経験しました。もともと婦人服を販売するような性格でもなかったことから、1年で会社を辞め京都に戻りましたが、当時はまだ景気が回復していませんでした。親がタクシー関係の仕事に就いていた縁があり、人生経験としてタクシー運転手を29歳までの約6年間続けました。
タクシー運転手として所得は上がりましたが、「いつまでも続ける仕事とは思えず」、次の職を探しました。その際、飲食店でサプリメント会社の社長と知り合い、誘いを受けて入社しました。そこから30歳過ぎまでの約15年間、勤務を続けました。しかし最終的には、その会社の社長と意見が合わず、考え方の違いから退社することになりました。退社当時は次の道が決まっておらず、一時的にうどん屋やラーメン屋を開業することも考えていた時期もありました。
そんな折、日本にまだ流通していない最高級の三七人参があると紹介を受けました。前職のサプリメント会社で仕事の進め方を学んでいたこともあり、「今度は自分の理想とする会社をつくりたい」という思いで、会社を設立して社長に就任しました。当時の薬業界では、誰もが知る朝鮮人参とは異なり、弊社で扱うことになる三七(サンシチ)人参は、1万人、10万人に1人しか知られていないほどの原材料でした。私はこれを日本の薬業界に広め、自分の理想とする会社を築くことを決意しました。
取材担当者(高橋)の感想
社長のキャリアは、一般的な道筋とは大きく異なり、大学卒業後のオイルショックから始まり、タクシー運転手、サプリメント会社勤務、そして自己資金による創業という多様な経験に満ちています。特に、会社を辞めた後すぐに起業するのではなく、一時的にうどん屋の開業を考えたという話からも、社長が常に柔軟な発想と、社会で生きていくための「人間力」を持っていたことがうかがえます。目の前の状況に流されず、理想を追求するために起業を決意した行動力は、自分の人生の目的を模索する就活生にとって大きな学びになると思います。

【希少な「三七」へのこだわりと信頼構築の歴史】
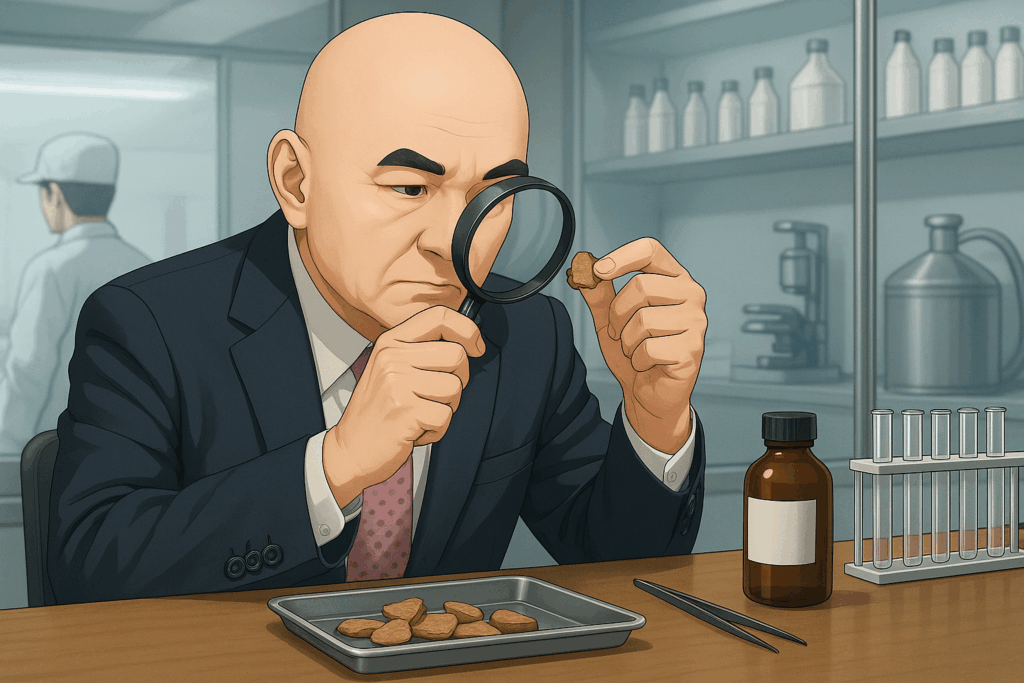
私たちが扱う三七人参は、中国の文山という場所の、ベトナム国境地帯の山岳地域でしか採れない非常に希少な人参です。創業当初、日本には品質の良い三七がほとんど入っていませんでした。そこで、最高グレードの人参を仕入れることからビジネスをスタートさせました。三七は中国では400年前の古書『本草綱目』にも記述があり、「金不換」(お金に変えられない)という別名を持つほど、高い評価を得ています。
この誰も知らない希少な商品を普及させるため、創業当初は、漢方に造詣の深い薬剤師がいる薬局を中心に取引を始めました。マニアックな先生方と情報を交換しながら訴求し、徐々に評価を得るようになりました。誰も知らない商品であったため、市場占有率は100%でしたが、通販やネットでは販売が難しく、ニーズを自ら作り出す必要がありました。
三七は中国では病院で処方されるほど評価の高い漢方薬ですが、日本では食品扱いです。中国で加工を依頼するとグレードが不明確であり、品質に対する信頼性が低いと判断しました。そこで、弊社では最高グレードの三七を日本に持ち込み、日本国内で加工しています。日本の製薬メーカーに依頼した方が、安全性も品質も高い製品を提供できると考えています。
薬業界では、薬局は自らの信用で販売を行うため、「疾患を治す」「難病を治す」といった答えが出る商品でなければ扱ってもらえないという厳しい現実があります。そこで、全国の取扱店様から販売実績や難病対応の情報を集め、共有・フィードバックしながら市場を拡大していきました。その経緯の中で、近畿大学薬学部の遠藤教授を紹介していただき、三七の研究を依頼することができました。販売にあたってエビデンスを持つことは、取扱店様の信頼にもつながっています。
取材担当(高橋)の感想
誰も知らない商品である三七を扱い、ニッチな市場を切り開いてきた背景には、その製品に対する揺るぎない自信と、品質への徹底したこだわりがあると感じました。海外加工のリスクを避け、国内で最高品質の加工を行うという判断は、長期的な信頼構築のために不可欠な戦略です。短期的な利益を追わず、エビデンスを積み重ねて社会的信用を築いていく姿勢は、若い世代にとっても学びが多いと感じます。

【医療業界の構造変化と「相談難民」への対応戦略】
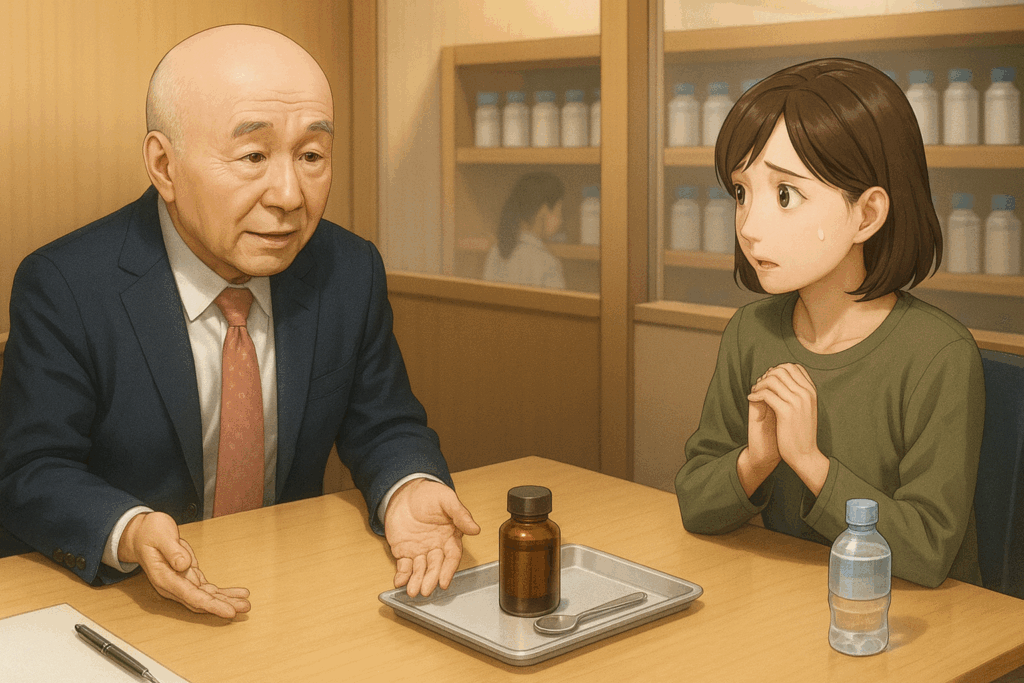
現在(令和6年)の日本の医療業界は、健康保険で得られる収入(約20兆円)に対して、医療費(47兆円)が大幅に上回り、27兆円の税金が投入されています。国は財政難から薬価を継続的に引き下げざるを得ない状況にあります。これに対応するため、約32年前に規制緩和が始まり、CMに登場するような量販店(ドラッグストア)が医薬品を扱うようになりました。量販店は資本力を背景に価格競争を展開し、地域の小さな薬局(個店)は次々と淘汰されていきました。
私たちの商品は、量販店では対応できない隙間(ニッチ)の領域に位置しています。病院も量販店も、多くのお客様(患者)を機械的に対応せざるを得ず、検査データを基に次々と薬を出していく傾向にあります。しかし、「病院に行っても治らない」「この薬を続けていいのか相談したい」といった、自分のことをわかってほしいと願う患者の方々が確かに存在します。私たちは、そうした方々に寄り添える取扱店様を探し続けています。
私は、そのような患者さんを「相談難民」と呼んでいます。この言葉は弊社が作った造語で、「相談できる場所がない患者さんが必ずいる」という意味を込めています。特に精神的な疾患は、薬だけではなかなか治らないため、患者に寄り添う姿勢や立ち位置が重要になります。
私たちの商品は、店頭での相談を通じて初めて販売される「推売商品(すいばいしょうひん)」と位置付けています。これは単に商品を売るのではなく、カウンセリングを通じて患者の病態や生活習慣、価値観、性格、遺伝など、健康の根本的な要因を考慮し、その人の幸せな人生を共に支えるアイテムとして提供しています。
弊社は一般消費者への直接販売を行わず、全国約700店舗の取扱店様(薬局・薬店)に商品を供給しています。店舗で販売される際には、お客様(患者)に必ずカウンセリングを実施していただくようお願いしています。カウンセリングは早い方でも30分、重い疾患の患者の場合は1時間半から2時間以上に及ぶこともあります。お客様が元気になり、病院からの処方薬を飲まなくてもよくなったと喜ばれる姿を見ると、私たちも大きなやりがいを感じます。
取材担当者(高橋)の感想
日本が抱える医療費増大や少子高齢化といった社会課題、そしてそれに伴う医療の機械化を深く分析した上で、「相談難民」という独自の概念を打ち立て、それをビジネスの軸としている点に強く感銘を受けました。単に商品を販売するのではなく、「患者が喜び、会社も利益を得る」という三方良しの理念を大切にしている姿勢は、まさに人が介在する価値を最大化する経営戦略です。カウンセリングの重要性(早い人で30分、重い疾患の場合は1時間半以上)を重視する考え方からも、現代社会における「人間力」の意義が伝わってきます。

【成長目標と「なんとかしてあげたい」という人間力を持つ人材への期待】
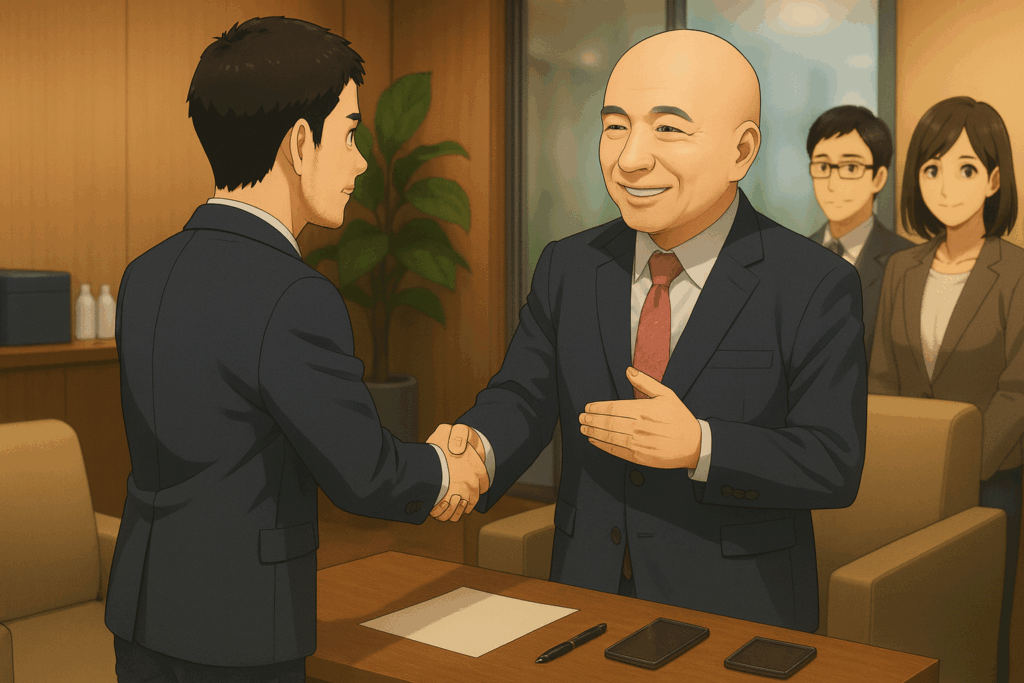
弊社の成長目標は明確です。人口5万人に1店舗が市場のピークだと仮定すると、全国で約2,400店舗の取扱店が見込めます。現在は全国で約700店舗に商品を供給していますので、最終的には2,000店舗ほどまで拡大したいと考えています。そうなれば、現在の売上(約6億円)を12億円程度まで伸ばせる見込みです。
しかし、単に販売量を増やすことが目的ではありません。本当に困っている人を助けていくことが大切だと考えています。そのため、ネット販売は禁止しており、お客様には必ず店舗に来店していただき、カウンセリングを受けることをおすすめしています。私たちの商品は、「知る人ぞ知る有名ブランド」「クローズドマーケットの最高級ブランド」として、本当に必要とする人に届けば良いと考えています。
現在の日本は少子高齢化が進み、健康保険収入が減少しているため、医療の面では「質より量的な治療」が重視される政策になっていると感じます。国は「保険証さえ持っていれば治してもらえる」という意識を国民に与え、結果的に健康に無関心な人々を生み出してきました。だからこそ、私たちは病院に行かなくても済むような人を増やし、47兆円の医療費を少しでも削減したいという使命を持っています。
売上が2倍、3倍になれば、社員数も現在の25名程度から50〜60名程度へ増員が必要になると考えています。採用に関しては、単に優秀な人材を求めているわけではありません。私は、「少し痛い目に遭った人」、例えばブラック企業などで苦労を経験した人を好みます。なぜなら、弊社の仕事は本当に困っている人を救いたい、「なんとかしてあげたい」という強い人間力と社会性を必要とするからです。
弊社の商品を求めるお客様の中心層は、40代から70代以上の「相談難民」と呼ばれる方々です。そのため、社員には人生経験を積み、健康に対する深い理解を持つ人物が求められます。健康の根本は、「3度の食事」「生活環境」「価値観」「性格」「遺伝子」の5つの要素が複雑に絡み合っており、私たちの仕事は物を売るだけでなく、これらの要素を整えながら、患者の幸せを共に作っていくことです。若い人たちには、何事にも一生懸命に取り組むこと、苦手な分野にも挑戦することが、人生を豊かにし、人間関係を豊かにするコツであると伝えています。
取材担当者(高橋)の感想
「質より量的な治療」という現状を厳しく捉える社長の言葉からは、社会情勢に対する鋭い問題意識と、自社が果たすべき使命への強い覚悟が伝わってきます。売上目標(12億円)を掲げながらも、真に困っている人を救うことを第一に据える姿勢は、ビジネスと社会貢献を両立する理想的な在り方です。
また、「なんとかしてあげたい」という気持ちを持つ人こそが、人の心を動かす仕事ができるという考え方に深く共感しました。私たち学生も、自分の人生の価値をどこに見出すかを考える上で、「助けたい」という純粋な想いが仕事の原動力になることを学びました。










