ハチ食品は、国産初のカレー粉を製造した元祖カレーメーカーとして、今や国民食にもなったカレー文化の普及に貢献し、日本の食文化を支え続けてきた企業です。現在は、カレーを中心にスパイス、ルウ、レトルト食品の製造・販売を主力事業とし、そのラインナップを拡大しています。特に、高齢者の単身世帯や共働き世帯の増加を背景に成長を続ける調理簡便食品(レトルト食品、フリーズドライ食品、冷凍食品)という市場において、独自の強みを発揮しています。2025年に売上高200億円、従業員数約360人の中堅企業でありながら、「エコアクション21」の認証を取得するなど、環境への配慮も忘れない企業です。本記事では、ハチ食品の社長である私自身が、未来を見据えたビジョンと、就活生へのメッセージを直接お伝えします。
<聞き手=遠藤光(学生団体GOAT編集部)>
【社長が語る、ハチ食品の「今」と「未来」】

私は2020年、コロナ禍の真っただ中にハチ食品の社長に就任しました。当時60歳であった私は、就任後約2年間は中断を余儀なくされつつも、2022年後半から様々な取り組みをスタートさせています。私自身も、単身赴任で大阪におり、レトルト食品は非常に重宝しています。その個人的な経験からも、レトルト食品の利便性を深く理解しているつもりです。
私は、現在の食品市場、特にレトルト食品が大きく伸びている状況に注目しています。その背景には、単身世帯の増加や、夫婦世帯の7割が共働きであるという現代のライフスタイルの変化があります。調理にかける時間や手間を減らし、手軽に食事を用意したいというニーズの高まりから、調理簡便食品としてのレトルト食品の需要はますます高まり、今後もさらに成長していくと予測しています。調理簡便食品には、レトルト食品、冷凍食品、フリーズドライ食品の3つの大きなカテゴリーがありますが、ハチ食品では冷凍食品は扱っていないものの、レトルト食品とフリーズドライ食品の二つを手掛けており、これらをそれなりの規模で展開する会社は日本では多くないため、経営環境としては非常に恵まれていると認識しています。
このような恵まれた市場環境の中で事業を展開できることに、私は大きなやりがいを感じています。現在の日本国内市場だけでも、まだ未開拓の部分が多く、成長のチャンスが豊富に存在します。さらに、10年後、20年後を見据えた海外展開も視野に入れています。日本のカレーがヨーロッパやアメリカで人気を集めていることを踏まえ、その可能性にも期待を寄せています。
取材担当者(遠藤)の感想
社長がご自身もレトルト食品を愛用されていると聞いて、とても親近感が湧きました。私も一人暮らしなので、日頃からレトルト食品には本当にお世話になっています。市場の伸びの背景にある社会の変化を具体的に説明してくださり、なるほどと納得しました。ハチ食品が単なる食品メーカーではなく、変化する社会のニーズに応える企業として、大きなやりがいを持って事業に取り組んでいることが伝わってきました。

【ハチ食品が描く、成長戦略の真髄】
ハチ食品の大きな強みは、調理簡便食品の中でも、レトルト食品とフリーズドライ食品という二つのカテゴリーを扱っている点にあると考えています。これら二つのカテゴリーを、日本でそれなりの規模で両方手掛ける会社は多くないため、これは明確な差別化要因になると考えています。事業の多角化は経営の基本であり、特定の事業に依存する「一本足打法」では困難な状況も起こりうるため、複数の事業の柱を持つことが重要です。
実際、ハチ食品は1年前にフリーズドライ食品の会社をM&A(企業買収)によって取得し、事業規模の拡大を図りました。これは、市場の成長を見据え、将来にわたる持続的な発展を目指す戦略的な一歩であると捉えています。このように、ただ市場の波に乗るだけでなく、自社の強みを活かし、積極的に事業領域を広げていく姿勢が、ハチ食品の成長を牽引していると考えています。
中堅企業である当社は、大規模な広告展開よりも、効率的かつ効果的な情報発信を重視しています。限られた予算を活かしながら独自の強みを消費者に届けるとともに、フレーク状のカレールウという製品特性をアピールするなど、地道ながらも緻密な活動を通じて、差別化とブランド力の向上に努めています。
また、ご家庭では一から作ることが難しい本格的な味わいのカレー、例えばグリーンカレーやバターチキンカレーといった商品を強化するなど、多様なニーズに応える商品開発にも力を入れています。当社のフレーク状ルウは非常に溶けやすく便利であり、一度お使いいただくと、その使いやすさを実感していただけます。。
取材担当者(遠藤)の感想
レトルトとフリーズドライの両軸で事業を展開されているというお話には、非常に戦略的な視点を感じました。M&Aによって事業を拡大し、未来を見据えているという社長の予測力と行動力に驚かされました。売上高約200億円という中堅企業でありながら、大手企業にはない独自の戦略で市場を攻めている姿は、まさに成長企業の魅力だと感じます。僕自身もカレーが大好きなので、ハチ食品さんのフレーク状ルウがどんな味なのか、ますます興味が湧きました。

【成長を支える「人財」への投資と求める力】
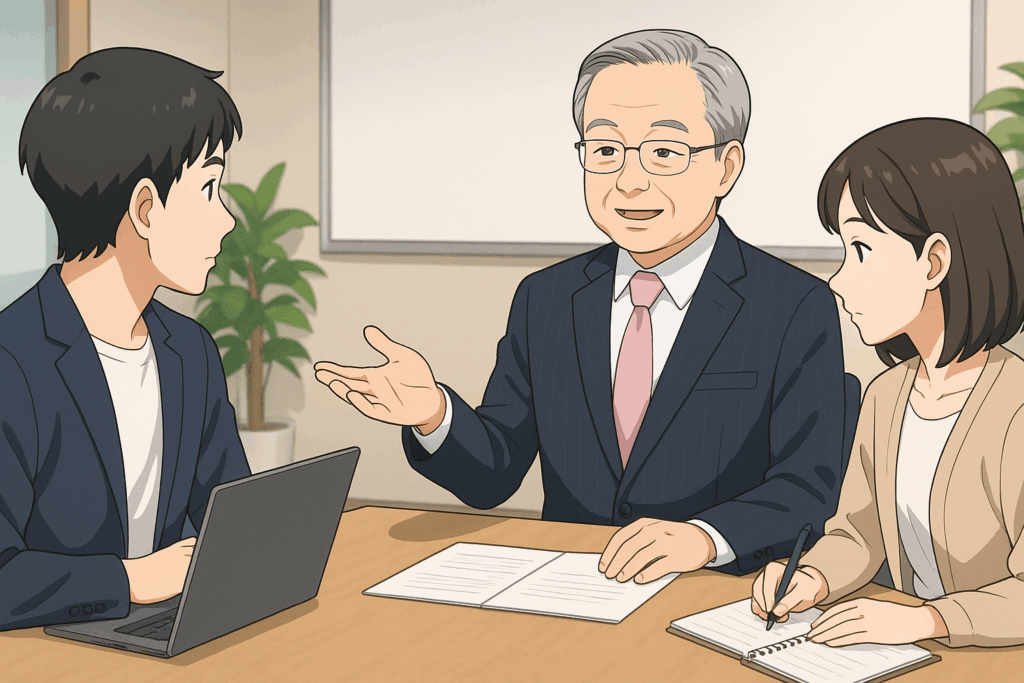
私は、中小企業の最大の弱みが「人材不足」であると認識しています。事業を拡大し成長させていくためには、何よりも人材の確保と育成が不可欠であると考えています。そのため、現在ハチ食品では、人材と人材育成に対して多くの時間と費用を投資しています。会社組織を強くし、事業の成長と人材育成を両輪で進めることが、健全な経営の根幹であるという強い信念を持っています。
就職活動中の学生に求める人物像については、特別な経験やスキルよりも、「自然で素直な人間関係のコミュニケーション能力」を重視しています。私自身の学生時代を振り返ると、社会に対して問題意識など持っていなかったと言えるように、学生に過度な期待はしていません。むしろ、会社に入ってから、企業が新入社員を教育し、様々な経験をさせることで人は大きく成長すると考えています。無理して学生時代に多くの経験を積む必要はありません。
さらに、Chat GPTのようなAIツールの普及により、学生時代に得た知識や経験の差が、仕事の成果の差に直結しにくくなっているという現代の状況についても言及します。これからの時代に求められるのは、AIを使いこなす能力に加え、オリジナリティや独自性を発揮することです。ハチ食品のような中堅企業では、大手企業と比較してチャレンジできる機会が多く、意思決定が早いため、一人ひとりが多様な経験を積み、大きく成長できる可能性を秘め、また若手が早期に活躍できる環境が整っています。
取材担当者(遠藤)の感想
「人材不足は日本全体の課題」というお話には深く共感しました。学生時代に無理して経験を積まなくても、会社に入ってから成長できるという言葉は、私たち就活生にとって大きな安心感につながります。Chat GPTの話も非常に興味深く、知識量よりも「オリジナリティ」が重要になるという考えは、これからの社会でどう活躍していくかを考える上で、とても学びになりました。若手社員が早期に活躍できる環境が整っているというお話は、中堅企業の魅力として強く心に残りました。

【社会とともに歩むハチ食品の企業文化】
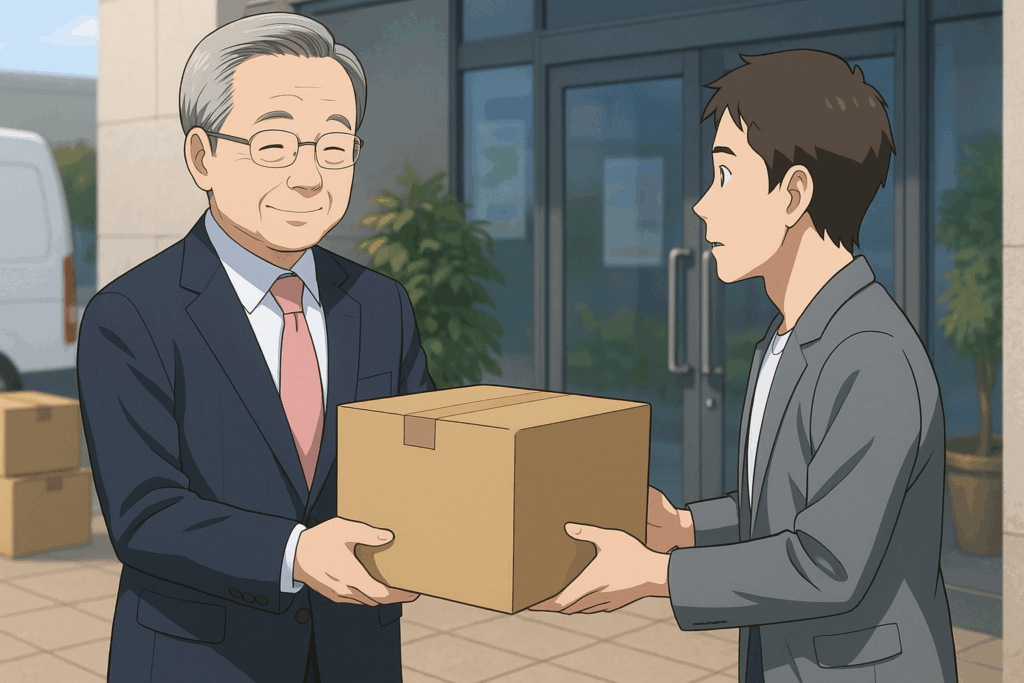
ハチ食品が事業を通じて特に力を入れている活動の一つに、社会貢献があります。食品メーカーであることの大きな利点は、作った商品が人々に喜ばれるという点だと感じています。カレーは特に人気が高く、子供食堂への寄付や、災害が起きた際の非常食提供など、NPO法人をはじめとする様々な団体からの要請に積極的に応じています。
これらの社会貢献活動は、単に社会に貢献するだけでなく、社員の成長にも大きく寄与すると私は確信しています。社員一人ひとりが、自分たちの仕事が社会に役立っている、人々に喜ばれているという実感を直接得られることで、大きなやりがいを感じ、それが個人の成長へと繋がっていくのだと考えています。これは、食品を扱う企業だからこそ享受できる、特別なメリットだと言えるでしょう。
しかし、マーケティングにおいては、幼い頃の食体験や家庭での記憶に根差した強いイメージが消費者心理に存在することも認識しています。こうした根強い価値観をどう乗り越えるか、あるいはどう活かすかが、今後のマーケティングにおける重要な課題の一つです。私はジェンダーの視点も意識し、多様な家族構成や価値観に配慮したブランディングの重要性を重視しており、広報活動においても細心の注意を払っています。
取材担当者(遠藤)の感想
食品メーカーが社会貢献に力を入れているというお話に、最後に胸を打たれました。特に、社員の方々が社会貢献の実感を通じて成長できるという点は、まさに企業文化の素晴らしさだと思います。自分が作ったものが誰かの役に立ち、喜ばれるというのは、仕事をする上で最高のモチベーションになりますよね。一方で、「幼い頃の食体験や家庭での記憶」というワードの持つ意味合いや、現代のジェンダー観に配慮した広報の難しさについては、私自身が大学でジェンダーを研究していることもあり、深く考えさせられ、とても勉強になりました。ハチ食品がただ美味しいカレーを作るだけでなく、社会や人、環境に配慮する多角的な視点を持っていることに感動しました。










