マロニー株式会社は、北海道産の馬鈴薯でんぷんなどを原料に、独自製法の澱粉麺「マロニー」を主力とする大阪・吹田の食品メーカーです。1950年に“もやし製造”の吉村商店として創業し、1963年に新製品を「マロニー」と命名、1964年には生産・試験販売を開始して家庭の鍋文化を支えてきました。
2017年にはハウス食品グループ本社の完全子会社となり、グループの商品開発力・品質保証力を活かしたブランド強化を進めています。
現在の代表取締役社長は井上寿夫氏(2024年就任)。今回は、「でんぷん麺の可能性で食卓をもっと楽しく」という想いとこれからの展望について、代表取締役社長 井上様にじっくりとお話を伺いました。
<聞き手=石嵜渉(学生団体GOAT編集部)>
【今までの経緯・背景】
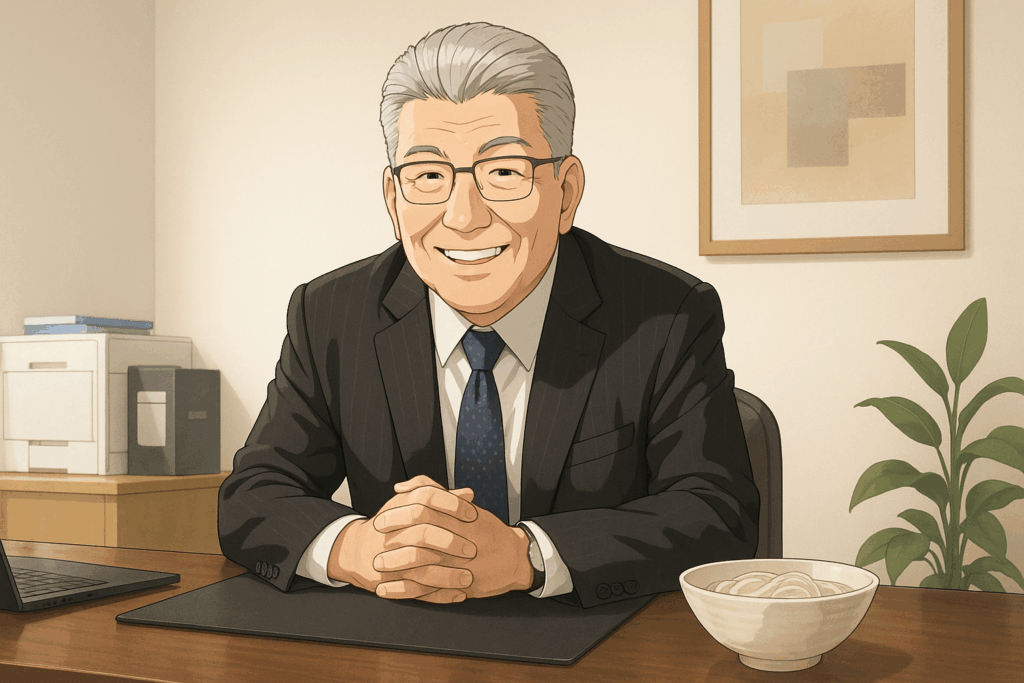
ハウス食品でのキャリアとマロニーへの就任
私自身は、1989年にハウス食品に入社しました。入社以来、営業一筋でキャリアを積みました。最初の赴任地が青森で、その後も盛岡、東京、広島、松山、札幌、大宮、大阪、東京など、全国各地を転々としてきました。ハウス食品で支店長などの役職に就くと、2年に1回または3年に1回といった頻度で異動がありました。最後はハウス食品の営業本部長を務め、去年の4月(2024年4月)からマロニーにお世話になる形となりました。マロニーの社長としての歴史はまだ浅く、1年半しか経っていません。
創業の志の継承と商品への愛着
マロニーが2017年にハウス食品グループのグループ会社となっても、深く知る機会は多くありませんでした。社長就任が決まってからは、まず50周年の記念誌を読み込むことから始め、マロニーの歴史や背景を深く調べました。この仕事に携わる者として、会社のことを好きになり、商品のことを好きにならないと、仕事は続かないと思っていましたから。
私は就任当時マロニーちゃんを使って自分で調理し、どういう食べ方が美味しいのか、新しい可能性がないのかというのを徹底的に探求しました。創業者の吉村氏がシベリア抑留という過酷な経験を経て、じゃがいものでんぷんを原料に新しいはるさめを開発した志を理解し、この商品をより深く愛するようになりました。
取材担当者(石嵜)の感想
大企業の営業本部長という要職から、別企業のトップへ就任された経緯に、井上社長のチャレンジ精神を感じました。特に、就任後すぐに自ら調理して商品への理解を深められたというエピソードに、仕事を成功させるためには、その対象(会社や商品)を心から好きになることが重要であるという社長の信念が表れていると感じました。これは、私たち就活生が企業を選ぶ際にも、給与や条件だけでなく、その会社や商品に「愛着」を持てるかどうかが重要であるという学びになりました。

【事業・業界について】
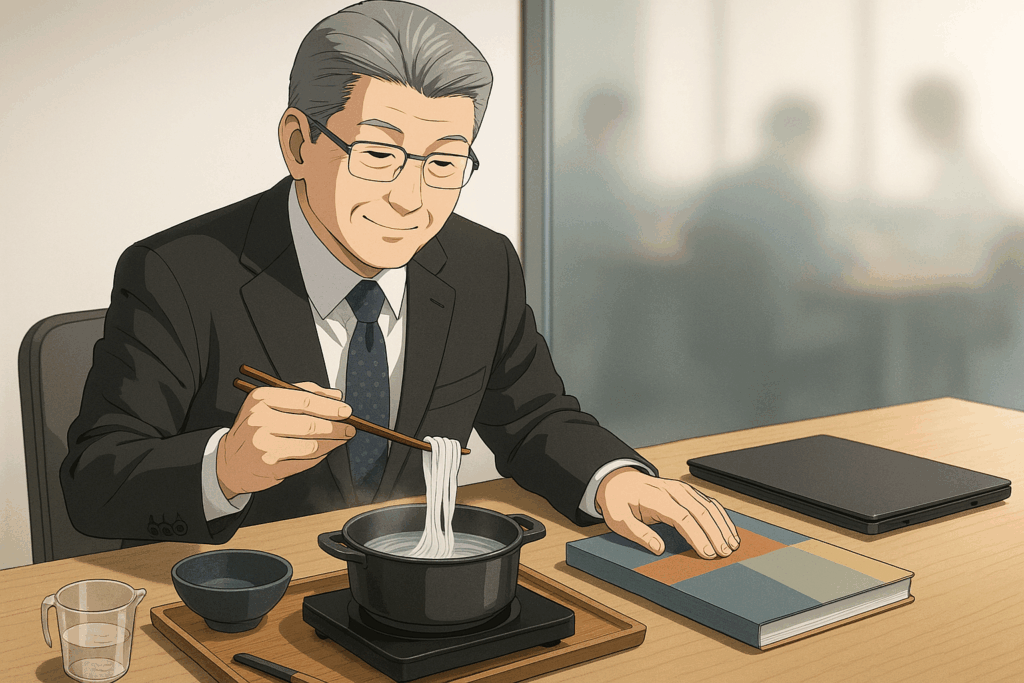
マロニー独自の強みと組織風土
マロニーの最も大きな強みは、特許を取った製法に由来する商品特性です。これが、長きにわたり多くの消費者に愛され続けている理由のスタート地点だと認識しています。
マロニーの組織文化は、元々社員が非常に真面目にしっかり働き、一人一人の守備範囲が広いという特徴があります。役職に関わらずある程度全体を把握している社員が多いです。
組織風土の改革と能動的な人材の育成
私自身が経営者として、会社全般のことを把握することに加え、組織風土をより良くすることを考えています。それぞれの会社には色があるため、当然良い色は残しながら、マイナスに作用する分であれば変えていく必要があります。社長が変わったからといって、前任者の全てを否定したり、ぶち壊したりするのではなく、変えるべきところがあれば変えていく姿勢で取り組んでいます。
こうした組織の改革を通じて、社員が能動的に動けるような環境を整えることを目指しています。自らが動かないと何も変えていけないと考えています。何を課題として捉え、その課題を放置せずどう解決していくのか、そういう人材は必要だと思っています。
取材担当者(石嵜)の感想
社員一人ひとりの守備範囲が広く、真面目であるという組織文化は、企業が長く愛されるための土台になっていると感じました。井上社長が「能動的に動く人材」を求め、課題を解決できる人材が必要だと語られている点は、社員の主体性を尊重し、成長を促す組織作りに力を入れている証拠であり、若手にとって非常に魅力的な職場環境であると感じました。

【今後の展望】
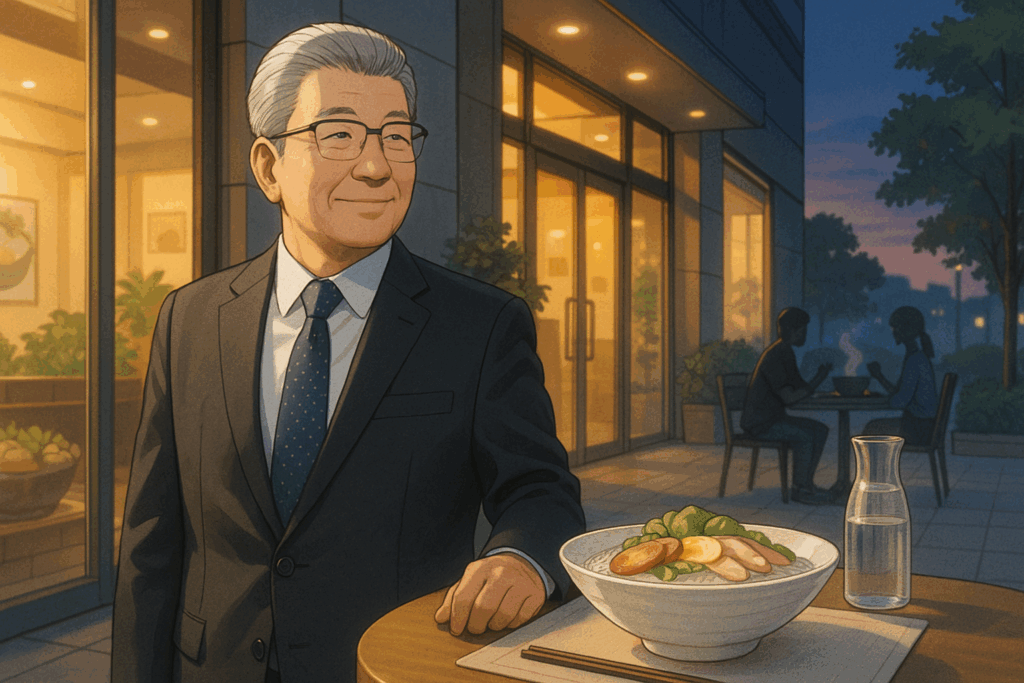
「お鍋の脇役」からの脱却と「主食化」
マロニーちゃんは、長年、お鍋の具材、つまり「お鍋の名脇役」というイメージで親しまれてきました。しかし、マロニーちゃんが生き残り、さらに成長していくためには、この固定概念から脱却する必要があります。
私たちは今後、マロニーちゃんを麺として、また主食として食べられるように育てていきたいと思っています。ハウス食品グループ全体を見ても、主食になる素材というのは多くありません。麺としての可能性は確実にあると思っています。
新しい時代の成長戦略
この「主食化」への道は、実現が簡単ではないと思っていますし、ステップを踏んでいかなければならないと考えています。しかし、マロニーがさらに成長していくためには、主食化の方向に舵を切るのも必要だと判断しています。
昨年がマロニーちゃん発売60年でした。今年が創業75年という歴史の中で、今後は「お鍋に入り続けて、ちょっと別の世界も見てみたいな」というストーリーで、「お鍋から出る」という仕掛けを作っていきたいと考えています。このビジョンは、既存の固定概念を打ち破り、新しい価値を創造することを目指しています。
取材担当者(石嵜)の感想
マロニーちゃんを「お鍋の脇役」から「主食」へと進化させようというビジョンは、非常に大胆で面白いと感じました。歴史ある商品が既存のポジションに安住せず、新しい可能性に挑み続ける姿勢は、私たち若者にとって、社会で働くことの面白さを教えてくれるメッセージだと感じました

【学生へのメッセージ】
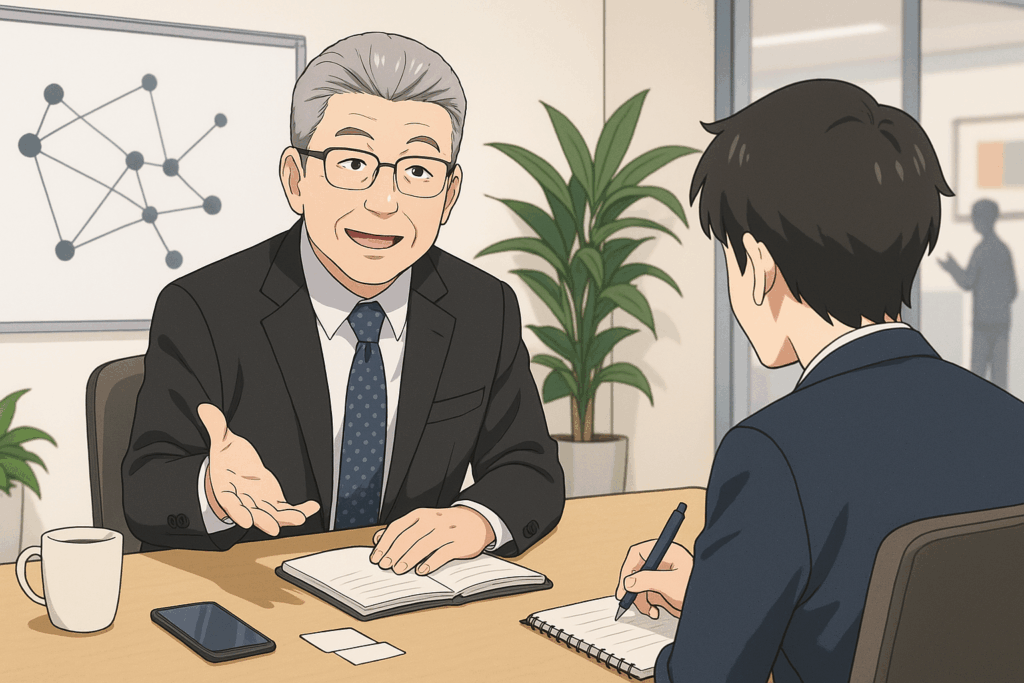
キャリア形成と企業側の整備
今の時代、終身雇用はもう流行らないのは事実です。自分のキャリアアップのために転職していくのが普通になっています。入社前から「何年後にこの部署にいたい」「10年後は海外に行きたい」と、まだ会社に入ってもいないのにキャリアプランをしっかり考えている学生が多いのを見ると、我々の世代とは全く違うと感じます。企業側もこの流れを分かった上で、どういうキャリアプランを用意できるのかという点を整備していかなければならないと思っています。
面接における「熱量」の重要性
面接の場では、学生が熱量を持って話しているかどうかを重視しています。過去、最終面接を担当していたとき、今の学生は事前準備をしっかりされ、よくリサーチされていると感じました。しかし、ちゃんと調べているのに熱量がないという学生も残念ながらわかります。言葉がうまくても思いが伝わらないことはありますし、逆に言葉が多少拙くても、気持ちが乗っていればプラスになります。口先だけで言われても、相手には響きません。
学生時代に積むべき経験値
学生時代に悔いを残さないように思いっきり謳歌しておくことも大切ですが、社会で活躍するためにやっておくべきこともあります。それは「人に会う」こと、そして様々な経験を積んでネットワークを広げることです。
例えば、アルバイトであっても、いろんな職に触れることができます。そこで様々な年代の人とも話すことで、経験値を積むことができます。会社に入ると、新入社員はなかなか社長や部長といった目上の人と話す機会が多くありません。だからこそ、学生時代に社会で活躍されている方と交流を持ち、ネットワークを作っておくことは、将来どこかで必ず活きてくる貴重な経験になると思っています。
取材担当者(石嵜)の感想
転職がトレンドとなっている現代において、企業側が学生のキャリアアップ志向を理解し、キャリアプランを用意していくべきだという考えは、非常に先進的だと感じました。一方で、面接で「熱量」が最も重要視されるという指摘は、私たち学生がどれだけリサーチをしても、最終的にはその仕事への情熱がなければ続かないという現実を突きつけられた気がしました。井上社長が推奨されるように、学生時代に多くの人と出会い、多様な価値観に触れることで、自分自身が本当に情熱を燃やせる仕事を見つけるための準備をすべきだと感じました。










