株式会社のぼるは、北九州を中心として、主に米を主体とした米飯加工品の製造販売を行う企業です。事業内容は、幼稚園・小学校給食、自園調理給食、施設食堂の委託業務などが主であり、事業の9割以上でお米が使用されています。当社は、安心で安全なものを安定して提供し続けることに重点を置いています。特にアレルギー対策に注力し、和菓子などの加工品を海外のバイヤーに紹介されるなど、国内のみならず海外展開も積極的に進めています。本記事では、ワタキューグループからの出向という形で社長に就任された川添社長の、経営の経緯、業界の現状、そして学生への期待についてまとめます。今回は、地域に根ざした米飯加工のものづくりを通じて、安全・安心な食の未来をどう描くのか、そして学生にどのような挑戦を期待しているのかについて、代表取締役社長・川添様にじっくりとお話を伺いました。
<聞き手=石嵜渉(学生団体GOAT編集部)>
【今までの経緯・背景】
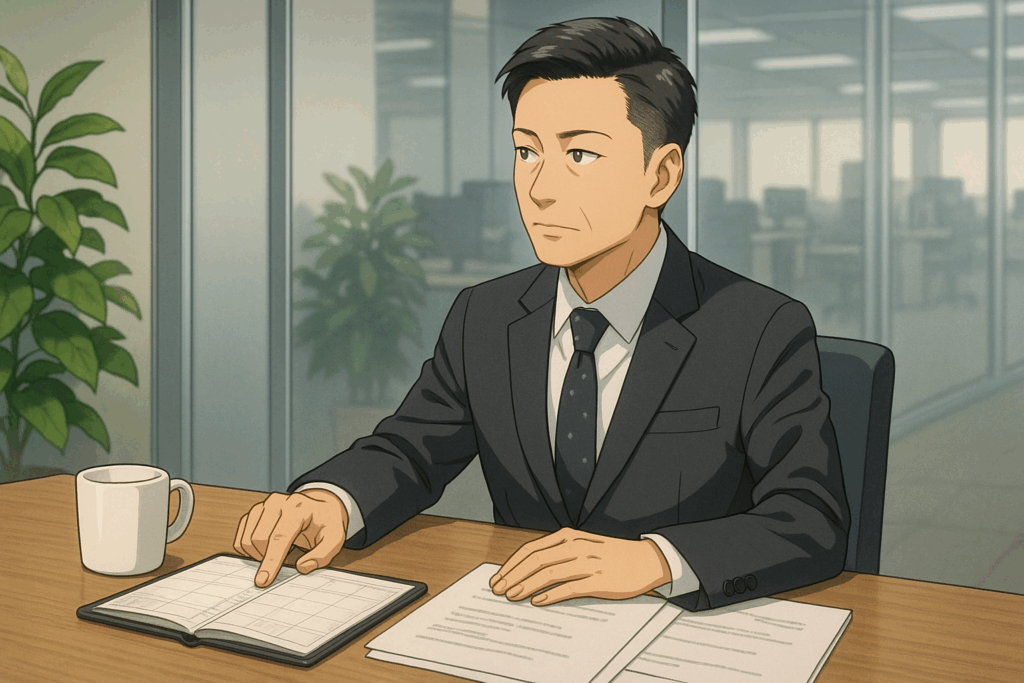
流れの中で食品業界のトップへ
私はワタキューグループの一員である日清医療食品からの出向という形で、株式会社のぼるの社長に就任しました。会社の創業者である前の前の社長がおり、私のひとつ前の社長からは日清医療食品からの出向という形になりました。前任の社長が65歳で定年退職したため、その後任として去年の11月からこの職務に就いており、約10ヶ月が経過したところです。こちらに来てからは2年が経過しましたが、前任の社長が辞めてからは約10ヶ月が経過したところです。
私自身、若い頃から自分で会社を経営、社長業を行うことは正直あまり考えていませんでした。ただ、食事に関することは学生時代のアルバイトから続けていたので、食に関わる仕事は元々やっていきたいという思いがありました。その流れの中で、この役割になったという感覚を持っています。
社長という立場に就任してからは、責任やプレッシャーを強く感じています。特にこの1年間は、米を主体とした米加工品や幼稚園のお弁当を扱う弊社にとって、非常に苦しい状況が続いています。株式会社のぼるでは、9割以上の部門でお米が使われています。この苦しい状況に対し、責任を持って対応しています。
取材担当者(石嵜)の感想
社長業に対して特別な志向を持っていたわけではなく、長年の食品業界での経験と、親会社からの出向という形で重要な役割を担うことになったという経緯に、キャリアの多様性を感じました。ご自身で社長業を意識していなかったとしても、食品への強いこだわりと責任感を持って事業に取り組まれている姿勢は、学生が将来のキャリアパスを考える上で、流れの中で役割を受け入れていく柔軟性も重要だと学ぶきっかけとなりました。

【事業・業界について】
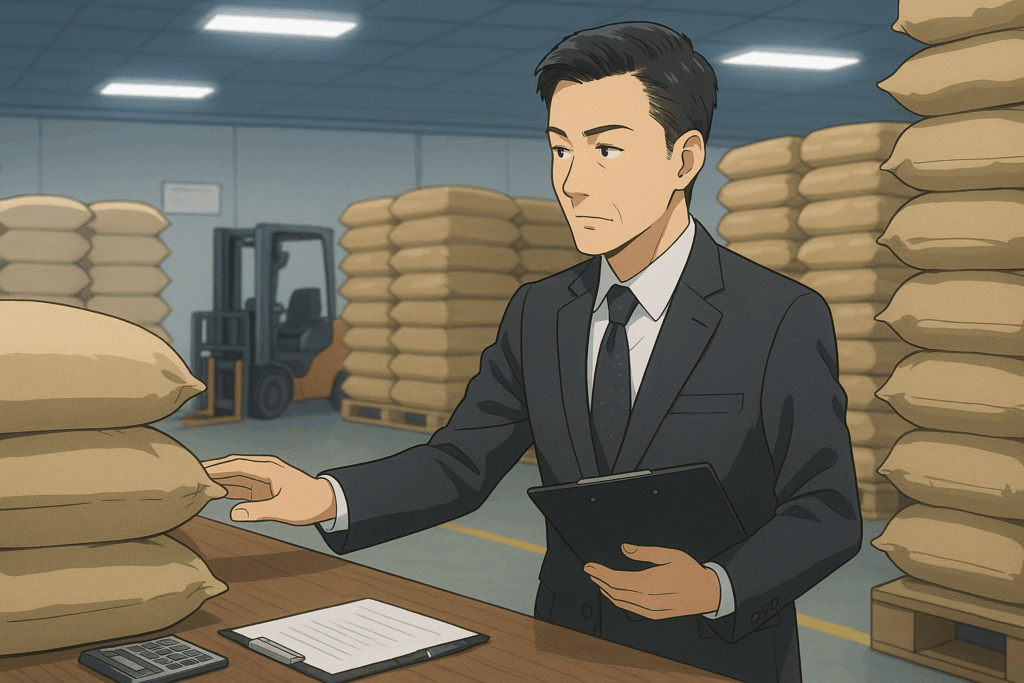
米価高騰と安心・安全への責任
米を主体とした米加工品、特に幼稚園のお弁当は弊社の事業の柱です。現在、温暖化の影響で米などの様々な原材料が手に入りにくくなっています。この中で価格転嫁をしながら運営していくことは非常に難しいと感じています。特に米の価格は急激に高騰し、以前と比べて一気に2倍3倍という形になりました。徐々に上がるのであれば、対応もできましたが、急激な高騰でした。
お米はすぐ値上げされますが、加工したものは、加工すればするほど価格に転嫁しにくくなっていきます。この価格転嫁の難しさが、ここ1年で非常に苦しい状況を作っていると感じています。さらに、国の備蓄米については、最終消費者に直接渡すルートしか使用が認められていません。我々のように、お客様と契約し、そこに下ろして販売してもらう形態では、備蓄米は一切使えないため、非常に苦しい状況が続いています。ただ、値上げに応じてくださるお客様も多くいるため、お客様に助けていただきながら、運営を進めていきたいと考えています。
弊社が製造する幼稚園のお弁当は、特に子どもたちが食べるため、安心で安全なものを安定して提供し続けられることが最も重要です。子どもの体重は大人(1/3の体重)に比べて小さく、食品の影響を良くも悪くも大きく受けると考えます。最近はアレルギーを持つ子どももかなり増えているため、アレルギー対応も含め、子どもたちが安心して食べられることは非常に大事な要素です。以前は病院や老人ホームの食事に関する仕事をしていましたが、より小さく影響を受けやすい子供たちの食事が非常に大事だと再認識しています。
現場での雇用戦略と外国人材の活用
当社の工場は365日、24時間稼働しています。夜中から朝方にかけて幼稚園のお弁当に関わる仕事があり、日中はスーパーや飲食店向けのデリカの製造・運搬を行っています。そのため、おのずと夜勤が発生します。夜の時間帯は今、人材確保が非常に難しく、現在は管理者と技能実習生が中心の運営になっています。
一方で、学校の厨房等の現場で働く日本人スタッフは、小学校などで働くため、小学生の子供を持つお母さん方が多いです。子供と同じタイミングで休みが取れるという利点を提供しています。また、子供が成長して手が離れると工場へ異動してもらったり、子供が小さい時は保育園や学校の仕事をするなど、柔軟に移動してくださる方もいます。夜勤については、日本では夜中に働きたいという人はなかなかおられません。しかし、ミャンマー、カンボジア、ベトナムなど技能実習生はハングリーなので、夜中働けば時間の単価が高いことを知っており、夜中の仕事をしたいという方も多くいます。そういった条件で、現地で採用させてもらい、彼女たち、彼らたちに大きな力を借りて運営させてもらっていると感じています。
北九州を中心に160以上の園でお弁当を取っていただいており、子供を持つお母さん方の中には、当社のことを知っていただいている方も非常に多いです。応募理由を聞くと、「子供が食べている、のぼる弁当の会社で勤めてみたいと思いました」と言っていただけるので、そういった面では、非常にやりがいのある仕事だと感じています。
取材担当者(石嵜)の感想
米価高騰や備蓄米利用の制限といった、食品加工業界が直面する厳しい現実を知り、衝撃を受けました。その中でも、特に幼稚園給食という、食の安全性が最も強く求められる分野で、責任感を持って事業を続けている点に感銘を受けました。また、夜勤が避けられない現状に対し、技能実習生の力を借りつつ、一方で子育て中の母親たちが働きやすいように柔軟な勤務体制を提供している点は、企業としての人材への配慮を感じ、非常に勉強になりました。

【学生へのメッセージ】
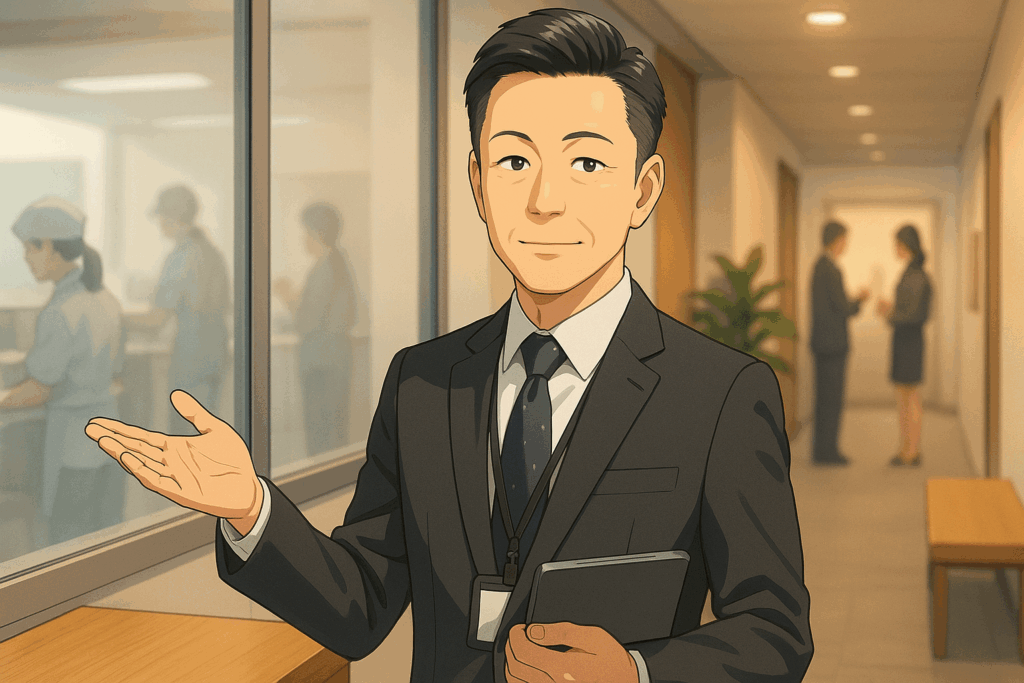
自分に合った職場選びと、変化への対応
食品製造業は、マヨネーズのようにボトル化された製品でない限り、どうしても人の介入が非常に多い産業です。人と人が集まって、人手で仕事を行う業務も少なくありません。現在、人とコミュニケーションを取るのが苦手な人も増えています。そのため、黙々とやる工場の仕事がしたいという方もいれば、コミュニケーションを取りながら働きたいと言ってくださる方もいます。学生の皆さんには、どのように自分に合った職場で働いていくか、どのように職場に合った自分に成長していくかをよく考えた方が良いと思います。
コミュニケーションの密度や、働く場所が自分に合うかを事前にしっかり考えないと、ミスマッチングが起きる可能性があります。就職活動では、業界の一般的な情報だけでなく、働く環境が自分に合っているかを深く見極めることが重要です。社会は絶えず変化しています。最近はTikTokで大量の商品が売れるなど、時代はどんどん変わっています。その変化に乗っていかなければならない部分もありつつ、食品製造業においては、足元でしっかり安全な食品を美味しく作っていくということが常に必要になっていきます。変化に対応しつつも、食品という基盤となる分野での基本的な取り組みが大事だと考えています。
取材担当者(石嵜)の感想
食品製造業が、AIやテクノロジーが進んでも「人の介入」が不可欠な産業であるという指摘は新鮮でした。就職活動において、業界の成長性や給与といった外的要素だけでなく、自分がどのような環境で、どれくらいのコミュニケーション密度で働きたいのかという、働く上での「相性」を真剣に考えることの重要性を再認識しました。

【今後の展望】
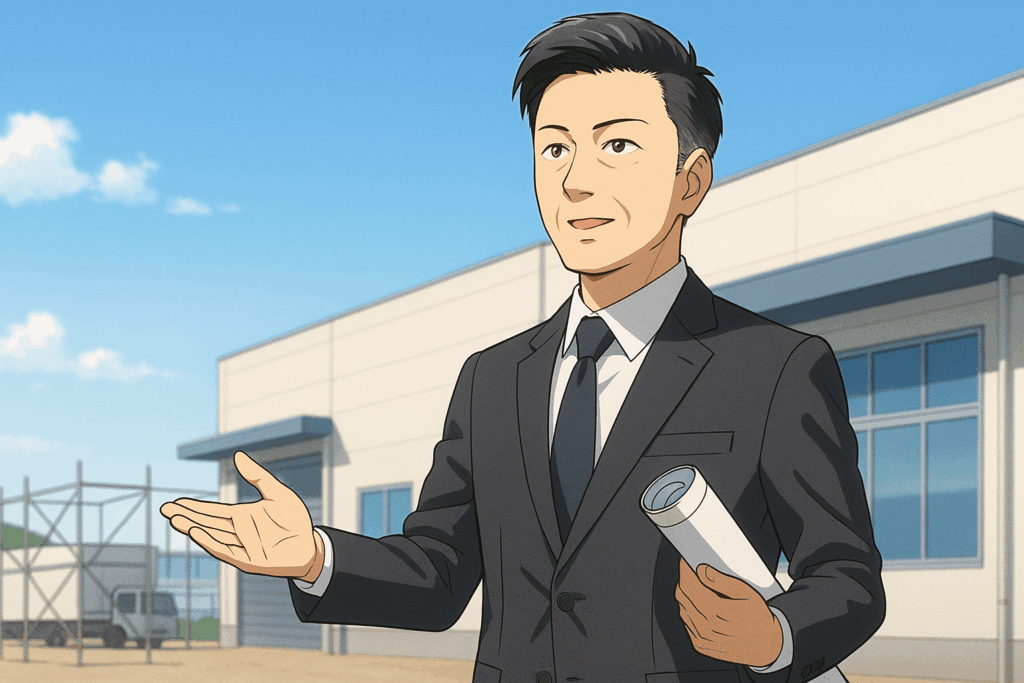
計画生産への移行による働き方の安定
現在の主力商品である日配品(幼稚園弁当など)は、賞味期限が非常に短いものを短期間で作って出荷する仕事がメインです。そのため、年末年始などの繁忙期にはどうしても働き方がデコボコになったり、少し辛い時期があったりします。当社には1時間に1トンの米を炊く炊飯機がありますが、繁忙期には何十トンもの米が必要になってきます。
この働き方の課題を解決するため、今後は賞味期限が長くて計画生産ができるような商品がないかと考え、冷凍の米飯半加工品、例えばおにぎり、いなり、おはぎなどを開発し、いろんなところに提供していこうとしています。この取り組みのために、現在、輸出用の専用工場を建築予定です。
冷凍商品は、日本国内の離島や山間部などの店舗や大手のスーパー様に取り扱ってもらっています。また、海外でも北米、スペイン、フランス、オーストラリアで定期的に購入いただいています。ある程度賞味期限があるので、計画生産が可能です。
お弁当のように日々製造していかなければならない仕事は、大変重要なお仕事ですが、働く方にとっては少し働きづらいと思われる方もいらっしゃると思います。この計画生産できる部分を増やすことが、これからの事業の柱となると考えています。例えば、冷凍のおにぎりであれば、夜中の作業にしなくてもいいわけです。夜中の仕事を少なくし、お昼間の仕事を増やすことによって、採用者が増えてくるのではないかと考えています。
取材担当者(石嵜)の感想
主力事業の特性上、夜勤や特定の繁忙期を避けることが難しい中で、冷凍加工品という新しい分野に挑戦し、事業構造そのものを変えることで、従業員の働きやすさや定着率を向上させようとしているビジョンに感銘を受けました。未来を見据えた計画生産への取り組みは、企業の持続可能性と社会貢献の両立を目指す、非常に優れた経営戦略だと感じました。










