日本には、脈々と受け継がれる伝統を守りながらも、時代の変化に合わせて進化し続ける企業があります。創業372年を誇る老舗寿司店「鮨萬」様もその一つです。承応二年(1653年)に魚屋として始まり、天明元年(1781年)には大阪名産の雀鮨専門店として確立しました。仙洞御所への献上や明治天皇からのご用命も賜るなど、その歴史と格式は日本食文化の礎を築いてきました。
「鮨萬」様は、創業以来受け継がれてきた伝統の味と調理法を守りながら、押し寿司の元祖としてその名を馳せています。今では、あべのハルカス近鉄本店、松坂屋名古屋店、そごう横浜店、渋谷西武店など、全国主要都市の百貨店やホテルにも店舗を展開しています。単なる老舗にとどまらず、新しい挑戦を続けるその姿勢は、Z世代の若者たちが社会で活躍するためのヒントに満ちています。今回は、370年を超える伝統と革新の歩み、そしてこれからの展望について、代表取締役社長 小倉様にじっくりとお話をお伺いしました。
<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>
【伝統を受け継ぐという選択:老舗の継承者が歩んだ道】
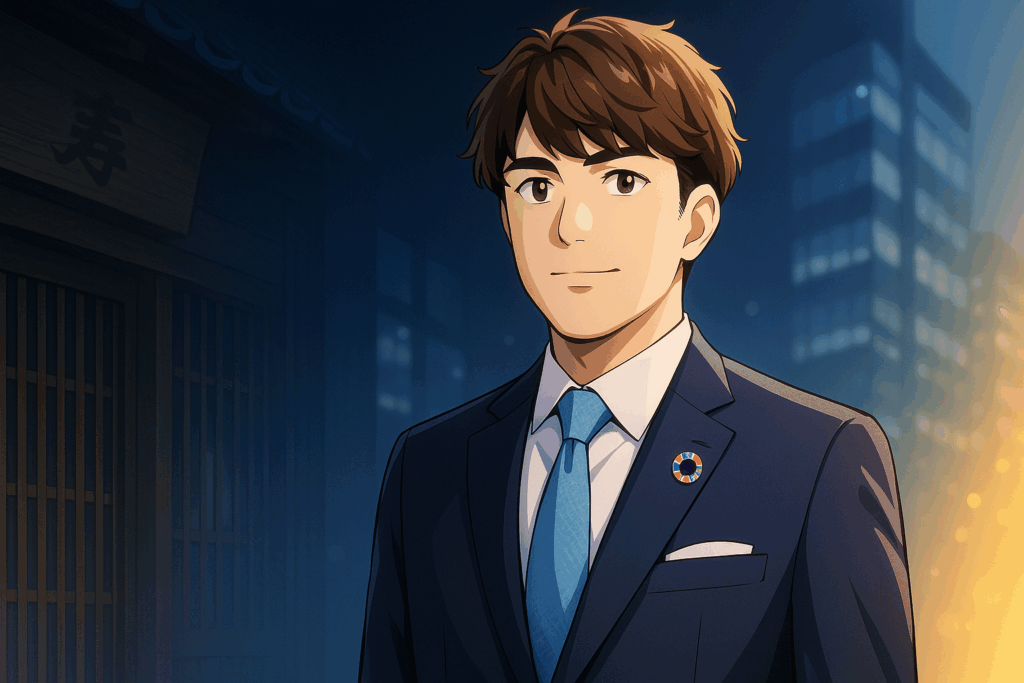
幼い頃から家業である寿司屋が身近な存在でした。高校時代には実際に店でアルバイトもしていました。しかし、学生時代は家業を継ぐつもりは正直ありませんでした。私は自分の好きなことを見つけたいと考えていたので、一般の就職活動を行い、食品・飲料メーカーで営業職として約8年間勤務しました。大阪、岡山での勤務を経て、30歳になるまで会社員としてのキャリアを積んでいたのです。
転機が訪れたのは、30歳の頃に父親である当時の社長から家業を継いでほしいと打診された時でした。すぐに決断できたわけではなく、3ヶ月ほど悩みました。しかし、家業がもたらしてくれた恩恵、例えば様々な人との出会いや育ってきた環境を考えると、「これを断るのは義理じゃない」と感じました。家族としてどうあるべきかを熟考した結果、会社を退職し、家業である「鮨萬」に入社することを決意したのです。この時、私は31歳でした。
「鮨萬」への入社後、私はすぐにお寿司を握ったり、押し寿司を作ったりする調理の現場には立ちませんでした。専務取締役として経営を学ぶことに専念したのです。これは、自身の外部の企業での経験を生かし、会社全体の組織改革を進めるための重要なステップでした。伝統を守るだけでなく、新しい風を吹き込むための準備期間であったと言えるでしょう。
取材担当者(高橋)の感想
小倉様が一度は家業とは異なる道を選び、社会人としての経験を積んでから再び家業に戻るという経緯は、多くの就活生にとって示唆に富んでいると感じました。特に、ご自身の意思だけでなく、家族からの期待や、家業がもたらしてくれた恩恵への「義理」を深く考慮された点は、自身の人生の目的を考える上で非常に学びになります。単なる義務感だけでなく、感謝の気持ちから生まれる決断の重みを教えていただきました。

【組織と味の革新:老舗を未来へ導く経営改革】
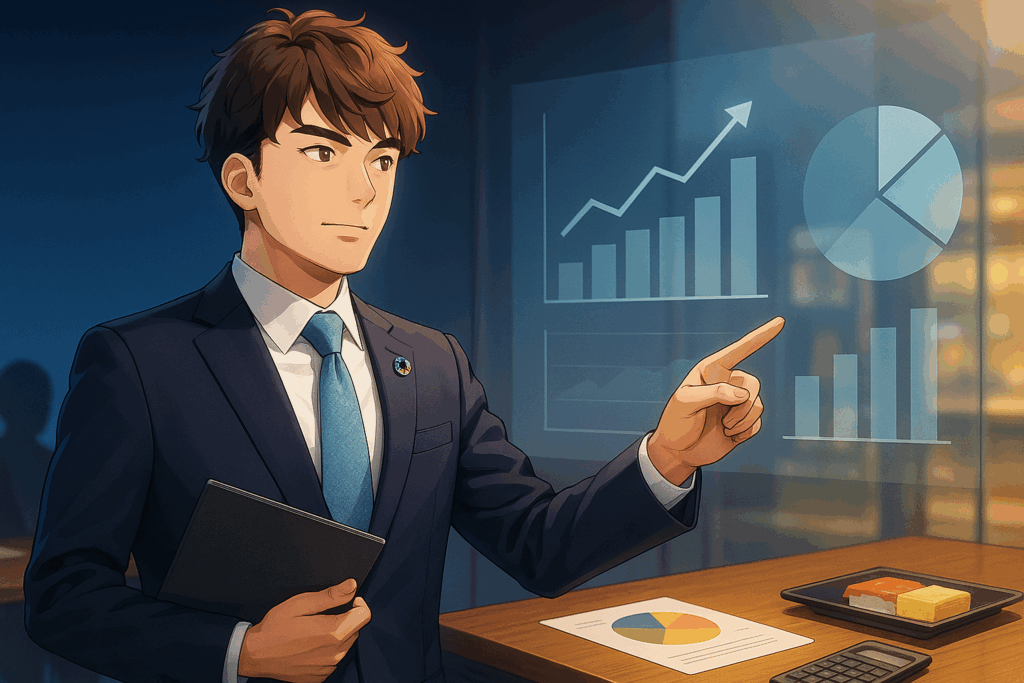
「鮨萬」に入社した当時、会社は好調で売上が落ちることはほとんどなく、順風満帆な状況でした。しかし、前職での大企業での経験から、当時の社内には定例会議や打ち合わせが曖昧で、経営が「どんぶり勘定」で行われている部分があることに気づきました。そこで、会社をさらに強くするため、組織の「粗を探す」ように改善点を見つけ出し、様々なルールを整備していきました。
具体的には、現場の店長たちと密に打ち合わせを行い、月替わりのメニューの企画、価格設定、原価計算などを徹底するようになりました。これにより、感覚ではなく具体的な数字に基づいた経営判断が可能になり、各店舗の収益性や従業員の給与支払い能力も明確に把握できるようになったのです。これは、安定した経営基盤を築く上で不可欠な改革でした。
また、伝統的な押し寿司を大切にしつつも、若い世代にもアプローチできる新たな商品開発の必要性を感じ、これにも力を入れました。伝統的なやり方だけでは今後生き残れないという危機感を持ち、「伝統ある会社にはしたいが、古臭いやり方をしていてはダメだ」という信念のもと、私自身の外部での経験を積極的に社内に取り入れました。そして、専務就任から3年後、34歳の時に創業360周年という節目の年に、代表取締役社長に就任しました。
取材担当者(高橋)の感想
右肩上がりの時期にあえて組織内部の課題に目を向け、改革を断行された小倉様の経営手腕には感銘を受けました。特に、これまでの「どんぶり勘定」から具体的な数字に基づいた経営へと転換されたことは、伝統企業が未来に向けて持続的に成長するための重要な一歩だと感じます。伝統を守りつつも、時代に合わせて「変えるべきところは変える」という柔軟な思考は、変化の激しい現代を生きる私たちZ世代にとっても大きな学びとなりました。

【飲食業界の課題と「働く場所」としての魅力創出】
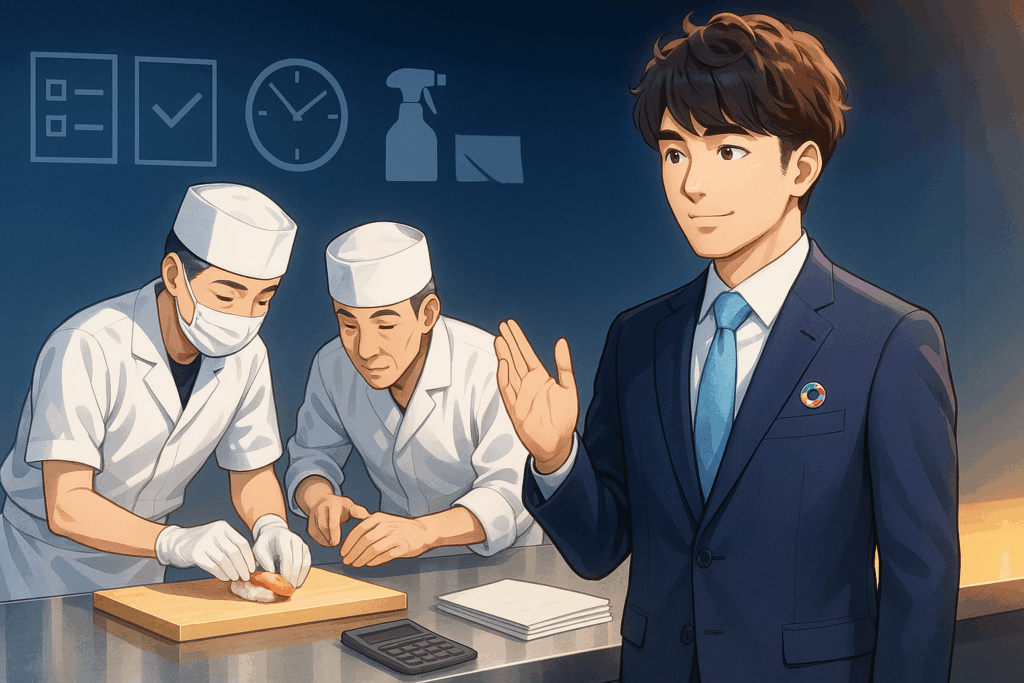
飲食業界全体が直面している最も大きな課題は「人材不足」だと感じています。少子高齢化が進む中で、飲食業界だけでなく、あらゆる業界で若手人材の獲得競争が激化しています。さらに、飲食業は平均賃金が他の業界に比べて低い傾向があり、多額の学費を投じた大学卒業生が選択肢に入れにくいという現実があるとも認識しています。
加えて、飲食業界には「きつい」「汚い」「危険」といった「3K」のイメージや、長時間の労働、かつてはパワハラが横行していたといった負の側面も存在すると感じています。これらのイメージが、若者が飲食業を志す大きな障壁となっているのが現状です。しかし、私は「鮨萬」を通じて、こうした業界全体のイメージを変えたいと考えています。
「鮨萬」では、「働きやすい、働きたい飲食業の実現」をビジョンに掲げ、「クリーンなホワイト企業」を目指しています。残業代の支払いや勤務管理の徹底など、労働環境の改善に積極的に取り組むことで、飲食業の「古臭い」イメージを払拭しようと努力しています。さらに、若手人材へのアピールポイントとして、回転寿司以外では珍しい熟練の職人が多く在籍していること、百貨店やホテルでの提供を通じて豊富な経験を積めること、そして希少な食材に触れる機会が多いことの3点を挙げています。
取材担当者(高橋)の感想
飲食業界が抱える厳しい現実と、それに対して小倉様が真摯に向き合い、改革を進めていることに心を打たれました。特に「クリーンなホワイト企業」を目指すという姿勢は、私たちZ世代が仕事を選ぶ上で重視する「働きがい」や「自己成長」といった価値観に合致すると思います。小倉社長が語る「鮨萬」ならではの魅力、例えば多くの熟練職人から学べる環境や、高品質な食材に触れられる機会は、技術を追求したいと考える学生にとって非常に魅力的だと感じました。

【400年企業への挑戦:誰もが「最高級」を感じる場所へ】
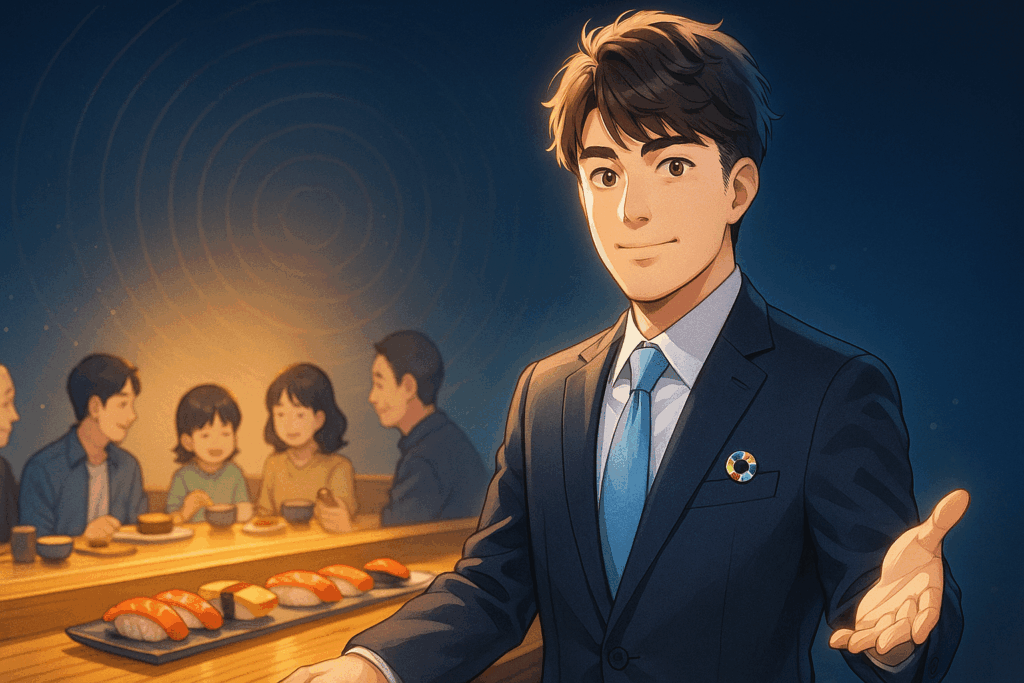
創業372年を迎える「鮨萬」の16代目社長として、私が掲げる今後の最大の夢は、会社の「創業400年」を達成することです。残り28年という道のりですが、私自身が社長を務める限り、この伝統をしっかりと受け継いでいきたいという強い思いがあります。そのミッションとして、「あらゆる人と人がつながる幸福な時間を提供する」ことを掲げています。
このミッションには、「鮨萬」が目指す「世界中の誰にとっても最高級の寿司店」というビジョンが込められています。それは、予約が困難な高級カウンター寿司店のように、特定の富裕層や限られた人々だけが利用できる場所ではありません。私は、来店客層の多くを占める60代、70代のお客様だけでなく、商品単価が高く気軽に手が届かないと感じる若い世代にも、もっと気軽に「鮨萬」の味を楽しんでもらいたいと考えています。
そのため、「鮨萬」は、商品価格を抑えたり、若い世代の嗜好に合わせた商品開発にも取り組んでいます。誰もが「鮨萬」の寿司を楽しめる「みんなの最高級」を目指し、誰もが気軽に足を運べる場所、3ヶ月に一度、半年に一度でも「また来たいな、楽しかったな」と思えるような店づくりを追求しています。この「みんなの最高級」という考え方は、伝統を未来に繋ぎ、より多くの人々に幸せを届けるという私の強い決意の表れです。
取材担当者(高橋)の感想
「みんなの最高級」という小倉様のビジョンは、非常に心に響くものでした。ただ単に技術や品質を追求するだけでなく、その「最高級」を誰もが享受できるものにしたいという思いは、私たちが社会貢献を目指す上で見習うべき視点だと感じました。長く続く企業の責任として、文化や伝統を守りながらも、時代と共に変化し、より多くの人々に価値を提供し続ける「鮨萬」の姿勢は、私たちZ世代が社会で自分たちの強みを生かし、貢献していく上での大きな指針になると確信しています。










