庄原市総合サービス株式会社様は、広島県庄原市を拠点に、地域に密着した多様なサービスを提供する第三セクター企業です。2004年1月20日に庄原市が100%出資して設立され、これまで市が直接運営していた体育館、保育所、学校給食などの公共施設の管理・運営を担い、市民生活を支える重要な役割を果たしています。従業員の健康増進にも注力しており、2022年には「ひろしま企業健康宣言 健康づくり優良事業所」の最高基準(金色:5つ星)に認定されるなど、働きやすい環境づくりも重視しています。本記事では、代表取締役の田坂様へのインタビューを通じ、当社の地域貢献、人材育成への想い、そして未来を担う若者への期待に迫ります。
<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>
【庄原市総合サービスの設立背景と地域貢献】
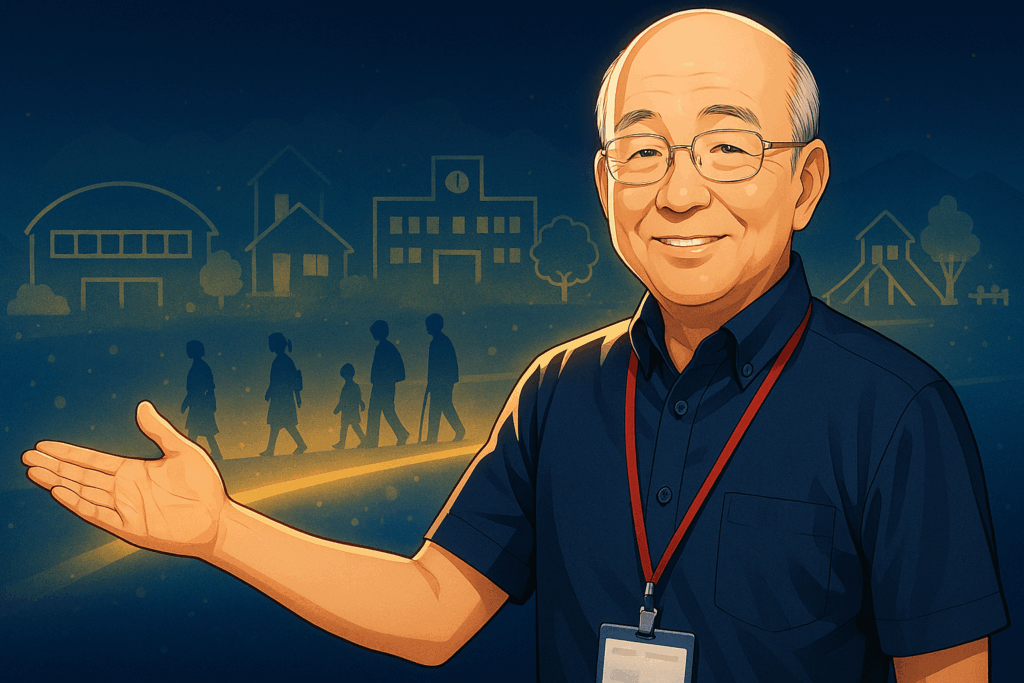
庄原市総合サービスは、市役所の人件費削減と知的分野への注力のため、公共施設管理業務が外部委託される形で誕生しました。当社が担う事業は、かつて市役所が直営で運営していた体育館、保育所、学校給食などの多岐にわたる公共施設の管理業務を含みます。
当初、保育所の運営委託を民間企業に任せることに対し、保護者や地域住民から不安の声が挙がりました。しかし、当社は市と連携し、十分な体制を整え、市の厳格な仕様書に基づいた運営を丁寧に説明することで、市民の信頼を築き、事業を開始しました。
私は、現在この会社の二代目の社長を務めています。当社に就任する前は、JR立花駅(尼崎の隣)を拠点に、三菱電機関連の電子部品メーカーで営業を担当し、全国を飛び回っていました。
そこで、売上、人件費、コスト管理といった民間企業での経営実務を経験しました。これらの民間での豊富な実績が評価され、社長に就任しました。私は、予算を使い切る傾向がある行政組織に対し、民間企業ならではの「もったいない精神」が効率的な経営には不可欠であると考えています。民間出身の社長だからこそ、会社経営を任せられると私は認識しています。
約20年にわたり、当社は庄原市が抱える様々な課題に対し、学校給食関連事業や多岐にわたる公共施設の管理を通じ貢献してきました。市民生活に密着したサービスを提供することで、地域になくてはならない存在として、庄原市の活性化の一翼を担っています。
取材担当者(高橋)の感想
庄原市総合サービス様が、もともと市の直営だった事業を引き継ぎ、市民の生活を根底から支えていることに感銘を受けました。田坂様が民間企業での豊富な経験を活かし、公共性の高い事業においても「もったいない精神」をもって効率的な経営を目指されているというお話は、民間ならではの視点が非常に重要であると感じました。地域に深く貢献する企業として、その設立背景と役割を理解できたことは大きな学びです。

【庄原市と若者の現状、そして人材確保への挑戦】
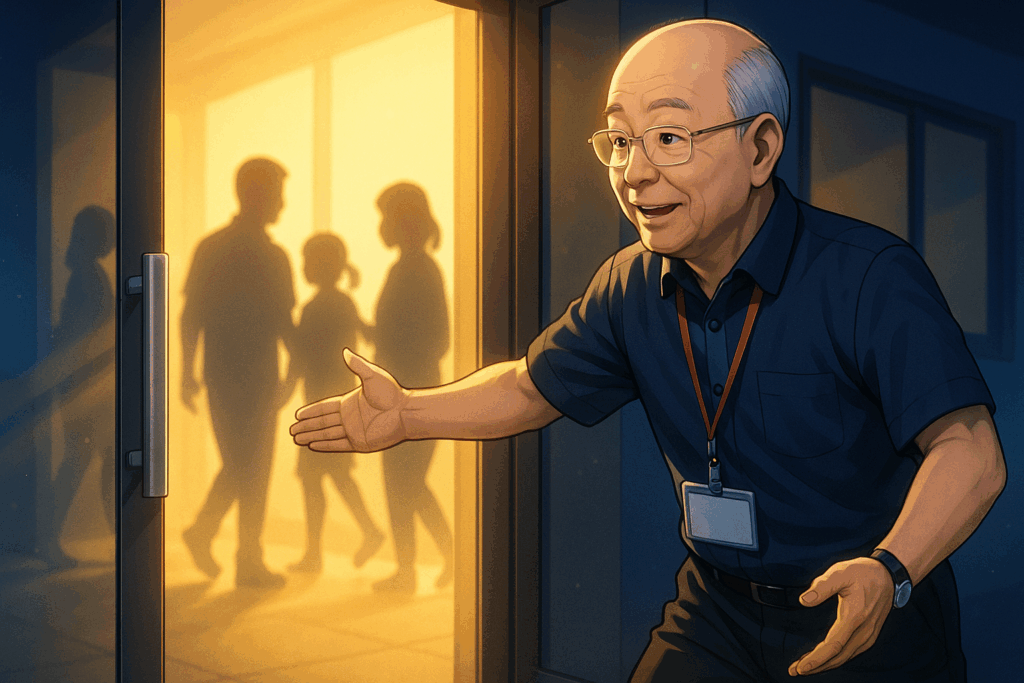
庄原市は、現在人口約3万1千人弱と人口減少が深刻な地域であり、特に20代の若者の市外流出が課題です。若者が職を求めて都市部へ移る傾向が強く、庄原市での若者の定着率は低いのが現状です。当社でも全社員約200名中、20代は1%にも満たず、保育士などの新卒採用に力を入れているものの、広島市内への就職を選ぶ若者が多いため、Uターン・Iターン人材が主要な採用源となっています。
当社が運営する保育所や学校給食の現場では、保育士、調理師、看護師などの資格を持つ人材が必須となります。庄原市内の限られた人材プールの中で、競合他社との人材獲得競争も激化しており、定年退職者への対応を含め、常に人材確保が大きな課題です。しかし、当社は単に資格保持者を採用するだけでなく、意欲ある若者を支援する体制も整えています。
20代や30代で資格を持たない応募者に対しても積極的に採用を行い、保育士や調理師であれば2年間の実務経験を積むことで資格取得が可能となる制度を活用しています。資格取得にかかる費用の一部を補助するなど、長期的な視点で人材育成と定着を促進しています。
庄原市自体は、ブランド牛、豊かな自然、広大な国営公園、伝統文化、そして当社の貢献による充実した子育て・教育支援など、多くの魅力を持っています。当社は、こうした地域の魅力を背景に、資格を持つ人材が庄原市に戻ってきても仕事がないという状況を避けるため、「仕事があるから戻ってきてほしい」というメッセージを発信し、雇用の受け皿となる役割も果たしています。採用活動では、新聞広告、ウェブサイト、SNSなどを活用し、若い人々の目に留まるように工夫しています。
取材担当者(高橋)の感想
人口減少という日本全体の課題が、庄原市という具体的な場所でいかに深刻であるかを痛感しました。特に、資格が必須な職種での人材確保の難しさや、若者の流出という現実を伺い、その中で会社が未経験者への資格取得支援まで行う手厚いサポート体制を築いていることに感銘を受けます。庄原市の持つ多くの魅力を活かしつつ、若者が安心して働ける環境を整えようとする企業の努力と覚悟を感じました。

【未来を見据えた新規事業と社内活性化への取り組み】
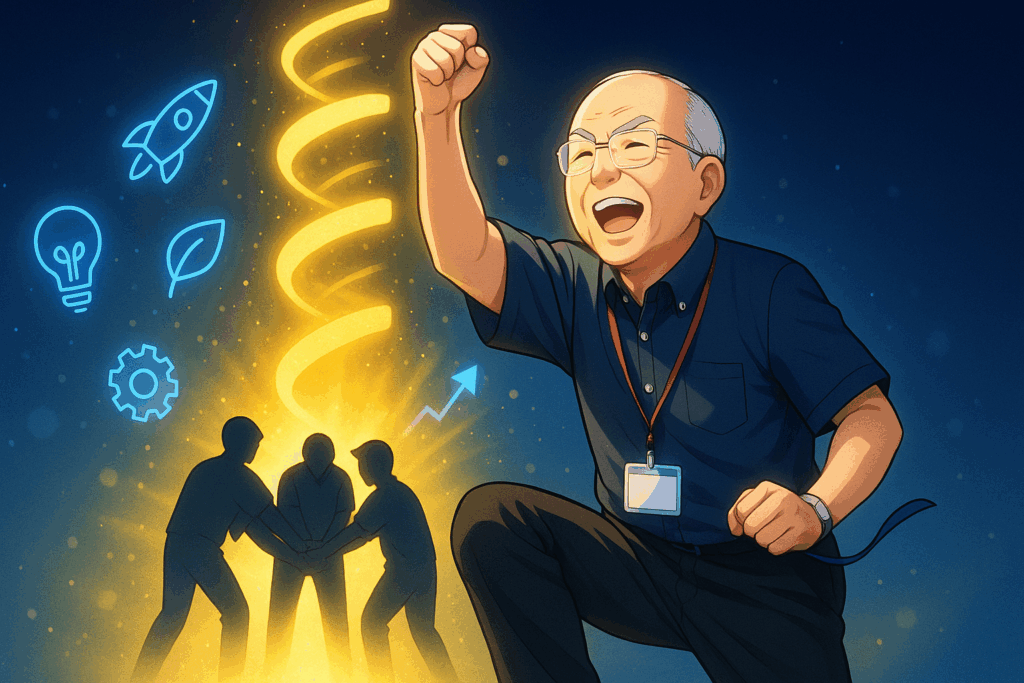
庄原市総合サービスは、人口減少の波に抗しきれない現状を認識しつつも、庄原市を活性化させるためには「一人でも多くの若者を呼び込みたい」という強い思いを抱いています。そのためには、現在の市の受託事業だけに依存するのではなく、新たな事業を創出する必要性を感じています。
市が100%出資する企業であるため、「民業圧迫」への懸念も指摘される難しい課題ですが、時間だけが過ぎて若者が入ってこない状況を避けるため、民間企業では採算が合わず難しいと判断されるような事業領域を見つけ、そこに挑戦することで新しい雇用を創出し、若者を呼び込むことを目指しています。私たちは「口を開けて待っていれば仕事が来る」という現状が社員を「茹でガエル」にしてしまう危険性を認識し、常に社員に刺激を与えることを重視しています。
その一環として、「新規事業プロジェクト」を立ち上げ、社員から新しい仕事のアイデアを募り、運営した経験もあります。社員が新しい仕事に挑戦することで新たな知識や地位が生まれ、それが社員自身の活性化、ひいては会社の元気、そして自分たちが稼いだお金を自由に使えるという好循環(スパイラル)を生み出すことを目指しています。
また、庄原市には林業、畜産、農業といった一次産業は存在しますが、サラリーマンが安定した給料を得られるような職種が少ないため、生活に不安を感じる若者もいます。私たちは、新たな産業や職種を取り込み、若者が生活に不安を感じずに暮らせる環境を整えたいという夢を持っています。これにより、庄原市と会社、そして働く人の双方が幸せになる状態を追求したいと考えています。
取材担当者(高橋)の感想
田坂様の「茹でガエル」という言葉に、現状維持の危険性と、そこから脱却しようとする強いリーダーシップを感じました。市の受託事業だけでなく、未来を見据えて民間では難しい新規事業に挑戦し、社員を巻き込みながら活力を生み出そうとする姿勢は、まさに地域を動かす原動力だと感じます。若者が安心して働ける新たな産業の創出という夢は、庄原市の未来にとって不可欠だと強く共感しました。

【学生・若者へのメッセージ:未来を切り拓くための視点】
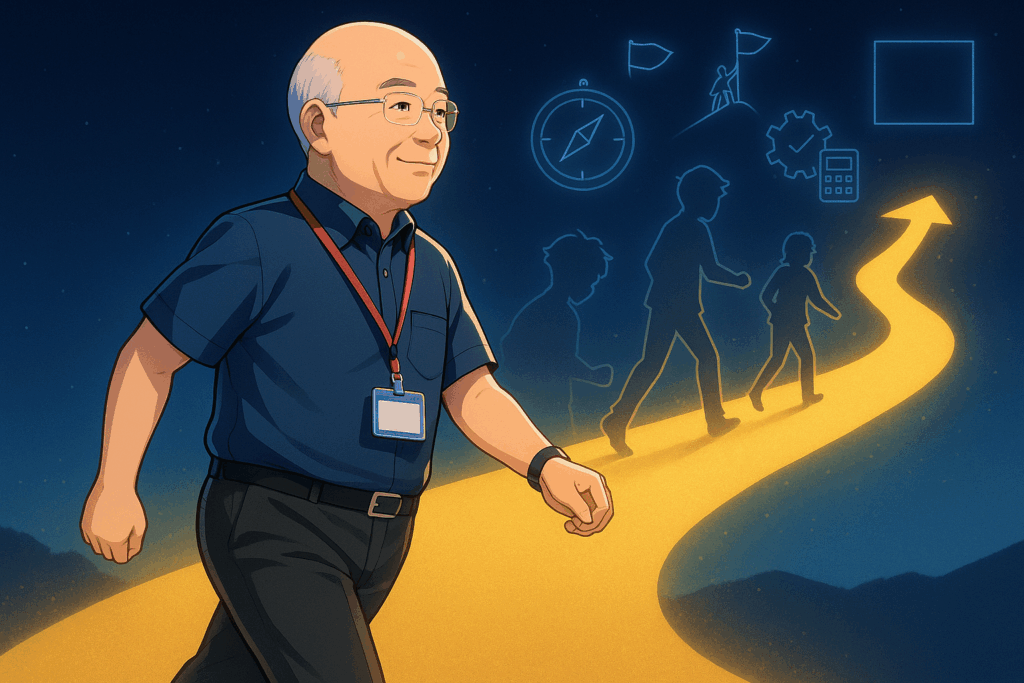
私は、未来を担う学生や若者に向けて、力強いメッセージを送ります。まず、今の若い世代は「打たれ弱い」傾向にあるという認識から、困難に直面しても立ち向かえる**「打たれ強さ」**を身につけることが重要であると強調します。また、指示を待つ「指示待ち」の姿勢では成長が難しいです。学生のうちから生徒会やクラブ活動で積極的に役割を担い、リーダーシップを発揮する経験を積んでほしいと考えています。
失敗を恐れず、むしろ失敗から学ぶことで大きく成長できるという考えに基づき、常に挑戦し続けることが大切です。さらに、社会人として不可欠な「金銭感覚」を学生のうちから養うことの重要性も説きます。特に、将来的に会社の幹部を目指すような人材にとって、健全な金銭感覚は経営の基盤となる要素であると考えています。
そして、若者が持つ最大の「強み」として、私が挙げるのは「何も知らない」こと、すなわち「真っ白な状態」であると考えます。長年事業を続けている企業には、常識が凝り固まり、非常識が常識となっているような状況が往々にしてあります。そのような環境に、先入観なく「何も知らない」若者が入ることで、「これはおかしい」「こうしたらどうか」といった率直な意見や疑問が生まれ、それが会社の変革や新しい発想の源となることがあります。この「何も知らない真っ白な状態」こそが、若者の最も魅力的で貴重な資質であると私は強調します。若いうちは、常識を身につけつつも、それ以外の点では「やりたい放題」で、様々なことに挑戦することが良いとアドバイスします。
取材担当者(高橋)の感想
田坂様からいただいたメッセージは、これからの社会に出ていく私たち学生にとって非常に示唆に富むものでした。「打たれ強さ」や「指示待ちからの脱却」、「リーダーシップ経験」といった具体的な行動指針に加え、「何も知らないことこそが強み」という言葉には、私たちの未熟さに対する肯定的な視点があり、大きな勇気をもらいました。
失敗を恐れずに挑戦し、既存の枠にとらわれず素直な疑問を持つことが、社会を変える原動力となることを学びました。また、金銭感覚の重要性についても、これからの社会人生活で意識すべき点だと改めて感じます。










