株式会社やまひらは、福岡県柳川市を拠点に、水産物の仕入れ・加工・流通から飲食・宿泊事業まで幅広く展開する企業です。創業は明治23年、鮮魚店「平野商店」から始まり、130年以上にわたって有明海とともに歩んできました。現在は、鮮魚・加工品の卸売やOEM商品開発、自社ブランド商品の製造に加え、直営食堂「夜明茶屋」や宿泊施設「夜明の宿」を通じて、海の恵みを幅広い形で提供しています。
「海の環境と向き合い、海の恵みに新たな価値を創造する」を理念に掲げ、地域資源を活かした商品づくりやサービス展開を続けてきました。その原点には、創業者が漁師にお茶を振る舞った“おもてなしの心”があり、以来五代にわたり「喜ばれることに喜びを」実践し続けています。
今回は、長い歴史の中で育まれた「地域とともに生きる精神」を大切にしながら、“食を通じて地方から世界へ発信する”挑戦を続ける株式会社やまひらの姿勢と、これからの展望について、代表取締役社長 金子様にじっくりとお話を伺いました。
<聞き手=石嵜渉(学生団体GOAT編集部)>
【金子様の今までの経緯・背景】
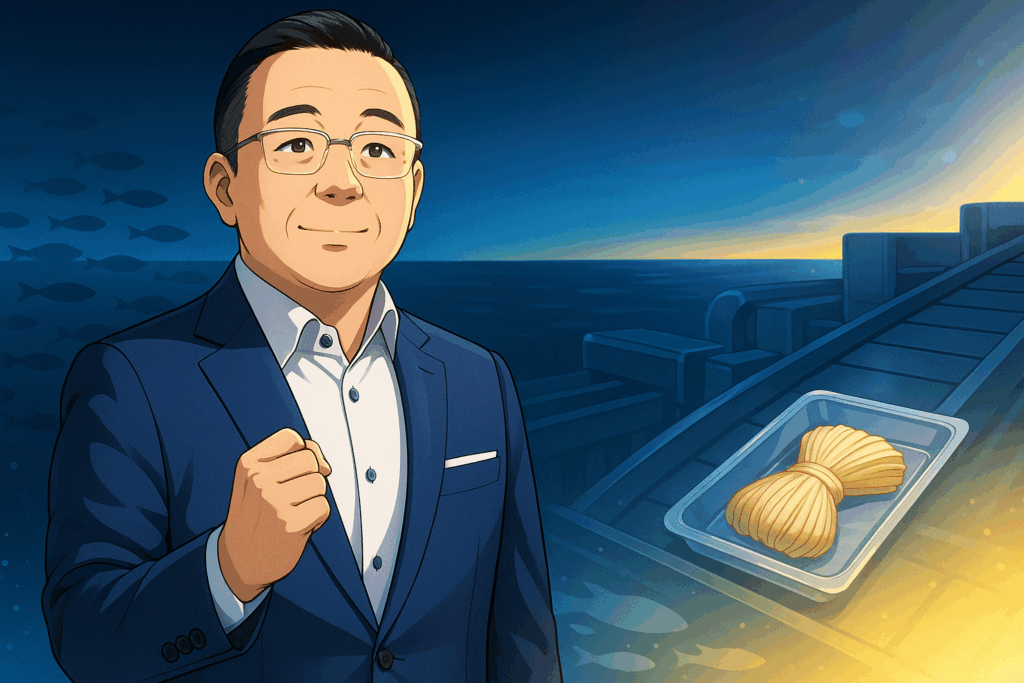
私は、創業から続く家業を4代目として継ぎました。小さい頃から父の働く姿を間近で見ていましたし、お手伝いもしていたため、仕事が常に身近にありました。正直なところ、継がなければいけないだろうなという雰囲気を感じており、辞めたいとは言えない、辞めるわけにはいかないという責任感を抱いていました。
ただ、中学生になる頃から有明海の漁獲量が減ってきていることを肌で感じるようになりました。父が「取れないね」と話すのを聞いたり、金銭的な感覚も遠目から見ていて、水産業は大変だと感じるようになりました。それでも、「やらないといけない」という思いは漠然と抱いていました。
昔ながらの漁師さんからの買付や卸だけでは事業が成り立たなくなり、同業者が次々と倒産・廃業する状況を見てきました。そこで、有明海が昔のように豊かな海に戻ってくれること、そしてそれを次世代に引き継ぐことが私たちの役目だと考え、仕事の延長線上にその目標を見据えて、加工に力を入れ始めました。素材に付加価値をつけること、これがこの30年間私が情熱を注いできたことです。料理屋や宿、ラーメン作りも、全てはこの「付加価値をつける」という原点からきています。
取材担当者(石嵜)の感想
金子社長の事業承継の背景には、幼い頃からの家業への親しみと、地域、そして家業を守るという強い責任感があるのだと感じました。特に、有明海の漁獲量減少という厳しい現実を目の当たりにしながらも、「やらないといけない」という思いを抱き、新たな事業展開に踏み切った行動力に感銘を受けました。付加価値創造への情熱が、現在の多角的な事業の原点となっているというお話は、学生にとっても「なぜその事業をするのか」という問いを考える上で非常に学びがあると感じます。

【株式会社やまひらの事業・業界について】
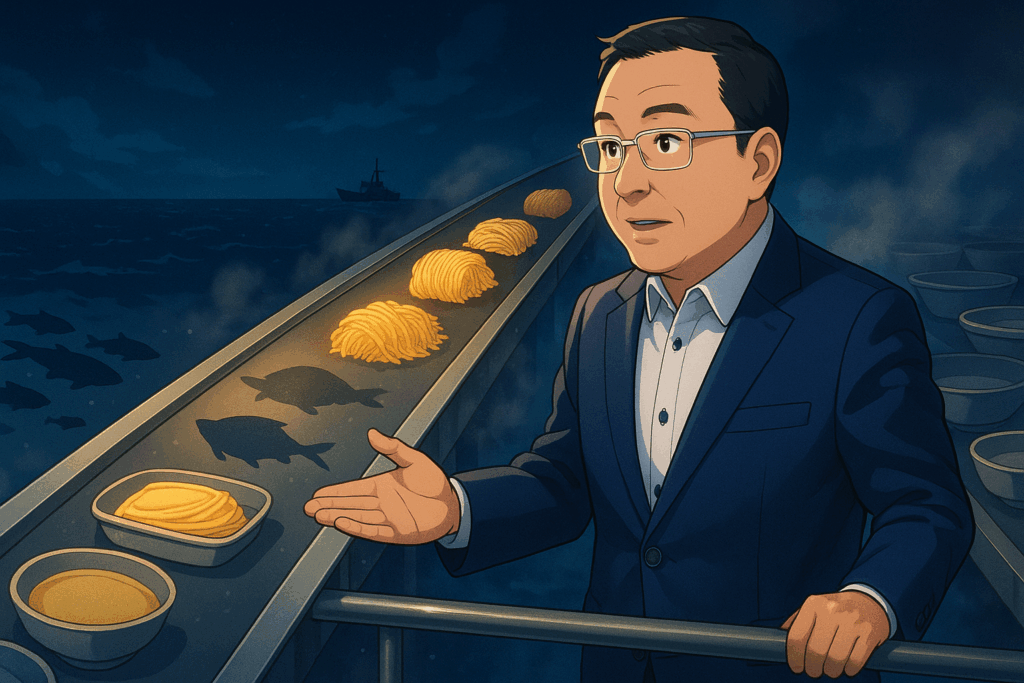
水産業界の最大の課題は、やはり資源量の枯渇だと思います。それに加えて、学校では教えられない「自然に時間を合わせる」「労働力を自然に合わせる」という点が、若い方、特に学歴の高い方には理解されにくいと感じています。漁師の仕事は朝9時から夕方5時までという定時制ではありませんし、大雨や強風が降れば船は出せません。毎日決まった量が獲れるわけでもなく、全く獲れない日もあれば、ものすごく獲れる日もあります。この自然に左右される不規則さが、今の若い世代には理解しにくいのかもしれません。私自身もそうでしたから、デートの約束をしても急な水揚げで無理になることもありました。
この業界で働き続けるには、そうした厳しさを超える情熱や役割意識が必要だと感じています。やりがいはあるものの、手取りや家族を養うという現実的な部分も非常に難しいと感じています。そうした中で私たちは、有明海の水揚げ量が減っても、漁師さんたちを支えるために、加工によって商品の価値を10倍に高めるような取り組みを進めてきました。同業者が次々と倒産・廃業していく中で、新しい分野やチャレンジをしていかないと生き残れないという危機感がありました。
例えば、「ムツゴロウラーメン」の開発がその象徴です。ムツゴロウが絶滅危惧種となり漁獲が一時停止された後、数年で増えましたが、流通が途絶えたことで市場から消えてしまいました。そこで、ラーメンという形でムツゴロウを再び食卓に届けることを発案し、地元柳川の製麺会社と協力して開発しました。これが「日本初の本格ご当地ラーメン」としてテレビや新聞で話題となり、漁師さんたちにも大変喜ばれました。
この成功を受けて「ワラスボ」を使った「エイリアンラーメン」も誕生し、さらには全国各地のご当地ラーメンのOEM製造依頼を受けるようになり、「マイラーメン企画部」を立ち上げるに至りました。これは、地域貢献にもつながる大切な取り組みだと感じています。水産物は足が早いので、常温で販売できる商品にしたいという水産業者共通の願いを叶える手助けもしています。
取材担当者(石嵜)の感想
水産業界が抱える資源枯渇や労働環境の課題は、非常に現実的で厳しいものだと感じました。しかし、金子社長がその困難を「加工」と「付加価値創造」という形で乗り越え、さらには地域活性化に貢献している事業展開は、まさに挑戦の連続だと感じます。特に、ムツゴロウラーメンから始まり、全国のご当地ラーメンのOEMまで手掛ける「マイラーメン企画部」の取り組みは、その発想力と実行力に驚かされました。業界の課題を逆手に取り、新たなビジネスチャンスを生み出す柔軟性は、私たちが社会で働く上で学ぶべき視点だと思います。

【金子様から学生へのメッセージ】
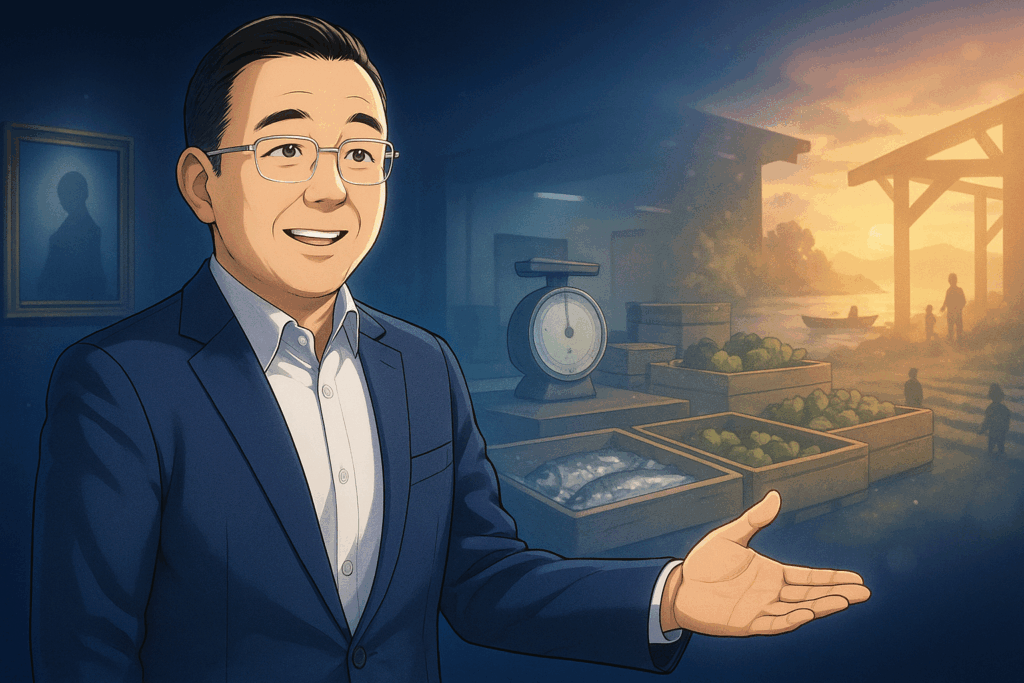
社会に出ていく皆さんには、まずたくさんの経験をしてほしいと思います。旅をすることも一つですし、多くの失敗を経験することも大切です。なぜうまくいかなかったのかを深く掘り下げて考えたり、恥をかくことを恐れずに「若気の至り」の精神で色々なことに挑戦してください。失敗は決して無駄にはならず、むしろ糧になります。
そして、「価値あるもの」や「本物」に触れる機会を多く持ってほしいです。例えば美術館でモナリザの絵を見るだけでも、その絵がなぜ何百億、何千億もの価値を持つのか、その視点で考えてみてください。それは、価値観を持たない人にとってはただの絵かもしれませんが、価値を知る人にとってはお金では買えないものです。なぜそうなのかを自分の目で見て考えることが非常に重要です。仕事をするようになると、そうした時間はなかなか取れなくなります。何が本当に大切なのか、自分の価値観を養うためにも、本物を見る機会を多く持つことが重要だと感じます。
また、SNSやデジタル化によって情報が溢れる時代だからこそ、自分で判断する基準、つまり「自分の価値観」をしっかりと持つ目を養ってほしいと思います。私自身も毎朝市場に行き、昨日100円のものが1万円や2万円になるという、その瞬間の価値が変動する世界を経験しています。農家さんの手伝いをしたり、漁師さんと関わったり、家を建てる経験をしたりすることで、なぜこの値段になるのか、この価値が生まれるのかということを肌で感じられるはずです。学生のうちに、お金を動かすだけでなく、なぜその価値になるのかという基本的な経済を考える時間を経験することが大切だと私は思います。
取材担当者(石嵜)の感想
金子社長のお話は、情報過多の時代を生きる私たち学生にとって、非常に心に響くメッセージでした。特に「本物」に触れ、自分自身の価値観を養うことの重要性や、あらゆる経験を通じて物事の本質を理解しようとすることの大切さを改めて感じました。私自身、社会に出てから後悔しないためにも、学生である今のうちに様々なことに挑戦し、自分の目で見て、肌で感じて、判断する力を身につけることの重要性を強く認識しました。

【株式会社やまひらの今後の展望】
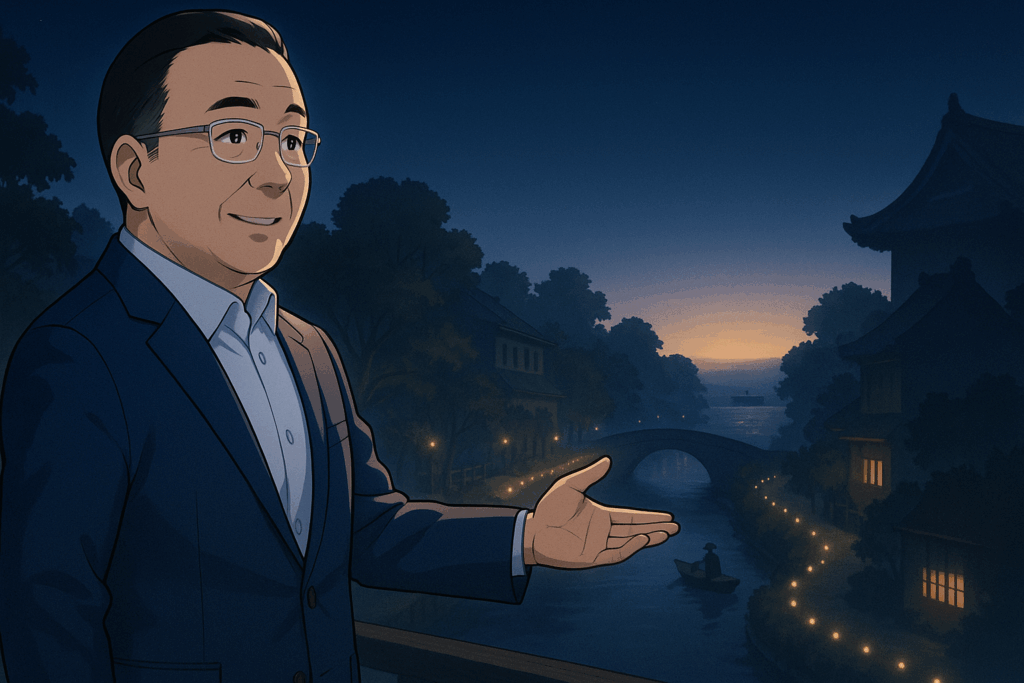
私の夢は、有明海が昔のように豊かな海に戻り、それを次の世代にバトンタッチすることです。そして、私の会社だけでなく、柳川という地域全体が良くなる方法を常に考えています。柳川は観光地でもありますので、今後は街づくりにも会社として積極的に関わっていきたいと思っています。
私はよくスタッフや行政の方々に「柳川ディズニーランド計画をやりたいんだ」と話しています。柳川には、立花のお花御殿のような素晴らしい歴史的建造物や川下り、有明海など、単体でも魅力的なコンテンツがたくさんあります。これらはディズニーランドでいう「シンデレラ城」や「リバーアトラクション」のようなものだと考えています。柳川は歩いて回れるコンパクトな街なので、これら全てを「柳川ディズニーランド」のように捉え、生活自体が豊かになる場所にしていきたいと考えています。毎日ミッキーに会えなくても、タイミングよくムツゴロウに会えたり、今日の川下りの船頭さんはナンバーワンの接客だね、といったような、暮らしの中の発見や出会いが価値となる街を目指しています。
「夜明の宿」も、この計画の一環です。田舎で増えている空き家を有効活用し、有明海の魅力を深く知ってもらうための拠点にしたいのです。朝早く市場に行く必要があるため、宿泊施設があれば柳川の生活をより深く体験してもらえます。今後はこの宿を増やしていき、柳川での暮らしを体験できる場を提供することで、地域貢献にもつなげていきたいです。
東京や大阪のような都会にいると分からないかもしれませんが、田舎では行政の方々とも密接に連携し、この街をどうしたらもっと良くできるか、どうしたら若い人が来てくれるかを話し合えるのは、非常にありがたいことだと感じています。人生一度きりですから、自分だけの欲ではなく、地域全体を豊かにするような事業を展開していきたいと強く思っています。若いスタッフも増え、彼らの柔軟な発想を取り入れながら、共に街づくりを進めています。
取材担当者(石嵜)の感想
「柳川ディズニーランド計画」という壮大なビジョンに、金子社長の地域に対する深い愛情と熱い思いを感じました。空き家活用や「夜明の宿」を通じた地域貢献の具体的な取り組みは、単なるビジネスではなく、地域と一体となった持続可能な未来を築こうとする姿勢が表れていると感じます。










