株式会社共栄食糧は、瀬戸内海に浮かぶ香川県小豆島に拠点を置く食品メーカーです。創業以来、伝統的な手のべそうめんの製造・販売を基盤としつつ、時代のニーズを捉えた多様な麺類や、地域資源を活かしたオリーブ関連の加工食品(食べるオリーブオイル、パスタソース、ドレッシングなど)の開発・製造・販売を手掛けています。安心・安全な商品づくりと、お客様の声に真摯に耳を傾けることを大切に、永続的に愛される企業を目指しています。今回は、小豆島の風土を活かしたものづくりへの想い、そしてこれからの共栄食糧が描く展望について、北原会長にじっくりとお話をお伺いしました。
<聞き手=丸山素輝(学生団体GOAT編集部)>
【北原様の今までの経緯・背景】
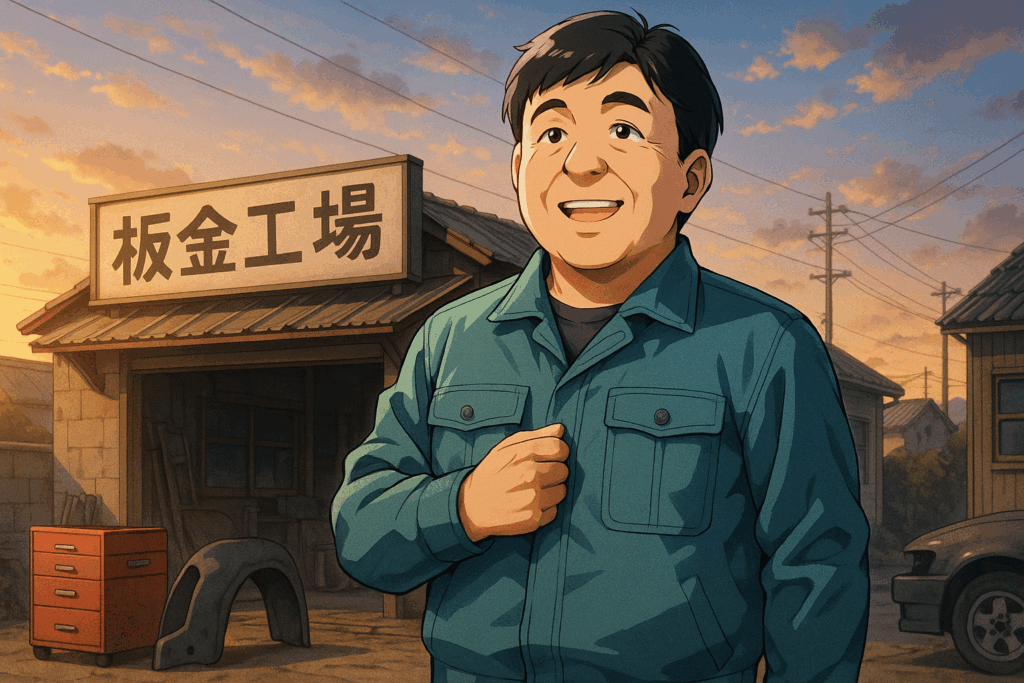
私は24歳で起業し、最初は自動車の板金の会社を経営していました。約4年間板金業を続けましたが、将来的な厳しさを感じていた時期に、小豆島の手のべそうめんが好調だったことから、28歳の時に現在のそうめん製造業に切り替えました。会社自体は倒産させず、事業内容と社名を変更して引き継いでいます。自動車板金工場の借金に加え、新たな借金をしてそうめん事業を始めた形です。
幼い頃から商売をしたいという思いがありました。親戚に商売人が多く、サラリーマン家庭だった自身の生活環境との違いを子供心に感じたことがきっかけです。大学に入学しましたが、このままでは商売ができないと感じ、手に職をつけようと決めました。特に自動車が好きだったわけではありませんが、商売として捉え、叔父が自動車屋を経営していた関係で、19歳から横浜で板金の仕事を見習いとして始めました。横浜で5年間修行を積み、長男だった私に親から帰郷を促された際に、「代わりに商売をさせてくれ」と頼み、父親からの資本援助と借入れで板金の会社を創業したのが最初です。
食品事業に本格的に関心を持ったのは、元々食い道楽で食べるのが好きだったからです。そうめん事業を始めてからも、在庫が長期間眠るような商売ではなく、常に在庫が動く商品を求めました。年間を通して食べられる麺として、うどんとそうめんの中間のような「小豆島長麺」を開発しました。百貨店の物産展に自ら出展し、お客様に直接試食・販売することで生の声を聞き、商品開発に活かしました。そうした中で、小豆島産のオリーブが注目され始め、オリーブラーメンやオリーブパスタを開発しました。
また、お客様から「そうめんを食べられる場所がない」という声を受け、流しそうめんの提供を始めたところ、「手作りのめんつゆを売ってほしい」という要望が多く寄せられ、めんつゆの商品化につながりました。オリーブサラダパスタに使うドレッシングも好評で、ドレッシング単体で販売するようになりました。このように、多くのお客様の声を聞きながら、徐々に商品の幅を広げていったのです。
商品開発においては、お客様からの「防腐剤や増粘剤、化学調味料が入っているのか」という問いかけが、無添加へのこだわりを持つきっかけとなりました。時代のニーズに合致したかは分かりませんが、お客様が気にしている点を重視し、無添加の商品作りに注力しています。物産展での対面販売は、お客様の反応を直接感じられる貴重な場でしたが、コロナ禍で難しくなり、広告宣伝費と考えていた物産展からの撤退を決めました。
その代替として、当社の強みである商品開発力を活かし、他社の商品開発(OEM)を手掛けることで売上確保を目指しています。弱みを改善するよりも、強みを最大限に活かすことが重要だと考えています。
取材担当者(丸山)の感想
24歳で起業され、その後、業種を全く変えるという大胆な決断をされた経緯には、子供の頃からの商売への強い思いがあったことを知り、大変驚きました。
手に職をつけようと大学を中退し、単身横浜へ修行に出られた行動力や、家業を継ぐという親の願いに応える中で、自身の商売の道を見つけられたというお話は、目標に向かって自ら行動を起こすことの重要性を教えてくれるように感じました。

【株式会社 共栄食糧の事業・業界について】
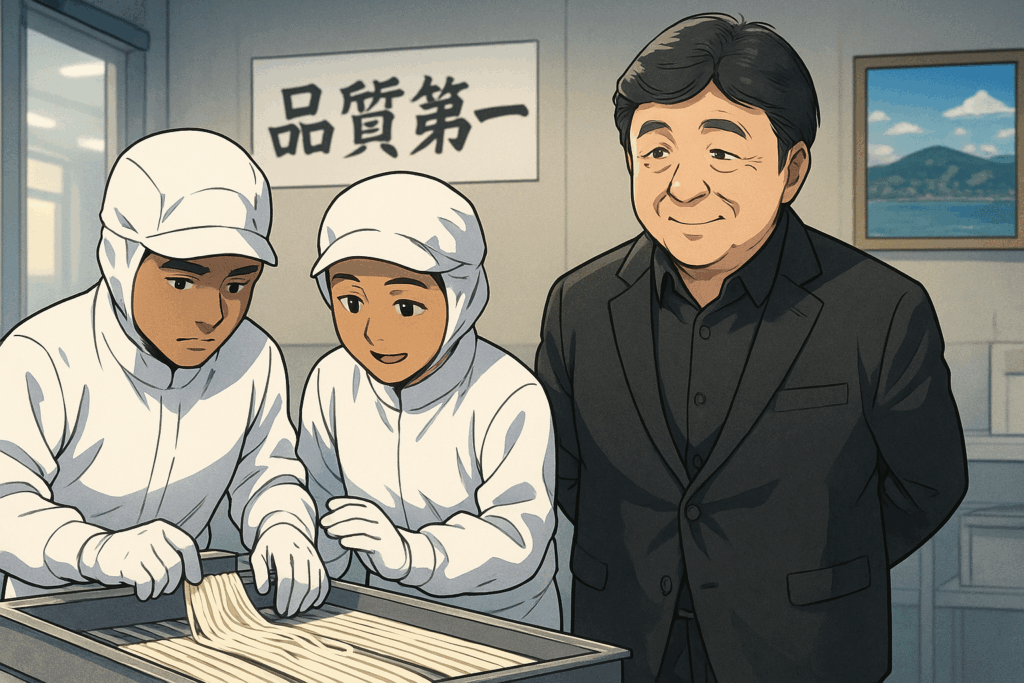
当社の主な事業は、伝統的な手のべ麺の製造・販売に加え、地域資源を活かした加工食品の製造・販売、そして卸売りとOEMです。販売チャネルは、オンラインでの消費者向け販売(BtoC)が中心ですが、小豆島や四国、岡山などの土産物店や、こだわりを持った高級スーパー、百貨店といった業者向け販売(BtoB)も行っています。ターゲット層は以前は高齢者が中心でしたが、オリーブ関連製品の増加に伴い、今は30代から50代のお客様が増えています。
当社の製品は、一般的なスーパーに並ぶ商品と比べて価格設定が高めです。これは、原料や製造工程に徹底的にこだわり、手間暇かけて作っているからです。例えば、めんつゆに使ういりこは、頭と腹を手作業で取り除いてから水出しでだしを取っています。こうしたこだわりがあるからこそ、価格に見合う価値を提供できていると考えています。
お客様の中には、無添加や品質にこだわる方が増えており、そういった層に当社の製品を選んでいただけていると感じます。原材料は、瀬戸内の魚介類や柑橘類なども積極的に取り入れています。ただし、オリーブオイル自体は国内生産だけでは量が足りないため、品質の高いスペイン産などを主に使っています。小豆島産のオリーブは貴重で、その多くは高価な化粧品として流通しています。
食品業界全体としては、人材不足が大きな課題です。特に小豆島のような地域では、若い人材が島外に流出してしまうため、この問題は深刻です。当社では労働力確保のため、10年ほど前から外国人技能実習生を受け入れています。当初はベトナムから、現在はカンボジアからの実習生が働いています。国の研修制度や組合を通じて受け入れており、リモート面接や手作業のテストで採用を決めています。
言葉の壁など課題はありますが、先輩実習生が新人に教えるといった工夫をしながら対応しています。現在、従業員の平均年齢は上がってきていますが、離職率は低く、長く勤めてくれる人が多いのはありがたいことです。しかし、営業力を持った人材が不足しており、今後採用していきたいと考えています。
コロナ禍を経て、物産展に代わる販売戦略や、業務効率化のためのDX推進にも取り組んでいます。例えば、手作業だった在庫管理をタブレットで行うシステム導入を検討しており、これにより年間稼働日数を増やせる見込みです。
常に前向きに、時代のニーズに合わせて変革していく姿勢が不可欠です。また、小豆島という立地を活かし、商品の魅力だけでなく、地域の情報も合わせて発信していくことで、お客様とのつながりを深めたいと考えています。将来的には、お客様が自分で商品の一部を調合してオリジナル製品を作るような体験型イベントなども実現できたら面白いと考えています。
取材担当者(丸山)の感想
素材や製法にこれほど手間暇かけているとは想像以上でした。価格が高い理由が明確で、品質への徹底したこだわりが伝わってきました。人材不足という地域ならではの課題に対し、外国人技能実習生の受け入れを積極的に行っていることや、教育体制の工夫など、具体的な取り組みを知ることができました。
小豆島という恵まれた観光資源を活かした地域連携や体験型イベントの構想は、今後の事業の多様化と顧客体験の向上につながる可能性を感じ、非常にワクワクしました。

【北原様から学生へのメッセージ】
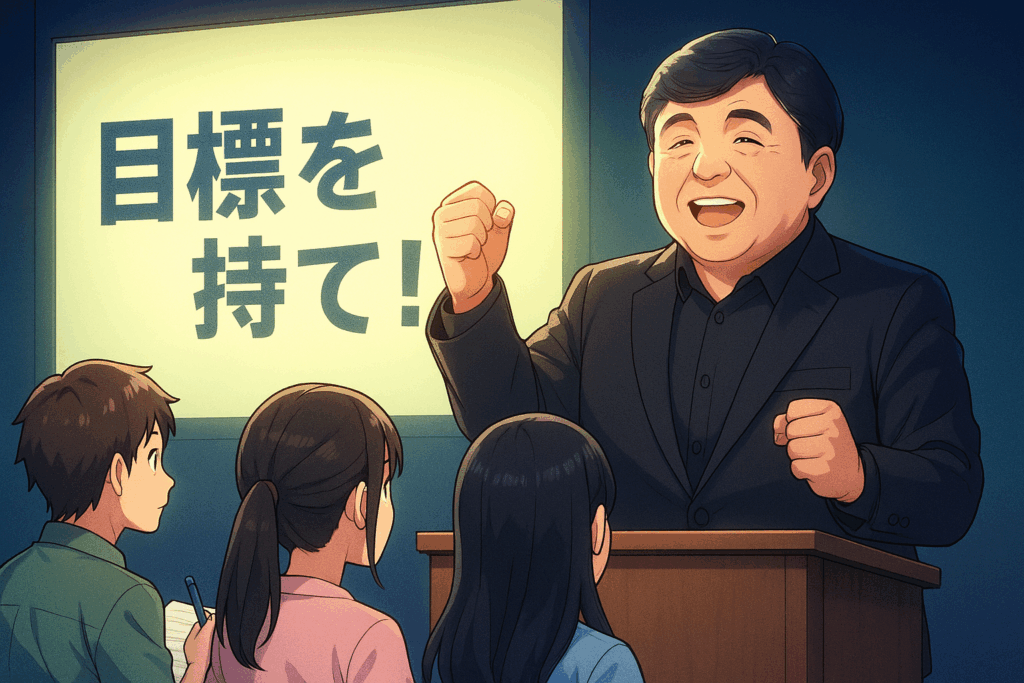
学生の皆さんには、まず自分が何をしたいのか、どうなりたいのかを明確に決めてほしいと思います。目標がはっきりすれば、それに向かってどう動けばいいのかが見えてきます。富士山に登るのとエベレストに登るのでは準備が全く異なるように、大きな目標を設定すれば、それだけ綿密な準備と努力が必要になります。
スポーツ選手が目に見えない努力を積み重ねているように、目標達成のためには地道な準備と継続的な努力が不可欠です。旅行に行くときも資金集めから計画まで準備をするのと同じで、自分で考えて準備をしていくことが大切です。私が商売をしたいという目標を決めて、それに向かって色々なことをしてきたように、目標設定こそがスタートラインなのです。
商売の世界では、時代のニーズは常に変化しています。この変化をうまく捉え、自社の立ち位置をどう変えていくか、自社の強みをどう活かしていくかが重要です。ただ安全な商品であるだけでなく、「こんなの今までなかった」と驚いてもらえるような商品を開発することも大切です。
同じ商品で価格競争をするような商売では、我々のような中小企業は大手には勝てません。他社との違いを明確にし、きちんと利益が得られる商売を追求する必要があります。規模の大小にかかわらず、特定の分野や地域、商品で「1位」を目指すことが、中小企業が生き残る道だと考えています。
経営においては、「情報がグローバルに、行動はローカルに」という言葉を常に意識しています。世界の動向や最新の情報をグローバルな視点で常に把握し、その上で、自社の立ち位置や具体的な行動はローカルな視点で細かく決めていくということです。
情報は時にコストをかけてでも手に入れるべきであり、経営者にとって最も重要な要素の一つです。そして何より、常にお客様の声に耳を傾けることが商売の基本です。お客様の声を聞き、それをどのように商品やサービスに活かしていくか、それが問われているのです。
取材担当者(丸山)の感想
「自分が何をしたいか、どうなりたいか」を明確にすること、そしてそこに向かって地道な準備と努力を積み重ねることの重要性について、具体的な比喩や例えを交えてお話しいただき、非常に分かりやすく心に響きました。
「情報がグローバルに、行動はローカルに」という言葉は初めて聞きましたが、時代の変化に柔軟に対応しつつ、自社の強みを活かす戦略の要諦を突いていると感じました。大手と戦わない、独自のポジションを築くという考え方は、これからのキャリアを考える上で大変参考になりました。

【株式会社 共栄食糧の今後の展望】
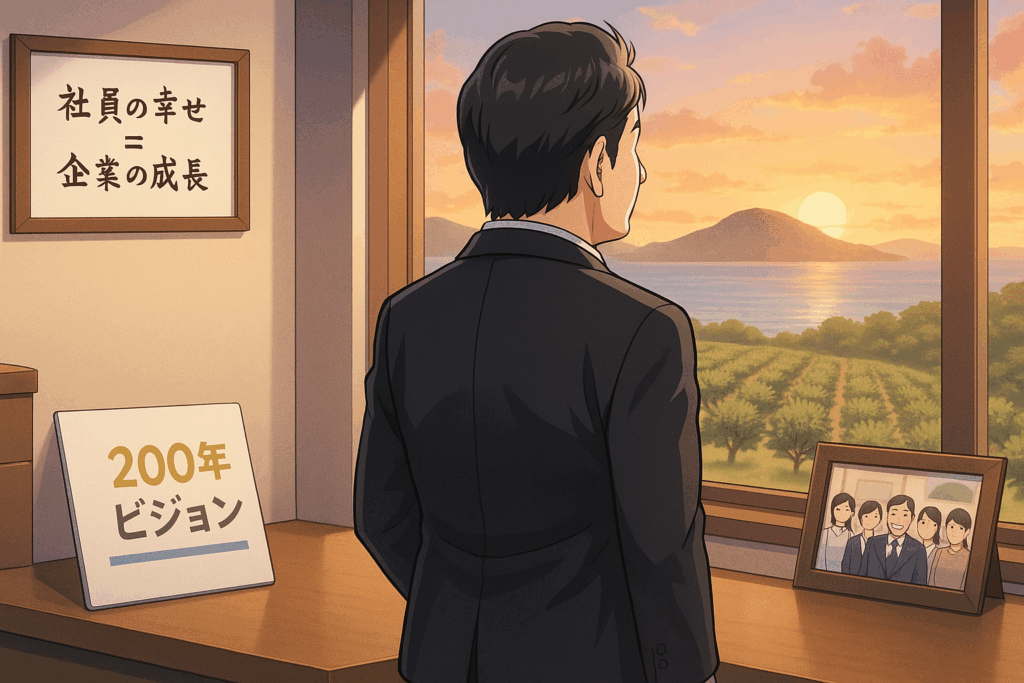
私の最大の目標は、お客様に永続的に愛される会社、そして200年、300年と続く会社にしていくことです。そのためには、常に新しい商品開発を行い、お客様に飽きられないように努力し続けることが不可欠だと考えています。商売は、商品力、販売力、宣伝力など、どれか一つが欠けても成り立ちません。これらのバランスをとりながら事業を進めていく必要があります。
自社の強みである商品開発力を活かし、驚きのある商品や、小豆島や瀬戸内の食材(オリーブ、魚介類、柑橘類など)を活かしたユニークな商品開発を進めていく方針です。単なる製造業にとどまらず、地域情報の発信や、お客様が商品づくりを体験できるようなイベントの開催など、新しい切り口での取り組みもしてきたいと考えています。
そして、最も大切にしている経営理念は、「社員が幸せになる」ということです。社員が幸せでなければ、良い商売はできません。社員の幸せを実現するためには、お客様に喜ばれる、安心・安全な商品を作り続けることが重要です。人財こそが会社の財産であり、人を大切にする会社でありたいと思っています。退職する社員にも「共栄食糧に入社して良かった」と思ってもらえる会社を目指しています。
事業承継についても考えており、私の子供に世襲させるのではなく、社員の中で最も優秀な人間に社長を任せたいと思っています。経営者には、全体を客観的に見て、時代のニーズに対応していける能力が必要です。だからこそ、社員の中から適任者を見つけて育成していくことが重要だと考えています。
200年、300年企業という目標は、決して簡単なことではありません。しかし、小さな目標しか持たなければ、結果も小さく終わってしまいます。だからこそ、大きく、ロングランで目指していきたいと思っています。日本の現状を見ると、中小企業の廃業や倒産が増えており、厳しい時代だと感じています。しかし、そんな時代だからこそ、悔しいですが、何とか生き残ってやろう、日本を支える中小企業の一員として頑張っていこうという思いがあります。
取材担当者(丸山)の感想
200年、300年続く企業を目指すというビジョンには圧倒されました。社員の幸せとお客様の喜びを追求することが、永続的な企業経営につながるという考え方は、非常にシンプルでありながらも深い学びがありました。
事業承継についても、会社と社員の未来を第一に考え、世襲にこだわらないというお考えは、真のリーダーシップを感じさせるものでした。厳しい業界状況の中でも、「生き残ってやろう」という強い意志を感じ、日本の中小企業を応援したいという思いが改めて強くなりました。










