群馬県桐生市に拠点を置く有限会社プライマリーは、介護保険制度が導入されて間もない2002年に設立されました。高齢化率が高い地域で、施設の飽和状態という厳しい環境下においても、安定した施設運営を続けています。プライマリーグループとしては、有限会社プライマリー(サービス付き高齢者住宅、通所介護など)、株式会社プライマリーコンサルティング(介護専門コンサルティング、新規立ち上げ支援、介護職員養成講座)、株式会社ラブアップ(介護スクール運営、事業所運営)、株式会社プライマリーイノベーション(イベント運営、広告企画、飲食店運営)を展開しています。特に人材育成や、安定した稼働率・離職率の低い施設運営の経験に基づいたコンサルティングに力を入れています。また、利用者様やスタッフへのタクティールケア導入など、質の高いケアと働きがいのある環境づくりを目指しています。今回は、地域の高齢化という課題に真正面から向き合いながら、多角的な事業展開と人材育成に取り組む梅澤社長に、プライマリーグループの成長の背景とこれからの展望についてじっくりとお話をお伺いしました。
<聞き手=丸山素輝(学生団体GOAT編集部)>
【今までの経緯・背景】
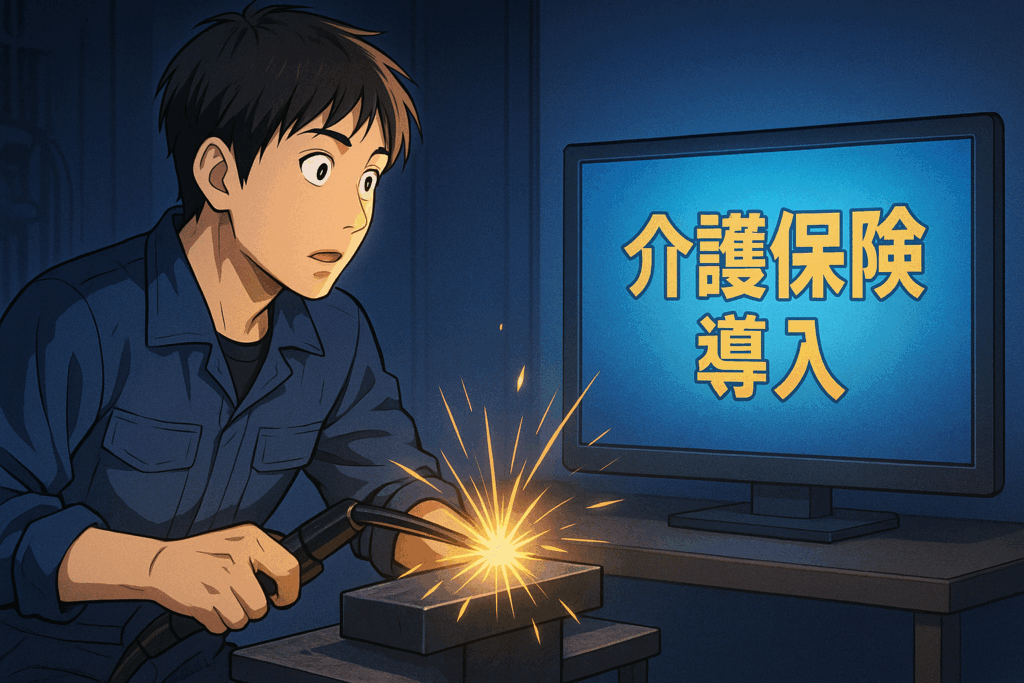
高校を卒業した18歳の当時は、特に夢や希望はありませんでした。高校卒業後、18歳から24歳まで溶接の仕事をしていましたが、これは特に嫌だったわけではなく、ごく普通に働いていました。幼い頃から両親が共働きだったため、祖父母に育てられる環境で育ち、祖父母のことが大好きでした。20歳の時に祖父が癌で亡くなった際、何もしてあげられなかったという後悔がずっと心の中にありました。祖母がそうなった時は面倒を見てあげたい、という思いもありました。
その数年後、テレビで介護保険導入のニュースを見た時、「介護をやってみたい」という気持ちになり、人生で初めて心が躍る経験でした。それまで溶接の仕事をしていましたが、初めて自分で何かをやってみたいと思えた瞬間でした。それで溶接の仕事を辞め、介護の世界に入り、そこからどっぷりはまっていきました。
介護の世界に入った当初は、祖父にしたかったような介護を現場で実現したいと考えていました。しかし、実際に施設で働いてみると、現実は忙しく、自分が思い描いていた「おじいちゃんおばあちゃんと楽しく過ごす」という介護は現場にはありませんでした。それでも利用者様からは頼りにされ、やりがいのある良い仕事だと感じていましたが、自分が本当にやりたい介護はそこにはありませんでした。
介護の世界に入って半年後、このまま自分の気持ちに嘘をついて仕事をするのは嫌だと感じましたが、介護そのものを辞めることは考えませんでした。そこで行き着いた結論が「自分でやろう」ということでした。まだ介護を始めて1年目であり、当時は介護事業は医師や政治家といった「お偉いさん」が中心で、経験者も少なかったのですが、自分で始めることを決意しました。
そして、24歳半ばの頃、28歳の誕生日に会社を作ろうと具体的な目標を設定しました。そこから逆算して3年間で何をすべきかを計画し、資金を貯めたり、介護について学んだりといった準備を進めました。当時、有限会社を設立するには現金で300万円の資本金が必要だったため、3年間あれば300万円を貯められるだろうと考えました。
介護事業は法人格がないと立ち上げられないため、この資金準備は必須でした。根拠はありませんでしたが、「3年」という期限を決めたことで、やると決めたらもうやるしかないという密度で過ごすことができました。10年というスパンにしていたら、途中でだれてしまったかもしれません。そして、28歳に会社を設立し、有言実行を実現しました。
取材担当者(丸山)の感想
高校卒業後すぐにやりたいことを見つけられず溶接の仕事に就かれたり、祖父への後悔から介護への道を志されたりした梅沢社長の経緯は、多くの就活生にとって身近に感じられるお話だと感じました。
特に、ご自身の理想とする介護を実現するために「自分でやろう」と決断し、具体的な目標を設定してそこに向かって走り抜かれた行動力と覚悟は、私自身の目標設定やキャリア形成を考える上で大変勉強になりました。

【事業・業界について】
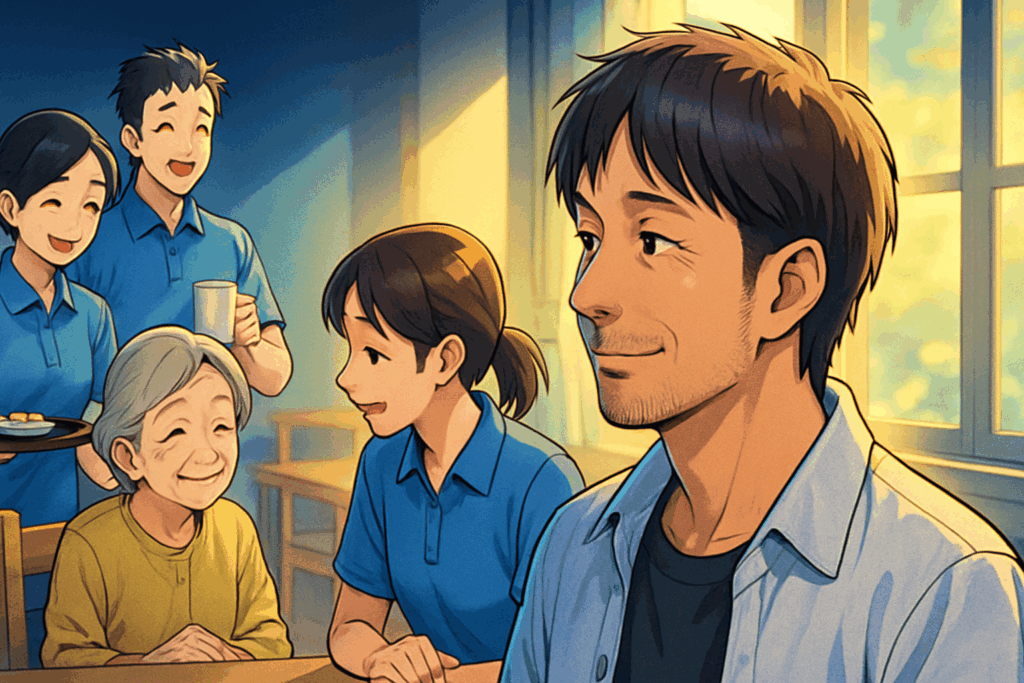
プライマリーグループとしては、介護施設の運営や訪問介護を主軸とし、その他に介護専門のコンサルティング事業、介護スクール運営なども行っています。以前行っていた人材派遣事業は時代の流れに合わせて終了し、飲食店経営は現在オーナーという立場でお店に任せています。
事業において大切にしていることは、社会が不足しているものに価値があるということです。常に「社会が何を求めているのか」を考えるようにしています。いくら良いものを持っていても、社会の流れに沿っていなければ力を発揮できません。
特に介護事業においては人材不足が深刻な課題であり、だからこそスタッフを大切にすることが最も重要だと認識しています。いくら採用にお金をかけても、すぐに辞めてしまっては意味がありません。スタッフを大切にするという企業の「フード」は、他の施設で働いている人たちが求めているものであり、そういった環境には人が集まってくると考えています。
スタッフが仕事を楽しんでいるかどうかは非常に重要です。仕事自体が好きでなくても、職場が楽しければ、きっと仕事に行くのは楽しいはずです。スタッフが楽しいと思えば、利用者様も楽しくなります。スタッフの笑顔と利用者様の笑顔は比例するからです。私自身ができることは、スタッフの満足感を高めていくことです。そうすれば、幸せなスタッフが利用者様に幸せを与えてくれる、この流れしかないと考えています。
介護業界の最大の課題は圧倒的な人材不足です。高齢者が増えるスピードに介護職の増加が追いついていない状況です。また、介護の仕事は「給料が安い」「大変だ」といったネガティブな情報が流れやすいこともあり、人が集まりにくい一因となっています。さらに、離職の理由として最も多いのは、介護の仕事そのものが嫌なのではなく、人間関係の問題です。介護が好きで入ってくる人が多いだけに、人間関係で辞めてしまうのは非常に「もったいない」状況です。このままでは、数年後には人がいないために潰れる会社が出てくるだろうと考えています。介護事業には人員基準があり、それを満たせないと事業継続が難しくなります。
また、介護事業者は「思い」は持っていても、「経営」ができない人も多いと感じています。「利用者様のため」という思いはあるものの、お金の管理や分配がうまくいかず、評判は良くても経営的には厳しい状況にある事業所も出てきています。法人として事業を運営している以上、しっかりとビジネスとして利益を追求する必要があります。しかし、介護業界には「福祉はお金儲けを目的とすべきではない」というような、そうした意識を持つこと自体をためらう風潮があると感じています。良いサービスを提供しているにも関わらず、お金を全く見ておらず、急に資金繰りに困窮するといった経営者も少なくありません。
こうした状況に対し、私たちは管理者会議などで売上や数字について率直に話し合っています。稼働率が低ければ上げていこう、スタッフに給料を多く払えるようにしよう、といった意識改革を行っています。毎年昇給を実現することで、働きやすい職場だけでなく、収入もしっかり得られる環境を作りたいと考えています。そのためにスタッフにも営業意識や数字の意識を持つことの重要性を伝えています。これは決して悪いことではなく、良いサービスを提供してお客さんを獲得する、当たり前のビジネス活動だと考えています。その結果、私たちのスタッフは非常に営業意識が高いです。
そして、起業から20年が経ち、「原点」に戻りたいという思いから、去年ケアマネジャーの資格を取得し、現場に戻りました。経営者でありながら現場で働くことは、経営的には必要ないですし、パソコン作業なども増えて大変なこともありますが、スタッフや利用者様と直接関わる現場はとても楽しいです。自分が現場で売上を作ることで、それをスタッフに還元できるというモチベーションがあります。スタッフが頑張ってくれているからこそ、自分も頑張れると感じています。
取材担当(丸山)の感想
介護業界が抱える人材不足や経営課題といったリアルなお話を伺い、課題の根深さを感じました。特に、人間関係が離職の主な理由であるという点は意外でしたが、人が中心となるサービスだからこそ、そこが重要になるのだと納得しました。
また、「福祉はお金儲けをすべきではない」という風潮の中で、経営者として利益を追求し、それをスタッフに還元していくという梅沢社長のお考えは、経営を学ぶ私にとって大変勉強になりました。経営者でありながら現場に戻られた行動は、まさにスタッフや利用者様への思いの表れだと感じ、素晴らしいと感じました。

【学生へのメッセージ】
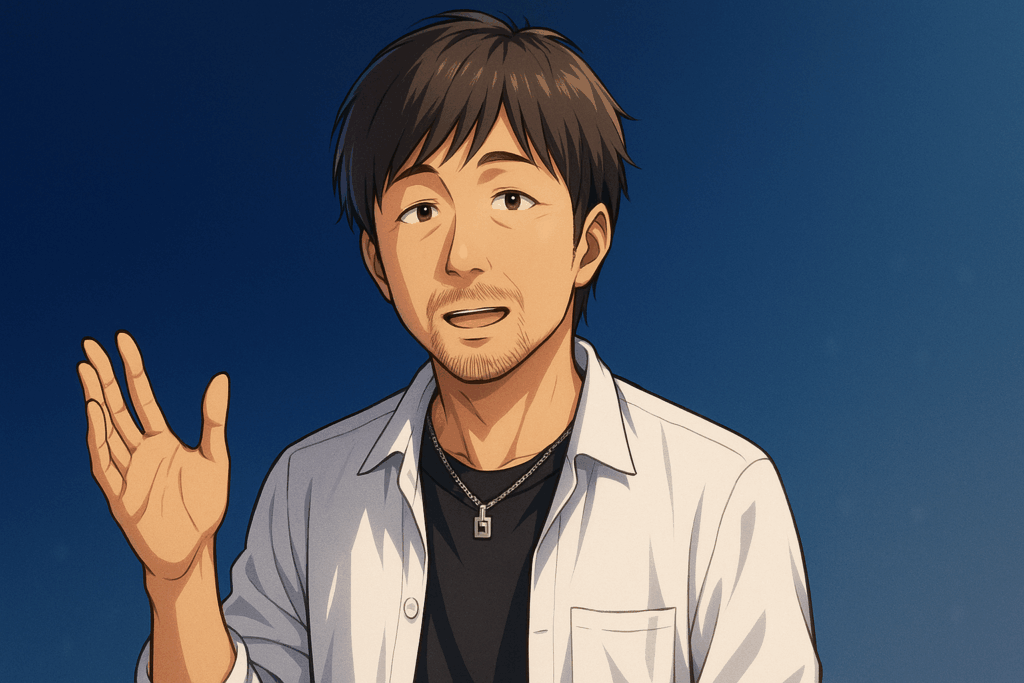
学生の皆さんには、まず自分が何をしたいのか、どうなりたいのかを明確に決めてほしいと思います。目標がはっきりすれば、それに向かってどう動けばいいのかが見えてきます。富士山に登るのとエベレストに登るのでは準備が全く異なるように、大きな目標を設定すれば、それだけ綿密な準備と努力が必要になります。
スポーツ選手が目に見えない努力を積み重ねているように、目標達成のためには地道な準備と継続的な努力が不可欠です。旅行に行くときも資金集めから計画まで準備をするのと同じで、自分で考えて準備をしていくことが大切です。私が商売をしたいという目標を決めて、それに向かって色々なことをしてきたように、目標設定こそがスタートラインなのです。
商売の世界では、時代のニーズは常に変化しています。この変化をうまく捉え、自社の立ち位置をどう変えていくか、自社の強みをどう活かしていくかが重要です。ただ安全な商品であるだけでなく、「こんなの今までなかった」と驚いてもらえるような商品を開発することも大切です。
同じ商品で価格競争をするような商売では、我々のような中小企業は大手には勝てません。他社との違いを明確にし、きちんと利益が得られる商売を追求する必要があります。規模の大小にかかわらず、特定の分野や地域、商品で「1位」を目指すことが、中小企業が生き残る道だと考えています。
経営においては、「情報がグローバルに、行動はローカルに」という言葉を常に意識しています。世界の動向や最新の情報をグローバルな視点で常に把握し、その上で、自社の立ち位置や具体的な行動はローカルな視点で細かく決めていくということです。
情報は時にコストをかけてでも手に入れるべきであり、経営者にとって最も重要な要素の一つです。そして何より、常にお客様の声に耳を傾けることが商売の基本です。お客様の声を聞き、それをどのように商品やサービスに活かしていくか、それが問われているのです。
取材担当者(丸山)の感想
「自分が何をしたいか、どうなりたいか」を明確にすること、そしてそこに向かって地道な準備と努力を積み重ねることの重要性について、具体的な比喩や例えを交えてお話しいただき、非常に分かりやすく心に響きました。
「情報がグローバルに、行動はローカルに」という言葉は初めて聞きましたが、時代の変化に柔軟に対応しつつ、自社の強みを活かす戦略の要諦を突いていると感じました。大手と戦わない、独自のポジションを築くという考え方は、これからのキャリアを考える上で大変参考になりました。

【今後の展望】
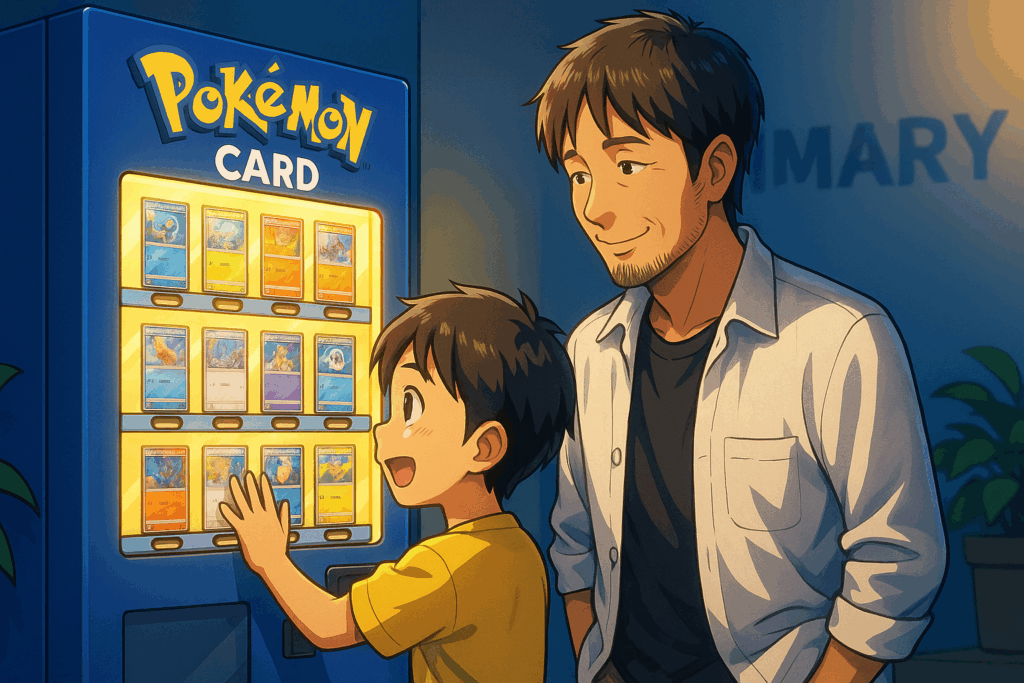
起業して21年目を迎え、改めて大切なものを大切にしたいと考えています。新たに大きな事業を始めることよりも、今いる利用者様やスタッフといった大切な人たちを幸せにすること、今ある事業をしっかりと運営していくことに注力していきたいです。それが結果的に収入アップにも繋がると考えています。大切な人たちと、大切な時間を共に歩んでいきたいです。
これまでの「夢を追いかける」というフェーズから変わり、今は好きなことをやっていきたいと考えています。例えば、最近息子が好きな影響で自分も好きになったポケモンカードの自動販売機を会社でやってみようかな、などと考えています。好きなことに関わっている時間が楽しいので、そういうことも取り入れていきたいです。
また、どっかで何かに出会って、再び事業を大きく展開することに目覚めるかもしれません。それはそれで楽しみです。若い方々には、私のように早めに起業した人間もいますが、色々なことにどんどんチャレンジしてほしいと思っています。
取材担当者(丸山)の感想
創業から20年以上を経て、新たな大きな夢を追うよりも、今ある事業とそこで働く人、利用する人を大切にすることに重点を置かれているというお話は、地に足のついた経営者の姿勢だと感じました。
その一方で、好きなことには積極的に挑戦していきたいという一面も持ち合わせており、ビジネスを楽しむ姿勢が伝わってきました。梅沢社長のこれまでの経験と、これから大切にされることに焦点を当てた展望は、働くことの価値観を考える上で大変勉強になりました。










