三和食品株式会社は、富山県南砺市に拠点を置く食品製造会社です。特に、石川県や富山県の一部に根付く発酵食品であるかぶら寿しや大根寿し、そしてこぶ巻といった商品を製造しています。これらの商品は、地元のスーパーマーケットを中心に販売されるほか、オンラインショップや直売所、業務用(飲食店)でも取り扱われています。親会社であるカナカン株式会社は酒類・食料品の卸売り会社であり、三和食品の商品は以前からカナカン株式会社を通じて多くの小売店に届けられています。今回は、地域の食文化を支え続ける発酵食品づくりへの想いと、今後の展望について、三和食品株式会社 市村社長にじっくりとお話を伺いました。
<聞き手=石嵜渉(学生団体GOAT編集部)>
【市村様の今までの経緯・背景】
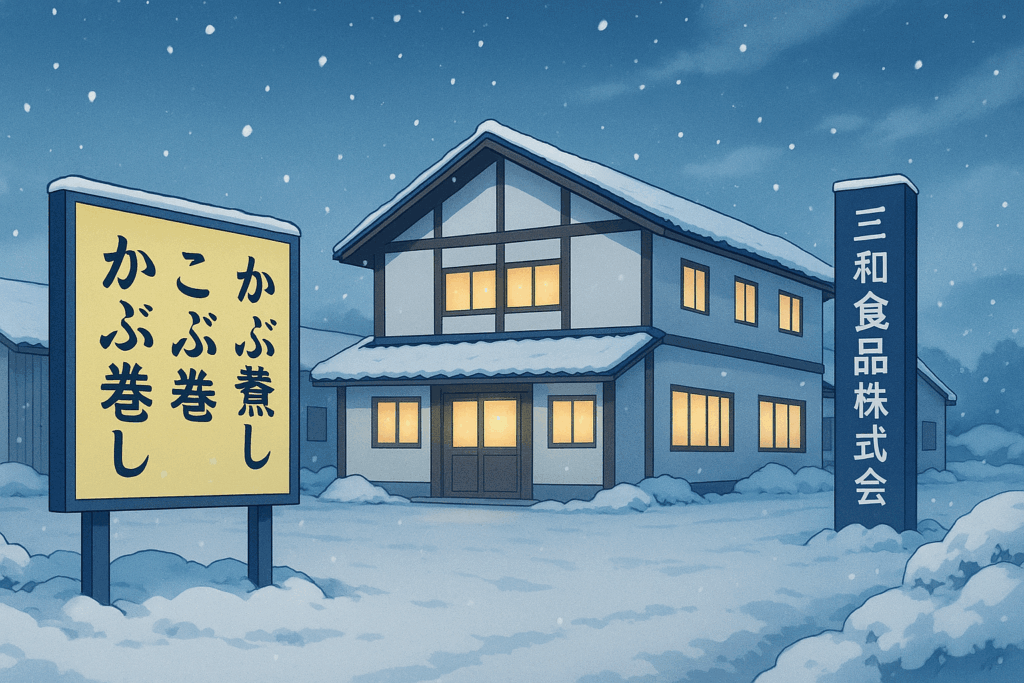
カナカン株式会社で私は長く外食部長として業務用部門の責任者を務めていました。その後、石川県の能登エリアで小売部門の支店長を4年間経験し、ある程度経営にも携わってきました。ただし、これまではメーカーが製造した商品を物流に乗せてお客様に販売するという流通業のビジネスしか経験がありませんでした。
カナカン株式会社が三和食品株式会社を100%株式取得し、グループ化したのは去年のことです。元々、三和食品が製造した商品をカナカンが仕入れて小売店に販売しており、三和食品にとってカナカンは最大の販売先でした。三和食品の先代オーナーが後継者について考える中で、カナカンの社長との話が進み、商品の持つ素晴らしい価値と、互いが納得する評価のもとでグループ化が実現しました。
私は、昨年10月から三和食品に出向し、社長に就任しました。初めての製造業の経営ということで、当初は不安もありました。しかし、事前に主力商品を購入して自宅で食べてみた時に、その美味しさに感動し、「これはやってみたい」という気持ちに変わりました。手前味噌ですが、本当に美味しい商品であり、これなら自信を持ってお客様にお届けできると感じました。
また、地元の高齢のスタッフが多い中で、彼らにもっと還元したい、そして若い人にも入ってきてもらい、会社を永続させていきたいという強い思いが湧きました。不安よりも、「絶対やりたい」という気持ちが勝りました。
取材担当者(石嵜)の感想
市村社長は、これまでのキャリアとは全く異なる製造業の世界に飛び込まれたとのこと。その決断の背景に、商品の美味しさへの確信と、共に働く人々、そして会社の未来への強い責任感があったことに感銘を受けました。
新しい環境での挑戦に対する不安を乗り越える社長の覚悟や、美味しさへの絶対的な自信が伝わってきて、私もぜひ商品を味わってみたいと強く感じました。

【三和食品株式会社の事業・業界について】
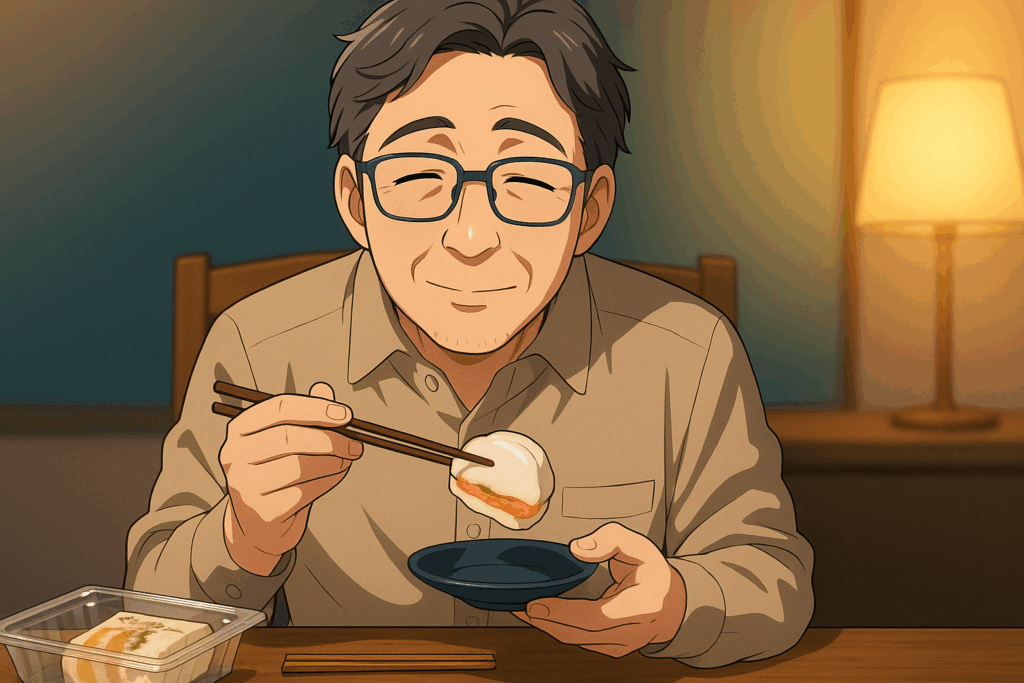
当社の主力商品は、かぶら寿し、大根寿し、そしてこぶ巻です。中でもかぶら寿しと大根寿しは、石川県と富山県南砺市という隣接したエリアに根付く地域独特の発酵食品です。この地域は元々、カブの生産地でもあったことから、お正月にカブの間にブリやサバを挟み、麹で発酵させたものを食べる風習が根付いています。
当社の商品の特徴は、カブの独特な甘みと発酵による旨味の調和にあります。特に西日本出身の方にとっては、見た目が珍しく、画像を見て驚かれる方もいらっしゃるかもしれません。中には、麹をまぶしたかぶら寿しを見て最初は戸惑われる方もいますが、一度食べていただければ「これ美味しい」と評価をいただけます。過去には関西の百貨店での試食販売で好評をいただいたり、金沢の近江町市場で行った試食販売では、フランスの食に関わる方々がその美味しさに驚き、白ワインに合うと絶賛し、フランスに持ち帰りたいとまでおっしゃられたほどです。
販売チャネルは、地元のスーパーマーケットを中心とした小売店、外食産業、オンラインショップ、そして直売所等が軸となっています。売上ボリュームとしては、やはり小売店での販売がメインです。ただし、かぶら寿しはカブの生産時期の関係で、主に11月から2月頃までの季節限定商品となります。特に12月は、お歳暮需要もあり、個人のお客様への配送が増えるため、売上が圧倒的に集中します。大根寿しとこぶ巻は年中製造販売しています。
製造業としては、良い商品を作るという点では強みがありますが、営業力には課題を感じています。私が社長に就任した際、営業と呼べるスタッフは2名でしたが、実質的な営業活動は限られていました。今後は、親会社であるカナカンの営業部門とも連携を強化し、販売体制を強化していく方針です。
かぶら寿しや大根寿しは、生のカブや大根を使用するため、冷凍保存が非常に難しいという課題があります。冷凍すると解凍時に細胞が壊れ、食感や白色感が損なわれてしまうのです。年間を通して安定供給するためには、この保存技術の向上が求められますが、現状ではまだ解決策は見つかっていません。
取材担当(石嵜)の感想
かぶら寿しや大根寿しの独特な見た目から受ける印象と、実際に食べた時の美味しさのギャップが、まさにこの商品の魅力なのだと感じました。
地域に根ざした伝統的な食品が、試食を通じて多くの人々に受け入れられ、海外の方からも高い評価を得ているというエピソードは、商品の持つポテンシャルを強く感じさせます。製造面でのこだわりや課題、そして親会社との連携による販売戦略など、事業の多角的な側面を知ることができ、大変勉強になりました。

【市村様から学生へのメッセージ】
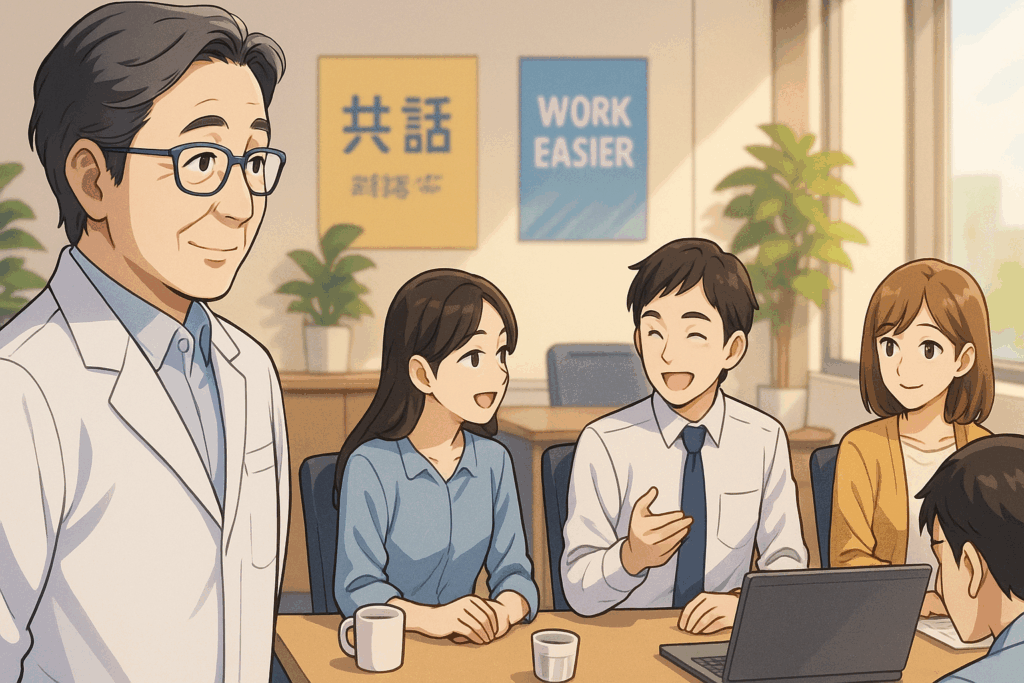
私が以前勤務していたカナカン株式会社では、新入社員研修に参加した経験があります。私が部長になった2014年頃は、新入社員は男性が中心でしたが、徐々に女性社員の比率が増加してきました。これは、流通業界という特性から、以前は働き方などで敬遠される面もあったのかもしれませんが、現在のカナカンでは社長の方針で休日を増やしたり、働き方改革が進められており、働きやすさが劇的に向上したことが影響していると感じています。その結果、女性でも活躍できる仕組みが整ってきています。
一方で、入社後のギャップから早期に退職してしまう方もゼロではありません。特に、ある程度仕事に慣れて楽しさが見えてきた頃、大体30歳前後で、自身の仕事量と所得との間にギャップを感じてしまうことがあります。私の経験上、きちんとした仕事をしていて野心のある社員ほど、この時期に退職を選ぶ傾向が多少なりとも見られました。
このような状況を防ぐために重要だと感じているのは、上司とのコミュニケーションです。営業所の所長が、部下としっかり対話し、彼らの得意なことや目指したい方向を共に考え、育成していくことができれば、離職は少なくなります。私も、若手社員とは極力機会を見つけて話をするように心がけていました。
現代の若者は、会社のためだけでなく、家族や自分のために働くという価値観を強く持っています。また、勤務地についても、転勤を避けたいと考える方が増えています。プライベートを尊重しつつ、どのように従業員と向き合い、会社の課題や目指す方向性を共有していくのかは、常に考えていかなければならない難しいテーマだと感じています。
取材担当(石嵜)の感想
市村社長のお話から、現代の若者の価値観の変化や、企業が直面している採用や人材育成のリアルな課題を学ぶことができました。特に、早期離職の原因として所得とのギャップや上司とのコミュニケーション不足を挙げられていた点は、私自身も就職活動をする上で非常に参考になる視点でした。
「会社のため」だけでなく「個人のため」に働く意識が強くなっていることや、転勤への抵抗感など、Z世代である私たちの感覚を理解しようとされている姿勢に、共感を覚えました。

【三和食品株式会社の今後の展望】
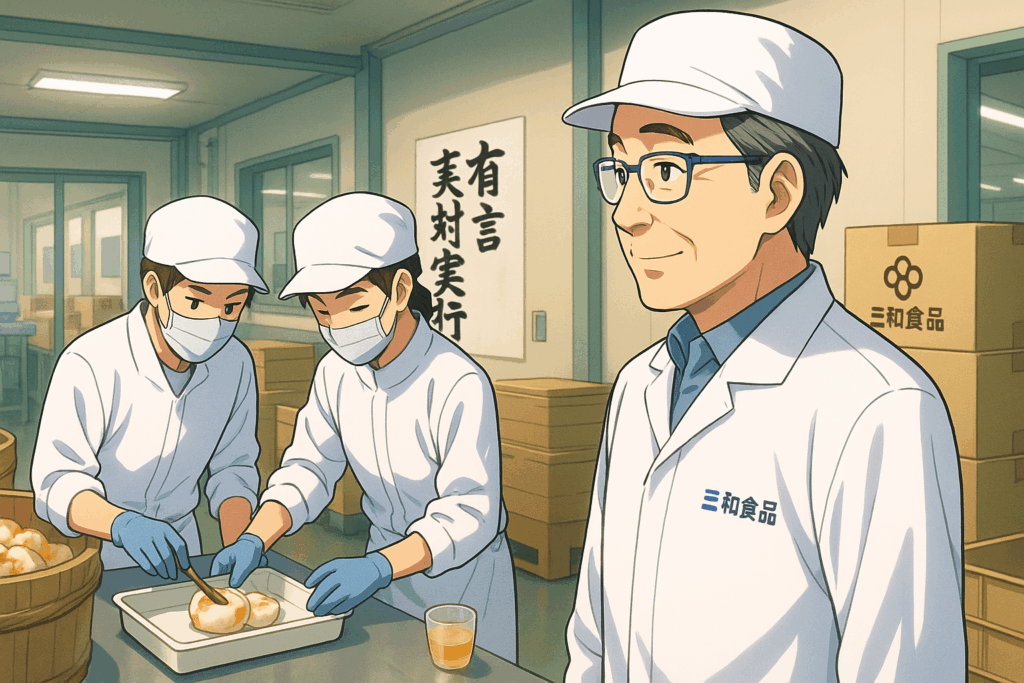
三和食品として、今後も変わらず守り続けていきたいのは、商品の品質です。コスト改善のために原料を安価なものに変えるなど、商品の根幹に関わることは絶対に行いません。一方で、変えていくべきは、働き方や生産性といった目に見えない部分です。従業員一人ひとりが会社を「自分ごと」として捉え、改善活動に積極的に関わってもらうために、各部門のスタッフと分科会を設け、「有言絶対実行」を合い言葉に、皆で目標を設定し、その進捗を話し合う取り組みを進めています。
素晴らしい伝統の商品はこれまで通り販売を続けていきますが、これに加えて、新しい商品開発にも積極的に取り組んでいきます。現在、いくつか新しい柱となるような商品開発が進められており、私が三和食品に出向している間に、新たな商品を軌道に乗せたいと考えています。
また、今後の重要なテーマの一つは、若い世代に当社の商品のファンになってもらうことです。現状、かぶら寿しやこぶ巻の需要を支えているのは50代以上の方が中心ですが、今後は20代、30代といった若い年齢層の方にも、当社の特色ある商品を手に取ってもらい、ファンを増やしていく必要があります。
そして、会社を永続させていくためには、若い人材の採用が不可欠です。三和食品はこれまで毎年定期的に新卒採用を行ってきた会社ではありませんでしたが、今後は親会社であるカナカ株式会社の人事スタッフとも連携し、採用活動を進めていきたいと考えています。
特に、当社のシェアが低い新潟や長野といったエリアでも、会社を理解してもらい、現地で働きたいと思う方をどう確保していくかが課題です。伝統を守りながらも、新しいことにも挑戦し、若い力も取り入れながら、会社を次の世代に繋いでいきたいと考えています。
取材担当(石嵜)の感想
商品の品質を第一に考え、伝統を守り続けるという強い意志に感銘を受けました。同時に、働き方や組織の改善、新しい商品開発、そして若手ファンや人材の獲得といった未来への挑戦も積極的に行われていることが分かりました。
親会社との連携を通じて、それぞれの強みを活かしながら成長を目指す戦略も非常に合理的だと感じます。変化を恐れず、常に前を向いて課題解決に取り組む市村社長のビジョンは、将来社会に出る私たちにとって、大いに刺激となり、学びとなりました。










