クオリム株式会社は、「人生と情報の質」を意味する「Quality of Life and Information」に由来する社名を冠し、五感で受け取る質の高い情報が人生を豊かにすると考えています。長崎県佐世保市を拠点に、情報技術・デザインを活かした「ものづくり・情報関連事業」、長崎県佐世保市と広島県広島市で学習塾やロボット・プログラミング教室を運営する「教育関連事業」、そして佐世保市で飲食店を運営・コンサルティングする「食品関連事業」を展開しています。歴史ある企業でありながら、常に時代のニーズに応え、地域社会への貢献を重視しています。今回は、IT・教育・食の三位一体で地域課題に挑む歩みと、長崎から「日本のシリコンバレー」を目指す次の一手について、代表取締役社長の酒見様にじっくりとお話を伺いました。
<聞き手=石嵜渉(学生団体GOAT編集部)>
【酒見様今までの経緯・背景】
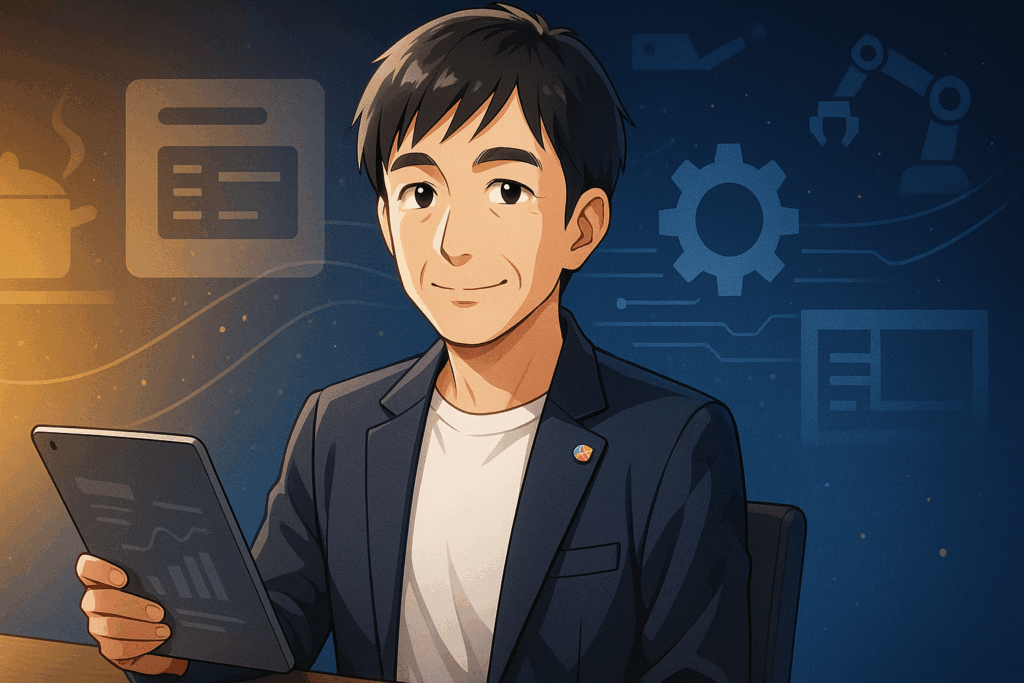
私が元々志向したのは、地方創生を目的としたIT企業でした。特に地方の中小企業が抱える紙文化や人手不足の課題をITで解決し、飲食店などを活性化させたいと考えていました。私は大阪のメーカーで研究開発に携わっていましたが、母の病を機に家業の飲食店を継ぐことになり、当初のIT事業構想を家業に統合することを決意しました。
まず飲食店の業務ツールを開発し、妻がデザイン事業を立ち上げました。勤怠や経理などの基幹システムも自社開発し、高齢社員や外国人留学生のフィードバックを基に、使いやすさを追求してシステムを磨き上げました。この過程でシステム事業部が誕生しました。
さらに、不登校や発達障害を持つ子どもたちがプログラミングで才能を発揮することに気づき、彼らを育成するSTEM教育事業(ロボット、プログラミング、3Dアート)を佐世保と広島で展開しています。これは、親が子どもを地元で活躍させたいという願いに応えるものです。システム開発者には、柔軟な働き方を尊重し、自営業から始める選択肢も提供し、社員の多様なキャリアパスを支援しています。創業約20年、私が社長になって約16年、会社組織としての信用が事業展開において重要だと感じています。
取材担当者(石嵜)の感想
家業の継承を機に、元々のITへの情熱と地域課題解決への思いが融合し、多角的な事業展開へと繋がった経緯に感銘を受けました。特に、従来の企業では見過ごされがちな不登校や発達障害を持つ若者の能力に光を当て、彼らが地元で活躍できる場を創造している点が、非常に社会貢献的だと感じました。

【クオリム株式会社の事業・業界について】
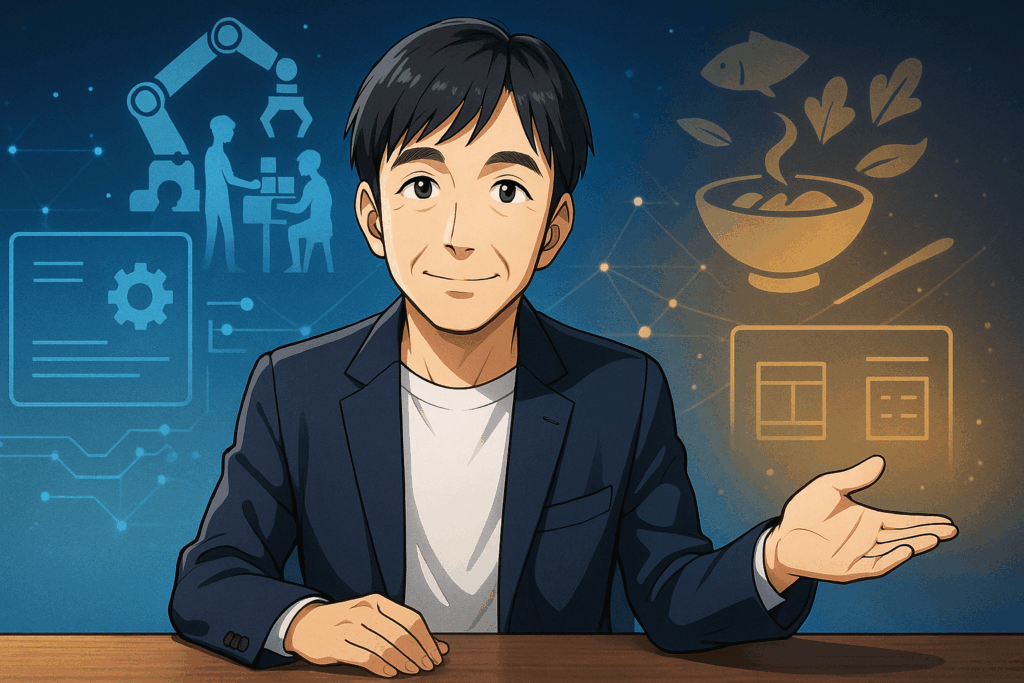
弊社は長崎県佐世保市を拠点に、まず地域で必要とされる企業になることを重視し、その上で県外への事業展開を通じて「外貨」を稼ぎ、地域に貢献することを目指しています。経営において最も大切にしているのは、右脳と左脳、アナログとデジタルのバランスです。特に地方の高齢化社会では、アナログの良さも残しつつ、何でもデジタルに偏らない「中庸」のバランス感覚が不可欠だと考えています。また、組織には直感派も理論派も、多様な人材が不可欠です。
弊社の事業は、情報技術・デザイン、教育、食品の三本柱です。情報技術では、独自の勤怠管理システムなどを開発し、高齢者でも使いやすいシステム作りを追求しています。デザイン事業では、中小企業のホームページ制作や採用広告を手掛け、人手不足の課題解決を支援しています。教育事業では、不登校や発達障害の子どもたちを対象に、STEM教育を通じて彼らの才能を伸ばしています。
食品事業では、佐世保市で飲食店を運営しながら、「フードテック」企業として食の品質と持続可能性を追求しています。長崎県産の食材を使った加工食品の開発や、漁港から直結の「活き造り」提供など、独自の高付加価値化を図っています。私たちは、長崎県のSDGs推進企業としてDX推進、地域産品開発、インターンシップ実施など多角的に地域貢献に努め、健康経営推進企業やネクストリーディング企業としても認定されています。
取材担当(石嵜)の感想
地方に根ざしながらも、IT、教育、食という多岐にわたる事業を展開し、それらがすべて地域貢献に繋がっている点に感銘を受けました。特にアナログとデジタルの「中庸」という考え方や、多様な人材を重視する組織哲学は、これからの社会で企業が持続的に成長するための鍵だと感じました。フードテックを通じた地域産品の高付加価値化やSDGsへの積極的な取り組みも、企業としての社会貢献意識の高さを示していると思います。

【酒見様から学生へのメッセージ】
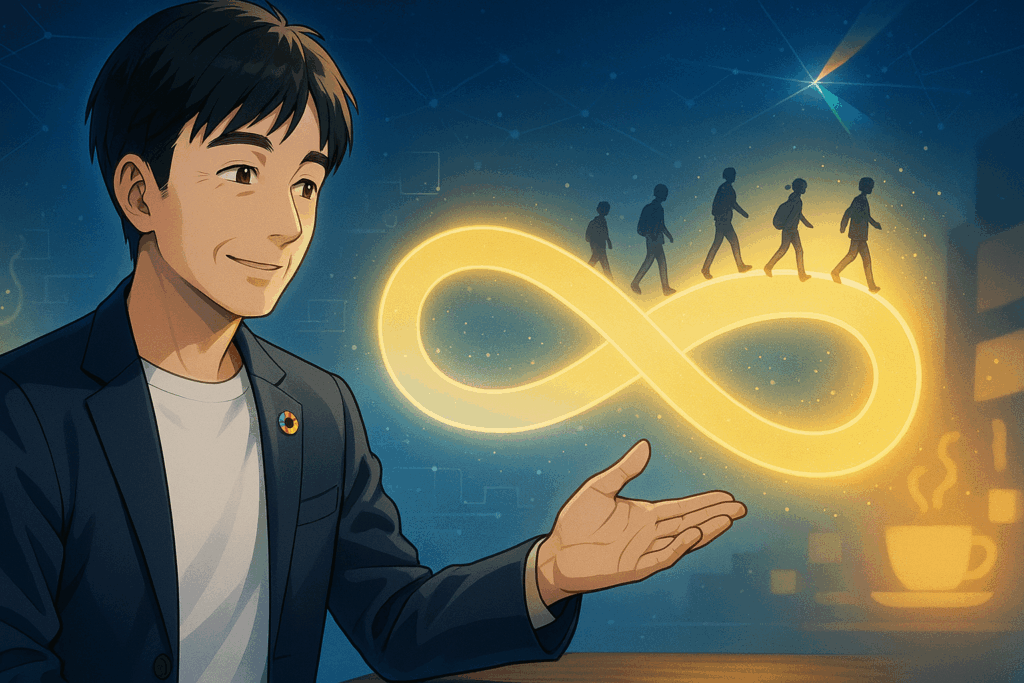
学生の皆さんには、若いうちに世界を広く見て、多様な価値観に触れることを勧めます。SNSなどで視野が狭まらないよう、異なる背景を持つ人々との関係構築を大切にしてください。また、苦手分野にも積極的に挑戦し、自ら壁を作らない姿勢が重要です。若い時期は多くの失敗が許される特権があり、何かに夢中になる経験を多く持つことが、人生を豊かにします。
私は「努力」という言葉よりも、「夢中」になって取り組むことを重視しています。夢中な時は努力と感じず、後から「努力した」と気づくものです。これからの時代は副業が当たり前になり、複数の仕事に携わることで、人生をより楽しむことができます。何をやっても「天職かもしれない」と思える人はストレスを溜めず、顔が晴れやかになるような生き方をしてほしいです。
「情報の質が人生の質を左右する」と私たちは考えており、情報を発信する際は、その信頼性と質を徹底的に確認してください。最終的に購入を決めるのは人間であり、リアルな体験に基づいた情報は、デジタル時代の今こそ重要です。仕事においては、個人的な欲求よりも公的な目的を優先する利他的な精神が、信用を得る上で不可欠です。弊社では、賃金が発生するインターンシップで相互理解を深め、入社後のミスマッチを防ぎ、社員を「褒めて育てる」文化を大切にしています。
取材担当(石嵜)の感想
「努力」よりも「夢中」という言葉に込められたメッセージや、「顔が晴れやかになる」という「頑張る」の解釈は、就職活動を控える私にとって新鮮で力強いアドバイスでした。多様な価値観を受け入れることや、苦手なことに挑戦することの重要性も、SNSが普及し情報が画一化しがちな現代において、改めて意識すべき点だと感じました。採用における相互理解や「褒めて育てる」文化は、学生が安心して成長できる環境だと強く感じました。

【クオリム株式会社の今後の展望】
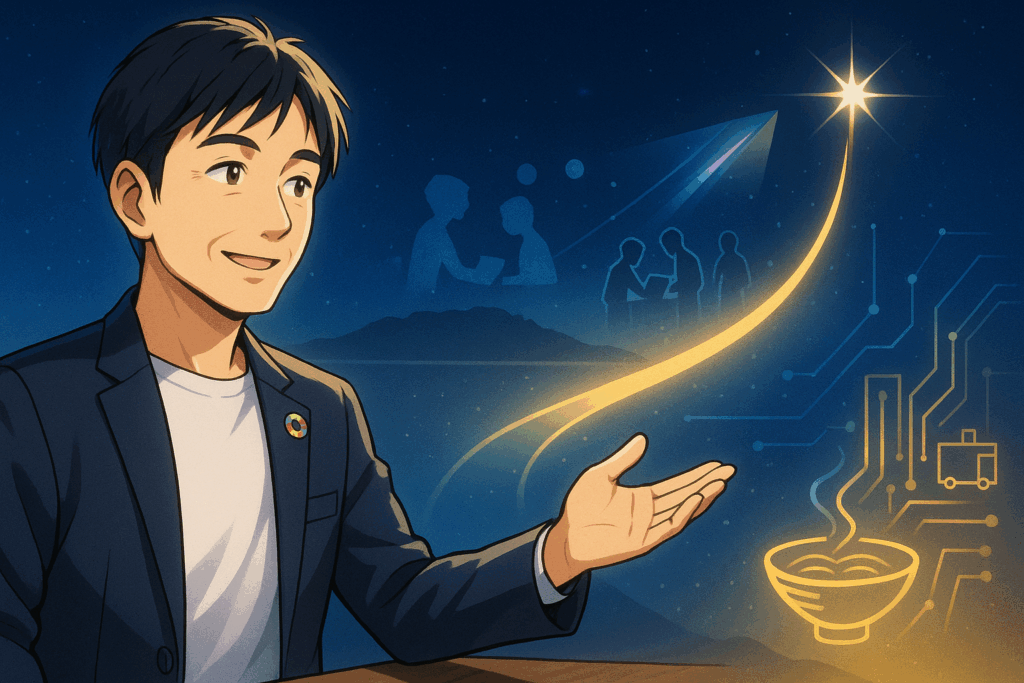
私の明確なビジョンは、日本の西の端である長崎県を、IT企業の集積地「日本のシリコンバレー」にすることです。九州のIT企業と連携し、特に弊社が注力する「フードテック」分野で、長崎の美味しいものをより広く、より長く届ける技術開発を進めます。これにより、都会でなくとも豊かな自然の中で子育てをしながらITベンチャーで働ける「両得」の場所を創出したいと考えています。
採用活動においては、会社が直接PRするのではなく、実際に働いている社員やアルバイト学生が「友人」という信頼関係の中で情報を発信することを重視しています。大学の先生やインターンシップなど、ワンステップの信用形成を経てからの情報が、説得力を持つと信じています。
会社が出すべきは正確な会社情報であり、それ以外の認知の部分は、人から人への信用を通じて広がるべきだと考えています。営業活動においても、銀行など既存の信頼関係を活用し、間接的に新規顧客を開拓しています。私たちは「人」と「信用」を軸に、地方からのイノベーション創出と持続可能な地域社会の実現を目指して、多様な取り組みを進めてまいります。
取材担当(石嵜)の感想
「日本のシリコンバレー」という壮大なビジョンに、地方創生とITの融合への強い意志を感じました。フードテックに関する具体的な取り組みも、地域の魅力を最大限に引き出し、新たな人の流れを創出しようとする情熱が伝わってきました。特に、採用や営業において「信用」を最も重視し、人から人への繋がりを大切にする戦略は、現代社会において非常に説得力があると感じました。このような、地に足の着いた信頼関係の構築が、クオリム株式会社の成長を支えているのだと確信しました。










