ダテ薬局様は、岡山県玉野市で1917年から100年以上にわたり、地域の皆様にご愛顧頂いてきた企業です。私たちは「人」と「心」を大切にする薬局として、医薬品提供に留まらず、地域社会への貢献に努めています。現在、岡山県内に8店舗の調剤薬局を主軸に、化粧品販売や介護福祉用具のレンタル、見守りサービスも提供し、地域の健康と生活を多角的に支える「地域密着型薬局」として活動しています。今回は、100年以上地域に根ざして歩んできた歴史と、多角的に広がるサービスの背景、そしてこれからの薬局のあり方について、専務取締役 朝田様にじっくりとお話を伺いました。
<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>
【私のキャリアパスとダテ薬局への入社】
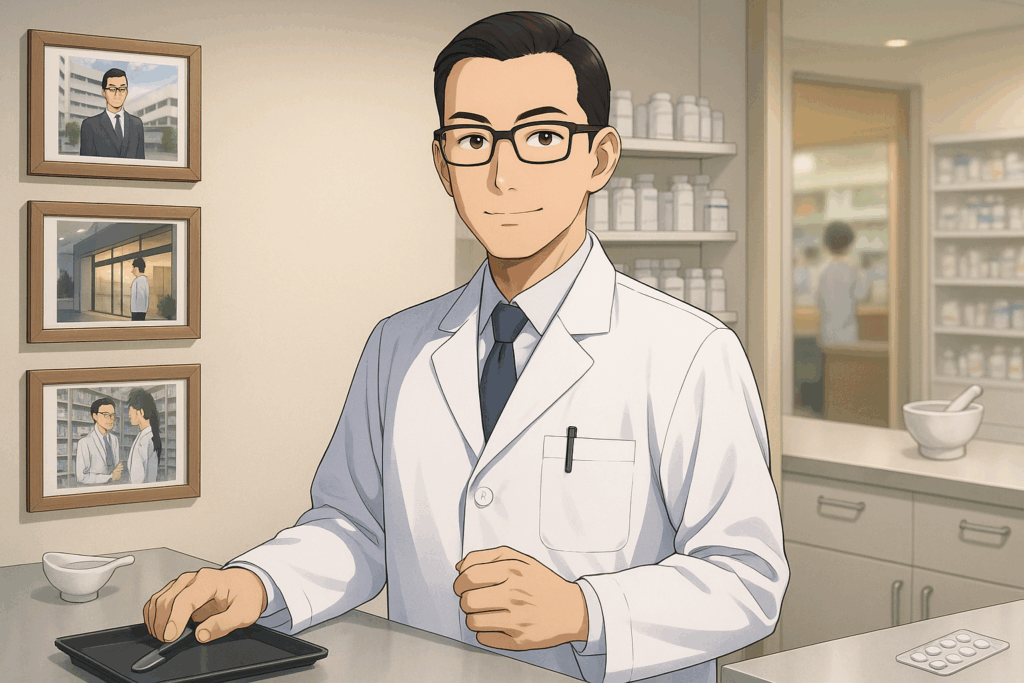
私は大学で薬剤師資格を取得後、まず製薬会社の営業、いわゆるMRとして9年間実社会を学びました。ダテ薬局は、私の曾祖父が1917年に創業した会社です。社長である叔父からは社会をしっかり見て勉強し、全く異なる環境で企業に入り、組織を学ぶよう言われました。製薬会社の営業に入ったのはそのためです。
2012年、新たな薬局店舗の出展機会に恵まれ、製薬会社を退職し、薬剤師としてダテ薬局に入社しました。入社していきなり経営に携わったわけではありません。まずは新店舗の管理薬剤師を務め、店舗が軌道に乗ってからは複数店舗の管理を経験しました。現在、私は調剤薬局部門全体の責任者として専務取締役を務めています。この道のりは、社会と組織を深く理解する貴重な時間となりました。
取材担当者(高橋)の感想
朝田様が大学卒業後すぐに家業を継がず、一度外部企業で社会経験を積まれたことに感銘を受けました。組織で働く経験や社会の仕組みを深く理解されたことが、現在の経営に活かされているのだと感じます。着実にキャリアを築かれたプロセスは、私たち就活生にとって自身のキャリアを考える上で非常に参考になります。

【地域社会への貢献を形にする】
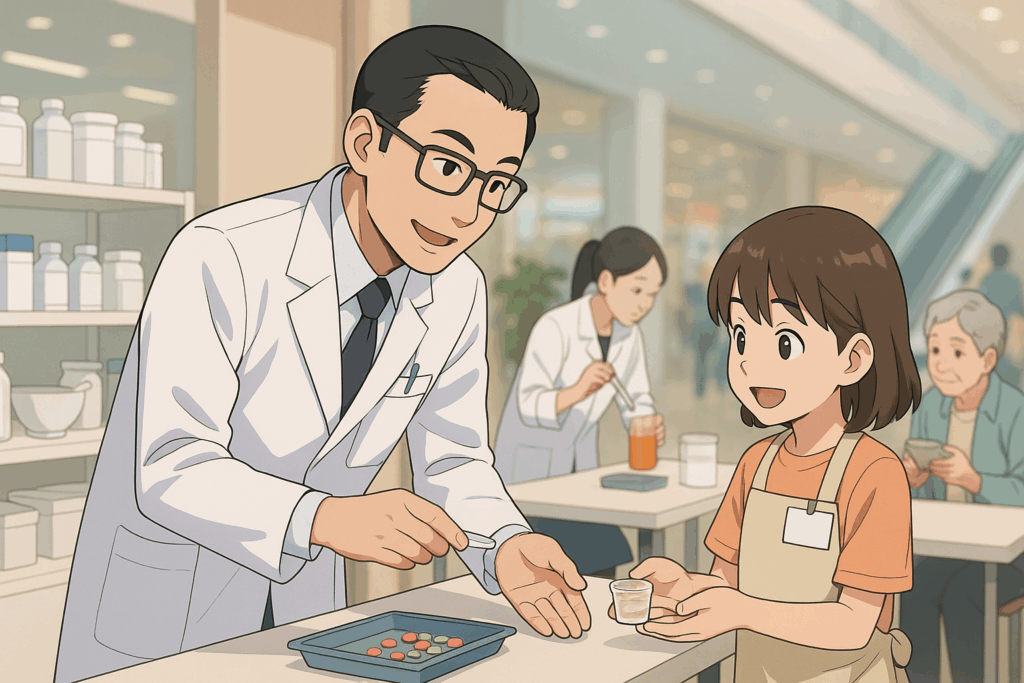
私が専務取締役に就任して以来、最も力を入れてきたのは、言葉だけでなく「行動で示す」地域貢献です。地域貢献を掲げる薬局は多いですが、実践し続けるのは容易ではありません。具体的な取り組みとして、行政と連携した活動を積極的に行っています。例えば、玉野市と連携し、地域の小学生向け「薬剤師体験」イベントを開催しています。お菓子を薬に見立てて調剤したり、ジュースで水薬を作ったり、服薬指導体験も実施しています。商業施設内で、子どもたちが楽しみながら薬や薬剤師の役割を学ぶ機会を提供しています。中学生の職場体験「チャレンジワーク」や、小中学校・高校での「職業講話」も毎年行い、薬剤師の魅力を伝え、地域の教育に貢献しています。
さらに、薬局に留まらず、地域のコミュニティへ積極的に足を運び、ニーズを把握する活動も行っています。公民館などで「お薬の勉強会」を開催したり、地域包括支援センターからの依頼で、お薬に加え熱中症予防や介護保険・福祉用具の説明会なども開催しています。これらは、薬局が単に薬を渡すだけでなく、地域の健康を包括的にサポートする存在となるためです。
取材担当者(高橋)の感想
「地域貢献」を掲げる企業が多い中で、ダテ薬局様が具体的な行動で実践されていることに驚きました。子ども向け薬剤師体験や公民館での勉強会など、地域住民の生活に深く寄り添う姿勢は、社会貢献を目指す学生にとって魅力的です。薬局の枠を超えた取り組みは、まさに「地域に根差す」ことの真髄だと感じます。

【「ラストアクセス」から「ファーストアクセス」へ】
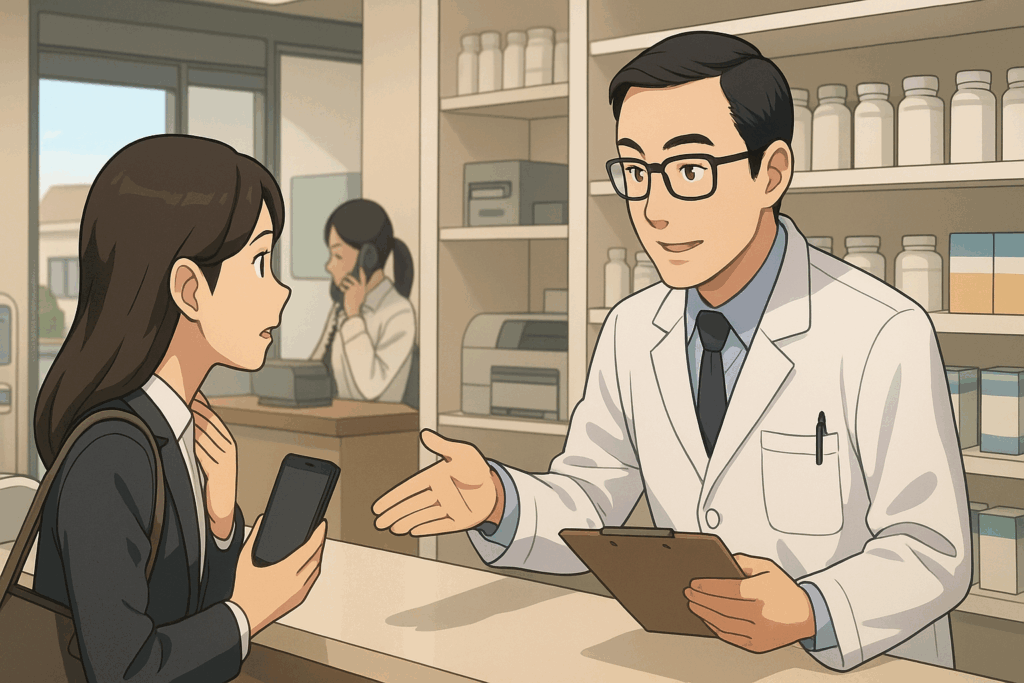
現在の薬局の多くは、病院で診察を受けた患者が処方箋を持って最後に訪れる場所、いわゆる「ラストアクセス」という認識が一般的です。しかし、薬局の役割はそれだけに留めてはならないと考えています。
私たちが目指すのは、地域の皆様にとって「最初に相談したい」と思ってもらえる「ファーストアクセス」の存在です。これは「病院に行く時間がない」「ちょっとした体調の不安がある」時に、まず私たち薬剤師に相談してもらい、必要であれば適切に医療機関へ繋げられる存在を目指しています。
この目標には、日本の医療経済の現状も大きく関わっています。少子高齢化が進む中で社会保障費は増大し、国の財源は減少しています。私たちの収益の柱である調剤報酬は2年ごとに改定され、将来的には確実に減っていくことが予想されています。そのため、処方箋に依存するだけでは、薬局は立ち行かなくなる時代が来るかもしれません。
だからこそ、私たちは地域の方々から信頼を得て、自らお客様を増やしていく必要があります。薬剤師は薬局の中に閉じこもっているイメージがあるかもしれませんが、今後はもっと地域に出て、積極的に行動すべきです。それが、私たちが持続的に地域に貢献し続けるための道だと信じています。
取材担当者(高橋)の感想
「ラストアクセス」から「ファーストアクセス」への転換というビジョンは、薬局業界の現状と未来に対する深い洞察が感じられました。単なる理想論ではなく、社会保障費削減という現実課題を見据え、自ら未来を切り開こうとする姿勢は、ビジネスを学ぶ上で非常に勉強になります。地域に出て行動する薬剤師という新しい役割は、今後のキャリアを考える学生にとって、新たな可能性を示しています。

【未来を担う人材の確保と育成】
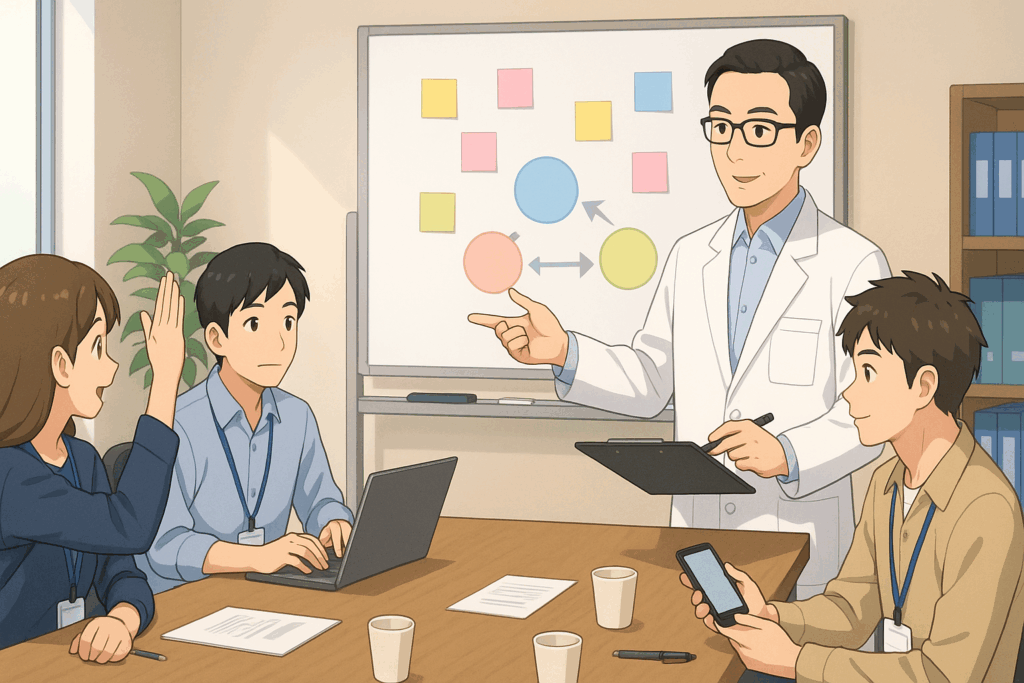
薬局の未来を築く上で、薬剤師や社員の確保は非常に重要な課題です。私たちは、まず既存の社員に対して、会議などを通じて会社のビジョンや業界の現状を丁寧に説明し、理解と覚悟を共有することから始めています。すぐに意識が変わるわけではありませんが、地道に伝え続けることで行動の変化に繋がると信じています。
具体的な採用活動としては、県内にある大学2校に定期的にアプローチしています。また、人材派遣会社にも常に応募をかけています。若い世代の薬剤師の確保については、既存の若手社員の協力も得ています。彼らの友人などで、以前の職場で期待と現実のギャップを感じて退職を考えている方がいれば、一度会って話を聞く機会を設けることで、採用に繋がったケースもあります。実際に、近年は20代から30代前半の若い世代の社員が全体の3割から4割近くを占めるほど増えてきました。これは、一人の若手社員が入社することで、そこから縁が広がり、次々と新しい仲間が増えるという良い流れが生まれているためだと感じています。また、会社側から見ても、若い人材がいることは、さらなる若い世代が安心して入社できる要因になると考えています。
私たちは「更に100年続く企業」を目指すというコンセプトのもと、若手社員中心の「100年プロジェクトチーム」を社内に立ち上げました。このチームでは、会社が今後も成長し続けるためにどうすれば良いかを話し合い、様々な取り組みを企画・実行しています。このように、社内から未来を創造していく力を育むことで、人材の定着と確保に繋げたいです。
取材担当者(高橋)の感想
社員への丁寧な説明や、若手社員のネットワークを活用した採用方法は、現代の人材確保において理にかなっていると感じました。若手が一人入ることで次の縁へ繋がるという話は、企業文化や職場の雰囲気がいかに採用に影響するかを実感させます。若手社員が会社の未来を考える「100プロ」のようなチームがあることは、主体性を重んじるZ世代の学生にとって、大きな魅力となるはずです。

【学生の皆さんへのメッセージ】
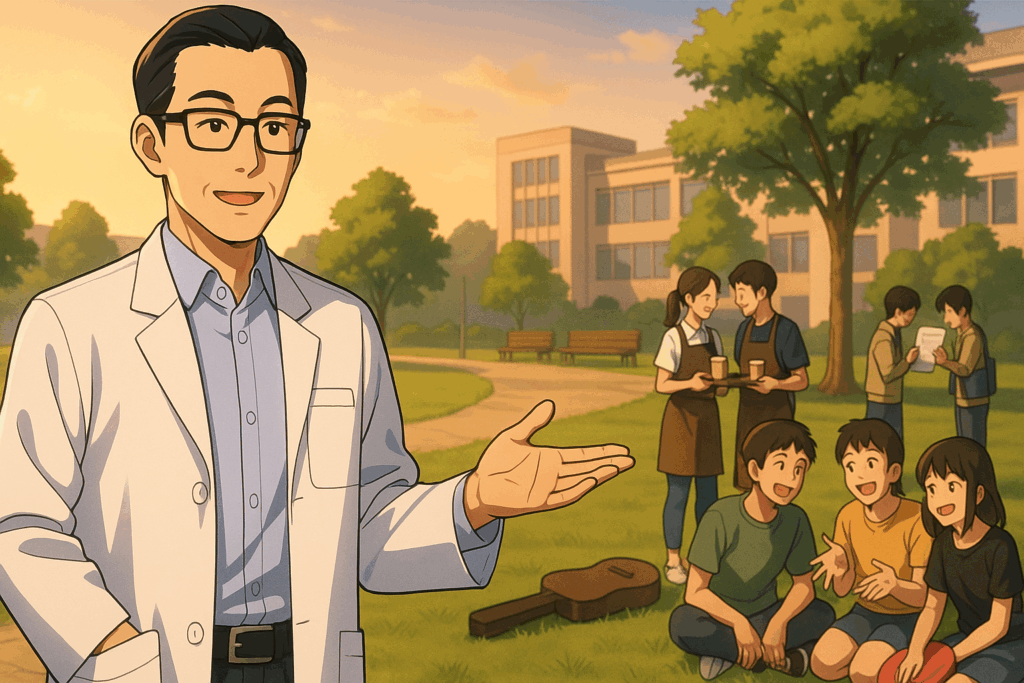
学生時代にしかできないことはたくさんあります。特に、友人たちと存分に遊び、多くの時間を共有してほしいと思います。そこで培われる人間関係や繋がりは、社会に出てからも必ず生きてきます。
また、アルバイトは色々な仕事を経験しておくことをお勧めします。私は面接の際に、必ずアルバイト経験について尋ねます。そこから、その人の適性や、どのような環境で力を発揮できるのかを見させてもらっています。学生時代の経験は、将来の自分を形成する上で非常に重要であるため、ぜひ様々なことに挑戦し、自分自身の可能性を広げていってほしいです。
取材担当者(高橋)の感想
「しっかり遊ぶこと」というアドバイスは意外でしたが、その後に続く「人との繋がりが生きる」「バイトで適性を見極める」といった言葉からは、深い意図と学生時代にしか得られない学びへの示唆を感じました。仕事が始まれば多忙になるからこそ、学生のうちにしかできない経験を大切にするというメッセージは、私たち就活生に響くものがありました。










