株式会社池利は、奈良県桜井市、三輪山のふもとに位置する、嘉永3年(1850年)創業の手延べそうめんメーカーです。170年以上にわたり、伝統的な手延べの技を受け継ぎながら、うどんや春雨など様々な乾麺、乾物の製造・販売を手がけています。池利は、ただ伝統を守るだけでなく、「常に新しさを求めることも伝統のひとつ」という考えのもと、次世代の感性で食のニーズに応え、独自の麺文化を提案し続けています。今回は、三輪の地で磨かれた手延べの伝統と挑戦の舞台裏、そして次世代へつなぐ麺づくりの展望について、代表取締役社長 池田様にお話を伺いました。
<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>
【池田様の今までの経緯・背景】
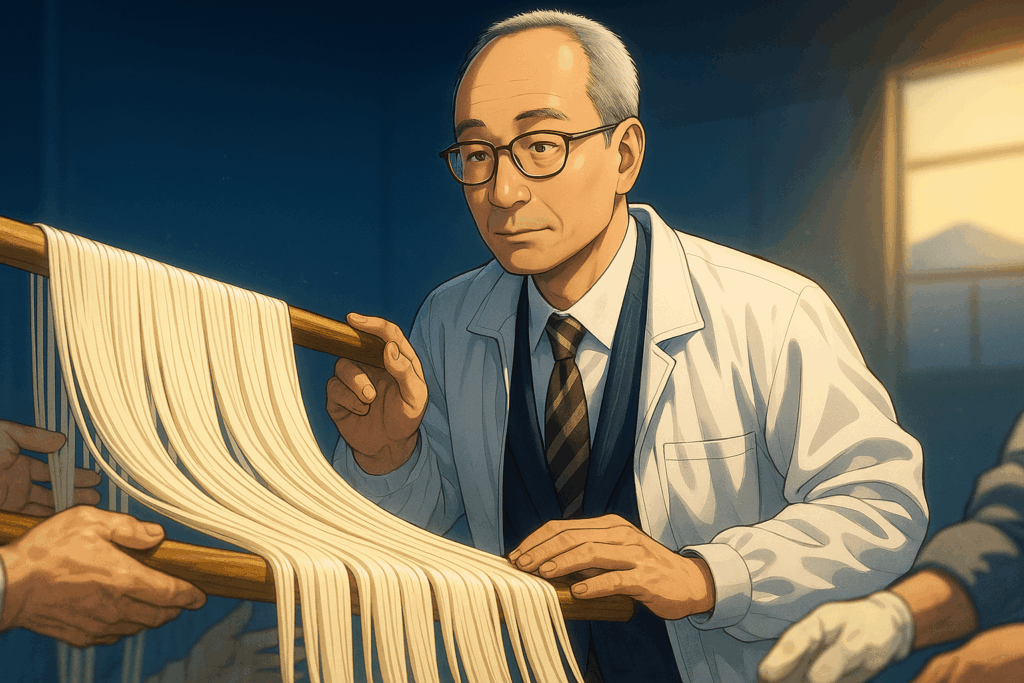
私がこの会社を継ぐことになったのは、本当に自然な流れだったと感じています。小さい頃から周りには「お前が継ぐんだ」と言われ続けていましたから、特に自分の強い意志があったわけではありません。なんとなく、という表現が一番正直なところです。大人になるにつれて、自然とこの道に進んだという感覚です。
もちろん、会社を継ぐことには大きなプレッシャーや不安がありましたし、今でもそれは変わりません。しかし、ありがたいことに、私は大学生の頃から夏休みには自社でアルバイトさせてもらっていました。当社は歴史が長く、勤続年数の長いベテラン社員がたくさんいるのですが、若い頃から彼ら、おじさんやおばさんと呼んでいた方々が本当に可愛がってくれたんです。そのおかげで、会社の中にスムーズに溶け込むことができたと思っています。
一方で、ベテラン社員が多いということは、皆さんそれぞれに強い「こだわり」があるということでもあります。そのこだわりを否定するつもりは全くなかったのですが、時代と共に変わっていかなければならない部分もあり、意見が衝突したこともありました。それでも、私が今日までやってこられたのは、本当に人に恵まれたからだと思います。
周りの方々に支えていただいたことが何よりも大きく、私が何かをしたから会社がどうなった、というようなことは、おそらくないでしょう。私にはカリスマ性がないと思っていますが、結果としてみんなの協力を頂き、甘えさせてもらうことで乗り越えられた部分は大きいですね。
取材担当者(石嵜)の感想
池田社長が会社を継ぐことを「自然な流れ」とおっしゃっていたのが印象的でした。幼い頃から家業を継ぐという道が見えていたとはいえ、その中にプレッシャーや不安も抱えながらも、社員の方々からの愛情と支えによって乗り越えてこられたことに、人間的な温かさを感じました。
特に、「人に恵まれた」という言葉から、社長の謙虚なお人柄と、周囲を大切にする姿勢が伝わってきました。これは、これから社会に出る私たち学生にとって、人間関係の大切さを改めて教えてくれる貴重な学びだと感じています。

【池田様から学生へのメッセージ】
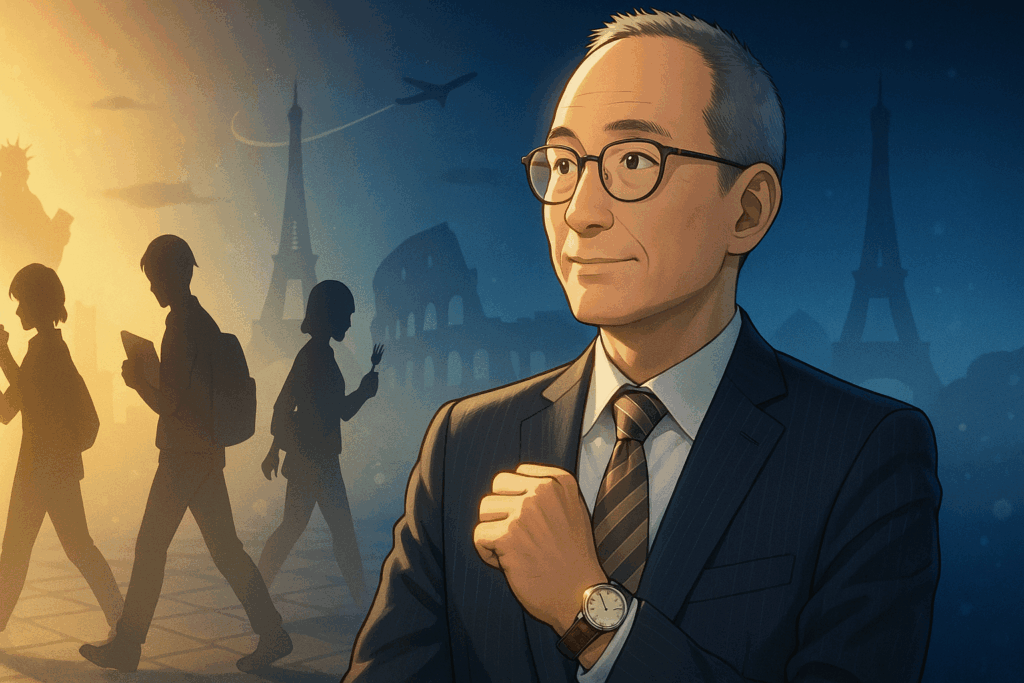
学生の皆さんには、社会に出る前に「時間を上手に使うこと」を強く意識してほしいと思っています。社会人になると、なかなか自分の自由な時間を作るのが難しくなりますから、今ある時間を最大限に活用してほしいですね。特に、コロナ禍が明けて自由に活動できるようになった今、ぜひ「見聞を広める」ことに挑戦してほしいです。
例えば、日本だけでなく世界に目を向けてみてください。ニューヨークやパリ、イタリアなど、世界の中心と言われるような場所に行き、どんな人がいて、どんな空気が流れているのかを肌で感じることは、大きな財産になるはずです。奈良県の中だけで物事を考えるのではなく、日本全国、あるいは世界レベルで物事を考える視点を持つことが、将来の皆さんの役に立つと思います。食べることが好きなら食べ歩きもいいでしょう。地方には美味しいものがたくさんありますし、口に合わないものも、それもまた経験です。
そうした経験を通じて、自分の視野が自然と広がり、ある意味「味のある大人」になっていけるのではないでしょうか。私自身は学生時代を「だらだら」と過ごしてしまい、もっと色々な場所に行き、色々なことをしておけばよかったと後悔している部分もありますから、皆さんにはぜひ、積極的に外の世界に触れてほしいと願っています。もし皆さんが将来、何か新しいことを始めたい、会社を立ち上げたいと考えているなら、天才でない限り、一人の力には限界があります。トヨタのような大企業でさえ、一人の力で動いているわけではありません。良い人や良いアドバイスをくれる人に恵まれ、彼らの意見に耳を傾けることが何よりも大切だと私は思います。
取材担当(石嵜)の感想
池田社長の「見聞を広める」というメッセージは、私自身の最近の経験と重なり、非常に心に響きました。私も大学4年生になって初めて海外に行き、フィリピンで日本とは異なる活気や文化を肌で感じ、それがどれほど貴重な経験であるかを実感したばかりです。
社会に出る前に、限られた時間の中でいかに多くの経験を積むか、その重要性を改めて教えてさせていただきました。また、これから起業を目指す私にとって、「周りに良い人、良いアドバイスをくれる人が大切」というお言葉は、今後の指針となるでしょう。

【株式会社池利の事業・業界について】
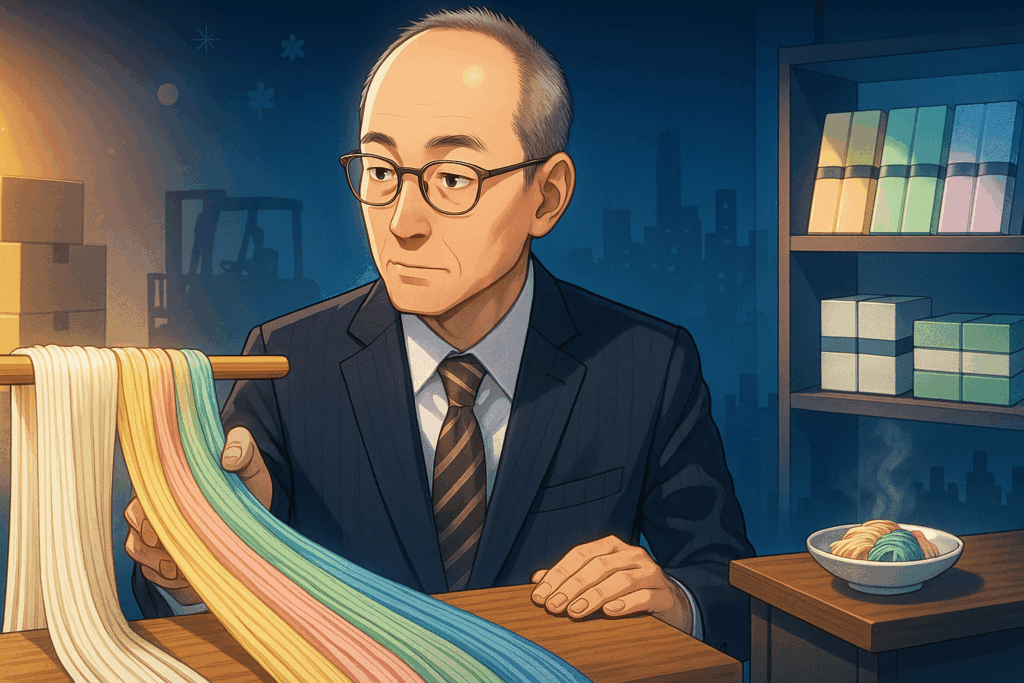
当社の主な事業は「おろし業務」、つまり問屋としてのビジネスがメインです。お客様と直接つながる直営店はレストラン(千寿亭)のみで、他はオンラインストアがお客様との主な窓口になっています。社員からはBtoC(消費者向けビジネス)を伸ばしていきたいという声も多く上がっていますが、口で言うほど簡単ではないというのが正直なところです。
そうめん業界の特性として、年間を通じて購入していただける商材としてはまだまだ遠いと感じています。やはり、夏場の売り上げが圧倒的に大きいので、通年で安定した売り上げを確保するのが難しいという課題があります。東京営業所では、そうめんの傍らで自分たちで仕入れた物を販売するなど、対面販売も行っていますが、これはメインまでは行かず中核事業です。現在は年間で110〜120名、ピーク時には130名ほどの従業員がいますが、それでも人材不足は否めず、特に人をまとめて動かすような職種では「正直ギリギリで回っている」状況です。
しかし、私たちは伝統に縛られるだけでなく、常に新しい挑戦を続けています。例えば、スーパーなどで見かけるカラフルなそうめん「色撫子(いろなでしこ)」は、実は当社が業界で一番最初に作った商品なんですよ。私の祖祖父が開発したもので、色とりどりのそうめんを作るのが当社の得意技であり、大きな「売り」にもなっています。そうめんが昔ながらの「お母さんの手抜き料理」というイメージだけでなく、もっと多様な楽しみ方があることを伝えたいと思っています。伝統を守るだけでなく、お客様にどれだけそうめんを「食べ続けていただけるか」を追求し、そこに力を入れているんです。
取材担当(石嵜)の感想
池田社長のお話から、池利が単なる伝統的なそうめんメーカーではなく、新しい価値創造に積極的に取り組む革新的な企業であることがよく理解できました。特に、カラフルなそうめんを業界で最初に開発したというエピソードには驚きと共に、そのチャレンジ精神に感銘を受けました。
そうめんが持つ伝統的なイメージと、池利が提案する新しい食文化のギャップが非常に魅力的で、これからの若い世代にも大いに響く可能性を感じました。また、業界全体の人手不足という課題にも真摯に向き合い、社員の皆さんの力で乗り越えようとされている姿勢に、強い組織のあり方を見ました。

【株式会社池利の今後の展望】
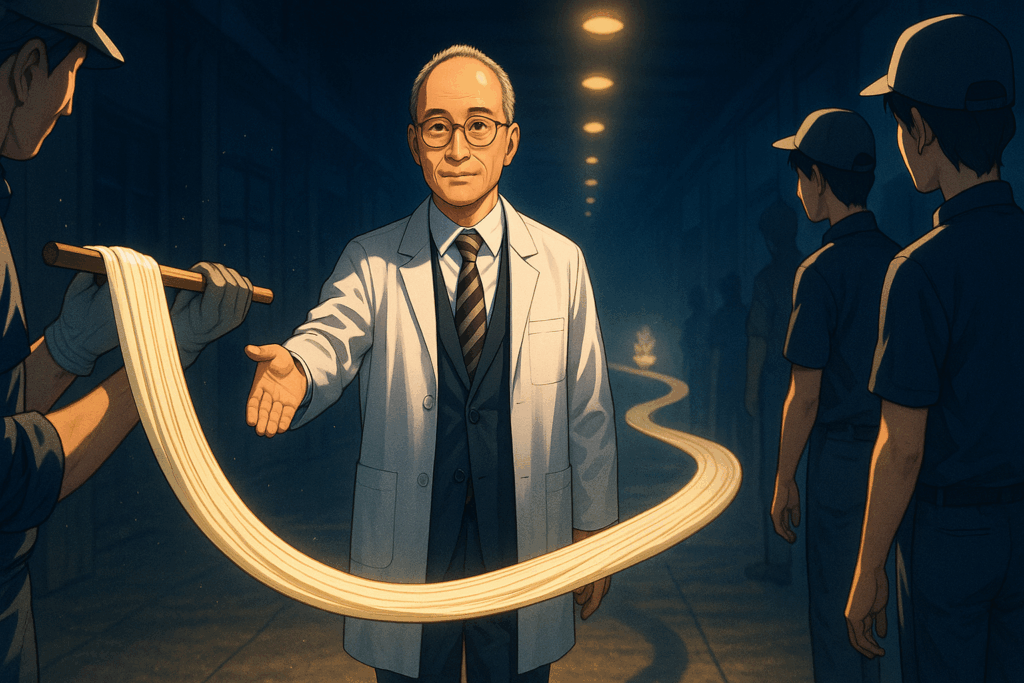
私の夢や個人的な目標というのは、あまりないんです。それよりも、私がずっと仕事をしていく中で、一番に考えるのはやはり「従業員の皆様のこと」です。従業員の皆さんが気持ちよく働けて、「池利で働いていて良かった」と言ってもらえるかどうか、それが私の全てだと思っています。
私自身が豊かになることには意味がないと思っています。従業員の皆さんが良くなるということは、結果的に会社が良くなっているということにつながるはずです。会社を良くする、という表現は抽象的ですが、社員一人ひとりに直接関係のあることを大切にする方が、皆さんと一緒に未来を築いていけると考えています。これだけ高齢化社会が進む中で、皆が年を取ってからも働き続ける必要があります。だからこそ、70歳になっても働けるような会社でありたい、それが私の一番の願いです。
私たちはメーカーとして、デジタルだけではない「アナログ」な部分で動いています。そうめんを作る過程には、見た目の美しさだけでなく、その裏側で地道に努力している人たちの「かっこよさ」があると思っています。これからの若い世代には、そうした「裏側の頑張り」にも目を向けて、その価値を感じてほしいと願っています。お客様にどれだけそうめんを「食べ続けていただけるか」を追求し、新たな伝統を築いていくことこそが、私たちの進むべき道だと考えています。
取材担当(石嵜)の感想
池田社長の「従業員が幸せであること」が会社の最大の目標というお考えに、深い感銘を受けました。ご自身の夢よりも、社員の皆さんの働きがいや満足度を最優先される姿勢は、まさに理想の経営者像だと感じました。そして、そうめんづくりの「アナログなかっこよさ」を若い世代に伝えたいというお話は、デジタルネイティブの私たちだからこそできる貢献があると感じ、非常に共感しました。
池利が持つ「伝統と革新」のバランス、そして人を大切にする文化は、これからの時代を生きる私たち学生にとって、企業選びの重要な指標となるでしょう。










