三重県四日市市を拠点とする株式会社ダイエンフーズは、前身の大遠冷蔵(1951年創業)から受け継いだ水産加工の技術を基盤に、まぐろ・かつおを中心とした水産生食流通の改革と製品開発に取り組んできた企業です。-55℃の超低温冷凍庫と直結した自社加工体制を備え、高品質な原料をスピーディーに加工・提供できる生産基盤を構築。水産物の加工・販売、営業倉庫、そして直営の「まぐろレストラン」を展開し、魚食文化の発展とお客様満足の最大化を目指しています。今回は、-55℃の超低温インフラを核にした生食流通の革新と「まぐろレストラン」に込めた魚食文化への想い、そして次の挑戦について、代表取締役社長にじっくりお話を伺いました。
<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>
【今までの経緯・背景】「食」への情熱から始まった予期せぬ経営者の道
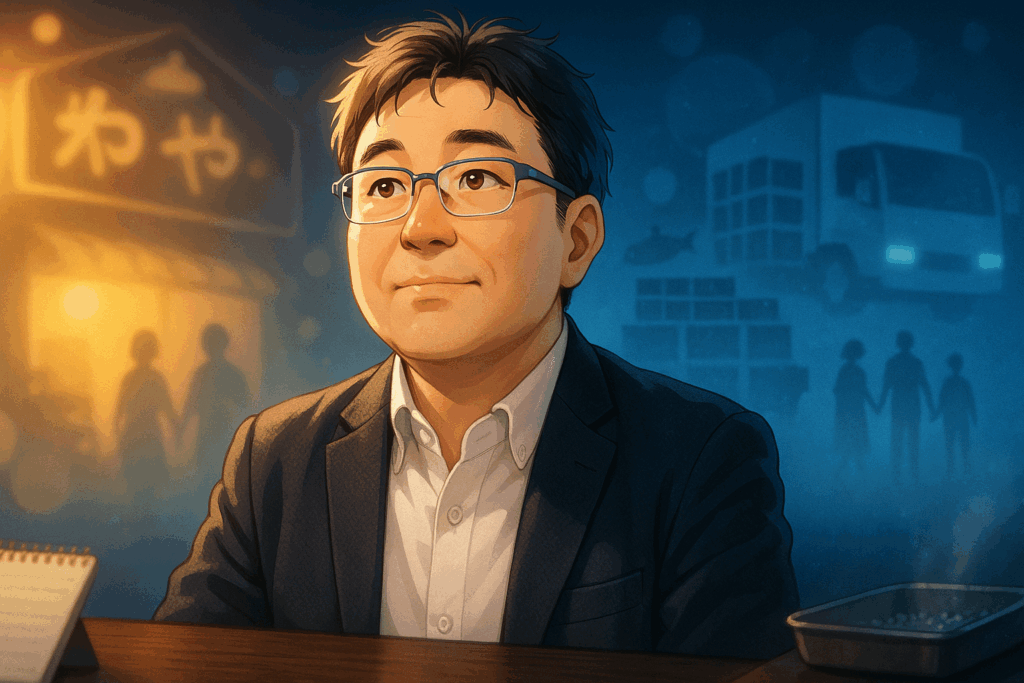
私は、実は最初から経営者を目指していたわけではありませんでした。新卒で株式会社バロー(現バローホールディングス)に入社し、スーパーマーケット事業の鮮魚部門で魚を扱うバイヤーとしてキャリアをスタートしました。スーパーマーケットを仕事に選んだ理由ですが、自分が幼い頃に両親は小さな喫茶店を開いていました。おぼろげですがその風景の記憶があります。
これが「食を扱う仕事がしたい」に繋がったのでしょう。私のキャリアの原点と言えるかもしれません。更に大学生の頃に経験したアルバイトや、友人 家族との食事を通じ、将来は食文化に携わる仕事ができたら楽しいだろうと益々考えるようになり、仕事にスーパーマーケットを選びました。まだインターネットも一般的ではなく、物も情報も手軽には手に入りにくい時代でしたから、流通や商品開発、産地開発に尽力しながら、地域の人々に美味しいものをどう届けるかということを考えて仕事をしてきました。
食品流通での業務経験を重ねる中で、私自身はバローグループのキャリア形成の一環として、関連会社への出向や転籍があり、その流れの中でダイエンフーズの代表に就任しました。但し経営の立場に近づくにつれて、これまでとは変わり自分がやりたいことや自己実現とは別に、従業員一人ひとりの生活や労働環境を守るという大きな責任が加わったことにプレッシャーを感じるようになりました。
「従業員が安心して末永く働き続けられる会社でありたい」という強い思いが、今の私を突き動かしています。今年会社が儲かっていても、来年傾いてしまっては意味がありません。従業員のお子さんが大学を卒業するまで、家を買ったローンを払い終えるまで、きちんとお給料が払える会社であり続けなければならないと思っています。従業員の人生に深く寄り添い、彼らの生活をいかに守り、安定させていくかということを、特に最近は強く考えるようになりました。現場に近い時は考える必要がなかったことを、今は考えることが増えましたね。
取材担当者(石嵜)の感想
堀部社長が元々経営者志望ではなかったということに驚きました。自分の「好き」を追求して仕事を選んだ結果、思わぬ形で経営という大きな責任を背負うことになったというお話は、私たち学生にとって非常に示唆に富んでいると感じました。特に、自己実現から従業員の生活を守る立場への意識の変化は、仕事の真のやりがいや責任の重さを教えてくれる貴重な視点だと感じました。

【事業・業界について】食文化の変革期を支えるダイエンフーズの挑戦
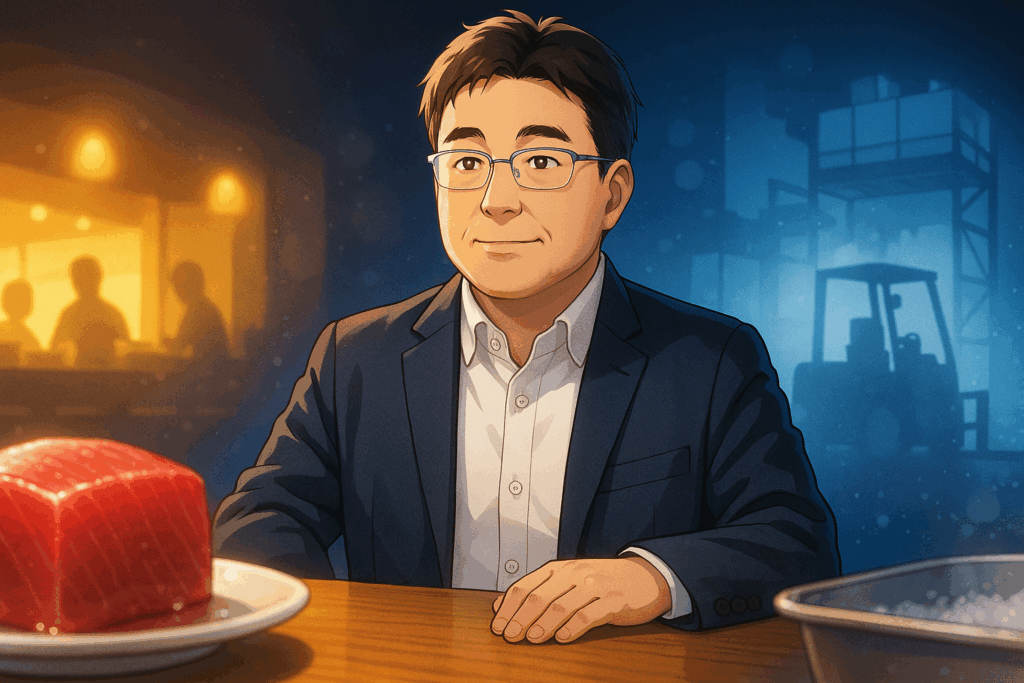
株式会社ダイエンフーズの主力事業は、水産物加工販売、飲食業、そして倉庫業の3つの柱で成り立っています。中でも、三重県四日市市に位置する「まぐろレストラン」は、その名の通りマグロ料理を専門とする人気の飲食店です。かつては「レトロなマグロ食堂」「昭和の社員食堂」として親しまれ、2018年の改修後も多くのメディアや雑誌に取り上げていただいています。
このレストランの大きな強みは、自社工場で製造したものを直接お客様に提供している点にあります。これにより、高品質な食材をコストパフォーマンス良く提供できていると私は自負しています。創業当時からダイエンフーズは、マグロやカツオを中心とした水産生食流通の構造改革と製品開発に尽力し、日本の和食文化・魚文化の発展に貢献してきました。
近年、食を取り巻く環境は大きく変化しています。家族構成の変化や単身世帯の増加により、家庭での食事が減り、スーパーマーケットでの買い物も減っている傾向にあります。その代わりに、外食や宅配、通販といった利用が増えていますね。このような社会の潮流に対応すべく、ダイエンフーズは自社の-55度の超低温冷凍庫と直結した新加工工場を新設し、より安全で高品質な原料を迅速に加工できる体制を整え、マグロ・カツオ以外の新たな分野にも対応できるようにしています。創業以来変わらぬ品質と製品加工へのこだわりを持ち続け、安全でおいしい商品をお届けすることに努めています。
取材担当(石嵜)の感想
昔ながらの食堂として愛されてきた「まぐろレストラン」が、時代に合わせて進化し、自社工場という強みを活かしている点に魅力を感じました。食のトレンドが大きく変化している中で、企業がどのようにその変化に対応し、生き残っていくのかという視点は、就職活動をする上で業界分析にも役立つ情報だと感じました。

【今後の展望】社会の変化に寄り添い、食の未来を創造する
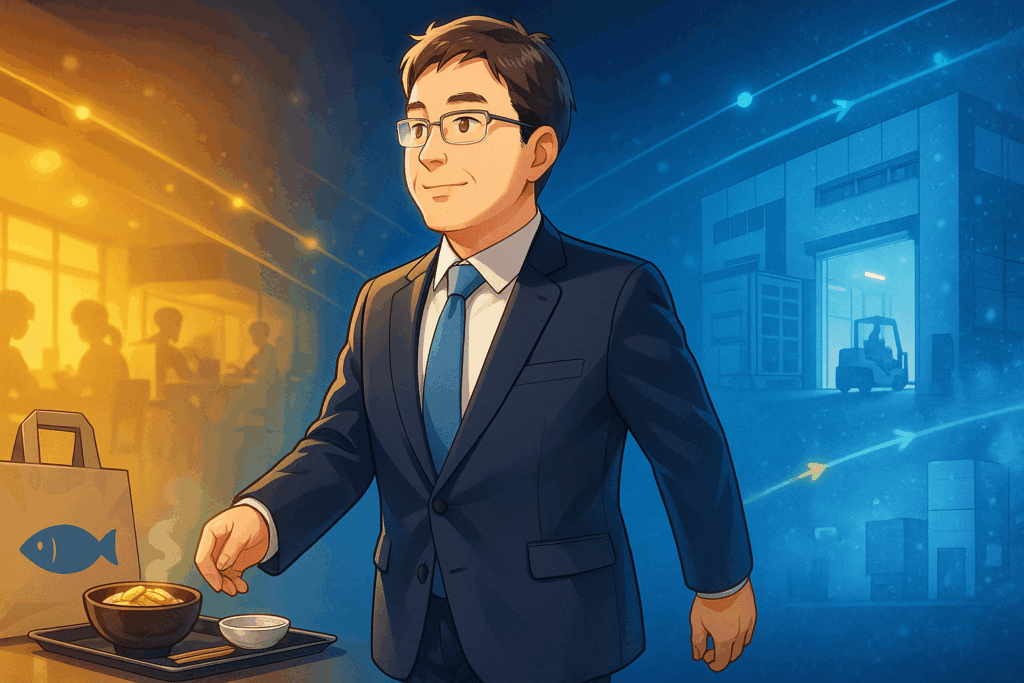
今後の事業展開については、「世の中の流れに沿っていかなければならない」と私は考えています。特に、家での家族全員揃った食シーンが減り、個食や外食、宅配が増えるという現代の食のトレンドを鑑み、飲食事業のさらなる強化が会社の存続にとって不可欠であると思っています。会社の事業内容を少しずつ修正しながら、この変革期を乗り越えようとしているところです。
ダイエンフーズは創業以来変わらぬ品質と製品加工へのこだわりを持ち続け、「お客様のお役にたてる会社」を目指し、お客様の幸せにつながる事業展開を進めていくことを理念としています。社会の変化の波を捉え、持続可能な食文化の未来を創造していくダイエンフーズの挑戦は、これからも続いていきます。
取材担当(石嵜)の感想
世の中の食のトレンドを冷静に分析し、飲食事業の強化に舵を切るという堀部社長の戦略的な視点は、とても勉強になりました。企業の将来的な事業の方向性を考える上で、社会の変化への適応が重要であることを改めて認識しました。

【学生へのメッセージ】「好き」を原動力に、仕事と人生の「やりがい」を見つける
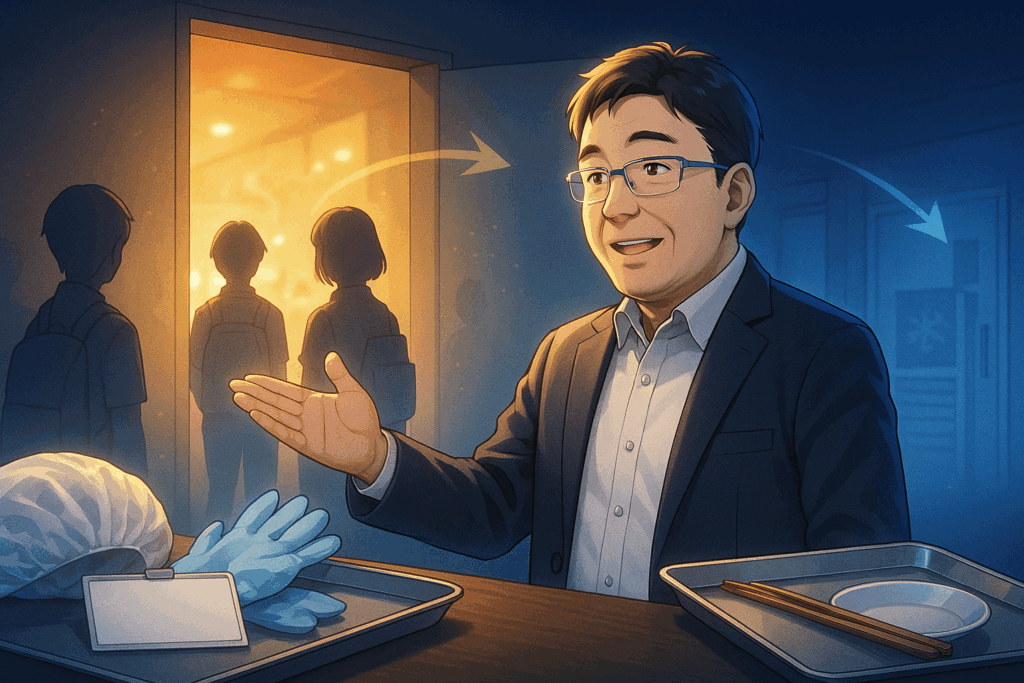
私は、就職活動中の皆さんには、仕事を選ぶ上で最も大切なことは「商品や仕事内容を好きになること」だと伝えたいですね。好きであること、興味を持つことが、情報収集力、思考力、行動力を高め、結果として通常以上の力を発揮できると強く信じています。そして、その「好き」の先に「やりがい」を見つけることが何よりも大切です。
やりがいは、後輩の育成、出世、社会貢献など、さまざまな形で見つけられると思います。まるで「好きこそものの上手なれ」という言葉のように、仕事に対する興味と情熱が、結果として給与や昇進、そして最終的には「幸せな人生」へと繋がっていくものだと、私は考えています。どんなに高収入であっても、好きではない嫌な仕事に人生の大部分を費やすことは幸せではありません。仕事は、あくまで幸せになるための手段であるべきだと、私は強く思っています。
また、情報が溢れ、選択肢が多い現代だからこそ、選んだ場所やサービスに対して「まずは全力で直接関わってみること」をアドバイスしたいですね。これは表面的な情報を見聞きするだけでは仕事の意味と本質を理解することは難しいからです。インターンシップやアルバイトなど、現場での経験を通じて実際に仕事に触れることの重要性を強調したいです。
仕事は常に変化していくもので、その変化に対応し、自ら仕事を作り出す力が求められる時代だからこそ、現場での直接の経験がその人の「幸せな人生」に繋がる一生の仕事観、人生観を形作っていくのだと、私は考えています。これに対し企業側も、学生の価値観を理解し、興味を掻き立てる会社の将来性や成長の可能性をしっかりと示していく必要があるとも思っています。
取材担当(石嵜)の感想
堀部社長の「仕事は幸せになるための手段」という言葉が、今の私にとって一番心に刺さりました。ついつい給料や安定といった面ばかりに目が行きがちですが、「好き」や「やりがい」を大切にすることで、結果的に良いキャリアと幸せな人生が手に入るというお話は、就職活動の軸を考える上で大きなヒントになります。また、現場経験の重要性についても、私自身のインターン活動を通じて改めてその価値を実感しているため、非常に共感できました。










