株式会社アルプス様は、山梨県に拠点を置き、創業から約50年の歴史を歩んできました。元々は高速道路の維持管理事業を主軸とし、中央自動車道の5箇所のパーキングエリア運営を40年以上にわたり手掛けています。現在、既存事業に加え、新たな事業の柱を築くべく新規事業にも積極的に挑戦しており、従業員数は約287名です。私は、このアルプスを「関わる全ての人を幸せにする」という理念のもと、日々経営しています。今回は、地域に根ざした事業展開の歩みと、新たな挑戦を通じて「関わる全ての人を幸せにする」という理念を追い求める金丸社長に、これからのビジョンについてじっくりとお話を伺いました。
<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>
【大手企業から焼き鳥屋、そしてアルプスへ:私のキャリアパス】
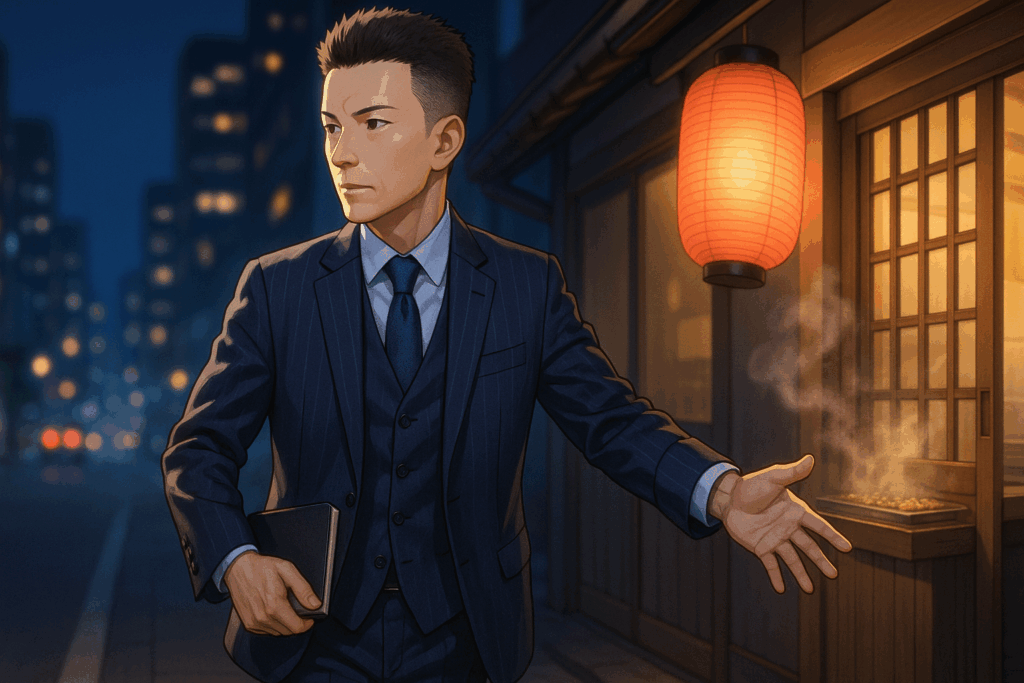
私は山梨県出身で、高校から東京へ出て、NECで7年間営業として勤務しました。その後、会社を辞め、自由に旅をしたり、29歳で六本木に焼き鳥屋をオープンし、1年間厨房に立って経営する経験もしました。30歳を目前に人生を考え直し、山梨へ帰ることを決意しました。この時、実家が株主である株式会社アルプスが選択肢に挙がりました。
当時のアルプスは高速道路の維持管理とパーキングエリア運営が主事業で、私は「ゼロイチ」(新しいものを生み出すこと)が好きで守りが苦手なタイプだったため、正直なところ魅力を感じていませんでした。しかし、入社半年前、会社に新規事業立ち上げ部門が設立されたことを知りました。新しいものを生み出す「ゼロイチ」のチームであれば面白いだろうと感じ、2004年に入社しました。
入社後は、まさに新規事業部隊で20年間、様々な事業の立ち上げに携わりました。約40店舗を開業し、6つの会社を設立する一方で、約20店舗を閉鎖する失敗も経験しました。この挑戦と失敗を繰り返す中で経験を積み、2018年に社長に就任し、現在に至ります。
取材担当者(高橋)の感想
金丸社長のキャリアは、大手企業から焼き鳥屋経営、そして家業の社長へと、まさに予測不能な「ゼロイチ」の連続だと感じました。自身の「ゼロイチが好き」という情熱に正直に行動し、旅を通して自分と向き合い、人生の目的を明確にしてきた社長の姿は、私たち20代にとって、何もないところから価値を生み出すことの重要性を教えてくれます。

【「全ての人を幸せにする」経営理念の確立】
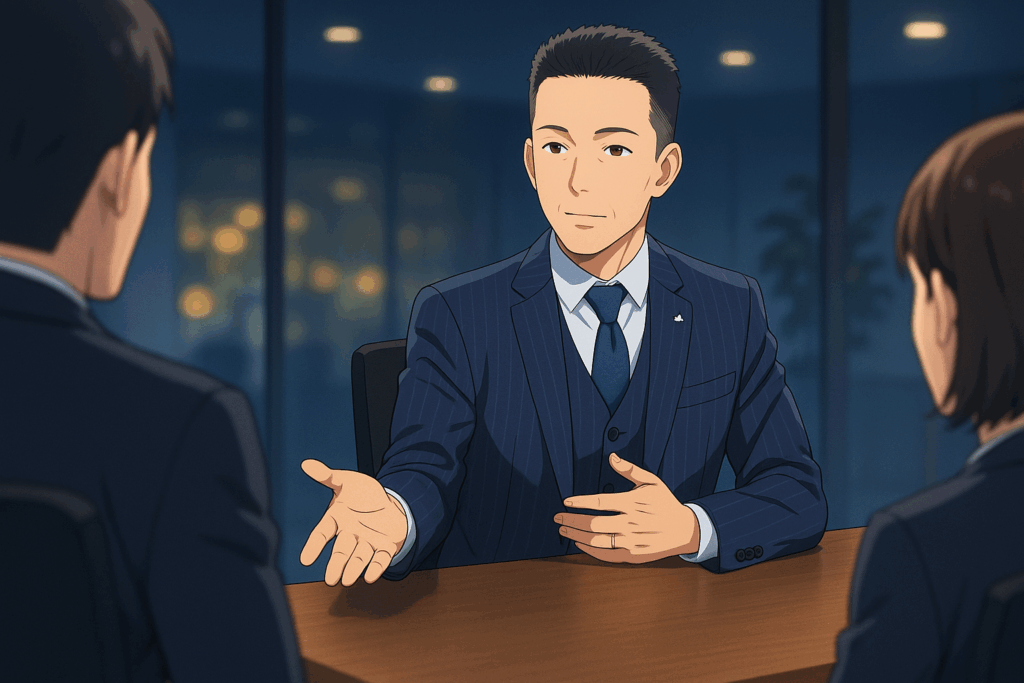
社長就任後、私が最も大きく変革したのは、会社の「経営理念」です。従来の「お客様の満足を信頼に、信頼を感動に」という理念を改め、「アルプスに関わる全ての人を幸せにする」という理念を経営の核に据えました。この根底にあるのは、お客様だけでなく、従業員、取引先まで、人との関わりの中で皆が幸せになることを目指すという思いです。
この理念は、対外的には社会やお客様への私たちの宣言であり、対内的には、従業員が日々の業務で判断に迷った際の「行動指針」となります。私は常に「どちらの選択肢がより幸せにつながるのか」という視点で判断するよう伝えています。この理念が浸透すれば、役職に関わらず皆が同じ判断基準で行動できると信じています。
私の仕事の工夫は、この「経営理念」をひたすら語り続けることです。細かい業務の指示は現場に任せ、私は「何のために仕事をしているのか?幸せにするためだ」という本質的な問いを常に発信し続けています。これにより、社員一人ひとりが自律的に考え、行動できる組織を目指しています。
取材担当者(高橋)の感想
金丸社長は、理念を経営の核に据え、社員が自律的に判断できる組織を目指す姿勢は、現代の企業が直面する課題に対する本質的な解決策だと感じました。理念の浸透が組織の強さに直結するという学びを得ました。

【数字目標に囚われない経営:変化し続けることの重要性】
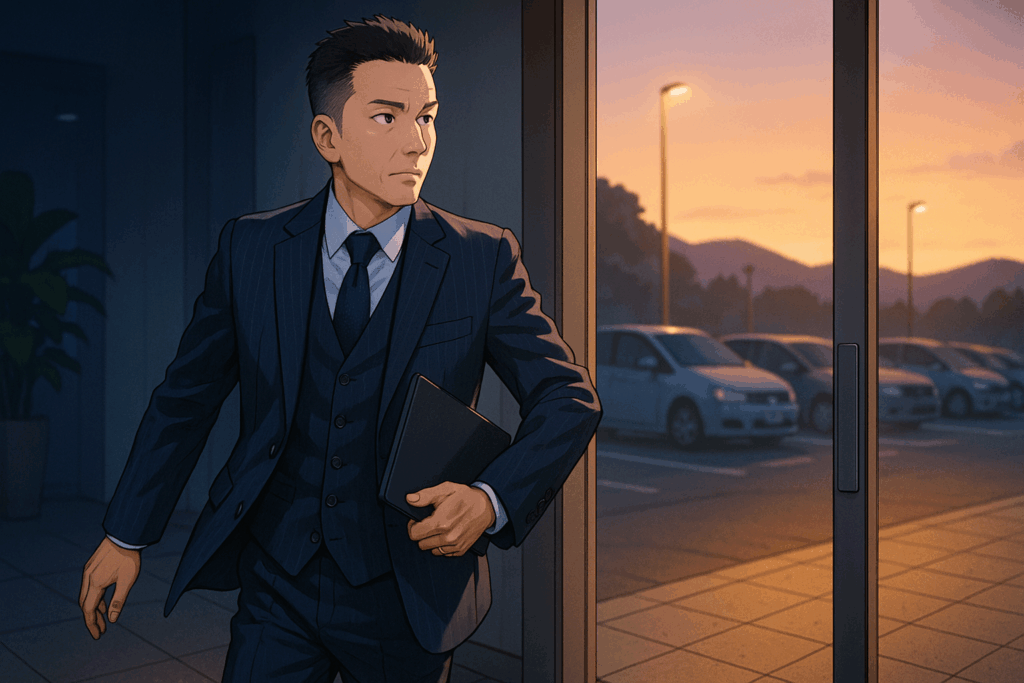
私は、具体的な店舗数や売上高、上場といった「数字の目標」は持っていません。過去のフランチャイズ事業で「100店舗」という目標を追った結果、無理な出店により失敗を経験したからです。根拠のない数字目標は判断を誤らせる、という痛い教訓を得ました。
その代わりに、常に「成長し続けること、変化し続けること」を社員に伝えています。ChatGPTのような技術が急速に発展する現代において、会社も個人も変化せずに生き残ることは不可能です。人間は変化を拒む傾向がありますが、理性と知性をもってリスクを取り、チャレンジし続けることが、人間である私たちの本質だと考えています。
失敗を恐れて行動しないのではなく、失敗から学び、恐れずにチャレンジし、変化し続けることを重視しています。その結果として、5年前には想像もしなかったような姿になったり、想定していなかった事業が始まったりする可能性があると考えています。かっちりとした事業計画を立ててタスクをこなすよりも、変化し続けた結果、今ある姿になったという状態を目指しています。
取材担当者(高橋)の感想
変化を恐れず、むしろそれを受け入れて自ら変化し続けることこそが、現代社会において企業が生き残るための不可欠な要素であるという金丸社長の考えは、私たち若者にも響くものでした。過去の失敗から学び、数字の目標に縛られずに本質的な成長と変化を追求する姿勢は、単なるビジネス戦略を超えた、哲学的な経営観を感じさせます。

【若者との共創と未来への人材戦略】
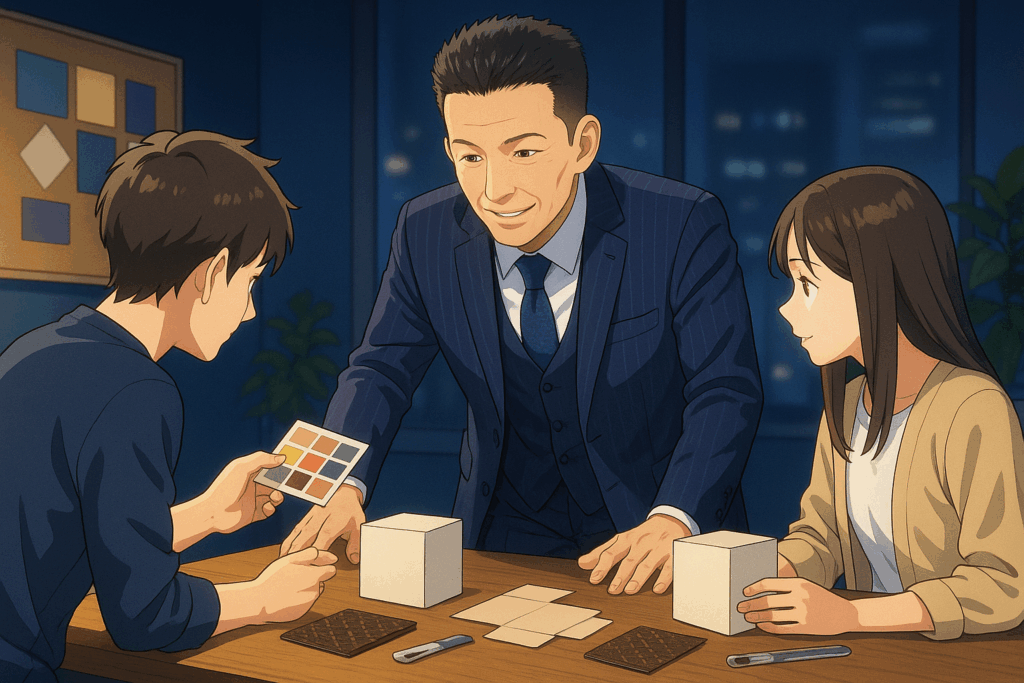
山梨県で長期インターンシップの仕組みに継続的に参加しており、毎年学生を数名受け入れ、特定のテーマに取り組んでいます。例えば、パーキングエリアで販売するお土産の商品開発やパッケージデザインを学生に任せたり、山梨の伝統工芸品である印伝のデザインを若者向けに作ってもらったりしています。私は、若者が欲しいものは若者しか知らないと考えているため、デザインに関して口出しせず、学生同士で決定するよう促しています。
これは、私自身が年を重ねる中で、今の流行やニーズを分かったふりして事業を進めることの危険性を認識しているからです。各世代のトレンドやニーズを知る人は、その世代にしかいないと思っており、若者だけでなく、外国人や主婦など、多様な従業員の声を聞くことで、そのニーズに応えようとしています。学生との関わりは、彼らが何を考え、何を欲しているのかを知るための重要な機会だと捉えています。また、私自身、若い人たちから話を聞くことで元気をもらい、それが非常に楽しい時間でもあります。
新卒採用においては、独自の哲学を持っています。長期インターンシップに参加した学生がアルプスに入社することは、今のところほとんどありません。私は学生に対して、「アルプスは最終的な滑り止めでいいから、もっと色々な会社にチャレンジしてきなさい」と背中を押しています。私自身、NECという大企業で社会人としての土台を築く半年間の研修を経験しており、その学びは非常に重要だったと考えています。アルプスでは、金銭的・時間的な制約から、大手企業のような充実した研修を提供することは難しいのが現状です。
そこで私は、「大手は研修が充実しているから学びが多いぞ。行ってみればいい」と学生に勧めています。そして、「もし大手で全て落ちて困ってしまったら、最後はアルプスで滑り止めでいいからおいで」と伝えています。この「滑り止め」という言葉には、いつでも戻ってこられる場所でありたいという思いと、彼らが社会で多くの経験を積んで成長した後、もしアルプスに戻ってきてくれたら即戦力として活躍してくれるだろうという期待が込められています。私はこれを「新入社員研修のアウトソーシング」と呼んでおり、社内でもそのように説明しています。採用活動は、目先の人数目標を追うのではなく、「社会の仕事とは何か」を語る場として、長期的な視点で行っています。人事部はなく、私自身が人事部長を兼務し、採用活動の全てを担っています。
取材担当者(高橋)の感想
金丸社長の「滑り止め」という言葉の裏にある、学生に対する深い愛情と、長期的な視点での人材育成戦略に感銘を受けました。単に自社の利益を追求するだけでなく、若者が社会で成長するための最適な道を提示し、一度離れてもいつでも受け入れるという懐の深さは、企業が真に人を大切にするという理念を体現していると感じました。これは私たち20代にとって、キャリアを考える上で非常に勇気づけられるメッセージです。










