柳瀬株式会社 は1972年に織物業として創業し(コメント:「発足」→企業の開始を示す一般的表現「創業」への修正提案です)、1979年に研磨材製造へ事業転換しました。各種研磨材の製造・販売を主事業とし、「磨き」を通じて、工業用途の製品から一般消費者の生活用品、さらに美容関連の製品まで幅広く開発しています。本社は兵庫県丹波市に置き、経営理念は「お客様のためになる商品をつくり、お客様のためになる製品を紹介し、お客様と喜びを共有する」ことです。2014年にはベトナム工場(YANASE VIETNAM)を開設し、グローバル展開を進めています。今回は、「磨き」という一見地味ながらも奥深い領域を軸に、時代の変化を先取りして挑戦を続ける柳瀬株式会社の歩みと、世界を視野に入れたものづくりへの想いについて、代表取締役社長にじっくりとお話を伺いました。
<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>
【商社経験が築いた、日本独自のルートセールス改革】
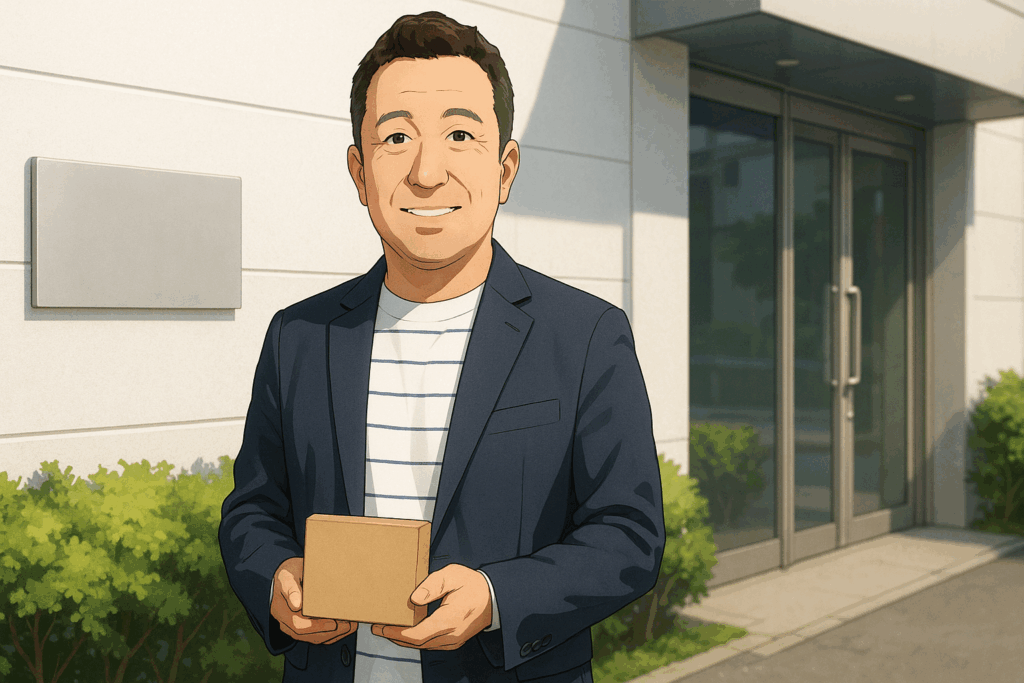
私は1972年生まれで、ちょうどその年に父が会社を創業しました。大学卒業後はすぐに家業に戻らず、父の会社と取引のあった商社で約7年間経験を積み、2001年に二代目として戻りました。商社での経験は自分にとって大きな財産になりました。先代(現会長)は物を作ることには長けていましたが、商売の方法や販売戦略は得意ではありませんでした。入社時、当時の売り方では「絶対ダメだ、伸びない」と直感し、販売体制の改革に着手しました。
特に注力したのは、商社を介して地域の販売店に卸し、それが工場へと流れるという、日本独特のルートセールスの整理・再設計です。この商流のルールとプロセスをきっちり整えたことが、製造はできても販売が不得手だった当社の基礎を立て直す重要な一歩になりました。海外ではメーカーが直接ユーザーやディーラーへ販売するなど自由度が高い一方で、日本では良くも悪くも、こうした商流のルールが厳格に守られる文化があります。
取材担当者(高橋)の感想
当時の状況は「作れば売れる時代」の終わりで、販売の仕組みを根本から変える必要があったことが伝わってきます。商社での7年の経験が、既存の体制を「絶対ダメだ」と判断し、ルートセールスを整理する土台になった点は、就活生にとって「最初に外部で経験を積む重要性」を示す好例だと感じました。

【ゼロからの販路開拓とグローバル生産体制への移行】
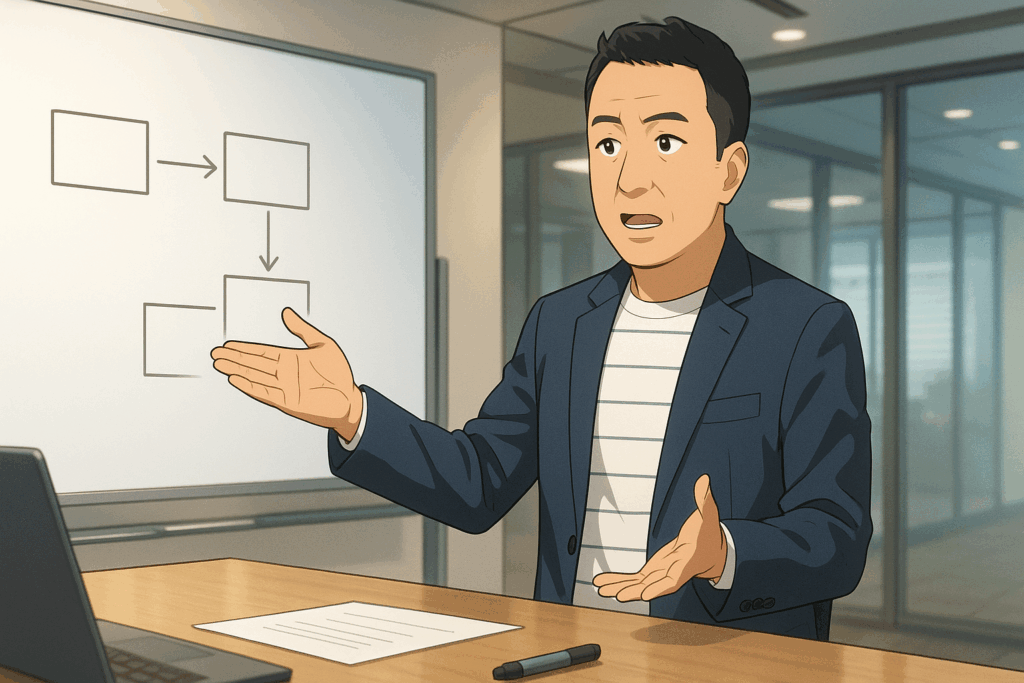
会社に戻った当時、正直に申し上げて売上はほとんどありませんでした。そこでまず、ホームセンターでの店頭販売や海外工場への輸出など、存在しなかった販路を一から構築することに注力しました。店頭販路に強い商社や、工業製品の輸出を手がける商社に営業をかけ、実績を積み上げていきました。
販路拡大の一例として、美容部門『Rooro』の販売強化があります。プロネイリスト向け店舗に加え、ドン・キホーテやPLAZAといったバラエティショップ、ドラッグストアなど、多様なチャネルで取り扱いを広げました。
また、販路を広げるだけでなく、それぞれのチャネルに適した商品仕様へと最適化してきました。同じ研磨技術でも、工場の溶接後研磨に用いる工業製品、一般消費者のかかとの角質ケア用品、爪の形を整えるやすりでは、用途も形状もまったく異なります。そうした需要に合わせ、一つひとつ商品開発を進めてきました。
製造拠点については、かつては日本のみでしたが、現在は中国とベトナム・ホーチミンにも工場を運営し、製造の約半分は海外生産です。販売の約90%は国内ですが、製造面ではグローバル化を大きく進めています。
取材担当者(高橋)の感想
ゼロから販路を築くプロセスは苛烈な挑戦に映りました。工業イメージの強い分野から美容『Rooro』へと射程を広げ、プロ向けから一般のバラエティショップまでチャネルを拡張した柔軟性に、挑戦の文化を感じます。国内販売中心でも、海外拠点を持つことでコストと供給安定を両立させている点に、組織力の高さが表れていると思いました。

日本の衰退への対応策:東南アジアへのシフトとM&A戦略
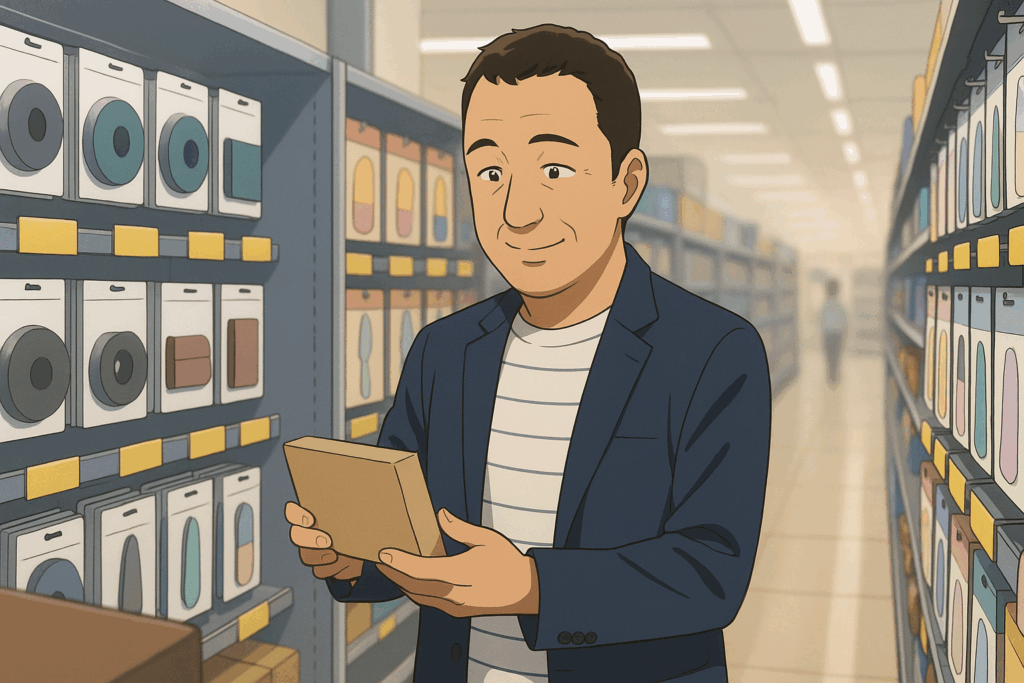
日本はいま、衰退局面に入っていると感じています。これにどう対応するかを考えなければなりません。特に深刻なのが少子化です。日本の人口分布が60~70代を中心とする逆三角形である一方、ベトナムのような国は若年層が厚い構成です。若い層は住宅・自動車・衣料などへの需要が旺盛で、消費が動きます。しかし、高齢化が進む日本では、こうした需要が伸びにくく、経済が回りにくくなります。
このため当社は、ベトナム工場を軸に東南アジアへの販路を加速して強化する必要があります。税制や物流面のハードルが比較的低い東南アジアで、人口が増える市場へ営業資源を集中する戦略です。ベトナムで生産した製品を、ベトナムやインドネシアなど域内市場へ展開する比率を高めていきます。
また、円安の影響も大きいです。現状の為替水準では、日本で働く外国人労働者のメリットが薄れ、韓国・中国・台湾など他国を選好する動きも出ます。加えて、日本の工場では熟練人材が定年を迎える時期にあり、引退する人数に対して若手の新規参入が明らかに不足しています。国内工場の現状維持は、今後いっそう難しくなるのが実情です。生き残るには、M&Aや多角化によって事業基盤を安定させることも重要です。実際、2021年には香川県に本社を置く超硬合金チップソーメーカーを買収し、子会社化しました。こうした取り組みを通じて、組織力を高めていきます。
取材担当者(高橋)の感想
少子高齢化が需要構造に与える影響を、ベトナムとの人口構成比較で具体化されていて納得感がありました。需要の厚い東南アジアに軸足を移す論理は明快です。円安がもたらす人材確保の難しさや、熟練人材の引退と若手不足という構造問題に対し、M&Aと海外展開を組み合わせる戦略は、現実的な打ち手だと感じました。

人材育成と20代への提言:「地域や国にこだわらない」生き方
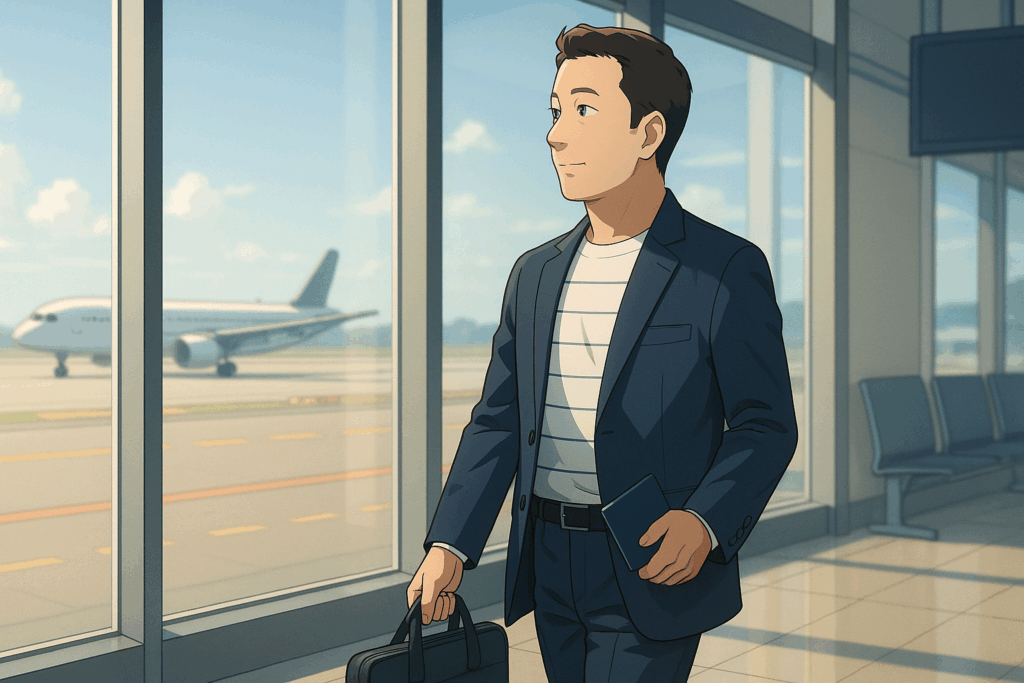
海外の採用文化は日本と大きく異なります。たとえばベトナムでは、給与水準が同程度なら人は集まりますが、わずかに低いだけでもすぐ転職するなど、会社への帰属意識は薄いです。そのため、標準的な給与体系だけでは不十分で、インセンティブが不可欠です。
個人の能力・スキルによって給与には大きな差がつきます。日本語・英語・簿記・PCスキルなどの有無で、待遇はまったく異なります。ベトナムの一般作業者の月給はおよそ5万円、マネージャークラスは15万円程度になります。日本は平等志向が強く差をつけにくいですが、能力差に応じた大きな賃金差は、海外では「夢がある」と受け止められやすいと感じます。
最後に、若い世代へのメッセージとして、地域や国にこだわらずに生きる重要性を強調したいです。「この地域が好きだから転勤はしたくない」という考えは理解できますが、特定の地域に縛られることは、自ら可能性を狭めることにもつながります。どこでも挑戦できる柔軟さを持てば、掴めるチャンスは増えます。
ウェブで人と情報がつながり、世界が近くなった現在は、フットワークの軽さが鍵です。ベトナムやアメリカへの出張を、奈良に遊びに行くくらいの感覚でどこへでも動けるくらいでないと、厳しくなってくるでしょう。かつての内向き志向から脱し、海外へ果敢に出ていく姿勢が欠かせません。日本国内だけで完結させようとする発想では、今後は難しくなると考えます。
取材担当者(高橋)の感想
ベトナムでの採用ではインセンティブ設計が肝心で、スキルに応じた賃金差が「夢」につながるという視点が印象的でした。20代への「地域や国にこだわらない生き方」というメッセージは、フットワーク軽く世界に出ていく重要性を背中押ししてくれると感じます。日本の構造的課題を前に、視野を世界に広げて動くことの価値を強く実感しました。










