オリエンタルシューズ株式会社は、創業者が祖父である同族経営の靴製造メーカーです。現在も奈良の地に工場を持ち、国内での靴づくりを続けています。
現代における靴の役割は、単なる生活必需品や歩くための道具ではなく、個性を表現するファッションアイテムです。靴はお客様が「なりたい自分に近づける」存在であり、履くだけで気持ちが高揚し、暮らしに彩りを添えるものでありたいと考えています。オリエンタルシューズの靴が、お客様の自分らしさを表現するツールになることを願っています。
<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>
【4代目としてのキャリアと経営への使命感】
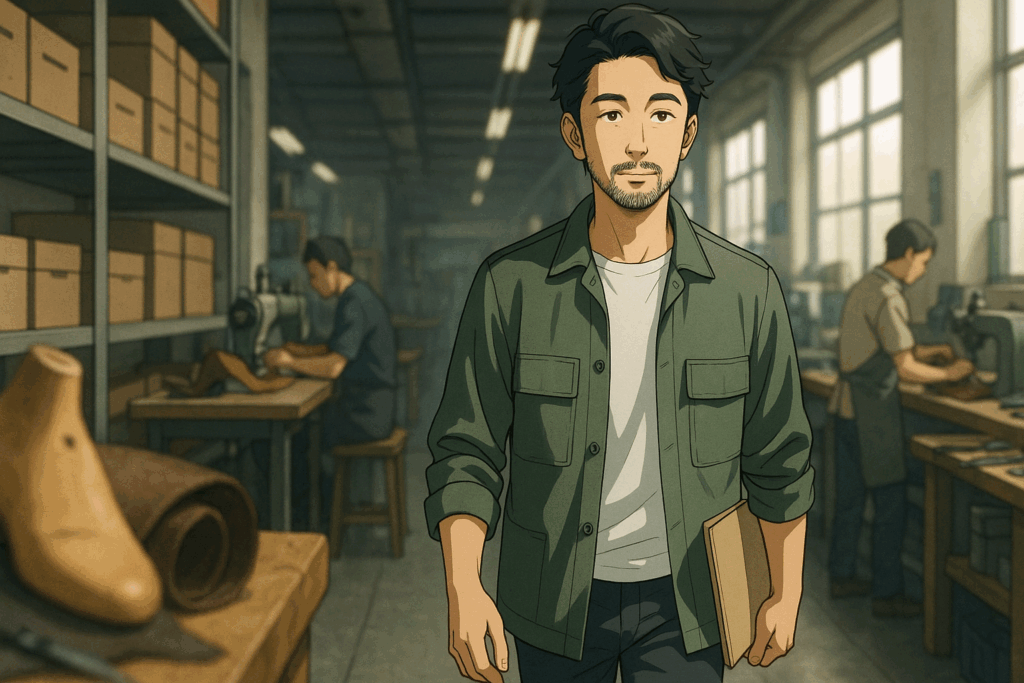
私は大学卒業後、3年間は別の会社に就職しましたが、大卒4年目からオリエンタルシューズに戻り、現在まで約13年が経ちました。入社当初は企画室に所属し、靴のサンプル制作などを担当しました。その後、2年目以降は営業部に異動し、約12年間、営業担当や営業部長として業務に携わってきました。そして、2025年7月に社長に就任しました。
同族経営の会社に入った日から、「会社を良くしたい」という強い気持ちと、「どうしたら良くなるか」という課題意識や危機感を常に持ち続けていました。目に見える大きな実績は自分から言うほどないと感じていますが、社内の仕組みや細部の改善を継続的に進めてきました。社長就任については、同族経営の性質上、「良い仕事をしたからステップアップして社長になった」というより、後継者として適切なタイミングで就任するという計画に従ったものです。
中小企業の同族経営は多く存在しますが、後継者には、無条件に創業者が築き、先代が受け継いできたものへの使命感や責任感が伴うと考えています。これは、会社を投げ出さない覚悟にもつながります。しかし、同族経営には、候補者が限定されるため、外部から優秀な人材を選ぶことができないというデメリットもあります。私は、奈良の地に工場を残していきたいという強い思いを持っており、その伝統的な技術やこだわりは守りつつも、広め方や経営の在り方を時代に応じて変えていきたいと考えています。
取材担当者(高橋)の感想
松本様が社長就任までに企画、営業と社内の幅広い分野を経験されていることに感銘を受けました。特に、同族経営という背景がありながらも、「会社を良くしたい」という根源的な使命感を持ち続け、細かいところから改善を積み重ねてきた姿勢は、若手社会人にとって大いに学びになる点だと感じました。また、同族経営では、家族だからこそ会社の歴史や先代の思いを知り、使命感を持って受け継ぐという側面があるというお話は、日本の伝統的な製造業の文化を理解するうえで非常に興味深かったです。

【製造メーカーにおける革新的なブランディング戦略】
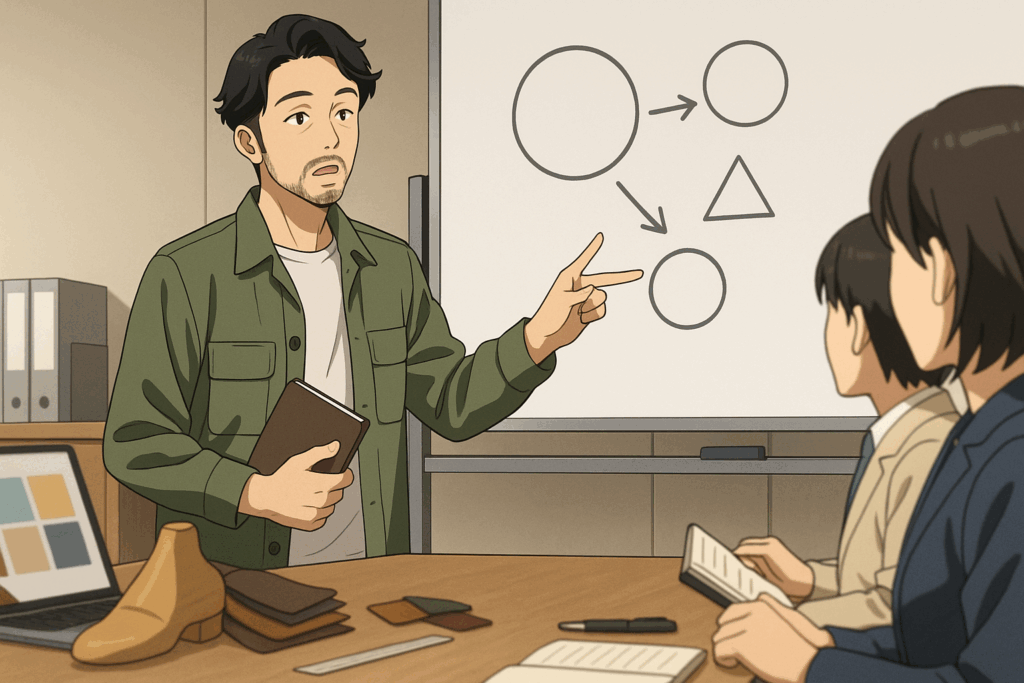
現在、社内で私が最も長けていると感じ、先頭に立って取り組んでいる部分は、自社ブランドのブランディングをいかに進めるかという点です。私が会社に入った当時、社内にはブランディングの進め方に関する枠組みがありませんでした。そのため、まず私自身でブランディングについて学び、その枠組みを社内に構築しました。
従来の製造メーカーのやり方は、「良い素材やアイデアを見つけ、靴をサンプルで作ってから、後からブランド名を決める」という流れが一般的でした。しかし、ブランディングとして正しい姿は、「どのような思いでブランドを立ち上げ、ユーザーにどう使ってもらいたいかというコンセプトを、背骨のような骨組みにして、そこから商品が出来上がってくる」ことだと考えています。具体的には、社員が立ち戻るべき「バイブル」となる書籍を選定し、ブランドを作る際に考えるべきポイントや、困った時に立ち戻れる枠組みを社内に整えました。
日本の製造メーカーの多くは、「物づくりに注力しすぎて、売ることや見せること(ブランディング)が苦手」という共通の弱みを持っています。高品質な靴を作ることに目いっぱいになり、Webサイトやビジュアルの質が、市場のユーザーの基準に達していないケースが多いのです。私たちは、製造メーカー基準ではなく、ユーザー目線で選ばれるために、「いい感じのブランド」、つまりユーザーが直感的に良いと感じるクオリティのWebサイトやビジュアルを作らなければならないという意識を持って取り組んでいます。
取材担当者(高橋)の感想
製造メーカーが持つ「作ることに注力するあまり、見せること(ブランディング)が手薄になる」という業界全体の弱みについて、松本様から伺い、地元の製造メーカーの状況と重ねて深く納得しました。古い企業ほど、ホームページが古かったり、デジタルでの発信が遅れていたりする傾向は確かに感じられます。松本様が、製造メーカーの常識ではなく、ユーザー目線で「いい感じ」のブランドを目指しているという点は、伝統ある企業が現代で生き残るための「革新」そのものだと感じました。

【市場課題への挑戦:「革靴を日常に」という逆張りのコンセプト】
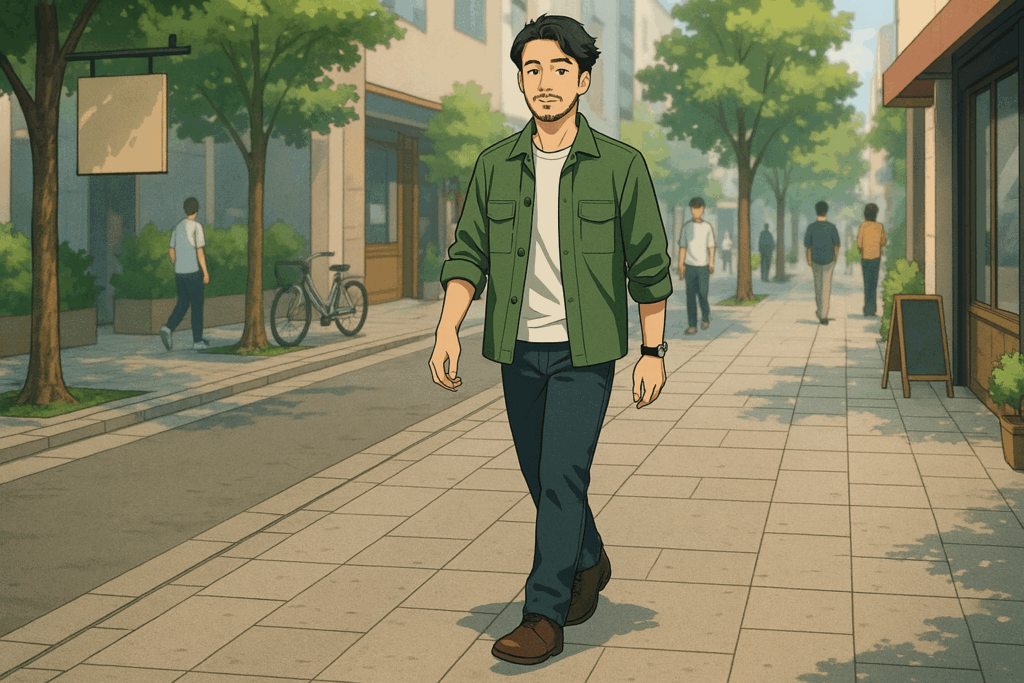
私が社長として直面する業界全体の課題は深刻です。まず、人口が減っているため、靴の市場規模そのものが縮小しています。加えて、洋服のカジュアル化が進み、スーツを着る機会が減ったことや、リモートワークの普及により、日常的に革靴を履く人が減り、スニーカーに押されている状況があります。
革靴が必要とされるのは、冠婚葬祭などの一部のシーンに限定されつつあり、日常的な需要が減っているのが現状です。革靴の市場規模は、日常的な需要に大きく依存しているため、スーツが必要な仕事でもカジュアル化が進むと、足元がスニーカーになってしまい、革靴業界全体が大きな危機に直面しています。
この危機感に対し、私たちが手がけている自社ブランド「オリエンタル」を通じて対抗策を打ち出しています。オリエンタルのブランドコンセプトは、「革靴を日常に」です。履きやすくて良いスニーカーがある中でも、革靴の魅力が薄れていくのはもったいないと思っています。その魅力を普及し、より日常的に履いてもらえるようにしたいという強い思いが、このコンセプトには込められています。私たちは、市場が縮小していくという課題感に真っ向から向き合い、このコンセプトを解決策として位置づけています。
取材担当者(高橋)の感想
革靴を履く人が減っているというお話は、私自身もプライベートで革靴を履く機会が少ないため、意外なようで納得できる部分がありました。厳しい市場環境下で、既存の「スーツに合わせる」という固定概念を超え、「革靴を日常に」というコンセプトを掲げ、日常使いを積極的に提案している姿勢は、挑戦的だと感じます。このブランドコンセプトは、若者に対しても革靴の新たな魅力を伝えるきっかけになるのではないかと思いました。

【顧客の視点を優先するコミュニケーション戦略の壁】
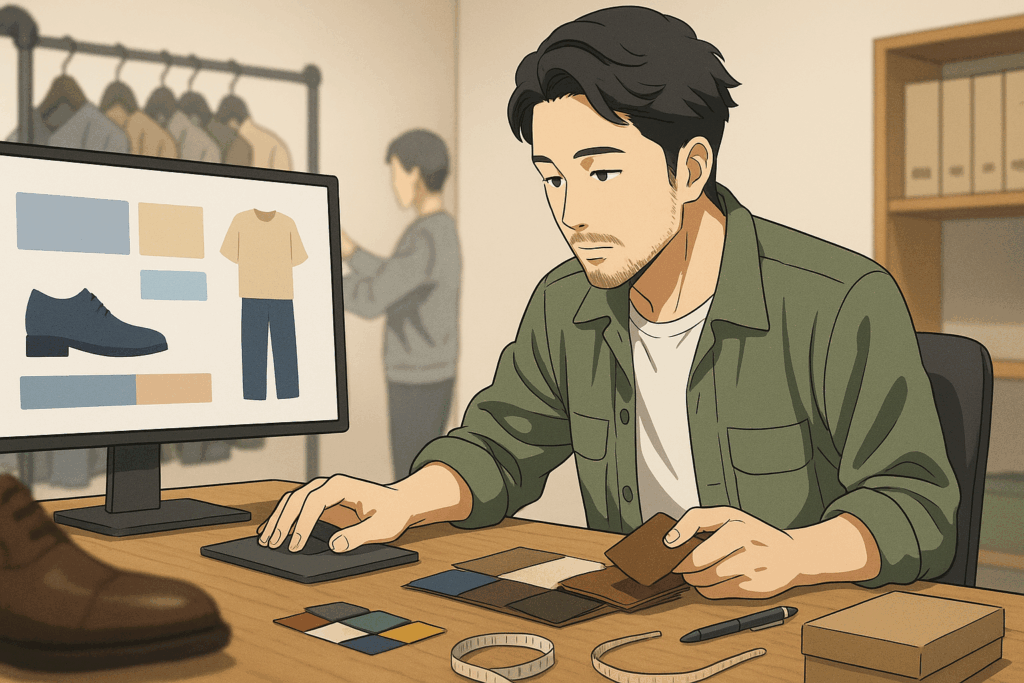
ブランディング活動において、私が最も難しさを感じ、課題としているのが「一言で語らずとも伝える」コミュニケーションです。コンセプトや伝えたい思いはあるものの、それを商品と共に前面に出しすぎると、お客様にとって押し付けがましく感じられてしまう可能性があると考えています。
お客様が商品を選ぶ際、最初に考えるのは「価格はどうか」「自分のスタイルに合うか」「履きやすいか」といった、ユーザー自身の欲求や便益です。作り手の「思い」や「熱意」を押し出すよりも、まず商品として「いい感じだね」と感じてもらうことが重要であるという哲学を持っています。思いは、お客様にご購入いただいた後に、自然と伝わればよいと考えています。
そのため、Webサイト上での表現においては、この思いをあえて内に控えて、「さりげなく伝える」工夫をしています。具体的には、商品の良さや便益を、ビジュアルや雰囲気を通じて感じてもらうことに注力しています。例えば、靴が服と合わさって「すごくいい感じ」に見える写真や、素材の良さが伝わる表現などです。これは、チラシのような即物的な分かりやすさを重視せず、ブランドとしての質感の高い見せ方をすることにつながります。高価格帯の商品を持つブランドとしての整合性を保つためにも、押し付けがましくならないように抑えることが、現在のブランディングにおける壁であり、難しい点だと感じています。
取材担当者(高橋)の感想
「押し付けがましくならないように抑える」という戦略は、インパクトの強い言葉や表現が溢れる現代のデジタルコミュニケーションにおいて、非常に洗練されたアプローチだと感じました。アート作品のように、作り手の思いを直接説明するのではなく、見る人に感じ取ってもらうという考え方は、ユーザーが能動的にブランドを理解するきっかけとなり、深く心に残るはずです。製造メーカーの弱点である「見せること」の克服において、単に綺麗にするだけでなく、メッセージの伝え方まで戦略的にデザインされていることに、松本様のブランディング能力の高さを感じました。

【未来の若者に期待すること:「自分基準を捨てる」両方のスキル】
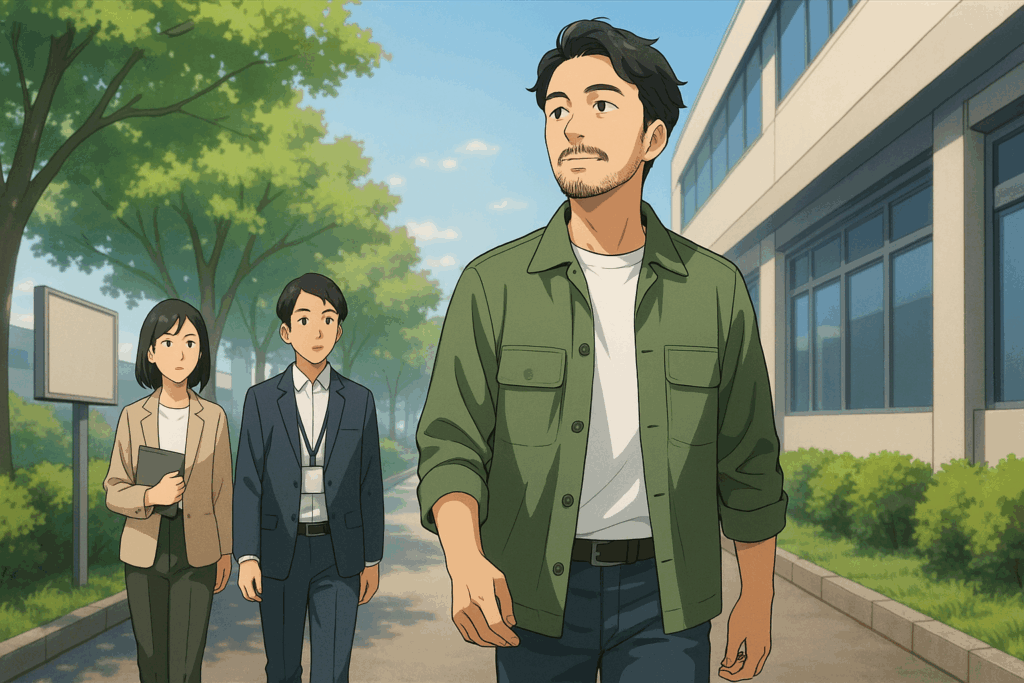
現代は、自分の基準で物を選んだり、自分がどれだけ豊かになるかを考えられる、非常に恵まれた時代だと思います。自分の価値観や欲求が尊重されることは大変良いことですが、企業という組織で働く上では、「自分基準を捨てる」ことも重要だと考えています。
自分基準で全てを進めたいのであれば、起業したり、個人事業主になったりすることが選択肢としてあります。多くの人は企業で働くことを選ぶ以上、組織に属する一員として、自己の基準をある程度抑制し、組織の目標やルールに合わせるスキルが求められます。組織の目標と個人の目標が一致しない場合でも、組織で成果を出すためには、自己を律する必要があります。
学生時代には必要なかったかもしれない「自分を捨てる」という行為は、社会人になったら持ち合わせた方が良いスキルだと考えています。組織で働くことと、個人の創造性ややりたいことを追求することの「両方のスキル」を兼ね備えることが、組織の中で成果を出し、長期的に活躍するために重要であると期待しています。
取材担当者(高橋)の感想
「自分基準を捨てる」という言葉は、現代の若者が重視する自己実現とは一見逆のように聞こえますが、企業で働く上での現実的なアドバイスだと感じました。私自身、個人の価値観を追求しがちなのですが、組織という枠組みの中で、より大きな目標を達成するためには、自分を律し、周囲と協調する能力、つまり両方のスキルが必要だという松本様のお話は、これから社会に出る学生にとって、深く心に留めておくべき「学び」だと感じました。










