有限会社しら河は、名古屋名物である櫃まぶしを中心としたうなぎ料理の専門店です。会社のルーツは古く、昭和23年(1948年)に公設市場で天麩羅屋として開業し、昭和28年からは「大森料理店」として長年にわたり和食を提供してきました。平成元年(1989年)11月に有限会社しら河を設立し、うなぎ料理、特に櫃まぶしに事業を専門化しています。現在の代表取締役である森田社長は、平成27年(2015年)6月に就任し、以来約10年間、経営を担っています。今回は、名古屋の食文化を体現する櫃まぶしへのこだわりと、しら河のこれからの展望について、代表取締役社長・森田様にじっくりとお話を伺いました。
<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>
【構造改革とデジタル化による「働きやすさ」の追求】
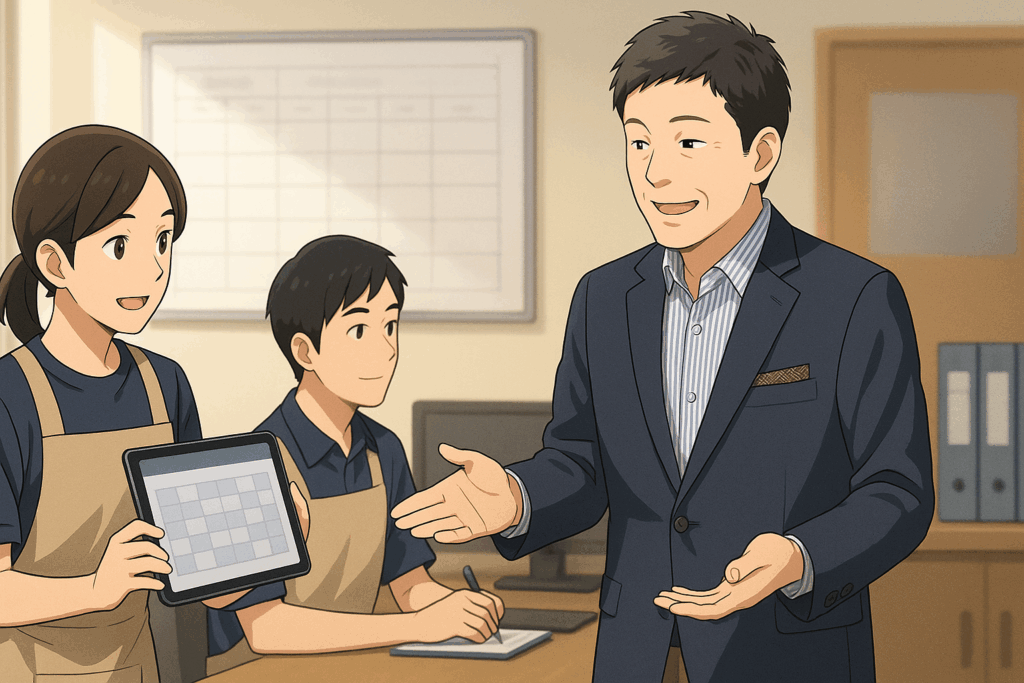
私が社長に就任してから今年でちょうど10年目になります。この期間で変革を試みたのは、まだまだ足りない部分は多いものの、やはり従業員の働く環境です。事業を持続的に続けるために、定休日を作ったり、営業時間を短くしたりといった構造的な改革を進めてきました。
また、システム導入も大きな変革の一つです。今でこそ当たり前ですが、電子の予約台帳などを導入しました。このデジタル化を本格的に導入したきっかけは、元々この西区の土地にあった料亭部門が、名古屋能楽堂に移転したことです。
以前は、料亭に併設していた事務所の事務スタッフが電話対応をしていましたが、移転によって物理的に事務所が離れてしまいました。移転先に事務所スペースを作ることはできなかったため、「電子の予約であれば、どこにいても状況を確認できる」という利点から導入を決めました。この物理的な変化を契機に、予約管理システムを完全にデジタルへ移行し、今は全店舗で電子予約台帳を導入しています。これにより、全員が予約状況を確認できるようになりました。
取材担当者(高橋)の感想
森田社長が、就任後すぐに定休日設定や営業時間短縮といった、従業員の働き方に関わる環境改善に着手された点は、経営者が「人」を大切にしている証だと感じました。特に老舗企業にとって、定休日を設けることは簡単な決断ではないはずです。また、料亭の移転という物理的な課題に対し、一気に予約台帳の電子化に踏み切ったスピード感と決断力は、組織を大きく動かす上で非常に重要だと学びになりました。

【未来の顧客(20代)を獲得するための戦略的挑戦】
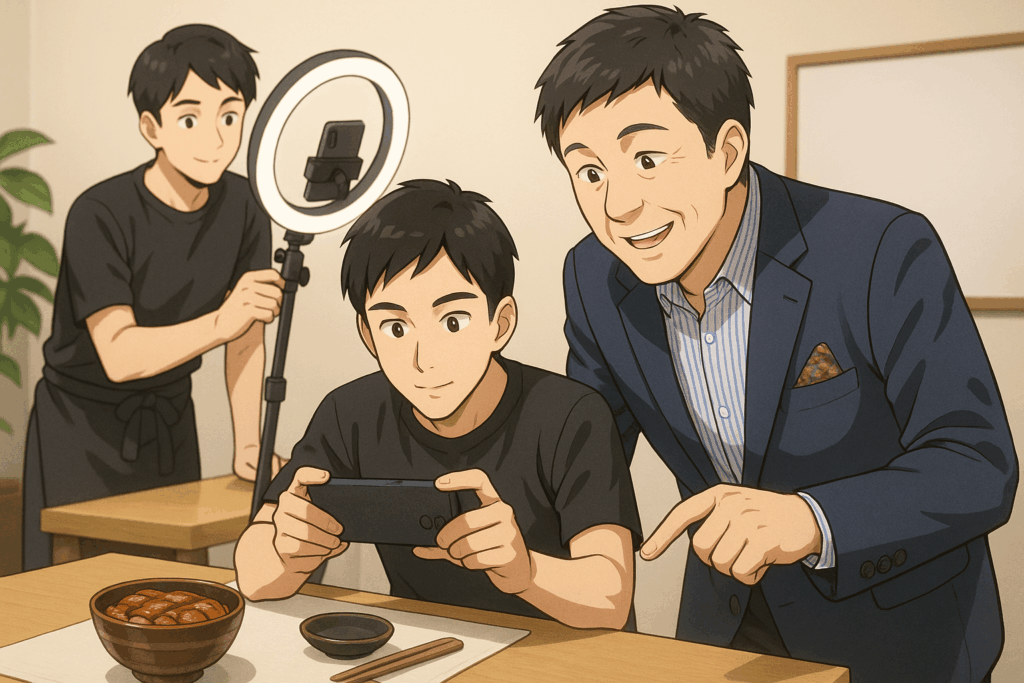
当社は現在、ポイントカードシステムを導入しており、会員様は約2万5,000名いらっしゃいます。会員様の年齢分布を確認した時、大きな課題が見えました。40代、50代、60代、70代のお客様は比較的均等にいらっしゃるのですが、20代のポイントカード会員様がほとんどいなかったのです。
もちろん、うなぎ料理は価格帯から見ても、若い方が「何かきっかけがないと難しい」というのは認識しています。しかし、彼らは「これから先のお客様」、未来の顧客ですから、若い方々にもお客様になっていただけるように働きかけをすべきだと考えました。
特に、旅行でたまたま来ていただくお客様だけでなく、日頃からご利用いただく常連さんになっていただきたいという思いがあります。ポイントカードの会員様は、日頃からご利用いただく方々だと考えているため、地元の方も含め、若い世代のお客様にも複数回来ていただけるように努めています。そういった方々へアプローチするため、デジタル分野に詳しい社員が中心となり、公式LINEやInstagramなどの情報発信もしてくれています。
取材担当者(高橋)の感想
私自身、学生時代に初めてひつまぶしを食べた時の感動を覚えています。価格は張りますが、それを超える価値があると感じました。森田社長が、鰻の価格が若い世代のハードルになっていることを認識しつつも、将来を見据えて20代を「未来のお客様」として明確にターゲティングしていることに感銘を受けました。また、その戦略実行において、若手社員のデジタル分野の強みを信頼し、実際に運用チームを任せている姿勢は、私たち若者が会社に貢献できる可能性を示してくれていると感じました。

【危機を乗り越えたテイクアウト強化とプロフェッショナルな採用戦略】
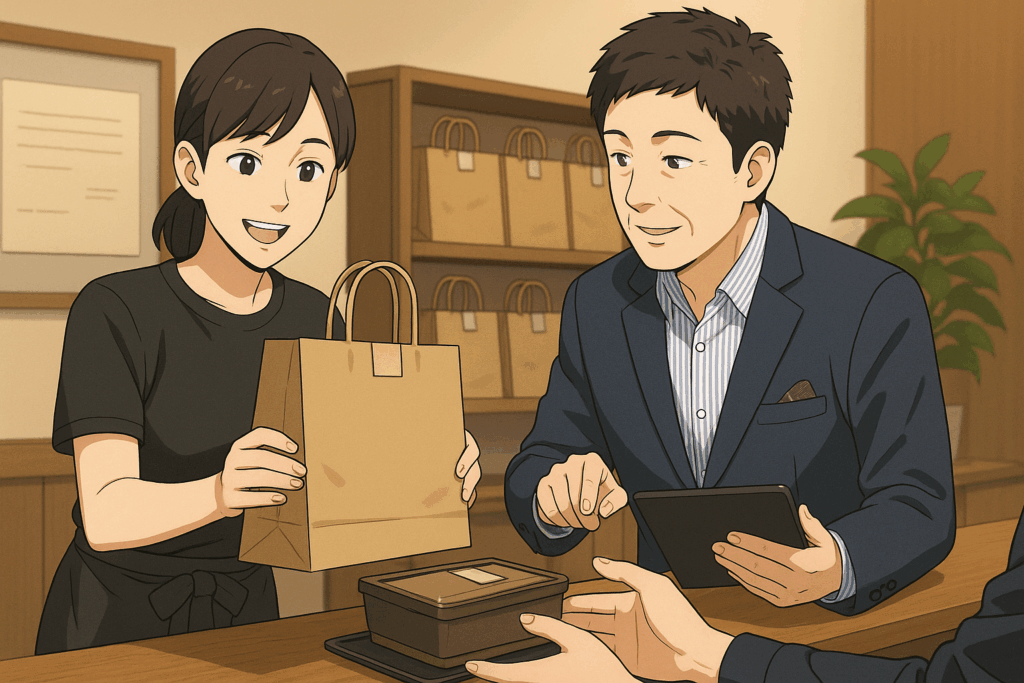
コロナ禍は2020年2月か3月頃から始まりました。最初は戸惑いましたが、私たちは元々テイクアウト(持ち帰り)に対応していたので、そこに力を入れることで危機を乗り切ることができました。
普段はご来店いただくお客様が8割、テイクアウトが2割ぐらいですが、コロナ中はこれが逆転し、テイクアウトが6割を占める時期もありました。また、当社の店長は、名古屋でUber Eatsが普及し始めた頃にいち早く営業に来ていただいていたこともあり、結構前から一部の店舗でUber Eatsを導入していました。そのおかげで、コロナ禍では電話注文とUber Eatsの両方で対応できたのは強みとなりました。
現在、お客様はたくさん来ていただいていますが、日本全体の問題である人手不足はやはり深刻です。採用難を打破するため、私たちは非常に良いコンサルティング会社と巡り合うことができました。その会社にお願いするまでは、費用をたくさんかけて求人媒体に載せても、応募が全く集まらない状況でした。闇雲に多額の費用をかけても人が集まるとは限らないという現実があったのです。しかし、プロのコンサルタントにお願いしてからは、状況がかなり改善しました。
プロの方は、媒体の精査や、オプションの取捨選択、そしてIndeedなどの求人検索エンジンのトレンドを踏まえて、応募が集まりやすいように原稿の修正などを常に行ってくれています。闇雲に費用をかけるのではなく、専門家の知見を活用した結果、特にアルバイトの採用において、以前より採用コストを抑えつつ、必要な人員を確保できています。アルバイトの応募は多すぎて、原稿掲載を中止することもあるほどです。正社員の採用については、このコンサルティング会社からの応募に加え、人材紹介会社を活用して確保しています。
取材担当者(高橋)の感想
コロナ禍でのテイクアウト比率の逆転現象や、Uber Eatsへの初期からの取り組みは、危機下における迅速な対応能力を示すものだと感じました。また、採用活動においても、従来のやり方で費用対効果が低いと感じるや否や、すぐにプロフェッショナルなコンサルティングを取り入れた決断力に感銘を受けました。これは、事業運営に必要なリソースを確保するために、プロに任せるという経営判断の重要性を教えてくれました。

【リスク分散を目指す、従業員総動員型の新業態開発】
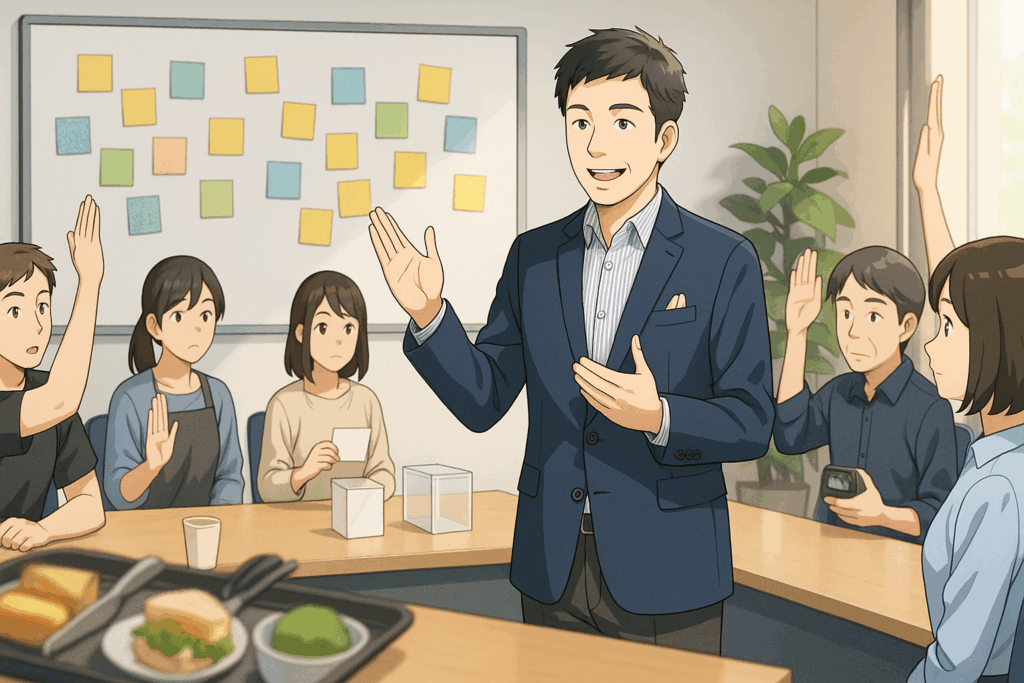
当社は元々、和食の料亭から始まり、その後うなぎの部門ができました。しかし、先般(令和3年3月)に料亭部門を閉店してしまったので、今はうなぎだけの「一本足打法」の状態になっています。この一本足打法は、リスク分散の観点から課題だと認識しています。例えば、牛肉のBSE問題があったように、もしうなぎに何か起こってしまったら、事業に大きな影響が出てしまいます。そのため、私たちは、うなぎを全く使わない新しい業態を育てていきたいと考えています。
この新規事業開発は、トップダウンではなく、正社員、パート社員を含めた全従業員を巻き込んだゼロベースで取り組んでいます。新しい店舗の「店名」「コンセプト」「メイン商品」などについてアンケートを取り、皆さんからいただいた意見の中から検討していく予定です。従業員が提出しやすいよう、コンセプトかメイン商品のどちらかだけは書いて提出してもらうようにしています。全社員の力を集めて、新しい挑戦を成功させたいと思っています。
若い世代の方で飲食業界を目指す方へのアドバイスとしては、「好き」という気持ちが大事だと思います。やはり、料理が好きな子は仕事の覚えが早いですし、成長も早い傾向があります。休みの日に自主的に市場に魚を仕入れに行って練習している社員もいます。興味を持つこと、好きなことが根本にある方が入ってきてくれると、会社としてもより良いですね。また、今の20代の強みとして、デジタル分野での貢献があります。当社のInstagramチームも若い世代を中心にやってもらっています。得意な部分で、会社に貢献してくれる機会もあると思います。
取材担当者(高橋)の感想
料亭の閉店を経て、鰻一本足打法のリスクを真剣に考え、鰻を使わない新業態をゼロベースで開発するという決断に、強い経営意思を感じました。特に、その新業態のアイデアを従業員全員からのアンケートで募るという手法は、参加意識を高め、新しい挑戦へのエネルギーを生み出す素晴らしい方法だと感じました。また、私たち(20代)が持つデジタルな強みを会社の成長に活かせるという具体的なアドバイスは、将来飲食業界を目指す学生にとって大きなヒントとなるでしょう。










