株式会社西洋軒は、滋賀県大津市・坂本の地で大正12年(1923年)に創業した老舗のパン工房です。創業以来、地元に根ざしたパン・洋菓子の製造販売を続け、現在は本店(大津市坂本4丁目)を拠点に「無添加」と「地産地消」へのこだわりで、焼き立ての美味しさと安心を届けています。
学校給食用パンの製造でも地域に貢献しており、1989年から大津・草津周辺の学校へ提供を拡大。累計3,000万個超のコッペパンを届けてきました。創業100年の節目となった2023年には、記念企画として給食用コッペパンの一般販売や、地元漬物店と共同開発した新商品「薫るたくマヨパン」を発表するなど、伝統を守りながら新しい挑戦を続けています。
看板商品の一つ「石積みのパン」は、坂本に残る穴太積みの石垣に着想を得て、レーズン(黒石)とくるみ(白石)で“石積み”を表現した地域発の名物。観光客の土産としても人気で、西洋軒の“地域とともに歩むパンづくり”を象徴しています。また、同店は「安心安全を第一のモットー」として幅広い定番からハード系まで多彩な商品を揃えています。創業100年を超えた今も、4代目・山岡忠樹社長のもと、日々の食卓を支える“まちのパン屋”として、そして地域の食文化を磨き続ける挑戦者として歩みを進めています。
<聞き手=石嵜渉(学生団体GOAT編集部)>
【山岡様の今までの経緯・背景】
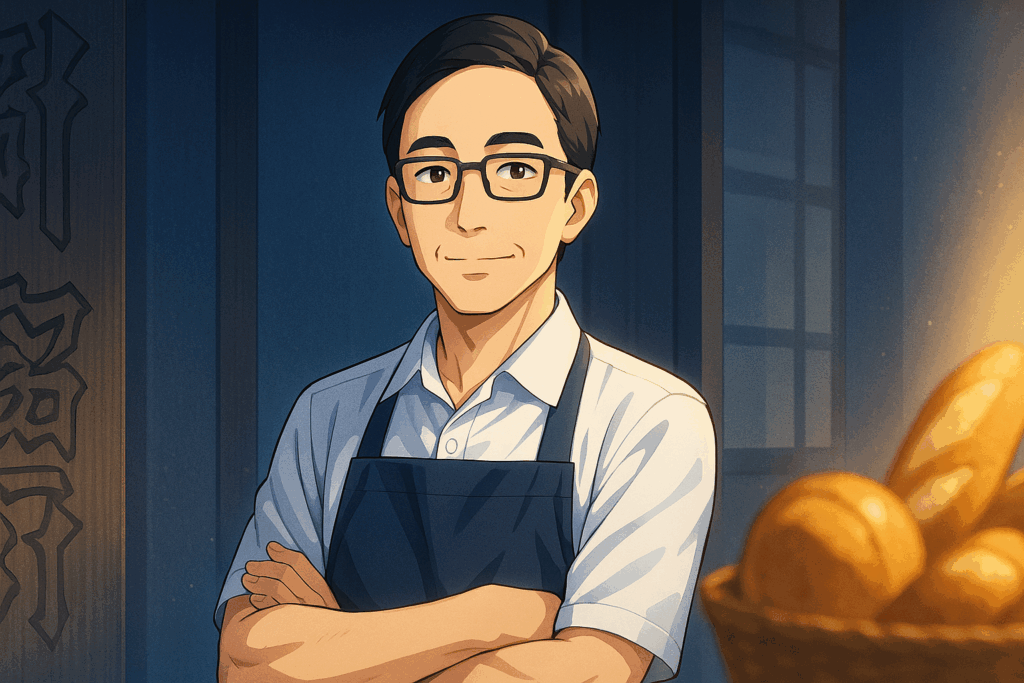
私はこの会社の4代目社長を務めています。創業は1923年、祖父の山岡延治郎が始めたのですが、今年で102年目を迎えることになります。祖父は元々京都にルーツがあり、戦前の苦しい時代に比叡山延暦寺で修行をし、「山岡」という名をいただいたと聞いています。その後、修行を辞めて坂本の町で商売を始めました。何をしようかと考えた時に、一族である京都にあった同じ名前の「西洋軒」というパン屋さんで修行し、横浜の横須賀でドイツパンの修行もして、その技術を持ち帰り京都西洋軒ののれん分けという形で「西洋軒」という屋号でパン屋を始めたのです。
父の姿は幼稚園の頃に見たきりで、大学に入るまではほとんど会うこともありませんでした。家に帰ってくる時間が短すぎて、生活時間も全く違ったからです。銀行で働き始めてすぐに、父から電話があり、「心臓が駄目になって仕事が続けられないから帰ってきてくれないか」と頼まれました。働き始めたばかりだったので悩みましたが、「しょうがない」と思って実家に戻りました。
しかし、戻ってきた会社は「何じゃこりゃ」という状態でした。社員は上から言われたことしかせず、完全なるトップダウン型の会社で、自主性に欠ける状況でした。当時の仕事は、学校給食が約7割を占め、他に店舗販売(当時4店舗)と、わずかな卸売事業がありました。蓋を開けてみれば、利益の薄い公共事業と、採算が合っているか分からない4店舗、そして卸売ももう利益が出ていない状態でした。
正直、「これ、ちゃんと利益出てるの?人件費考えてる?」というレベルで、そこから全てを立て直す必要がありました。「ここからどうしよう」と途方に暮れましたが、毎年「修正、修正、修正」の繰り返しで、気が付けば14年が経ちました。父が3年前に亡くなってからは、本当に自分の自由が効くようになり、会社の改革を本格的に進められるようになりました。私が社長になったのは、ある日突然、登記が変わっていたという、まさに父の「パワハラ」でしたね。
取材担当者(石嵜)の感想
山岡社長が、祖父の代からの歴史ある会社を継ぎ、銀行員から一転して家業を立て直すまでの壮絶な経験に感銘を受けました。特に、先代の社長が突然の体調不良で引退し、準備もないまま自身が社長に就任したエピソードは、その後の経営改革への熱意の源泉だと感じました。ご自身の「しんどいのが嫌」という言葉とは裏腹に、会社のために泥臭く、しかし着実に改革を進めてこられた行動力と覚悟は、まさにロールモデルとなるべき姿だと思います。

【株式会社西洋軒の事業・業界について】
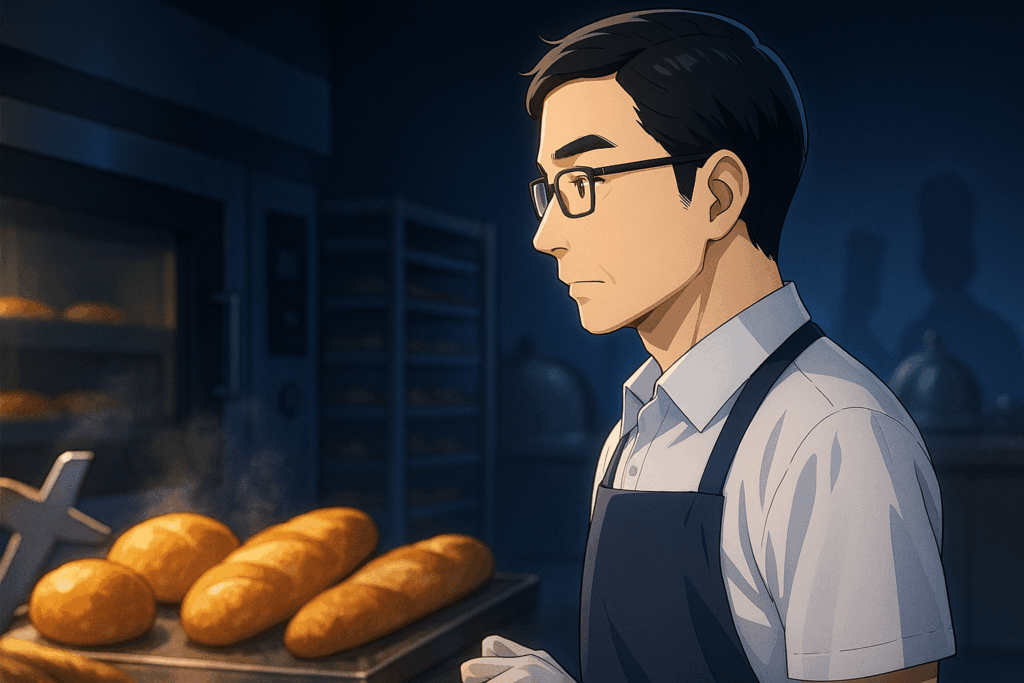
近年、特にここ2、3年はコロナ禍ということもあり、既事業の在り方を見つめなおす時期になりました。その中で、採算の合わない仕事はどんなに長い付き合いでも全て切ってきました。後ろ指を刺されたり、わけのわからない噂も流されましたが、構いませんでした。仕事を減らしたことで、従業員からは「この会社大丈夫?」と心配されましたし、ベテランや中堅社員の中には、結局辞めていった人もいました。なんやかんやで、本社工場にいた約25人の従業員が、最終的には13人にまで減りました。
私はそれまでほとんど事務方の仕事をしていましたが、いざ現場を見てみると、セクションごとに仕事を分担していたため、一から十まで状況を把握・管理できる「職人」と呼べる人がいないことに気づきました。そこから現場にも入り、一人で失敗しながらも仕事を覚えていきました。これは、残っている職人たちに舐められないためでもあります。幸い、意識だけでなく技術も伴ってきたので、今はそこからさらに組織を構成していく段階にあります。現在は、今はどこをどう伸ばし、どのような仕事を受けていくかを同時並行で考えています。
仕事の内容もガラッと変わりました。ホームページを見ると、直営の販売店舗やオンラインショップといった消費者向け事業が強いイメージがあるかもしれませんが、オンラインショップは認知度も低く、魅力ある商品展開ができなかったため、ほとんど動いていません。店舗も2店舗しかなく、ちょうど今月末で唯一の支店も閉めることになります。集約化を進めているため、現在はほぼOEM(他社ブランドの製品を製造する受託生産)がメインの事業になっています。表には出ませんが、皆が「しんどいな」と思うような仕事を請け負わせてもらっています。
その代表格がホテル向けのパン製造です。ホテルの宴会やビュッフェ用のパンを製造しており、去年くらいまではホテルベーカリー部門も人手不足の状況でした。そのため、コロナ禍以前のような大人数の宴会を受けられない悩みがあるとしり、またご縁があって紹介してもらい、今ではがっつりホテル向けのパン製造を請け負っています。
パン業界、特に工場は、情報が先行して「しんどい」というイメージが強く、人気がないと感じています。実際、何千、何万個を製造するうえで、品質、衛生管理においてかなりのレベルを求められるため、時にはなぜ?と感じてしまうような厳しいクレームもあります。例えば、学校給食のパンは、何万個のうちのたった1個でも焦げが付いていたり、髪の毛が入っていたりすると、異物混入として非常に厳しい対応を求められることになります。
確かに私たちにとっては何万分の1個でも、子供たちにとってはたった1個のパンですからね。ホテルの仕事に至っては、5mm大きいだけで返品されることもあります。彼らは品質維持のために、あらゆる細部にまでこだわられていますし、請け負った我々もその基準に追いつくことが求められます。しかし、その中で自分が作ったパンがホテルのシェフの助けになり、大企業の集まりなどで食べられていることを知ると、非常にやりがいを感じます。直接お客様の顔を見る機会は減りましたが、東京などで「美味しかったです」と連絡をいただいたりすることもあり、それが私たちのやりがいです。
取材担当者(石嵜)の感想
西洋軒の事業が、一般にあまり知られていないOEMという形で社会を支えていることに驚きました。学校給食やホテル向けパン製造における品質基準の高さと、それに応え続ける社長のプロ意識に感銘を受けました。若者が「しんどい」というイメージで敬遠しがちな製造業の現場で、誇りを持って仕事に取り組む社長の姿勢は、私たち学生が仕事選びをする上で、表面的な情報だけでなく、その仕事の奥深さや社会貢献性を知ることの重要性を教えてくれます。

【株式会社西洋軒の今後の展望】
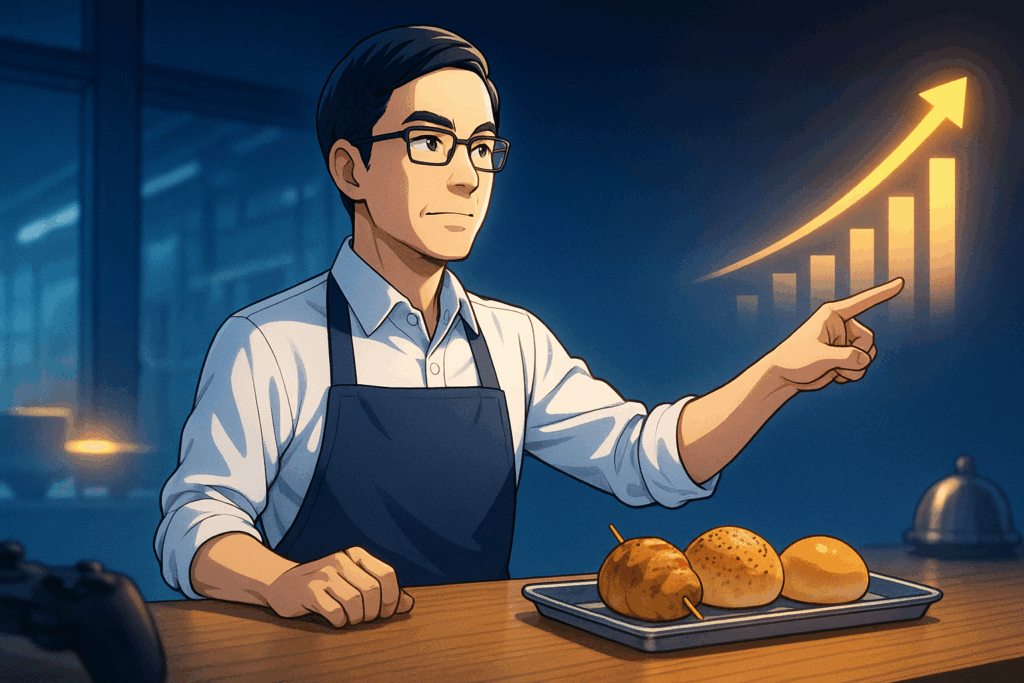
今後3〜5年で倍増させることを目標にしています。具体的にはまず5億円を目指し、そこから組織化を徹底すれば、自動的に10億円へ達すると考えています。将来的には、例えば私が社長室でテレビゲームをしていても収益が上がるような状態を作り、50歳までにはセミリタイアしたいですね。
ホテル事業では、大手と競合しつつも、品質で勝負し、「縁の下の力持ち」として確固たる地位を築きたいです。卸売事業では、他社の模倣品ではなく、「西洋軒らしさ」を前面に出した独自製品の開発を進めます。個人的には、焼き鳥パン3種や中華風カレーパンを開発中です。
従業員を増やしたいのですが、売り手市場となっている現在、過去に比べると初任給の水準は高くなり、なかなか来てもらえないのが現状です。そのため、現状では従業員の半分が外国の技能実習生です。私は若い人材、特に考え方が柔軟で真面目な子に来てほしいと思っています。イエスマンではなく、自分で考えて努力し、結果を報告できる、仕事に真摯に向き合える人材が理想です。
現在、仕事を取ることと人を増やすことのバランスが非常に難しい段階です。過去には、仕事を取る前に人を増やしすぎてしまい、過剰な状態になった失敗があります。逆に、人が減ったところで仕事が急増し、忙殺されたこともあります。先月末には3徹しましたからね。(笑)
今は、まず既存の従業員がスキルアップし、効率が向上することを目指しています。それが達成されれば、自然と生産量は上がり、品質も向上するため、新たな取引先獲得に動けます。そのタイミングで増員を考えています。将来的には、給食部門と卸売部門で担当を分けることも検討しています。最終的な夢は、子どもの時の夢だった全国を旅しながら仕事ができる、大型トラックの運転手になることです。
取材担当者(石嵜)の感想
社長が掲げる「売上倍増」という明確な目標と、それを実現するための組織改革のビジョンに、社長の本気度と先見性を感じました。個人的な「50歳でのセミリタイア」という目標も、会社を成長させ、組織を自走させる動機となっている点が興味深いです。新商品開発への意欲や、人材確保の課題への率直な言及は、リアルな経営者の視点を与えてくれました。最終的な夢がトラック運転手という意外性も、社長の人間的な魅力を引き立てていると感じました。

【山岡様から学生へのメッセージ】
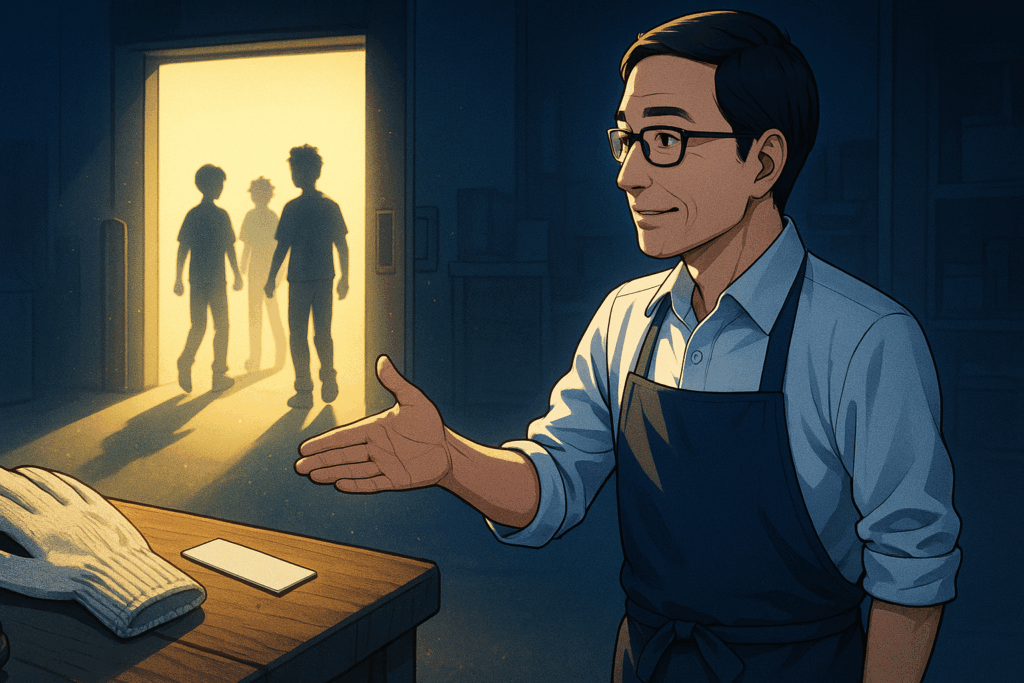
学生の皆さんには、指示待ちではなく、自ら考え、行動する姿勢を持ってほしいです。言われたことを忠実にこなすのは大事ですが、その先を自分で考え、ステップアップしようとする意欲をはっきり示してほしいと思います。辞める時に「もっといろんなことしたかった」と言うなら、なぜもっと早く言わなかったのかと残念に思いますね。私たちは見て学ぶ世代だったので、一から十まで言われなくても、自分で汲み取って行動していました。
世の中には様々な人がいます。たった一人でも気の合う人に出会えれば幸せなことです。会社で合わないからといってすぐに辞めるのは賢い選択かもしれませんが、辞める時もたとえ腹が立っていても、ちゃんと自分の意思をはっきりと伝えるべきです。面倒くさいことでも、それを乗り越えることで人は成長しますし、私たちはそのような努力にはきちんと報います。仕事には良い面も悪い面も全て含まれているのです。
また、職場で感情的になったり、馴れ合いの態度を取ったりしないよう注意してください。個人的な感情で仕事を阻害したり、先輩に対してため口をきいたりする態度は、たとえその場で許容されていても、他の場所では通用しません。(許容されているように思えて、実のところ呆れられていることが多いです)
情報が溢れる現代ですが、全てを鵜呑みにせず、自分の目で確かめることが非常に重要です。企業が作ったイメージ動画だけでなく、実際にその場所に行ったり、働いている人の顔を見たりして、リアルな雰囲気を知ることができます。
だからこそ、インターンシップのような形で、実際に体験してみることが何よりも大切です。学歴や頭の良さだけでなく、「面白いやつだな」「一緒に働きたい」と思わせるような、自分の経験や個性をアピールすることが、就職活動では重要です。私も銀行の面接では、型にはまらないアピールで合格しました。
最後に、死ぬこと以外は何でもできます。会社がうまくいかなくても、自己破産したとしても、命があればいくらでも再スタートできます。だから、皆さんも面白いことを見つけてどんどん挑戦し、失敗を恐れずに経験を積んでください。私も社員とその家族を守る使命があるからこそ、面白くないことでも、より高みを目指して頑張れるのです。
取材担当者(石嵜)の感想
社長からの学生へのメッセージは、非常に率直で、私たちZ世代が陥りがちな課題を的確に指摘していると感じました。特に「指示待ちではなく自ら行動すること」「情報に踊らされず、自分の足で確認すること」「死ぬこと以外は何でもできる」という言葉は、恵まれた現代に生きる私たちにとって、主体的に人生を切り開くことの重要性を強く訴えかけてくれました。
社長自身の波乱万丈な経験が言葉の説得力を高めており、このような本音で語ってくれる大人に出会えたことは、今後の私の人生にも大きな影響を与えると確信しています。










