有限会社マルシモは、「働く人の豊かな明日のために」をモットーに、365日24時間体制の訪問介護事業所として東京都内を中心に事業を展開しています。訪問介護に加え、通所介護(デイサービス)や居宅介護支援事業も手掛けており、利用者様とそのご家族の生活を総合的にサポートしています。創業者の「社会人が当たり前にできていることが、介護になった途端にできなくなるのはなぜか」という強い思いが、現在の事業の根幹となっています。有限会社マルシモは、創業者の想いを受け継ぎながら、「働く人の豊かな明日のために」というモットーのもと、利用者とそのご家族の暮らしを支える多角的な介護サービスを展開しています。今回は、その挑戦の背景やこれからのビジョンについて、代表取締役社長・下地様にじっくりとお話をお伺いしました。
<聞き手=石嵜渉(学生団体GOAT編集部)>
【今までの経緯・背景】創業の想いと事業の展開
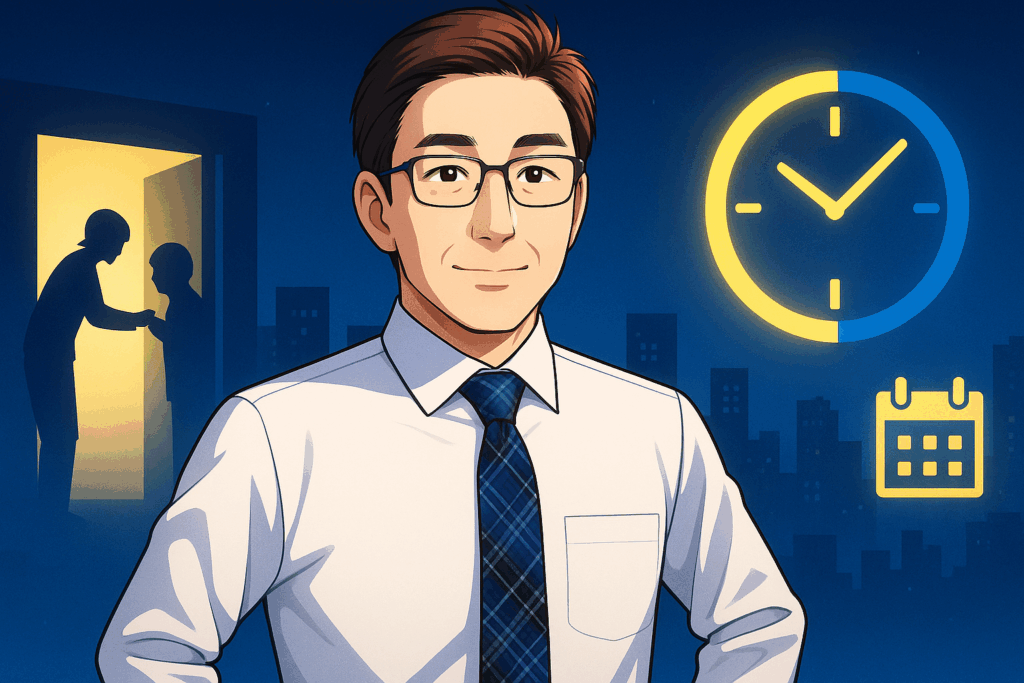
私は以前、大手の介護事業法人に在籍しておりました。その中で、介護を必要とする方々は土日や祝日、夜間といった時間に関わらず日常生活を送られているにもかかわらず、当時の介護サービスは時間的な制約が多いことに疑問を感じていました。私自身が当たり前にできている入浴や食事といったことが、介護を必要とする方々にとっては難しい状況である。それならば、365日24時間体制で、その人らしい生活を支える事業所を作りたい、そう強く思ったのがマルシモを立ち上げたきっかけです。これが、弊社が「働く」を支える事業の第一歩となりました。
創業当初は訪問介護事業が中心でしたが、利用者様の多様なニーズに応えるべく、通所介護(デイサービス)事業、居宅介護支援事業所(ケアマネジャーによるケアプラン作成など)へと事業を多角化してまいりました。時代の変化や利用者様の声に耳を傾け、柔軟に事業を展開してきたことが、弊社の成長の背景にあると考えています。長年の事業展開の中で、常に「お客様のために」という思いを大切にしてきました。現状に満足することなく、変化を恐れずに挑戦し続ける姿勢が、今日の多岐にわたる事業展開に繋がっています。
取材担当者(石嵜)の感想
「24時間365日」で“その人らしい生活を諦めさせない”発想が、理念ではなく運営設計にまで落ちていると感じました。訪問→通所→居宅へと広がった多角化もニーズ起点で一貫性があります。現場の疑問を起点に事業化する流れは、就活生として入社後の役割を具体的に描け、挑戦の余地が大きいと感じます。

【事業・業界について】「働く人の豊かな明日」を支える使命
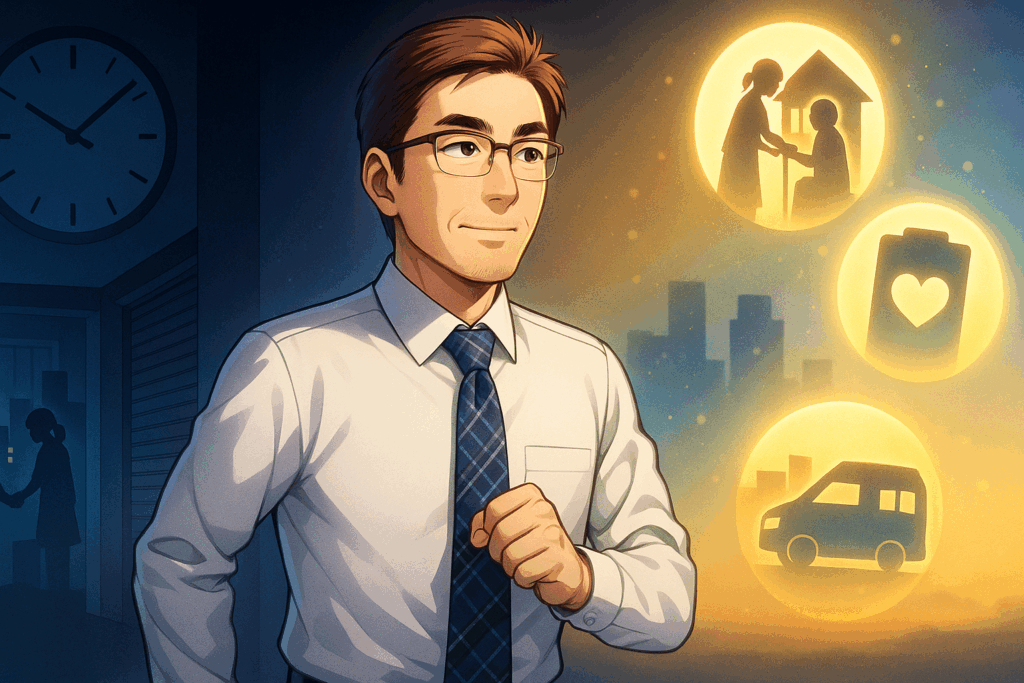
弊社の事業は、「働く人の豊かな明日のために」というモットーのもと、介護サービスを通じて、利用者様とそのご家族の生活をサポートすることです。訪問介護事業では、利用者様のご自宅に訪問し、身体介護や生活援助など、一人ひとりの状況に合わせたきめ細やかなサービスを提供しています。通所介護(デイサービス)事業では、ご自宅で生活されている高齢者の方々が日帰りで施設に通い、食事や入浴、レクリエーションなどのサービスを受けることで、社会参加や心身機能の維持・向上を図っています。また、居宅介護支援事業所では、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、利用者様の状況やご希望に応じた適切な介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、様々な介護サービスとの連携を調整しています。
介護業界は、高齢化が進む日本において、ますます重要性を増している業界です。しかしながら、人手不足や賃金の問題、社会的地位の低さなど、多くの課題も抱えています。私は、「介護の仕事は日の当たる仕事になってほしい」「介護事業者の社会的地位を向上させたい」という強い思いを持って事業に取り組んでいます。単にサービスを提供するだけでなく、利用者様やそのご家族の生活の質を高め、地域社会に貢献することを使命としています。
弊社では、多職種連携を重視し、医療機関や地域の関係機関との連携を密に行うことで、利用者様にとってより質の高いサービス提供を目指しています。代表的な取り組みとして、「収穫祭」というイベントを毎年開催し、地域の医療・介護関係者が集まり、情報交換や交流を行っています。これは、それぞれの専門性を活かしながら、利用者様中心のケアを提供するための重要な取り組みです。縦の関係ではなく、横の連携を大切にしています。
取材担当者(石嵜)の感想
働く人の豊かな明日”がスローガンで終わらず、訪問・通所・居宅の運営と多職種連携にまで落ちている点が心強いです。『収穫祭』で横のつながりを仕組みにする発想は、利用者中心のケアを地域で実装する具体策だと感じました。業界の地位向上という意思も明確で、就活生としては連携設計や現場の改善に挑める余白が大きいのが魅力です。

【学生へのメッセージ】仕事で最も苦労すること、そして成長のために
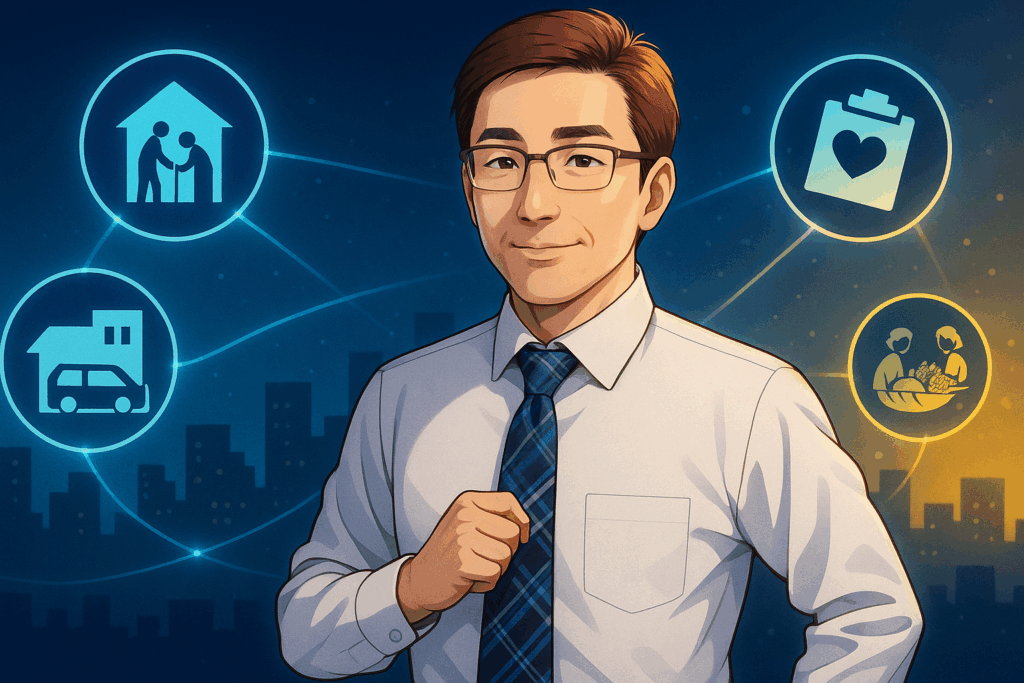
仕事で最も苦労したことは、一言で言えば「人」に関わることでした。採用から始まり、人材育成、そして従業員のメンタルケアまで、多岐にわたる「人」の問題に日々向き合ってきました。介護の現場では、必ずしも利用者様から感謝されるばかりではなく、自身の提供するサービスに納得がいかず悩む従業員もいるため、一人ひとりに寄り添い、サポートしていくことの難しさを感じています。現代社会においても、人手不足や早期離職は多くの企業が抱える課題であり、弊社も例外ではありません。
弊社では、離職率を下げるために、職場環境の整備に力を入れています。物理的な環境だけでなく、従業員のメンタルケアや配慮を重視し、管理者による定期的な面談を実施するなど耳を傾ける体制を整えています。早期退職の理由として、給与だけでなく、職場の雰囲気や人間関係が大きく影響することを認識しており、従業員が安心して働ける環境づくりに努めています。管理者は彼らの悩みを吸い上げ、解決に導く重要な役割を担っており、その能力が問われる部分も大きいと感じています。
就活生の皆様に向けて、最も伝えたいのは「コミュニケーション能力」の重要性です。どのような業種であっても、円滑な人間関係を築き、相手を尊重した上で意思疎通を図る力は不可欠です。特に現代社会においては、ハラスメントに対する意識が高まっているため、言葉遣いや伝え方一つで相手に与える印象が大きく変わることを理解しておく必要があります。例えば、業務上の指示を出す際も、「~に行ってきて」と伝えるのと、「~に行っていただけますでしょうか」とお願いするのでは、相手の受け取り方が全く異なります。相手への配慮を忘れず、気持ちよく仕事ができるようなコミュニケーションを心がけることの重要性は、学生のうちから意識しておくべきでしょう。
取材担当者(石嵜)の感想
“人”の難しさを真正面から捉え、定期面談やメンタルケアで個人頼みを仕組みに置き換えている点が具体的で頼もしさを感じました。指示の言い回しまで解像度高く設計する姿勢は、配属初期の不安を和らげます。就活生としては、コミュニケーション=場を整える技術として磨ける環境だと受け取りました。

【今後の展望】介護の未来を拓く挑戦
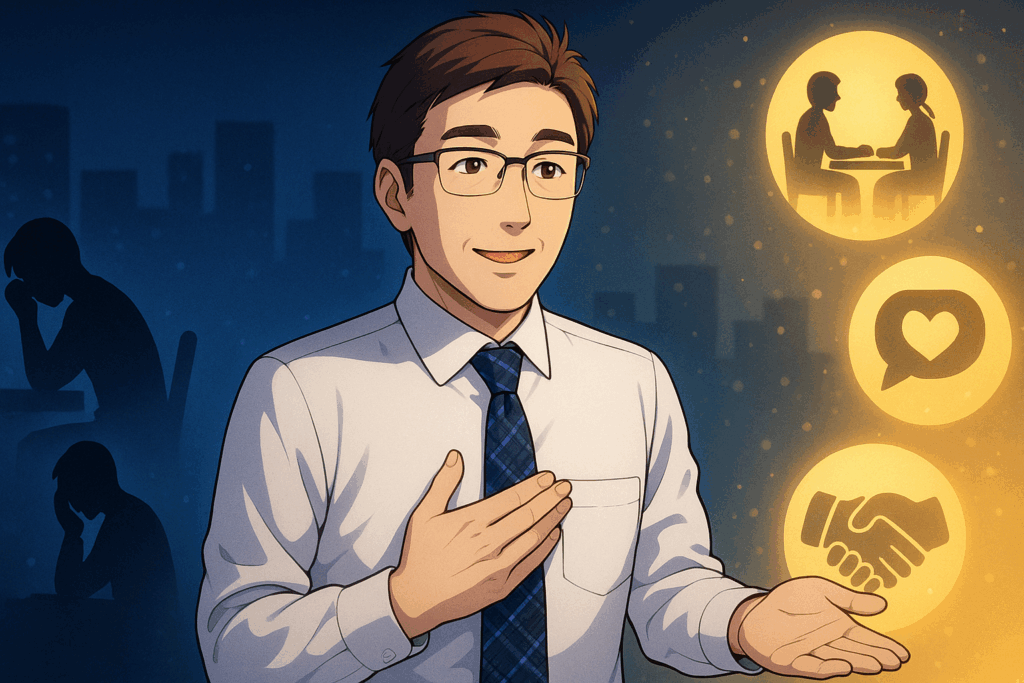
弊社は、創業100周年に向けて、会社を持続的に発展させていくことを目指しています。そのためには、時代の変化に対応し、常に社会に必要とされるサービスを提供し続けることが重要であると考えています。特に、介護業界全体の社会的地位向上を強く願っており、「訪問介護という仕事が日の当たる仕事になってほしい」という熱い思いを持っています。人材不足が深刻化する介護業界において、仕事の魅力ややりがいを発信し、次世代を担う人材を育成していくことの重要性を認識しています。
介護報酬の改定や人件費の上昇など、介護事業を取り巻く環境は決して楽観視できるものではありません。しかし、そのような状況の中でも、従業員に働きがいのある環境を提供し、質の高い介護サービスを提供していくために、様々な工夫を凝らしています。例えば、東京都の助成制度を活用した社内制度の整備をするなど、柔軟な働き方を支援する取り組みも行っています。
今後の事業展開としては、訪問介護事業を核としつつ、更なる事業所の展開を目指しています。資格や役職に応じて適切な評価と待遇を提供することで、従業員のモチベーションを高め、成長を支援していく方針です。また、新卒採用にも意欲を見せており、専門学校からの新卒者も入社しています。若い世代が介護の現場で活躍できるよう、丁寧な育成と温かい歓迎の姿勢を示していくことは、今後の介護業界にとっても希望となると信じています。
取材担当者(石嵜)の感想
介護業界の未来に対する強い危機感と、それを変革していきたいという熱意がひしひしと伝わってきました。介護の仕事の価値を高め、次世代が憧れるような魅力的な業界にしたいという強い思いは、社会貢献に関心のある就活生の心を打つのではないでしょうか。100周年に向けて、変化を恐れず挑戦し続ける下地様の今後の展開に、大いに期待を感じました。










