株式会社やまじょうは、滋賀県に本社を置く老舗の漬物製造会社です。明治43年(1910年)に糀・味噌加工業として創業し、昭和11年(1936年)に漬物加工業を開始しました。日野菜漬けやさくら漬けで農林大臣賞や通商産業大臣賞を受賞するなど、数々の栄誉に輝いています。現在では、全国のスーパーや生協、百貨店などに商品を展開する一方で、滋賀県内に複数の直営店「近江の地漬 専門店 山上」を構え、地域に根ざした事業展開を行っています。素材本来の旨味や風味、歯ごたえを活かし、本物の美味しさを追求することで、お客様に感動を届けることを使命としている企業です。今回は、百十余年の伝統を礎に地域密着で磨いてきたものづくりと直営店の取り組み、そして漬物の未来を見据えた挑戦について、代表取締役社長・上西宗太様にじっくりとお話を伺いました。
<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>
【会社の歴史と承継】
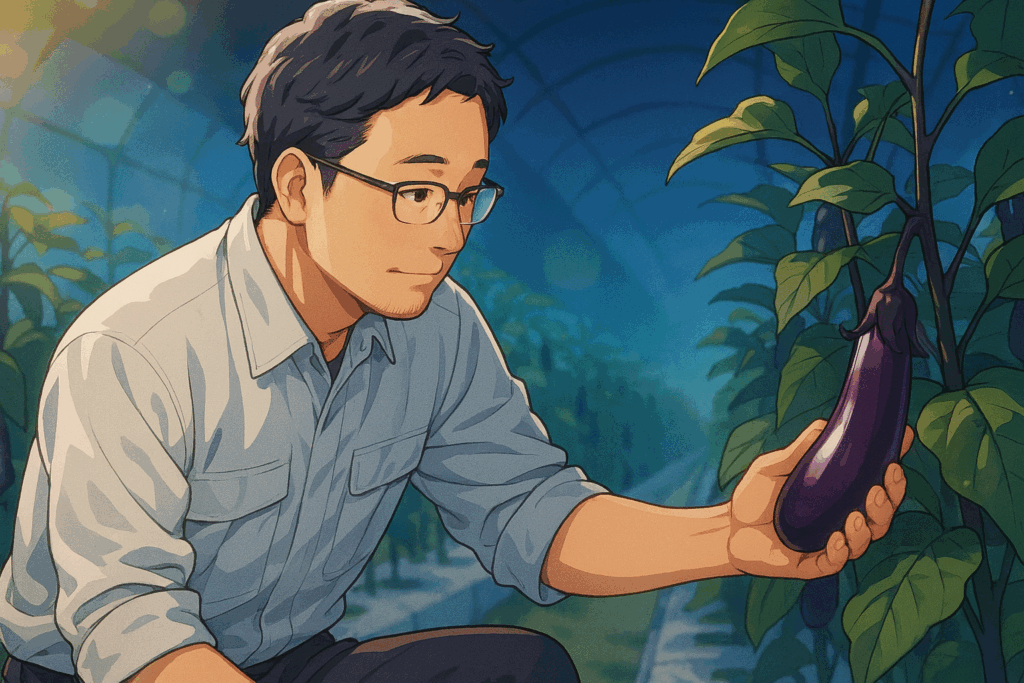
株式会社やまじょうは、およそ89年前に漬物業を本格的に開始し、私が4代目にあたります。もともと、漬物業を始める前は糀や味噌を製造していました。会社は「山中」と「上西」の2つの家が共同経営を始めたのが特徴で、これは業界でも非常に珍しい形態だと感じています。この共同経営は、約89年前に漬物業を始めるタイミングで、「一緒にやろう」と決まったことから始まりました。
私は前任の社長(自身の父親)が70歳を超えたことを機に、昨年7月に事業を引き継ぎました。社長就任前は専務として、いわゆるナンバー2の立場で会社の運営に携わっていました。共同経営の歴史を持つ会社は珍しいとよく言われますが、当社の歴史は山中家と上西家、二つの家が共に歩んできた証です。現在の経営形態に至るまで、さまざまな経緯がありましたが、この独自の歴史も当社の強みだと捉えています。
取材担当者(高橋)の感想
株式会社やまじょうの共同経営の歴史は、多くの漬物会社を見てきた中で特に興味深いと感じました。滋賀県の漬物屋さんとしては珍しい形態であり、歴史を持ちながらも新しい取り組みをしている会社だと感じました。共同経営という創業時の珍しい形から、現代まで事業を継承していることは、会社の根底にある強固な協力関係と、時代に合わせた柔軟な変化を物語っているように思います。

【経営者の挑戦と苦労】
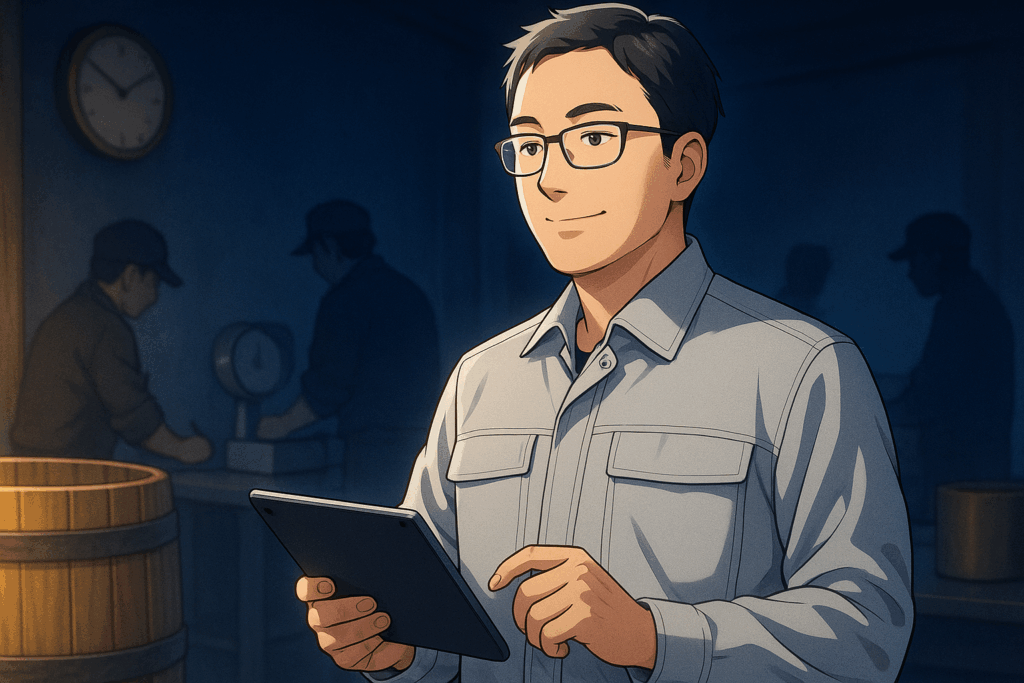
社長に就任してから特に苦労している点は、歴史ある会社ゆえの「昔ながらの体制」と、長く勤める従業員の方々との仕事の進め方です。中には40年以上、50年以上勤めている従業員もおり、彼らの経験を尊重しつつ、今の時代に合わせた経営へと少しずつ変革を進めている最中です。
例えば、工場では私が生まれた時に入社した従業員が40年を超えて勤務しており、店舗では50年以上のベテランもいます。こうした長く会社を支えてきた方々と共に、より良い会社へと変化させていくことに、日々気を配りながら取り組んでいます。会社の体制としても、歴史はありますが、悪く言えば昔ながらの慣習も残っていると感じています。その部分を、今の時代に合わせた運営や経営ができるよう、少しずつ変えていこうと取り組んでいる最中です。
伝統と新しい挑戦のバランスを取ることは、常に経営の大きな課題です。特に、長年培われた文化や仕事の進め方を尊重しつつ、変化を促していくことは、細やかな配慮と対話が求められます。しかし、これもまた会社を次世代へ繋ぐために必要なプロセスだと考えています。
取材担当者(高橋)の感想
外部から見ると、株式会社やまじょうの取り組みは現代的で新しい印象を受けます。しかし、実際には内部で伝統的な慣習も残っているとのお話は、企業経営の奥深さを感じさせました。新旧の調和を図りながら会社を率いていくことは、どのような企業においても重要な課題だと考えられます。特に、長年の経験を持つ従業員の方々を大切にしつつ、会社を変化させていく社長の姿勢に感銘を受けました。

【地域と伝統へのこだわり】
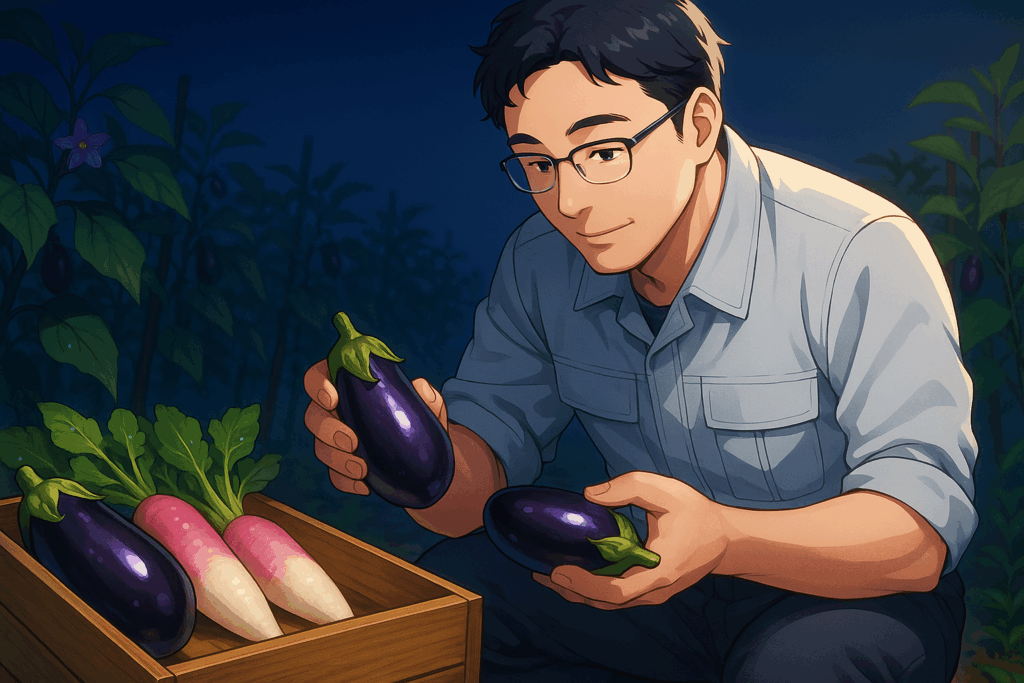
当社は、地元の滋賀県で育まれた伝統野菜を使った漬物作りを大きなコンセプトとしています。特に、夏には「下田なす」、秋冬には滋賀県で最も有名とされる伝統野菜「日野菜」など、地域の特産品を活かした商品開発に力を入れています。
しかし、これらの伝統野菜は栽培に手間がかかる上、高齢化や気候変動の影響で生産者が減少しており、収穫量が年々減っているという現状があります。この課題に対し、当社は15年以上前から「下田なす」の自社栽培に取り組むなど、伝統野菜を守り、作り続けるための努力を続けています。過去には「朝国生姜」のような特殊な野菜の復活プロジェクトにも関わりましたが、量の確保や継続の難しさに直面した経験もあります。それでも、伝統的な特産品を未来へ繋ぐことの重要性を強く感じています。
伝統野菜を生産し続けることは、非常に困難な道のりです。手間がかかり、収益に結びつきにくいという農業の現状も理解しています。それでも、滋賀の豊かな食文化を支える伝統野菜を次世代に伝えていくことは、漬物屋としての使命だと考えています。
取材担当者(高橋)の感想
漬物が大好きな私としては、株式会社やまじょうが地元の伝統野菜を大切にし、自社農場でまで生産していることに感銘を受けました。高齢化や気候変動といった農業が抱える問題は、日本全体で直面している課題であり、このような企業が伝統を守るために奮闘している姿は、非常に尊いと感じます。特産品を守り、継承していくことの重要性を再認識させられました。

【事業戦略と未来への展望】
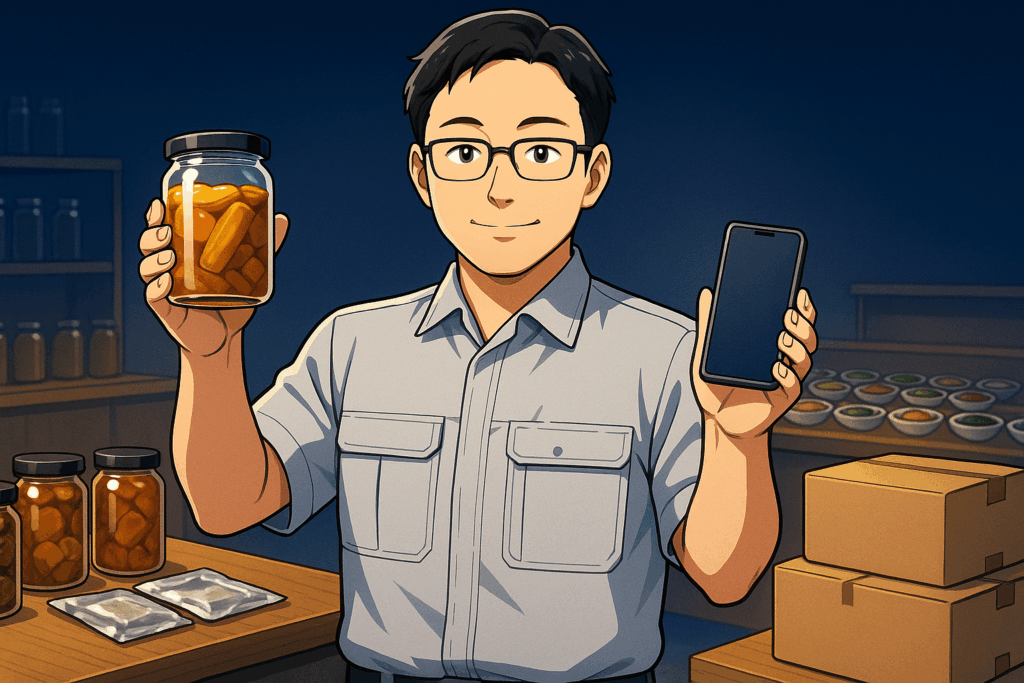
当社の主力事業は、全国のスーパーや生協への卸売ですが、全体の売上の約2割を占める直営店事業にも力を入れています。スーパーでは価格競争や制約が多いと感じる中で、自社が最も美味しいと思える商品を、適切な価格でお客様に直接提供したいという思いから、17年前に直営店事業を開始しました。現在は滋賀県内に4店舗を展開し、地域に根ざした事業を目標としています。
また、今後の取り組みとしては、日持ちのする商品の開発にも力を入れています。野菜の収穫量に左右されやすい浅漬けの課題を補完し、より安定した商品供給を目指しています。さらに、インターネットを通じてより多くのお客様に当社や漬物のことを知っていただき、商品をお届けできるよう、販路を広げていくことにも取り組んでいきたいと考えています。
来年創業90年を迎えるにあたり、100周年、そしてそれ以降も会社を続けていくことを大前提とし、漬物を日本の伝統食品として未来に残していくことをビジョンとして掲げています。漬物業界は厳しい実情にあるものの、昔からある伝統食品として必要なものだと考えています。直営店では、彦根の店舗の2階で20種類以上の漬物が楽しめるバイキングも開催しており、お客様に漬物の魅力を存分に楽しんでいただけるよう工夫しています。
取材担当者(高橋)の感想
スーパーでの価格競争という現代的な課題に対し、直営店という自社でコントロールできる場を設けて顧客体験を追求している点は、非常に戦略的だと感じました。また、漬物業界が厳しい現状にある中でも、日本の食文化の一部である漬物を未来に繋いでいこうとする社長の熱意は、就活生にとっても大きな学びとなるのではないでしょうか。お客様が漬物の魅力を存分に楽しめる工夫が凝らされており、伝統を守りながらもお客様を第一に考える姿勢が伝わってきました。

【若い世代へのメッセージ】
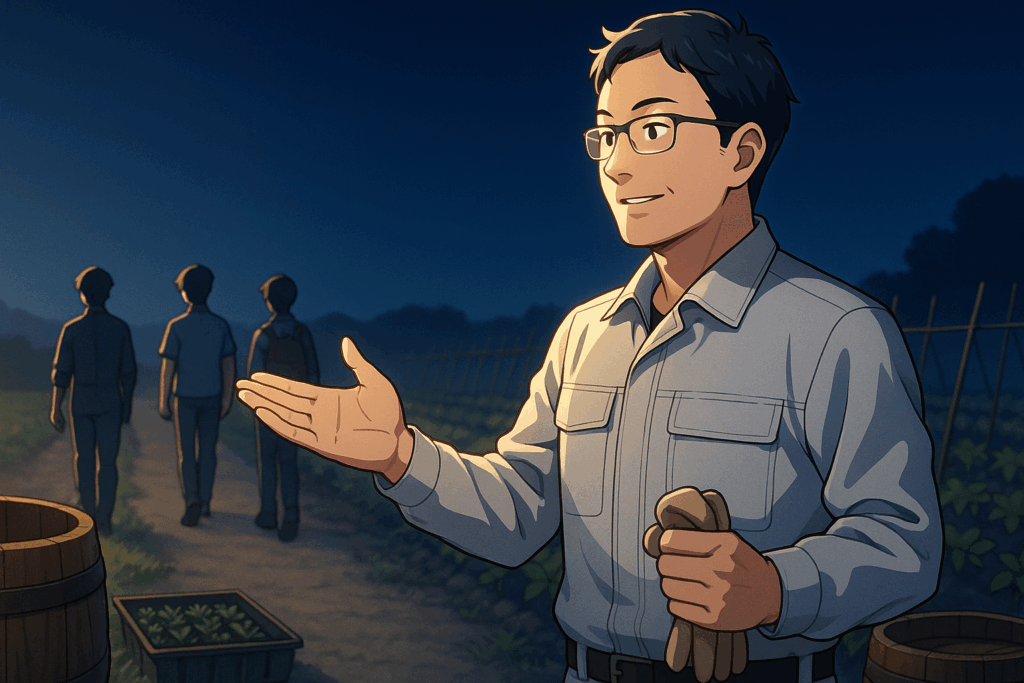
学生や20代の若者へのメッセージとして、「いろいろなことに挑戦してほしい」という言葉を伝えたいです。年を重ねるごとに挑戦しにくくなる部分があるため、20代という社会に出て間もない時期に、大小さまざまな挑戦を経験することが将来の自分のためになる、と考えています。ここでいう挑戦は、資格取得といったことだけでなく、自分のしたいことを追求し、行動に移すことの大切さを意味しています。
さらに、すぐに仕事を辞めるのではなく、多少の我慢をしてやってみることも大切です。我慢しすぎる必要はまったくありませんが、多少の困難を乗り越えることで見えてくるものも必ずあります。挑戦することに遅いということはありませんが、20代でできる挑戦と50代、60代でできる挑戦はまた違うという事実もあります。
社会に出たばかりの皆さんは、多くの可能性を秘めています。目の前の課題や困難に臆することなく、積極的に行動を起こすことが、将来の成長に繋がると信じています。私も常に新しい挑戦を模索し、会社をより良くしていくことを目指しています。
取材担当者(高橋)の感想
社会に出たばかりの私たちZ世代にとって、上西社長の「挑戦することに遅いということはない」という言葉は励みになりました。同時に、「多少の我慢」が必要という現実的なアドバイスは、社会の厳しさと向き合う上での重要な視点を与えてくれました。仕事を通じて成長し、社会に貢献していくことの意義を改めて考えるきっかけとなりました。自らの人生を切り開くための、力強いメッセージだと感じています。










