ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城は、世界遺産・首里城に最も近いホテルとして、地域に深く根差し、お客様に特別な体験を提供しています。当ホテルはヒルトンブランドの一員として、オーナー様からホテルの運営と経営を任される立場にあります。沖縄県内にはダブルツリーbyヒルトンが他に2箇所(那覇、沖縄北谷リゾート)あり、当ホテルは中でも長年の歴史を持つランドマーク的な存在です。今回は、首里城に寄り添う唯一無二のホテルとしての役割、そして地域と共に歩むこれからの展望について、総支配人・西野 貴志様にじっくりとお話をお伺いしました。
<聞き手=石嵜渉(学生団体GOAT編集部)>
【西野様今までの経緯・背景】
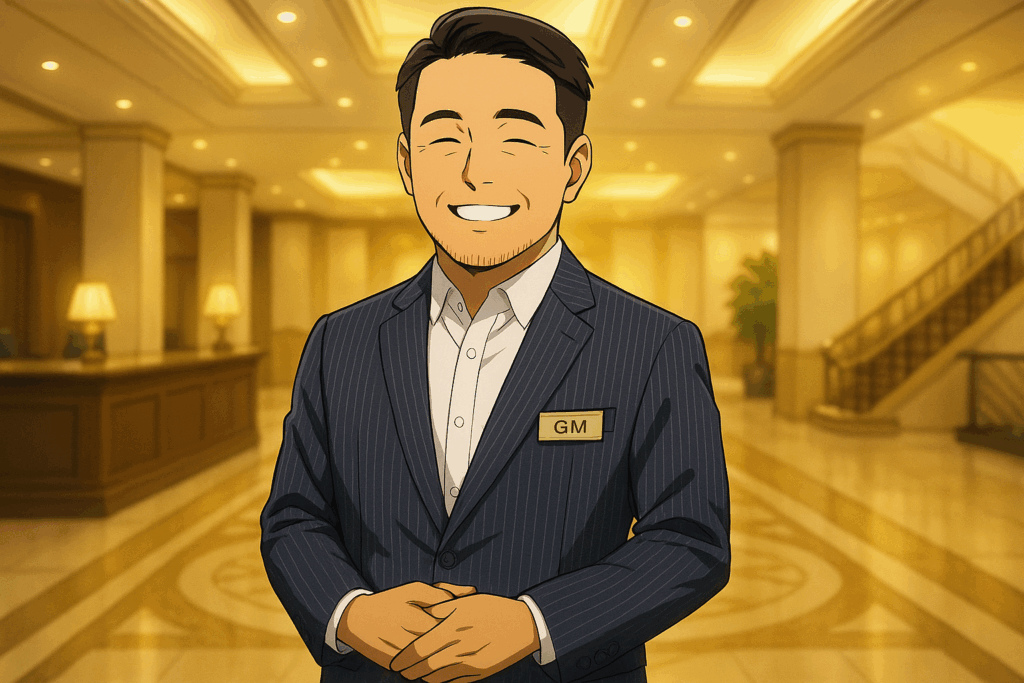
私のキャリアは、幼少期の旅行体験にルーツがあります。家族旅行で目にした添乗員の方々を見て、「仕事で旅行ができるなんて」という単純な憧れを抱いたのがきっかけです。この思いが、中学生の頃に旅行業界への道を真剣に考えるようになりました。
当時は日本の大学に観光学やホテル経営学を教える学校が少なく、この業界に進むためには海外の大学が唯一の選択肢でした。親の希望もあり、英語の習得も兼ねて、アメリカの大学へ進むための高校のカリキュラムを選び、ホテル経営学を専攻しました。
アメリカの大学を卒業後、日本のホテルに就職し、当初は大阪のホテルで営業や宿泊部門、レベニューマネジメントなどに携わっていました。転機が訪れたのは、宿泊部長を務めていた頃です。当時の社長から「あなたはGM(総支配人)をやるべきだ」と言われました。私自身は営業の道に進みたいと考えていましたが、社長からの強い推薦を受け、GMの職に就くことを決意しました。
最初にGMを務めたのは福岡のホテルでした。そこで3年間、ホテル開業以来最高の業績を更新し続けることができ、GMの仕事が予想以上に楽しいと感じ、「意外とこの仕事は自分に向いているかもしれない」と確信しました。
その後、大阪のホテルで再びGMを務めた後、ヒルトンから直接声がかかりました。ヒルトンは世界的に認知されたホテルブランドであり、そこで総支配人を務められる機会があるならば、と沖縄への赴任を決意しました。沖縄ではまず系列のホテルで3年間勤務し、昨年4月より現在のダブルツリーbyヒルトン那覇首里城に着任しました。私にとってこの業界は、単に旅行が好きという気持ちから始まり、多くの経験を経て現在に至っています。
取材担当者(石嵜)の感想
西野様が幼い頃からの純粋な憧れを胸に、自ら道を切り拓いてこられたことに感銘を受けました。特に、GM職への転身という大きな決断が、結果としてご自身の適性と才能を開花させるきっかけになったというお話は、キャリアを考える学生にとって、予期せぬ道にもチャンスがあることを示唆していると感じました。

【ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城の事業・業界について】
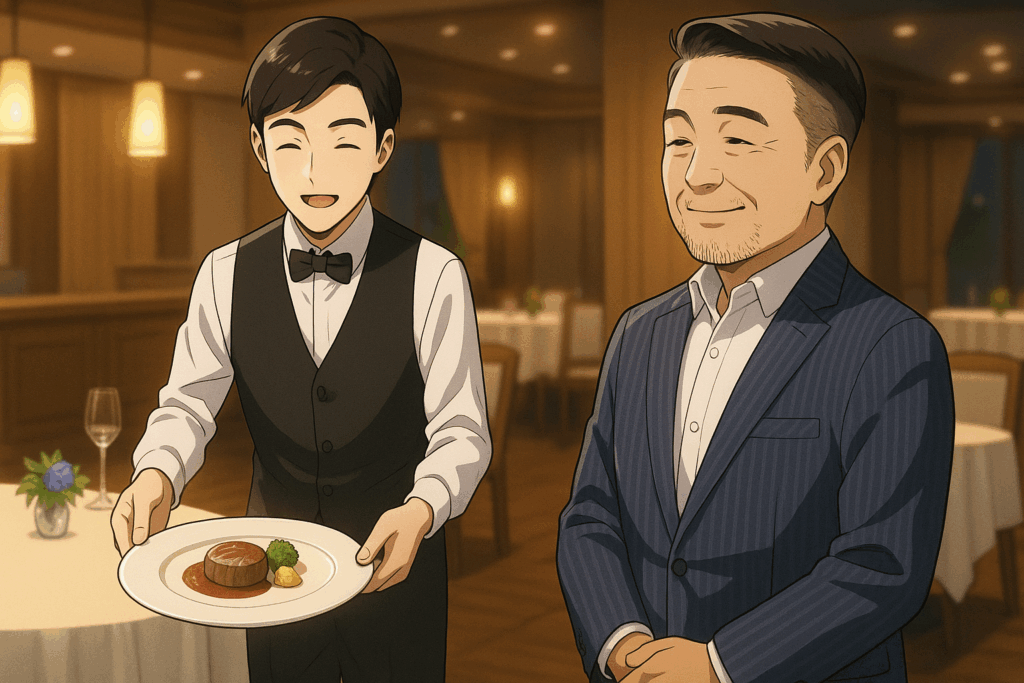
私たちは「ヒルトン」というブランドを冠していますが、ヒルトンはホテルの運営を担う「オペレーター」であり、建物の「オーナー」は別にいらっしゃいます。オーナーは個人の場合もあれば、複数の会社が共同出資して会社を設立しているケースもあります。
私たちはヒルトンとして、運営側の責任者を務めています。そしてホテルの総支配人は、ホテルの経営責任者であり、分かりやすく例えると、プロ野球チームのGMのような存在です。オーナー様からホテルの運営や経営を任されており、私の裁量でほとんどの物事を進めることができます。
当ホテルがターゲットとするお客様層は、部門によって大きく異なります。宿泊部門の主なお客様は、東京や大阪などの大都市圏から観光目的で沖縄を訪れる内地のお客様、すなわち日本のレジャー旅行客です。
年齢層は幅広く、若い方からご年配の方、修学旅行生まで様々です。当ホテルは首里城に最も近いホテルであるため、首里城を訪れる観光客にとって最適な立地です。2019年の火災で焼失した首里城の正殿が来年再建されることで、さらなる観光客の増加を見込んでいます。
一方、ホテル内の3つのレストランとバー、そして宴会場は、宿泊のお客様だけでなく、地元のお客様にも積極的にご利用いただきたいと考えています。ランチの時間帯は、宿泊客は観光に出かけてしまうため、地元の方々をはじめ、主婦の方々にも多くご利用いただいています。夜は接待や家族の利用を含め、地元の方々にご利用いただくことを重視しています。レストランの訴求は、特に女性客を中心に展開しています。宴会場は市内最大級の規模を誇り、地元の企業様の宴会や周年行事、そして地元の方々の結婚式を主なターゲットとしています。
ホテルが提供する商品は、物質的な価値だけでなく、「体験」に大きな比重が置かれています。同じサービスを提供しても、お客様が感じる価値は人それぞれ異なります。この「体験価値」を高めることが、私たち事業の重要な課題であり、同時に無限の可能性を秘めています。
例えば、提供方法の一つをとっても、単純に1プレートのメニューとして出すのではなく、一品ずつ皿に盛り付け、食材のストーリーを語りながらサービスすることで、お客様が感じる価値と価格は大きく変わります。大がかりな設備投資をかけずとも、サービスの工夫や見せ方の改善によって、お客様の感動や満足度を高める余地はまだまだあると考えています。私たちは、リピーターのお客様を増やすためにも、常にサービスを進化させていく必要があると認識しています。
取材担当(石嵜)の感想
GMの役割が単なる経営者ではなく、まるでスポーツチームのGMのように多岐にわたることに驚きました。「体験価値」という概念は、ホテル業界の奥深さを物語っており、形のないサービスにどのように価値を付加していくかという戦略は、ビジネスの普遍的な学びになると感じました。

【西野様から学生へのメッセージ】
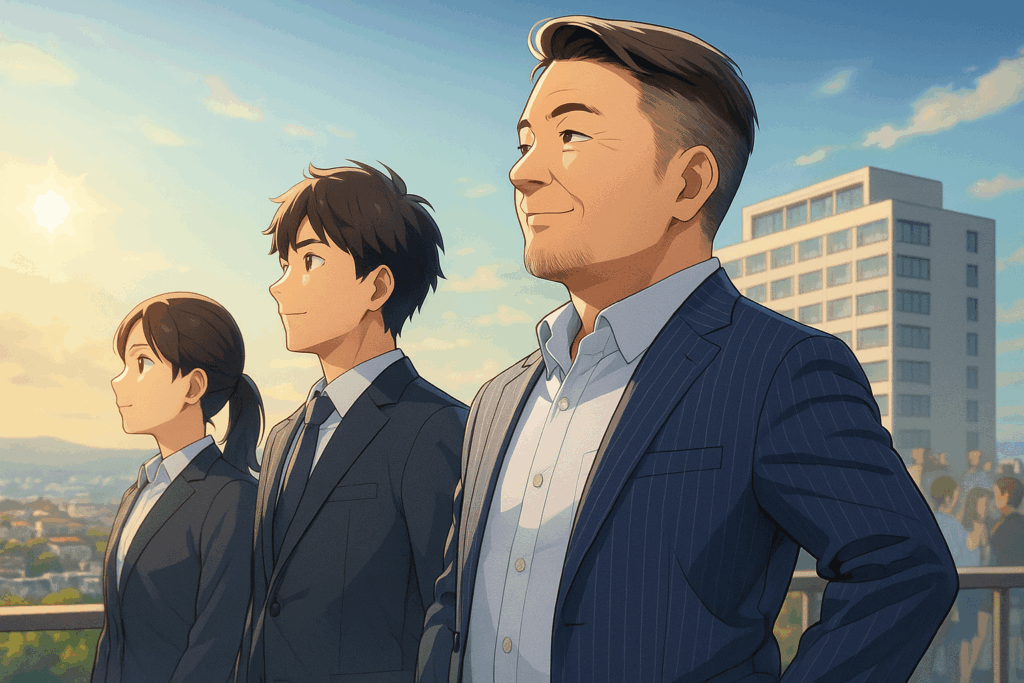
総支配人の仕事において、私が最も大切にしているのは、自身のビジョンをチームメンバーに一貫した言葉で伝え続けることです。私の目指すところは「自走する組織」の構築です。組織は一人では何も動かせません。従業員一人ひとりが私と同じ思いを持ち、同じ方向を向いて仕事に取り組んでくれる状態こそが、私が理想とする組織です。
そのためには、上司である私から部下へ、そして彼らがさらにその下のメンバーへと、ビジョンを浸透させていくしかありません。自分の直下にいるメンバーがまず自分と同じ思いで動けるようになるまで、それを伝え続けることが重要だと考えています。
メンバーが自身の成功体験を通じて「この人の言う通りにやったら成功した」「この人の考え方で動けば道が開ける」と実感できるようになると、彼らは自ら考えて行動するようになります。そうなれば、私が何も言わずとも、私の思い描いた通りに物事が進んでいくのです。
私は、自分が目指すゴールと、そこに到達するためにメンバーに何をしてほしいかを常に伝え、そのメッセージがぶれないように心がけています。この10年間、どのホテルに赴任しても、この方針を貫いてきました。
私たちのホテル業は、お客様がいて初めて成り立つ「商売」です。従業員一人ひとりが「自分が幸せになりたい」と願うのは当然のことですが、その幸せはお客様を幸せにすることによって初めて得られるものです。お客様を幸せにできない人は、この業界で成功することはできませんし、自身の幸せも回ってこないでしょう。
お客様が私たちに給料を支払うお金をくださっているという意識を持つことが重要です。お客様を幸せにし、提供する商品やサービスの価値を高めていくことこそが、この商売の基本的な考え方であり、私がチームメンバーに常に訴え続けていることです。
取材担当(石嵜)の感想
「自走する組織」という目標と、そのためにビジョンを伝え続けるという強い信念に感銘を受けました。特に、「お客様を幸せにできなければ、自分たちの幸せも回ってこない」という言葉は、仕事の本質を突いており、学生が働く上で大切にすべき視点だと深く心に響きました。

【ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城の今後の展望】
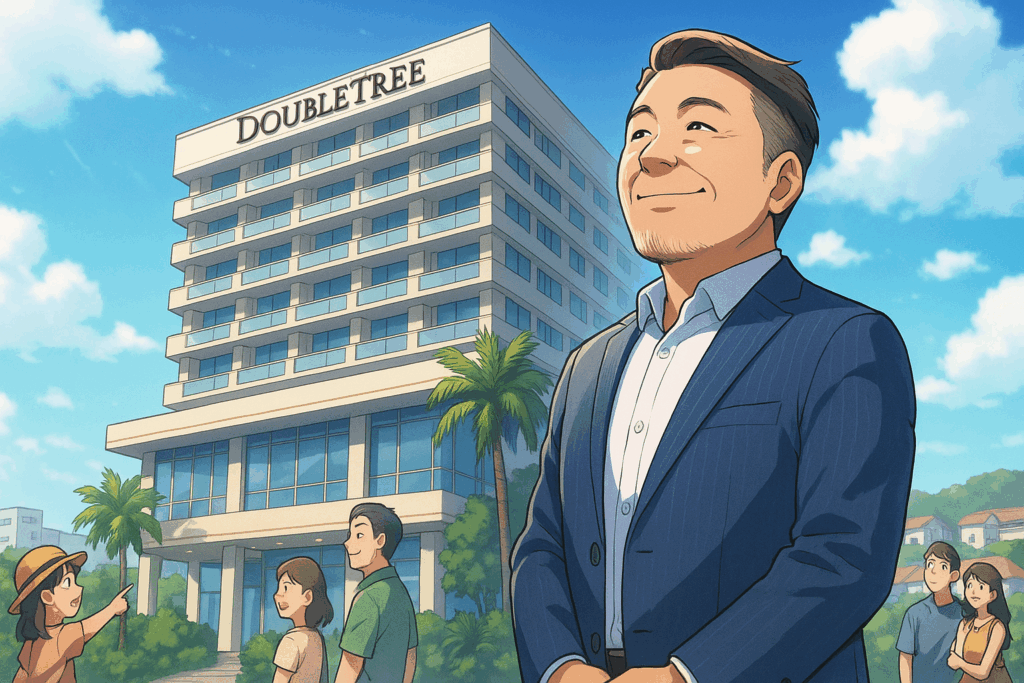
当ホテルにおける私のビジョンは、「街の誇りになろうよ」と従業員に伝え続けていることです。このホテルはすでに地元の方々から長く愛されている存在ですが、それに甘んじることなく、心から「このホテルが我が街の誇りだ」と感じてもらえるような存在を目指しています。例えば、沖縄から東京や大阪に出た家族が帰省する際、内地の知人が沖縄に来ると聞いたら「我が町にはこんな素晴らしいホテルがあるから、ぜひあそこに泊ってほしい!」と勧められるようなホテルになりたいと考えています。
この目標を達成するためには、従業員一人ひとりがそうした振る舞いをすること、そして何よりもお客様に幸せな気持ちで帰っていただくことが重要です。お客様に感動と幸せを提供し続けることで、地域の方々からも愛され、誇りに思われるホテルへ成長できると信じています。
一方で、業界全体が抱える課題にも向き合っています。特にコロナ禍の影響でホテル業界を離れた人が多く、現在は調理部門や中間管理職の採用に苦戦しています。組織の「空洞化」と呼ばれるこの課題に対して 若手従業員の育成を強化し、一般職からの突き上げを図ることが喫緊の課題です。
将来的には、フリーランスの専門家やリゾートバイトといった柔軟な働き方を取り入れ、技術を持った人材の確保も視野に入れています。お客様をどれだけ幸せにできるか、それがホテル業務において最も大切なことであると私は考え、これからもそれを訴え続けていきます。
取材担当(石嵜)の感想
「街の誇りになろうよ」というビジョンは、地域に根差したホテルの理想的な姿だと感じました。お客様の幸せがホテルの誇りへと繋がるという考え方は、ビジネスの枠を超えた社会貢献であり、企業が目指すべき姿を明確に示していると感じました。










