群馬県渋川市に本社を置く鳥山畜産食品は、食肉事業に加え、グループ会社で生産牧場を営む企業です。牛を扱う商売としては80年の歴史を持ち、現在の鳥山社長は牛を扱う商売としては3代目、お肉屋さんとしては2代目に当たります。経営のバトンを引き継いだのは2010年、15年前のことです。単なる食肉販売にとどまらず、自分たちで子牛の生産から手掛け、どういう考えや思いで牛肉を作っているのかを大切にしながら、国内外にその価値を届けています。今回は、「牛の命を預かる」責任と真正面から向き合い、生産から販売まで一貫して取り組む鳥山畜産食品の歩みと、世界に向けて“鳥山にしかできない価値”を発信し続ける3代目・鳥山社長の展望について、じっくりとお話をお伺いしました。
<聞き手=石嵜渉(学生団体GOAT編集部)>
【鳥山様の今までの経緯・背景】
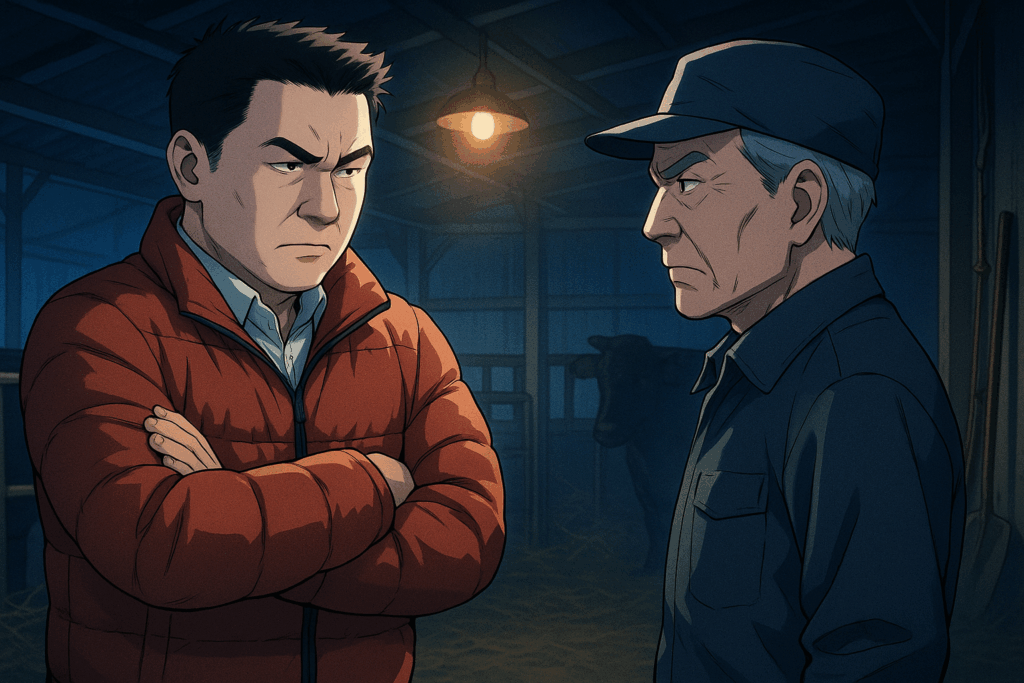
私は、いわゆる家業である牛を扱う商売の3代目として育ちましたが、学生時代は家業を継ぐつもりは全くありませんでした。群馬県は海がなく山に囲まれた土地柄もあり、小さい頃から冬山でのスキーが好きで、学生時代は年間100日ほど雪の上で過ごすほど打ち込んでいました。人にスキーを教えるアルバイトを続けており、漠然と「1年中スキーをして生活できるのではないか」とさえ考えていました。
学生生活の後、8年間東京で生活していましたが、両親から群馬に戻ってこないかという話がありました。特に当時、生産牧場の経営環境が非常に厳しかったのです。実家の家業は順調な時に帰ってきても意味がなく、大変な時だからこそスタッフと一緒に色々やってほしいと言われ、私が25歳の時に帰郷を決意しました。
家業に入ってみると、生きた家畜を売買する家畜商という世界で、父は全国的にも有名な立場にあり、その存在感や実績に圧倒されました。私がこの業界で自分自身の名前で呼んでもらえるようになるまでには、5年ほどかかりました。それまでは「息子」「ジュニア」「セガレ」と呼ばれていました。
家業に入って2、3年経つうちに、うまくいっていない理由が自分なりに見えてきました。素人でしたので、父親にどんどん質問としてぶつけていきましたが、生産に関する考え方や大切にしていることの順序が全く違うと感じ、最初の大きな苦労は親子の確執でした。特に生産現場では、親の指示と私の発信する内容でダブルスタンダードができ、現場のスタッフにはものすごく迷惑をかけたと思います。時には父に「あんた会社潰す気か」とまで言ったこともあります。ある晩、父に呼び出され、「俺を誰だと思ってんだ」と言われた時には、自分の腕一つで会社を作り上げてきた父のこだわりや価値観は簡単には崩せないと感じました。
そこで私は、父親のやり方を見るのをやめ、全く違うアプローチから生産を変えようと決めました。業界で天才と言われていた感覚的な父に立ち向かうため、現場のスタッフを味方につけ、徹底的にデータを取ることにしました。当時はエビデンスがなければという表現になると思いますが、具体的には、感覚的に買った子牛が本当に利益をもたらしたのかどうかを数字で見えるようにし、儲からない牛はやめて儲かる牛をもっと買うといったことから始めました。私が感覚的な父のやり方を否定するようなデータを出すにつれて、父の口数は減っていき、いつしか牧場に関する牛の出し入れの権限は私にバトンタッチされました。
取材担当者(石嵜)の感想
鳥山社長が家業に入られた背景や、お父様とのご経験を聞いて、会社をより良くするためとはいえ、長年培われてきたお父様のやり方をデータに基づいて変えていくというのは、相当な覚悟と粘り強さが必要だっただろうと感じました。
特に親子という関係性の中で、意見がぶつかり合いながらも前に進んでいく過程は、困難でありながらも、組織を強くしていく上で避けては通れない壁だったのだと思います。データに基づいた経営判断や、現場のスタッフと共に改革を進めるという考え方は、非常に現代的で素晴らしいと感じました。

【鳥山畜産食品株式会社の事業・業界について】
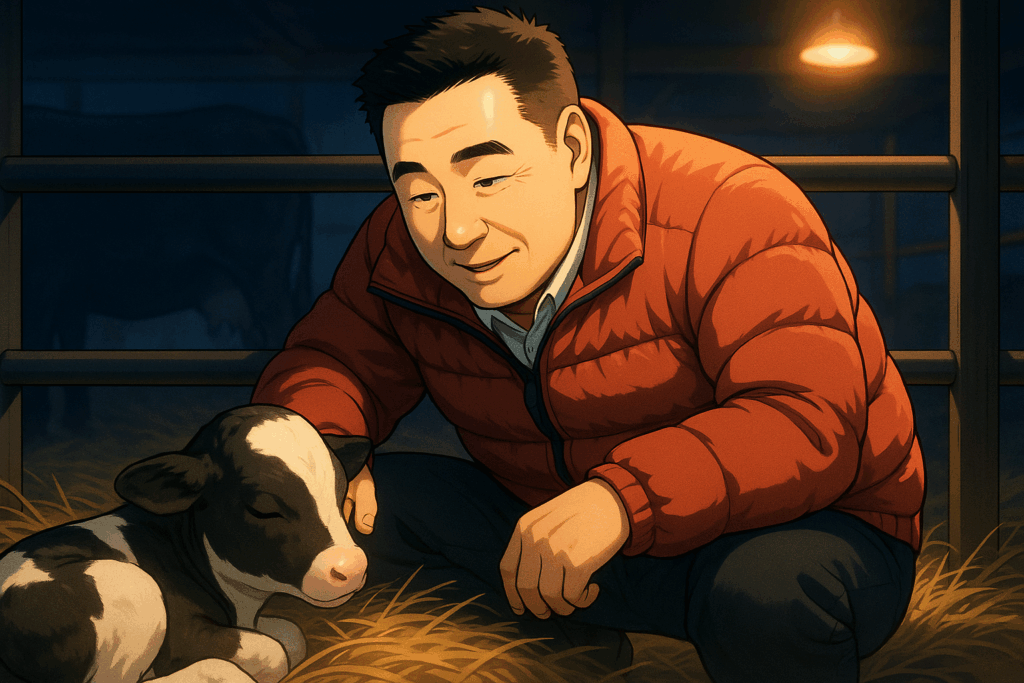
畜産業界、特に和牛の世界は時代とともに変化しています。私がこの業界に入った約30年前は、霜降り牛肉は非常に貴重品でした。霜降り牛肉を作っている生産者の価値や希少性が世の中にありましたが、今では技術が進み、霜降り牛肉は差別化になりません。ですので、何をしなくてはならないかというと、ただモノを売るのではなく、どういう考えや思いで商品を作っているかを伝えることが重要になっています。
私たちの農場では20年ほど前まで、子牛を外から買ってきて育てていましたが、今は毎日牧場で子牛が生まれています。自分たちで母親牛を用意し、子牛の生産から全て自前で行っています。これは、外から買ってくる子牛では私たちがイメージする牛肉にならないと感じたからです。自分たちでデザインした牛肉を作るために、子牛作りから全て自分たちでやる取り組みを始めました。
これは一貫生産という表現を使いますが、国内にあまりない取り組みだと分かりました。さらに、それを自分たちで加工して販売する会社も国内にはそんなにありません。これを狙って始めたわけではなく、自分たちが何のためにこの牛肉を作っているのかを説明できることが大切だと思っているからです。目の前にあるものだけでなく、その背景にあるものを伝えることを大切にしています。
事業の柱は卸売であり、事業全体の60%を占めています。また、10年以上前から海外輸出にも取り組んでいます。国内向けのブランドは群馬県の赤城山から名を取った「赤城牛」「赤城和牛」ですが、海外向けのブランドは「Umami Wagyu」として展開しています。このブランド名には群馬県の名前は入っていません。産地ブランドでの差別化にならないという思いがあり、「鳥山に任せてくれれば美味しさを外しませんよ」ということを看板に海外輸出を行っています。
海外輸出の最初のきっかけは13年ほど前、ヨーロッパの若いエージェントと知り合ったことです。彼に「お前ら面白いね」と言ってもらい、新しいビジネスの話がありましたが実現しませんでした。その後、彼からシンガポールで輸出を始めてみないかという声をもらい、商社を紹介してもらったのが始まりです。
取材担当(石嵜)の感想
霜降り牛肉が差別化にならないというお話は、業界の現状を知る上で非常に興味深かったです。技術の進化によって、求められる価値が変化しているのですね。そのような中で、一貫生産という他社にはない取り組みを行い、その背景にあるストーリーやこだわりをお客様に伝えることを大切にされている点は、単なる食品メーカーではなく、「鳥山畜産食品」というブランドとして、お客様と深く関わろうとされている姿勢を感じました。
特に、子牛作りから自分たちで行い、理想の牛肉をデザインしているというお話は、品質への強いこだわりと、そこから生まれる独自性を感じられて面白かったです。

【鳥山畜産食品株式会社の今後の展望】
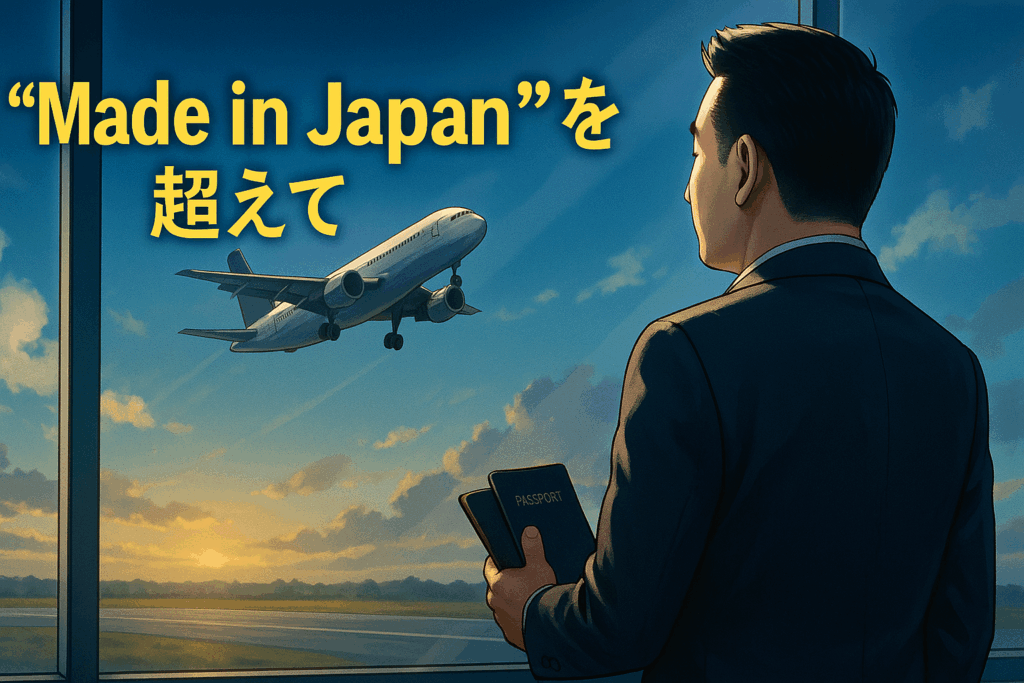
会社の将来を考える上で、日本国内の人口構造が逆ピラミッドになっていることは避けて通れません。畜産業界は食品に携わる世界であり、日本国内の胃袋の容量は縮小していきます。一方で、食肉の消費量はわずかながら毎年増加しており、その背景にはインバウンドや食の欧米化があります。お肉がなくなるということはまず間違いなくないでしょう。しかし、私たちがターゲットとし、私たちの取り組みの価値を伝えたいお客様は、日本国内だけではこれからも不十分だと考えています。だからこそ、海外輸出は引き続き伸ばしていかなければなりません。
現在の海外輸出の割合はざっと10%から15%ですが、これを50%にまで増やせば、全体の実績も大きく変わる可能性があります。ただ、牛肉は牛1頭を解体すると14種類の異なる部位が出てきますが、世界中どこでも私たちが考える価値が認められるかというと、国や地域によって食文化が異なるため課題があります。
牛1頭全てを海外で売り切ることはまだ難しい状況です。したがって、輸出を伸ばしていく上での条件は、国内とのバランスです。国内でも私たちの取り組みに共鳴してくれて、一緒に取り組んでいただけるお客様が増えれば、海外も伸ばせるという流れになります。
実績はあくまで結果であり、そこに向かうプロセスとして会社が目指すのは、国内でも数少ない取り組みをやっている企業として、「なぜ鳥山なのか」をより広く、より強く伝えられるように、自分たちの取り組みの価値を磨くことです。これをひたすらもっともっとやっていきたいと考えています。海外に行くと、「Made in Japanでいいじゃん」と言われることがあります。
これはものすごく目から鱗が落ちるような話で、その通りなのです。海外のお客様から見れば、私たちは「Made in Japan」という一つの括りにしか見えていないのです。私たちがアメリカ産やオーストラリア産の牛肉を食べる時に、それが何州のものかなど聞かないのと同じです。こういうことに気づくと、実はもっと気にしたり頑張らなければいけないことが違うところにあるのだと分かります。牛を育てている農家さんにも、海外のそういった話ができると、自分たちの世界が広がるため、ものすごく面白いと感じてもらえると思います。そういった取り組みはこれからも一緒にやっていきたいです。
取材担当(石嵜)の感想
日本国内の市場の現状を踏まえ、海外展開を積極的に進めていくというビジョンは、非常に現実的かつ挑戦的だと感じました。特に、海外で「Made in Japan」として評価されるというお話は、国内での細かなブランド戦略とは異なる視点であり、海外のお客様から教えてもらったというエピソードが印象に残りました。
牛1頭を無駄なく使い切るという課題は難しそうですが、それを乗り越えるために国内と海外のバランスを取りながら進めていく戦略は、まさに「鳥山畜産食品」にしかできないことへの挑戦だと感じました。将来、海外で鳥山畜産食品のお肉を目にするのが楽しみです。

【鳥山様から学生へのメッセージ】
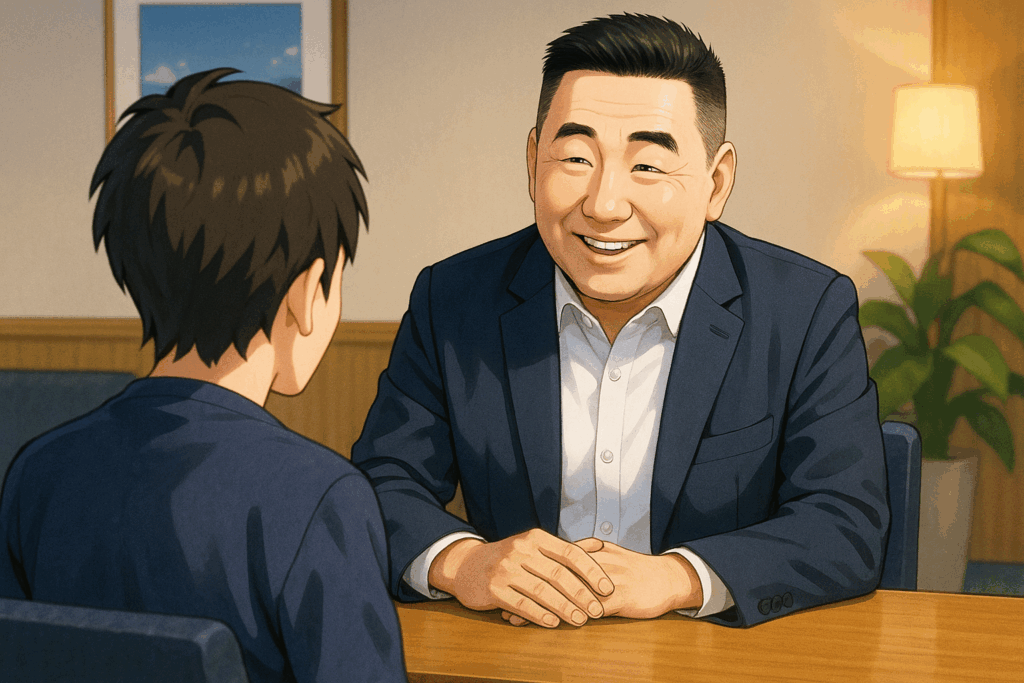
私たちはちょうどコロナ禍から、新卒採用に比較的費用をかけて取り組んでいます。その中でたくさんの学生さんと話をする中で感じるのは、良くも悪くもみんな「いい子」だということです。これは社会に出てからを考えると、圧倒的に経験値が足りていないということです。勉強が足りていないというよりも、経験が足りていないのです。みんな「いい子」すぎて、まるでいつも日向を歩いているような感じで、応用力のようなものがものすごく足りないと感じます。
私たちが学生時代から言われてきたことですが、これから社会に出る皆さんは、今学生時代にある時間というものが想像以上に自由に使えるということに、気づきません。社会に出ると時間すらだんだん自由が効かなくなってきます。その時間の使い方を自分で決められるのは、実は学生時代だけです。その時間をどのくらい無駄にせずに、いろんな経験ができるか。それは海外旅行でもいいかもしれないし、アルバイトでもいいかもしれないし、やはり数多くの人と接してほしいと感じます。
その中でならば、やっぱり何か失敗の経験をしておくと、すごく社会に出て役に立つと思います。でも失敗の経験というのは、何か一つのことに打ち込まないとできないことです。上っ面だけで、「あれもできます、これもできます、これも知ってます」というのは、私の考えでは経験には入りません。一つでも二つでも、集中して一生懸命取り組んだ中から生まれる失敗の経験。
ひょっとしたら対人関係がうまくいかなかった、連絡を取らなくなってしまった人がいる、なんていうことも。そうしなさい、ということではありませんが、それは確実に自分の血となり肉となる貴重な経験になるはずです。今でも採用の時には、必ず「記憶にあって忘れられない失敗の経験」と「忘れられない成功体験」を教えてくださいと聞くようにしています。これらはやはり経験しないと生まれてきません。
今の質問の冒頭で「みんないい子なんですよ」と言いましたが、これらの経験がなかなか出てきません。みんな普通のこと、みんながやっている同じことしかやらないということです。早期の離職が社会問題になっている裏側には、実はこういったことがかなりの確率で潜んでいると思っています。今はコミュニケーションで人に会わなくても済む時代になってしまいました。
面と向かって口喧嘩や議論をいくらでも避けられる時代です。でも、何か一つ、大きくても小さくても山を乗り越えるためには議論しなくてはいけないし、目の前の課題に向き合わないといけません。じゃあどうしようかと、小さな集団でもそういう経験を学生時代にやったことがあるかというのは、すごく大切な経験だと思います。思っている以上に、社会に出ると時間は自由が効かなくなります。その時間を本当に大切に使ってほしいですね。
取材担当(石嵜)の感想
学生時代の時間の使い方や、失敗の経験についてのお話は、まさに今の自分にとって心に響くメッセージでした。社長がおっしゃるように、社会に出ると時間の自由が効かなくなるというのは想像できますし、学生時代だからこそできる経験はたくさんあると感じます。
特に、一つのことに打ち込んで経験する失敗の重要性や、対人関係の苦労も貴重な経験になるというお話は、これからの自分の行動の指針になります。残り少ない学生生活で、様々なことにチャレンジし、多くの人と積極的に関わっていきたいと強く思いました。










