株式会社サブールは、和歌山を拠点とする、モダンで洗練された味わいのケーキを提供する専門店である。同社は、丁寧な手仕事と厳選素材を用い、誕生日・結婚式・記念日といった大切な瞬間を彩る特別なケーキを提供している。ふんわり焼き上げたスポンジに、なめらかな生クリームといちごをサンドした定番の「いちごショート」や、創業当初から変わらない「マドレーヌ」など、高品質と美味しさの追求を続ける企業である。現在は、和歌山市内に本店・和歌山近鉄店・イオンモール和歌山店の3店舗を展開している。
<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>
【考察力で道を切り拓く:理系研究から事業継承へ】
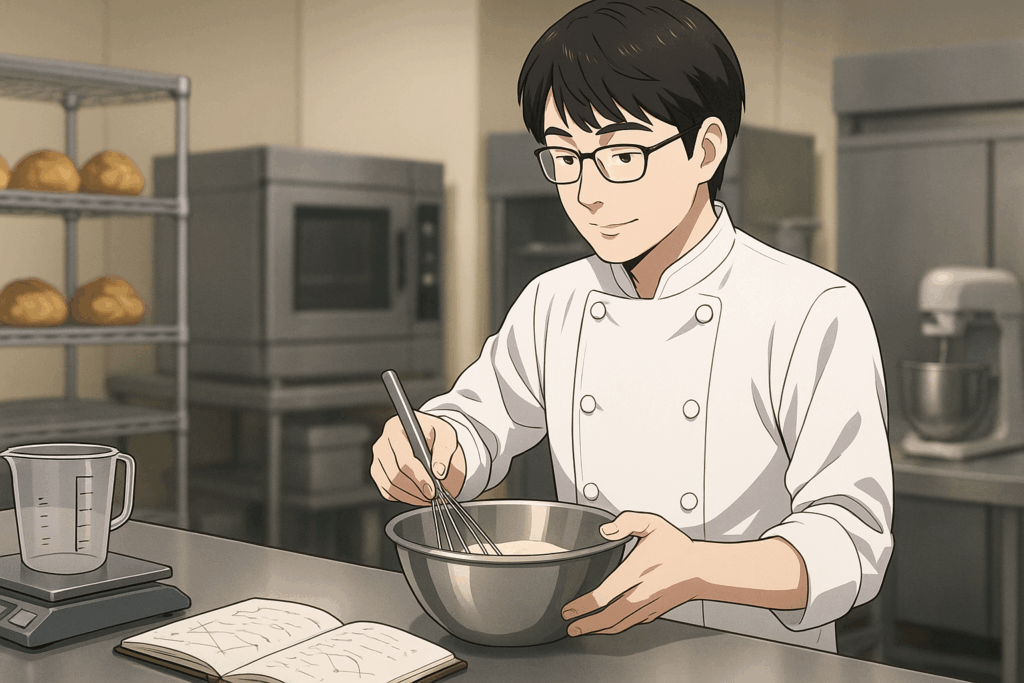
当店は1979年に創業しました。創業者である父は、さまざまな事業を経験したのち、洋菓子、なかでもケーキに将来性を見いだし、店を始めました。創業当時の洋菓子業界は作り方がまだ確立されておらず、各社が新しい製法を模索している時期でもありました。父は、当時日本で一般的でなかったマスカルポーネを使うティラミスのような新しい菓子にも、「あの味が美味しかったから作ってみたい」という思いで、手探りでも挑戦を続けていました。
私は幼い頃から、店が周囲の方々に「美味しい」と言われている姿を見て育ちました。家業を継ぐ決意をした最初のきっかけは、小学校5年生のときです。店の目玉商品である大きなシュークリーム「キャベツ」を初めて食べ、その美味しさに強い衝撃を受けました。そこから「この店を継いで、残したい」と強く思うようになり、これがケーキ屋を目指す原点になりました。
私は数学や化学といった理系分野が得意で、大学でもその道に進みました。実験や研究を通じて、失敗の要因を深く分析・考察し、次の成功につなげる経験を重ねました。こうした分析して考察する力は、現在のお菓子づくりや経営判断にも大いに生きています。大学卒業後は専門学校で技術を学び、さらに神奈川県で就職して現場経験を積みました。社長に就任したのは2021年(約4年前)で、先代である父の病気と逝去がきっかけです。継承にあたり、父は「やりたいことがあるならどんどんやれ」「味も変えたかったら変えていい」と背中を押してくれました。
取材担当者(高橋)の感想
井社長が、大学で培った分析と考察の力を、現在のお菓子づくりと経営に生かしている点が非常に印象的でした。幼少期に継承を志しつつも、まず学問で強みを磨き、その後に専門的修行を積むというキャリアパスは、計画的かつ合理的だと感じました。一見遠回りに見える道が、結果として大きな力になると学びました。

【「美味しさは前提」とし、お客様との接点を創造します】
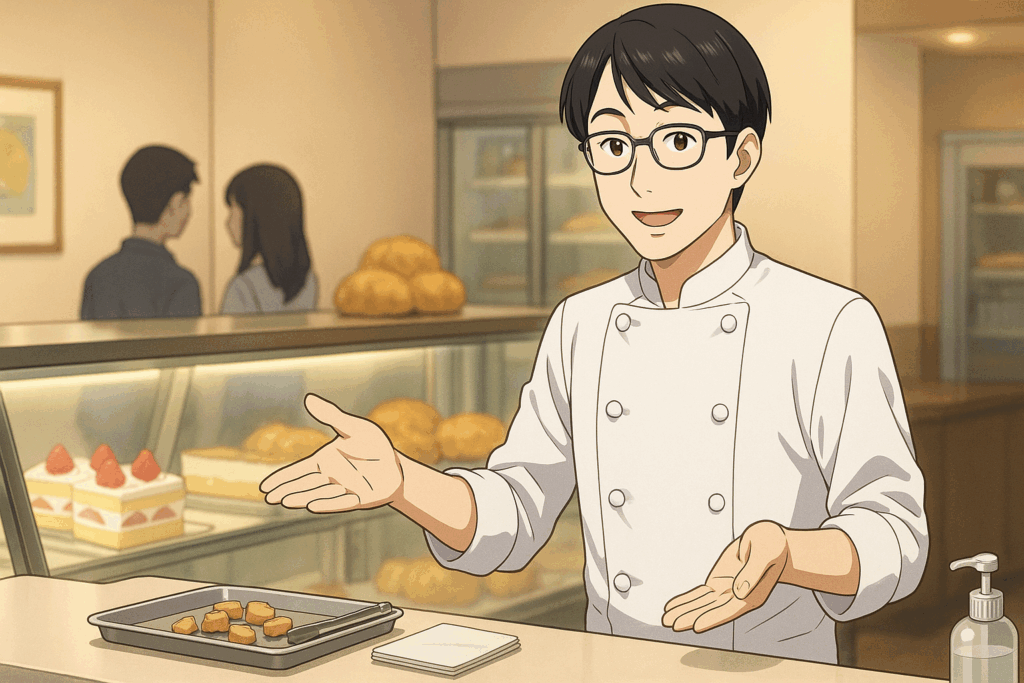
私が社長に就任した2021年頃は、コロナ禍と時期が重なりました。多くの飲食店が打撃を受ける一方で、ケーキ業界は比較的活発でした。外食が難しい状況で「家で少しいいものを」と考える層がテイクアウトでケーキを購入したためです。全国的にも、ケーキ店はコロナ禍で相対的に影響が小さかったという特異な状況にありました。
就任後の4年間で、私が重視してきたのは「お客様に食べてもらう機会を増やすアプローチ」です。従来は長年のファンや口コミでの来店が中心でしたが、「食べてもらわなければ美味しさは伝わらない」と考え、アプローチを見直しました。もちろん美味しいものを作ることは大前提です。そのうえで、試食の積極提供など食べてもらいやすくする工夫を行っています。
たとえば、クッキーを焼く際に生じる端の部分(端材)を試食に回すなど、適切なタイミングで提供しています。これは、新規顧客へのアプローチを広げ、一度体験していただければファンになっていただけるという信念に基づく取り組みです。今後、店舗が拡大し商品が広まっても、本店と同じ品質でがっかりさせず、喜んでいただける店づくりを続けていくことを目標にしています。
取材担当者(高橋)の感想
コロナ禍におけるケーキ業界の相対的な活発さに驚きました。また、駒井社長が「美味しさは前提」という高い基準を守りつつ、体験機会の創出に注力して変革された点から、時代に合わせた柔軟な企業努力の重要性を感じました。

【企業とお客様をつなぐ「販売職」の難しさと専門性】
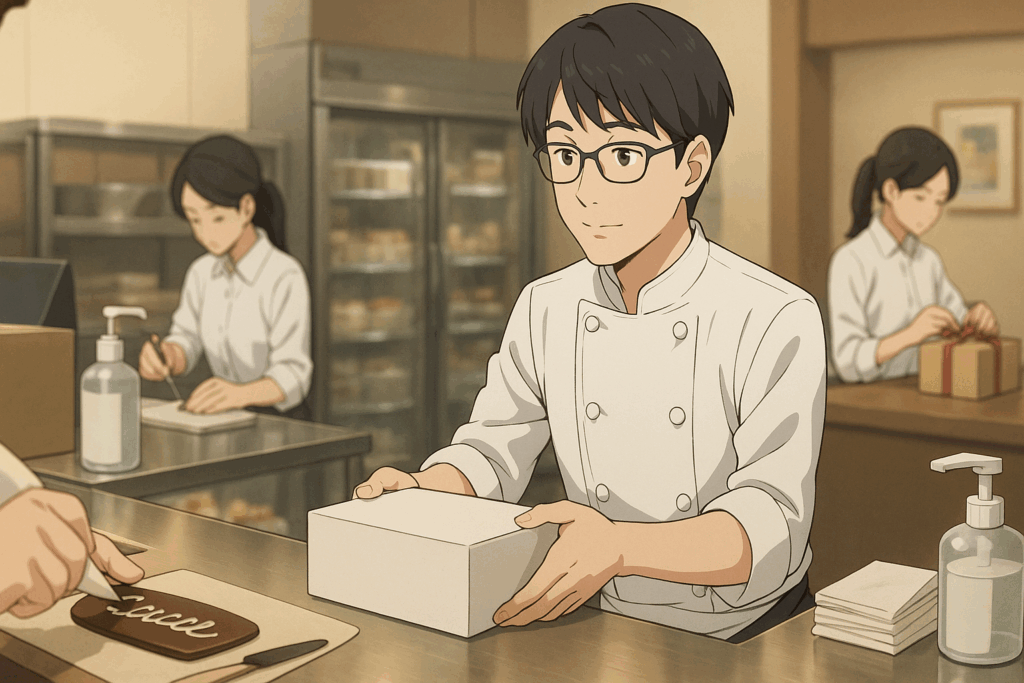
今後は店舗数を増やしていきたいと考えていますが、現在は販売員の人材不足が大きな課題です。販売スタッフが足りないため、以前は4店舗体制でしたが、現在は3店舗体制になっています。採用募集は積極的に行っていますが、希望者は集まりにくい状況が続いています。給与面での優遇を図っても、販売職は接客によるストレスが生じやすく、仕事の難易度が高いと捉えられがちです。
ケーキ店の販売職は業務範囲が広く、高いスキルと柔軟な対応が求められます。ファストフードのようにマニュアルが徹底された接客とは異なり、お客様が迷いながら商品を選ぶ時間が長くなる場合も多いです。急いでいるお客様への対応、アレルギーの確認、予約商品の受け渡しなど、状況に応じた最善の判断が欠かせません。
特にケーキは誕生日や記念日、お礼など特別な日のために購入されることが多いので、販売員には「失敗が許されない」状況で期待に応える丁寧な対応が求められます。筆ペンでのメッセージ記入や特殊なリボンの結び方など、細やかな技術も必要です。販売員は企業とお客様が接する最前線の接点であり、ケーキの美味しさだけでなく接客体験そのものが記憶に残って次回購入につながるため、極めて重要な役割を担っています。
取材担当者(高橋)の感想
販売職は、単に商品をお渡しするだけではなく、高度な専門知識と技術、そしてお客様の特別な瞬間を支えるホスピタリティが求められる難度の高い仕事だと理解しました。忙しい状況でも「サブールで買いたい」という期待に応えるというお話から、プロ意識の重みを学びました。

【物価高に挑み、幸せを形にする経営哲学と若手への期待】
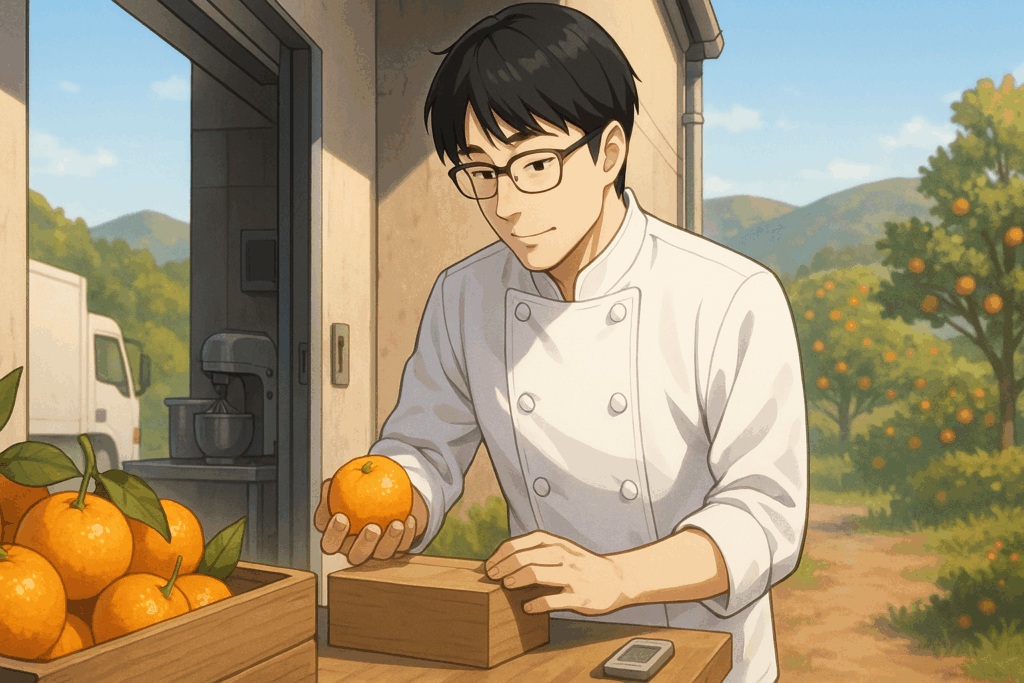
私たちが目指す未来は、「美味しいのは当たり前」という高品質を保ちながら、店舗が拡大しても本店と同等の品質でがっかりさせず、喜んでいただける店づくりを続けることです。ケーキは生活必需品ではありませんが、人を笑顔にし、幸せが形になったものだと私は考えています。
現在は原材料の価格高騰が深刻です。牛乳・卵・小麦粉など主要原材料は大幅に上がっています。ケーキは嗜好品であるため経営の工夫が欠かせませんが、新鮮食材の使用や鮮度管理の徹底は品質維持のために不可欠です。さらに、和歌山特産のみかんなど地元食材を積極的に活用しています。地元の方が親しむ食材の価値を県外の顧客にも伝えられるよう、地元フルーツを使った焼き菓子などの商品開発にも取り組んでいます。
これから社会に出る若者にお伝えしたいことがあります。社会では理不尽に直面することもありますが、やみくもに我慢する必要はありません。理不尽だと感じたら、なぜそうなのかを言語化し、相手に伝わるように働きかければ、改善の機会に変えられます。一方で、「筋トレ」のように、成長に必要な厳しい経験(勉強や経験の蓄積)は理不尽ではありません。そこは耐えることが重要です。
現代社会では「まず自分を守る」傾向が強いですが、少し頑張って互いに助け合う意識を大切にし、その輪を広げていく努力が必要です。短所は裏を返せば長所になり得ます。すべては捉え方次第であり、経験を通じて自分を成長させていくことが大切です。長年の既存顧客と新規顧客の双方を大切にし、「食べていただき、美味しいと言っていただける」機会を増やし続けることが、私たちの目標です。
取材担当者(高橋)の感想
駒井社長が、物価高の中でもケーキを「人の幸せが形になったもの」と捉え、品質と美味しさを妥協なく追求し続けている姿勢に深く感銘を受けました。また、「理不尽の言語化」によって状況を変える力と、成長に必要な経験は耐えるべきだという助言は、経験や知識の不足に危機感を抱く私たち学生にとって、具体的で力強い学びになりました。










