株式会社すしプラザ丸忠は、愛知県名古屋市を拠点に回転寿司店と居酒屋を展開する「山文・丸忠グループ」様の一社です。グループは、株式会社鮮魚丸忠、株式会社寿司丸忠、株式会社丸忠、株式会社山文、株式会社東貿など、6社で構成されています。グループとして仲卸業を行っているため、毎日市場へ出向き、仕入れから調理、提供までを一貫して行う体制を敷いています。この体制により、新鮮で上質な魚介を安定的かつリーズナブルな価格でご提供できることが最大の強みです。
弊社では現在、「回転 でらうま寿司 まるちゅう」「うみっ子」(回転寿司)、「どんたかたん」(居酒屋)の3ブランドを運営しています。企業理念は「仲卸が本気で取り組む寿司屋」をコンセプトとし、お客様第一主義のもと、食を通じた社会貢献を目指しています。感動、感謝、喜びを共有し、弊社とご縁のあるすべての方々が幸福になれるよう、地道な成長を遂げていくことを目標としています。
<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>
【異色の経歴:現場のプレイヤーから経営者への転身】
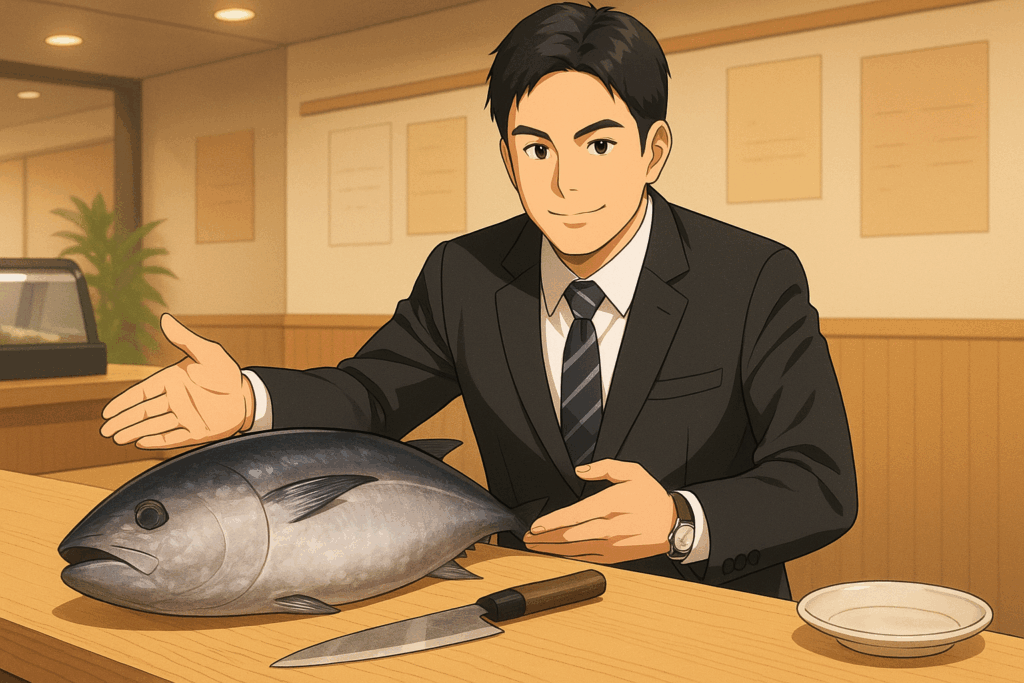
私は、先代社長の引退に伴い、社長職を引き継ぎ、社長に就任しました。社長になる以前から、私は長年、寿司職人という現場のプレイヤーとしてキャリアを積んできました。現場に立ちながらメニュー開発に携わり、少しずつ経営にも関与するようになりました。社長となった今も、私は現場のプレイヤーとしての役割を兼任しています。これは、私自身が好きで続けていることでもあります。私が社長に就任できた背景には、数字に対して常にストイックに取り組み、誰よりも目標を必ず達成してきたという実績があります。
そして、「こういう会社にしたい」という強い思いを常に持ち続けていました。私自身が若い頃に辛いと感じた経験があったため、今の若い世代や社員には同じ困難を経験させたくないという強い思いがあったのです。現場のプレイヤーの立場だけでは達成できない変革を実行するため、経営者という今の立場に就きました。
取材担当者(高橋)の感想
現場の職人として活躍されていた方が、確かな実績と強い使命感を持って経営のトップに就任された経歴は、非常に魅力的だと感じました。経営者となった今もプレイヤーとしての感覚を大切にされているのは、現場の課題を深く理解されている証拠だと思います。過去の経験から「こういう会社にしたい」という明確なビジョンを持ち、自ら行動してその実現を目指されている姿勢は、これから自身のキャリアを築く就活生にとって、大きな学びになるのではないでしょうか。

【組織変革:給与の向上と公正な評価制度の確立】
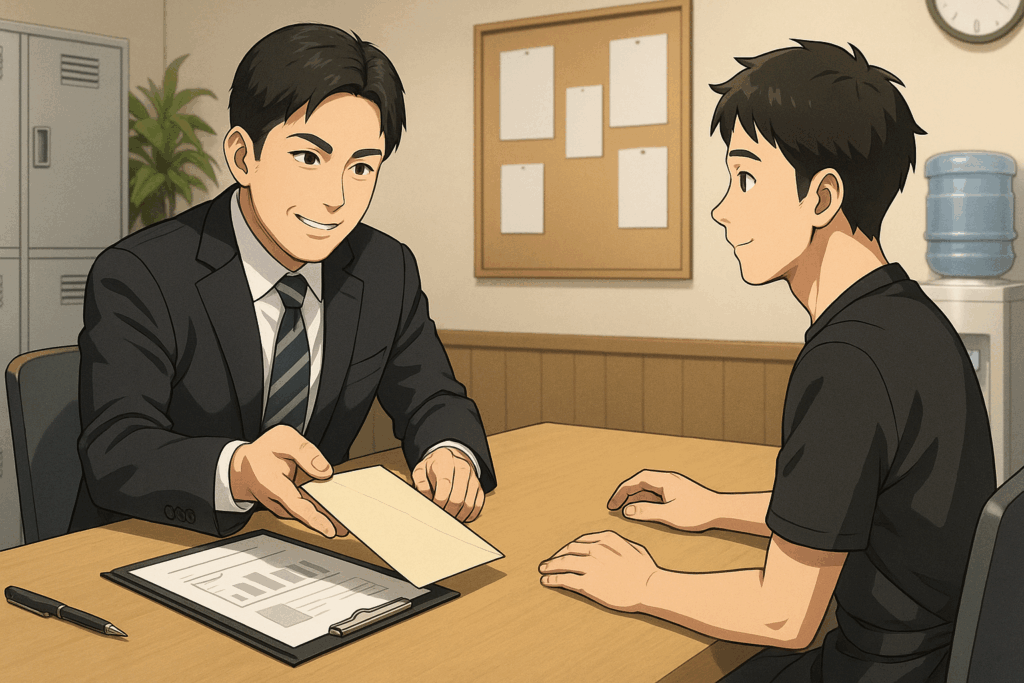
私が具体的に目指している組織のあり方は、まず従業員の給与水準を引き上げることです。従業員が自身の出した実績に対して正しく評価され、しっかりと報われる仕組みが重要だと考えています。単に給与を引き上げるだけでなく、実績に応じて適正に評価することが不可欠です。この公正な評価制度と報酬の仕組みによって、社員は働くやりがいを強く感じられます。結果として、これは優秀な人材の定着にも繋がると確信しています。
私の経営者としての原動力は、現場で働く若い世代や社員が、以前私が感じたような辛い経験をしないようにしたいという強い思いです。この思いを実現するため、給与面や評価面での変革を、最優先事項として進めています。
取材担当者(高橋)の感想
実績に対する正当な評価と給与の向上を経営の最重要課題とされている点に、久野様の現場出身者ならではの強い責任感を感じました。社員が抱える困難を自分事として捉え、経営者としてその根本的な解決を目指す姿勢は、これから入社を考える学生にとって、信頼できるリーダー像だと思います。従業員一人ひとりが報われる環境づくりを目指すスタンスは、学生が求める理想的な職場環境だと感じます。

【競争優位性:仲卸直営が生む徹底的な商品力】
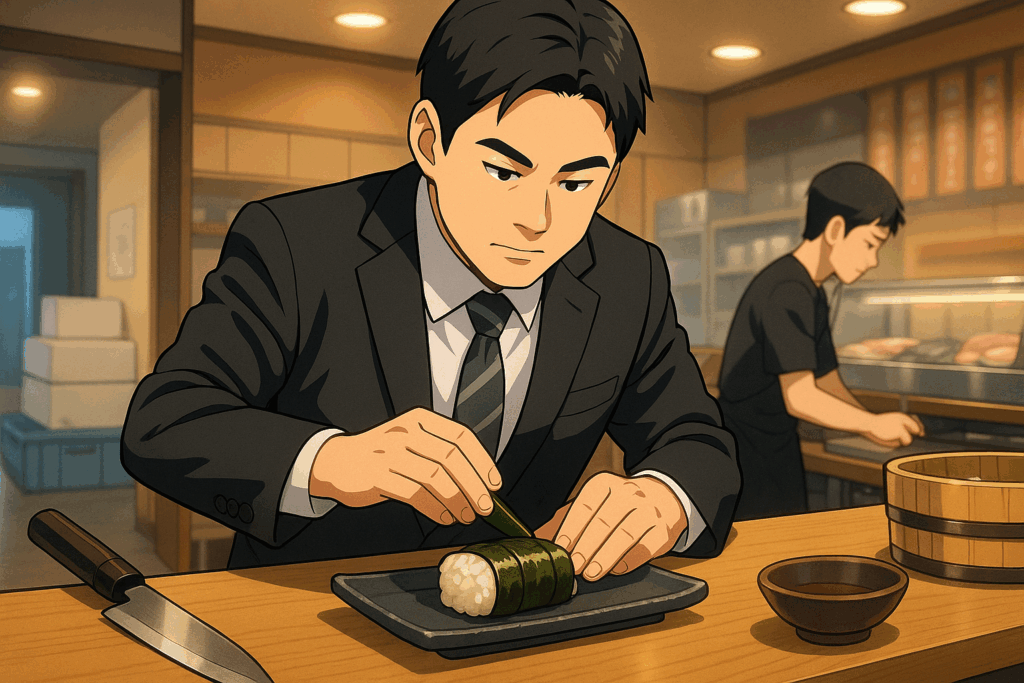
弊社の最大の強みは、市場の仲卸機能を基盤とする商品力です。このアドバンテージがあるからこそ、他の競合他社にはない圧倒的な優位性を確立し、新鮮で質の高い魚介類を安定的に仕入れることができます。私たちは、一般的な「入りやすいが本格的ではない」回転寿司チェーンと、「本格的だが敷居が高い」高級寿司店との間を狙った事業を展開しています。価格設定は決して安価ではありませんが、職人が愛情を持って商品を作り上げること、そして提供の細部にまでこだわる職人肌のこだわりが特徴です。
例えば、提供時にはしっかりとした陶器を使用したり、名物である「包み寿司」一つをとっても、あえて一手間を加えています。回転寿司業界では提供スピードが重視されがちですが、弊社はあえてスピードを過度に重視せず、商品一つひとつに手間をかけ、シャリの温度にまで徹底的にこだわっています。外食は「たまの贅沢」であるため、お値段をいただく以上は、心を込めた質の高い商品を提供したいと考えています。
取材担当者(高橋)の感想
仲卸という強みを最大限に活かしつつ、単なる大量生産ではなく、職人の技術と愛情に裏打ちされた商品を提供されている点に、同社の食に対する真摯な姿勢を感じます。スピードよりも品質と手間を優先し、本格的な寿司が好きな層もファミリー層も満足させるというバランス感覚は、企業が市場でどうポジションを取るべきかを考える上で、非常に勉強になる視点だと思います。

【若い世代との共創:会社の未来を作るための人材戦略】
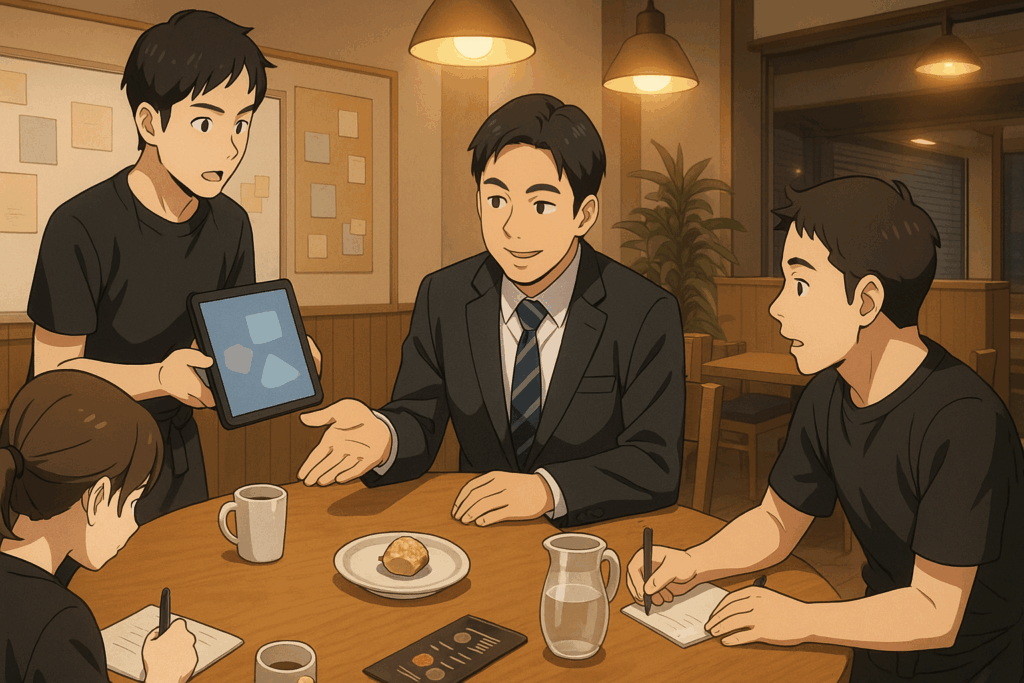
新しい会社づくりにおいては、若い世代の意見や発想を積極的に取り入れる姿勢を重視しています。私たち経験豊富な社員は、営業利益や過去の失敗といった制約から、無意識のうちにアイデアに「ストッパー」をかけてしまいがちです。
しかし、若い社員が持つ、制約のない率直な発想が、時に「その手があったか」と感じるような革新的なヒントになることがあります。私はアルバイトを含む多様な従業員から意見を募り、現場の声を吸い上げて会社づくりに役立てています。現場でのプレイヤーとしての経験があるからこそ、お客様やスタッフとの会話から得られる生の声が、最高のビジネスのヒントになると考えています。
若い人たちと一緒になって会社を作っていく意識を持つことで、働くやりがいにも繋がり、最終的に会社全体の成長に繋がると信じています。特に新しい事業を考える中で、経験者にはない斬新な発想を期待しています。若い力が活躍できる新しい事業を展開することで、その姿を見た人が「ここで働きたい」と感じ、結果として人材が集まるという好循環を目指しています。
取材担当者(高橋)の感想
社長自らが、若い世代の「先入観のない意見」や「単純に面白いこと」を求めて、アルバイトにも積極的にアイデアを求められていることに驚きました。経営者としての視点だけでなく、プレイヤーとしての視点も持っているからこそ、現場のスタッフが何を面白いと感じるか、何にやりがいを見出すかを深く理解し、実践できるのだと感じました。従業員一人ひとりの考えを聞き入れ、皆で会社を成長させるというスタンスは、学生が求める理想的な職場環境だと思います。

【業界の現状と未来戦略:コスト増に立ち向かう出店計画】
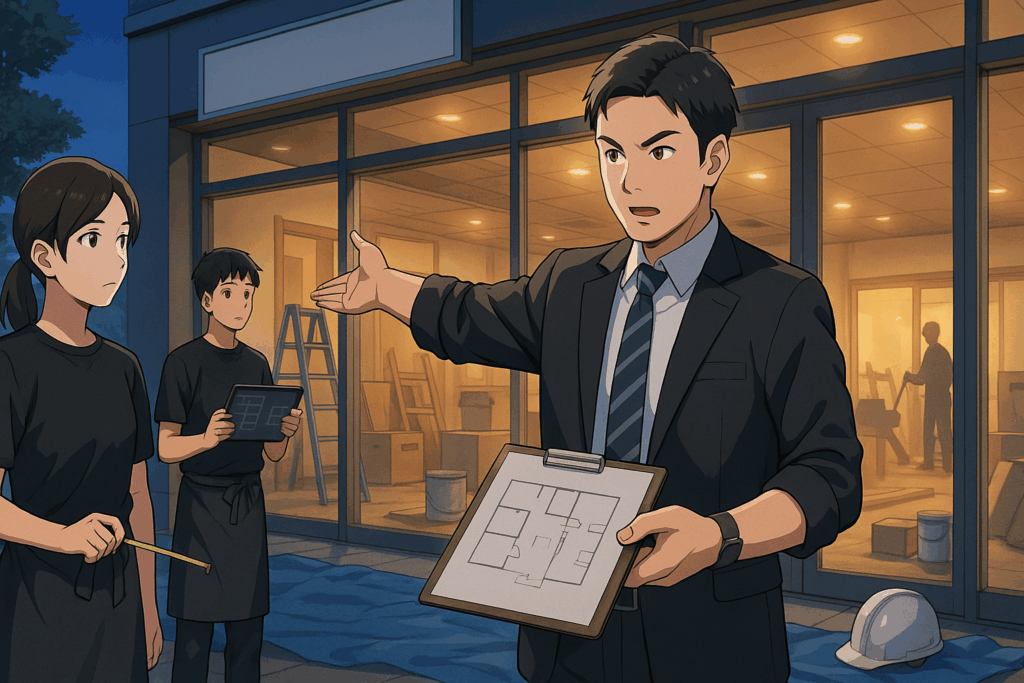
現在の飲食業界は、物価高騰や最低賃金の上昇といった二重のコスト増に直面しており、厳しい戦いを強いられています。景気の回復が十分でない地域もあり、どこの会社も苦戦していると感じています。特にコロナ禍を経て、アルコールの需要自体がかなり減少し、居酒屋業態では苦戦している地域が多いのが現状です。
一方で、回転寿司に関しては、売上はコロナ以前あるいはそれ以上まで回復した店舗もあります。しかし、正社員の採用は依然として大きな課題です。アルバイトは地域によっては集まるものの、正社員として長く働いてくれる人材を確保するのは困難です。主な採用手段は、調理学校や水産の学校への求人、そしてアルバイトから社員への登用です。
今後の売上向上戦略としては、社員への還元(給与アップ)を実現するためにも、出店(=店舗数の増加)を最も重要な手段として掲げています。出店によって売上を創出していくことが重要です。
ただし、闇雲に拡大するのではなく、まずは既存店の売上と運営体制をしっかりと固めてから、新規事業や未来型の事業の出店を計画しています。若い力が活躍できる新しい事業を展開することで、「ここで働きたい」と感じる人が増え、人材が集まってくるという好循環を目指しています。
取材担当者(高橋)の感想
物価高騰や人手不足といった業界全体の課題を率直に語られながらも、その解決策として「出店」という明確な目標を打ち出し、若い世代の活躍の場を創出するという未来志向の戦略が印象的でした。久野様が会社の「透明感」を重視し、現場にも顔を出し、正面で寿司を握るなど、自ら行動して従業員や求職者との心理的な距離を縮め、人を集める工夫をされている点も、他社にはない魅力だと感じました。この姿勢こそが、今後の成長と人材確保の鍵になると思います。










