株式会社エイチケイアール(HKR)は、RDCグループの一員です。私たちは、グルメ回転寿司「函太郎(かんたろう)」を中心に、とんかつ「かつきち」、ピッツェリア「Pizzeria AMORINO」などの飲食店を国内外で運営しています。特に「函太郎」では「函館を握る」を合言葉に、函館から日本一の寿司を目指し、素材と鮮度、出来立てにこだわり、「美味しさに一生懸命」日々精進しております。お客様の貴重な時間を「食」を通してより豊かな時間に変えていただけるよう、「歓んで喜ばす」の精神で、従業員一人ひとりが夢や目標を持って高め合える企業文化を醸成し、お客様に最高の満足を提供できる店舗づくりを目指しています。
<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>
【危機を成長の機会に変える:26年のキャリアとコロナ禍での進化】
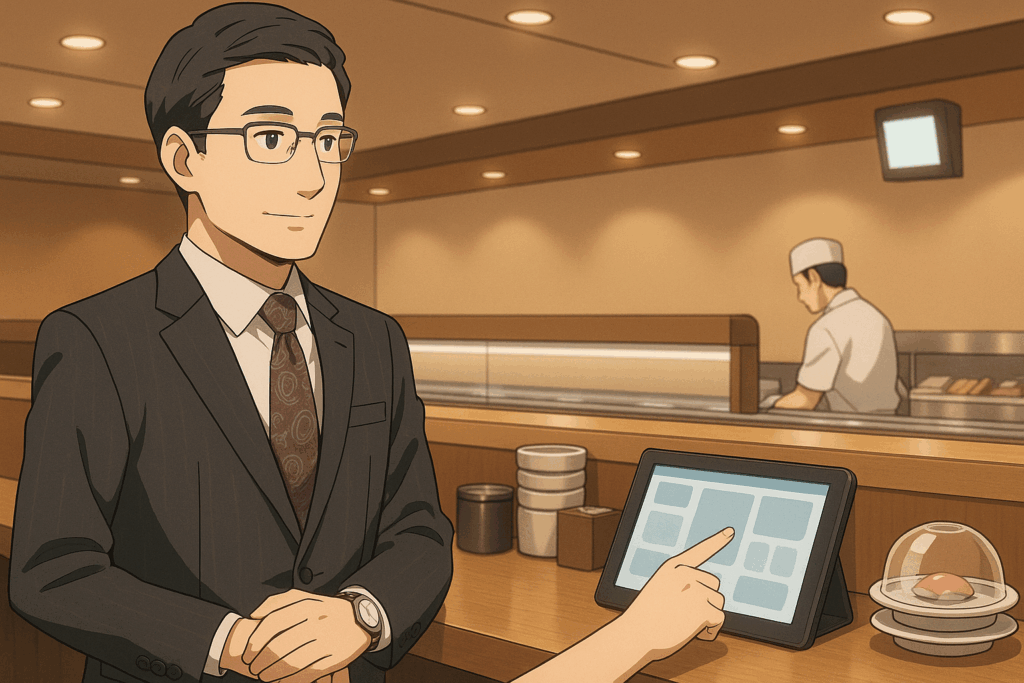
私は1999年にRDCグループに入社し、飲食業界で約26年のキャリアを積んでまいりました。入社から2017年までは仕入れ業務を主に担当していました。当時は寝る間を惜しんで働く時期もありましたが、そこで得られた経験や人脈が、今の仕事の土台になっています。これまでのキャリアでは、リーマンショック、牛海綿状脳症(BSE)の危機、東日本大震災など、様々な危機を乗り越えてきました。その中でも、コロナ禍は最大のピンチであったかもしれません。
飲食業界、特に居酒屋業態は時短営業で夜の売上の大半を失う状態に追い込まれました。ビュッフェスタイルも、業態自体を根本的に見直さなければならないほど厳しい状況でした。一方、私が当時見ていたとんかつ業態は、比較的昼間の売上比率が高かったため、グループ内では業態によって明暗が分かれることとなりました。しかし今になって思えば、そういった危機を乗り越えるたびに、会社はより筋肉質で強靭な体質に変わってきたと実感しています。
コロナ禍で大きく進んだのが、デジタルトランスフォーメーション(DX)によるシステム化です。回転寿司の基本は、レーンに流れる寿司をお客様が取る方式ですが、コロナ禍ではそれを避ける必要が生じました。そこで、注文を受けてから提供する方式(100%オーダー制)へと切り替えました。従来の仕組みのままでは、注文が集中するとオペレーションが崩壊しかねません。この変革を可能にしたのが、タッチパネルシステムの導入です。握り手が頭で全てを記憶しなくても、システムで正確に対応できるようになりました。
このシステム化は、食品ロス削減というSDGsの観点からも重要です。寿司は握り手の手を離れて流した瞬間から時間との勝負となります。時間が経った寿司は下げなければならず食品ロスが発生しますが、注文分だけを提供できればロスは抑えられます。また、HKRは北海道、東北、関東、大阪など全国に店舗を展開していますが、コロナ禍でウェブ会議システムが導入され、全国に散らばるマネージャーや店長との情報共有が容易になったことも大きな進化です。危機は必ずありますが、その中でいかに会社が変わっていくかが最も大事だと考えています。
取材担当者(高橋)の感想
松本社長が、長年の経験の中でリーマンショックや震災、そしてコロナといった様々な危機を乗り越えてこられた歴史には感銘を受けました。危機を単に耐え忍ぶのではなく、「会社がより筋肉質に変わる機会」と捉え、DX推進によって働き方やオペレーションを根本的に改善されている姿勢には、企業としての強靭さを感じます。特に飲食業界のような現場中心の業界で、デジタル技術を効果的に活用し、新しい働き方を実現していることは、将来性を見極める上で非常に重要な視点だと感じます。

【競争激化に挑む:目標達成に必要な「人への投資」と教育戦略】
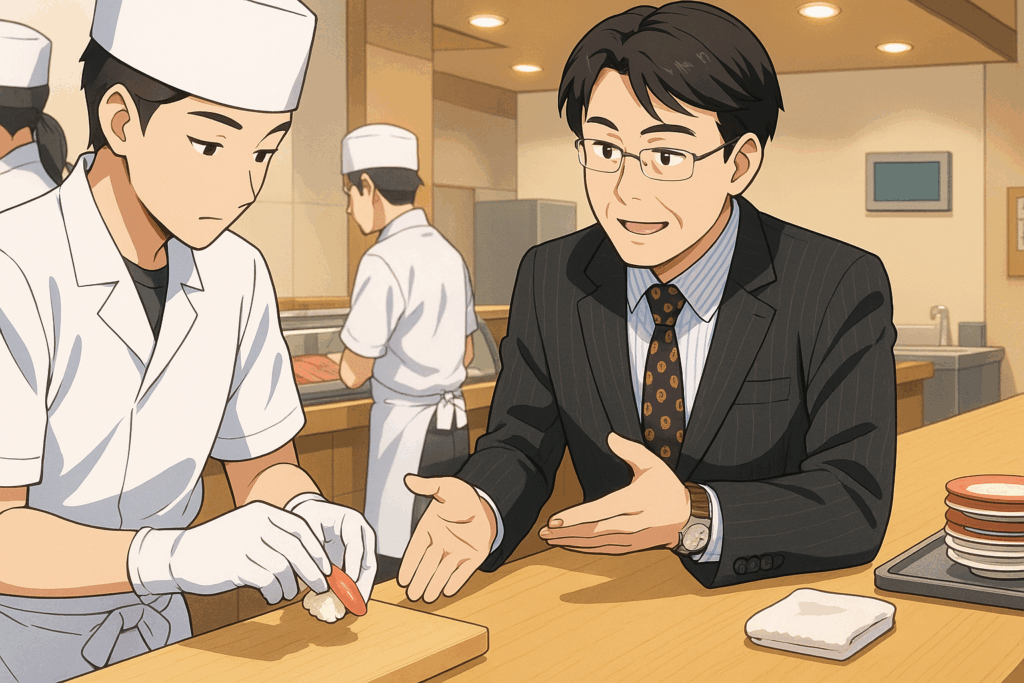
日本は少子高齢化が進み、将来的に働く人もお客様(食べる人)も減っていくという厳しい市場環境にあります。年間出生数は50年前の半分以下です。飲食店ポスト自体は減っていませんが、外食業界全体の規模が縮小傾向にあるため、売上は分散し、競争は激化しています。今後は業界全体で淘汰が進む時代が必ず来るでしょう。その中でいかに勝ち残っていくかが、私たち外食企業にとって最大の課題です。
RDCグループ全体では、来年度500億円、将来的には700億円、1000億円という売上目標に向かって動いています。この目標を達成するためには、店舗展開だけでなく、人材の力が不可欠です。単に社員数を増やすだけでなく、今働いているパート・アルバイトの方々も含めて、より高度な業務ができるようにスキルアップさせる教育体制の強化が重要です。例えば、学生アルバイトでも夜のシフトで握りに入れるようにするなど、パートだからここまで、社員だからここまで、という壁をなくしていく必要があります。
しかし、外食業界、特に和食系は採用に苦戦しているのが現状です。和食系よりも洋食系やカフェの方がアルバイト応募が集まりやすい傾向があります。これは、お寿司屋に対して「魚の匂いがする」「裏が濡れている」**といったネガティブなイメージや、外食産業特有の労働環境、特に土日や祝日が忙しく休みにくい点が敬遠されがちであるためと考えられます。特に大卒の採用が少ない状況です。
私たちは、ネガティブなイメージを払拭し、興味を持ってもらうための発信を継続しています。さらに、入社後の教育や、社員のケア(コミュニケーション・相談体制)を強化することで、定着率向上を図っています。仕事を通じて「成長実感」が得られることが、人材をつなぎ止める上で非常に重要だと考えています。
取材担当者(高橋)の感想
少子化による働き手の減少は、学生にとっても切実な問題です。その中で、企業が売上目標達成のために、既存従業員のスキルアップと教育に注力している点は非常に魅力的だと感じました。採用競争の激しい中、外食産業が抱えるネガティブなイメージに対し、教育制度の整備や入社後のケアに力を入れていることは、長くキャリアを築きたい就活生にとって大きな安心材料になるでしょう。

【飲食業が担う社会貢献性:世界と繋がる「アンカー」の役割】
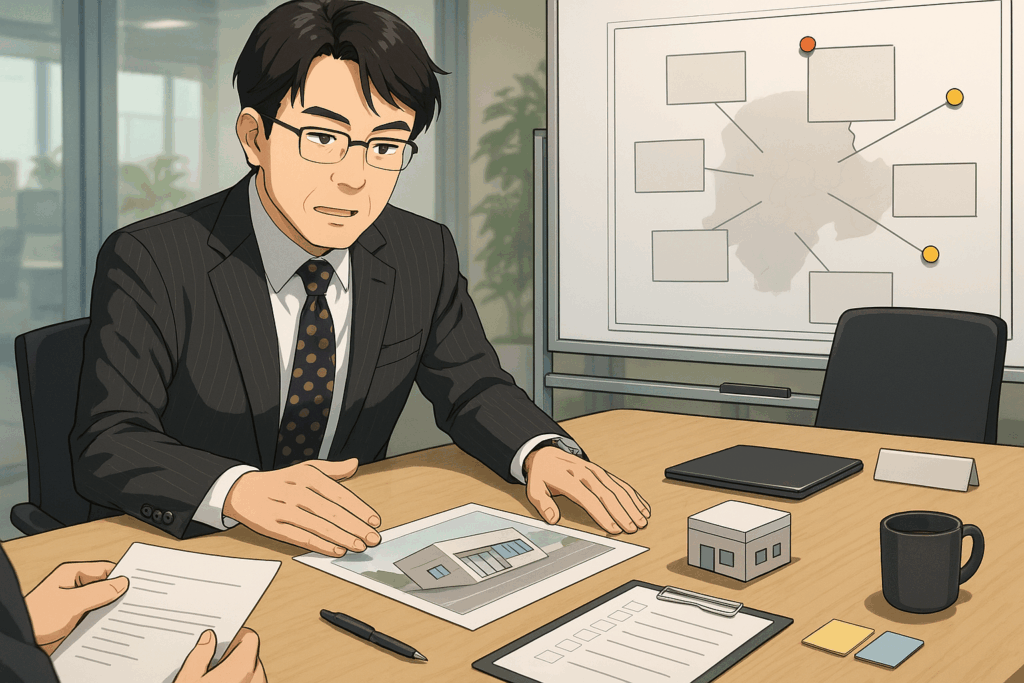
飲食業で働くことの最大のやりがいは、お客様に喜んでもらえることで「ありがとう」という感謝を直接いただける点だと思います。長く続けている従業員の大部分も、「お客様に喜んでもらえることが非常に嬉しい」というやりがいを強く感じています。しかし、飲食業の魅力はそれだけにとどまりません。私たちの仕事は、世の中のインフラ全てに関わる、非常に奥深い仕事です。料理の提供には、電気・水道・ガスといったインフラはもちろん、食材の仕入れ、物流、貿易、さらには店舗建設に関わる建築業者の力も必要です。
特に、お寿司の食材は世界中から来ています。海外の工場で加工する人たちや物流業者、貿易会社など、非常に多くの人が関わって初めて店に寿司ネタが届きます。お客様に寿司を握って提供する行為は、世界中の人が携わった食材に対する「最終仕上げ」なのです。握り手は、その食材の最高の状態をお客様に届けるという、重要な「アンカー」(最終走者)の役割を担っています。ここで私たちの仕事が崩れると、全てが終わってしまいます。この仕事は「たかがお寿司」に見えるかもしれませんが、その裏側にあるストーリーや社会全体との関わりが見えてくると、仕事は非常に面白くなってくるはずです。
この仕事は、人としての成長を促す貴重な機会でもあります。見知らぬ人に会って接客し、対応する経験は、人間力を高めます。社会に出るための基本、すなわち「いらっしゃいませ」「ありがとうございました」といった感謝の気持ちを学ぶ上でも、学生時代にアルバイトとして経験することは大いに推奨できます。
取材担当者(高橋)の感想
飲食業を単なるサービス業ではなく、「世界中のインフラと人が携わる最終仕上げ」と捉える松本社長の視点は、この仕事のスケール感と重要性を教えてくれました。私たちが求める「社会への貢献」や「熱い気持ち」が、この業界でこそ実現できる可能性があると感じました。自分の仕事が社会のどこに役立っているかが見えた時に仕事は楽しくなるという言葉は、仕事選びの重要な学びになりました。

【強いブランド力を守る:品質維持へのこだわりと未来への展望】
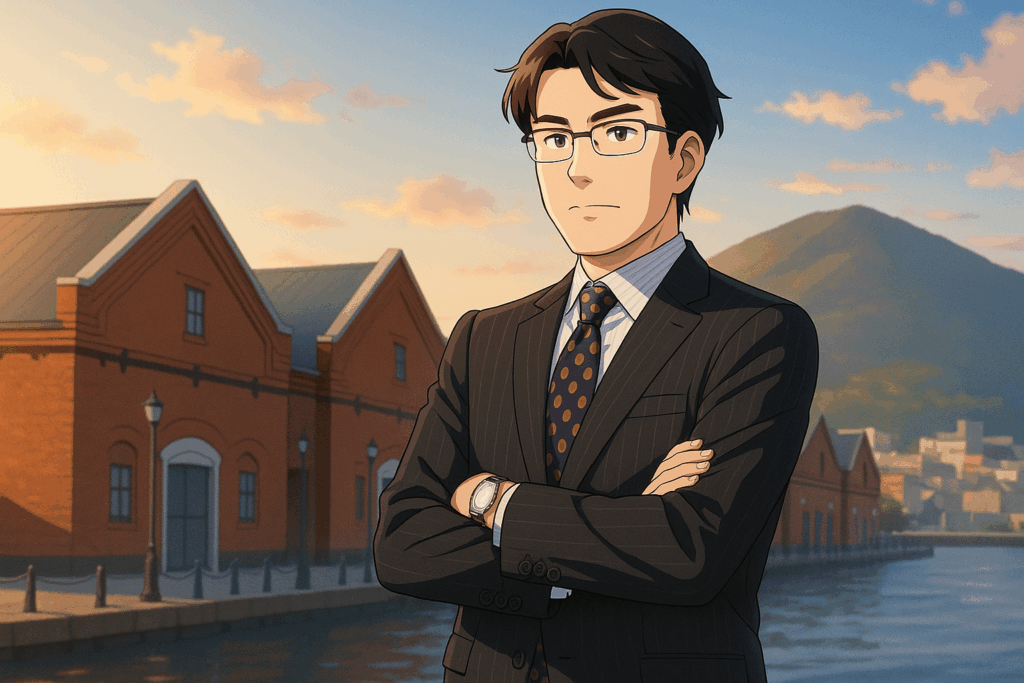
RDCグループ全体では、来年度500億円、その先の700億円、1000億円という売上目標に向かっています。私たちは今後も成長し続けます。私たちが運営する「函太郎」は、非常に強いブランド力を持っています。特に「函館」というブランド力が強く、函館を代表するグルメ回転寿司として認知されているため、どの地域でも他の回転寿司より1店舗あたりの売上が高いという特徴があります。物件や出店依頼はひっきりなしに寄せられています。正直に言って、今の弊社(HKR)の売上を短期間で2倍にも3倍にもできると考えています。
しかし、それでもすぐに店舗を増やさないのは、人の力が最も重要だと考えているからです。グルメ回転寿司は、100円寿司とは違い、それなりの価格をいただき、職人がきちんと握ります。そのため、最終的に人の力が非常に大きいのです。人がいないと、出店したくてもできないのが現状です。例えば札幌エリアでも出せる物件はありますが、現状では人員を確保できていないため出店できていません。
店舗数を増やすことは簡単ですが、私たちが目指す「函太郎」のグルメ回転寿司としてのコンセプト、接客、店のクオリティを維持するためには、人材を集め、体系的に教育する仕組みが必要です。店舗の質が落ちてしまうくらいなら、闇雲に出店すべきではないと考えています。私たちは教育制度や研修を強化していますが、当社に参画してくれる人材が不足しているのが今の最大の課題です。
今後は国内だけでなく、世界展開も視野に入れており、ソウルにも店舗を出店しました。また、来年秋頃には、長らく出していなかった函館での新店舗がオープンします。この店舗は赤レンガ倉庫のすぐ近く、海沿いに位置し、窓越しに赤レンガ倉庫と函館山を望める景観を計画しています。函館の観光スポットとなる店になるはずです。私たちは、人を増やし、教育に投資し、DXの手段も活用しながら、今後も目標に向かって成長していきます。
取材担当者(高橋)の感想
函太郎のブランド力の強さと、それにもかかわらず、店舗のクオリティ維持のために「人がいなければ出店しない」という判断に、松本社長の品質への強いこだわりを感じました。グループとして大きな成長目標を掲げる一方で、その鍵を人への投資と教育だと明確に位置づけている点は、安心してキャリアを築ける環境だと感じました。函館の新店舗は、ロケーションからも意気込みが伝わってきて、非常に楽しみです。










