三陽工業は、日本の製造現場を元気にするというビジョンを掲げ、製造業と製造派遣業(HR事業)の二つの軸で事業を展開しています。 三陽工業様は単なる利益追求にとどまらず、製造派遣業と中小製造業において、「真面目に一生懸命働く人が報われる世界をつくる」という存在意義(パーパス)を目指されています。今回は、日本の製造現場を元気にするビジョンと「真面目に一生懸命働く人が報われる世界」というパーパスを、製造×HRの二軸体制でどう実装するのか、同社代表にじっくりと話を聞いた。
<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>
【使命感から入社、そして会社の立ち位置を根底から変えたリーマンショック】
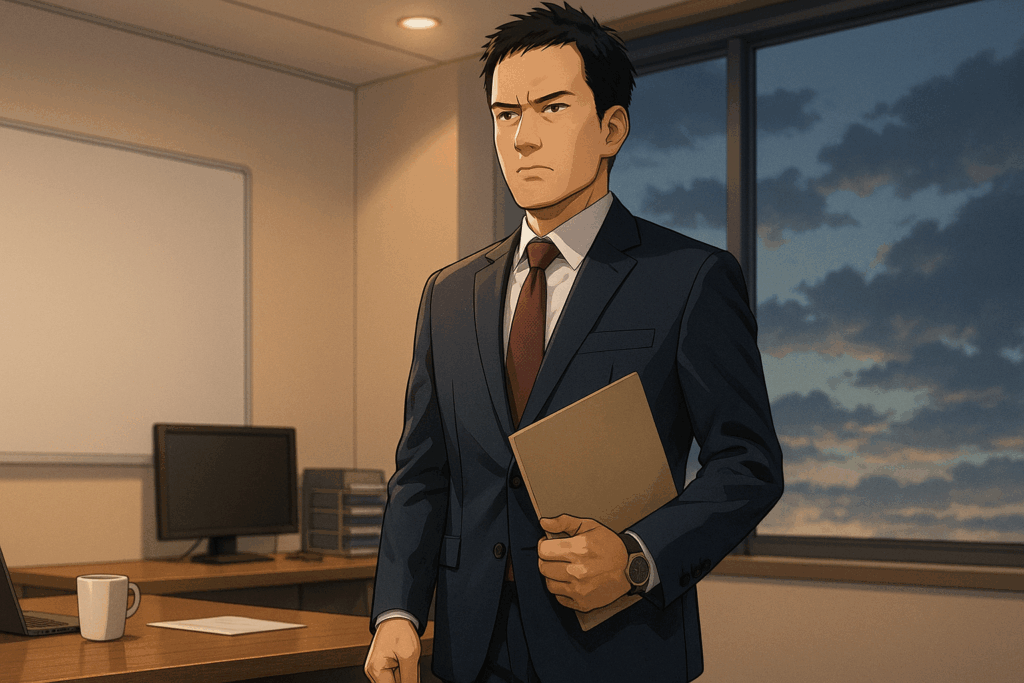
私は20年前、27歳のときに会社に戻りました。元来、事業としては3代目、会社としては2代目にあたります。会社ができたのは1980年、私が3歳のときでした。いつから会社を継ぐと思っていたかという質問をよくされますが、小学校3年生のころからですと答えています。具体的な仕事内容はわかっていませんでしたが、なんとなく「それはやらないといけないんだ」という漠然とした使命感や責任感のようなものは常にありました。
大学卒業後5年間は会社員として生活し、2005年に入社しました。そして入社してわずか3年後の2008年、私たちにとって非常に大きな転機となるリーマンショックが発生しました。ひと言でいうと、世界経済全体が冷え込んだ、そんな大きなショックでした。ものが売れない、サービスが売れない、結果としてものがつくれないという状況に陥ったのです。
入社3年後、当時31歳でしたが、このままではダメだという強い危機感を抱きました。この危機的状況で、売上はなんと1年間で4割も激減しました。当時の売上高である7億1,800万円という数字は、年間で5億円売上が落ちたことを示しており、私にとって一生忘れられない数字として胸に刻まれています。この大幅な売上の落ち込みがあったからこそ、それまでの危機感が行動へとつながり、新しい三陽工業のスタートとなりました。
取材担当者(高橋)の感想
井上社長が幼少期から抱かれていた使命感が、会社経営の土台になっていたのだと感じました。特に、世界経済を揺るがす危機(リーマンショック)を単なるマイナスではなく、変革の最大の機会として捉え直し、積極的に行動に移されたというエピソードは、激動の時代を生きる私たち就活生にとって「物事の捉え方」の重要性を教えてくれます。また、わずか1年で売上が4割も落ちるという想像を絶する苦境に直面しながらも、その数字を忘れることなく教訓としている姿勢は、事業への強い覚悟を示すものだと思いました。

【既存概念を打破した「やったことがないこと」への挑戦とV字回復への軌跡】
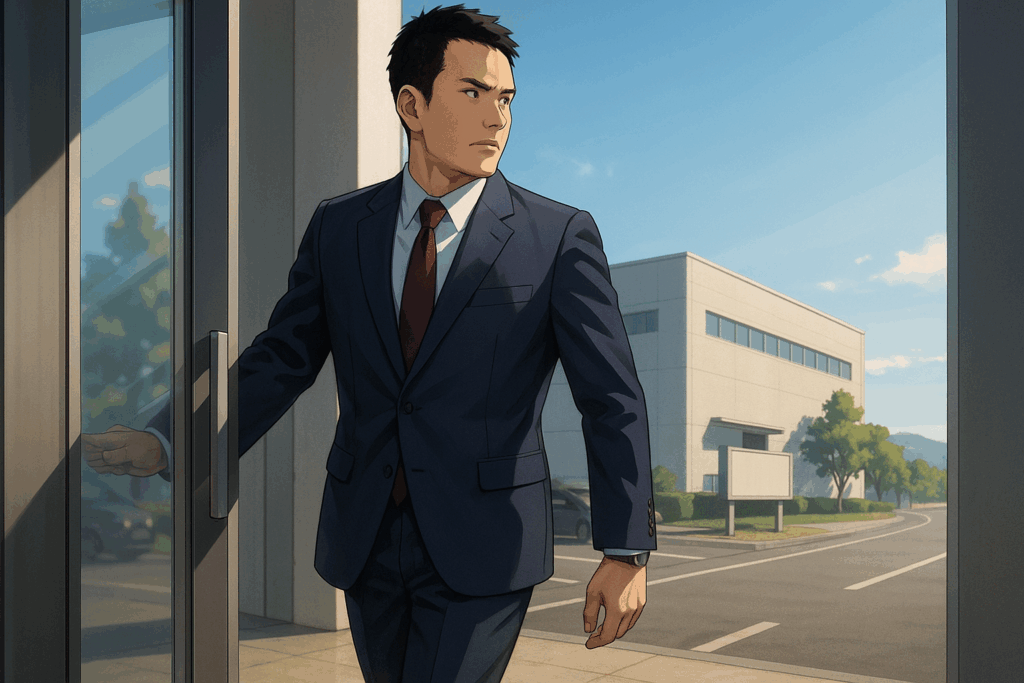
リーマンショック後の危機感を受けて、私たちが行った最初の大きな施策は、それまでの事業領域を取り払うことでした。当時、私たちのビジネス領域は、本社のある兵庫県明石市から車で30〜40分程度の圏内に限られていたのです。私たちはこの枠組みを解除し、さまざまな課題が出てくることは承知の上で、とにかく「やらないといけない」と決意しました。車で1時間かかろうが2時間かかろうが、そこにお客様がいるのであれば取り組むべきだと判断しました。さらに、県をまたいだ積極的な進出を図るため、拠点営業所を新設する必要がありました。
2011年に初めての県外拠点として、岐阜県に岐阜営業所を開設しました。この県外進出を皮切りに、その後約10年間で拠点を増やし続け、現在では27の営業拠点を有しています。社長就任前は専務という肩書きでしたが、この拠点展開はすべて自分の意思で実行してきました。
私たちはこの新しい動きの中で、数多くの「やったことがないこと」にトライ&エラーを繰り返して進化してきました。こうした挑戦を積み重ねた結果、売上は底の7億1,800万円から10倍を超える金額まで成長し、V字回復を遂げました。前期の第45期では、この「やったことがないこと」への挑戦が1,208件に上っています。私たちは過去の自分たちを超えて成長しています。
取材担当者(高橋)の感想
危機を前にして、それまでの「変わることがリスク」という考え方から脱却し、「やったことがないこと」に挑戦し続けることで道が開けたという事実に感銘を受けました。特に、それまでの商圏に縛られず、県外へ積極的に拠点を開設していくという行動力と決断は、地域の中小企業という枠を超えて成長するために不可欠だったと感じます。私たちも、これまでの常識や固定概念にとらわれず、自ら課題を見つけ、挑戦する姿勢を持つことが、将来の成功につながると確信しました。

【「人」を正社員として育て、M&Aで社会問題に立ち向かうHR戦略】
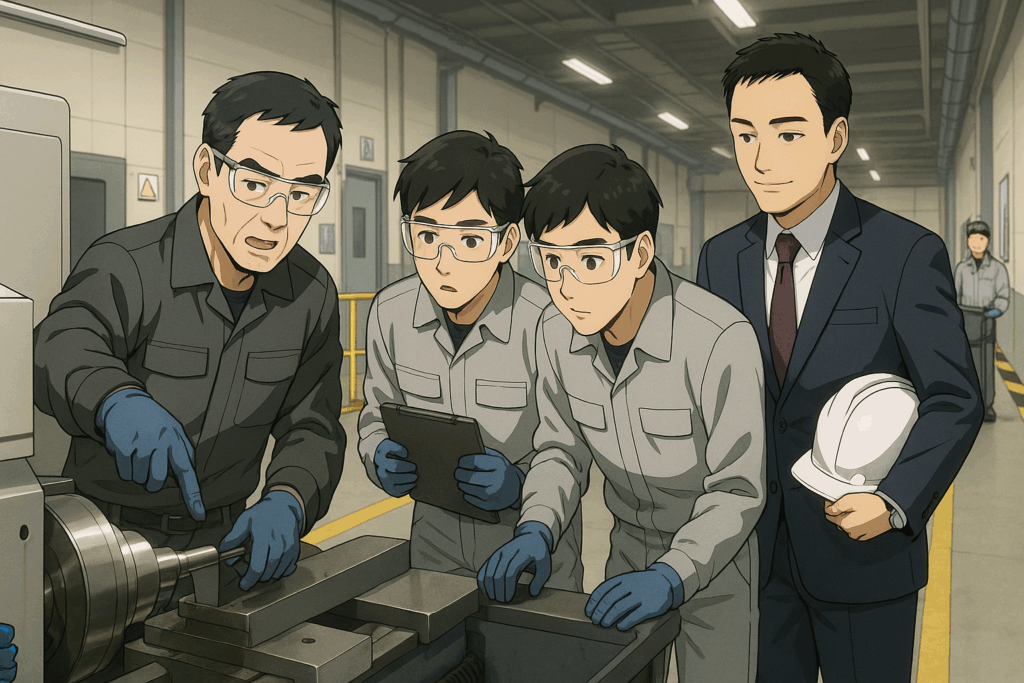
三陽工業の成長を支える柱の一つである製造派遣業は、社内では「HR事業」と呼んでいます。私たちは単なる人材の採用と派遣とは一線を画し、採用・定着・育成の三本柱で人を育てることに特に力を注いでいます。派遣の世界では、人がすぐ辞めてしまうといった問題や、働く人が派遣先・派遣会社に対して不信感や不安、不満を抱き、負のスパイラルに陥ることが少なくありません。この負のスパイラルを解消するために、私たちは2016年、今から9年前に生産推進グループを設立しました。
このグループのメンバーは派遣という仕組みで働いていますが、全員が三陽工業の正社員です。正社員という安定した雇用を基盤に、働く人々に安心して成長できる環境を提供しています。現在、このHR事業部では、有期雇用を含め約1,800名のメンバーが働いています。もう一つの柱である製造業部門では、継続的なM&Aを通じて社会問題の解決を目指しています。私たちが解決したい社会問題は2つあります。1つは事業承継者不足、もう1つは技能継承者不足です。
M&Aで会社を引き継ぐ際、事業承継については社内から幹部を送り込み、経営全体をグループでサポートします。そして、技能継承には、HR事業部で育成された約1,800名の社員の中から選抜された人たちが立ち向かっていきます。このHR事業部の平均年齢は約32歳で、20代や30代がメインで活躍しています。
例えば、昨年4月にM&Aをした会社では、社長が72歳で、50人いる現場の平均年齢がちょうど60歳でした。私たちはこの若手がいない現場に対し、20代・30代の若手8人を送り込み、技能伝承と現場の活性化を図っています。また、事業承継者として当時47歳の幹部を送り込むことで、一気に若返りを図りました。私たちはこのM&A戦略を通じて、中小製造業の持続可能性を守り、日本の製造現場を元気にすることに正面から取り組んでいるのです。
取材担当者(高橋)の感想
製造派遣という業界の課題(人がすぐ辞めてしまう、派遣先との不信感)に対し、派遣社員をすべて正社員として雇用するという独自の仕組み(生産推進グループ)を導入されている点は、真に「人を大切にする」という理念を体現していると感じました。また、M&A戦略が、中小企業が抱える深刻な事業承継や技能継承といった社会課題を解決するための手段になっていることに驚きました。若いうちから成長意欲や責任感のある仕事がしたいと考える人材が、このM&Aの現場で活躍し、日本全体の製造現場を元気にしているという仕組みは、就活生にとって大きな魅力になるでしょう。

【変化の激しい時代を勝ち抜くための哲学:「動きながら考える」】
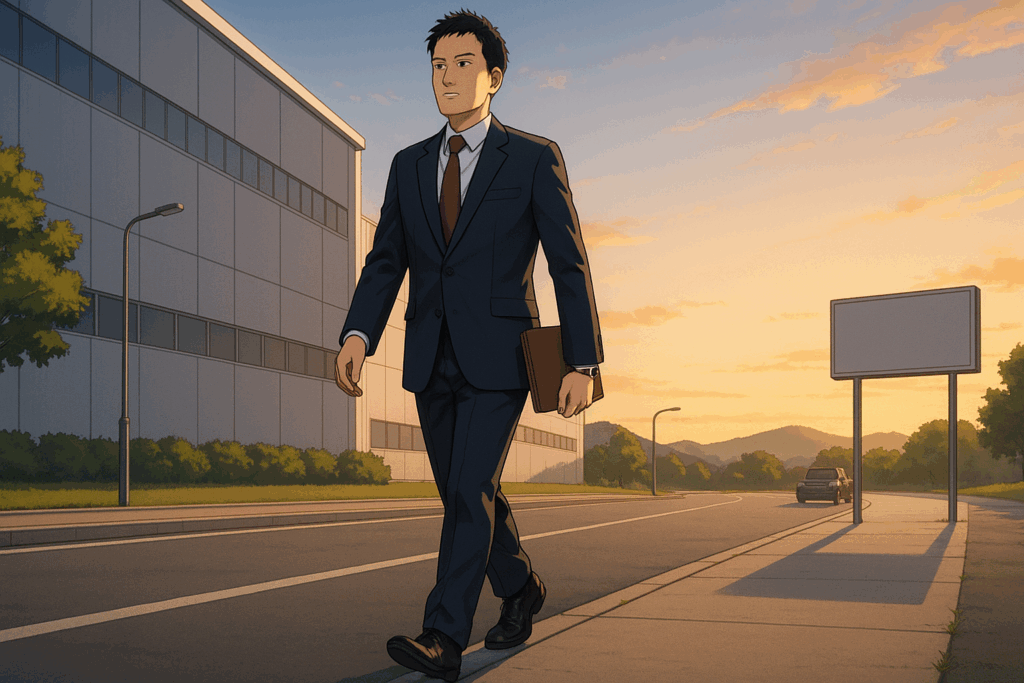
私がこれまで最も大切にしてきた価値観は、「動きながら考える」という行動哲学です。何かを始めようとしたときに、立ち止まって考えすぎてしまうと、リスクやネガティブな要素にとらわれてしまい、結局何もやらない状態に陥りがちです。
しかし、行動しながら考えるほうが、意思決定が早くなるのはもちろん、もし仮に最初の考えが間違っていたとしても、動いているので軌道修正が非常に容易になります。考えすぎてから動くと、間違っていたときに「あれだけ考えて結論を出したのに」と、修正が難しくなる場合があります。たとえば、1週間考えて左の道を選んだ後、やっぱり違うと思っても、「決めたから行こう」となってしまいがちですが、そうではなく、行ってみてダメだと思ったら違う方向へ行けばいいのです。
今の世の中は変化が激しく、外部環境は一瞬で変わっていきます。人口減少や人手不足が進む現代において、誰かと同じことをしていては勝ち残れません。同業他社と同じことをやっていたとしても、勝ち残れるわけがないのが今の世の中であり、個人においても、誰かと同じことをやっていては差が出てこないのです。
AIやテクノロジーによる自動化が進む一方で、さまざまなことを突き詰めたとき、最終的には人が重要になるという結論に至ります。人が行う事業活動において、人間にしかできない「感性」や「直感」にこそ付加価値をつけていくべきだと考えています。もちろん、闇雲な勘は正しくありませんが、さまざまな情報や過去のデータをインプットした上で出てくる直感は、当たることも多いので大切にしています。人を大切にする、人に寄り添う、人を成長させていくというスタンスは、今後、よりフォーカスされてくるでしょう。私たちはそこに焦点を当てながら、日本の製造現場を元気にするというビジョンに取り組んでいきます。
取材担当者(高橋)の感想
井上社長の「動きながら考える」という考え方は、まさに変化の速い現代を生き抜くための極意だと感じました。失敗を恐れず、まずは行動してみることで、修正点が見つかり、より良い方向へ進めるという教訓は、私たちの学生生活や就職活動においてもすぐに生かせる学びです。また、AI時代になっても最終的に「人を大切にする」というスタンスをより強化していくという未来への展望は、テクノロジーに仕事を奪われるかもしれないという不安を持つ若者にとって、非常に心強いメッセージだと感じました。










