宮城県鎌先温泉に位置する「湯主一條」様は、約600年の歴史を持つ格式ある旅館です。大正時代から昭和初期にかけて、宮大工によって釘を一本も使わずに建てられた木造建築の本館は、その歴史の重みを感じさせつつも、お客様に心安らぐ快適な空間を提供しています。ミシュランガイド宮城で3レッドパビリオンを獲得し、個室料亭「匠庵」で提供される「森の晩餐」は、その料理の質の高さで多くの評価を得ています。伝統を大切にしながらも、お客様の声に耳を傾け、常に改善を続けることで「人気の宿」としての地位を確立しています。今回は、600年の歴史を受け継ぎながら革新を重ねる背景、そしてこれから描く未来像について、湯主一條・20代目一條様にじっくりとお話を伺いました。
<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>
【20代目の継承と覚悟】
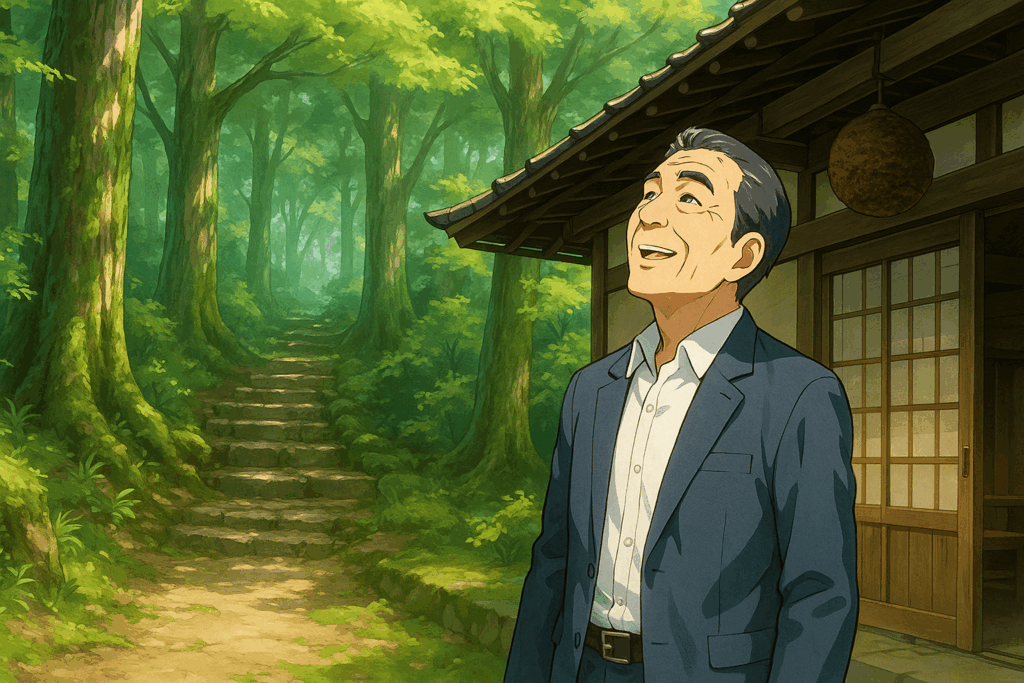
私は旅館の20代目として、この重責を担っています。一條家には、長男が家業を継ぐという習わしがあり、私自身、中学1年生の時にはすでに親が保証人となって会社に入社していました。これはなかなか聞かない話かもしれませんが、私は生まれた時から次の経営者となることが決まっていました。親が名付けてくれた名前「達也」を、初代からの全てを背負う覚悟を持って「一條一平」に改名しました。歌舞伎役者が名を変えるのと異なり、私の場合は本名そのものを変えました。周囲からは「若旦那さん」と呼ばれ、自然と経営者として育てられる環境で育ちました。
元々はホテル業界への憧れが強く、東京のホテル学校へ進学し、ホテルマンとして働いていました。二度と旅館には戻らないと思っていたのですが、社会人になってある日突然、東京で母親とばったり会うという予期せぬ出来事がありました。その頃地元ではメインバンクが破綻し、金融機関から連帯保証人を求められていた時期でした。そして2003年には、事業の継続を諦めた父が、その命をもって得た保険金で「旅館を立て直してほしい」という遺書を残し亡くなりました。このような経緯で、私は突然経営者となることになったのです。
私の父は、戦後の高度経済成長の時代に育ちました。商売が右肩上がりでしたから、バブル崩壊後は打手が少なくなり客足が低迷。資金が底をつき倒産寸前という状況でした。その教訓から、「これまでと同じことを続けていてはダメになる」と強く感じました。この継承の経緯は、私にとって決して平坦な道ではありませんでした。しかし、その経験が現在の経営哲学の根幹を築いています。
取材担当者(高橋)の感想
一條様が生まれた時から次期経営者として定められ、名前まで変えて事業を継承されたというお話は、まさに歌舞伎のような伝統の重みを感じさせました。ご自身の意思とは異なる形で旅館に戻らざるを得なかった状況や、先代の苦悩を経て経営者になられた背景には、並々ならぬ覚悟と責任感があったのだと感じました。

【新時代への挑戦と「湯主」の役割】
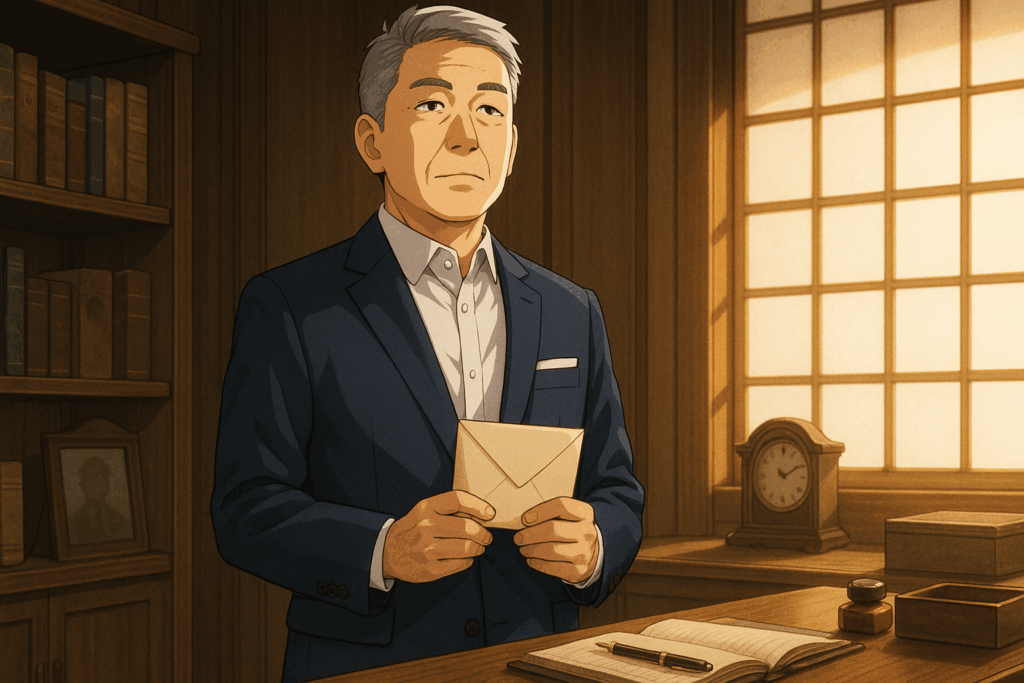
私は、歴代の当主たちが村長を務め、江戸時代には湯守(ゆもり)として入湯税を徴収する役目を担っていた歴史があります。東北大学の先生に調べていただいている資料の中には、永久に湯守としての役割を許可(永湯守)された文献や、この蔵本エリアを領地として治めるよう藩からの命令があった記録もあり、一條家はかつて政治力も持っていたことが分かっています。父からは「鎌先の将来を考えるのが一條の勤めだ」と常々言われていました。
鎌先温泉は上空から見ると非常に小さな集落で、これ以上広げることも伸ばすこともできない場所に位置しています。建物にもいずれ限界が来るため、私は現在の経営状況が良くなったからといって、息子世代に老朽化の旅館を引き渡すわけにはいきません。そのため、信用という形で借金が増えたとしても、それを会社の盤石な経営のための資本と捉え、新しい挑戦をしています。
現在の取り組みとしては、9月2日にグランドオープンする「THE YUKAWA一條支店」があります。当初11部屋で8.1億円の予算が、最終的には18億円にまで膨らみました。ここで私は、旅館とは異なるリゾートホテルを作りたかったのです。旅館には昔から独特の接客の流れがありましたが、ホテルはスマートでエレガントだと感じていました。私自身がホテルマンとしてコンシェルジュとして働いていたので、そのホテルの良さを取り入れたいと考えました。単にハイセンスなだけでなく、少し田舎っぽさも残しつつ、良いものを提供することで、新しいお客様を創造したいと考えていました。
約20代にわたり旅館が続いてきたのは、どこかで原点回帰があったからだと考えています。今回、新しい源泉も掘り当てたのですが、その成分が現在の鎌先温泉とほぼ同じでした。これはまるで神様に守られているような感覚です。初代が旅館を始めた時の気持ちに立ち返り、サービス業というものをやり直していきたいという気持ちがあります。
取材担当者(高橋)の感想
過去の歴史を深く理解し、未来を見据えて大胆な投資を行っている一條様の経営手腕に感銘を受けました。特に、リゾートホテルへの挑戦は、伝統を守りつつも新たな顧客体験を追求する姿勢の表れだと感じます。先代の教訓を活かし、借金を「信用」と捉える前向きな発想は、就職活動中の学生にとっても大きな学びとなるでしょう。

【デジタルへの適応と伝統の継承】
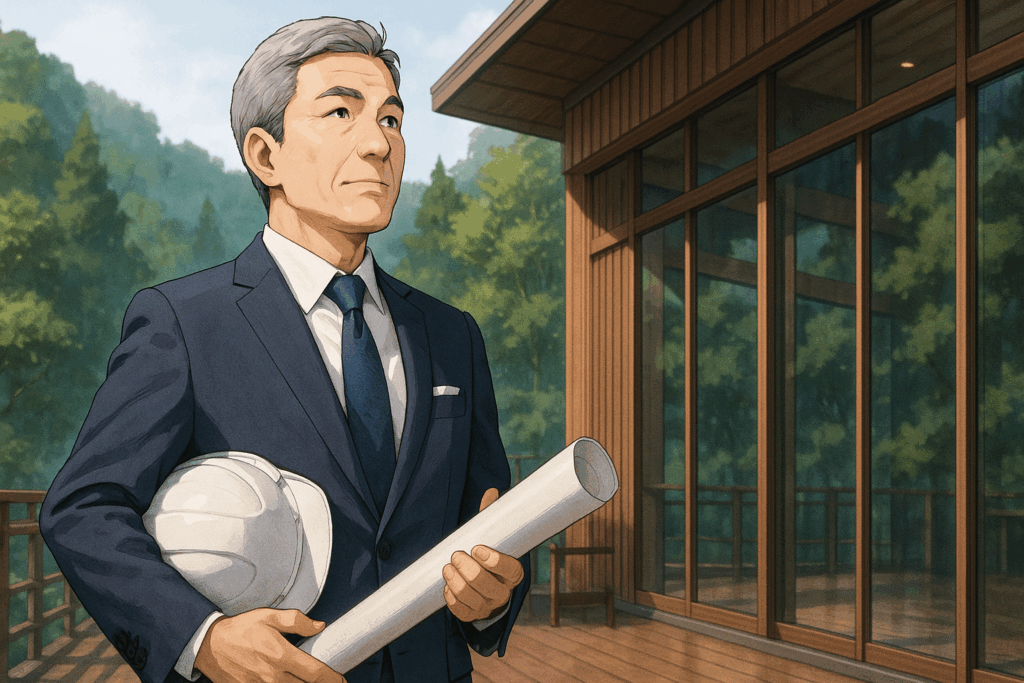
私が旅館を継いだ2003年当時は、まだインターネットマーケティングが黎明期でした。しかし、楽天トラベルなどの登場からインターネットの可能性を強く感じ、これは絶対に必要だと確信しました。約20年経った今、経営者としてデジタルについていくのは最低限必要なことです。
ただ、私が気をつけているのは、あまり情報を出しすぎないことです。情報の非対称性を大切にし、お客様には全てを語らず、実際に来ていただかなければ分からない部分を残しています。AIで検索すれば多くの情報が集められる時代ですが、インターネット上の文字だけでは伝わらないもの、例えば写真や、実際に訪れた時のスタッフ一人ひとりの接客で、お客様に「もっと聞いてみたい、行ってみないと分からない」と感じてもらえるような目的設定をしています。
時代についていかなければ取り残されてしまうため、新卒採用を積極的に行っています。私よりもはるかにデジタルに強い人たちを採用し、SNS担当者として業務を任せています。彼らとの相談時には私もきちんと答えられるよう、SNSに関する知識や操作を自ら学び、勉強しています。旅館の経営において、倒産寸前までいった父の教訓から、「これまでと同じことを続けていてはダメになる」というシンプルな考えに行き着きました。持っているリソースをどう活用すればいいのか、やり方を変えなければ本当に終わってしまうという危機感がありました。
当時は建物やお金がなく、私自身も信用がなかったため、まずは自分たちができることとして、清掃を徹底したり、接客を改善したり、原価管理をきちんと行ったり、お客様に楽しんでもらうためのテーマを作ったりすることから始めました。これらはお金をかけずにできることでした。少しずつ信用がついてきてから、次の投資、その次の投資へと進めていきました。最初に新しい設備を整えてからサービスを考えるのではなく、サービスの質を高め、従業員のレベルを上げてから投資をしていく方が良かったのかもしれないと考えています。
例えば、元々客室だった場所を女将が「ここで食べさせたら雰囲気が良いのでは」と考え、個室料亭「匠庵」に転換しました。お金をかけられない中でも、客室をお食事場所に変える発想の転換で、お客様に喜んでいただけました。コロナ禍の際も、売上は上がり続けました。私たちは完全な個室空間を提供していたため、飲食店の制限を受けず、お客様に安心して過ごしていただけたからです。最大4人までの利用で、ほとんどが家族や恋人、友人など、関係性の深いお客様でした。
Gotoトラベルなどが始まる中で、私たちは割引された分を単価で補う戦略を取りました。単価を上げた分、料理、接客、清掃の質をさらに高めることに注力しました。結果として、2019年決算から昨年決算までの間に、一人当たりの単価が2万円以上も上がりました。多くの旅館が補助金を使って設備投資をしていた中で、私たちはハード面で最低限の投資をし、その代わりに人材採用と教育に力を入れました。そのおかげで売上は少しずつ伸びています。
これはこれまで積み上げてきた信用だと考えています。お客様からは「料理が美味しい」「丁寧な接客」「唯一無二の食事が楽しめる」といった口コミをいただいています。団体客は極力少なくし、個人のお客様を増やし、著名人なども含め、全てのお客様に個室で食事を提供することでプライベートをしっかり守っています。そのため、安心して来られるという評判が本当の口コミで広がっていったと感じています。
現代の旅行者は、「良い部屋、良い風呂、良い料理」といった従来の贅沢だけでなく、より深い体験を求めていると感じています。高価なものではなく、心が揺さぶられるような体験、例えば古い建物を見た時に日本の建築美に感動するような感情こそが、これからのラグジュアリーだと考えています。
取材担当者(高橋)の感想
インターネットやSNSの活用において、単なる情報発信に留まらず、お客様の「行きたい」という気持ちを喚起する巧みな戦略に驚きました。コロナ禍での売上増加や、設備投資ではなく人材教育に注力した経営判断は、逆境をチャンスに変える一條様のシンプルな思考と深い洞察から生まれるものだと感じました。

【宿泊業界の課題と「人」への投資】
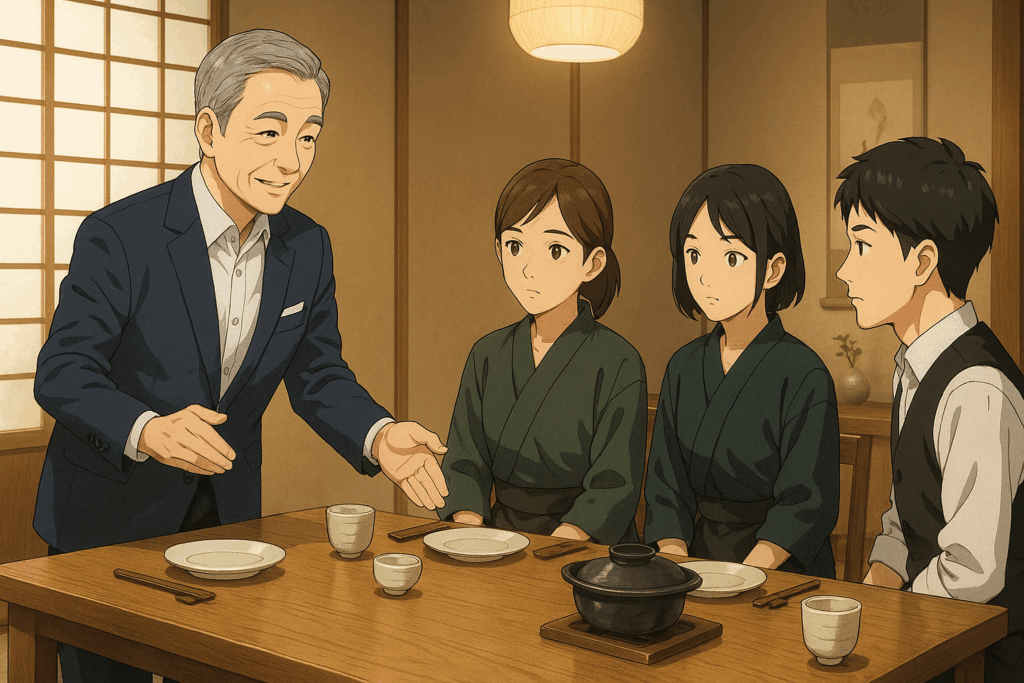
宿泊業界全体の問題点として、多くの旅館が「ブランディング」が課題と考えています。例えば、マクドナルドの「M」や日産のロゴのように、それを見ただけで何を意味するのかがわかるようなブランドイメージが、温泉地や旅館にはまだ確立されていません。湯主一條は、「朝夕個室料亭で森の晩餐をいただく美食の宿」という短いフレーズをキーワードに、自社の強みを明確にしています。しかし、他の大型旅館では「自分のところを一言で言うとどういうところか」を説明できていないところが多いのが現状です。
私の友人が経営する岩手の「愛隣館」は、「赤ちゃん向け」というブレないコンセプトを貫き、東日本でトップクラスの評価を得ています。子供が減っている時代にも関わらず、収益を上げ続けています。お母さんたちの間では「赤ちゃん連れなら愛隣館がいいよ」と口コミが広がり、子供が騒いでも周りに嫌な顔をされないといった、簡単なブランディングが成功しています。ブランディングに取り組まず、旅行代理店に頼ったり、大手プラットフォームに広告を出したりするだけでは、大手にやられてしまうと危惧しています。わずか24部屋の小さな宿である湯主一條でもブランディングを徹底することで、設備投資ができないほどひどかった状況からここまで立て直すことができました。
日本全体の問題である人手不足は、宿泊業界でも非常に深刻だと感じています。大型旅館では外国人スタッフが多いのはそのためです。日本人が来ないという状況に対し、私たちは8年前から新卒採用を積極的に行っています。5年前からのスタッフは定着しており、今では中堅として活躍してくれています。
売上を優先する経営者は多いと思います。しかし売上を作るのは「人」です。旅館の場合、DX(デジタルトランスフォーメーション)でできることには限界があり、特に単価の高いサービスは人が頭を使わなければ成り立ちません。私は採用に力を入れており、新卒が入社した際の福利厚生や働く環境整備にも注力しています。過去4年間で5つの寮を新設し、現在43名が滞在できる状況です。
人員という意味では、今のところ充足しています。毎年、余剰になったとしても採用し続けるつもりです。金融機関も「人が増えている会社、つまり採用をしっかりやっている会社にお金を融資する」と言っています。私は従業員を人件費ではなく「資本」だと考えています。彼らが稼ぎ出す資本であり、24時間稼働する旅館では、お客様を待たせないためにも頭数が必要だからです。人がいれば、サービスの評価が上がり、単価を上げてもお客様に納得してもらえる好循環が生まれます。私は世の中のムードに逆らうタイプで、効率化ばかりを求める声がある中で、人を増やすことを重視しています。
採用方法としては、リクルートさん(リクナビ)を使い、オープンカンパニーを実施しています。会社説明会だけでなく、実際に宿泊体験をしてもらい、旅館へのコンセプトワードを考える課題を学生に出しています。私は最初の1時間だけ説明し、その後は学生とスタッフで過ごしてもらうことで、入社に繋がるケースもあります。学生がインスタグラムやブログを見て予習してくることも多く、ありがたいことだと感じています。
インスタグラムの投稿は、ホームページ制作会社からのレクチャーを受け、写真の撮り方や質の向上に取り組んでいます。半年ごとに来てもらい、写真の撮り方などを指導してもらうことで、担当者のレベルも向上し、自社で内製化を進めています。
入社後の離職理由のほとんどは人間関係だと考えています。社長に怒られた、先輩と馬が合わない、いじめられるといった経験も私自身がしており、その改善のため、定期的にコミュニケーション研修を行っています。この研修は、まず経営者である私が検定を受け、落ちることも含めて恥をかく姿を見せることで、組織全体のコミュニケーション改善に繋がると考えています。仲が良い職場は辞めたくありませんし、給料や福利厚生だけでなく、出社して人の顔を見たくないと思われない環境が重要です。人の増加に伴い、コミュニケーションの改善は経営者として考えなければならないことであり、売上よりも人の教育を優先し、会社を休館にして研修を行うこともあります。
取材担当者(高橋)の感想
「売上は人が作る」「人は資本である」という一條様の言葉は、現代の企業経営において非常に重要な視点だと感じました。特に宿泊業界の人手不足が深刻化する中で、新卒採用を積極的に行い、働く環境や人間関係の質を高めることに徹底して投資されている姿勢は、多くの企業にとって模範となるでしょう。

【Z世代へのメッセージ】
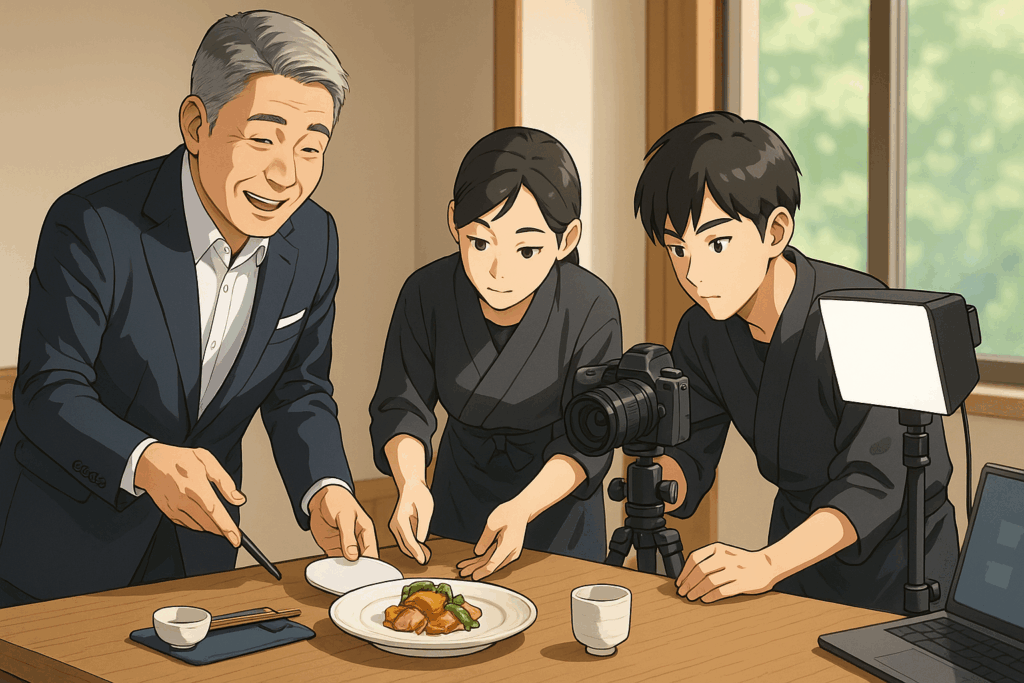
Z世代の強みは、生まれた時からデジタルの中で育っていることだと思います。これは私には敵わない部分であり、どんどん教えてもらいたいと感じています。弱みというか苦手なところは、「別れ」を経験していないことだと思います。小学校から大学まで人間関係が繋がりっぱなしで、人の投稿を見て羨ましがったり、嫌でも「いいね」を押さなければならないといった、デジタル的な不安を抱えていることが弱みだと感じています。
私たちは高校卒業後に地域から離れたり、一人暮らしをしたりすることで、物理的に人間関係が切れる経験をしてきました。関係が切れた瞬間に「ああ、良かった」と感じることもあり、そういった経験が少ないと、デジタル上での繋がりが疲労やストレスに繋がり、うつ病になってしまう可能性もあると考えています。デジタルから離れる場所や時間を持つことが重要だと感じています。
取材担当者(高橋)の感想
Z世代のデジタルネイティブという強みを肯定しつつも、精神的な側面での弱点を的確に指摘された一條様のお話は、大変示唆に富んでいました。デジタル社会に生きる私たちにとって、「つながり」がもたらす疲労やストレスに目を向け、意図的にデジタルから離れる時間を持つことの重要性を再認識させられました。










