株式会社歌行燈は、明治10年(1877年)に三重県桑名市でうどん店として創業しました。その後、「歌行燈」と屋号を改め、麺料理や和食料理、食品の製造加工・販売を手掛ける老舗の和食料理店として、現在に至ります。特に、桑名名物の蛤(はまぐり)にこだわった料理は、多くのお客様からご好評をいただいております。創業以来、地域に根差し、皆様に美味しい料理と心温まるサービスを提供し続けています。
私たちは、桑名から東海、関東、そしてかつては海外へと事業を拡大してきました。様々な時代の出来事を経て、もうすぐ創業150周年を迎えます。お客様をはじめ、多くの方々からの長年にわたるご支援の賜物であり、心より厚く御礼申し上げます。
私たちができる恩返しは、美味しい料理と良いサービスを通じて、皆様の幸福な食事の時間を提供し続けることです。これからも従業員一同、より一層美味しいもの、より良いサービスを提供できるよう努力を重ねていきます。地域に、日本に、そして世界に誇れる企業となるよう、10年先も20年先も、今以上に全てのお客様から愛される店づくりを目指して精進してまいります。今回は、創業から150年近い歴史の重みと、地域やお客様への感謝を胸に、未来へと挑み続ける株式会社歌行燈の歩みと展望について、横井社長にじっくりとお話を伺いました。
<聞き手=石嵜渉(学生団体GOAT編集部)>
【横井様の今までの経緯・背景】
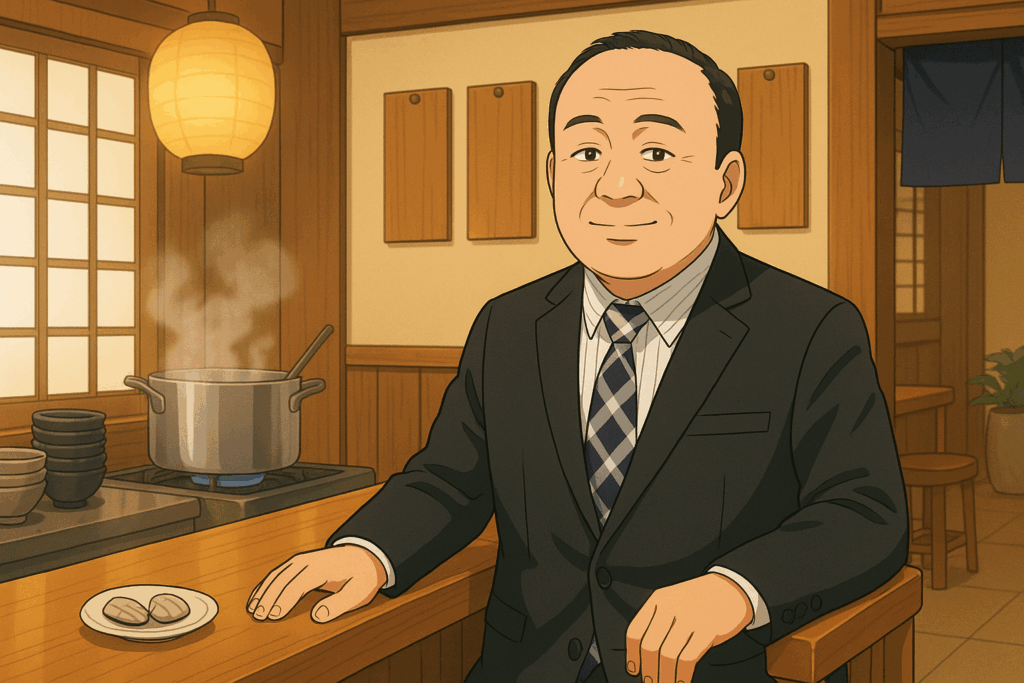
私は、物心ついた頃から、このお店が生活の中心にありました。自宅もお店のすぐ上にあり、学校から帰ってくるとお店でおやつを作ってもらうような生活でしたので、お店自体が私の日常そのものだったのです。周囲の人たちからも「次はお前がやってくれるんだよな」といった期待の声は自然と聞こえてきましたが、父から直接「お前が継がなければならない」と言われたことは一度もありませんでした。
若い頃から経営者となることや、この会社を自分が引っ張っていくといった大それた意識は全くありませんでした。ただ、一緒に働く人たちのことが好きで、「この人たちと一緒に何か仕事がしたい」という気持ちが大きかったです。もちろん、自分の家族の店ということもあり、この店や味が好きだったというのも、自然とこの道に進んだ大きな理由であると考えています。
会社を継ぐということに対して、プレッシャーやストレスを感じないように努めています。この立場に生まれ育ち、自然な流れで自分の意思を持って取り組んでいることなので、誰かにやらされているわけではありません。責任感はもちろん感じていますが、そうしたネガティブな感情を持たないように心掛けています。
取材担当者(石嵜)の感想
横井社長が幼い頃からお店が生活の一部だったというお話は、まさに歴史ある会社ならではの背景だと感じました。プレッシャーを感じさせない自然体な姿勢の中に、共に働く人々やお店への深い愛情が垣間見え、それが今日の歌行燈を支えているのだと感銘を受けました。

【株式会社歌行燈の事業・業界について】
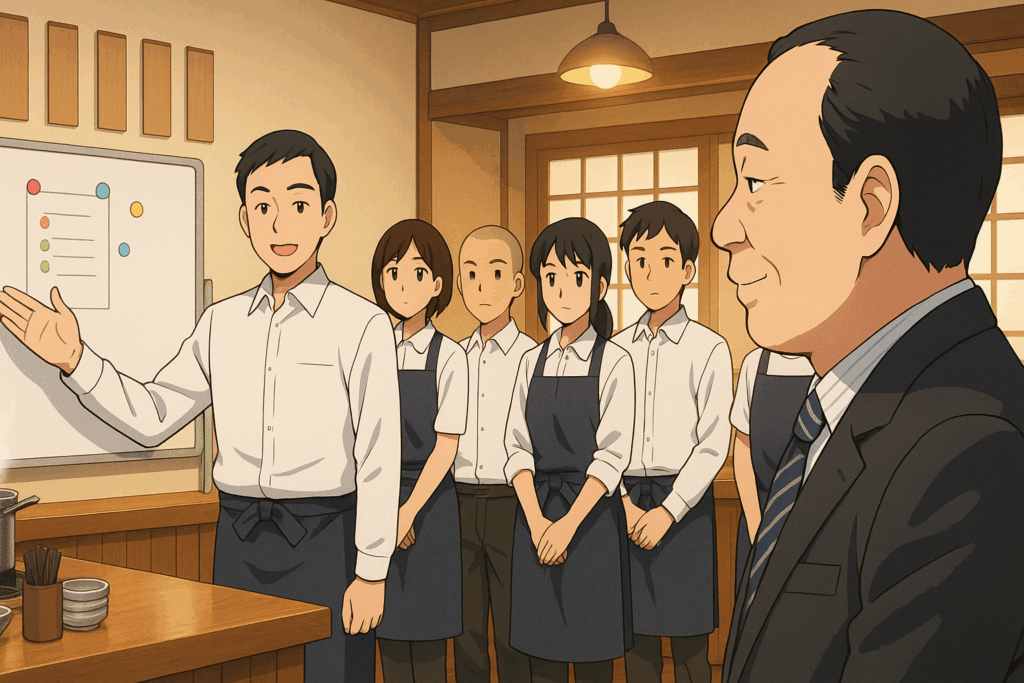
私たちが経営する会社は、私の個人的な所有物というよりも、従業員皆のものだという意識を常に持っています。正社員が約80名、パート・アルバイトを含めると全体で約930名(インタビュー時点)という大人数ですので、彼ら、彼女らのための会社であるということを強く意識して経営に当たっています。
飲食業界全体で人手不足が深刻化し、従業員の平均年齢が上昇しているという課題は、私たちも認識しています。当社でも、個々の店舗を見ると、人員や能力が十分に充足しているとは言えない状況にあり、基本的に常に人手不足の状態です。そのため、求人活動は積極的に行っています。
当社の採用戦略は少し特徴的かもしれません。新卒採用は20年以上行っておらず、中途採用、特に経験者や転職希望の方々を中心に採用しています。私たちは、教育に力を入れるというよりも、即戦力となる人材を求めているという方針があります。労働時間や土日も仕事となること、学生にとっては友人と遊べないといった制約が生じることなど、飲食業界では人材確保に苦労する点があると考えています。
各店舗の運営においては、基本的に1店舗につき最低1名の社員を配置する体制をとっています。店長の業務内容は多岐にわたるため、複数の店舗を兼務することは難しいのが現状です。各店舗には店長と、もう1名程度の社員、そして多くのパート・アルバイトの方が働いています。このパート・アルバイトの方々の入れ替わりが常に発生するため、いかに良い店長を育てるかが、採用以上に重要だと考えています。
店長の質が高ければ、パート・アルバイトの方も辞めにくくなり、結果として求人に苦労することが減ります。従業員が「仕事が少し大変でも楽しいから行きたい」と思えるような職場環境を作れる店長を育成することに力を入れています。現在、当社はホームページに掲載されているものを含め、約8つのブランドを展開しており、それぞれのブランドの責任者が店舗管理を行っています。かつては海外にも店舗を展開していましたが、現在は一時的に休止しています。
取材担当者(石嵜)の感想
「会社は従業員のもの」という横井社長の考え方や、人手不足の課題に対し新卒採用を行わず即戦力となる中途採用に特化しているという戦略は、非常に明確で実践的だと感じました。特に、店長の質が従業員の定着に直結するというお話は、組織運営におけるリーダーシップの重要性を改めて認識させられる学びとなりました。

【横井様から学生へのメッセージ】
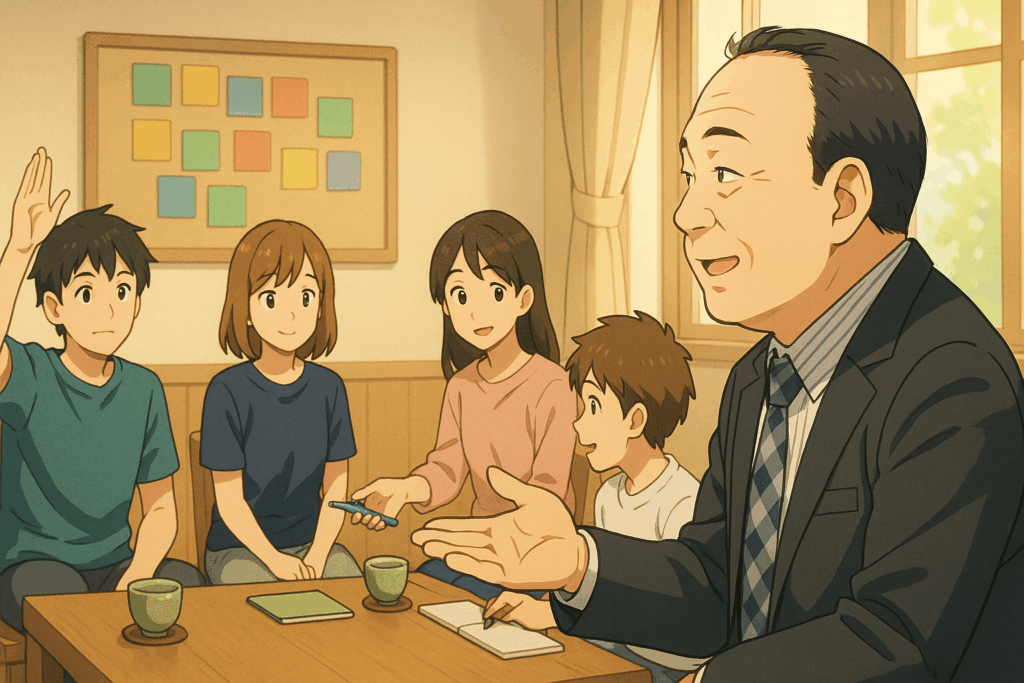
学生の皆さんには、まず何よりも「やるべきことをやる」という意識を大切にしてほしいです。そして、「やらなければいけないことを好きになる」という姿勢を持つことが非常に重要であると考えています。今の若い世代には「やりたいことをやろうよ」という風潮が強いと感じていますが、本当に成功している人たちは、決してやりたいことだけをやってきたわけではないはずです。
人生には必ず嫌なことや困難なこともあります。そうした時に、「嫌なことだからやらない」という選択をするのではなく、いかにそれを楽しんで取り組めるかが、その人の成長に繋がります。私自身も、これまで全ての経験は無駄ではなく、必ずプラスになると信じています。やりたいことをやるのはもちろん大切ですが、やりたくないことを楽しんでやることの方が、さらに価値があることだと感じています。これは、私自身にも常に言い聞かせていることです。
さらに、もう一つ皆さんに伝えたいのは、「人に助けてもらえる人であること」の重要性です。どんなに能力がある人でも、自分一人で全てをこなせる人はいません。困った時に、周りの人たちが「助けてあげたい」と思ってくれるような人間関係を築くことこそが、最も強いことだと私は考えています。これは、日々の誠実さや真面目さ、相手を思いやる気持ち、そしてきちんと挨拶をするといった基本的な行動の積み重ねから生まれるものです。一人で抱え込まず、弱さを見せても、悩んでも良いのです。大切なのは、前向きに進み続けることであると考えています。
取材担当者(石嵜)の感想
「やるべきことを好きになる」「嫌なことも楽しむ」というメッセージは、僕が今まで漠然と考えていた「やりたいことだけやる」という考え方と対極にあり、非常に深く響きました。また、「人に助けてもらえる人であること」という言葉は、社会で生きていく上で本当に大切な視点だと感じ、僕自身の今後の行動にも大きな影響を与えてくれるはずです。

【株式会社歌行燈の今後の展望】
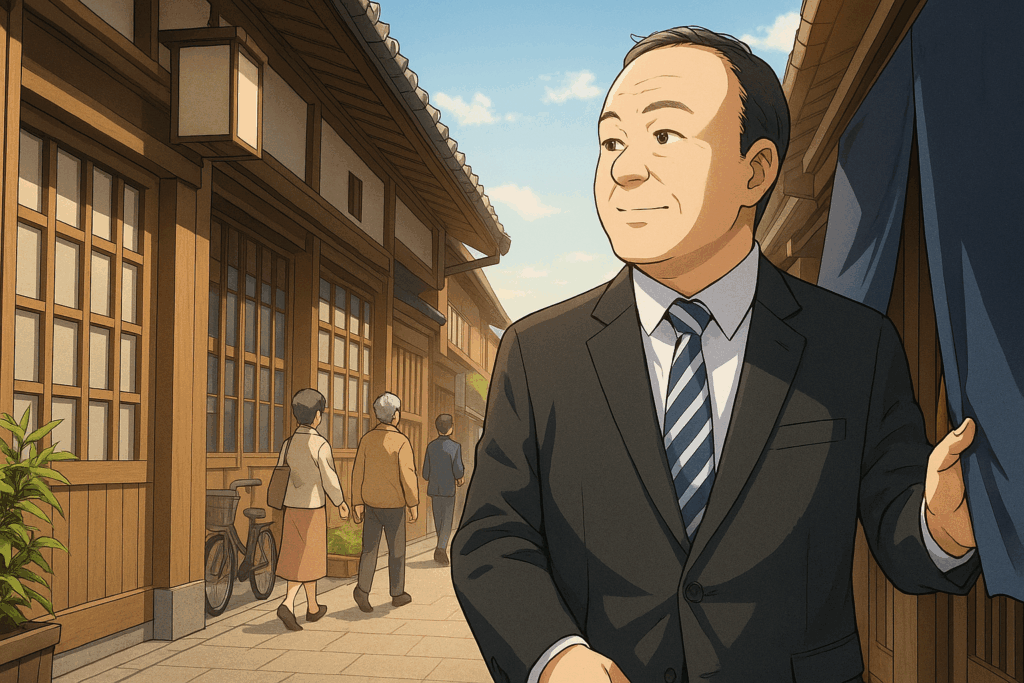
歌行燈は間もなく創業150年を迎えますが、私の目標は、さらにその先、合計300年続く会社を創ることです。この目標は、単に店舗数を増やしたり、売上を伸ばすことだけを意味しているのではありません。最も重視しているのは、地域に深く根差し、「歌行燈があることが、地域の人たちにとっての誇りになる」と感じてもらえるような存在になることです。地域との強固な関係性を築くことで、お客様との絆も深まり、事業が長く続いていくと信じています。
商売である以上、利益を追求するのは当然ですが、自分たちだけが儲かれば良いという考えではありません。特に歌行燈は、これまで地域の方々に育てていただいたという感謝の気持ちが強くあります。ですから、お客様のお孫さんの世代まで、ずっと「歌行燈がそこにあって良かったね」と言ってもらえるような店であり続けたいと願っています。
私自身、社長として常に変化に対応し、変革を続けていくことの重要性を感じています。歴史が古いからといってお客様が来るわけではありません。やはり美味しいもの、魅力あるものを提供し続けることが不可欠です。当社の「らしさ」は残しつつも、「歌行燈はこうでなければならない」という固定観念にとらわれず、柔軟に新しい挑戦を続けていくことが、これからの歌行燈の未来を創ると考えています。
取材担当者(石嵜)の感想
「300年続く会社を創る」という壮大な目標には、横井社長のこの会社と地域への深い愛と責任感が込められていると感じました。地域と共に歩み、利益だけでなく「誇り」となる存在を目指すというビジョンは、企業が社会において果たすべき役割を深く考えさせられるものでした。変化を恐れず、常に最高のサービスを追求する姿勢は、学生にとって将来のキャリアを考える上で、非常に参考になる指針となるでしょう。










