株式会社ケンシンは1995年12月に滋賀県草津市で設立され、現在、滋賀県栗東市に本社を置く企業である。業務請負事業、一般貨物自動車運送事業、一般労働者派遣事業、倉庫事業を主軸とし、地域経済に貢献している。現在の資本金は5,000万円、従業員は100名である。特に、全従業員を正社員として雇用し、終身雇用を推奨するなど、従業員の人生を大切にする経営方針が特徴である。今回は、全従業員を正社員として迎え入れ、人生設計まで寄り添う「人を大切にする経営」を実現する田原社長に、創業からの歩み、そして今後のビジョンについてじっくりとお話を伺いました。
<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>
【安定を捨てた20代。ターニングポイントは一冊の詩】
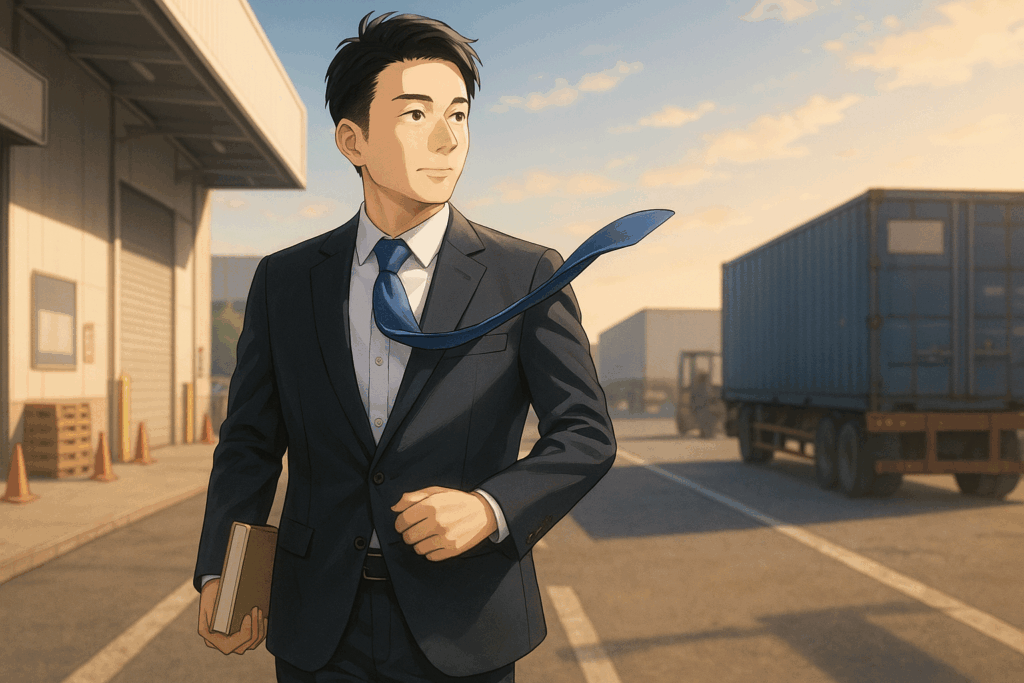
高校を卒業した後、大学へは行かずに、三洋電気という電気メーカーに2年間サラリーマンとして勤めていた。工業高校出身であった当時の私の夢は、このままサラリーマンを続け、職場結婚し、マイホームを建て、子供を育てるという安定した人生であった。そこに幸せを感じながら時を過ごしていた。
しかし、人生の大きなターニングポイントとして、ナポレオン・ヒルの『成功哲学』という「詩」に出会った。その詩をきっかけに人生の道が大きく変わったのである。この詩を持ってきた人物から、自己啓発のトレーニングがあるという話を受け、2泊3日のトレーニングに参加したのが、一番大きなポイントである。
実はそのトレーニングは自己啓発ではなく、組織販売(マルチに近い商売)をするためのものであった。私はサラリーマン生活が夢であったため、商品(健康器具)にも全く興味がなく、販売員になるつもりもなかった。しかし、私がそのトレーニングに一番最初に入ったため、ネズミ講のような形式で、私の下の組織が動くとお金が入ってくる仕組みができてしまった。サラリーマン時代の給料は手取り9万円程度であったが、何もしなくても月収が100万円、200万円ととんでもない金額になっていった。周りの組織の仲間が次々と仕事を辞め、そちらに専念していく中、私は何もせずにお金を得ることに違和感と危機感を覚え、最終的に会社を辞め、組織販売の道を選ばざるを得なくなった。
販売経験のない20代の私が健康器具を売っても説得力はなかったため、思った通り、22、23歳頃には組織は崩壊し始めた。何十人もいた組織は3〜4人になり、何百万とあった利益も伸びなくなった。幸い、当時はバブル期であり、保有していたマイホームや株が何倍にもなり資金的な余裕はあったが、組織がなくなっていく恐怖感から、「技術を持とう」という結論に至り、仲間と共に生体(整体)の免許を取得した。
整体の技術を身につけた後、サウナの一室を借りて施術を始め、非常に人気が出た。割のいい収入を得るために夜の街でも施術を行ったが、ほとんど寝る間もなく一生懸命働いた。そこで次に考えたのが「整体の学校を作る」というアイデアであった。学校経営に乗り出そうとしていた時、知人からトレーラーの荷物(コンテナ)の積み下ろし作業を依頼された。夏の炎天下、コンテナ内での作業は過酷であったが、1日6台を下ろせば30万円の収入が得られる。当時お金しか見ていなかった私は、これを「割りが悪くない」と感じた。元々体育会系で野球をしていたこともあり、肉体を使う仕事の仕組み(派遣事業や請負事業)に直感的に可能性を感じ、整体業からすぐに撤退し、現在の物流業界へと進むことになった。元を正せば、成功哲学の詩との出会いが発端である。
取材担当者(高橋)の感想
高校卒業後、安定を求めるサラリーマンからスタートしたにもかかわらず、一本の詩との出会いから人生が大きく動き出し、組織販売の崩壊、整体ビジネスの立ち上げ、そして物流事業へのピボットという、想像を絶する波乱万丈のキャリアを歩まれてきたことに驚いた 。
特に、組織が崩壊していく過程の恐怖感から「技術を持とう」と決断されたことや、整体の学校経営の途中で体力勝負の物流事業に直感で飛び込む行動力は、今の20代に欠けがちな、チャンスを掴むためのエネルギーと決断力の重要性を教えてくれると感じた 。

【 崩壊の恐怖から生まれた「世のため人のため」の理念】
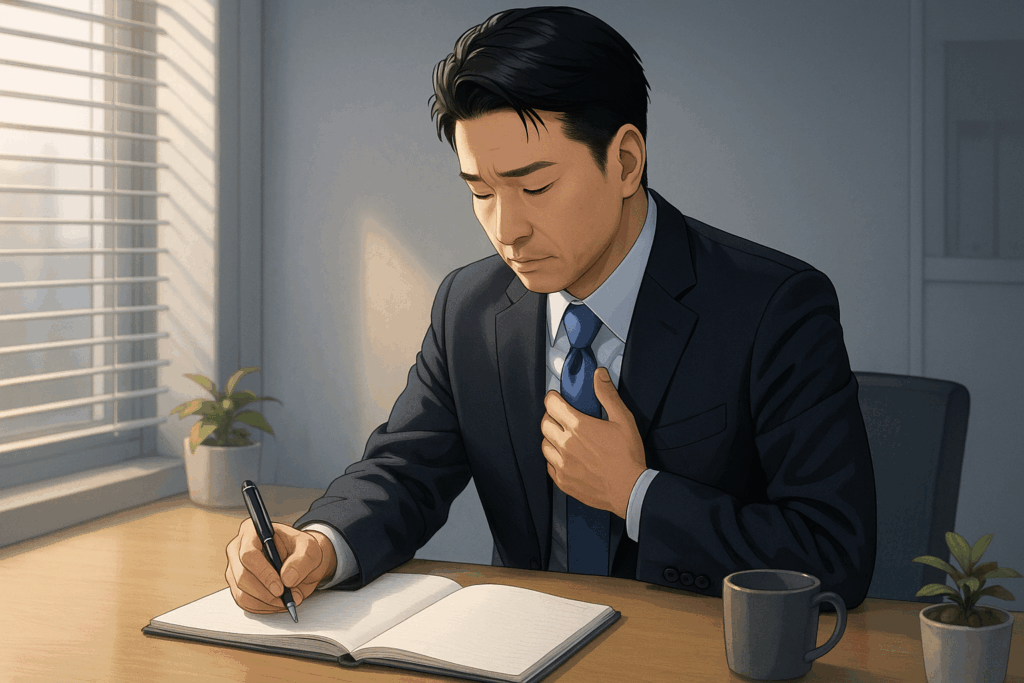
若い頃は組織販売で大金を稼いだ経験もあり、お金を稼ぐことしか見えていなかった。しかし、法人化して2年ほど経った頃、あるコンサルタントの研修を受けた。その研修の目的は「経営理念を作りましょう」というものであったが、私は「経営理念とは何か」という状態であったため、恥ずかしながら私だけ理念を作ることができなかった。
それ以来、自分の中で深掘りを続ける日々が1年半もの間続いた。毎朝散歩しながら、「自分は何のために会社をしているのだろう」「何のために生きているのだろう」と問い続けた。その結果、ハッキリと見えてきたのが、今の経営理念である「世のため人のためにする」という考え方である。
当初は「自分を犠牲にしてボランティアとして世のため人のためにする」という考えであったが、経営者に話したところ、「ある意味ボランティアは相手に無責任であるかもしれない」と指摘を受けた。やりたい時にやって、できない時はやらない、それでは相手を待たせてしまうためである。それを聞いて、「継続するにはどうしたらいいか」と考えが行き着いたのが、近江商人の「三方よし」の考え方であった。自分たちの利益もちゃんと確保しつつ、相手にも利益を取ってもらい、世間にも貢献するという継続可能な形こそが重要だと気づいた。この理念が、現在の里山構想や雇用戦略の根源となった。
取材担当者(高橋)の感想
1年半かけて「何のために仕事をしているのか」を突き詰め、導き出した「三方よし」の理念は、短期的な利益追求から脱却し、企業活動の真の意義を見出そうとする強い意志を感じた 。この理念こそが、企業が社会に貢献し続けるための最も本質的な仕組みであると理解できた。

【終身雇用を支える「里山構想」と次世代への準備】
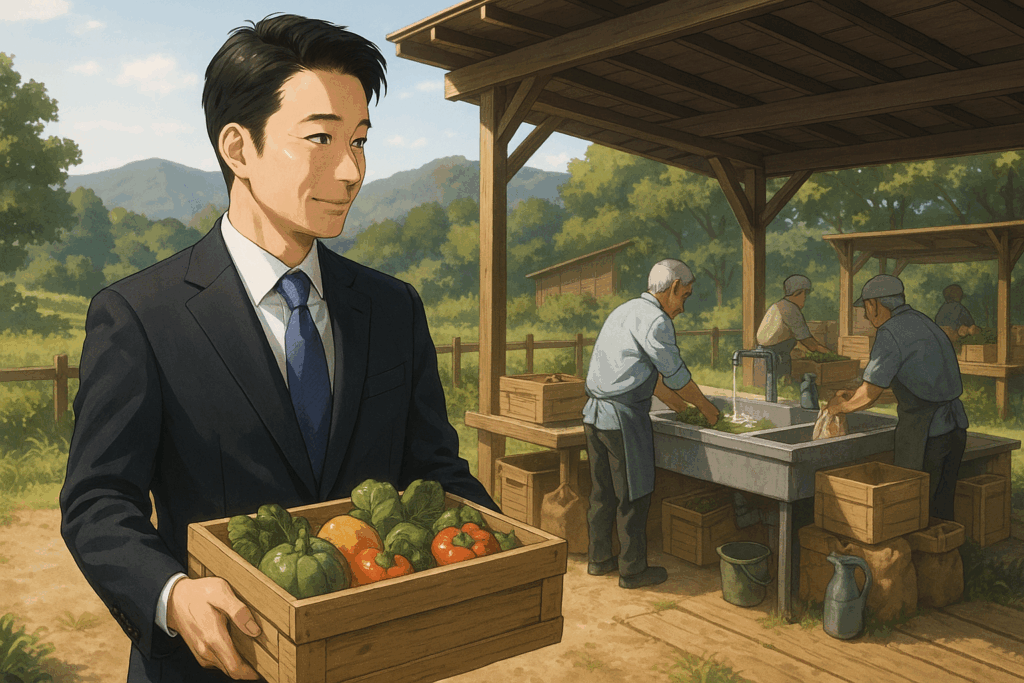
この理念に基づき、私の会社では縁があってうちに来てくれた人たちのために、雇用を固め、組織を安定させる目的で、従業員全員を正社員として雇用している。さらに、今の時代からは逆行しているかもしれないが、「終身雇用」を推奨している。
定年退職は60歳であるが、その後も再雇用し、賞与以外の固定給は現役時代と一緒の給料を支払うという条件にしている。これは、従業員に長く勤めてもらい、安心して生活してほしいという思いがあるからである。実際、70歳を過ぎてもリフトに乗っている社員もいる。リフトは機械が物を動かすため、安全運転さえしてくれれば、長く働いてもらうことが可能である。
この終身雇用と深く結びついているのが、「里山構想」である。うちには独身の従業員が多くいるが、彼らが60歳、70歳になった時、社会との繋がりを持てずに天涯孤独になっていく人生を想像してしまった。縁があってうちで長く働いてくれたなら、人生の最期まで何か関わりたいという思いがある。そこで、山や土地を買い、道の駅のような施設を作り、地域社会への恩返しとして活用したいと考えているのが里山構想である。
例えば、農家さんから運んだ農産物の泥を洗ったり袋詰めしたりという簡単な仕事を提供することで、70歳でも社会と繋がり、社会に恩返しができるようなボランティア活動に近い施設を作りたい。私の中で究極の安心は、「雨風がしのげて、ご飯が食べられること」である。独身の彼らが将来、家賃が払えなくなるパターンも想像すると、里山に住居と食事がちゃんと取れる仕組みを作っておきたい。彼らが社会と繋がって恩返しをする生き方をしてほしいという願いを込めて、今計画を進めている。
組織運営については、従業員は現在100名であるが、今後も上限を100名と決めている。これは、私が最終的な責任を持ち、目が行き届く人数が100人程度だと考えているからである。当社の大きな強みは、従業員からの紹介で入社する人が多く、親子三世代にわたって社員がいることである。お父さんが勧めるほど、安心して長く働ける会社である証拠だと、私自身非常に嬉しく思っている。
組織を未来へ繋ぐ準備として、息子が大学卒業後8年間東京での営業職を経験し当社へ2年前に入社してきており、次の世代へ継続できる計画を立てている。そのために今最も重要だと考えているのが、「人事部」の設立である。人事部には、従業員全員の「笑顔を作ってくれ」「目を輝かせてくれ」というミッションを与えている。単に管理するのではなく、従業員が仕事にやりがいを感じ、幸せに働ける環境を作ることで、組織全体の安定と成長を目指す。私個人の夢としては、里山構想を完結させ、次世代に会社をバトンタッチした後、若者たちに対して**チャンスを提供できる立場**になりたい。私が苦労した銀行からの信用や資本力の課題を解決するため、ベンチャーキャピタル的な役割を果たし、挑戦を支えたいという目標がある。
取材担当者(高橋)の感想
従業員数を意図的に100名に制限し、質の高い組織運営を維持しようとする姿勢は、目先の利益よりも従業員への責任を重視する田原社長の経営哲学の表れだと感じた 。特に、親子三世代にわたる紹介採用の多さは、企業の信頼性と働きやすさの具体的な指標であり、学生が会社選びをする上で非常に魅力的である。
従業員の幸福度を追求する人事部の設立や、バトンタッチ後のベンチャーキャピタル的な支援といったビジョンは、単なるビジネスを超えた、利他の精神に基づく究極の社会貢献であると感じた。

【20代の君たちへ:成功に必要な「エネルギー」と「覚悟」】
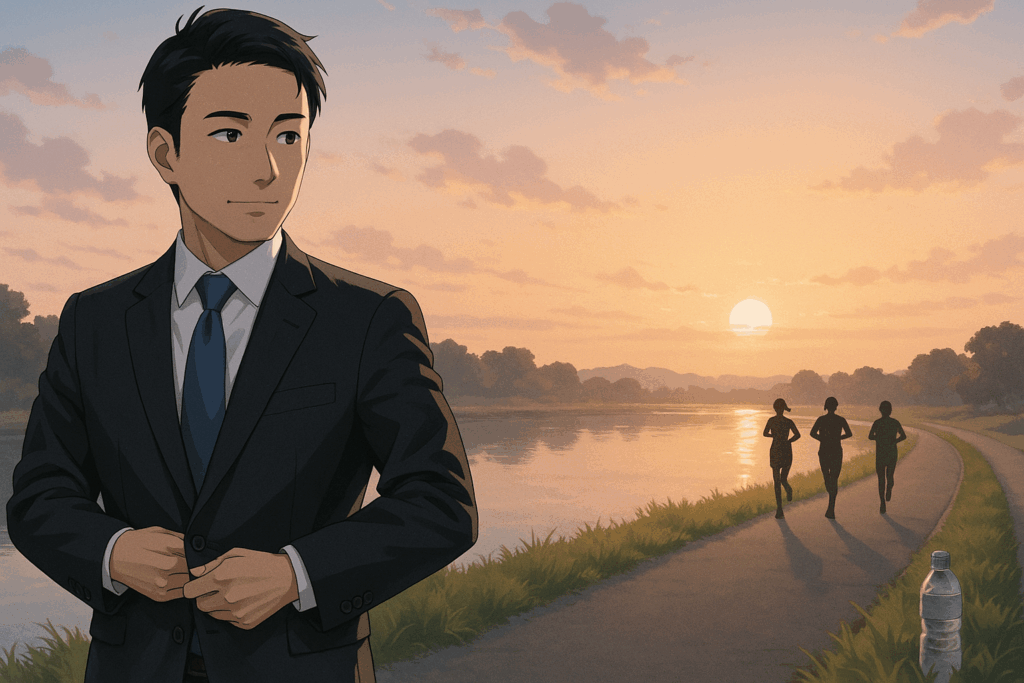
今社会に出る学生や20代の若者へ伝えたいことは、まず彼らの最大の強みは、何と言っても「エネルギー」が溢れていることである。その有り余るエネルギーを使わない手はない。若さゆえのエネルギーは、どんな人でも誰にも負けない強みだと断言できる。
一方で、弱みとして感じるのは、「死ぬほど何かをした経験がない」こと、すなわち精神的な根性や覚悟が浅いことである。人間は、死ぬ一歩手前ぐらいまで頑張った経験しか思い出に残らないと私は思っている。その極限まで頑張り抜いた経験こそが、その人のバックボーンとなり、メンタルを強くする。私自身、高校時代に野球で脱水症状で倒れたり、腹筋、背筋、足が同時に痙攣して死ぬかと思った経験がある。こうした経験をしていると、少々のことでは心が折れない強いメンタルが養われる。
成功や失敗の定義は人それぞれでどうでもいいと思っている。甲子園に行けなかった経験から私が学んだのは、勝ち負けや結果よりも、「本当に自分に嘘なく、精一杯ごまかさずに一生懸命やったかどうか」が成功であるということである。受験でも仕事でも一緒で、合格・不合格や成功・失敗の結果よりも、そこで何を学んだかが一番大事である。
だからこそ、自分のやりたいことを見つけるために立ち止まって悩むのではなく、「目の前にある仕事をとりあえず一生懸命やってみろ」と伝えたい。皿洗いでも何でもいい。皿が擦り切れるくらい一生懸命やってみる。そこで一生懸命になれば、必ず何かを得るものがあるからである。
そして、人生において最も重要な幸せは、感謝することと、感謝されることである。すべてに対して「ありがとう」という思いを持てる心が幸せであり、その感謝力が幸せのバロメーターである。さらに、感謝されることが、脳内の幸せホルモンが出る最高の瞬間である。自分が誰かの役に立ったと認識した時、幸せ感はむちゃくちゃ出る。それが、長続きする幸せに繋がるのである。
取材担当者(高橋)の感想
田原様の「エネルギー」を最大限に活かせというメッセージと、「死ぬほど何かをやりきった経験」の必要性という指摘は、恵まれた現代で生きる私たち20代にとって、耳の痛い、しかし最も重要なアドバイスだと感じた 。
成功の定義を結果ではなく「一生懸命やったかどうか」に置くという考え方は、すぐに結果が出ないと諦めてしまう私たちの世代にとって、行動を継続する上での大きな指針になる。最後に語られた、感謝の念を持つこと、そして「感謝されること」が最高の幸せだという哲学は、社会への貢献の根源的な意味を理解する上で、最も心に響くものであった。










