浅野日本酒店は、「買えるし、飲める。」を合言葉に純米酒を中心とする日本酒の魅力を伝える酒販×スタンディングバーのハイブリッド店です。大阪・梅田の創業店を拠点に、関西・首都圏へ展開。店内では常時約150銘柄を利き比べでき、気に入ったお酒をその場で購入可能—“試して、買える”体験が特長です。運営会社は株式会社浅野日本酒店(酒類小売・飲食店経営/代表取締役 浅野洋平、2016年設立)。2025年1月には横浜店オープンを予定し、イベントや蔵元紹介を通じて日本酒文化の裾野を広げています。
<聞き手=石嵜渉(学生団体GOAT編集部)>
【今までの経緯・背景】
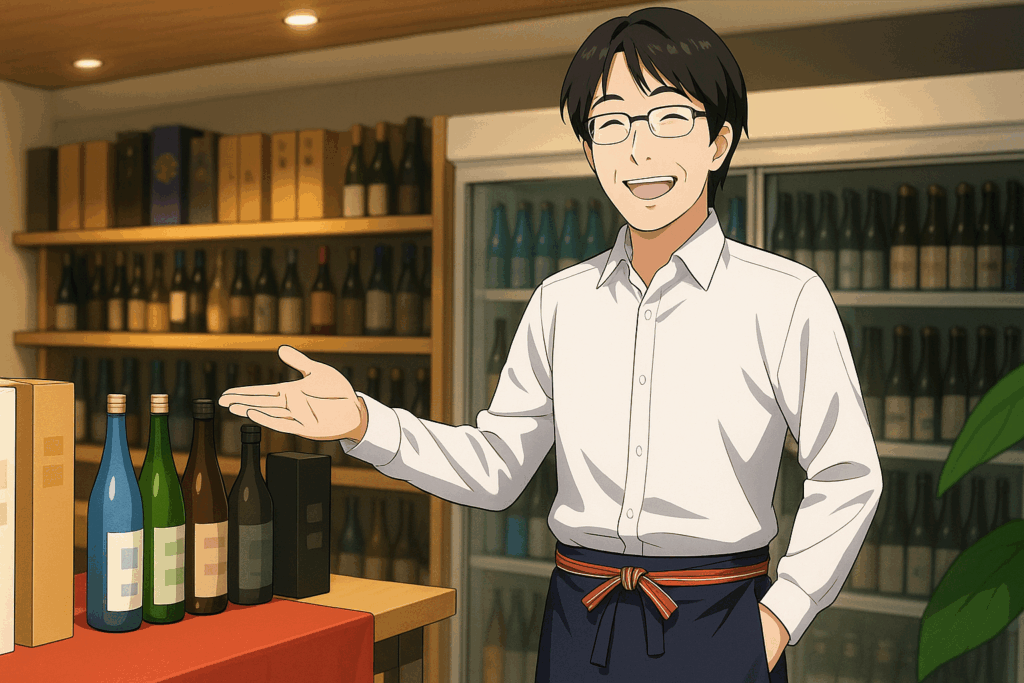
私が浅野日本酒店を立ち上げたきっかけは、私自身が元々お酒好きであったことです。今の商売を始める前はサラリーマンをしていましたが、親が元々事業主をやっていたこともあり、「いつか何かをやりたい」という思いが昔からありました。その中で日本酒を選んだ理由は、やはり「好きなことやりたい」というシンプルな理由です。仕事と趣味は一緒にしない方がいいと言われることもありますが、私は一緒の方がいいと思っています。なぜなら、楽しいことを突き詰めることができるからです。
しんどくなるぐらいの趣味だったらやらない方がいいかもしれませんが、できるのであればやった方が、とても楽しいと感じています。私はやりたいことやっているという感覚です。この会社を立ち上げてからちょうど10年になります。私は基本的に、寝ている時間や食事、少し遊んでいる時間以外は仕事をしている状態です。おそらく労働時間はかなり長いと思いますが、何より仕事が楽しくて仕方がないと感じています。
1日24時間のうち、約6時間睡眠をとり、プライベートに3時間使ったとしても、ざっくりと15時間くらいは仕事をしている感覚です。仕事の仕方は、単に店に立つことやデスクワークだけではありません。例えば、いろんなお店に飲みに行ったりすることも、顔を繋いだり、他店の売り方を勉強したり、市場を勉強したりする仕事の一部だと考えています。全く日本酒が関わらない自分の時間というのは、おそらく1日8時間から9時間ぐらいしかないと感じています。
10年間経営してきて、特に大きな苦労があったかと問われると、正直、好きなことをやっているので、そこまで「苦労」だと感じたことはありません。もちろん、お客さんが少ない時や、特に新型コロナウイルス感染症のパンデミックの時期は非常に大変でした。しかし、それは業界全体が皆一緒だったことなので、仕方がないことだと捉えています。基本的には、楽しいことをしているので、「苦労だった」というようなことは正直思いません。
取材担当者(石嵜)の感想
創業のきっかけが「好きなことを仕事にする」という非常に明快な動機であることに、まず共感を覚えました。さらに、社長自身が「仕事が楽しくて仕方がない」と感じ、1日15時間ほど仕事に熱中しているという姿勢は、まさにワークとライフを分断しない生き方を体現されていると感じました。これは、自分の人生を豊かにするための「手段」として仕事を捉えるのではなく、「人生そのもの」として捉えているからこそ実現できることです。就職活動において、自分が本当に情熱を注げる領域を見つけることの重要性を再認識しました。

【事業・業界について】
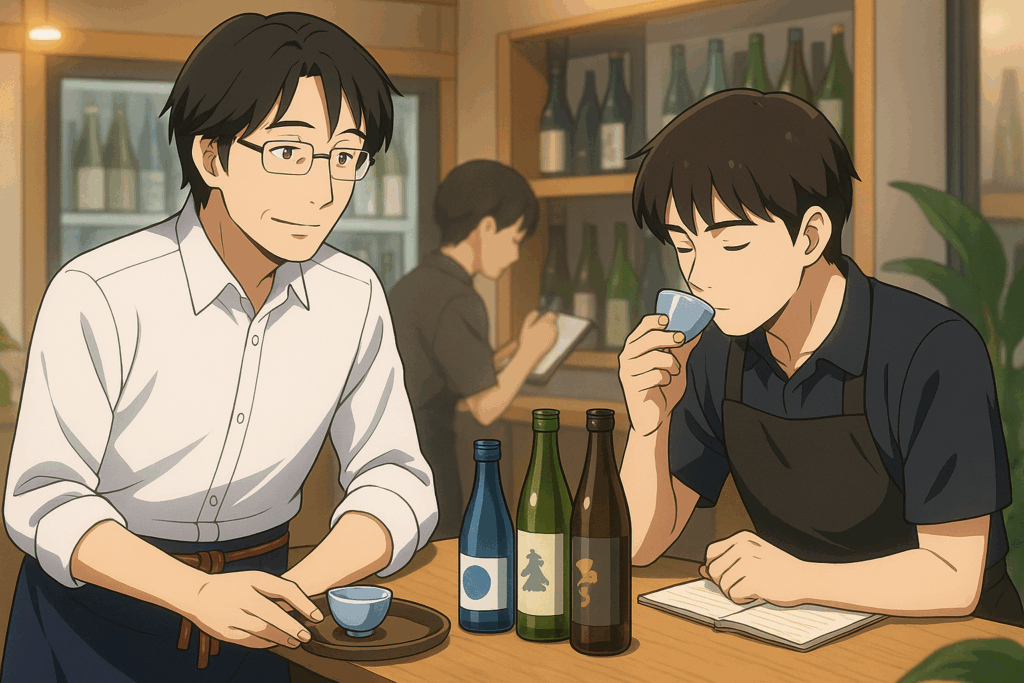
当社の採用に関しては、比較的うまくいっていると感じています。なぜなら、会社自体が非常に分かりやすいからです。私たちは日本酒の店なので、日本酒が好きで、日本酒に興味があり、学びたいという人しか採用しません。逆に言えば、日本酒の仕事がしたいと思った人にとっては、働く場所が分かりやすいといえます。また、当社の店舗は現在5店舗あり、いずれも都会や県庁所在地のターミナル駅徒歩圏内にあるため、働きやすい環境であることも、良い人材を集めることにつながっていると考えています。
業界全体の人手不足については、もちろん認識しています。しかし、それは日本酒業界に限らず、ほぼ全ての業界で直面している課題ではないでしょうか。重要なのは、業界全体でどうこうという話ではなく、結局は会社ごとに状況が異なるということです。うまくやっている会社には応募がいっぱい来る、というのはどんな業界でも同じだと思います。例えば飲食業だって人手不足と言われる中で、全然採用に困っていない店もあるのです。
採用や人材の定着について、私が最も重要だと考えているのは「商品力」です。商品がしっかりしているからこそ会社の魅力があると思いますし、魅力的な会社だからこそ良い商品をちゃんと作れるという両輪の話だと考えています。お酒がまずくて、どこでも買えるようなお酒を扱っていて、会社も魅力的でなければ、誰も来てくれないでしょう。給料が良ければ来る人もいるかもしれませんが、やはり商品が一番、会社を具現化していると私は思います。
人を集めること(採用)と、会社の内部を強くすること(定着)は分けて考えるべきではありません。商品開発や営業、経理など、会社全体が全てにおいてちゃんとしていれば、人はまず集まると思います。そして、人が来ても会社の内部がボロボロであればすぐに辞めてしまうので、定着も非常に重要です。人を辞めさせないこと、長く続けてもらうことが非常に大事です。定着のためには、給与や福利厚生、労働時間ももちろん重要ですが、やはり一人ひとりと喋り、向き合っているかどうかが最も大切だと考えています。
気持ちが入らないと、究極的に良い仕事にはならないからです。私はスタッフと飲みに行ったりしてよく話すようにしています。飲みニケーションは今あまりない風潮ですが、飲みに行って話すことで「この人のために頑張ろう」とお互いに思えれば、結果的に良い仕事になると思います。たとえ能力が高くても、気持ちが入っていなければ良い仕事には繋がらないのではないでしょうか。
取材担当者(石嵜)の感想
日本酒という特定の領域に特化しているからこそ、採用においてもミスマッチが少ないという点は、企業理念を明確化することの強みだと感じました。さらに、採用と定着の根幹を「商品力」に見出している点が非常に勉強になりました。
学生はつい企業の福利厚生や給与に目が行きがちですが、自分が愛着を持ち、熱量を持って提供できる「商品」があるかどうかが、働く上での自信ややりがいに直結するという指摘は、就職先を選ぶ上で非常に重要な視点だと思います。一人ひとりの従業員と真摯に向き合うことで定着を図るという姿勢は、現代の働き方に合致する素晴らしい考え方だと感じました。

【今後の展望】
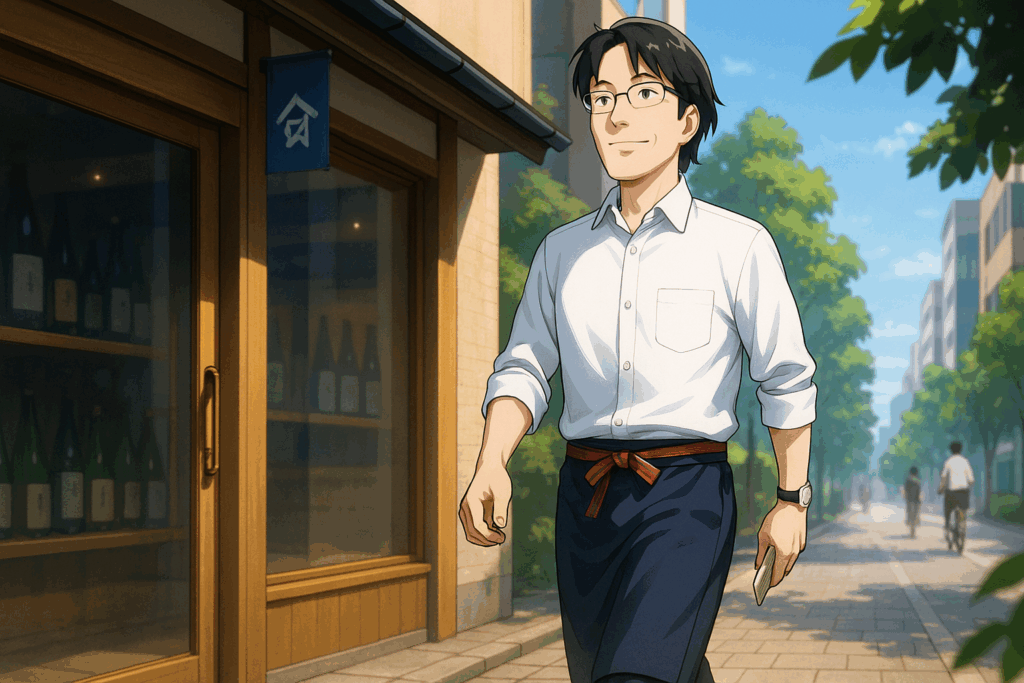
今後の展望として、正直、大それたことは考えていません。自分ができる範囲で、事業を広げていきたいと思っています。現在5店舗ありますが、まずは10店舗にはしていきたいと考えています。これはあと5年か10年ぐらいで達成できると思っています。おかげさまで、どの店舗も順調に推移しています。
その先のことはまだ深く考えてはいませんが、とにかく今は、店舗を増やし、日本酒を飲んでくれる人を増やしたいと考えています。日本酒を広げていくことが、私にできることです。大それた違うことをやるというよりは、今の本業に集中し、地道に店舗を増やしていくことしか今のところありません。
日々営業を頑張り、お客さんを増やしていく。そして、その結果として店を増やしていくという流れです。この目標は、単に規模を拡大することだけでなく、日本酒という文化をより多くの人に広め、定着させるという使命感に基づいています。大したことない答えで申し訳ないのですが、これが私の考える今後の展望です。
取材担当者(石嵜)の感想
現在の5店舗から10店舗への拡大という目標は、具体的な数字でありながら、地に足の着いた地道な努力の積み重ねを重視する社長の姿勢が表れていると感じました。目の前の本業に集中し、着実に事業を拡大していくという考え方は、華やかなスタートアップのイメージに憧れる学生に対して、事業継続のリアリティを伝える貴重なメッセージとなるでしょう。

【学生へのメッセージ】
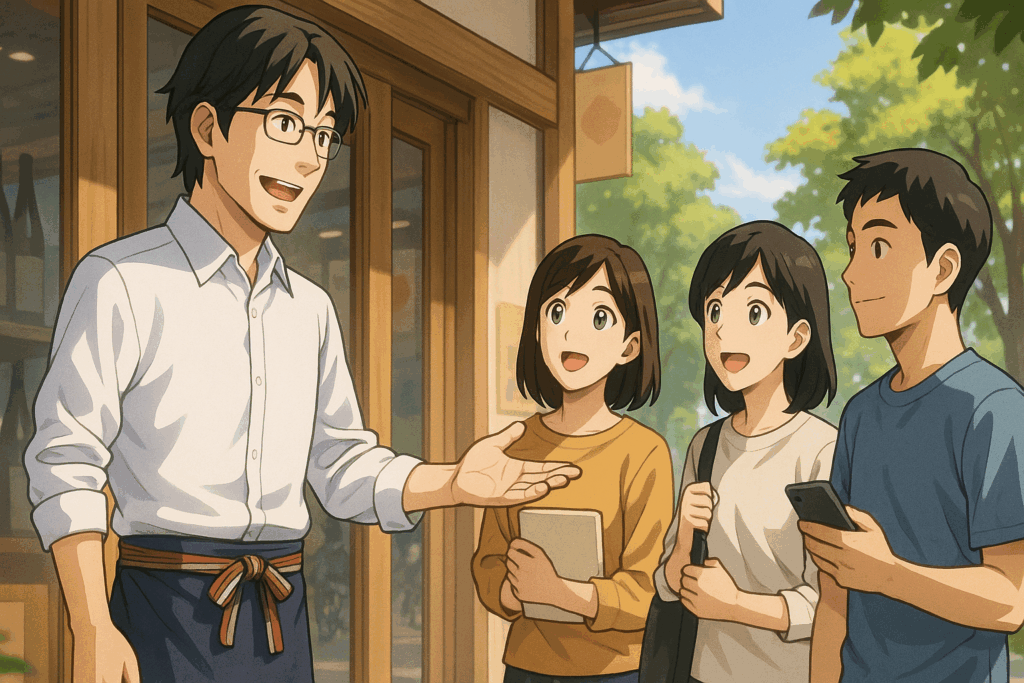
私から学生の皆さんへ伝えたいことは、まず「とにかくやったらいい」ということです。起業であれ、新規事業の立ち上げであれ、やりたかったらどんどんやってみればいいと思います。もちろん、始める前に準備をすることは大切ですが、準備をきっちりしたからといって成功するわけではありません。成功率は高まると思いますが、「畳の上の水練」ではありません。畳の上でいくら水泳の練習をしても上手にならないのと同じで、やってみて、修正して、というプロセスの方が絶対に成長します。水に溺れながら、自転車に乗る時は転びながらやるように、実践を通して学ぶのが本質です。
今の時代は、スタートアップしやすい環境が非常に整っています。昔に比べて、お金を借りやすい創業支援的な制度や補助金もありますし、若者が何かを始める時にヘルプしてくれるような人も多いです。クラウドファンディングのような仕組みもあります。昭和や平成の初めから比べると、今はすごくスタートアップしやすい時代だと私は思います。
しかし、実際に最初の一歩を踏み出せる人は、全体の1割ぐらいしかいないと私は思います。皆、やりたい気持ちはあるのに、やらないだけなのです。お金や失敗への不安など、色々な不安があると思いますが、結局そこで踏み出せないということは、もうできないということです。やりたければやればいいし、やれないのなら大人しくしていればいい、というのが私の考えです。おそらく、10人に1人ぐらいしか決断できる人はいないでしょう。計画はもちろん立てますが、私は100%準備が整った状態でスタートしたわけではなく、だいたい6割くらいの準備で「なんとかなる」と思ってやっていました。
若いうちに挑戦できるのは本当に特権だと私は思います。若い時こそ体力もあり、行動力もあり、やれることが多いです。年を取ると、だんだんそういうことがしんどくなってきます。そして、若いうちに始めた方が、仲間や味方が増えやすいという利点もあります。例えば、私の知り合いには22歳で酒屋を始めた人や、24歳で酒蔵を買収した人がいるように、若いというだけで話題になりやすいのです。早く始める方が得なことは間違いありません。人生一度きりなので、いつまで経っても動かなければ動けないまま終わってしまいます。思い切って飛び込める人自体が少ないので、ぜひ挑戦してください。
取材担当者(石嵜)の感想










