秋田県仙北市角館町に根差す株式会社安藤醸造様は、嘉永六年(1853年)創業の老舗企業です。享保の昔から角館の地主として、米の一部を原料に味噌や醤油を醸造し始め、現在は味噌、醤油、漬物の製造を専業としています。170年以上にわたり、代々受け継がれてきた伝統の味を守りながら、常に新しい挑戦を続けている企業です。今回は、170年を超える伝統を守りながらも、時代の変化に合わせて進化を続ける姿勢、そしてこれからの挑戦について、株式会社安藤醸造 代表取締役専務・安藤様にじっくりとお話をお伺いしました。
<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>
【入社の経緯と家業への想い】

私は、幼少期から家業が営まれる環境で育ち、いずれは自身がこの家業を継ぐものだと自然に考えていました。弟や妹がおりましたが、私の父が家業を継いでいたこともあり、それが当然の流れだと感じていました。その中で、地元への深い愛着と、地域の方々がこの「商売」を大切にしてくださっているという実感から、「これは自分でやりたい」という強い思いが芽生えました。
家業を継ぐ上で、専門知識を深めることの重要性を感じ、私は東京農業大学の醸造科学科に進学しました。そこでは、味噌、醤油、酒など、醸造に関する学問に没頭しました。将来的に家業を継ぐという意思を明確にした上で就職活動を行い、一旦は別の企業に入社しました。東京での約6年間の勤務は、家業とは全く異なる野菜の宅配事業に携わるもので、外の世界を知る貴重な機会となりました。
そして30歳を機に、私は故郷の角館に戻り、安藤醸造の専務として新たな一歩を踏み出しました。この決断は、これまで培ってきた知識と経験を家業に活かしたいという強い思いがあったからです。家業を継ぐという道は、私にとって幼い頃からの自然な流れであり、同時に自らの意思で選び取った道でもあります。
取材担当(高橋)の感想
安藤様のキャリアパスからは、家業への深い理解と、それを継ぐための計画的な準備が感じられます。特に、専門分野での学びと、一度社外で経験を積んでから家業に戻るという選択は、将来的に家業を継ぎたいと考える学生にとって、非常に参考になるのではないでしょうか。目の前の「継ぐ」という道だけでなく、多角的な視点から自身のスキルを磨くことの重要性を教えてくれます。

【老舗の伝統を守りながら、挑戦し続ける革新】
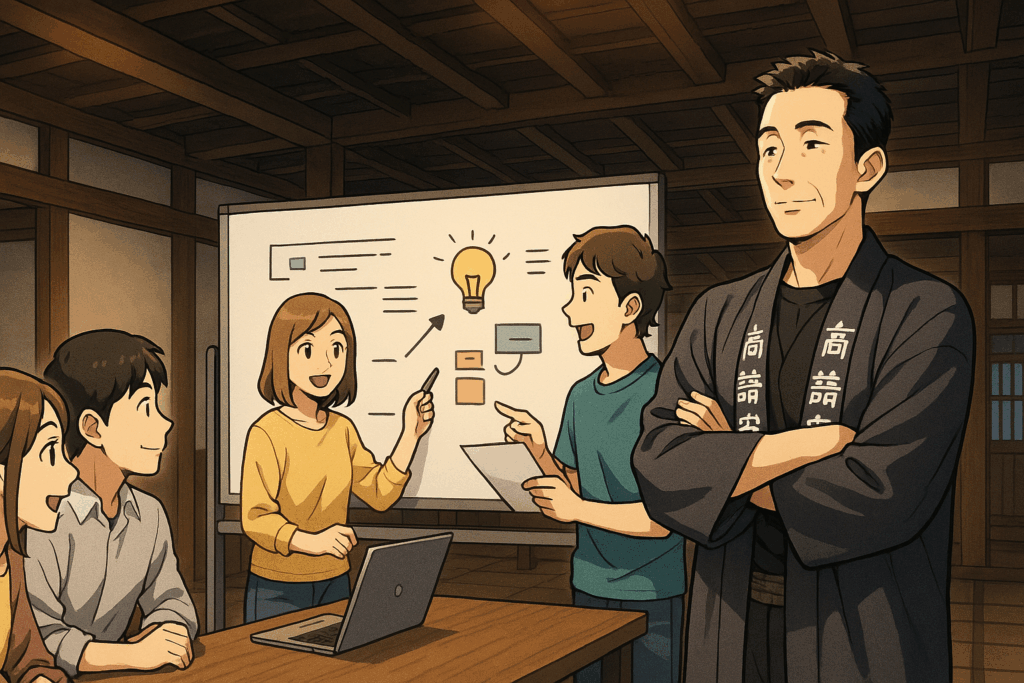
安藤醸造に戻ってきてから、私は多くの変革を手がけてきました。商品開発はその代表的な例です。今はまだ社長ではありませんが、経営の大部分を任されています。特に力を入れているのは、大学とのコラボレーションです。国際教養大学の学生たちと2〜3ヶ月間住み込みで、当社が抱える大きな課題を解決するためのプロジェクトに取り組んでもらっています。
学生たちは「デザイン思考」を活用して具体的な打ち手を考案し、PDCAサイクルを回しながら実践します。私たちは大きな課題のみを提示し、「これをやりたい」という学生の提案に対し、「なぜそう思うのか?」といった根本的な問いかけから、予算、実行、検証まで、すべてを学生自身に考えて実践してもらっています。この活動を通じて、学生は就職後もなかなか経験できないような、自ら考え、実践する貴重な機会を得ていると私は考えます。
当社の最大の強みは、170年にわたる味噌・醤油づくりの技術と歴史に裏打ちされた確かな品質だと考えています。私は、「間違いない商品、美味しい商品を作っていくこと」こそが重要だと考えています。そのため、時には価格がやや高くなることもありますが、それに見合う価値をお客様に提供することを目指しています。
また、社屋である蔵そのものも、東北で最も古いとされる170年の歴史を持つものであり、その管理には特別なこだわりがあります。それは、「時間はお金で買えない」という私の哲学に根差しています。100年前のものを今から作ろうとしても不可能であり、時間が経つことで生まれる価値を何よりも大切にし、それを守り続けています。
取材担当(高橋)の感想
170年の歴史を持つ老舗でありながら、安藤醸造様がこれほどまでに新しい試みに意欲的であることに感銘を受けました。特に、学生とのコラボレーションは、単なる社会貢献に留まらず、企業側にも新しい視点をもたらし、次世代の育成に貢献するという点で、素晴らしい取り組みだと感じます。伝統を守りつつも、時代に合わせて変化を恐れない姿勢は、企業が成長し続ける上で不可欠な要素だと改めて認識させられました。

【地域と共に歩む危機感と未来への展望】
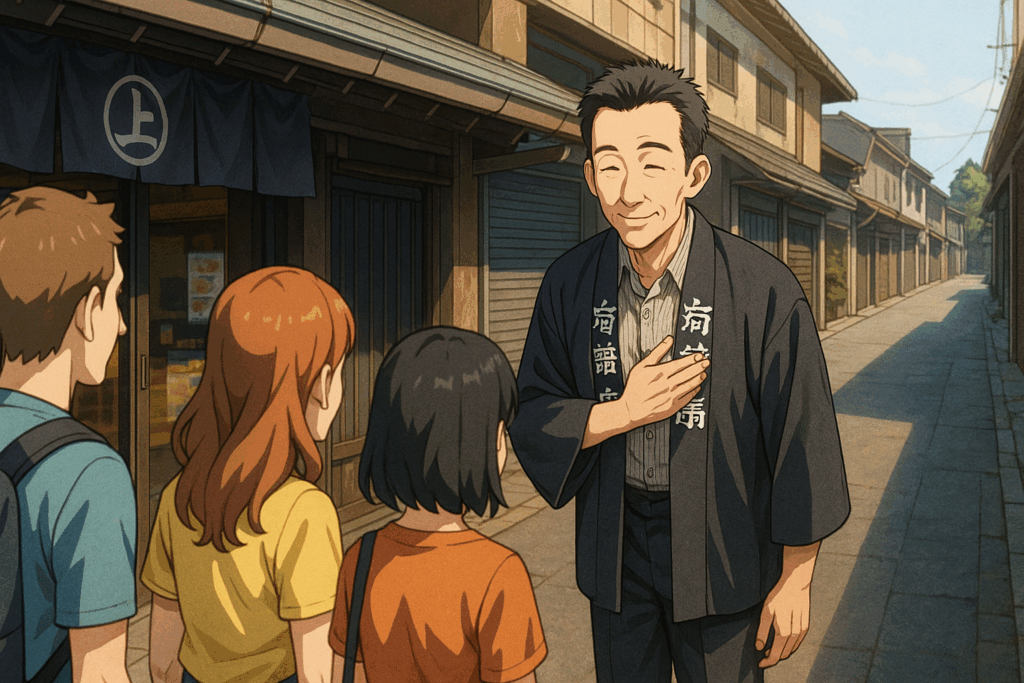
当社は、秋田という地域に深く根差しながらも、現代日本が直面する社会課題、特に人口減少に強い危機感を抱いています。秋田県は全国でも突出して高い人口減少率を抱えており、角館でも空き家が増えている現状があります。これは、味噌や醤油といった基礎調味料の消費量減少にも直結し、事業の存続に関わる喫緊の課題だと捉えています。
味噌や醤油の消費量は、核家族化の進行や食生活の変化に伴い、減少傾向にあります。例えば、朝食に味噌汁を作る機会が減ったり、昔は少なかった様々な調味料が登場したりすることで、食卓における味噌や醤油の「出番」が少なくなっていると感じています。さらに、社内においても高齢化が進み、20代の若い人材が不足していることも課題として認識しています。新卒採用も行っていないため、若手育成は喫緊の課題です。
こうした現状に対し、私は積極的に改善策を講じています。例えば、ブランディングの一環としてパッケージの統一を進め、接客レベルの向上にも注力しています。価格はやや高めでも、その分の価値を伝え、お客様に選ばれる商品づくりを目指しています。当社の店舗を「目的地」として、国内外から多くの観光客が角館、ひいては秋田を訪れるきっかけとなるよう、魅力的な店づくりを進めていきたいと私は考えています。
安藤醸造が地域全体の活性化に貢献し、お客様だけでなく、街や市、そして県全体が「みんながハッピーになる」ような良い循環を生み出すことが、私の長期的な目標です。当社を目指して多くの人が秋田に来てくれるような、地域を牽引する存在になりたいと願っています。
取材担当(高橋)の感想
地域社会が直面する厳しい現実を直視し、それを自社の課題と捉えて行動する安藤様の姿勢には、真のリーダーシップを感じました。単に自社の利益を追求するだけでなく、地域全体を巻き込み、活性化させようとするビジョンは、社会貢献への意識が高い現代の学生にとって、非常に魅力的に映るでしょう。企業が地域と共に歩むことの重要性を改めて教えてくれる内容でした。

【次世代へのメッセージ:情報の活用と主体性】
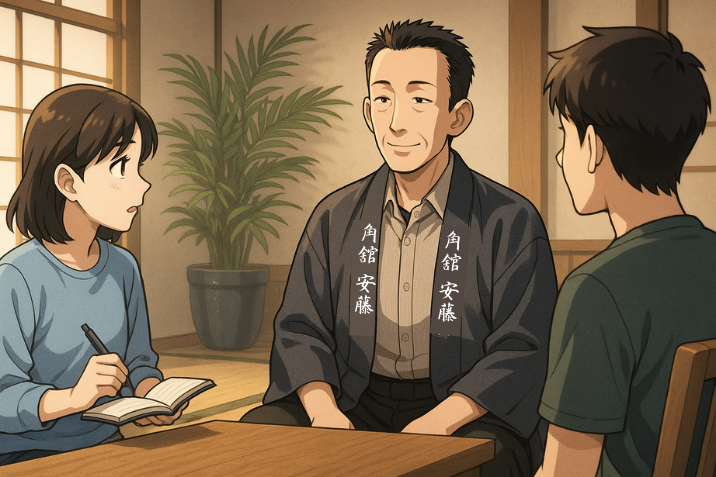
Z世代や若い世代へのアドバイスとして、私は「情報の使い方」が非常に重要だと考えています。現代は情報が溢れ、意識せずとも多くの情報が耳に入ってくる時代です。しかし、そこで大切なのは、その情報が単なる「ツール」であることを理解し、その上で「自分はどうしたいのか」を主体的に問い、行動することです。「この情報がある、あの情報がある」と羅列するだけでなく、その情報を「どう活用するか」が問われています。情報を受け取るだけでなく、それをいかに自身の意思決定や行動に繋げるか。これが、これからの時代を生き抜く上で非常に大切な力だと私は考えています。あくまでも情報はツールであり、そのツールをどう使うかは自分次第です。
また、特定の世代という区切りにとらわれず、自分より若い世代、あるいは県外出身者や移住者など、多様な視点を持つ人々の意見を積極的に取り入れることが重要だと考えています。異なる視点から得られる気づきは、すぐに具体的な成果に繋がらなくとも、やがて何かを解決しようとする際に役立つ「引き出し」となり、自身の成長にも繋がると信じています。これは、これからの社会を担う若い世代の視点を大事にしたいという思いがあるからです。
取材担当者(高橋)の感想
情報過多な現代において、「情報はいかに活用するか」という安藤様からのメッセージは、私たちZ世代にとって非常に示唆に富んでいます。SNSなどで多くの情報に触れる機会があるからこそ、その情報を鵜呑みにせず、自らの頭で考え、行動に移す力が求められていると実感しました。異なる視点を積極的に受け入れる柔軟な姿勢も、未来を切り拓く上で不可欠な要素だと感じました。










