株式会社KOA-LABOは、新潟を拠点に介護サービス「あいごケア」、児童福祉・教育サービス「SPARK」、フィットネスデイサービスなど、多岐にわたる事業を展開しています。私たちのビジョンは「信頼しあい 感謝しあい 夢を語りあい いつも笑顔で全ての関わる人々の 『幸せの花を咲かせよう』」であり、これは「Blooming of happiness」と表現されています。人々の健康を人生の幸せの根本と考え、利用者様一人ひとりが輝くライフステージを送れるよう、様々なサービスを通じてサポートしています。今回は、多角的な福祉・教育サービスを通じて「幸せの花」を咲かせる株式会社KOA-LABOの取り組みと、その根底にある想い、そして今後の展望について、じっくりとお話をお伺いしました。
<聞き手=石嵜渉(学生団体GOAT編集部)>
【吉田様の今までの経緯・背景】
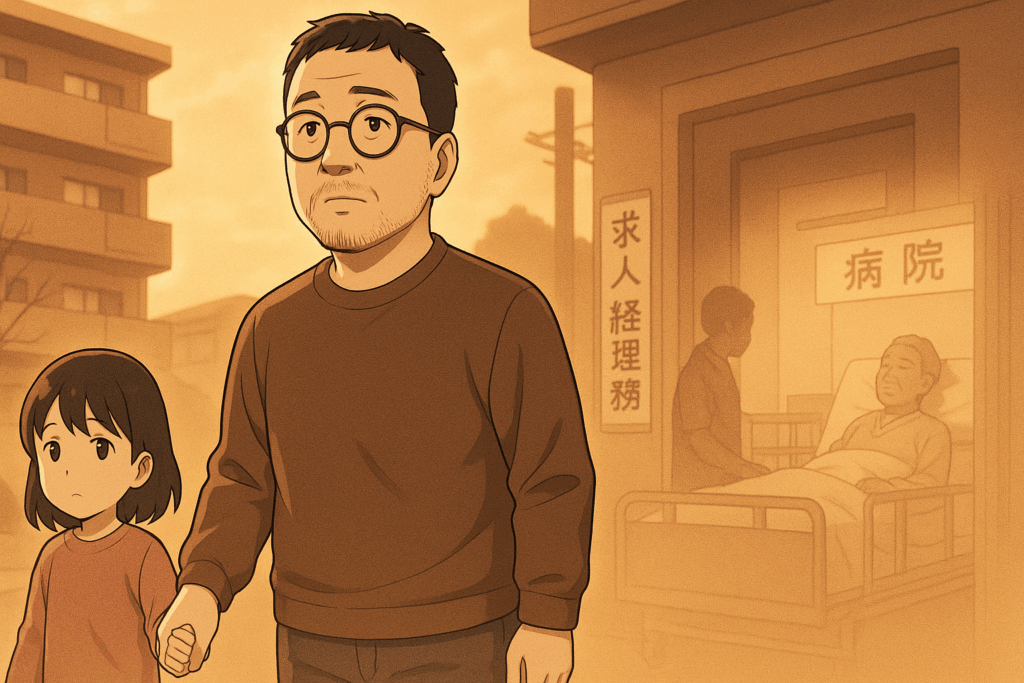
私が全く異なる異業種から介護業界に入ったのは、今から23年前、40歳の時でした。当時はサラリーマンを辞め、娘が幼かったこともあり、2年間ほど専業主夫として子育てに向き合っていました。妻が公務員として安定した職に就いていたこともあり、私が家庭に入るという選択をしました。ちょうどバブル崩壊後の就職が難しい時期で、転勤があるような働き方はワークライフバランスが崩れると考え、新しい道を模索していました。
そんな中、自宅近くの会社で経理総務事務の募集を見つけ、それが現在の会社の前身でした。創業間もない頃で、当時の社長は市議会議員も務めており、片手間で事業を行っているような状況でした。そこで手伝いをすることになったのが、この業界に入る直接的なきっかけです。同時期に、一人暮らしだった義父が脳梗塞で倒れ、要介護4となり入院しました。
2ヶ月ほどで退院を促され、施設を探すことになったのですが、これが非常に大変でした。どこにどんな施設があるのか情報が少なく、行政やケアマネージャーに聞いても明確な答えが得られない状況を経験し、この国の制度に対して疑問を感じたことも、この世界に入る大きな要因となりました。
元々、介護や福祉の業界でやっていこうという思いは全くなく、むしろ切羽詰まって、なんとなく行き着いた先がここだったというのが正直なところです。かっこいい話ではなく、システム的に行き詰まってたどり着いた場所でした。
取材担当者(石嵜)の感想
吉田社長が異業種から介護業界へ参入された背景には、子育てや家族の状況、そして社会の現状に対する問題意識など、様々な要因が複雑に絡み合っていることが分かりました。
特に、ご自身の主夫経験や義父の介護経験から、この業界の課題を肌で感じられたことが、その後の事業に対する強い原動力になっているのだと感じました。壮絶なご経験を乗り越えられて、今の事業に繋がっているのだと、社長の言葉から熱量を感じることができました。

【吉田様から学生へのメッセージ】
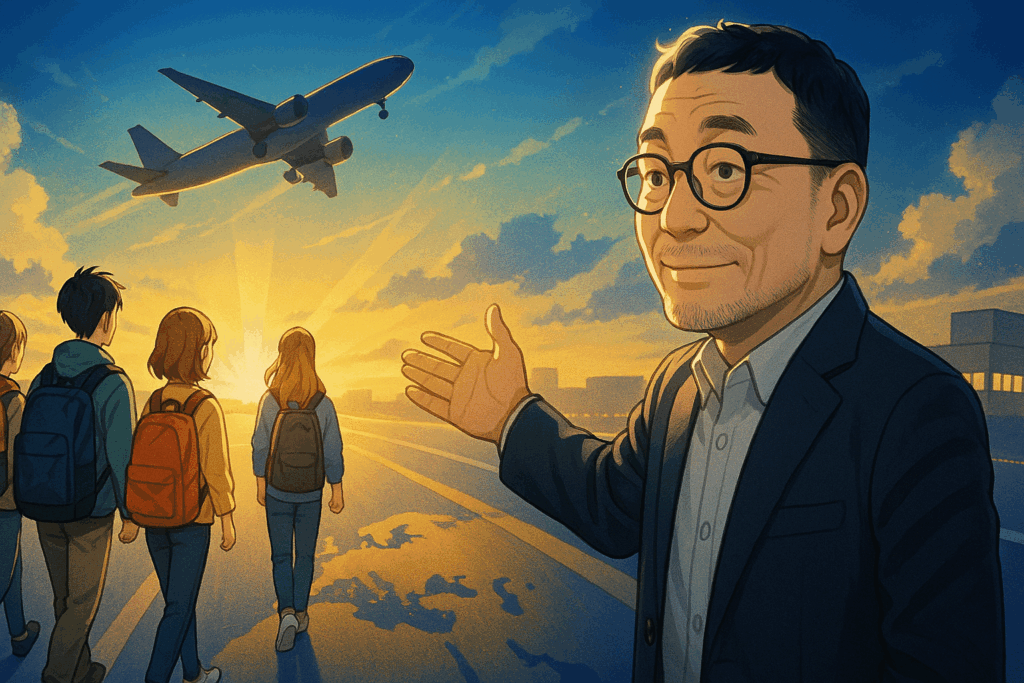
若い皆さんにお伝えしたいのは、抽象的に言えば「チャレンジ」することです。とにかく挑戦してください。そして、大切なのは「失敗」することです。挑戦と失敗、つまりトライアンドエラーこそが、皆さんの最も大きな成長につながると確信しています。
具体的に皆さんにおすすめしたいのは、日本から出て「旅」をすることです。全く違う国に行き、そこで様々なことを感じ取ることが、必ず皆さんを成長させてくれます。考えているだけでは何も始まりません。
海外に行きたいと思いながら何年も経ってしまったという話がありましたが、それは非常にもったいないことです。お金がない、時間がないなど、色々な言い訳を考えてしまうものですが、計画なんて実はそれほど必要ありません。飛行機の中で計画を立てることも可能です。どこに行っても学びはあります。
東南アジアでも、他の国でも、その国ならではの学びがあります。難しく考えすぎず、何を食べたいか、どんなものを見たいかといったシンプルな動機でも構わないので、まずは一歩踏み出すことが重要です。
取材担当(石嵜)の感想
「チャレンジ」と「失敗」の重要性、そして「旅」をすることの価値についてのお話は、私自身にも深く響きました。海外に行きたいと思いながらも、様々ないいわけをして一歩踏み出せずにいた自分自身の状況と重なり、まさに「ギクっと」きました。
計画ばかり立てて行動に移せないことのもったいなさ、そして時間の有限さについて改めて気づかされました。社長の力強いメッセージは、多くの学生の背中を押してくれると確信しています。

【株式会社KOA-LABOの事業・業界について】
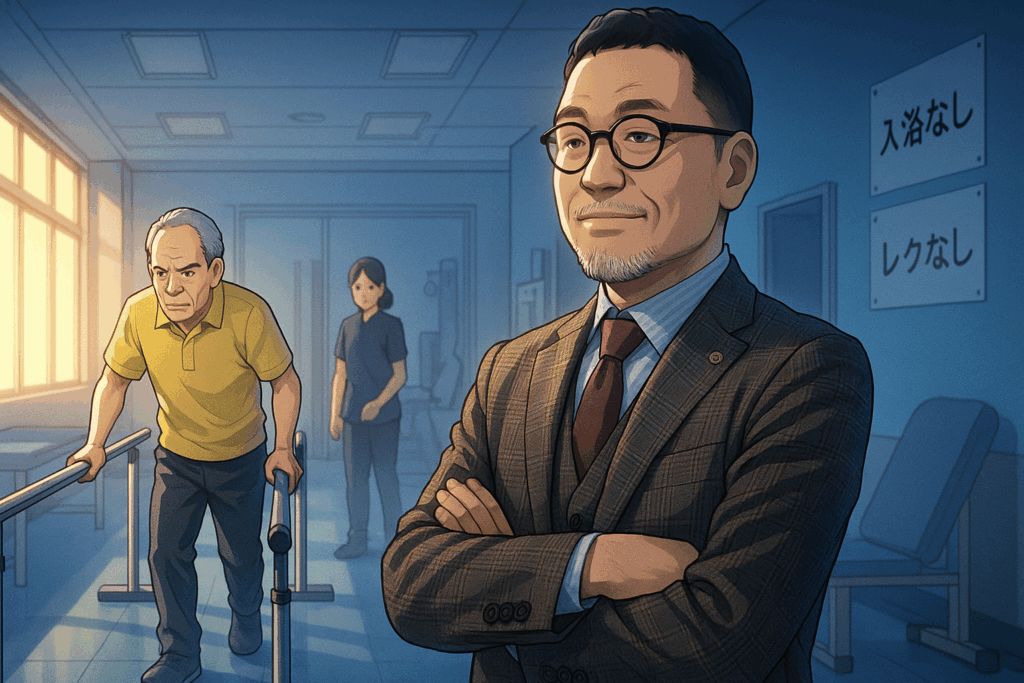
私の事業方針は、「人がやっていることをやりたくない」というものです。介護業界に入った当初、デイサービスといえば利用者を預かることが中心でした。しかし私は、あえてその真逆を行くような、お風呂も昼食もなく、レクリエーションもない「機能訓練特化型」のデイサービスを始めました。
これは当時の常識から外れており、周囲のケアマネージャーからは「そんなのはデイサービスではない」と批判もされました。しかし、それは既存の「固定観念」に捉われているだけであり、私はそれとは違う世界、より良い世界を作りたいと考えていました。
事業の核として私がフォーカスしたのは「健康」です。人生において、健康に生きることこそが最も重要であり、それが幸せの根本だと考えているからです。機能訓練特化型デイサービスは、まさに健康に焦点を当てた取り組みです。
機能訓練しか行わないこのサービスから、介護度3だった方が新潟マラソンを完走するという素晴らしい成果も生まれました。これはご本人の努力があってこそですが、このような世界が実現できたことは事実です。
現在は、介護サービスだけでなく、フィットネスや児童福祉・教育サービスなど、多角的な事業を展開しています。これは、将来的にマーケットがシュリンクしていく(人が減っていく)ことを見据え、多様な事業ポートフォリオを組むことが重要だと考えているからです。子供たちの教育においても、健康へのフォーカスは共通しており、プログラミング教育では「Steam education」という概念を取り入れています。
これは、創造力を育むことに重点を置いた教育であり、日本の「答えは一つ」という視野狭窄な教育とは異なります。この国に必要なのは、新しいものを受け入れ、変化していくことです。変化こそが成長であり、失敗を恐れずに挑戦する姿勢が求められます。
現在の介護業界は深刻な人材不足に直面しており、他の産業でも求人倍率が非常に高くなっています。これは、少子化対策など、政治が本来やるべきことをおざなりにしてきた結果だと感じています。短期・中期的な人材対策としては、海外人材の活用が非常に重要だと考えています。
海外の方々は真面目で目が輝いており、一緒に働くことで私たちも学ぶことが多いと感じています。しかし、言葉や文化の壁もあり、彼らが抱えるリスクに対して、受け入れ側(行政も含め)の準備が十分でない現状があります。相手の文化を尊重し、相互理解に基づいたコミュニティづくりが必要だと感じています。
取材担当(石嵜)の感想
吉田社長の「人がやっていることをやりたくない」という事業に対する考え方が、機能訓練特化型デイサービスのような革新的なサービスの誕生に繋がっているのだと分かりました。また、事業の多角化も単に手を広げているのではなく、将来の市場環境を見据えた戦略であること、そして全ての事業の根底に「健康」と「人々の幸せ」があることに感銘を受けました。
人材不足という社会課題に対する現実的な認識と、海外人材の活用における相互理解の重要性についてのお話は、この業界が抱える課題と未来への展望を深く理解する上で非常に勉強になりました。

【株式会社KOA-LABOの今後の展望】
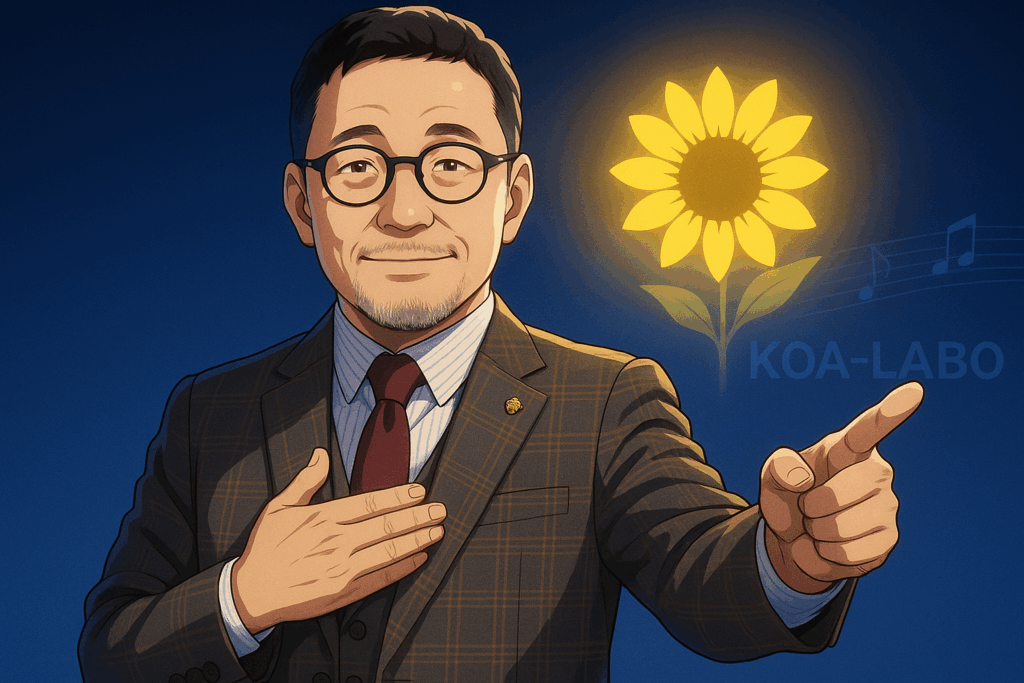
私たちの法人のビジョンは、「信頼しあい 感謝しあい 夢を語りあい いつも笑顔で全ての関わる人々の 『幸せの花を咲かせよう』」です。この「Blooming of happiness(幸せの花を咲かせよう)」というビジョンを達成するために、私が作詞・作曲した同タイトルのコーポレートソングもあります。
今後も、「健康」にフォーカスした取り組みを続けていきます。健康こそが人生の幸せの根本だと考えているからです。私自身もそれを体現していくつもりです。そして、健康をベースにした食物や運動プログラム、各種メソッドの開発を通じて、社会の課題解決に貢献していきたいと考えています。
児童福祉・教育分野では、「SPARK運動療育」というプログラムの普及活動に携わっています。これは発達障害の子どもたちに効果的な運動プログラムであり、ハーバード大学の脳科学者がエビデンスを作っています。これは世界的に見ても素晴らしい取り組みであり、私が日本に広めた第一人者となりました。
なぜこれほど力を入れているかといえば、子供たちの健康にフォーカスしているからです。子供たちは私たちの未来そのものであり、「Children’s Future」に時間と労力をかけるのは当然のことだと考えています。
私自身の生き方としてのミッションは、「既存の考えや常識に抵抗する」ことです。それを体現し、実証したいという思いが強くあります。だからこそ、常にアグレッシブに動き、新しいものを作り、今までなかったことをやりたいと考えています。そして、新しい発想を持つ若い人たちと積極的にプロジェクトを組んでいきたいと思っています。
取材担当(石嵜)の感想
「幸せの花を咲かせる」というビジョン、そしてその根幹にある「健康」への強いこだわりが非常に印象的でした。単なる事業展開ではなく、社会課題の解決や未来への投資(特に子供たちへのSPARK運動療育)に繋がる取り組みに感銘を受けました。
吉田社長の「抵抗する」という生き方や、新しい発想を歓迎する姿勢は、凝り固まった考え方や停滞しがちな社会に対する強いメッセージだと感じました。吉田社長の目指す未来が、これから社会に出る私たち学生にとって、非常に大きな希望となることを確信しました。










