奈良に蔵を構える倉本酒造は、1871年の創業以来、地の利を活かした酒造りを続けてきた歴史ある酒蔵です。
日本清酒発祥の地である奈良の都祁(つげ)に位置し、標高約500mの寒暖差が大きいこの地で育まれた良質な米と、自社の山で採取される清らかな山水を酒造りの要としています。
今回は、創業から今日に至るまで、この土地の恵みを活かし、伝統を守りながらも新たな日本酒のスタンダードを目指す倉本酒造の事業への取り組みや、その背景にある自然、歴史、そして酒造りへの想いを深く掘り下げてご紹介します。
日本酒業界に飛び込んだきっかけ

足立
日本酒業界に飛び込んだきっかけはどのような決意だったのですか?

私は家業として日本酒造りを行う家に生まれましたが、大学進学の際には日本酒に関する勉強ができる学部を選び、将来的に継ぐことを考えていました。
しかし、卒業時点で日本酒業界は右肩下がりで、市場規模も全盛期の1/4程度まで縮小してしまったのですね。そのため、当時は家業を継がず、父の代で酒蔵を終わらせる決断をし、一般企業に就職することを決意しました。
社会人として12年間働く中で、次第に「やはり日本酒造りをしたい」という気持ちが強まっていきました。
特に、父がサラリーマンの定年に近づいたころ、「自分が継がなけば、この酒蔵はなくなってしまう」という思いが募り、2015年の冬に退職を決意し、酒蔵に戻ることにしました。
事業を再建するまでの苦労
足立
事業を再建するまでは相当な苦労があったのではないですか?

はい。その通りです。
酒蔵に戻った時点では、販路がほぼなく、商品数も少ない状況でした。そのため、まずは自分の酒を作り、収益を確保できる状態にするまでに約5年を要してしまったのですね。
もともと当蔵の商売は地元向けの直販が中心で、流通に強みがあるわけではなかったため、新しい販路を開拓する必要がありました。
当初は販路がないことに苦しみましたが、それが逆に良い方向に作用しました。既存の流通に依存せず、新しい市場開拓に専念することができたのです。
特に、お酒の専門店への販路を拡大し、そこでブランドを確立することで徐々に認知度を上げていきました。

経営者としての信念
足立
そんな苦難を乗り越えた〇〇さんの経営における信念を教えてください。

現在、日本酒市場は縮小傾向にあり、単に流行に乗るだけでは持続的な成長が見込めません。
そのため、私はレッドオーシャン(競争の激しい市場)ではなく、ブルーオーシャン(未開拓の市場)を開拓することを意識しています。
具体的には、日本酒に馴染みのなかった人々が飲みたくなるような商品作りを目指し、新たな市場を形成することに注力しています。
しかし、現実的には現在の顧客層は日本酒愛好者が中心です。そのため、パッケージデザインや商品コンセプトを工夫し、より幅広い層に興味を持ってもらえるよう努めています。
h1
h2
h3
h4
h5
h6
- list1
- list2
- list3
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa







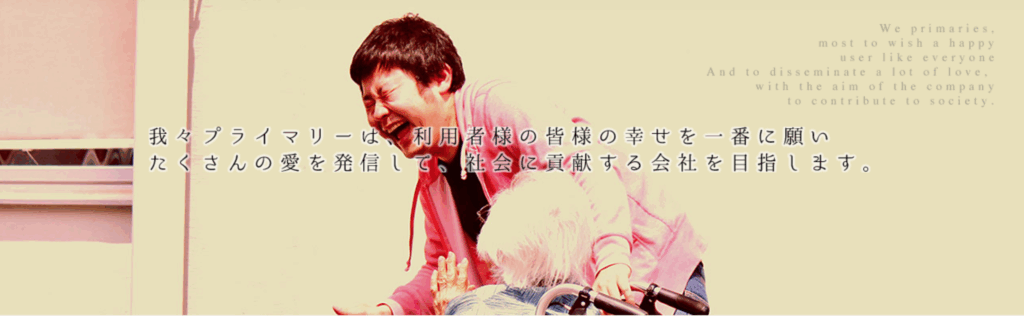

立体画像-1024x442.png)