株式会社フォレストファミリーは、2011年に設立された介護サービス事業者です。通所介護事業(デイサービス)、居宅介護支援事業、訪問看護ステーション、企業主導型保育園「もりなか保育園」を運営しており、0歳から100歳までの地域住民を支える企業となることを目指しています。創業のきっかけは、渡辺社長ご自身の家庭での介護経験でした。
当時の介護サービスに感じた「利用しづらい」「利用に抵抗がある」といった社会的なイメージや課題を解決し、「利用しやすいサービス」「喜ばれるサービス」を実現したいという強い思いを持って会社を立ち上げられました。介護職員不足という業界全体の課題にも向き合い、企業主導型保育事業を立ち上げるなど、職員が安心して働ける環境づくりにも力を入れています。今回は、地域に寄り添う多様なサービス展開の原点や、介護の枠を越えて挑戦を続ける姿勢について、株式会社フォレストファミリー・渡邊社長にじっくりとお話をお伺いしました。
【渡邉様の今までの経緯・背景】
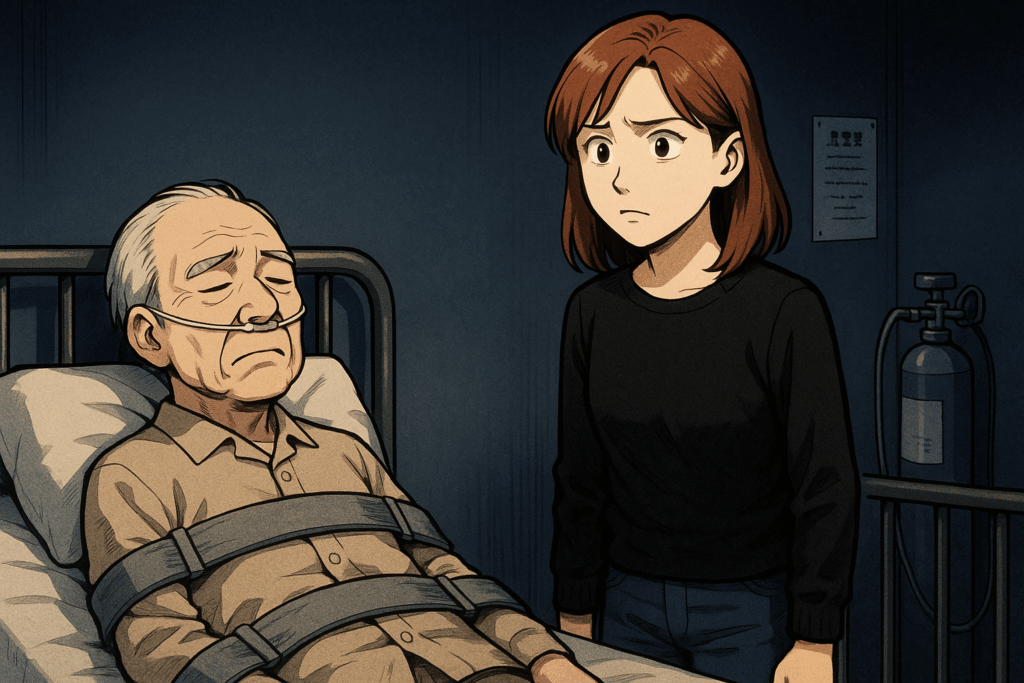
私の父は、私が小学校3年生の時に倒れ、麻痺が残る身体障害者でした。家庭で介護はしていましたが、私が大人になってから祖父母が高齢になり、当時の介護保険制度がなかった頃に祖父が認知症の症状を示し始めた時、家族はかなり戸惑いました。穏やかだった祖父が怒りっぽくなったり、徘徊したりする姿を見て、当時は「おかしくなってしまった」という捉え方で、認知症だと思いませんでした。
精神科などに連れて行った時、認知症かもしれないと言われ、病院から介護施設を勧められました。見学に行ったのですが、当時は虐待や拘束に関する整備が進んでいなかったため、歩き回ってしまう祖父はベッドの上で拘束されていました。その姿は私にとって衝撃的でした。ここまでしなくてはならないのかと思いながらも、家では見られないという状況に、今思うと後悔が強く残っています。
その後、今度は祖母をデイサービスに通わせようということになり、見学に行きました。そこでは、介護職員が利用者の方に赤ちゃん言葉で話しかけたり、レクリエーションで利用者が寝ていたり、参加を嫌がっているのにそのまま進めていたりするのを見ました。ここに祖母は通わせられない、そして私自身や両親も将来ここに来なければならないのかと思った時、これは正しいのだろうかという疑問を持ちました。その頃、私は飲食店のフランチャイズ本部で働いていました。
飲食業界ではサービスの質を追求し、1円単位でどう利益を出すかを追求していました。どうしても介護の世界が気になり、当時の会社の上司に副業としてアルバイトをさせてほしいと頼み、介護の会社で働き始めました。すると、本部には人がたくさんいて皆暇そうにしているのに、現場とのギャップを感じました。これは改善しなくてはならないと感じ、そこから自分でできないかと調べたり勉強したりするようになりました。
創業のきっかけは、行政の創業ベンチャー支援センターに相談に行ったことでした。当時は漠然と創業したいという思いだけで、拙い事業計画しかありませんでしたが、思いだけを乗せた内容のものでした。それを持っていったところ、コンペがあるから出てみないかと勧められました。コンペで改めて思いの丈、これは問題でこうするべきだということを話したところ、採択を受けました。そこからは創業アドバイザーもついてくれ、もう創業するしかないという流れで進んでいきました。
取材担当者(石嵜)の感想
渡邊社長の幼少期からのご経験が、介護業界の現状に対する強い問題意識に繋がっていることを感じました。特に、当時の介護施設の状況やデイサービスの見学で感じた疑問は、多くの人が利用に抵抗を感じる要因だったのではないかと共感しました。
飲食業界での経験で培われたサービスの質や利益追求の視点が、介護業界の改善に繋がると考えられた行動力に学びがありました。また、行政の支援をきっかけに創業の道が開けたというお話は、挑戦したいという気持ちを持つ上で参考になる部分だと感じました。

【渡邉様が感じた創業後の苦労】
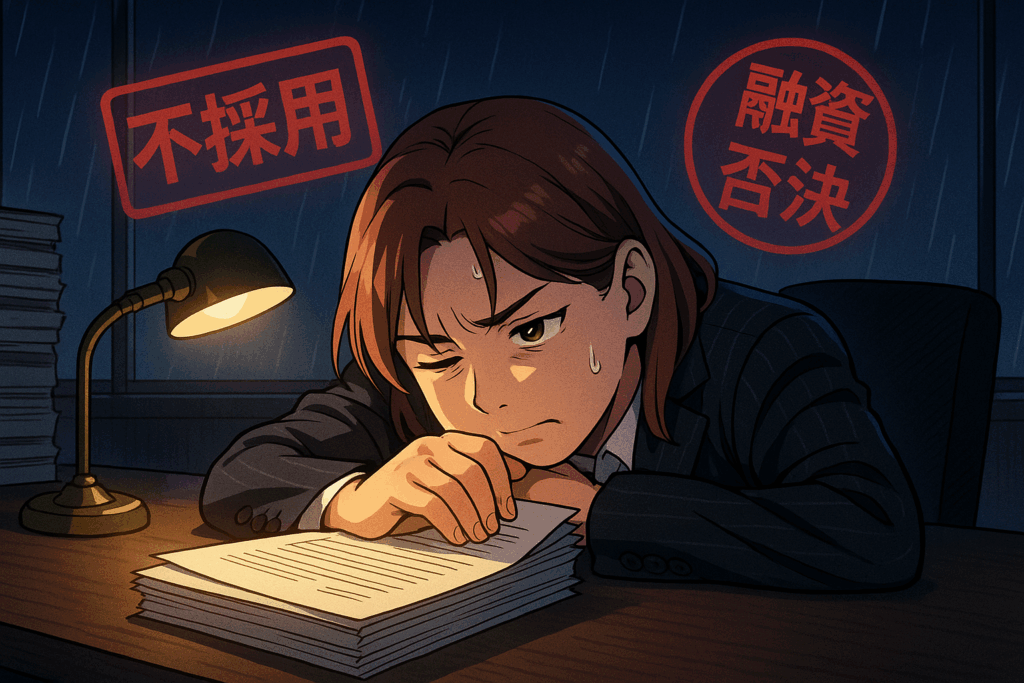
創業後の苦労は、アドバイザーにも「本を書いた方がいい」と言われるほどたくさんありましたが、その都度、苦労の中身は違いました。一番初めの頃は、ずっと資金繰りでした。創業時は思っていたより見込みが甘く、資金が全く足りませんでした。銀行からはそもそも貸してもらえない状況でした。
支援センターでアドバイザーについてもらい、事業計画を作って会社を設立する(2011年4月)までは誰でもできますが、そこから事業を始めるために必要な資金を借り入れる段階が大変でした。私は日本政策金融公庫で借り入れを5回断られました。通常、5回申し込む人はなかなかいないと思いますが、私は通るまで申し込もうと毎月申し込み続けました。さすがに3回目くらいになると、ここで終わってしまうのか、始められないまま終わるのかと感じました。
なんとか資金を借りて事業を始めましたが、私の予測は甘く、あっという間に資金が尽きてしまいました。一度借りているので、前回よりは銀行も貸してくれましたが、結局借りたら返さなくてはなりません。また、介護業界のことを知らずに飛び込んだため、闇雲に近隣の高齢者の家を回って挨拶してもダメだということが分かりませんでした。高齢者にはケアマネージャが担当についており、ケアマネジャーがサービスを提案すること、そしてケアプランを作成してもらわないとサービスを利用できないという仕組みを全く理解していませんでした。
きちんと仕組みを理解して売上を上げるところまでに、すごく時間がかかりました。その分、資金の無駄も多く、広告宣伝費などもたくさん使ってしまいました。それをひっくり返すのに10年くらいかかりました。銀行も本当によく貸してくれたと思います。創業時はこれが一番きつかったです。
その後も、3年ごとに毛色の違ったトラブルや倒産危機が何度かありましたが、これは創業した方なら皆同じだと思います。10年続く会社は1割に満たないと言われているので、多分そこで諦めるか諦めないかの差だと思います。私は諦めなかっただけです。14年経っても、まだまだ今の規模ですが、それが良いのか悪いのかは分かりません。
会社をどんどん発展させることを望む方であればもっと展開していくと思いますが、私の場合はどちらかというと中身や初めに感じた問題を解決していくこと、地域課題・社会課題を解決していく方に力を入れたかったので、儲けるために会社をするという感じではありませんでした。時間をかけてやっています。
取材担当(石嵜)の感想
日本政策金融公庫に5回も申し込んだというお話は、非常に印象的でした。多くの方が諦めてしまうような状況でも挑戦し続ける粘り強さが、今の会社の継続に繋がっているのだと感じました。
また、介護業界の仕組みを理解するのに時間がかかり、資金的な苦労があったというリアルなお話は、起業や新しい分野に挑戦することの難しさと、事前の準備や理解の重要性を教えてくれました。どんな困難があっても諦めずに乗り越えてきた経験は、これから社会に出る私たちにとって大きな学びとなりました。

【株式会社フォレストファミリーの事業・業界について】
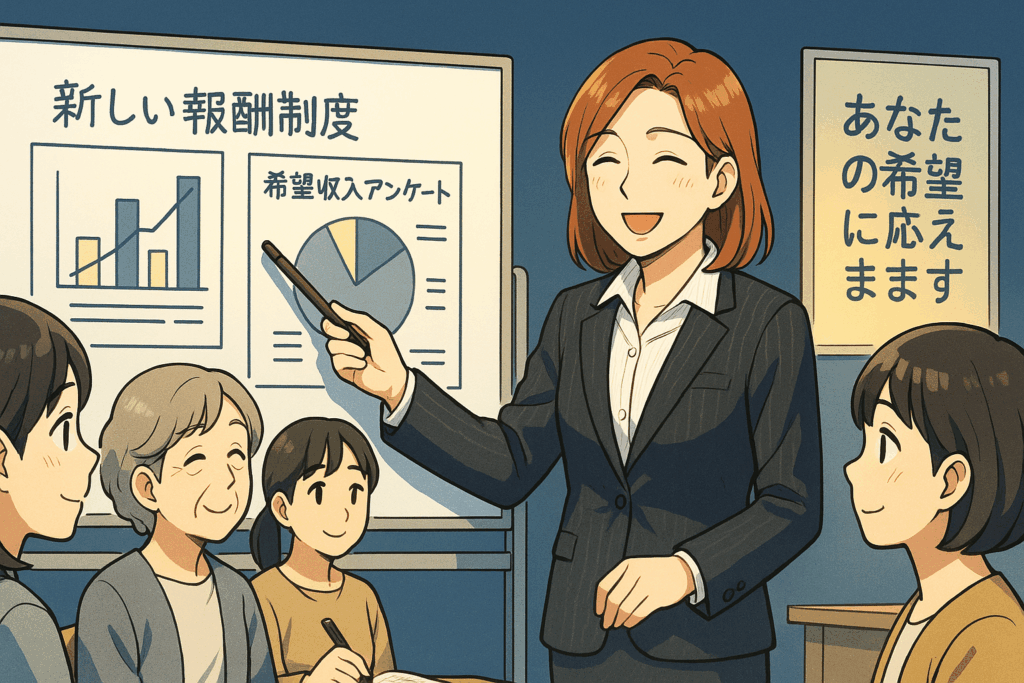
介護業界では人手不足が深刻な課題となっています。もう5年ほど前から足りなくなるということは言われていましたが、ここ1〜2年は特に強烈に体感しています。求人募集をかけてもなかなか応募がなく、来ても60代の方が多い状況で、厳しいと感じます。他の経営者の話を聞いても、人がいなくて事業所を閉じているところも増えています。
人がどんどん業界から離れていくのは残念な気持ちで、何とかしないといけないと思っていました。一時期は求人疲れをしてしまい、もう人がいないと言っていても仕方がないと考え、まずは今いる従業員に目を向け直すことにしました。
そこで、業務内容を全て見直し、パートさんは管理者の指示やルーティンワークのみを行うという働き方だったのを変えました。物価も高くなり生活費をもっと稼ぎたいという人もいるため、従業員全員にどれくらい稼ぎたいかというアンケートを取りました。手取りでいくら欲しいかなども全て聞き、会社の報酬体系を全て見直しました。
これくらいやったらこれくらいもらえるという明確なものに変えていきました。稼ぎたい人は稼げるシステムにしましたし、扶養内で働きたい人は扶養内で働けるようにしました。そして、やったことをきちんと評価してもらえるような内容に変えていきました。これにより、パートさんたちもプラスアルファの業務をやってくれるようになり、人手不足と言っていたところが、一人一人のパワーが上がったことで少しずつやれる人が増えてきました。
それでも圧倒的に数が足りない状況は変わりません。今は埼玉市のSDGs認証企業になっていることもあり、SDGs認証企業同士や埼玉市とも連携して、社会課題の解決に取り組んでいます。今、ケアマネジャーや介護ヘルパーが足りず、介護を受けられない「介護難民」が出てきています。
企業のSDGs活動として、彼らを支援できないか、そしてヘルパーさんやケアマネジャーさんの負担になっている部分を企業が担うことができたら、安定した介護保険制度の事業を続けることができるのではないかと考え、動き始めたところです。人がいないと言っているだけでなく、できることが何かなという感じで色々なことをやっています。
取材担当(石嵜)の感想
介護業界全体が抱える人手不足という大きな課題に対し、従業員の方々へのアンケートに基づいた報酬体系の見直しや、一人ひとりの能力向上を図るという社長の取り組みは、従業員を大切にする姿勢の表れだと感じました。
また、SDGsと結びつけて他企業や自治体と連携し、地域全体の課題解決を目指すという発想は、企業の社会的な役割を深く考えていらっしゃるからこそだと思います。介護難民問題やロボット導入のお話からは、この業界の現状と将来の可能性、そして人と人との繋がりが不可欠な部分があるということを改めて学びました。

【渡邉様が経営者として大切にしていること】
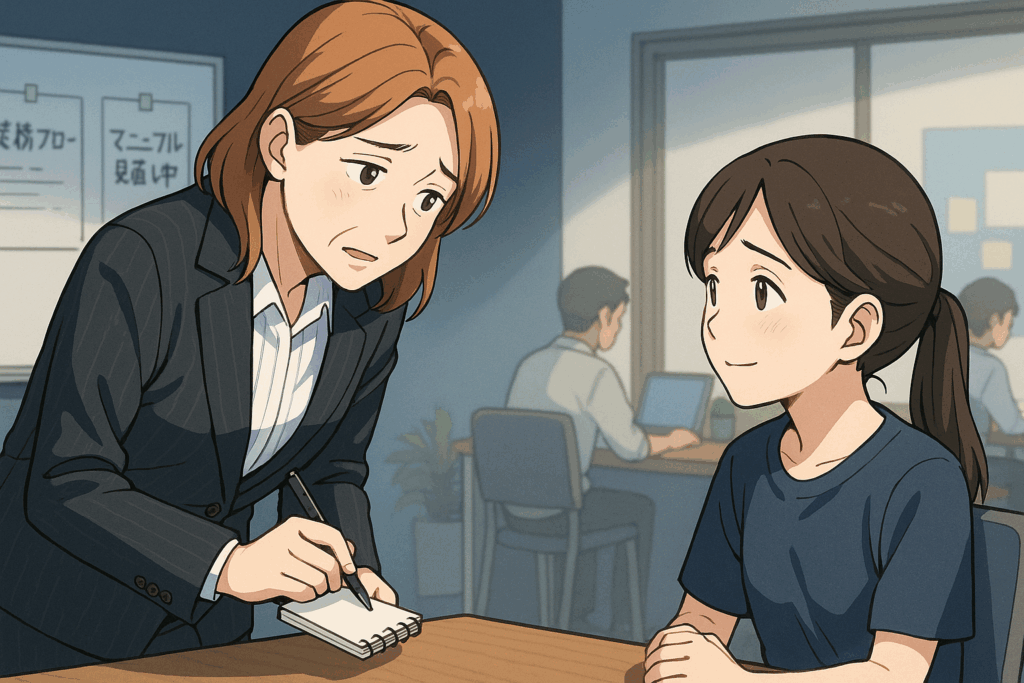
経営に正解はありませんので、私のやり方ということになりますが、大切にしているというよりは、私のやり方として、すごく細かいのかもしれません。他の経営者の方も言うと思いますが、職員の本当にちょっとした変化にも気づくようにしています。少し元気がないかな、という時に放っておかないようにしています。何かあった時は、すぐに本人に話を聞き、火種を小さいうちにトラブルを解消させるようにしています。
運営も経営も、多分細かいと思います。やっぱりリスクを小さいうちに潰しておきたいので、ちょっとした違和感にすぐ気がつくようにしていますし、気がつくようになりました。それがずっと引っかかってしまうので、あれやっぱりおかしいな、と思うと調べます。例えば、ある事業所に入った時に、なんとなく雰囲気が違うなと感じた時、調べてみると、最近従業員の間でうまくいっていないことがあった、ということが分かります。
そうすると、私はもうそこに入り込んで改善していきます。全員を集めて、正直にこういうことが起きているらしいね、と話します。そして、問題が起きているのは人が悪いのではなく、システムが悪い、私が最終的に悪いのだと思う、と伝えます。システムを一緒に見直そうと、業務フローやマニュアルを見直して改善します。
仕事のできるできないには必ず差がありますが、それは受け入れようと思います。均一にすることはできません。できる人を高く評価するのが私の仕事なので、評価や報酬などで評価します。
人を見るのではなく、自分の与えられた業務ができているかどうかを考えていこう、という話を、すぐ首を突っ込んで入っていくような感じです。なので、すごく細かいですし、かといって職員が見張られていると感じることはないと思いますが、反面、パートさんなどもすぐに私に相談してしまったりするところがあり、役職の人間からすると社長に相談しないで、ということになってしまうので、難しいな、距離感が難しいな、と感じることもあります。
従業員数は約30名です。30名を超えたあたりから、一人ひとりに必ず気づくというのはなかなか難しくなってきました。バランスも難しいですね。誰か一人だけに偏らないように、一人にやったことは全員にやらなければならないと思っていますし、公平にいなければならないと思っています。
取材担当(石嵜)の感想
従業員の方々の小さな変化にも気づき、リスクを早期に摘み取るという経営スタイルは、組織全体の健康を保つ上で非常に重要だと感じました。問題の原因を個人のせいにするのではなく、システムにあると考え、皆で改善に取り組むという姿勢は、従業員の方々も主体的に仕事に取り組める環境を作るのだと思います。
30名規模の組織で一人ひとりに目を配り、公平な評価を心がけるというのは並大抵のことではないと感じ、渡辺社長の細部へのこだわりと従業員への愛情を感じました。

【株式会社フォレストファミリーの今後の展望】
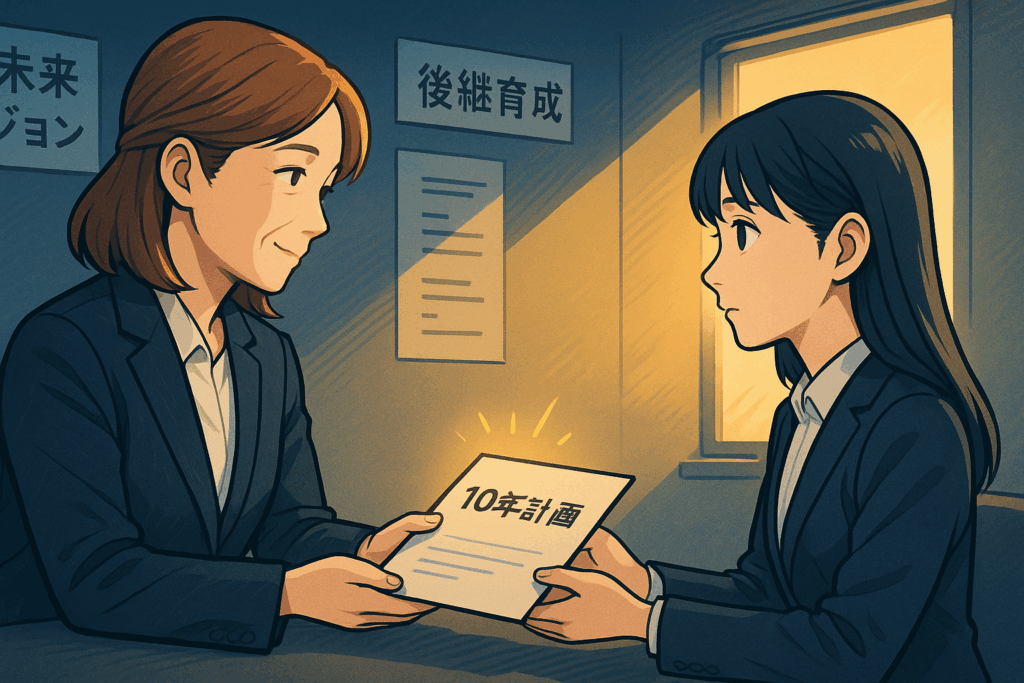
創業してから必死に走り続けてきて、15期目に入り、やっと会社が安定してきたと感じています。1年目の頃はパートさんより給料が低かった時期もありましたが、今は正社員よりは高くなりました。デイサービス一つだけだと、どれだけ頑張っても年商が3000万円くらいでしたが、私の体感では5000万円を超えてこないと余力は作れませんでした。介護事業は利益を考えると余裕がなく、備品が壊れても買えないというような状態でした。
3000万円だと月に300万円いかないくらいなので、車を買い替えるのも大変でした。5000万円を超えた頃から少し余裕が出てきて、1億円を超えてくると深呼吸できるというか、備品が壊れても「あ、買っていいよ」と言えるくらいになるという感じです。
安定してきた今、人手不足という課題があるため、新しい事業展開には少し尻込みしてしまっています。私自身は今40代なので、あと何年働くのだろうと考えた時、今後会社をどうしていこうかなということを考えるようになりました。
後継者を育てるにしても、すぐに引き継ぐわけではないので、5年、10年かけて引き継いでいくと考え、今から探して育てていかなければならないと思っています。65歳まであと17年なので、どのように会社を維持していくかということに今は目を向けています。
もちろん、その中でまた社会課題を感じて新しい事業展開をするとなればすると思いますが、今まで事業展開してきたのは、結局一つのデイサービスだと従業員にアッパーがある、管理者のその先の上位役職がない、目標を作ってあげられないという理由もあったからです。それで、デイサービスを2つ作り、居宅事業所、訪問看護、保育園と展開し、本部機能もできて役職もできてきたので、目標を作れる組織になってきたのかなと感じています。
その上で、この先会社をどうするかというと、私が65歳や70歳で働けなくなった時に会社が潰れてしまってもいけないので、今はどうやって会社を今後継続していくかということをよく考えるようになりました。事業承継ですね。少子化や人手不足と同様に、経営者不足も問題視されていると思います。
M&Aが増えていますが、大企業に買収してもらうのは簡単ですが、中小企業なりのサービスの質や細かいところに目が行くようなサービスができなくなるのが良いのかどうか、昔の介護サービスに戻ってしまうのではないかという懸念もあります。こういうものを残していきたいなと思っています。
取材担当(石嵜)の感想
会社の安定化の目安を具体的な年商で示してくださったことで、経営のリアルな側面を理解することができました。また、人手不足という課題が新たな事業展開への慎重さに繋がっているというお話は、現場の課題が経営判断に直結していることを感じさせられました。
そして、今後の事業承継や後継者育成、中小企業ならではのサービスの質を守りたいという思いは、会社の継続と、これまで築き上げてきたものを未来に繋げていきたいという強い意志を感じました。

【渡邉様から就活生へのメッセージ】
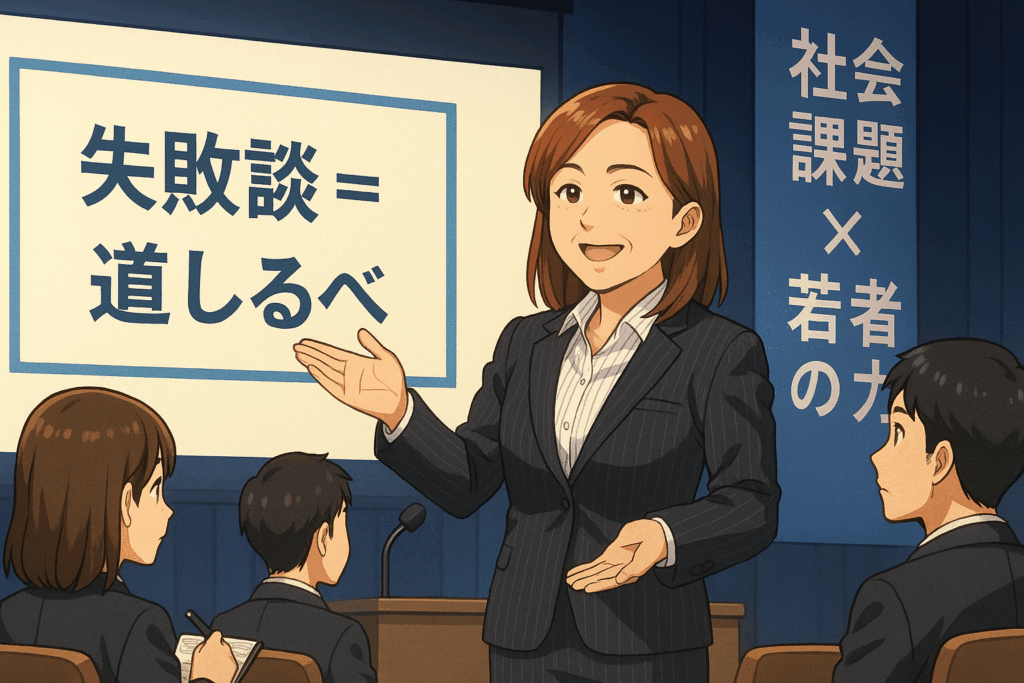
メディアに出るとしたら失敗談しか書かない、失敗なら山ほどあると言っています。しかし、それは後輩たちへの道しるべになる、勉強になると思います。創業セミナーの講師に行ったこともありますが、私は失敗談しか出てこないので、参加者のキラキラした目を裏切るわけにはいかないと思い、あまり生々しい話はできないと思ったりします。でも、起業したら失敗しないで挫折しないで欲しいと思ったりすると、本当はリアルな話もした方が良いのだろうとも思います。
初めの希望はどうやってもだんだん薄れていくものです。自分でこんな風になれるだろうという期待値は薄れていきます。初めは期待値や希望、夢がたくさんあって良いと思います。
起業したいと言っている人の中で、実際に創業する人もどれくらいいるでしょうか。セミナーに参加している人全員が創業するかというと、しないものです。やはり勢いも必要だと思いますし、準備ばかりしていても進まない部分もあります。
とはいえ、計画があまりできていないと失敗してしまいますし、バランスが大切だと思います。あまり慎重になりすぎて前に進めなくなってしまうより、やってみてからどんどんと改善していくのが普通だと思います。初めからうまくいくことなどなかなかないと思います。社会問題に関心を持ってくださるのは、本当にありがたいです。
今後は人だけで回すだけではダメなので、機械も使う必要があると思いますが、人がやらなければならないところもあります。そういった仕組みを若い人たちが学んで考えてくれると早い段階で色々なアイデアが出てくると思います。どんどん社会問題の解決に向けて考えていっていただきたいと思います。
取材担当者(石嵜)の感想
起業における失敗談を包み隠さず話してくださる姿勢に、誠実さと同時に強さを感じました。これから起業や新しいことに挑戦しようと考えている私たちにとって、成功だけでなく失敗から学ぶことの重要性を教えていただきました。
また、「勢いと準備のバランス」「やってみてからの改善」といった実践的なアドバイスは、漠然とした思いを行動に移す上で非常に参考になります。社会問題への関心の重要性についても触れていただき、私たち若い世代が社会の一員として何ができるのかを考えるきっかけとなりました。










