富山県高岡市に本社を構える竹中銅器は、400年以上の歴史を持つ伝統工芸「高岡銅器」の技術と精神を受け継ぎ、1927年の創業以来、ものづくりに励んでいます。日本最大級の銅像・胸像製作実績を誇り、伝統的な銅器製品に加え、時代に合わせた新たな製品開発にも積極的に取り組んでいます。今回は、4代目となる竹中社長に、創業の経緯から今後の展望まで、幅広くお話を伺いました。
<聞き手=石嵜渉(学生団体GOAT編集部)>
【竹中様のこれまでの経緯・背景】
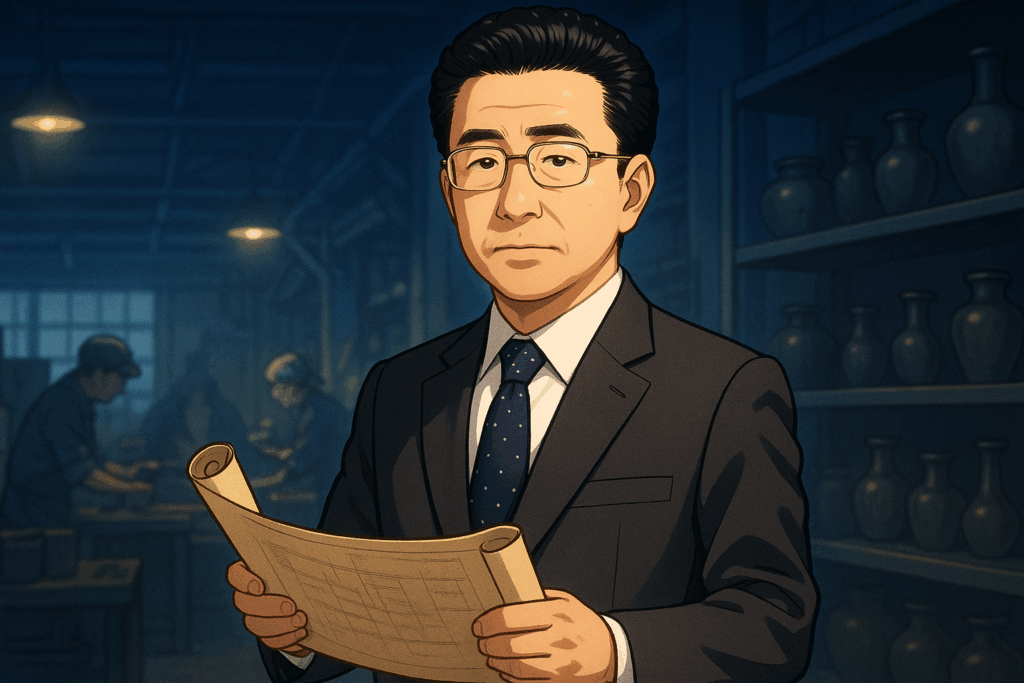
当社は、創業から98年になります。最初は、この地の伝統品である高岡銅器の製造販売からスタートしました。その後、様々な事業展開を行い、現在は別会社ではありますが、建材関係の会社もグループに抱え、グループ全体で約50億ほどの規模になっています。私自身は4代目の経営者となりますが、会社を継いだきっかけと背景には、いくつかの要因がありました。
私の父までの3代が築き上げてきたこの伝統工芸の会社でしたが、若い頃の私は、決められたレールの上を歩むことに反発も感じていました。しかし、結果的には実家の会社に入社することになりました。その後、40歳で社長に就任したのですが、その時の会社は実質的な債務超過の状態でした。
様々なことを考えましたが、自分以外に事業を継承する者がいなかったという点が一つ。そして、もし継承しなければ、先祖にも申し訳ないという思いがありました。さらに、取引先にも迷惑をかけることになり、従業員とその家族も路頭に迷う可能性があると考え、最終的に事業承継を決意しました。
取材担当者(丸山)の感想
伝統ある家業を継ぐことへの葛藤や、社長就任時の厳しい状況を知り、竹中社長の責任感の強さに感銘を受けました。債務超過という危機的な状況の中、先代からの歴史、取引先、従業員の生活を守るという強い意志が、事業継承の原動力になったのだと感じました。

【竹中様が経営において大切にしていること】
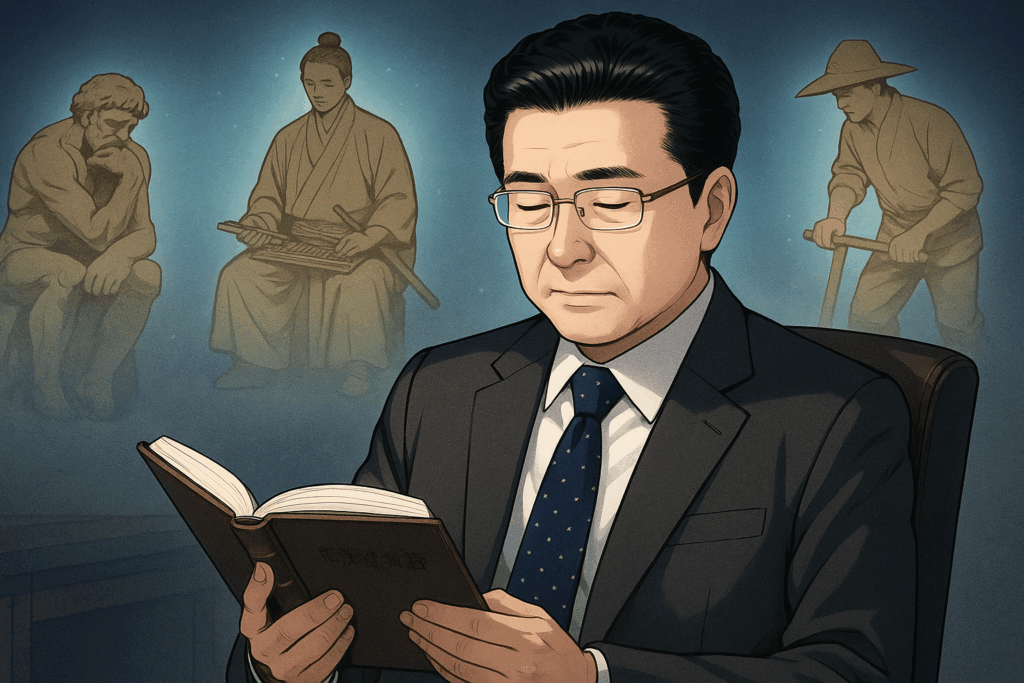
経営者として最も大切にしていることは、嘘をつかないということです。社長就任時に、社員の前で嘘は絶対につかないと誓いました。その背景には、先代社長の代で信用を失墜するような出来事があり、信用を取り戻すことに非常に苦労した経験があるからです。江戸時代の書物にある、藩の改革に取り組んだ人物の逸話にも感銘を受けました。
その人物は、自身が嘘をつかないと宣言し、嘘をつく可能性のある者を側から遠ざけ、組織全体の信頼を取り戻したのです。信頼関係は、取引先との関係においても最も重要なことだと考えています。
また、福沢諭吉氏の言葉に、「思想の深遠なるは哲学者のごとく、心術の高尚正直なるは元禄武士の如くにして、これに加うるに、少俗吏の才能をもってし、これに加うるに土百姓の身体をもってして、はじめて実業社会の大人たるべし。」というものがあります。
これは、哲学者のような思想、武士のような実直さ、商人のような狡猾さ、そして百姓のような忍耐強さの4つが大切だという意味です。私は、武士の商法というものもあると思いますが、武士のような実直さに加え、商売においては詳細な計画性や、時にはずる賢さ、そして忍耐力も必要だと考えています。
しかし、それだけでは十分ではなく、哲学者のような思想や武士のような実直さがあってこそ、それらの要素が真に活きてくると考えています。会社経営においても、利益を上げ続けなければ存続できませんが、利益だけが目的ではありません。
それは人間も同じで、食べることは生きるために必要ですが、食べること自体が目的ではないのと同じです。いかに生きるかということが大切なのと同じように、会社も社会にどのように貢献していくのかという目的が重要だと考えています。利益は社会貢献のバロメーターであり、儲からない仕事は価値のない仕事とも言えるでしょう。目的を明確に持つことも重要で、ピラミッドの例え話のように、同じ仕事でも目的意識によってやりがいや結果が大きく変わってきます。
当社の企業理念は、「お客様をワクワクさせることによって、地域の社会に貢献する」ということです。ワクワクという部分が非常に大切で、お客様の期待を超えるサービスを提供してこそ、真の喜びと満足を得られると考えています。
取材担当(石嵜)の感想
嘘をつかないという強い信念は、過去の苦い経験に基づいていることを知り、その言葉の重みを感じました。
また、福沢諭吉氏の言葉を通して、経営者に求められる多様な資質について深く考えさせられました。利益だけでなく、社会貢献やお客様の喜びを追求する竹中社長の経営哲学は、非常に共感できるものでした。

【竹中様から学生へのメッセージ】
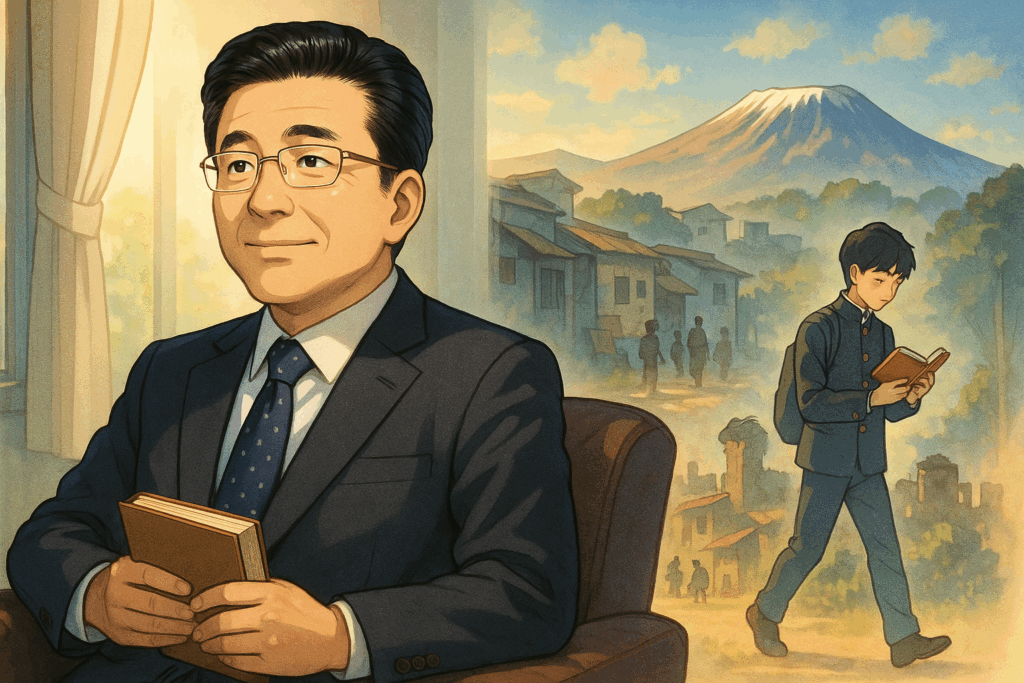
若い人たちの特権は、お金はないけれど時間があるということです。社会人になると、自由な時間はなかなか持てなくなってしまいますので、自由な時間を活用して、経験値を高めてほしいと思います。私自身、若い頃から読書が好きで、1日に1冊を目標に様々なジャンルの本を読みました。それが様々な意味で自分の蓄積となり、人生を豊かにしてくれていると感じています。
また、学生時代には、貧乏旅行でも良いので、旅行を経験することも良いのではないでしょうか。私自身、学生時代にフィリピンへ行った際、東アジア最大の貧民街と言われる場所に滞在したり、普段できないような経験をしました。社会人になってからは、なかなかまとまった時間が取れませんが、60歳を過ぎてから一人でキリマンジャロに登頂するなど、旅の経験は今も私の人生を豊かにしてくれています。
嫌なことでも、無駄だと分かっていることでも、とりあえずやってみるというのも良いかもしれません。それが20年後、30年後に役立つ可能性もあるからです。
取材担当(石嵜)の感想
お金がない学生にとって、時間は無限の可能性を秘めているという言葉は、非常に勇気づけられるメッセージだと感じました。
読書や旅行といった経験を通じて、視野を広げ、人間性を豊かにすることの大切さを改めて認識しました。また、若いうちは様々なことに挑戦し、失敗を恐れずに経験を積むことの重要性を学びました。

【株式会社竹中銅器の事業・業界について】
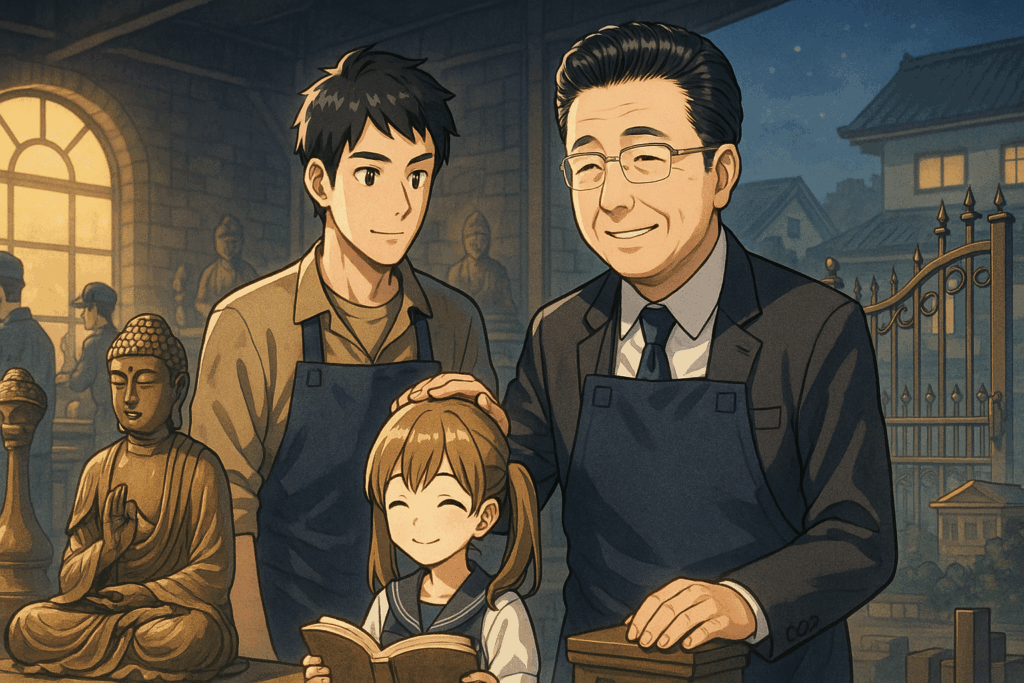
当社の主な事業は、創業以来の高岡銅器の製造販売です。身近なものでは、銅像や記念品、最近ではアニメキャラクターの銅像なども手掛けています。しかし、高岡銅器の業界全体としては、最盛期には375億円ほどあった生産額が、現在は100億円程度まで減少しています。これは高岡銅器に限らず、日本の伝統工芸品全体に言えることで、ライフスタイルの変化や洋風化などが背景にあります。
このような状況の中で、当社は創業100年近くの歴史がありますが、将来に向けて200年企業を目指し、銅器の伝統を守りながらも、より良いものを後世に残していきたいと考えています。そのためには、規模だけを追い求めるのではなく、質を重視していくことが重要です。
また、伝統工芸品だけにとらわれず、長年培ってきた鋳物の技術を生かし、新たな分野にも積極的に挑戦しています。例えば、エクステリア商品(門扉やフェンスなど)の製造販売も行っています。この分野の売上は、現在では銅器の売上を上回るほどになっています。これは、伝統的な技術を核としながらも、時代のニーズに合わせて変化していくことの重要性を示していると言えるでしょう。
現在、多くの業界で人手不足が深刻化していますが、中小企業である当社も例外ではありません。大手企業に比べて報酬面で劣る部分もありますが、一方で、大きな組織に比べて、自分の意見やアイデアを実現しやすいというメリットもあります。
今後は、少人数でも効率的に仕事を進められるような体制を整えていくとともに、利益率の向上を図っていく必要があります。採用に力を入れ、経験豊富で意欲のある人材を積極的に採用していきたいと考えています。会社として長く勤めてもらうためには、社員が会社の理念や目標に共感し、やりがいを持って働ける環境づくりが不可欠だと考えています。
取材担当(石嵜)の感想
伝統工芸という歴史ある分野でありながら、現状に甘んじることなく、積極的に新しい素材や市場に挑戦する竹中銅器の姿勢に感銘を受けました。伝統を守りながらも革新を続けることの重要性を学びました。

【株式会社竹中銅器の今後の展望】
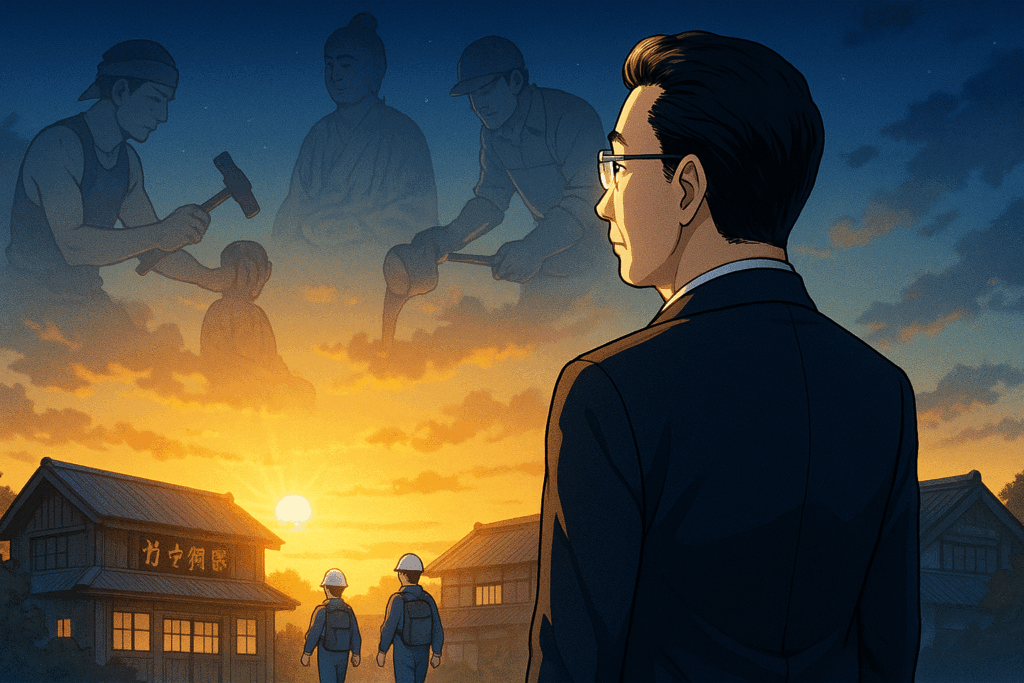
今後の展望としては、まず創業200年を目指し、企業として持続的に成長していくことです。同時に、高岡銅器という伝統工芸の技術と文化を後世にしっかりと残していくことも重要な使命だと考えています。そのためには、単に規模を拡大するのではなく、より質の高い、後世に残すべきものづくりを追求していきたいと考えています。
そのためには、伝統を守るだけでなく、常に新しいことへの挑戦を続けていく必要があります。当社のエクステリア事業のように、これまで培ってきた技術を応用し、新たな素材や市場を開拓していくことが、これからの100年を生き残るための重要な戦略だと考えています。
伝統とは革新の足跡であるという言葉があるように、過去の革新が今日の伝統を築き上げてきました。これからも、常に新しいことに挑戦し続けることで、未来の伝統を創造していきたいと考えています。
取材担当(石嵜)の感想
200年企業という壮大な目標を掲げながらも、足元をしっかりと見つめ、伝統と革新の両輪で未来を切り拓こうとする竹中社長の力強い vision に感銘を受けました。伝統を守りながらも、時代の変化に対応し、新たな価値を創造していくことの重要性を改めて認識しました。










