香川県さぬき市に拠点を置く株式会社安岐水産は、日本の豊かな海から届けられる水産物を加工し、食卓へ届けている企業です。創業60周年を迎え、日本の魚食文化を未来へ繋ぐため、海の環境保護や魚食文化の推進にも積極的に取り組んでいます。
水産加工事業に加え、社長自身が外国人材の受け入れや派遣を行う組合事業も展開するなど、地方創生と外国人との共生という社会課題にも向き合っています。今回は、代表取締役社長である安岐社長に、これまでの歩みや事業にかける想い、そして未来への展望について伺いました。今回は、魚食文化の継承や地域社会との共生に向けた多角的な取り組みについて、株式会社安岐水産 代表取締役社長・安岐様にお話をお伺いしました。
<聞き手=石嵜渉(学生団体GOAT編集部)>
【安岐様の今までの経緯・背景】
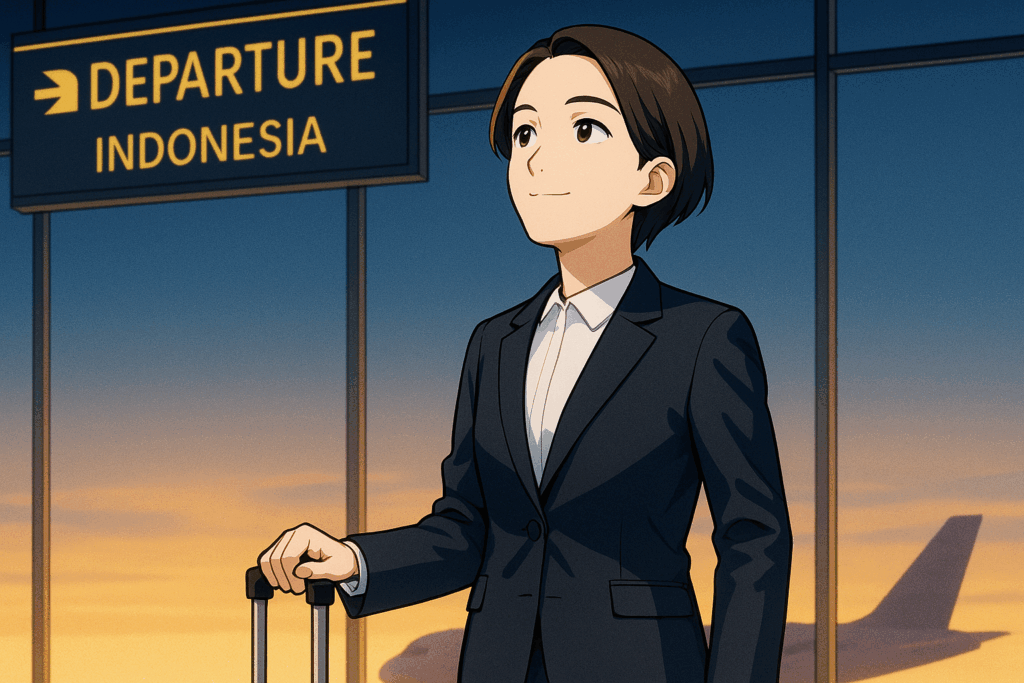
この会社は、私の父が創業しました。私は大学卒業後、ホテルのフロントで約6年半勤務した後、実家のある香川に戻りました。
自分で何か事業を始めたいという思いは、高校生の頃から漠然と持っていました。海外との仕事や、自分で起業することにも関心がありました。父が海外で水産原料開発を手掛けていたこともあり、その影響もあったかもしれません。
実家に戻って最初に始めたのは、父の会社が作っていたイカそうめんの下請け加工でした。そんな中、約30年前に父がインドネシアでチリメン(しらす干し)開発をしていた頃の取引先で、インドネシアで日本人向けスーパーを経営している方から連絡がありました。
その方が食品の輸出元を探しているという話を聞き、経験はありませんでしたが、その場で「ぜひやらせてほしい」と申し出て、貿易の仕事を始めたのが輸出事業の始まりです。
その後、自分の会社でインドネシアの日本人向けスーパーに食品を輸出する事業を長く行っていました。約15年間順調に進めていましたが、インドネシアの法律が変わり、多数の品目を一度に輸出することが困難になったため、事業の継続が難しくなりました。
そこで、取引先と相談し、日本の惣菜を現地で作る事業を検討し、惣菜の勉強を始めました。インドネシアで事業展開するつもりでしたが、父の会社が水産加工、私の会社が惣菜加工として、日本で協力して加工事業を行うことになりました。これが、私の仕事が父の水産事業に近いものになっていった転換期です。
インドネシアとの関わりを続けたいという強い思いから、水産加工と惣菜加工の工場に技能実習生を受け入れることを決めました。当初は他の組合を通じて受け入れていましたが、当時の「労働力」として見られるような扱いに違和感を覚えました。
インドネシアに長年思い入れがあり、自分の子供のような年齢の若者を預かる立場として、その扱いに納得できなかったのです。そこで、自ら組合を設立し、技能実習生の派遣事業を始めました。
約6年前からは、父の会社である安岐水産の事業承継も行い、現在は両社の社長を務めています。製造部門は安岐水産に一本化し、水産加工と組合事業(人材派遣)を中心に事業を展開しています。
取材担当者(石嵜)の感想
安岐社長の経歴からは、早い段階から海外への関心を持ち、自ら事業を始めようという強い意志を感じました。サラリーマン経験を経て、一度決めた道を再び自らの手で切り開く行動力には感銘を受けます。
変化や困難に直面しても、それを乗り越えるために新たな一歩を踏み出す姿勢は、私たち学生にとって大変な学びになります。また、漠然とでもなりたい自分を思い描き続けることで、それを実現するためのチャンスが巡ってくるというお話は、将来について考える上で重要な示唆を与えてくれました。

【株式会社安岐水産の事業・業界について】
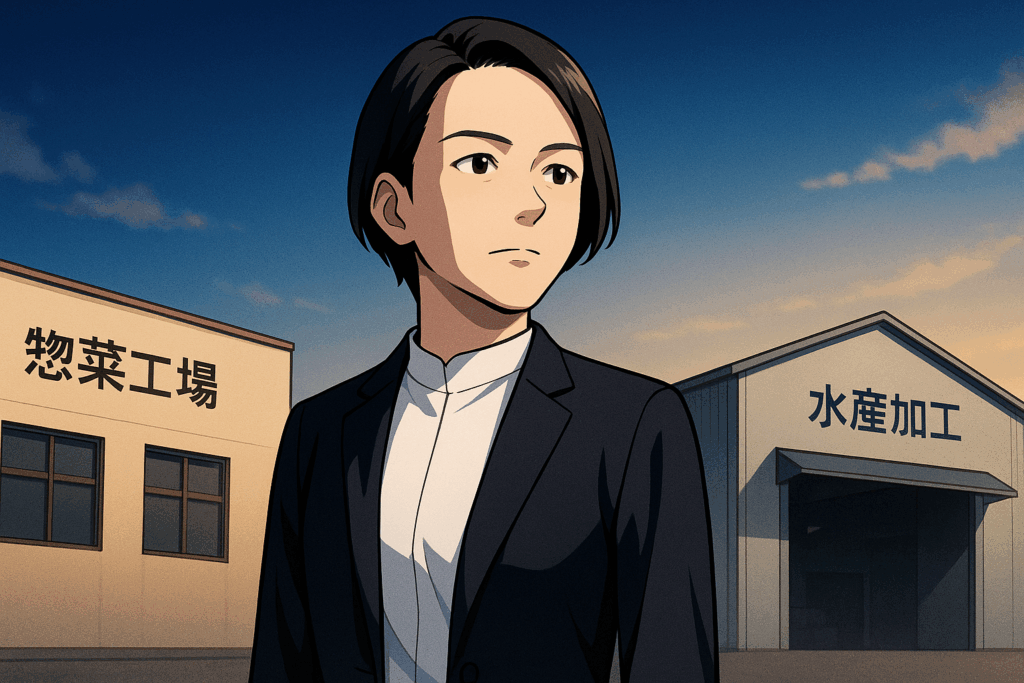
現在の事業は、父から引き継いだ安岐水産での水産加工事業と、自ら設立した組合での外国人材派遣事業が中心です。水産加工では、生の水産加工と惣菜加工の製造を安岐水産に一本化して行っています。
組合では、技能実習生や特定技能生を様々な企業に派遣しています。派遣先は水産加工だけでなく、農業や建築、介護など多岐にわたります。現在、約350名の外国人材を派遣しています。
現在、日本全体、特に地方では深刻な人手不足が課題となっています。私が会社と組合を置いている香川県さぬき市も、かつて遠洋漁業の基地として栄えましたが、今は高齢化が進み、漁師さんも数人しかいないような状況です。総務省から過疎地域の指定も受けています。このような状況下で、働き手がいないというのはまさに地方の中小企業が直面している現実です。
私は、この人手不足という課題に対して、外国人材の受け入れが有効な解決策の一つであると考えています。ただし、単に労働力を補うだけでなく、優秀な外国人材を会社のコアな人材として迎え入れ、共に事業を展開していくことが重要だと感じています。
地方の中小企業にとって、大卒の優秀な日本人人材を確保することは容易ではありません。しかし、成長著しいアジア諸国などから優秀な人材を受け入れることで、将来の選択肢を増やすことができると考えています。
例えば、受け入れた外国人材を通じて、自社の商品を海外で販売したり、海外企業との技術提携や資本提携を進めたりすることも可能になります。実際に、私が受け入れた実習生の女性がインドネシアで日本語学校の代表を務めてくれています。
また、帰国した男性実習生がインドネシアの大学の先生になり、その大学と私たちの組合でMOUを結び、実習生の受け入れにつながった事例もあります。このように、外国人材は海外との繋がりや新たな展開の起点となり得るのです。
日本は99.5%以上が中小企業で成り立っています。私たち中小企業一つ一つができることは小さな繋がりかもしれませんが、その繋がりが重なることで、会社の存続の力になりますし、地方全体の力、さらには日本の力になる可能性があると考えています。外国人材の受け入れは、単なる働き手の確保にとどまらず、企業の、そして日本の未来を拓くための重要な選択肢となり得るのです。
取材担当(石嵜)の感想
人手不足という社会課題に対して、外国人材の受け入れを単なる労働力の確保ではなく、企業の未来を切り拓くための重要な戦略と捉えている点が印象的でした。特に、地方の中小企業が外国人材を海外展開の起点や新たなビジネスチャンスと捉える視点は、私たち学生にはない斬新な発想で、大変勉強になります。
地方にポテンシャルを見出し、グローカルという視点で海外と繋がっていくお話にも共感しました。

【安岐様から学生へのメッセージ】
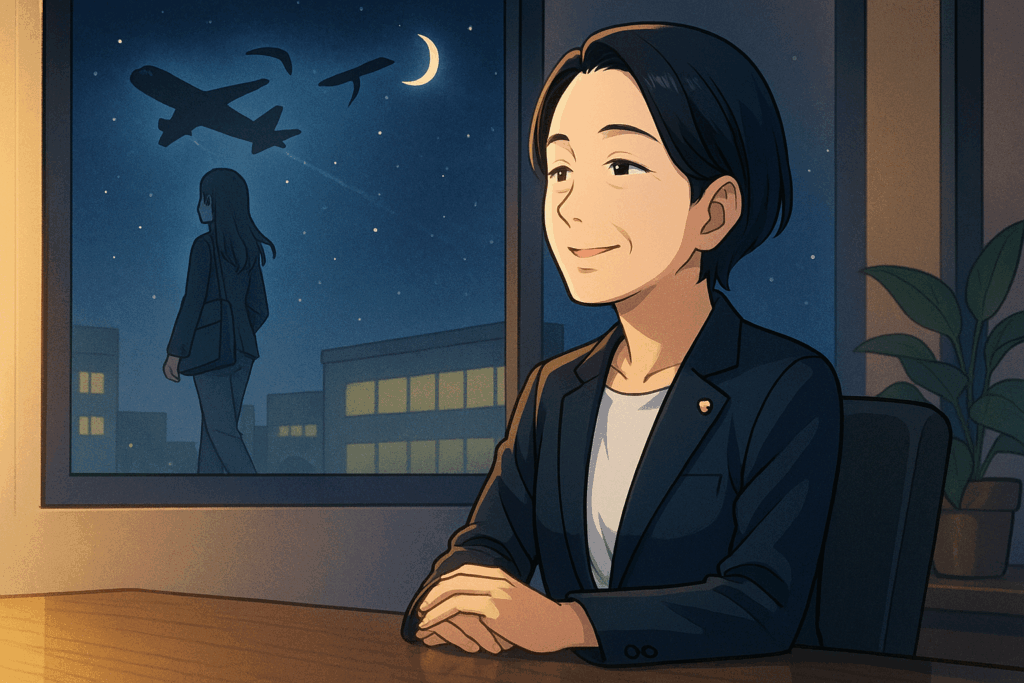
学生の皆さんへのメッセージとしては、とにかく色々なことにチャレンジしてみてほしいと思います。学生時代は、失敗してもやり直しがきく時間がいっぱいあります。何か「やりたい」と思うことがあれば、積極的に挑戦してみてください。
自分のことがなかなかわからない、という人は多いのではないでしょうか。自分が何が得意で、何が好きで、何が欲しいのか。これに対する簡単な答えはありません。自分自身を知ることは、時間がかかる道のりだと感じています。だからこそ、学生のうちに自分を知るために時間を費やすことは非常に大切だと思います。色々な経験を通じて、自分と向き合う時間を持ってください。
そして、もう一つ大切なのは、「なりたい姿」や「欲しいもの」を思い描くことです。明確な根拠がなくてもいいのです。ぼんやりとでも、こうなりたい、これが欲しい、という姿を心の中に描いてみてください。そうやって未来に「ブーメラン」のように投げかけておくイメージです。
そうすると、不思議なことに、それにフィットするような人に出会ったり、出来事が現れたりすることがあります。私自身も、海外との仕事がしたい、自分で何かやりたい、と漠然と思っていましたが、その思いがあったからこそ、輸出事業の話が来たときに飛びつくことができたのだと思います。
映像で具体的に思い浮かべられることは実現しやすい、という感覚があります。逆に、イメージできないことは実現しにくいかもしれません。ですから、頭の中で自分の未来を具体的に描いてみることが、実現への第一歩になるのではないでしょうか。
取材担当(石嵜)の感想
学生時代に積極的にチャレンジすることの重要性、そして自分自身を知る努力の大切さというメッセージは、まさに今の私たちに必要な言葉だと感じました。
特に、「なりたい姿を思い描くこと」がチャンスを引き寄せるというお話は、これまでの自分にはなかった視点です。未来を具体的に想像することの重要性を改めて認識し、早速実践してみたいと感じました。

【株式会社安岐水産の今後の展望】
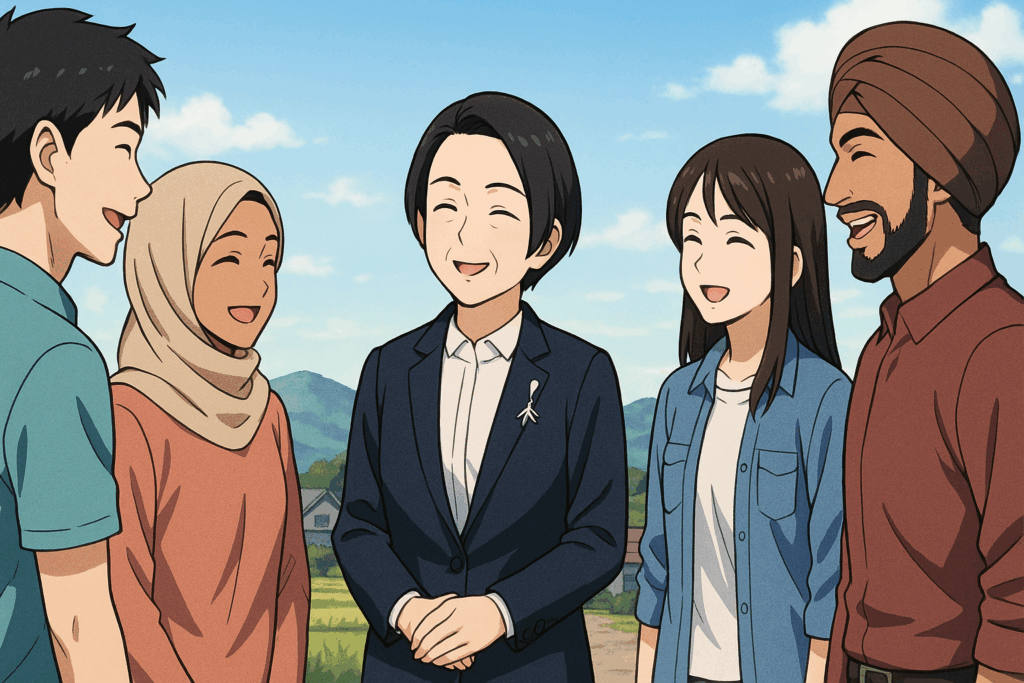
私にとって、インドネシアと日本を繋ぐことは、これまでの経験から自分の人生のミッションのようになっています。それは、インドネシアで出会った素晴らしい方とのご縁が始まりでした。
今後は、安岐水産の事業(地方創生)と、これまでのインドネシアとの繋がりで培ってきた外国人材の受け入れ・活用事業を掛け合わせることで、地方創生と外国人との共生という社会課題に対して、何かできることがあるのではないかと考えています。この課題は、一企業だけで解決できるものではなく、人との協業やネットワークを通じて進めていく必要があると感じています。これまでの経験で培った様々な繋がりを活かしながら、具体的な形にしていけたらと思っています。
経営者として、何が原動力になっているかというと、「誰かと何かができていること」に楽しさを感じます。特に、社員の方々と関わる中で、その人の成長を一緒に喜べたり、人と人との繋がりを感じられる瞬間が、仕事をする上での一番のご褒美だと感じています。
例えば、過去に受け入れた実習生たちが、帰国後もそれぞれの場所で活躍し、今も繋がっていることが私の大きな喜びです。インドネシアでの日本語学校の運営や、現地の水産大学校との連携など、実習生とのご縁から生まれた新しい動きもあります。
社員とは、人生の非常に長い時間を共に過ごす家族のような存在です。彼らと共に、いかに毎日を工夫して楽しく過ごせるか、そういった人との関わりを深めることに大きな興味があり、それが経営を続ける上でのモチベーションになっています。
これからも、人との繋がりを大切にしながら、社会課題を解決していく取り組みを続けていきたいと考えています。
取材担当(石嵜)の感想
地方創生と外国人との共生という大きな社会課題に対して、自身のこれまでの事業経験や人との繋がりを掛け合わせて取り組もうとされる姿勢に、社長の人生をかけたミッションという強い意志を感じました。
単なるビジネスだけでなく、そこで生まれる人との「ご縁」や「繋がり」を一番の喜びとされているお話は、まさに人間味溢れる経営者だと感じました。困難も楽しみに変えていく社長なら、きっとこの大きな挑戦も実現されるだろうと感じ、私たちも応援したい気持ちになりました。










