シンエーフーヅ株式会社様は、神戸市に本社を置く1969年創業の老舗の飲食企業です。懐石料理、中国料理、パスタ、カフェ、ケータリングなど、多岐にわたるジャンルの店舗を兵庫県を中心に展開し、お客様に「食」を通じた豊かな体験を提供しています。地域のランドマークとなる施設内でのレストラン運営や、高速道路のサービスエリアでの事業も手がけるなど、幅広い事業を展開しています。長年にわたり培ってきた信頼と実績を基盤に、常に時代の変化に対応しながら、お客様に愛される企業として成長を続けています。今回は、地域に根ざした多角展開の歩みと、これから描くビジョンについて、代表取締役社長の宮内 賢二様にじっくりお話を伺いました。
<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>
【宮内様の社長就任までの道のり】
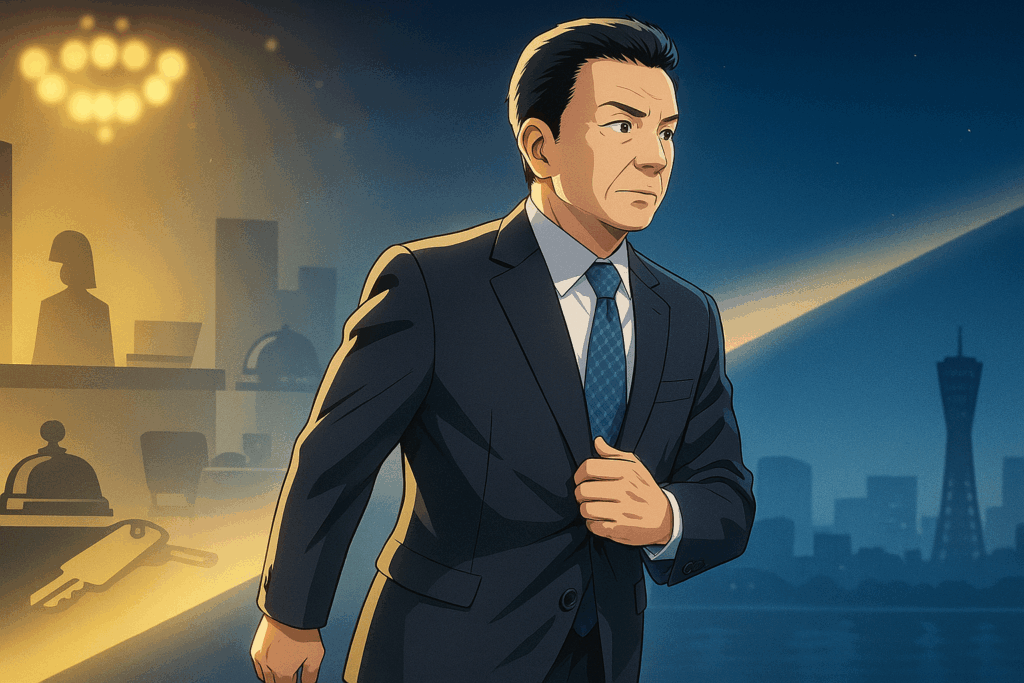
私が飲食業界に足を踏み入れたのは、1981年神戸ポートアイランド博覧会が開催された年でした。当時、博覧会に合わせて神戸に大規模なホテルが建設され、私はそのホテルに就職しました。
ホテルでは宿泊業務をメインに担当しましたが、その他にも飲食、宴会、セールスなど、ホテルの様々な部門で経験を積むことができました。実に32年もの間ホテルマンとして働き、お客様をもてなすことの奥深さを学びました。
現在のシンエーフーヅは、実は私が勤務していたホテルの関係会社にあたります。ホテルでの経験を経て、2013年にシンエーフーヅでの勤務を打診され、出向期間を経て2017年に社長に就任しました. 正直なところ、私はホテルにいた頃、飲食業は「儲けることが難しいビジネス」と感じていましたが、この業界で挑戦することを選び、今日まで努力を重ねてきました。
取材担当(高橋)の感想
宮内社長が、ホテルでの長年の経験を経て、系列会社の飲食事業の社長に就任されたという経緯に大変驚きました. この経験は、私たち学生が将来のキャリアを考える上で、自身の経験や先入観にとらわれず、新たな挑戦に飛び込むことの重要性を教えてくれます。

【経営における変革と業界の課題】
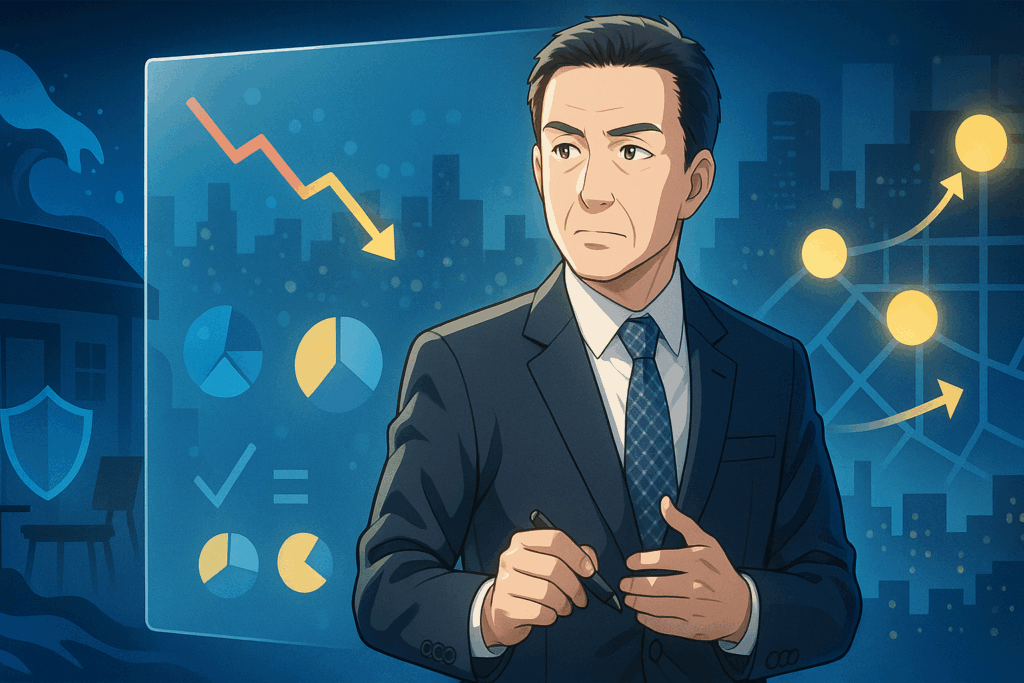
社長就任後、私が真っ先に強化したのは「数字を追う」という意識でした。特に飲食業においては、FLコスト(食材費と人件費の合計)を売上の65%以内に抑えることが必須です。 この比率が70%を超えると、経営が立ち行かなくなるからです. 大手チェーンのように均一な店舗展開とは異なり、私たちのように多種多様な店舗を持つ企業では、一つ一つの店舗の採算性を個別に厳しく管理していく必要があります。「儲かる時に儲ければいい」という感覚では経営は成り立ちません。常に数字にこだわり、土台を強化することが、会社の成長には不可欠だと考え、それを強化してきました。
新型コロナウイルスの影響は、飲食業界全体にとって非常に厳しいものでした。売上が立たなければ、人件費や食材費を賄うことができないため、多くの企業が苦境に陥りました. 幸い、当社は先輩の方々が残してくれた資産があったため、無借金でこの危機を乗り越え、赤字も1年間に抑えることができました。コロナ禍後のリバウンド需要もあり、2023年度、2024年度はこの20年間の中でも最高の営業利益を残すことができました。
しかし、目下の最大の問題は人口減少です。日本人の「胃袋の数」が減り続ける中、特に地方都市ではそのスピードが加速しています。闇雲に店舗を増やすのではなく、人が集まる場所でビジネスを展開する戦略が不可欠です。例えば、大型ショッピングセンターができ、店舗が増えても消費者人口が増えなければ競争が激化し、経営は苦しくなります。そのため、私たちは人が常に集まる場所を見極め、そこに出店する戦略を採っています。
取材担当(高橋)の感想
飲食業界がコロナ禍で特に苦労したことは理解していましたが、シンエーフーヅ様が赤字を1年に抑え、さらに過去最高の利益を出したという事実に衝撃を受けました。これはまさに、徹底した数字管理と、変化に即応する経営戦略の賜物だと感じました. 人口減少という日本全体の大きな課題に対し、「胃袋の数」という視点から飲食業界の未来を語られている点は、非常に具体的で、私たち学生が社会課題とビジネスを結びつけて考える上で大きな学びとなります。

【人材確保と働き方の改革】
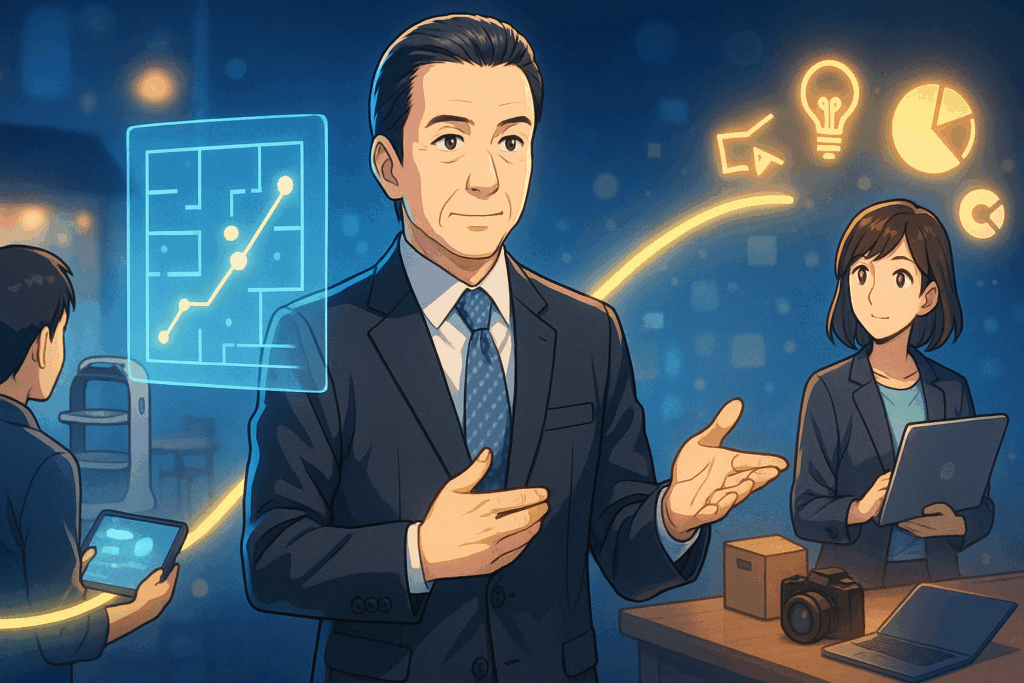
若手人材の確保は、飲食業界全体の課題であり、私たちも例外ではありません. 学生の皆さんはアルバイト経験から、飲食業を「皿洗い」や「きつい仕事」「給与が低い」「休みが少ない」といったイメージで捉えがちです。お客様からのクレーム対応や上司からの指導など、大変な側面ばかりがクローズアップされ、将来の仕事として選択肢に入りにくいと感じているのは理解できます。
しかし、飲食業の仕事はそれだけではありません。私たちは、新卒採用においては、学生の皆さんが持つパソコンスキルやノウハウを活かせる、マーケティング、商品開発、広報といった多様な業務があることを伝えています。特にDX(デジタルトランスフォーメーション)を進め、人が行っていた作業を機械に任せることで、業務効率を高め、より創造的な仕事に時間を使えるようにしています。例えば、お客様への配膳ロボットを最大限に活用できるよう、ロボットの動線を優先した店舗設計を行うなど、先進的な取り組みも行っています。
入社後数年間は現場研修があるかもしれませんが、その後は必ず経験を活かした創造的な仕事に就いてもらいたいと考えています。このようなアプローチを通じて、飲食業の新たな魅力を発信しています。現状では、希望する新卒採用人数(10人程度)に対して、実際には5人程度に留まっているのが現状ですが、今後も継続して取り組んでいきます。
取材担当者(高橋)の感想
私たちZ世代が飲食業に対して抱くイメージは、アルバイト経験からくるものが大きいという宮内社長の指摘は非常に納得できました。しかし、社員として働く上でクリエイティブな仕事やマーケティングといった専門的な業務に携われるというお話は、飲食業の新たな可能性を示してくれました。
これはまさに、私たち学生が求める「やりがい」や「成長実感」につながる部分であり、今後のキャリア選択において、業界の固定観念にとらわれずに深く企業研究することの重要性を再認識させてくれました.

【未来への挑戦:既存顧客と人に焦点を当てる】
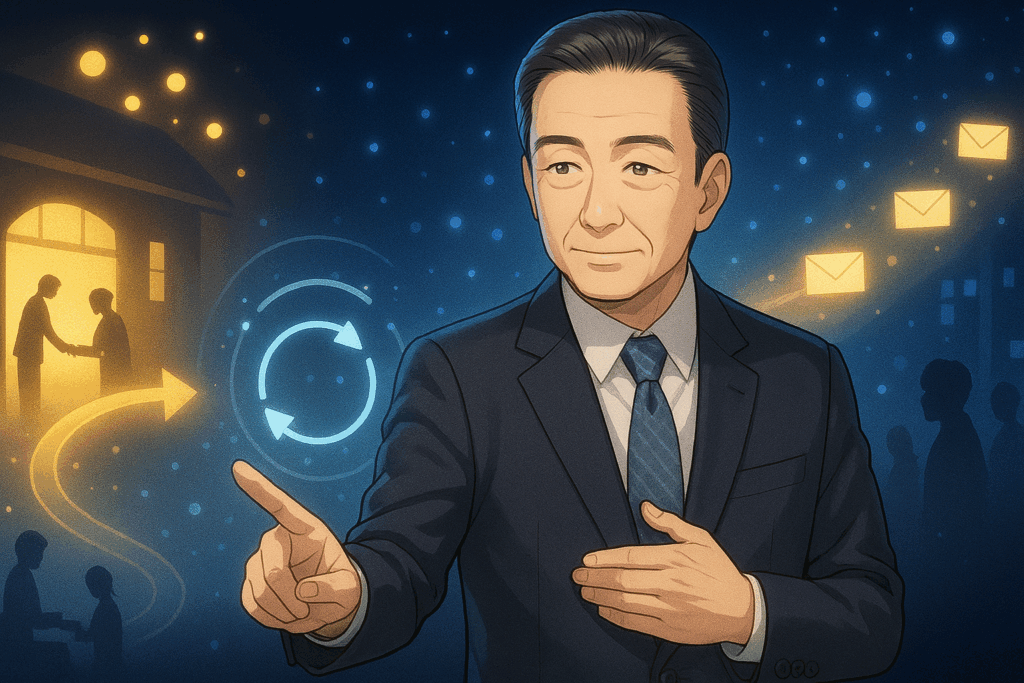
今後の経営において、私たちは「既存のお客様を大切にする」ことを最重要課題と捉えています。会社としての業績と数字を出すことは当然の責任ですが、闇雲に新しい店を出すことには慎重です。人口が減少する中で、闇雲に新規顧客を追い求めるのではなく、既にいるお客様に何度も足を運んでいただくことが、持続的な成長には不可欠です。
私たちは、いわゆる「2対8の法則」(売上の8割は上位2割のお客様によってもたらされる)を意識しています。この「宝物のようなお客様」をいかに守り、さらに育成していくかが鍵となります。新しいお客様を獲得するための情報発信も重要ですが、そこから繰り返し来店していただく「リピート」の仕組みをいかに構築するかが、今後の私たちの成長を支える柱となります。
来店されたお客様をお名前でお迎えし、「いつもご利用ありがとうございます」と感謝を伝えるような、きめ細やかなサービスは、お客様を「宝物のようなお客様」に変える上で非常に重要です。これはAIや機械では代替できない、人にしかできない「おもてなし」の真髄であり、サービス業である私たちの強みだと考えています。また、毎月2万人以上のお客様にメールで情報配信を行うなど、直接的なコミュニケーションも重視しています。全ての事業においてPDCAサイクルを徹底的に回し、計画を立て、実行し、結果を検証し、改善というプロセスを厳しく追求して次につなげることで、未来の飲食業界を切り拓いていきたいと考えています。
取材担当者(高橋)の感想
「宝物のようなお客様」という言葉に、宮内社長の経営哲学が凝縮されていると感じました。人口減少という逆境の中で、新規開拓以上に既存顧客のリピートを重視し、一人ひとりのお客様との深い関係性を築こうとする姿勢は、顧客体験を追求するサービス業の本質を捉えていると思います。特に、「人にしかできないおもてなし」の重要性を強調されていた点は、デジタル化が進む現代においても、人間らしい温かいサービスが持つ価値を教えてくれるものでした。厳格なPDCAサイクルを回し続けることで、常に変化に対応し、持続可能な企業を目指す宮内社長のビジョンは、私たち学生にとって大きな刺激となります。










