インプルーブ株式会社は、2008年に現代表の尾張社長が29歳で起業しました。大阪府大阪市に本社を置き、東京・神戸・博多・奈良・埼玉・広島・京都・りんくうなど全国9拠点で展開する人材派遣・人材紹介会社です。創業から12期連続で増収を記録し、2020年のコロナ禍では一時的に減収となりましたが、企業理念を実践してV字回復を果たし、創業以来一度も赤字に転じていません。キャッチフレーズは「確かな『キズキ』のクリエイティブカンパニー」であり、「気付き」「築き」「絆」の三つを大切にしています。
企業理念として『道徳的資本主義の追求』を掲げています。これは、利己に偏らず人の絆を大切にし、高い道徳心と精神力をもって社会と向き合うことを目的としています。主力の労働者派遣事業に加えて、グループ会社を通じ、災害関連事業(臭わない仮設トイレを開発するインプルーブエナジー株式会社)や農業(インプルーブファーム株式会社)といった社会貢献性の高い事業にも積極的に取り組んでいます。今回は、『道徳的資本主義』を軸に三つの「キズキ」で人と社会の価値を築く経営の原点と、人材から災害・農業へ広がる挑戦の展望について、代表取締役社長・尾張様にじっくりとお話を伺った。
<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>
【企業理念の原点――「武士道精神」との出会い】
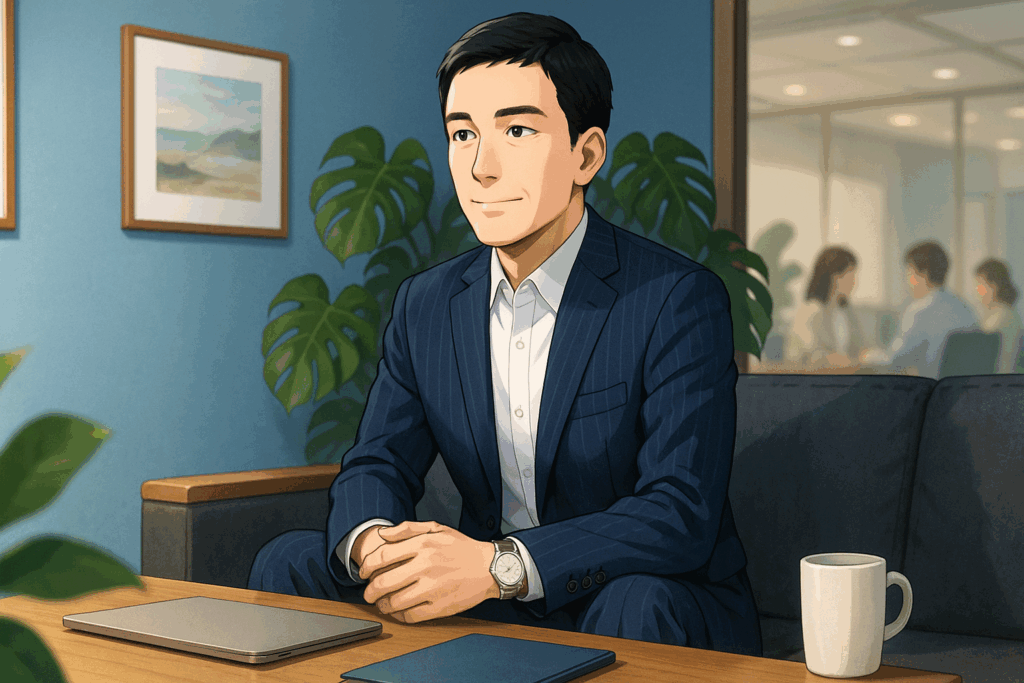
武士道について学びを深めた結果、その精神の根幹は「道徳と精神」にあると気づきました。これは私個人の理念となり、「武士道精神の追求」を企業全体で実践するために「道徳的資本主義の追求」という企業理念が生まれました。これは「道徳をもって社会と向き合う」ことを意味します。道徳とは「思いやりと感謝」に基づく利他(他人の利益)であり、自己犠牲を通じて利己(自分の利益)に打ち勝つ精神力が必要になります。したがって、道徳力と精神力は一体として成長していきます。
道徳的資本主義は、道徳(ギブオンリー)と資本主義(ギブ&テイク)を組み合わせた考え方です。社会の原理原則はギブ&テイクであるため、必ずギブから始めることが重要です。両者とも初動はギブなので、この原理原則に従って先に与える行動(ギブ)を貫けば、対価(テイク)は後から自然に返ってきます。この「道徳」と「経済活動」の融合は、渋沢栄一の『論語と算盤』(論語=道徳、算盤=経済)が説く内容と一致しており、成功の普遍的原理だと確信します。入社時の社長研修では、会社の存在価値や目的、給料の定義など根本概念の「定義づけ」を行い、道徳的資本主義を共有して社員の人間力向上を目指しています。
取材担当者(高橋)の感想
海外の成功者が日本の武士道精神を成功の秘訣として挙げたというエピソードは衝撃的でした。現代の資本主義社会はともすれば「いかにリスクを減らして利益を得るか」に傾倒しがちですが、尾張社長の思想は、利己ではなく「人の絆を大切にし、社会と向き合い社会に貢献する」という人間としての根本的な倫理に立ち返ることを教えてくれます。就活生として、目先の利益や華やかさだけでなく、企業が持つ理念の深さや、それが社会の原理原則にどれだけ沿っているかを考えることが重要だと感じました。

【成功の原理原則――「ギブ」と「長期」で考える】
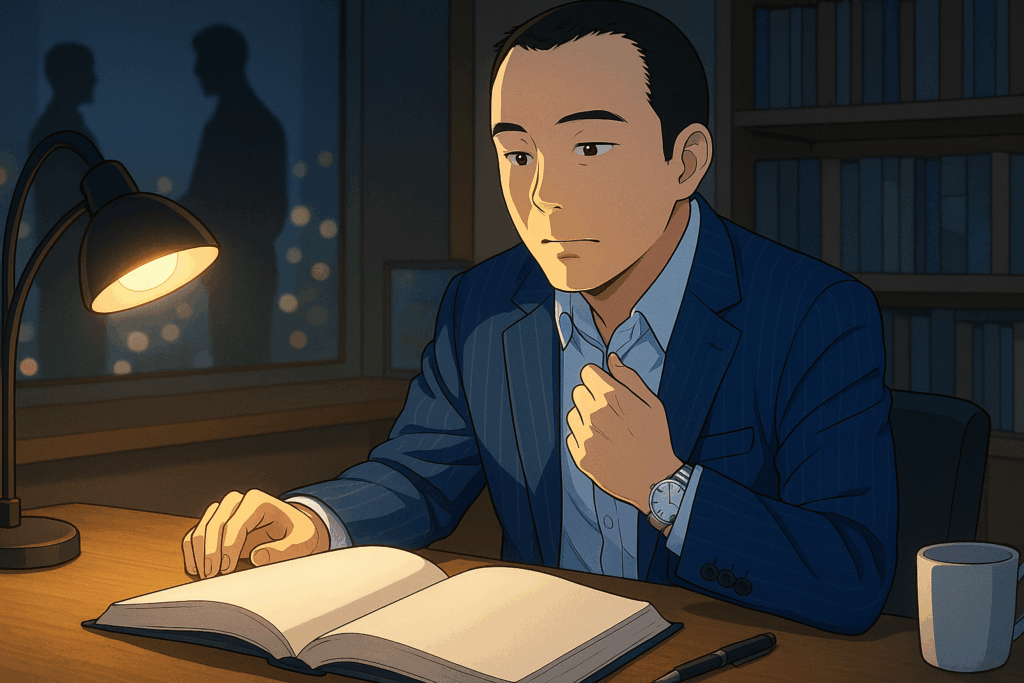
世の中の仕組みは、資本主義の原理原則に基づいています。「ギブ&テイク」「トレードオフ」「リスクとリターン」といった概念で成り立っており、原理原則に沿って行動するほうが理にかなっています。たとえば重力に従えば物は上から下へ落ちますが、原理原則に逆らって下から持ち上げようとすれば大きな力が要ります。
多くの人が成功できないのは、この原理原則に反する行動を取っているからです。本来は「ハイリスク・ハイリターン」あるいは「ローリスク・ローリターン」であるにもかかわらず、リスク(ギブ)を抑えたままローリスクでハイリターン(テイク)を求めようとする人が増えています。これは原理原則に反するため、ロケットを垂直に持ち上げるような莫大なエネルギーが必要になり、長期的にはうまくいきません。
短期的な利益は得られても、それは一時的です。自分の人生も含め、物事を長期的な視点で捉えることが重要です。社会という原理原則において、人と人との良好なつながりを維持する鍵は「思いやりと感謝」にあります。思いやりをもってギブすれば、相手は感謝で応じます。その繰り返しが社会の円滑な循環を生み出します。この原理原則を理解し、長期視点で道徳的資本主義を貫くことが、結果として成功と幸福に通じる道だと考えます。
取材担当者(高橋)の感想
「原理原則を知る」という考え方が、非常に腑に落ちました。自分の人生を重力に例えて、無理な力を入れずに進むためには、資本主義の根幹にある「ギブ&テイク」をギブから始めるという原則を理解する必要があると学びました。目の前の成果だけでなく、人生全体を長期プロジェクトとして捉え、「思いやりと感謝」を基盤に人と関わることは、私たち若者にとって重要な羅針盤になると感じました。

【常識を疑え――挑戦と自己成長を続ける理由】
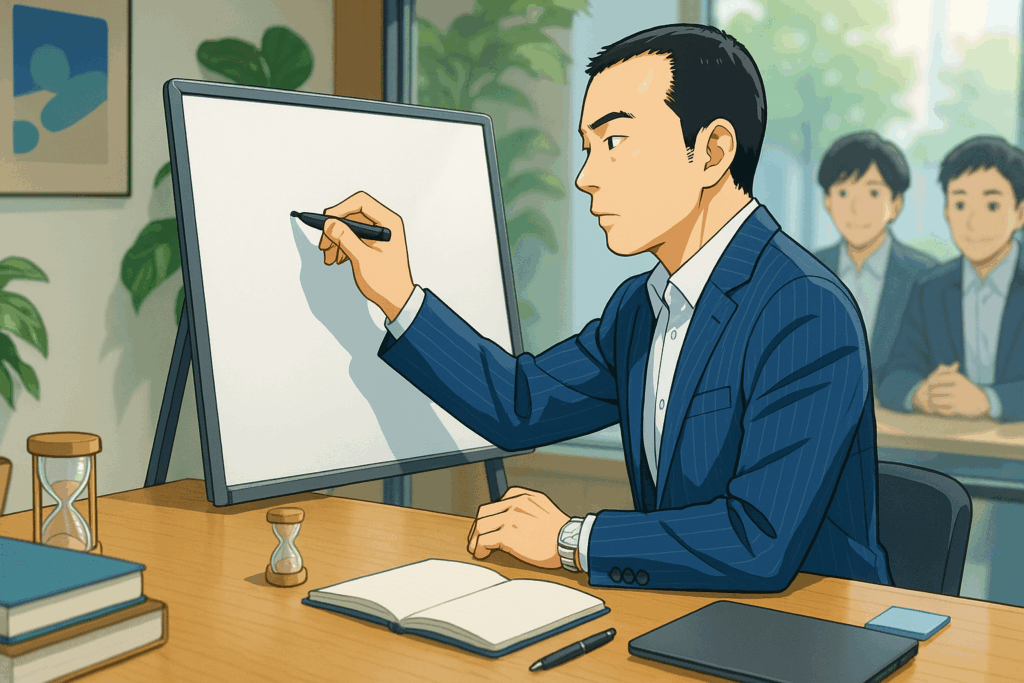
私は自分を「アホの高卒」と揶揄するほどの学歴でしたが、高学歴の人々より優れていない分、より多くの努力と経験を積む必要があると考え、がむしゃらに行動し続けた結果、成功を収めました。この経験から、多くの人が学生時代の強制された学習を終えると、社会人になって学びを止めてしまうことに気づきました。
しかし、社会人になってからの学びこそが真の成長につながります。人生八十年時代において学生期間は二十年程度で、人生は社会人としての時間のほうが長いからです。しかも社会人の学びは「必要だ」と感じて自ら選び、実践するため、成果が現れやすい一方、学生時代の勉強には目的が見えにくい時間も少なくありません。成果を出せない人は、社会に出てから学びを止め、日々の作業に終始してしまいます。
学生時代はレールが敷かれた「チュートリアル」ですが、社会人からはレールのない「フリー探索」になります。自分で計画し、実行しなければ経験値は積めず、レベルも上がりません。大きな成功(財宝)を得るには、敗北や挫折のリスクを負って挑戦する必要があります。本を読む目的は、単に知識を得るだけでなく、自分の考えが妥当かを検証するためです。日頃から多様な情報に触れ、物事の本質を深く考えることが重要だと考えます。
最も重要な成長行動は、学んだこと・考えたことを実践し、アウトプットすることです。理解しただけでは記憶からすぐ抜け落ちます。また、成長の伸びしろが最も大きいのは、自分の「嫌いなこと」や「興味のないこと」です。好き・得意はすでにレベルが高い一方、不得意領域に挑戦して経験を積めば、たとえば本来は「大胆タイプ」か「繊細タイプ」に分かれるところを、「大胆かつ繊細」という両極的な強みに高められ、バランス能力が飛躍的に向上します。経営者に重要なのは尖った個別能力よりもバランス力です。行動の基準は「好き嫌い」ではなく**「重要かどうか」であり、重要であれば嫌いでもやる**という選択を取ることが肝要です。
取材担当者(高橋)の感想
社長が「過去をサボっていたカメ」だからこそ、社会人になってからの努力量が周囲を上回ったという話にはハッとさせられました。受動的な勉強ではなく、自ら学び、実践とアウトプットで定着させるプロセスは、就職活動やその後のキャリア形成における「成長の定義」だと感じました。とりわけ「重要かどうか」を基準に、あえて興味のないことにも飛び込む姿勢が将来の希少価値につながるという示唆は示唆的です。

【社会課題への挑戦――人材派遣から仮設トイレ、そして農業へ】
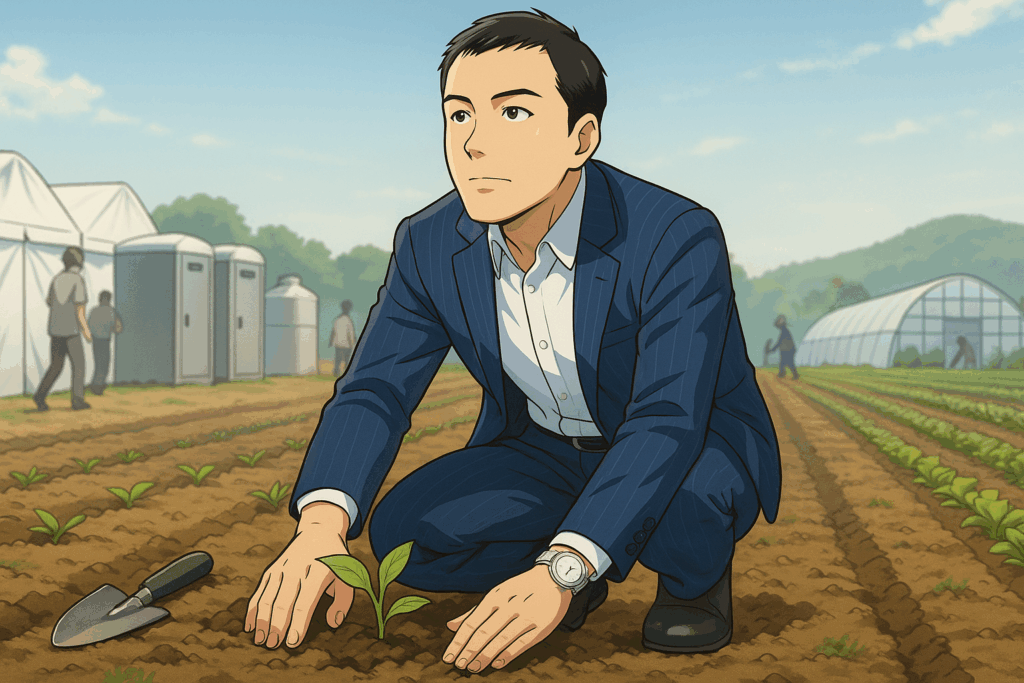
インプルーブグループは、企業理念である道徳的資本主義に基づき、社会課題の解決を企業の存在価値と位置づけています。その一つが、グループ会社インプルーブエナジーが開発した「臭わない仮設トイレ」です。これは建設現場やイベントのみならず、災害時の避難所における深刻な課題を解決し得ます。
災害発生後、直接的な死因よりも「災害関連死」で亡くなる方のほうが多いと指摘される場合があります。その要因の一つがトイレ問題です。臭い仮設トイレを避けて水分摂取を控えた結果、エコノミークラス症候群やストレス、免疫力低下を招き、命を落とすケースにつながり得ます。この「臭わない仮設トイレ」は、避難所環境を大きく改善し、災害関連死の低減に資する可能性が高いと考えます。
仮設トイレ業界は長らく停滞してきました。発注者(費用を負担する側)と利用者(作業員や参加者)が異なるという構造的課題のため、発注者側は仮設トイレをコストと見なし、品質向上への投資が後回しになりやすいからです。結果として、イノベーションが起きにくい状況が続いてきました。こうした課題を自らの存在意義として引き受けるプレーヤーが参入すれば、業界に大きな変化をもたらせると考えます。
また、将来AIが多くの仕事を代替する時代が来ると予測し、最終的に残るのは「食」に関わる第一次産業だと見立てています。人材派遣を含む多くの業界でAI代替の可能性があるからこそ、グループ会社としてインプルーブファームを設立し、農業分野にも参入しています。これも「社会課題の解決」という企業理念に基づく、長期視点の事業展開です。
取材担当者(高橋)の感想
人材派遣というメイン事業から一見離れて見える「仮設トイレ」や「農業」への参入も、すべてが「社会課題の解決」という企業理念に接続している点に感銘を受けました。特に、発注者と利用者が異なることでイノベーションが生まれにくいという構造的課題への着目は、まさにクリエイティブカンパニーの真骨頂だと感じました。就活生として、業界動向だけでなく「その企業がどの課題を解決しようとしているのか」という本質を見る目を養いたいと思います。

【未来を生き抜く――学生に求められる「恐れず知ること」】
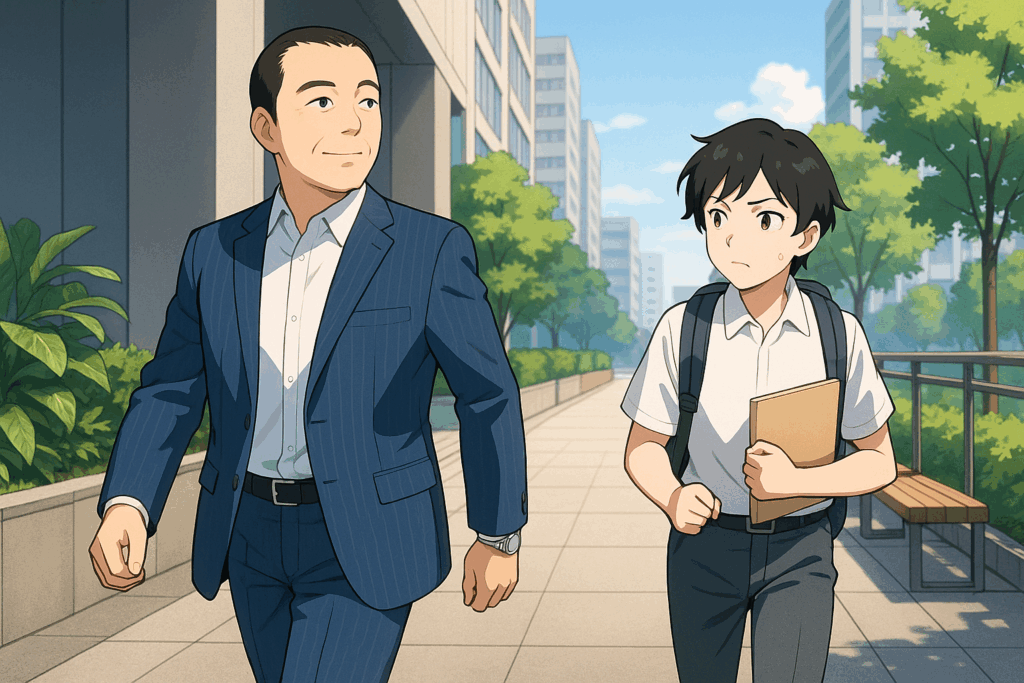
AIやディープフェイクが進化し、未来が不確実で「怖い時代」に突入する中で、若者がまず行うべきことは「世の中の原理原則を知ること」です。次に重要なのは「死を恐れないこと」、すなわち恐怖を乗り越えることです。人間は、死やそれに連なるお金を失うことへの恐怖から、挑戦を避けがちです。恐怖を乗り越える鍵は「理解」にあります。理解できないもの(未知)には恐怖や嫌悪が生じ、排除しようとします。常に相手目線で考え、理解を深めることが重要だと考えます。
また、現代の多くの人は『進撃の巨人』でいう「壁の中の人々」のように、与えられた常識やルールの中で自らの不自由さに気づかずに生きています。だからこそ、調査兵団のようにリスクを負って自由を獲得する生き方を目指してほしいと思います。多くの人は「好きか嫌いか」「やりたいかやりたくないか」で行動を選びがちですが、そうではなく「重要かどうか」で選ぶべきです。嫌いなことや興味のないことこそ伸びしろが大きい領域であり、挑戦を通じて総合力を高めてほしいと考えます。
そして、日本という豊かな環境に生まれた者には、豊かでない国々の子どもたちの分まで含めて社会に貢献する役割があると考えます。ボランティアのような一過性ではなく、より大きな影響力をもって世の中を良くしていく必要があります。原理原則を学び、恐怖を乗り越えて行動し、自由を勝ち取る生き方こそが、激動の時代を生き抜く道だと確信します。
取材担当者(高橋)の感想
私たち学生団体の活動の根幹にある「夢」や「活動」について、「まずは原理原則を知ること」「恐怖を乗り越えて挑戦すること」という具体的な指針をいただけたのは大きな学びでした。『進撃の巨人』の比喩で、自分の人生を「村人A」で終わらせるのか、「調査兵団」としてリスクを負い自由を取りにいくのかを問われ、深く考えさせられました。この学びを胸に、固定観念にとらわれず、さまざまな経験を積んでいきたいと思います。










