株式会社おとうふ工房いしかわ様は、「自分の子どもに食べさせたい豆腐づくり」を原点に、国産大豆を100%使用することにこだわる企業様です。豆腐やおからを素材にしたパン、お菓子、デザートなど多種多様な商品を展開し、直営店舗やオンラインストアを通じてお客様に届けています。同社は「全ての人を幸せにしたい」という社是のもと、「日本の農業を守る」「地域の環境を考える」「食文化を継承創造する」「地域でCSV貢献する」という4つの企業理念を軸に、地域社会に貢献する多角的な活動を行っています。本記事では、石川社長の創業から現在に至るまでの軌跡と、その根底にある経営哲学に迫ります。
<聞き手=高橋宏輔(学生団体GOAT編集部)>
【創業の経緯と理念の確立:バブル崩壊と「子供に食べさせたい」思い】
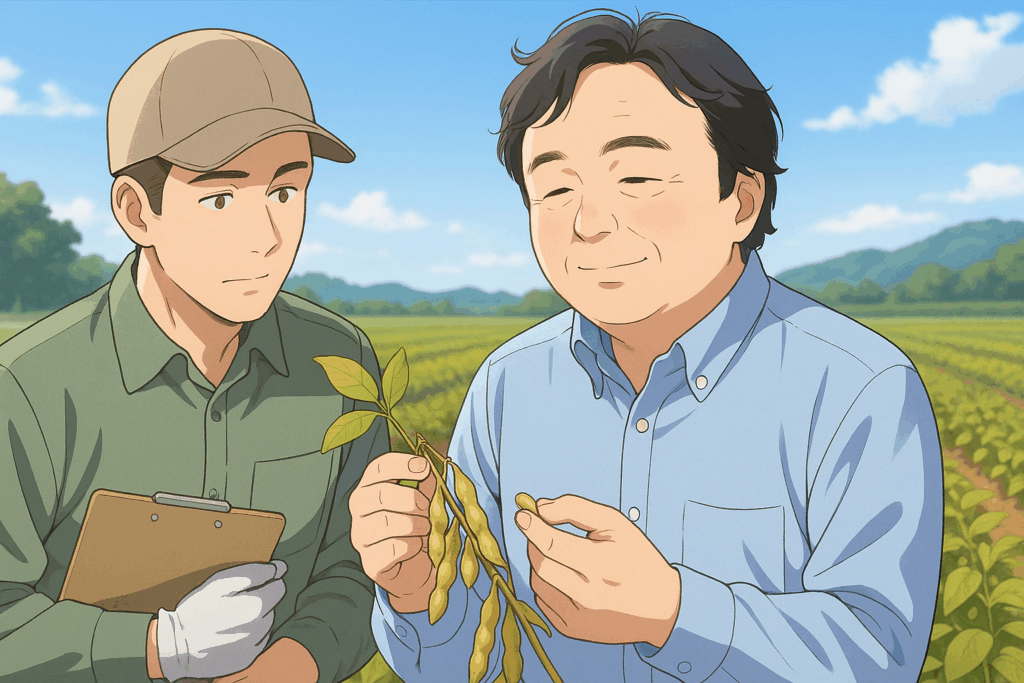
大学卒業後、東京の商社で5年間勤務した後、27歳で結婚を機に実家のある地域に戻りました。そして、バブル崩壊が始まった1991年5月にこの会社を創業しました。創業当初、私の両親が営んでいたのは小さな町の豆腐屋で、スーパーとの取引もなく、妻と二人で新たな事業を立ち上げました。商社での営業経験や、元々技術職であったことから新商品開発にも自信があり、当初は順調に進むと考えていました。
しかし、創業直後にバブル崩壊の波が押し寄せ、世の中は安いものを求める時代へと変化していきました。そんな中で、私自身の長男・次男が生まれ、子育てをする環境に身を置いたことが大きな転機となりました。「自分の子供に食べさせたい豆腐」という明確なテーマを掲げ、安価な輸入大豆ではなく、高価であっても安全で安心、そして生産者の顔が見える国産大豆にこだわることを決意しました。これは、ただ単に高いものを売るのではなく、そこに明確な価値と理由があるという確信から生まれた選択でした。
国産大豆へのこだわりを貫く中、2002年と2003年には冷夏と台風の影響で国産大豆が極端に不足するという事態に直面しました。この時、半年間限定でカナダ産の有機栽培大豆を使用した豆腐を製造しましたが、その際は正直にパッケージにカナダ国旗を印刷し、お客様に事情を説明しました。この経験から、お客様からの信頼を得るためには真実を伝えることが不可欠であると再認識しました。
また、この出来事は、仕入れ先の農家との関係性の重要性を深く考えるきっかけとなり、農家にも喜んでもらえるよう、通常の200円増しで大豆を買い取るプレミアム契約栽培を始めるという「逆張り」の戦略へと繋がりました。これらの経験を経て、2004年には「日本の農業を守る」ことを最優先とする企業理念を確立しました。この理念は、「地域の環境を考える」「食文化を継承創造する」「地域でCSV貢献する」という4つの柱となり、現在のおとうふ工房いしかわの事業活動の根幹を成しています。
取材担当者(高橋)の感想
石川社長のお話から、企業経営における理念確立の重要性を深く学びました。特に、バブル崩壊という困難な時代に直面し、個人的な経験である子育てから「自分の子供に食べさせたい豆腐」という原点を見出した点は、非常に共感しました。危機的状況下での国産大豆不足の際にも、誠実にお客様に真実を伝えることで信頼を勝ち取ったエピソードは、単なるビジネス戦略を超えた、人間としての誠実さの大切さを教えてくれます。

【ビジネスにおける真実と等身大の重要性:公器としての会社経営】
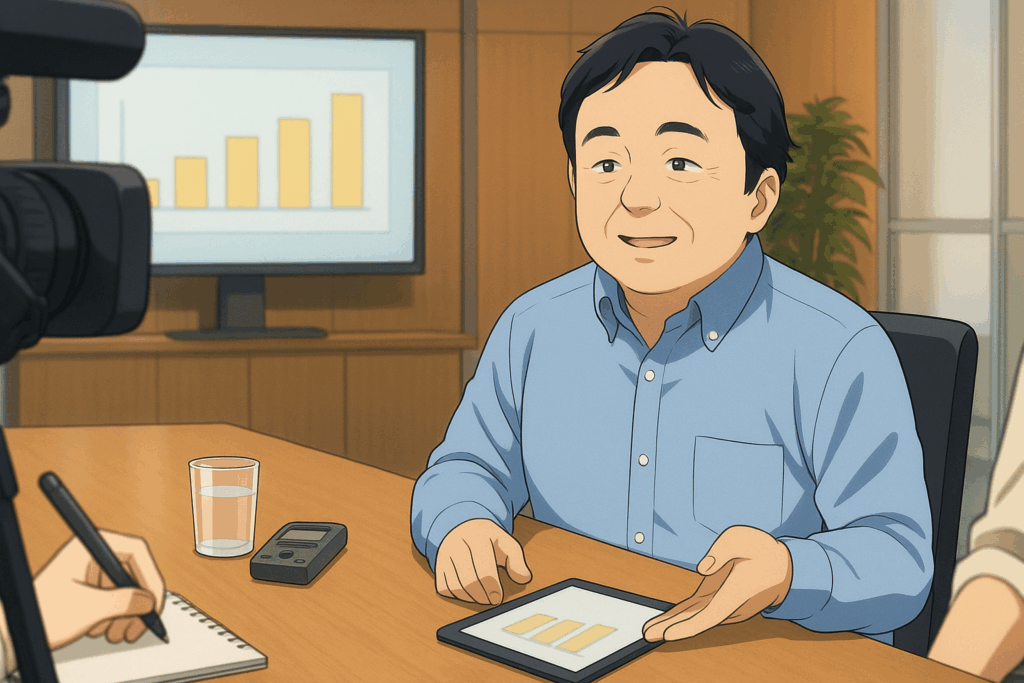
私たちは、企業活動において「等身大」の姿を飾りなく伝えることを最も重視しています。メディアを活用した情報発信においても、テレビや雑誌、ラジオといった多様な媒体を通じて、私たちの企業理念や製品へのこだわりを多角的に、しかし常に真実に基づいて伝えてきました。例えば、かつてカンブリア宮殿に出演した際も、「自分に食べさせたい豆腐作り」というテーマや、多種多様な大豆加工品の開発、直営店・移動販売・ネット販売といった多角的な販売チャネルの展開が紹介されました。これは、他社と同じことをしていては取り上げられないという認識のもと、私たちの独自性と本質的な活動が評価された結果だと考えています。
バブル崩壊後の「安いものこそ良いもの」という風潮に対し、私たちは市場がやがて「高いもの」を求める「振り子の法則」が働くことを見越していました。そこで、たとえ価格が高くても、安心・安全な国産大豆を使用した高品質な製品を提供することに注力しました。お客様はただ高いものを求めるのではなく、「テレビで紹介されている」「美味しい」「体に良い」「子供に食べさせたい」といった具体的な理由があれば、価値を理解し、喜んで購入してくださいます。この価値観を共有する層、特に自然食品業界やこだわりのスーパーマーケットが、私たちの製品を最初に見出してくれました。
また、私たちの行動の根底には、「大豆3粒の教え」と「Pay it forward(ペイ・イット・フォワード)」の精神があります。大豆を蒔く際に3粒蒔くのは、1粒は鳥のため、1粒は土のため、そして1粒が自分のためという教えです。これは、必ずしも100%のリターンを期待せず、無駄を恐れずに与えることの重要性を示しています。私たちは、情報発信においても一方的に真実を伝え続ける「ノーリターン」の姿勢を貫いています。会社は「公器」であり、経営者は会社を私物化してはなりません。納税を通じて社会に貢献し、多くの人々を幸せにすることが、企業としての最も大切な役割だと考えています。この「嘘をつかない誠実さ」こそが、顧客、特に女性からの絶対的な信頼を築く上で不可欠なのです。
取材担当者(高橋)の感想
石川社長の「等身大で真実を伝える」という経営哲学は、情報が溢れる現代において、本質を見抜く力を養う上で非常に重要な示唆を与えてくれます。単なる利益追求ではなく、顧客や社会との信頼関係を第一に考える姿勢は、企業が持続的に成長するために不可欠だと改めて感じました。法人を「公器」と捉え、納税の義務を全うすることで社会に還元するという考え方は、経営者としてのあるべき姿を示しています。

【人手不足と組織づくり:等身大の採用と「職育」の価値】
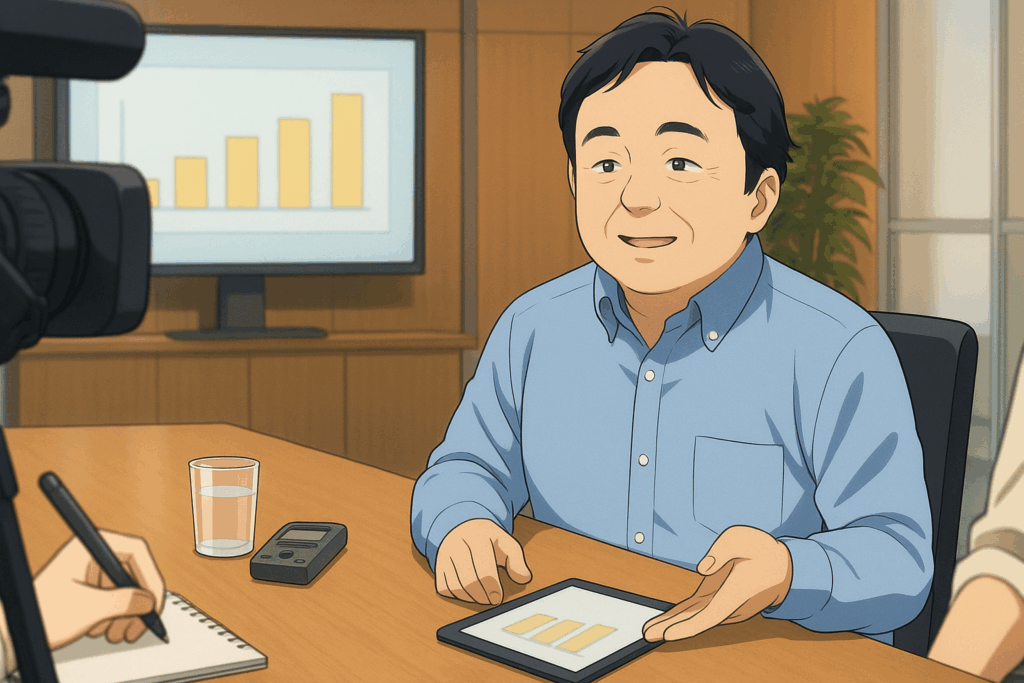
過去には、私たちも従業員の離職という形で人手不足の苦しさを経験しました。その原因は、経営者である私の企業価値観と、従業員の価値観がすれ違っていたことにあると分析しています。このずれを解消するために、私たちは「自分の子供のための豆腐作り」という私のライフワークを、会社全体で取り組む「食育(しょくいく)」活動へと発展させました。社員がボランティアで小学校の子供たちに豆腐作りを教えたり、大豆の種まきイベントに参加したりすることで、会社が目指す方向性や社会貢献の意義を共有できるようになりました。この活動はNPO法人「だいずきっず」として継続され、社員のエンゲージメント向上に繋がっています。
私たちは愛知県高浜市に位置しており、近隣にはトヨタ自動車のような高給の企業が数多く存在します。そのような地域環境の中で、単に高給を提示するだけでは、真に私たちの理念に共感し、長く働き続けてくれる人材は得られません。私たちは、会社の売上高を上げることよりも、多くの人々に自分たちの商品を届け、企業としての社会的な使命を果たすことを最重要視しています。そして、自分たちの能力以上のことはしないという「等身大で生きる」価値観を大切にしています。
採用活動においても、この「等身大」の姿勢を貫いています。私たちは、求職者に対し、特別な高給や過剰な休日を約束することはありません。給与や休日の条件は正直に伝え、会社でどんな活動をしているのかを飾らずに話します。無理に誘うようなことはせず、「それでよければ来てください」というスタンスです。もし誰も来てくれないのであれば、それは会社が社会から必要とされていないということだと受け止めます。私たちは金銭的な魅力だけで動く人材ではなく、「人並みに暮らせ、自分の家族が仕事を誇らしく思ってくれる環境」を求める、会社の理念に共感してくれる人材を求めています。
取材担当者(高橋)の感想
石川社長の「食育」活動や「等身大の採用」という考え方は、まさにこの本質的な組織作りに繋がるものだと感じます。特に、若者が仕事に求めるものが給与だけでなく、社会貢献性や自己実現、そして「やりがい」へと変化している現代において、会社の理念や文化に共感する人材を惹きつけるための誠実な姿勢は、企業が成長するための鍵となるでしょう。

【若者へのメッセージと未来への展望:次世代へ繋ぐ「三方よし」の精神】
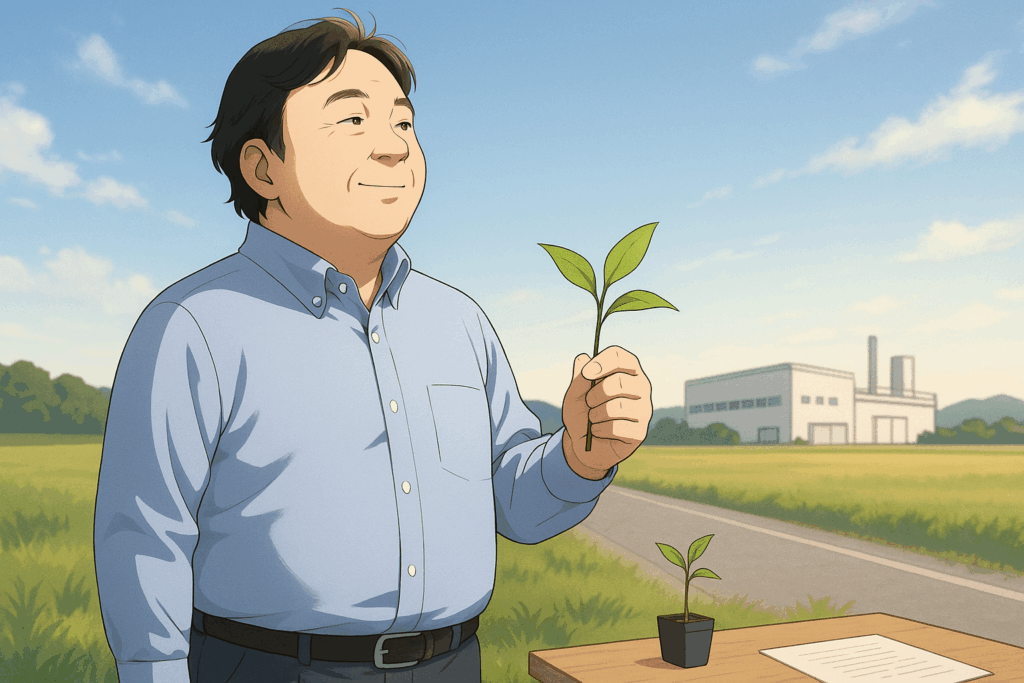
未来を担う若者の皆さんには、「バカでいい、賢くなるな」と伝えたいです。現代は効率や合理性を求めすぎますが、人生には無駄に見える経験こそが重要です。若いうちは、失敗を恐れずに挑戦し、苦しむことを経験してほしい。の経験は買うことができません。だからこそ、若者には多くのことを経験し、自ら学び取る特権があるのです。私自身、37歳の時に人生の半分を終えたと感じた際、自分のためではなく「与える立場」になることで、無限の可能性が見えました。お金は生活に必要なものですが、心の豊かさがあれば、過度な金銭への執着は必要ありません。
会社経営においても、多様な価値観を持つ社員を受け入れ、会社の器を大きくすることが不可欠です。そして、私たちのビジョンは、日本という国が未来永劫存続し、豊かで平和な生活が、私たちの子供や孫、そして多くの仲間たちに受け継がれることです。食は生命の根源であり、腹が減っては戦争もできません。ミサイルよりも水や食料が重要であるように、食べることを守り続けることは、日本人だけでなく、人類全体、ひいては地球上に存在する全ての生命が平和に命を繋ぐために最も大切なことだと考えています。
このビジョンを実現するためには、「売り手よし、買い手よし、世間よし」という「三方よし」の精神が不可欠です。単に金銭的な取引だけでなく、消費者、実需者(私たちのような加工業者)、そして生産者である農家が、心の通った相互関係で繋がることが最も重要です。消費者が農家の方々に感謝の気持ちを持ち、農家の方々も食べてくれる人々への感謝を持つこと。この心の三角形を形成することこそが、豊かな社会を築く基盤となります。私たちは、この「三方よし」の精神を次世代へと繋ぎ、日本の農業を守り、持続可能な未来を創造していくことを目指しています。
取材担当者(高橋)の感想
石川社長が若者に向けた「バカでいい、賢くなるな」という言葉は、私の胸に深く響きました。効率や合理性ばかりを追求し、失敗を恐れて行動しない現代の若者にとって、石川社長の言葉は、人生において経験や本質的な価値を見出すことの重要性を強く示唆しています。また、「三方よし」の精神に基づく、持続可能な社会への貢献というビジョンは、Z世代が求める社会貢献や倫理的消費といった価値観にも通じるものであり、未来を考える上で多くの学びを得ることができました。










