株式会社新進様は、今年で創業131年を迎えた歴史ある企業です。漬物を中心とした食品事業を展開しており、特に福神漬は業界トップクラスのシェアを誇ります。長きにわたり日本の食卓を支えてきた同社は、「喜ばれながら創り 喜ばれながら商う」という社是を掲げ、「関わるすべての人に誠実であること」「社名を旨に変わることなく変わり続けること」を社訓として大切にしています。これらの社是社訓には、創業者の思いと、挑戦を続けるという会社の姿勢が込められています。今回は、131年にわたり日本の食卓を支え続けてきた歴史、そしてその根底にある理念と進化への意志について、株式会社新進 代表取締役社長・籠島様にじっくりとお話をお伺いしました。
【会社を継ぐ決意と修行の日々】
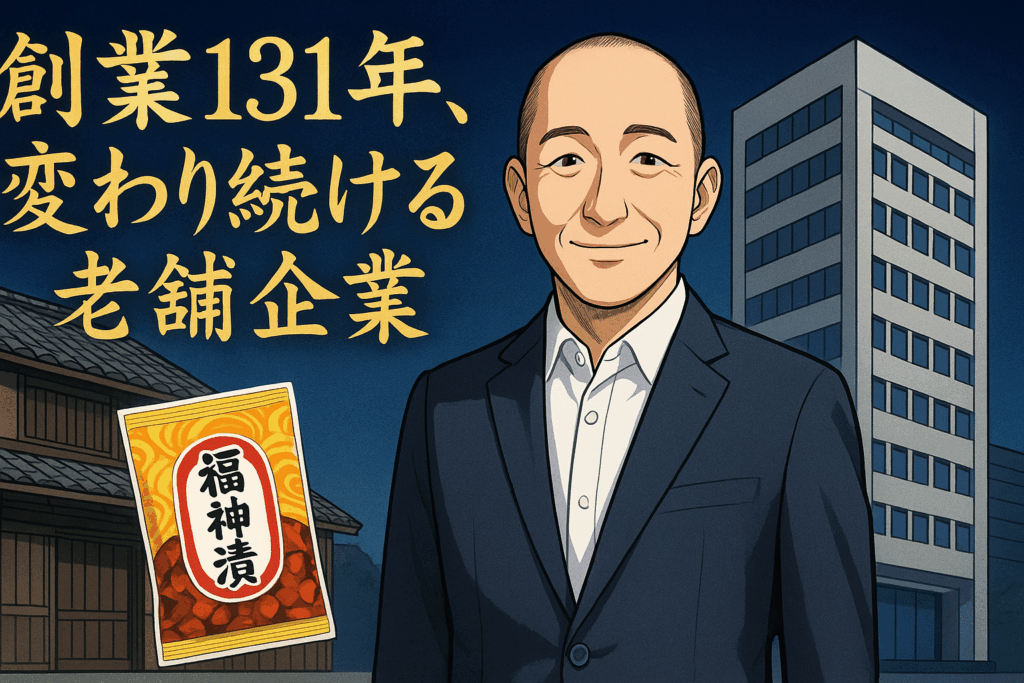
幼少期から家業が身近にあった私にとって、将来この会社で働くことは漠然と意識していました。しかし、入社するからには「いずれそれなりの立場になるであろう」という前提があったため、まずは現場の肌感覚を身につけたいという強い思いがありました。そこで、食品営業の世界で経験を積むことを決意し、ご縁あってキューピーマヨネーズの業務用営業として入社しました。
キューピーでは約7年弱にわたり修行を積みました。最初の3年半は業務用営業として現場の最前線で経験を積み、残りの3年半は商品開発本部で商品開発の知識を吸収しました。この7年間で得た営業と開発の知識は、家業に戻った後の私の大きな財産となりました。2014年1月1日に家業である株式会社新進に戻り、その年の6月には取締役に就任しました。
取材担当(高橋)の感想
籠島社長が家業に戻る前に、異なる環境で自ら営業や商品開発の経験を積んだという話は、将来を真剣に考え、自らの成長のために行動する重要性を示していると感じました。これは、すぐに結果を求めがちな現代において、長期的な視点を持つことの大切さを教えてくれるエピソードです。

【社長就任、そして改革への転換点】
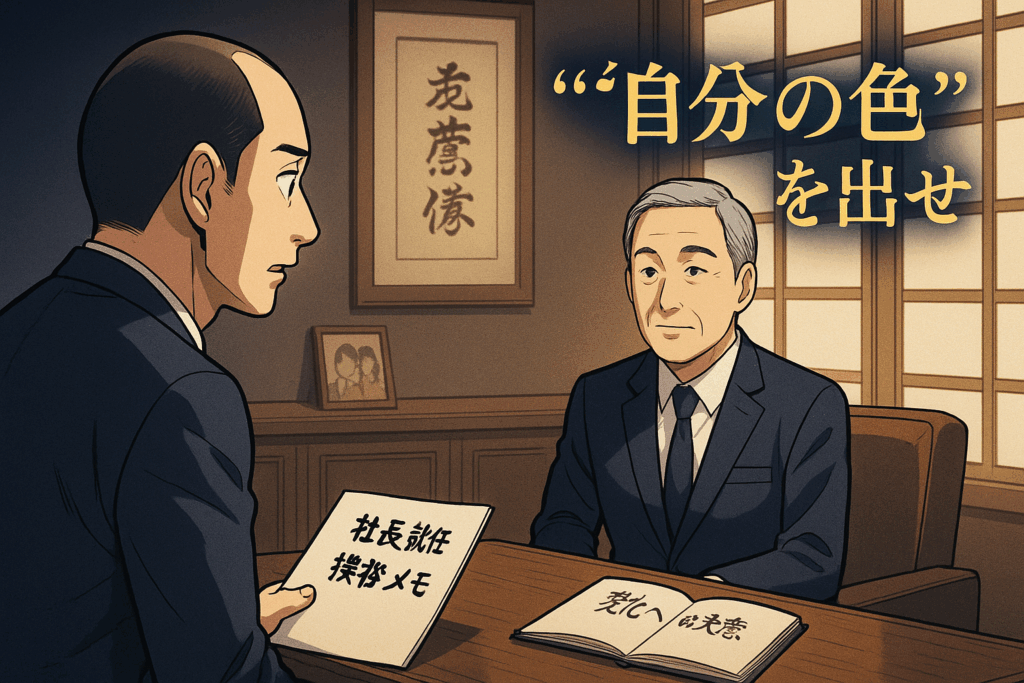
2014年1月1日に入社後、執行役員として家業に入り、同年6月の株主総会で取締役に就任しました。その後、2015年6月には常務取締役に昇進し、そして2016年6月の株主総会で社長に就任しました。入社からわずか2年半での社長就任は、私自身も「早い」と感じるほどのスピード感でした。
社長に就任した当初の私は、先代である父(現会長)のやり方を踏襲していくと周囲に伝えていました。しかし、しばらくしたとき会長から「オーナー会社の社長が変わるというのは数十年に一度のタイミングだ。従業員も期待感を持って見ているのに、先代のやり方を踏襲するだけでは何も会社は変わらないのではないか」と静かに言われたことが、私の心に深く響きました。この言葉が、私自身のカラーを出すべきだという意識改革のきっかけとなりました。
会長の言葉を受けても、すぐに自身のカラーを出せたわけではありません。就任から3、4年ほどは悩む時期も続きましたが、このままではいけないという思いが募り、そこから「変えるべきものは変える」という方向へとかじを切っていきました。
取材担当(高橋)の感想
長く続く企業のトップに立つことの重みと、そこでの葛藤が伝わってきました。先代のやり方を尊重しつつも、会社の未来のために自身の信念を貫き、変革に踏み出す勇気は、多くの学生がキャリアを考える上で参考にすべき点だと感じます。

【従業員を最優先に据えた経営改革】
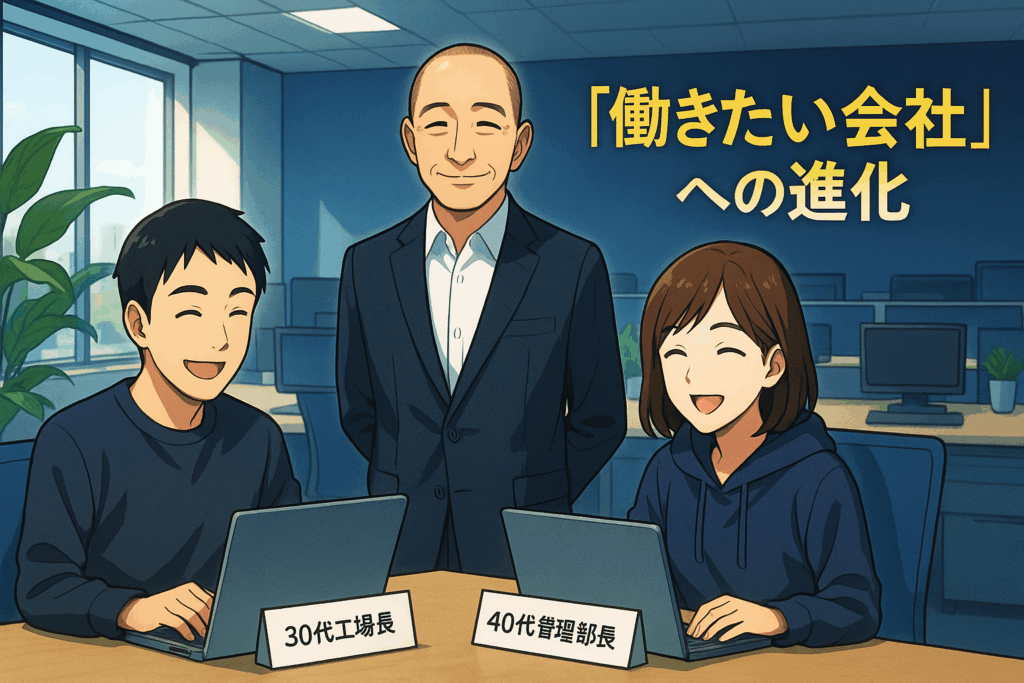
改革を進める上で、私が最も意識したのは従業員の方々です。一般的に株式会社では株主の利益最大化が重視されがちですが、弊社がこれからも会社を続けていくためには、何よりも従業員の方々が大事だと考えています。従業員の方々が「この会社で働いてよかった」と心から思えるようにすることが、私の使命だと感じています。
具体的には、働きやすい環境づくりに注力しています。131年続く会社ゆえに、昔ながらの慣習も多く、変革には大きなエネルギーが必要でした。それでも、フレックスタイムの導入や、ビジネスカジュアルな服装での勤務を許可するなど、今の時勢に合わせた柔軟な働き方を取り入れました。また、年功序列が強かった人事制度からも少しずつ脱却し、やる気と情熱に満ちた人には、年齢に関わらず役職をお任せし、それに見合った処遇や給与を提供できる仕組みに変えてきました。例えば、主力工場である利根川工場の工場長は当時30代後半で抜擢され、今の管理本部長も40代半ばで取締役に抜擢されています。
このような取り組みの結果、20代の若手従業員も増え、以前は課題だった若年層の離職率も減少傾向にあります。さらに、一度退職したベテラン従業員が「戻りたい」と声をかけてくれたり、親子三代にわたって弊社で働いてくださっているご家族がいらっしゃるという嬉しい事例も出てきています。これらは、弊社の職場環境が改善され、従業員の皆さんに愛される会社へと少しずつ変化している証だと感じています。
取材担当(石嵜)の感想
「人が幸せになること」を願う経営理念が、具体的な働き方改革や人事制度の変更に繋がっていることを知り、深く感銘を受けました。従業員を「何よりも大切」と語る籠島社長の言葉通り、社員の幸福を追求する姿勢が、定着率の向上や素晴らしいエピソードに結びついているのは、学生が企業選びをする上で非常に参考になる視点だと感じます。

【激動の時代への挑戦と未来への展望】
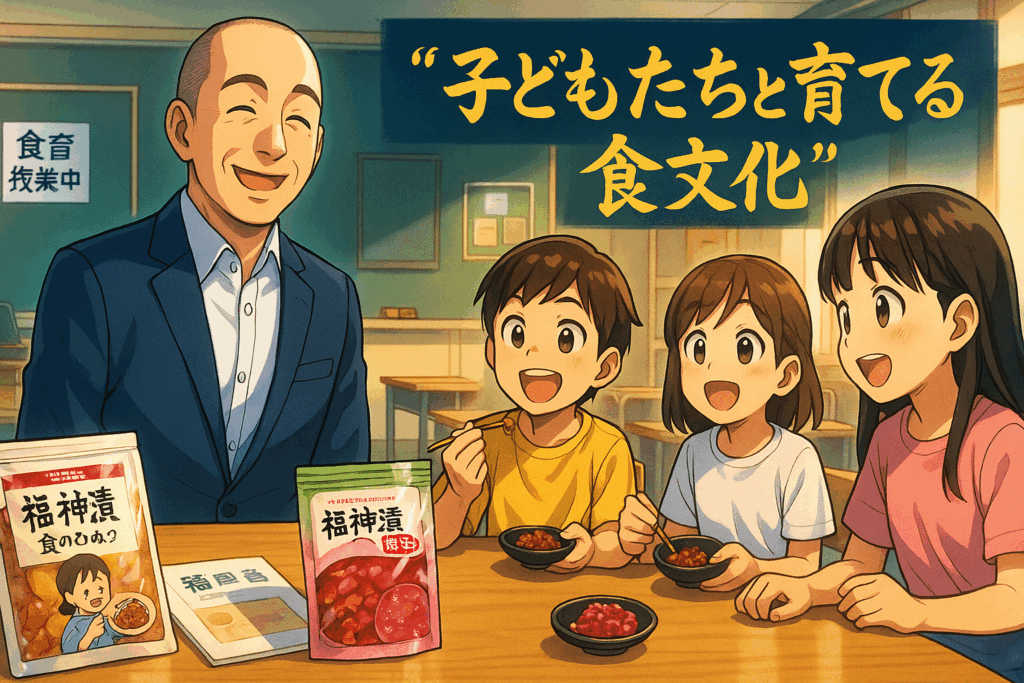
現代は食文化が多様化し、漬物市場の規模は最盛期だった1990年代と比較すると約2/3にまで縮小しています。こうした状況の中で、弊社は漬物の売上構成比率を8割から5割にまで減らし、他の事業を伸ばすことで対応してきました。これは「変わることなく変わり続ける」という弊社の社訓が示す通り、常に挑戦し、新たな事業モデルを構築していくことの重要性を物語っています。事実、弊社の創業は漬物ではなく、澱粉加工業でした。昭和5年に漬物製造に着手して以降も、他の食品事業や、かつてはボーリング場経営など、様々な事業に挑戦し、時には失敗も経験しながら成長してきました。
これからも淘汰されないためには、積極的に新たなチャレンジを続けていく必要があると考えています。現状維持ではなく挑戦を続けることが、生き残るための鍵だと認識しています。漬物消費が減少した背景には、食文化の多様化だけでなく、核家族化の進行も大きく影響しています。漬物を食卓に並べる習慣が親から子へ継承されにくくなっている現状に対し、弊社では食育に力を入れています。ライバル会社であるやまうさんと手を取り合い、小学校の家庭科の授業で使える副教材を制作し、毎年1万部以上を関東圏の小学校に配布しています。さらに、希望する学校には弊社とやまうさんの福神漬を無償提供し、実際に食べてもらう機会を創出しています。
この取り組みの結果、児童からは感謝の手紙が届き、中には「梅味の福神漬があったら面白い」というアイデアも寄せられました。これを受け、梅味の福神漬の試作品を小学生に配布するとともに、地域貢献の一環として、その小学校近隣のスーパーで「小学生が考えた福神漬」として地域・数量限定で実際に販売するに至りました。このような活動を通じて、子供たちが食と社会の繋がりを意識し、漬物の魅力を再認識してもらえることを願っています。
取材担当者(高橋)の感想
変化の激しい時代に生き残るための企業の努力と、その根底にある社会貢献への強い意識に感銘を受けました。特に、競合他社と協力して次世代の食文化を育むという取り組みは、短期的な利益だけでなく、長期的な視点で社会全体を豊かにしようとする企業の姿勢が表れており、未来を考える学生にとって多くの学びがあると感じました。

【未来を担う若者たちへ】
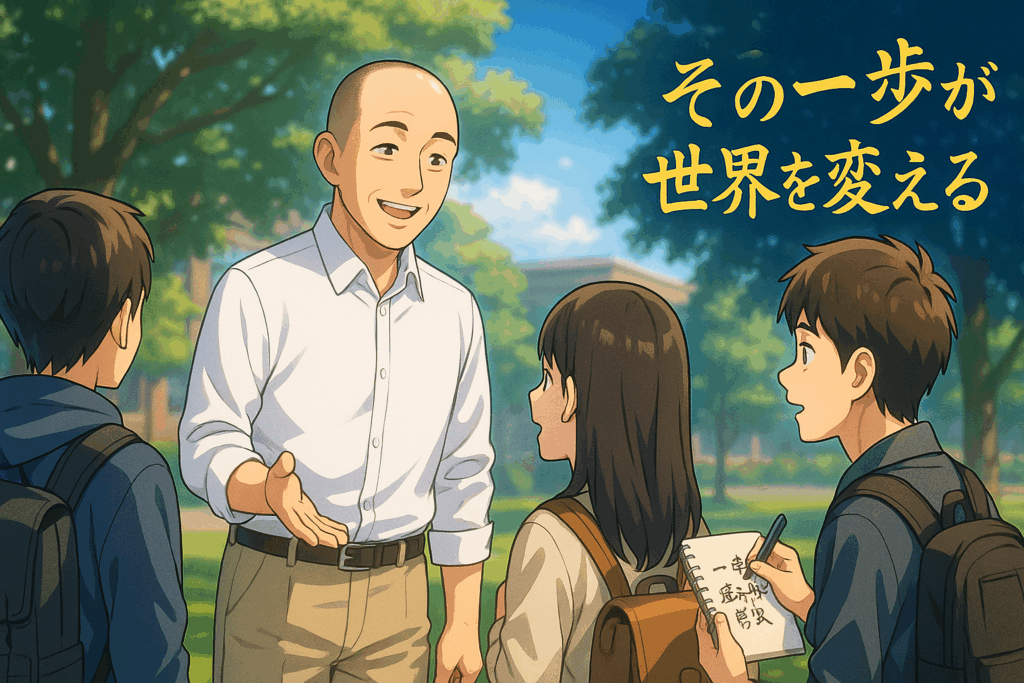
学生の皆さんには、自分の時間を最大限に活用してほしいと願っています。社会人になると、驚くほど自分の時間がなくなります。大学生活における長い夏休みや春休みといった時間を、漫然と過ごすのではなく、様々なことに興味を持ち、積極的に行動し、多くの経験を積むことが重要です。その中で、自分が本当にやりたいことを見つけることができるはずです。
「何かしたいけど、何をしたらいいか分からない」という学生も多いと聞きます。そんな時、いきなりハードルを高く構える必要はありません。ほんの少しの勇気、ほんの少しの「面倒くさい」からの脱却が、大きな一歩となります。その一歩を踏み出して、色々なことにチャレンジし、経験を積んでみてください。それが仕事に繋がるかどうかに関わらず、興味があることに積極的に取り組む姿勢は、社会に出てからも必ず自分の力となります。
現代は情報が溢れ、受け身でいても多くの情報が手に入ります。しかし、受け身の姿勢で満足していては、社会に出てから会社が求める人材とは少しずれてきてしまう可能性があります。失敗を恐れずに、アクティブに行動し、やりがいを持って物事に取り組める人材が、社会では求められています。学生のうちからそうした経験を重ねることで、社会に出てからも自ら一歩を踏み出せる人に成長できると信じています。
取材担当者(高橋)の感想
「何かしたいけど何をしていいか分からない」という多くの学生の悩みに寄り添い、具体的なアドバイスをくださったことに感謝します。情報過多な現代において、自ら考え、判断し、行動することの重要性を再認識させられました。このメッセージは、これからの社会で活躍したいと願う学生にとって、大きな励みとなるはずです。










